漆黒の剣士エバ
ステインの町を出た一行は、一路神聖王国に向かって北に進路をとっていた。
一行の回りには背丈ほどのすすきに似た植物に覆われた丘が見渡す限り広がっていた。
その大草原は、茶色に染められ、それを冬の到来を予感させる北風が撫でると、降り注ぐ太陽の光とあいまって、まさに黄金の大海原を連想させる美しい風景が広がっていた。
「美しい風景ね。」
薄い緑の布を被った、色白のほっそりとした女性が、ため息をつくように呟いた。
彼女の名はマリーウェザー。
彼女は黄金の大海原に囲まれている自分を、斜め上空から見下ろしてみたところを想像してうっとりした。
美しい自然。スケールの大きい自然。そしてそれに囲まれたちっぽけな自分。そんな風景がマリーウェザーは好きだった。
「そうね。」
マリーウェザーの斜め後ろ、風に乱れた長いプラチナブロンドの髪を掻き揚げながら、同じように白い肌をした女性が応えた。
彼女の名はアレンティー。
アレンティーもこの風景を美しいと感じていたが、なぜかその感情をストレートに表現できないでいた。
彼女達2人を初めて見た人は、その姿に神秘的な感動を覚えるであろう。
それは、2人の掻き揚げた髪の間から伸びている長く尖った耳のせいである。
彼女達はエルファという人間に似た生物だった。エルファと人間は非常に近い生物であるが、その長く伸びた耳によって一目で見分けることができる。
その二人の前をマントを羽織った二人の人物が先導して歩いている。
一人はアレンティーと同じように尖った長い耳をしており、とても痩せている男で、その細い腕はすぐに折れてしまうのではないかというほどだ。
彼もまたエルファであったが、実はマリーウェザーとアレンティーの兄であり、3人はエルファの兄妹であった。名はマーリンと言った。
一番先頭を歩いている男は、筋肉質であるがスマートな印象を与えた。
レッドブラウンの寝癖のついたままの髪が目元を覆い隠しており、一見してその表情は読めない。
しかし、下からその瞳を覗き込むと青い澄んだ瞳はまっすぐに正面に向けられていて、青年が若さゆえ一途に前を見つめているような、そんな表情を見ることができる。
腰に吊るされたブロードソードは、柄周りが磨耗しており、よく使い込まれているのが分かる。
また、羽織ったマントの下に身に付けた金属製の胴当てには、細かい傷がたくさんつけられており、彼が幾多の戦いを経験した、プロの剣士であることを想像させた。
だが、そのような細かい点を除けば、一見して彼が恐ろしいほどの腕前を持つ剣士であるとは、だれも想像することはできない。
どちらかといえば、彼の印象は内気で大人しそうな印象であった。名をエバと言った。
そんな一行の後ろから2頭立ての馬車が1台走ってくると、御者台に座っている2人のうちの1人が大きな声をかけた。
「エバ!」
馬車はエバ達の横まで来ると止まった。
「どうしたんだ、ルー。」
エバが声かけに答えた。
「ルーさん。」
エバの横からマーリンも声をかけた。
御者台に座っているのは、カウボーイ・ハットに皮製の上着を着た若い2人で、声をかけてきた一人は帽子からはみ出したブロンドの髪によって女性であることがわかる。
ルーというのはその女性の名前だった。
御者台に座ったまま、ルーはエバ達に向かって愛嬌のある笑顔を見せた。
「エバ、乗っていかないか?今からこの荷物を次の次の、シャロムの町まで運ぶんだ。歩くよりはずっと早く着くよ。」
シャロムの町とはこの先10km程先にある宿場町で、エバ一行もできればシャロムの町で今日の宿が取れればと予定していたところだった。
「エバ乗っていけよ。早く着いたら、その分ゆっくりできるだろ。」ルーの横に乗っていた、手綱を握っている男が帽子のつばをちょっと上に持ち上げながら言った。
彼の名前はキッド。
少し目尻が下がった目は優しい印象を与えるが、鼻筋の通った、整った顔立ちはなかなかの男前だ。
二人はライダーと呼ばれる町と町の間を結ぶ運び屋だった。
若い彼らは、普段は早馬を駆って、誰よりも早く荷物や郵便物を次の町にまで届けることを誇りにしていた。
このライダー2人とエバ達は、ひとつ前の町で、ある事件をきっかけに出会い、お互いに信頼できる間柄であった。
「そうか。じゃあ、悪いけど乗せてもらうよ。でも急ぎじゃないのか。」
エバがルーに向かって答えた。
「大丈夫。とっておきの道があるから、2時間もしないうちに着けるよ。」
と、ルーがウィンクして見せると、「乗れよ」という感じで、後ろの荷台に向かって親指を向けた。
「そのかわり・・・」
キッドがもったいぶったような仕草をする。
「到着したらこの積荷の積み下ろしを手伝ってくれるといいんだけどな。」
「私はそういう仕事は得意じゃないんですがね。」
マーリンがちょっと口を尖らして言った。
「別にあんたに期待はしていないからさ。」
すかさずルーが答えた。
「そうそう、別にあんたに言っている訳じゃない。何勘違いしてるんだ。荷物を持つ前に腕が折れちまう。」
キッドが悪びれる様子もなく肩をすくめると、その様子に思わず笑い声が上がった。
荷台に乗っけられたエバ達は、意外にも荷台の乗り心地が良かったのにびっくりした。
それは積荷が袋詰された小麦であったからだ。
エバたちは荷台に敷き詰められた麻袋の上に横になると、熟睡はできないものの、うつらうつらしながら馬車に揺られていた。
今進んでいる街道の道幅は、馬車1台がやっと通れる程度の広さしかないため、地元の人しか利用しない裏道のようなものであった。
シャロムの町まであと30分というところで、御者台に座っていたルーは前方の街道脇に2人の人影がいるのが分かった。
馬車が2人に近づくと、脇に立っていたその2人が馬車の前を塞ぐように道の真ん中に出てきた。
耳垂れのついた皮製の帽子を被った二人は、いかにもガラが悪そうな斜がかかった目つきをしていた。
手入れされていない無精髭もルーは嫌だった。
彼らの腰には刃の大きな片刃の剣が吊るされており、見るものに威圧感を与えた。
「シャロムの町のチンピラだな。前に酒場で見たことがある顔だ。」
キッドがルーに言った。
「相手にしない方がいいね。」
キッドは立ち塞がる2人の少し手前で馬車を止めた。
「おい、おまえ達どこに行くんだ。」
立ち塞がった2人の内の1人が声を掛けてきた。
「俺達はライダーだ。シャロムの町まで荷物を運んでいるところだ。」
というかこの道は1本道。シャロムの町に行く以外ない。こいつは馬鹿かと思いながらキッドは答えた。
「おまえに聞いてるんじゃねえよ。俺はそこの女に聞いてるんだ。」
うつむき加減にしていたルーに向かって、男は腰の剣を抜くと刃を向けた。するとそのまま、御者台の横まで寄ってくるとその刃をルーの顔まで近づけた。
「俺達はただのライダーだ。この荷物を次の町まで届けているだけだ。何か文句でもあるのか。」
ルーはあえてその男の顔を見ないで、冷静に答えた。
こんな奴等でも、揉めれば後日どんな問題になるか分からない。特に自分達はライダーだ。嫌でもこの道を毎日何往復も通らなければ仕事にならない。
「積荷は何だ。」
「小麦だ。」
「本当に小麦だろうな。」
ルーに刃を向けていた男が、もう1人に目配せすると、そいつは荷台に向かって歩いて行き、荷台の後ろ側に回り込むと、後部入り口に被せられている幌を開けた。
「どうだ。中身は小麦だったか?」
ルーに刃を向けていた男が、後ろの荷台を見に行った男に問い掛けた。
だが、返事はない。
「聞こえてんのか。中身は何だ。」
2度呼びかけるが返事がないため、不審に思った男はルーの腕を掴むと御者台から乱暴に引っ張り下ろした。
「痛い!」
「ルーに何するんだ。」
キッドが叫んだ。
「うるせえ。中身を確認するんだ。こっちへ来い。」
男はルーの首に手を回し体を密着させると、さらに首筋に剣を当てがった。男から放たれる異臭と、密着している感触に、ルーは思わず吐き気を催しそうになった。
ルーを盾にした男は、御者台に残ったキッドを睨みつけながら、ゆっくりと荷台の方に近づいて行った。
どうやら、積荷を確認しに行った男は、まだ荷台の後ろ側から、荷台の中を覗いているように見えた。
だが、さらに近づいていくと何かがおかしいのがわかった。
荷台を覗き込むように立っている男は、微動だにせずじっと立っている。
しかしその顔面には、何か刺さっているように見える。
その突き刺さった物が何かを認識したとき、男も、羽交締めにされているルーも恐怖と驚愕に襲われた。
それは剣であった。荷台の中から伸びている剣が、その男の顔面から頭蓋骨を貫通し、頭の後ろから剣先が突き出ているのだ。
「きゃあー!」
ルーが自分の置かれている状況も忘れて、叫び声をあげてしゃがみ込んだ。羽交締めにしている男も、思わずルーを離してしまった。
ズル。
その瞬間、突き刺さっていた剣が男の顔面から引き抜かれた。
荷台を覗き込むように立っていた男は、支えを失って硬直したまま倒れ込み、つぶれた顔面を荷台にぶつけると地面に転がった。
次の瞬間、荷馬車の幌を突き破って剣が飛び出した。いや、エバが剣で幌を切り裂くと飛び出してきたのだ。
エバは唖然として立ちすくんでいる男に向かって跳んでいくと、幌を切り裂いた剣をそのまま返して男の首に斬りつけた。
エバの剣は真っ直ぐに男の頚骨を切り裂くと、男の頭を胴体から切り離した。切り離された頭は、そのままごろんと地面に転がった。
ルーの叫び声に慌てて御者台から飛び降りたキッドも、首の無い男が立っているのを目にしたとたん、動けなくなってしまった。
エバは地面に降り立つと、首のなくなった男を蹴り倒した。そして剣についた血糊を振るうと、倒れた男の衣服で刃を拭い、鞘に収めた。
精神的にショックを受けたルーは気分が悪くなったので、荷台で休憩することにした。替わりにエバがキッドと一緒に御者台に座ることにした。
ルーは気持ちを落ち着かせようとちょっと横になっていたが、気持ちが高ぶるばかりで一向に落ち着かない。
ふと首を横に向けると、エルファのアレンティーとマリーウェザーがおしゃべりしているのが見えた。
(この2人もさっきの状況を見ていたのに、何も感じないのかな。)
アレンティーは自分達に目を向けているルーに気が付くと、微笑みながら声をかけた。
「大丈夫ですか。」
「気分は良くなった?」
マリーウェザーも心配そうに声をかけた。
「いえ、まだちょっと。」
ルーはこの2人のことがちょっと気になり始めた。
「お2人は大丈夫なんですか?」
無意識の内に敬語を使ってしまった。
「今は大丈夫ですよ。始めて戦いに巻き込まれたときは、すごくショックを受けたけど。」
アレンティーが答えると、マリーウェザーが続いた。
「私もそう。初めてエバさんの戦いを見たときはショックが大きかった。特に姉さんは症状がひどくて、1週間くらいまともに食事ができなかったのよ。」
「1週間くらいだったかしら。食事のときになると、においとかその時の情景が蘇ってきて、食べられなかったの。彼の戦い方は残酷だから。」
「私も始めはそうだったんだけど、何度も何度も見ているうちに、あまりショックを受けなくなったわ。信じられないけど、慣れてきているのかも。」
この状況に慣れるということが、ルーには信じられなかった。見た目だけで比べても、私のほうがこの2人よりはずっと気が強いように思えた。
「でも、どうしてエバはあの男を殺したのかしら。殺す必要はなかったと思うけど。」
「それは彼らが私達を殺すつもりでいたからですわ。」
アレンティーが答えた。
「えっ。」
ルーは戸惑ってしまった。なんでこの人はそう言い切れるのだろう。しかも2人とも至極分かりきったことのように言っている。
「なんで、そんなことが言い切れるの?」
「それはお兄様がそう言ったからですわ。」
そう言うとアレンティーは、こっちにお尻をむけてごろんと横になっているマーリンを見た。つられてルーもマーリンに目を向けた。
ちょっとこの兄弟とは会話が合わないのかも。とりあえず何も考えないようにしよう。
エルファの2人にちょっと休むと伝えると、ルーはまた横になり目を閉じた。
鈴の音がしたので、店のマスターが入り口を見ると、サラサラとした長い金髪に、少々切れ長の碧い目をした女性が立っていた。
「マスター。馬を1頭貸してくれないか。あと、次の町まで道案内を頼む。急いでいるんだ。」
そう言って女性は懐から大粒の赤い宝石を取り出すと、カウンターに転がした。
これはなかなか大きなルビーだとマスターは思ったが、それ以上に彼女の外見にふと見入ってしまった。
まず、彼女の顔には大きな傷跡が左右の頬に一つずつあった。
特に、彼女の左頬の傷跡は大きく、首から顎を通って目の下辺りまで続いており、その形状から何か鋭利な刃物で切り付けられたことを想像させた。
しかし、その傷跡は彼女に不思議な魅力を与えていて、ただの美女ではない、何か彼女の強さのようなものを発散させているようだった。
そして、普通ならきつく感じてしまうだろう切れ長の碧い目も、何か優しさを含んだように見えた。

「どうした。馬は出せるのか。」
そう言われて我に帰ったマスターは、壁に掛けてある予定表に目をやった。
個人的に早馬を出すというのは値が張るため町の貴族でもそうそうあることではない。
「大丈夫です、だんな。最高のライダーがご案内します。馬も飛ぶように走りますぜ。」
「そうか、それはありがたい話だが・・・」
彼女はカウンターに肘を着くと、マスターに向かって、人差し指をクイクイと曲げて、マスターに耳を貸すようにジェスチャーを送った。
マスターはゆっくりと彼女の顔に自分の顔を近づけていった。あんまり近くに寄ったのでマスターはちょっとどきどきした。
すると、彼女は急にマスターの襟首を締め上げた。そしてマスターを睨みつけると、マスターの顔に息がかかるように、そしてゆっくりと言った。
「女には気をつけな。特に頬に傷のある女にはね。変な気を起こしたら、あんたの命だけじゃ済まないよ。」
「べ、別に変な気を起こそうだなんて思っちゃいませんよ。」
いきなりの展開にマスターは一変にビビッてしまった。
彼女はそんなマスターをじっと睨みつけた後、締め上げていた襟首から手を離した。すると、もとの優しさを含んだ目に戻っていた。
「私はただ、ちゃんと道案内をしてくれってことを言っているだけさ。金を払わないって訳じゃないんだからさ。」
そう言うと彼女は、転がっている大粒のルビーをマスターの手に握らせた。早馬の代金としては充分すぎる程であった。
「ただ、女1人だと思って舐めたことはするなよ。」
彼女は続けた。
「目には目を、歯に歯を。それが掟だ。分かったか?」
マスターは黙って頷いた。
彼女は上体を起こして、やっとマスターから顔を離した。
マスターもふーっと一息つくと、上体を起こした。そしてカウンターの奥に着いている扉を開けると大きな声で呼びかけた。
「ビリー!お客さんだ。さっさと降りてこい。」
扉の奥は通路になっており、だれか慌てて階段を降りているような音が聞こえた。
「だんな。お名前はなんて言うんです。」
マスターが彼女に尋ねた。
「私の名はシェリル。」
そう言って振り向いた彼女から、店に入って来た時のように、また鈴の音がかすかに聞こえた。よく見ると、胸に赤い色の鈴を身につけているのが見えた。
マスターはシェリルという名前に聞き覚えがあった。
(この女性が女海賊のシェリルか。)
現在の賞金首ランキング第1位。世界の中心であると公言してはばからない青の帝国と領海を巡って戦争し、帝国の軍船を何十隻と沈めたという。
その海賊の首領が女海賊シェリルだ。
帝国側もシェリル側も、お互いに領海を侵犯したのは相手側であると主張しているが、シェリル側が帝国の輸送船を新たな獲物とするため、帝国に喧嘩を売ったというのがその筋の見方であった。
喧嘩を売られた帝国はその威信をかけて、“シェリルとその一党”を討伐するため乗り出したものの、そのゲリラ的な戦術と、小回りの利く中型船、さらに予想以上に統率が取れ、恐れを知らずに戦う海賊達に、ことごとく連敗を重ね、とうとう帝国側にその領域を諦めさせたのだ。
それ以降、シェリルは青の帝国の賞金首ランキング第1位として破格の賞金がかけられている。
(陸に上がるといろいろと面倒なことが多いな。)
シェリルは一人気を吐いた。
なぜこんな危険を冒してまで、青の帝国を抜けてここまで来たのかと思うと、自分でも呆れてしまうが、しかしあの男が呼んでいるのであれば、行かずにはいられない。
それは一枚の手紙がその男から届いたからだ。北へ向かうとただそれだけが書かれたその手紙だが、なぜか妙に惹きつけられる。
その男の名前はエバであった。
エバ達は、キッドの馬車に乗って目的地であるシャロムの町に到着した。
町の入り口でエバ達は道路税と町に入るための料金を支払った。
キッド達は税金を支払う必要はなかった。既に年間でまとめて支払っているためだ。
町のメイン通りをキッドの馬車が進んでいく。
メイン通りは結構な人通りで、馬車が何台も走っており、交通の要所として賑わっていた。
この辺りの気候は、大きな川がないせいか非常に乾燥していた。風が吹くと乾燥した砂が舞い上がり、空気が砂っぽく、視界も靄がかかったように見える。建物は木製の簡素なものが多く、ウェスタンの特徴を色濃く出していた。
キッドの馬車は一軒の商店の前で止まった。
すばやくキッドは馬車を降りると、店の中に入っていき、またすぐに出てきた。
「よし、荷物を中に運び入れよう。」
キッドはエバとルーに声を掛けると、3人は麻袋を店内に運び始めた。
ほぼ積荷の運び入れが終わったころ、エバはふと通り沿いのちょっと先にある建物から、髪の毛を掴まれた女性が、上半身裸の男に引きずり出されて来るのが見えた。
男は店先から通りまで女を引っ張り出すと、何か凄い剣幕でその女に対して怒っている。
だが、女も負けていないようで、立ち上がると男と正面から対峙した格好で何か抗議しているようだった。
どうやら、その建物は売春宿らしく、男はその客で女は娼婦であるらしかった。
そのうち、口で勝てなくなったのか、又は怒り心頭で切れてしまったのか、男が女に腕を大きく振りかぶってパンチを喰らわそうとした。
しかし、女はそのパンチを右腕で受けると、その右腕をくるっと回して男の腕を絡めとリ、そのまま自分の方に引き付けた。
とっさのことに反応できなかった男は、そのまま腕を取られてバランスをくずし彼女のほうによろけた。次の瞬間。
パァン!
女は男の右腕を掴んだまま、バランスを崩して避けることもできない男の顔面にハイキックをお見舞いした。
よく見れば、つま先を返した上足底で見事に顎を蹴り抜いている。
エバから見ると、重力に逆らうかのように上に伸びあがった蹴り足と軸足が、見事に一直線になっていて、そのスタイルは非常に美しいと感じた。
顎に蹴りを喰らった男は脳震盪を起こしたのか、その場に倒れ込んでしまった。
しかし、自体はそれだけでは終わらなかった。
どうやら男には仲間がいたようで、いつの間にか店先に出てきていた男3人が、剣を持って店先から通りに出てきたのだ。
(そろそろかな。)
奇妙に思えるかもしれないが、エバは暴力は嫌いだった。
とくに女性や子供に対して暴力を振るうことは絶対に許せなかった。それが、相手の命を奪うことになったとしても。
エバは小走りに、その女のところへ走り寄った。
「行きましたね。」
馬車から様子を見ていたマーリンは、エバの後姿を見ながら呟いた。
「アレンティー、マリーウェザー。一応準備をしておきなさい。」
そう2人の妹に声を掛けると、マーリンは別に何でもないというようにエバの方に視線を移した。
先ほど見事に男を倒したさっきの女も、3人を相手にしてしかも剣を持っているとなると、さっきのようにはいかないようだった。
男3人はじりじりと動きながら、女の背後に回り込むチャンスを伺っていた。
「威勢がいいじゃねえか。俺は強気な女は好きだぜ。せいぜい楽しませろよ。もちろん2階でもな。」
男はわざと下品な笑い顔で言うと、この後どうこの女を料理してやろうかと、妄想を膨らませた。
すると、そこへエバがタタタっと何となしに走りこんでくると、抜刀と同時に妄想男に切りつけた。
「あ、危ない!」
他の仲間が警告を発した時にはもう遅かった。
妄想男は手に熱さを感じたので自分の腕を見ると、手首から先がきれいに無かった。
「ああああああああ!」
呻き声のような叫び声をあげている男を尻目に、エバは近くのもう1人に剣先で突きを放った。
「おっと。」
男はとっさに、バックステップでエバの突きをかわす。しかし、エバの突きはここからが真骨頂。
エバの突きはほとんど力が込められていなかった。
余計な力は剣の動きを硬直なものにさせるし、体を疲れさせる。
エバはただ狙っている1点に剣が到達するよう、相手の動きに調和して剣先を動かしているだけだ。
顔面に繰り出される突きを本能的にバックステップで後ろにかわしたと思った男であったが、エバの剣先は後ろに下がる男の顔面から近づくことはあれ、離れることはなかった。
男はさらに後ろに下がろうにも足の運びが間に合わない。
剣先は柔らかな皮膚を容易く切り裂くと、顔の筋肉に沿ってそのまま頭部深くに侵入していく。
エバはただ、鋭く研ぎ澄まされた剣先の斬り易きに合わせて剣を差し入れているだけだ。
「げべぇ!」
剣が顔面を捉えると、剣の3分の1くらいが顔に突き刺さった。
男は声にならない声を出した。
エバは咄嗟に剣を引き抜くと、男は顔面から血を流しながら地面に倒れ込んだ。
エバはさらに最後の1人にも突きを放った。
しかし、男は突きを避け損なって地面に転んでしまった。そのおかげで、エバの突きをかわすことができ顔に傷をつくっただけで済んだ。
しかし、男には戦う意志はなくエバの目の前で背中を見せると、地面を這うように逃げていった。
逃げていく男を見ていたエバは、自分に向けられた視線を感じて、そっちの方に目をやった。
その視線は、先ほど男に見事なハイキックを喰らわした女のものであった。
エバは改めて、彼女の顔をまじまじと見た。
銀髪に、ちょっと大きめな緑色の瞳をした美人だった。
その瞳は何か心の秘めた思いを写しているような特徴的な眼差しをしていて、その瞳で自分をじっとみつめてくるのでエバは恥ずかしくなった。
恥ずかしくなって視線を下に降ろすと、彼女の衣服がちょっと下着のような薄手のものだったので、エバはいかんいかんと自分を戒めたが、まあ、助けてあげた訳だし見えてしまうのは許されるだろうと、思い直してもう一度良く見てみると、なかなか良いスタイルをしているなと思った。
傍から観るとその姿は、お互いに2人見詰め合って、じっと佇んでいるように見えなくもない。
「助けてくれてありがとう。剣士さん。」
「あっ。いいよいいよ。気にしなくて。」
ちょっと他に気をとられていたエバは、慌てて答えた。
「お礼がしたいから後で店に来てね。」
そう言って彼女は一礼すると、売春宿の中に消えた。エバは彼女の一礼に高貴な感じを受けた。
(後で行ってみようかな。)
エバは行ったらどうなるんだろうとちょっとドキドキしながら、でも彼女のことが純粋に気になってもいた。
(こんなときに相談に乗ってくれるのは。)
エバはふと一人の女性の顔が目に浮かんだ。
ああそうか、こういう時はシェリルに相談するといいかも知れない。早くシェリル来ないかなとエバは思った。
シェリルは若いライダーに案内されて、エバの後を追って、ステインの町からシャロムの町に向かっていた。
若い、と言っても自分とほぼ同年代であろうライダーは、なかなか動きが機敏でしかもよく気が回る男だった。
ライダーはビリーという名前のウェスタン野郎で、対応はそっけない感じがするが、雇い主のシェリルに対しても物怖じせずにはっきりと物を言うところがシェリルは気に入った。
2人は今、馬を休めるため街道の脇で休憩を取っていた。
「ビリー。シャロムの町まではどれくらいだ。」
シェリルは水袋の水を少し口に含むと、木の根に腰を下ろしてチーズをかじっているビリーに尋ねた。
「あと30分くらいです。」
「そうか。」
シェリルは、近くの木に結ばれている、自分が乗ってきた馬を見た。
たてがみや毛並が綺麗に揃えられていて、手入れが良く行き届いている。
しつけも良くされていて、気性も大人しく良い馬だった。さすがにライダーというだけあって、馬にはしっかり手を掛けているようだ。
「いい馬だね。」
「ええ、一番大人しい馬です。あなたみたいに馬に素人でも、掴まっているだけでちゃんと連れって行ってくれる。」
実は、シェリルは乗馬は得意ではなかった。
この馬に乗る時も1人では鞍の上に乗ることができず、ビリーに手を借りたのだ。
その時は、さすがのシェリルも恥ずかしかったが、「どんな荒波でも、乗りこなす自信はあるが、馬となると勝手が違うものだな。」なんて言い訳をしたりした。
ビリーは気を使ってくれたのか笑顔でシェリルを手取り、足取り鞍の上に押し上げてくれたが、内心大海賊の首領が馬に乗れないことを面白がっているに違いない。
まあ、この辺りの馬は体つきが大きく、今まで乗ったことのある馬は結構小さめな馬であったので、勝手が違っているというのもあるかもしれない。
まあ、手を借りたのがビリーで良かった。
もし、さっきあれだけ脅しをかけたマスターに手を借りたりして、自分のお尻を鞍の上まで押し上げてもらうような事にでもなっていたら、それでもってマスターに「まあ船と馬では勝手が違いますから。」なんて、にやにやしながら気でも遣われた日には、恥ずかしくてそのまま馬から飛び降りると、走ってこの町から逃げ出してしまうかも知れない。
シェリルは立ち上がり、馬に近づくとその頭を撫でてやった。
「私を振り落とさないでくれよ。」
シェリルはまつげの長い馬の瞳を見つめながら、優しくお願いした。そして、後ろを振り返ると、出発するためにビリーが立ち上がって、お尻の砂を払っているところだった。
「シェリルさん。そろそろ行きますよ。」
「ああ、分かった。」
ビリーは手馴れた手つきで、木に繋がれた手綱をほどくと、シェリルの横に馬を連れてきた。
「手伝いますよ。」
ビリーはシェリルに向かって、右手を差し出した。馬に乗るのを手伝ってくれるというのだろう。
「ありがとう。だが、さっき教えてもらったし大丈夫だ。」
「船と馬じゃ勝手が違うでしょう。それに、突然馬が暴れてレディに怪我でもさせたら、申し訳ない。」
ビリーはちょっとにこっとしながらそう言った。
(こいつ私に気を遣っているのか。なかなか気が利くことも言える男なのだな。)
レディなんて言われて、シェリルはちょっと嬉しかった。
「じゃあ、よろしく頼む。」
シェリルはビリーの右手を握ると、鐙に足を掛けた。
ビリーが軽く腰を支えてくれたが、今度はさっきよりも楽に乗ることができた。シェリルを馬に乗せると、ビリーは素早く自分の馬に跨った。
「やぁ!」
ビリーが掛け声と共に、馬の横腹に軽く蹴りを加えると、ビリーの馬は並足で街道を進み始めた。
すると、シェリルが何もしていないのに、シェリルの馬も続いて歩を進め始めた。
ビリーが馬を並足から速歩、速歩から並駆け足へ段々と速度を上げると、シェリルの馬もビリーの馬を追いかけるように、速度を速めた。
2人が進み始めて10分もしないうちに、ビリーは馬を止めた。
「どうしんたんだい。」
後ろからシェリルが声を掛けた。
「そこに血の跡がある。」
ビリーが促す方をみると、街道の真ん中に確かに血の跡が見えた。
しかも、それはかなり大量の血が流れたらしく、水溜りくらいの大きさがあった。
また、恐らく死体を引きずったのであろう跡が、その血痕から道端の背丈ほどもある草むらの中まで続いていた。
ビリーはさっと馬から飛び降りると、腰のブロードソードに手を掛けながら慎重に草むらに近づいて行った。
「わっ。」
ビリーは思わず驚きの声をあげた。
「どうだった。」
馬から降りたシェリルもビリーの隣に来ていた。
草むらには2体の死体が転がっていた。一つは顔面が血だらけになっており、もう一体は頭が体から切り離されて別々に転がっていた。
シェリルはビリーを押しのけて死体の横に座り込むと首の無い死体の腕を取った。
指先の間接は固くなっているが、肘の関節はまだやわらかい。お腹を触ってみるとまだ暖かかった。
「まだ2時間と経っていないな。」
次にシェリルは2体の傷口を確認した。
「お見事だな。」
ふっ、とシェリルは笑みを浮かべた。
シェリルがお見事と言ったのは、例えば顔面が血だらけになっている死体で言えば、その傷口はちょうど鼻筋に沿って裂けていた。
顔面というのは骨で覆われていて、ただ闇雲に顔面を突いただけでは致命傷にはならない。
しかし、顔面にも骨に覆われていない箇所がある。それは目、鼻、口だ。
この死体は、鼻筋から剣を差し入れ、鼻腔を通して脳に達した後、頭蓋骨を破壊して後ろに抜けている。
また、頭が切り離された死体を見れば、その切り口が見事に真っ直ぐになっている。
それは、剣自体がよく切れるものであるとともに、斬る際に刃のぶれがなく、まだ刃が良く立っているということだ。
刃が立っているというのは、つまり、ナイフで肉を切る場合であれば、肉に対してナイフの刃を垂直に当ててから、刃を手前に引かなければうまく切ることはできない。
いくらナイフの側面を肉に押し当てて引いても、切れないのは当たり前の話だ。
下手に変な角度で剣を振ってしまうと、骨に刃を取られて折れてしまったり、刃が欠けてしまう恐れさえある。
この目の前の死体の首の切り口は、まさに、まな板に頭を固定して肉切り包丁で一気に切断したかのように見事に切れている。
当然、敵がじっとまな板に横になっていることなど、実際にありえる訳はない。
頭を貫通された死体といい、首をはねられた死体といい、こんな芸当ができる人間をシェリルは一人しか知らない。そう、エバだ。
「これは、エバさんがやったんじゃないか。」
シェリルは、ビリーの口からエバの名前が出てきたので驚いた。
「あんた、エバを知ってるのかい。」
「ええ。エバさんにはいろいろ助けてもらったんですよ。」
ビリーは、自分達ライダーと、ある傭兵グループとの間で、ちょっとしたいざこざが原因で対立してしまい、仲間のライダーの1人が嬲り殺しにあったこと。そして、その仇をエバが取ってくれたこと。また、仇討ちの際の殺し方が、ちょうど目の前の死体とそっくりであること。また、エバの恐ろしいまでの剣の腕前に本当に驚いた。およそそんな内容のことをシェリルに話した。
シェリルは、ビリーのその口ぶりから、エバの剣に対して、恐怖と一緒に憧れを抱いている、そんな風に感じた。
「実はエバは私の友達で、私はエバを追っかけてここまで来たんだよ。」
「そうだったんですか。それであれば恐らく今日にでも会えますよ。」
「本当かい。」
シェリルは嬉しそうな声をあげた。
「ええ、エバさんがステインの町を出たのが昼前だから、今向かっている町で、今日は一泊するはずです。」
「そういうことなら、こんな死体は放っておいてさっさと行こうか。」
「そうですね。」
2人は馬のほうに歩いていくと、馬に跨った。
シェリルもだいぶ馬に慣れてきて、比較的速やかに乗ることができた。2人が先を急ごうと馬を進めようとしたときだった。
チリン、チリン
シェリルの首輪につけられた鈴が鳴った。シェリルは出発しようとするビリーを手で制した。
「ビリー気をつけな。この先やっかいなことがありそうだ。」
「えっ、何があるって言うんです。」
ビリーはシェリルに向かって、分からないという表情を見せた。
「この紅い鈴は魔法が掛けられていて、危険が近づくとさりげなく鳴って教えてくれるのさ。」
シェリルは首の紅い鈴を指で転がした。不思議なことに、シェリルが指でいくら転がしても鈴が鳴ることは無かった。
「本当ですか。」
魔法と聞いて興味を持ったらしく、ビリーが馬に乗ったままシェリルの横に並ぶと、鈴をじっと眺めてきた。

「まあまあ、見た目じゃただの紅い鈴だよ。でも、こいつのおかげで今まで何度も助けてもらっているからね。」
「へぇ。確かに見た目はただの鈴にしか見えない。で、この先何があるって言うんです。」
「さあね、それは分からないな。でも充分注意した方がいいよ。危険はもうすぐのはずだから。」
「じゃあ、充分注意して進みますよ。」
ビリーは周りに視線を配りながら、並足で馬を進めた。すると馬を進めて5分もしないうちに、ちょうどぐねっとした曲がり角をまがったところで、道の先で4人の男達が1人の男を取り囲んでいるところに遭遇した。
「ビンゴ。」
シェリルが呟いた。
「これですか。」
ビリーはシェリルの言葉に半信半疑だったが、とりあえず目の前の連中に注意した。
取り囲んでいる男達はそれぞれ顔が汚く、ガラの悪い印象で、職を失った傭兵か街のチンピラのようだった。
一方、囲まれているのは1人の男であったが、身に付けている素朴な麻の衣服に、赤や緑色の色とりどりの幾何学模様が描かれており、顔にもペインティングを施していて、原始的な生活をしているような印象を受けた。
そして、一番特徴的なのは彼の耳が長くウサギのように伸びていることだ。そう、その男はエルファだった。
「この地方に住んでいる原住民ですね。狩猟をしながら移動生活を送っている部族ですよ。でも何故こんなことに。」
ビリーはシェリルに話しながら分からないという風に、首を傾けて見せた。
男達に囲まれているエルファの男は、激しく殴打された跡が、顔面や裸の上半身にたくさん青く残っていた。口の中が切れているらしく、下にうつむいた顔の半開きになった口から、血液のまじった唾液が地面に向かって糸をひいていた。
周りの男達が、中心のエルファをリンチしたのだろう。
シェリルは、その光景に嫌悪感を覚えた。
シェリルにとって、リンチが行われたこと自体は何ら精神的ショックを受けるものではない。ただ、リンチを受けているのがエルファだということが、彼女に嫌悪感を抱かせたのだ。
シェリルにはエルファの仲間がたくさんいた。
マーリンもそのうちの1人だった。
シェリルは仲間のエルファと付き合う中で、エルファというものがどういう生物がよく分かっているつもりだ。
エルファは自然と共に原始的で文化的な生活を送っている生物で、その性質は至極閉鎖的だ。
人間からちょっかいを掛けることはあっても、逆は無い。
彼女の頭の中では、もう既にエルファが正しくて、男達が間違っているという構図が出来上がっていた。
「おっと、すまねぇな。すぐにどくからよ。」
取り囲んでいた男の中の1人が、シェリル達に気が付いた。取り囲んでいた男達も通る道を開けようと道の端のほうに寄り始める。
「ほら、寝てんじゃねえよ!邪魔じゃねえか!」
エルファの横腹に男の1人が蹴りを入れた。
エルファは唸るような息を漏らすと、体を横にして地面に倒れ込んだ。
すると、先ほど蹴りを入れた男がさらに倒れ込んだエルファの背中に蹴りを入れた。
蹴られたエルファはさらにごろんと一回転し、道の端のほうに転がった。そこにさらに別の男が今度は腹に蹴りを入れる。どうやらエルファを蹴って、転がして、道の端に連れて行くつもりなのだろう。
ビリーがシェリルに“行きましょう”という感じで先を促したが、シェリルはそれを制した。
シェリルは馬から降りて男達に近寄ると言った。
「このエルファが何かしたのか?」
「別にあんたには関係ねえよ。」
男の1人がシェリルの前に立ち塞がると、シェリルを見下ろすように言った。
たしかに身長は男達のほうがシェリルよりかなり上だ。
「何で分かるのさ。私にはエルファの親友がいるんだよ。親友の親戚かも知れない。」
「そんな訳ねえよ!」
男はシェリルの問いにすぐに答えた。答えるついでにシェリルに向かって一歩踏み出して来た。威圧しているつもりなのだろう。
「じゃあ、このエルファの名前を教えてくれよ。」
「・・・・・・・・・・」
男達がお互いに顔を見合わせていた。シェリルはピンときた。
(こいつらエルファ語が喋れないんだな。)
「何だ?名前も分からないのか?名前も分からないのにリンチしていたのかお前らは。」
最後のくだりは屁理屈この上なかったが、男達は思いがけない展開にあっけにとられているようだ。続けてシェリルは言った。
「いいよ、じゃあ私が直接そのエルファに聞くから、そこをどいてくれ。」
シェリルの前に立って道を塞いでいた男も、思わず後ろの男に振り返り顔を向けた。
明らかに動揺している。
男達が皆一番後ろの男に視線を向けているところを見ると、そいつがリーダーなのであろう。
「どうした。どけよ邪魔だろう!それとも、何か聞かれて都合が悪いことでもあるのか?」
男達の視線がリーダーの男に向けられている。
一瞬の沈黙の後、自体を収束させる引き金が引かれた。
「その女を殺せ!」
後に控えていたリーダーの言葉に、今まで凍り付いていた男達3人が一斉に腰の剣に手を掛ける。
シェリルの前で立ち塞がっていた男も、自分の腰の剣に手をやると、一歩後ろに下がりながら腰の剣を抜こうとした。その時だった。
シェリルは、右手を左の腰の剣に手を掛けると一気に剣を引き抜いた。
しかし、シェリルの動きはまだ止まらない。
引き抜いた腕が左の腰から時計回りに円を描くように動くと、立ち塞がった男が引き抜こうとした剣に斬りつけた。
ギィーン!
甲高い金属音と共に、何かが宙を飛んで道端の草むらの中に消えた。
ふと見ると、シェリルの目の前に立っている男の剣が、ちょうど根元あたりからぽっきりと折れて、無くなってしまっていた。
シェリルとエバはよく剣の練習を一緒にしていた。
剣を抜刀してからの動きというのは、開けた土地で戦うことが多かった戦場の兵士にとっても、また支配階級である騎士達にとっても全く重要視されていない技術であるが、相手が剣を抜くより速く斬りつけることが許される、ノールールの世界で生きているエバ達にとっては非常に重要なテクニックだった。それについてシェリルとエバは、よく2人で練習したものだ。
それは、2人があと一歩の間合いで立会い、布を巻き付けた木剣を、抜刀と同時に相手の利き腕に斬りつけるというものだ。
当然スピードは最大だが、加える力は最小にしてお互いに怪我をしないように注意して行うのだ。
もともとシェリルよりエバの方が運動神経が良いためか、練習ではエバの方が先にシェリルに斬りつけることが多かった。
いくら力を抑えているといっても、何度も利き腕を叩かれていると、二の腕が真っ赤に腫れ上がってくる。
シェリルが赤く腫れ上がった二の腕を痛そうに撫でている姿を見て、エバは本当に嬉しそうに笑っていた。
エバが笑っている様子を見て、シェリルは悔しい思いをしたものだった。
だが、ある日それが逆転することとなった。
エバがいくら一生懸命速く動いても、シェリルの方が先に斬りつける事が多くなったのだ。
悔しそうに腕を抑えて痛がっているエバを見て、シェリルは嬉しくてしょうがなかった。
ここぞとばかりに大笑いしてやったものだ。
何がシェリルとエバの違いになったのか、それは、シェリルがエバと対峙した時、シェリルはさりげなく一足分だけ左足を前に出しておき、さらに前に出した左足に体重を掛けておく。
こうすることで、エバとの距離を詰めるのと同時に、エバから見るとシェリルがこちらに浮き出てくるように見えるのだ。
例えば、エバがプレッシャーに負けて先に剣を抜こうとした時、エバはシェリルとの距離が近いため、一歩下がりながら抜刀しなければならない。
しかし、シェリルは一歩も動く必要は無い。シェリルは既に斬る体勢ができあがっているため、そのまま抜刀して斬りつければ良いのだ。
端からみれば足を一歩前に出しているだけで、2人に違いは無いように見えるが、実際には既に斬る体勢に入っていて、エバが動くのを待ち伏せしているシェリルと、そんなことは知らずに必死に早く動こうともがくエバには大きな違いがあった。
勝負は、笑顔で何気なしに立っている状態から既に始まっていたのだ。
先に剣を抜いた方が斬り負ける。これが抜刀術のテクニックの一つめだ。
さらにエバとシェリルの違いで大きいのは、お互いに横に剣を抜刀しているのだが、剣が描く円の大きさが、エバよりもシェリルのほうが小さい円を描いてエバの腕に到達している。
小さい円を描くシェリルの方が、当然エバより速く斬ることができる。
しかし、シェリルの動きはエバと比べて常識から考えれば少々窮屈であるし、力が入らないように見える。
実際にエバもその斬り方は手打ちではないかと抗議したが、シェリルはそれならばと、近くの薪を抜刀した木剣で叩き割って見せた。
人にはそれぞれ自分の力を効率よく伝達できる距離と動きがある。
確かに自分が一番力を引き出せる体勢で斬れば、目標には最大の破壊をもたらすことができる。
しかし、逆を言えばその距離とその体勢でなければまともに剣を振れないということでもある。
さらに言えば相手が実力を出せない距離と体勢で、自分が80%以上の力を出すことができるなら、戦いは決定的なものになる。
シェリルはエバでは距離が近すぎて斬りにくい距離を斬るために、腕を極端に折り畳んだ状態から、左手で鞘を大きく引くと共に、腰もコンパクトに引いて全身で抜刀し、右腕をぎりぎりまで引き付けた状態からやっと折り畳んだ右手を開いていく。
剣は真横ではなくできるだけ立てて袈裟斬りとし、且つ刃が良く立つように気をつける。こういう練習を何度もして、体に覚え込ませたのだ。
当然、体は得意な動きではないため抵抗するし、力も最初は入れられるものではない。しかし、何度も繰り返し行うことによって、体は確実にその動きを記憶させていき、剣に威力が吹き込まれていくのだ。
己の斬り難きを斬る。
シェリルが身に付けた抜刀術の奥義の2つめだ。
もっとも、しばらく練習するとエバもすぐに体得してしまったために、お互いにプレッシャーを掛けながら動けなくなってしまった。
後に下がれば斬られてしまう、しかし前進したところで近すぎて斬ることはできない。
そうなってしまうと、その拮抗した状況を打破するには、さらに高レベルの技術が必要になってしまったのだが。
今目の前でシェリルに剣を折られた男も、気付かないうちにシェリルに有利なポジションを取られてしまい、気付いたときには一歩後ろに下がらなければ斬れない、そんな状況に追い込まれていたのだ。
もっとも、男の持っている剣は刃が大きく、抜くのに大きなモーションが必要であるし、素早く抜刀する為の練習もしたことが無いのか、最初に柄に手を添えることさえ手間取る状態であったため、シェリルには楽に斬り勝つ自信があった。
折れた剣を見つめながら、男は正に電光石火のシェリルの動きに、実力の違いを実感していた。
また、自分の剣を折られて、且つシェリルの剣には刃こぼれの一つも無いことが、持っている剣の格の違いを表している。
男達の持っている剣は、固いものに斬りつければ一発で曲がってしまうような代物だった。
だが、それは別に特別彼らの剣が粗悪な物という訳ではなく、鉄を鋳造して作られた剣は、どんなに良くできたものでも激しくぶつければ曲がってしまうものだ。
それにいくら安物といっても、それなりに高価なものであるから剣は大切に扱わなければならない。
彼らの常識からすれば、相手の剣を叩き折るということは、自分の商売道具が折れてしまう可能性も多分にあるわけで、それを平然とやってみせるシェリルの腕前は、その点についても彼らの常識外に存在していた。
「ビリー私の馬を連れて下がってな。」
シェリルは片手で正眼に剣を構えると、振り返りもせずにビリーに指示した。
「男3人とは上出来じゃないか。」
シェリルは目の前の状況を確認した。
幸いにも道幅が狭く、両側にはススキに似た植物で覆われているため、剣を振り回すには男1人が精一杯だ。だが、プレッシャーに押されて剣を折られた男が後ろに下がってしまったため、今は男3人がその道幅一杯に横並びに並んでいた。これでは、とても剣を振り回せる状況にはなかった。
(もう一押ししておくか。)
シェリルはニヤっと笑みを浮かべると、男達に向かって言った。
「この私に剣を抜かせたんだ。1人は死んでもらわないと気が済まないね。そうだ、3人で相談して1人決めなよ。一番死んで欲しいと思ってた奴をさ。」
3人がそれぞれお互い同士を気にしている様子だが、その内の1人が後ろに控えているリーダーらしき男を気にしているようだった。
しかし、剣を向けているシェリルが目の前にいるので顔を後ろに向けられないでいるようだ。
「決められないんだったら、私が決めてやろうか。」
シェリルは3人の内、後ろのリーダーを気にしている男に剣を向けた。
「あんたはどうだい?そうだ、後ろにいるリーダーに聞いてみようか。リーダー!死ぬのはこいつでいいかい?」
「・・・・・・・」
シェリルは後ろに立っているリーダーに話し掛けたが、リーダーの男は判断に迷っているようだ。
「どうやら、あんたでいいようだね。リーダーも嬉しそうな顔しているよ。」
シェリルは“いつでも切り込むぞ”という感じで剣を微妙に揺らしながら言った。
「この野郎、騙そうたってそうはいかねえぞ!」
剣を向けられた男は、額から汗を流しながら答えた。
「そうだ、テッド!その女はお前を騙そうとしているんだ!お前が最初に斬りかかれ!」
一番後ろで控えているリーダーの男が、シェリルが剣を向けている男に命令した。この場の動揺を抑えようとしているのだろう。しかし、リーダーの言葉に続いてシェリルは言った。
「おやおや、ひどいリーダーだね。あたしにも島に戻れば部下がたくさんいるけどさ、私だったらこういう状況になったら自分が先頭に立つよ。リーダーだったら普通そうするだろう。」
3人の男達は、シェリルの言葉に迷っている表情を浮かべている。
「あんた一体何者なんだ。」
3人の内の1人がシェリルに問い掛けた。
「私の名前はシェリル。海賊シェリルだ。もっとも今は訳あって陸に上がっているけどね。」
続けてシェリルは3人を睨みつけながら言った。
「他の2人も良く聞きな。私も鬼じゃないからね。そのひどいリーダーを差し出すってんなら、あんた達3人は見逃してやってもいい。」
「おい、お前ら騙されるな!はやくこの女を黙らせろ!」
シェリルはリーダーの言葉に被せかけるように続けた。
「判断を間違うな!命を落とすよ!それに・・・あたしの剣は痛いよ。この剣には魔法がかかっているんだ。」
そういうとシェリルは片手で正眼に構えていた剣を、円を描くように回した。
すると独特のヒューンという風切り音を立てながら剣がま円を描く。
すると、円を描く刀身から白く輝く粉がサラサラと舞い、それはまさに剣の残像のように白い円の軌跡を残した。そしてその白い軌跡は、一瞬のうちに粉雪が舞うようにさらさらと消えた。
「ほら、剣を振ると白い粉が舞うだろう。これは氷の粒だよ。私の剣で切られると傷口が凍りつき、冷たいのに熱い激痛が走るのさ・・・ほれ、リーダーが逃げ出したよ!」
シェリルが男達3人の後ろを指差してそう言うと、3人はぱっと後ろに振り返り、リーダーに向かって走り出した。
その様子に慌てて逃げ出すリーダー。
しかし、その逃げ出す様子が、追いかける3人にリーダーの裏切りを確信させることとなった。
リーダーはすぐに3人に取り押さえられると、自分が着ていた衣服で手足を縛られ、道の真ん中に転がされてしまった。
そこへ悠然とシェリルは歩いてくると、転がった男の頬に剣を押し当てた。
「ぎゃあ!」
シェリルはうめくリーダーの頬に数秒剣を押し当ててから、剣を離した。男の頬は皮が剥けてひどい火傷のようになっていたが、血は止まっていた。
「さあ、約束どおりあんた達3人は行っていいよ。あとは私が気の済むまでこいつをいたぶってやるからさ。」
3人は、ここにきてどうしようかという表情になった。
「何しているんださっさと行きな!それとも私の気が変わるのを待つとでも言うのかい。」
シェリルは男達に向かって剣を振り回した。すると、3人はわっと走り出し、その姿を消した。
走り去る3人が姿を消すのを見届けると、シェリルは足元で転がっている男をチラッと見て、側にいるビリーに言った。
「悪いけどビリー、こいつとあのエルファを次の街にまで連れて行きたいんだが。」
「馬の背に縛り付ければ、何とか運べるでしょう。でも、街まで運んでどうするんですか?」
「ガヤンに突き出すのさ。そして、先に逃げた3人もこいつの証言で檻にぶち込んでやる。」
ガヤンというのは正義と法の神であり、その神の教えを実践している信者達は、そのガヤンの法を犯す悪人を捕まえ、法の前で裁く権限を国王から与えられていた。
「さっき見逃してやるって言った3人もですか。」
シェリルの言葉を聞いて、ビリーはちょっとびっくりした表情を見せた。
「当然さ。その為にこいつを生け捕りにしたんだ。」
(始めから逃がすつもりなんて無かったんだ。)
ビリーは思った。
シェリルは、ビリーがちょっと驚いている様子を見て、機嫌が良くなった。
「エルファは馬に載せるにしても、こいつは馬に引きずらせればいいよ。どうせ、ゆっくりとしか進めないだろ。」
シェリルは、足元で転がっている縛られた男の頭に足を乗せながら言った。
「わかりました。」
ビリーは、シェリルに踏み付けられている男を引きずって行くため、鞍に括りつけていたロープを解き始めた。
「ところで、シェリルさん。そのエルファから名前を聞いてみたらどうです。気になっていたんでしょう?」
シェリルはビリーに問い掛けられると、意味ありげな視線をビリーに送った。そうしておいて、さも面白そうにニヤニヤとした笑顔を見せて言った。
「ビリー、残念だけど私はエルファ語なんて喋れやしないのさ。」
「えっ!じゃあ、それも嘘だったんですか!」
ビリーがびっくりした様子で言った。
「まあね。面白いだろ。・・・笑っていいよ。」
シェリルがビリーに向けているその表情は、まさにいたずら大成功といった感じだった。
「はは、はははははは。」
ビリーはちょっと引きつった顔をシェリルに向けながら、笑った。
この人は凄い。剣の腕でも、頭でもビリーは勝てる気がしないと感じた。
そのビリーの様子を見て、おかしさが込み上げてきたのか、シェリルはとびっきりの笑顔をビリーに向けると大声で笑った。
シェリルとビリーはシャロムの町の入口に来ていた。
入口の門は杉の柱と板材を組み合わせたもので、その門から左右に同じく木製の壁が街をぐるりと取り囲んでおり、ハンマーを使用すればものの数分で破壊が可能な代物であったが、それは、逆にこの街が普段から大きな脅威にさらされる環境ではないことを表していた。
南の青の帝国との境界線からは街2つ3つ離れた位置であり、北の神聖王国の首都からもかなりの距離がある。地形は広い平地が広がっており、見晴らしが良く、水は豊富とはいかないが、この街からでも遠くに眺めることができる北山脈群からの雪解け水が地下水となって、街の機能を維持する程度には十分な量が安定的に供給されていた。
街の入口の門の前には、街に入場しようとする者が、道路税と街に入るための入場料を支払うため行列が出来上がっており、入場までにおよそ15分程度はかかりそうな塩梅であった。
入口の門の前には、税を徴収するため4人の男が徴税人としてそれにあたっており、4人の徴税人のうち、1人が街に入場しようとする者を確認し、税金の額を入場者に通知し、1人が徴収し、1人が木の板に切り込みを入れて記録を取っていた。残りの1人はその様子を眺めており、リーダーであることが分かった。
「足12本で12ムーナ、車輪2本で8ムーナ、入場料6ムーナ、占めて26ムーナ。」
道路税は足1本につき1ムーナ、車輪1本につき4ムーナであり、街への入場料は1人につき一律3ムーナであったが、これは相場感としては平均的なものであった。
シェリルとビリーは馬から降りると行列の最後尾についたが、5分もすると自分達の後ろにも行商人と見受けられる人達が列をなしていた。
「これはまた、野盗にでも襲われたのですか?」
後ろに並んでいた商隊の中から、40代とおぼしき無精髭が黒く年季の入った印象を与える男がシェリルに話し掛けてきた。
馬で人を引きずって歩いているシェリル達は周りからの好奇の視線に包まれていた。
「まあね、でも襲われたのは脇道だから、本道を歩いている分には大丈夫じゃないか。」
「ああ脇道の方ですか。安心しました。」
「帰りもここを通るから。ということね。」
「まあそうなんですが、もともとルークスで商いをしておりまして。」
「なるほど。」
ルークスとはエバ達が向かっている神聖王国の名前である。
「野盗はどんな奴らでしたか。人数はどの程度ですか。」
ルークス出身であればちょうど良い。いろいろ話を聞いておこうとシェリルは思った。
「いや、こんな奴が4人。エルファを道の真ん中でリンチしていた。」
シェリルは転がっている男の頭に足を乗せながら言った。
「ふむ。」
男は顎の無精髭を撫でた。癖なのだろう。
「どうした。」
「いや、少人数というのは分かります。この辺りは大きな野盗集団はいませんから。でもエルファをリンチする理由が分かりませんな。」
「そうなんだよな。何か、例えば狩猟地を巡ってエルファと揉めているとか、そんな噂を聞いたことはないか?」
「いや。・・・ないですな。おおよそ半年ごとにこの街を訪れているのですが、聞いたことないですな。」
無精髭の男は少し顎の無精髭をいじって思案した後、答えた。無精髭の男とシェリルの視線が交差する。
「・・・ああ、どうも。私はボワロと申します。」
「私はシェリルだ。ときに、羽振りはどうだい。」
シェリルは男に向かって少し首を傾けると、はにかむような微笑みを見せた。
「景気はまあまあですな。ご存じか分からんがルークスは寒く貧乏で、しかも生活習慣が独特ですから。いわゆる売れ筋の商品が普通と異なるのです。」
「主に何を扱っているんだ。」
「一番は香辛料ですな。これはルークスでも人気がある。サフランやシナモンは王家や貴族の方々に。庶民の方には胡椒、マスタード、ナツメグやタイムが人気ですね。ルークスでは鹿肉を煮込むのですが、いまや香辛料は必需品となっています。実はこれでも香辛料の普及に私も一役買っているんですよ。」
「タイムなら私の故郷でも良く使っていた。ナツメグも。でも肉ではなくて魚だけどね。貝などと一緒に煮込むんだ。塩加減が最も重要なんだけど、タイムを乗せるかどうかで美味しさが全く違うね。」
シェリルの表情がぱあっと明るさを増し、瞳がくるっとした印象へと変わり輝く。
「ほう。ルークスでは魚は食べられませんので、一度食べてみたいですな。どちらのご出身ですか。」
「オーデハーゲンだよ。紫の群島にある都市さ。」
「おお、紫の群島と言えばナツメグの原産地ではないですか。」
「オーデハーゲンでは大々的にナツメグ栽培はやってないんだけどね。」
「でも紫の群島から、よくこんな大陸の奥地まで足を伸ばしましたな。」
「そうだね。・・・ちょっと知り合いに呼ばれてね。」
シェリルは瞳を細めると視線を遠くに反らす、すると瞳は切れ長な印象に変わり物憂げさを醸し出した。
無精髭の男は知らず知らずのうちにシェリルのことを可愛いなと思うようになっていた。
シェリル本人も正確に自覚していないが、顔に刀傷をつけ、物怖じせずサバサバした男勝りの話し方であるのに、顔の表情を見ているとくるくる変わり、どきっとする美しさ、少女のような可愛さ、幼馴染のような懐かしさ、心配したくなる物憂げさを遠慮なしに発散させてくる。このギャップに異性だけでなく同姓でさえも、もっと一緒の空間を共有していたいと思ってしまうのだ。
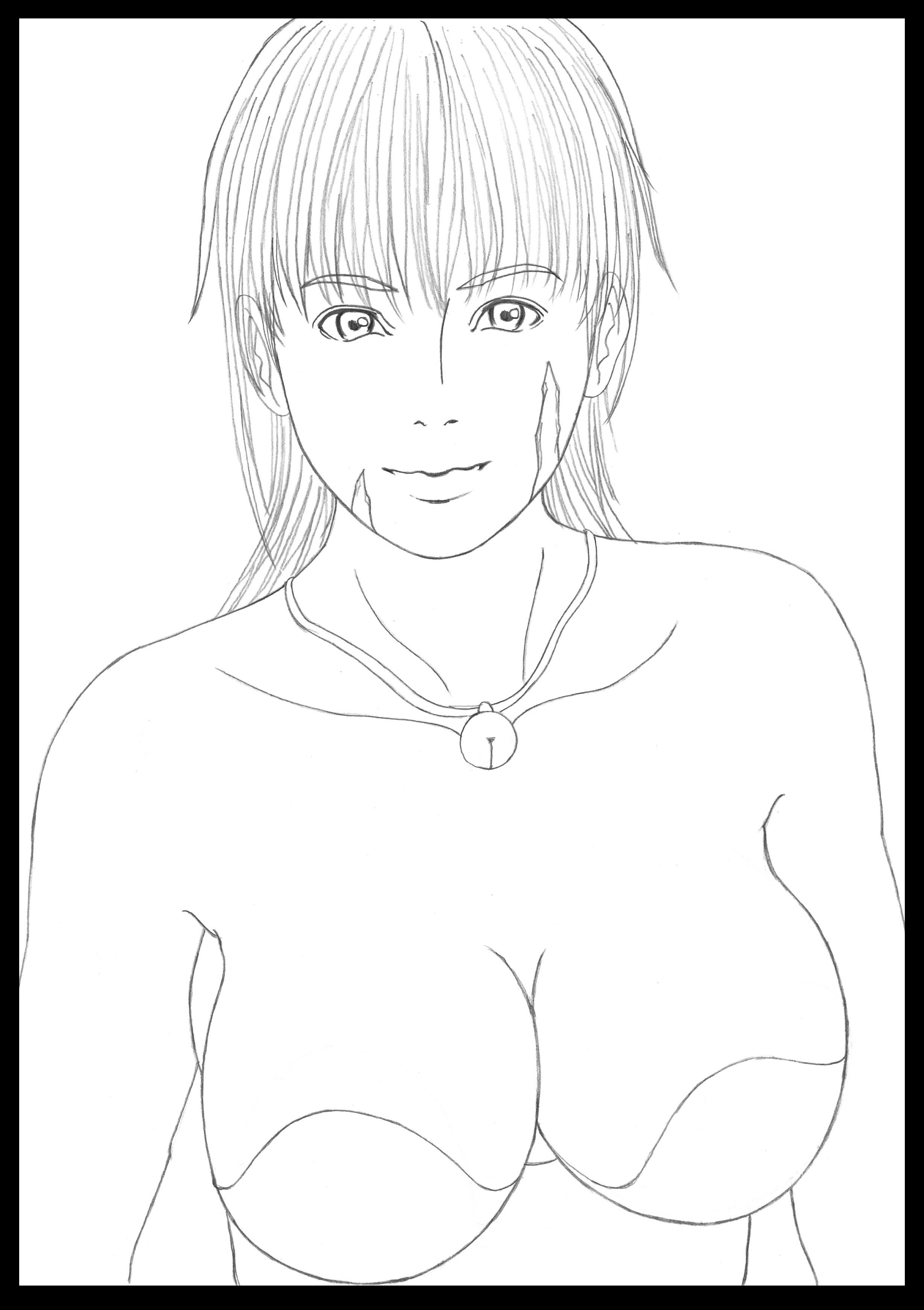
「やはり、お姫様の戴冠式が目当てですか。」
「ああ、そうなんだけど。」
シェリルは戴冠式など知らなかったが、これは知っておいた方が良いとピンときた。
「・・・正直詳しく知らなくてね。知っていたら教えてくれないか。」
といいつつ、表情を見ると、知らなくてちょっとはにかんでいるような、くやしいような表情をしているので、また男は可愛いなと思ってしまい、何か役立つことでも教えてあげたい、自分が役に立つところを見せたいと無意識に思ってしまうのだった。
「ルークスは神様から遣わされた巫女様が女王として代々治めているのですが、今年の夏にお姫様が女王となる戴冠式が行われるのですよ。」
「噂には聞いていたが、女王が亡くなると一旦神の御許に召された後、再び地上に舞い戻って来るのだったな。いくつで戴冠式を迎えるのだ。」
「18です。」
「成人の時期とは違うのだな。」
「成人は12ですが、その後修道院を3年。神凪の3年を経て18歳で戴冠を迎えるのです。」
「女王が不在の間は誰が国を治めるのだ。」
「形式的には巫女は存在しているので巫女が治めていることになっているのです。実質的には女王に仕える四司祭長がいますから、彼らが国を取り仕切っているのですがね。」
「四司祭長というと、ガヤン、ペローマ、サリカ、ジェスタの青の四大神のことか。」
「そのとおり。」
「ガヤンの教派は。」
「教派ですか?」
「古典派とか新興派とか。」
「そうですね。原理派ですね。ルークスは閉鎖的な国ですから、教義について対抗する考えのようなものは出てきていません。がちがちの原理派です。」
「司祭長の名前は。」
「ゴールディ伯家が代々ガヤンの司祭長を務めています。まあ、世襲ですね。」
「なるほど。良く分かった。・・・良く知っているな。」
シェリルはボワロに微笑んだ。
「戴冠式は国で一番盛大な神事ですよ。ルークスでは温かな時期が夏を含め3ヶ月しかありませんが、その3か月の間中お祭りをやります。市場も開かれますし、劇場や闘技場も開かれます。そして最後に戴冠式。皆、雪や純粋さを表す白い布でできたサーティーンという服を着て、雪の城にお姫様が入っていくのを見送ります。戴冠式が終わると花火が上がります。お知り合いもそれでルークスにお招きになったのでしょう。」
「それで積み荷に大量の布地があるんだな。」
シェリルはボワロの商隊が率いている荷車のいくつかが、沢山の布地が積まれているのを確認した。
「ルークスには毛皮はたくさんあるのですが、布が作れませんから青の帝国のシルクと交換してきたのです。」
「シルバーウルフだね。“War with the Wolf”。ルークスは狼との闘いの歴史が有名だからね。」
「ルークスの狼は本当に恐ろしですよ。村を襲うんですから。奴らは家畜を襲うだけではないんです。誇り高くて、自分達の縄張りを侵すものを許さない。たとえ相手が人間であっても夜中に集団で襲ってくる。」
「その狼と闘う戦士、“スパイクス”も蛮勇さで有名だね。」
「よくご存じですね。狼の毛皮を被り、スパイクの着いた丸盾と三つ又の槍“トライデント”を使う。帝国がルークスに進撃した際もその勇猛さで震え上がらせたらしいですよ。」
「いまでも帝国との小競り合いなんかはあるのか。」
「いや、今は聞いたことがないですね。でも帝国のスパイ狩りは行われているみたいですが、難しいみたいですね。」
「難しいというのは何が難しいのだ。関所で止めてしまえば良いのではないか。」
「いや、そう簡単にはいかんのです。ルークスには全ての神様の神殿があって、全ての信者の参拝のために開かれているのです。たとえ、帝国の者であっても、参拝が目的であれば止めるという訳にもいかんのです。」
「そこで、街の中で怪しい動きをしている者を見つけて捕まえていると。」
「そういうことです。」
「シェリルさん、順番が来ましたよ。」
ビリーがシェリルに声を掛けた。ようやく街に入る順番が回ってきたようだ。
「シェリル嬢、良かったら今夜一緒に食事でも。」
ボワロがシェリルに声を掛ける。
「ありがとう。でも今夜は先約があるのでね。また、機会があれば。」
シェリルはボワロに笑顔を返すと、徴税人達の方に向きを変えた。
シェリルは道路税2ムーナと入場料3ムーナ計5ムーナを徴税人に支払った。
馬に引き摺らせてきた男の分は、男が腰のベルトに縛り付けていた財布の中から払った。男の財布の中には数日暮らしていく程度の金しか入っていなかった。
ビリーは徴税人に木札を見せていた。すると徴税人は木札の裏に切り込みを入れていた。
シェリルの紅の鈴は徴税人達に対して鳴ることはなかった。
「バーク。またやらかしてんのか。本当に馬鹿なんだなお前。」
徴税人の1人が道に転がされている男の頭を足でぐりぐりと踏みつけながら言った。
「あんたこいつのこと知っているのか。」
シェリルは徴税人の1人に聞いてみた。
「知ってる?知ってるというか馬鹿だよ馬鹿。クソ馬鹿だよ。」
お前も相当頭弱そうだけどな。シェリルはそう思いながらももう少し粘ることにした。
「こそ泥でもやっているのか。」
「そんな訳ねえだろう。こいつに泥棒の技なんてねえよ。ただのチンピラ。街の外で弱そうなのを襲ってるクソ野郎だよ。」
シェリルは想定どおりの回答だと思った。やはり、問題はこいつにエルファを襲わせた誰かなのだ。
シェリルはバークをガヤンに引き渡すため、ビリーの案内でガヤン神殿に来ていた。
ガヤン神殿と言っていも、周りの木製の建物と大して変りがあるものでないが、表にガヤンを象徴する蜘蛛の網のような看板が出ているため一見して分かるようになっていた。
信者が参拝するための社殿の隣に、ガヤンの神官が詰めている詰所があり、詰所の軒先には椅子にどかっと座って足を組み、談笑している男が二人いた。男たちは胸に蜘蛛の網のような紋章をつけており、ガヤンの神官であることが解った。
シェリルは紅の鈴が鳴らないことを確認してからガヤン神殿に馬を進めた。
「仕事を持って来てやったぞ。」
シェリルは軒先の2人に声を掛けた。ガヤン神官は立ち上がりもせずに引き摺られているバークに目をやると、バークに向かって話しかけてきた。
「今度は何をやらかしたんだバーク。」
「まさか女を襲って逆に掴ったんじゃないだろうな。」
ガヤン神官は馬鹿にするように笑った。
「おいおい、笑いごとでは済まないかもしれないぜ。」
シェリルがキッとした視線を送ると、シェリルの勢いに呑まれたガヤン神官は笑うのを止めた。
2人のガヤン神官のうち1人は30代程度の顎髭を小奇麗に整えている男で、この詰所の責任者“神官長”であろうと思われた。残り1人は20代前半の無精髭の男で若いのにおでこが広い男だった。
2人のガヤン神官はバークを奥の拘置用の檻に収容し戻って来ると、シェリルの話を聞くため執務室のテーブルについた。テーブルには、シェリルと神官2人の他にビリーがついた。例のエルファは執務室端の床に横にしてあった。
「私は神官長のバクウェル。こっちが部下のルードです。じゃあお話を伺いましょうか、お嬢さん。」
神官長バクウェルがシェリルに向かって口を開いた。
シェリルは、シャロムへ向かう脇道で、まず2体の死体があり争った形跡があったこと。また、バーク達がエルファをリンチしているところに出くわし、バークを捕えてここまで連れてきた経緯を話した。
もっとも、男4人をどうやってやりこめたのかについては詳しくは話さなかったが、ビリーが証人になってくれたおかげで神官達はシェリルの話を信じたようだ。
「バーク達に襲われ、捕まえてここまで連れてきたくだりは分かっただろう。問題はバーク達がなんでエルファをリンチしていたのか。」
「たまたまエルファがバーク達と出会ってしまったというのは。」
シェリルが人差し指を立てて左右に振る。
「あの辺りに獲物がいると思うか。この付近で一番近いエルファの居住地は?」
「確か街を東に行ったところにエルファの森がある。行くのに5日程かかるが。」
「つまりこの付近でたまたま単独のエルファに出くわすという可能性はまずない。」
神官長バクウェルが指でテーブルをリズミカルに2回叩いた。
「誰かが意図的にエルファをリンチにした。」
「そのとおり。その誰かは心当たりがあるんじゃないか。さっき外で話していたところだとバークがここに来るのは初めてという訳じゃないんだろう。」
「ヤドゥイカ子爵か。」
2人の神官が顔を合わせる。
「そいつは誰だ。」
シェリルが2人に顔を近づけると声を抑えながら、しかし強い口調で聞いた。
「この街を治めている貴族だ。なぜかバークが悪さをすると、その罰金をヤドゥイカ子爵が肩代わりしている。」
「そいつは厄介だぞ。それにさらに危険性が増すことになるな。」
神官の2人はまだ良く分からないという顔をしている。
「例えば、そこの床でくたばっているエルファが自分の居住地に傷だらけのまま戻ったとする。そして、人間達にどんなひどい仕打ちを受けたか話したとする。それがこの街の領主がやったことだとなれば。」
「戦争になるとでも言いたいのか。」
「そうなったときに、この街の薄い壁で守り切れるか。」
シェリルが喋り終えるとその場の誰もが口をつぐんだ。
「まさかな。」
「じゃあ、私が言った可能性を否定できるか。」
また、神官の2人は黙り込んだ。そしてしばらく沈黙が続いた後、神官長バクウェルがつぶやいた。
「しかし、否定できる可能性は残っている。」
「そのとおり。」
シェリルが答えると、神官長バクウェルとシェリルが目を合わせる。シェリルは続けた。
「1つは我々人間側の方に道理があること。これは子爵に確認してみれば分かるだろう。何のためにこんなことをやらせたのかと。もう一つはあのエルファが重要人物でないこと。例えば、エルファの森から追放された者で、リンチされてもエルファと人間の関係に悪影響を及ぼさないのであれば問題はない。これはエルファに話を聞いてみるしかない。」
「ようやく何をすれば良いか分かってきたよ。ありがとうお嬢さん。確かに危険な芽は小さいうちに摘んでおくのが良い。それに、それは我々の仕事だ。」
神官長バクウェルがシェリルに感心したような表情を見せた。
「でもどうします。子爵には当たれば良いとしても、エルファに話を聞くのは。この街にエルファ語が話せる人がいますかね。」
部下のルードが神官長に問いかけると、神官長は首をかしげた。
「それなら、私の知り合いのエルファがちょうどこの街に来ているはずだから、こっちで当たってやろうか。」
シェリルはバクウェルに提案すると、バクウェルは少し考えたところでシェリルの目を見て答えた。
「そうか。分かった。じゃあお嬢さんにお願いしてよろしいかな。」
「分かった。それじゃあ何か分かったら連絡する。それではまた。」
シェリルはようやく笑顔を見せると神官長にそう答えた。そしてビリーに行くぞと目配せすると、さっさと詰所から出て行った。
神官長バクウェルはシェリル達が見えなくなるまで見送っていたが、とうとう見えなくなると、また軒先の椅子にドカッと足を組んで座った。
「笑顔が可愛いじゃねえか。」
シェリルの笑顔の余韻に浸りながら、持ち込まれたこの問題について思案を巡らせるのだった。
襲われていた娼婦を助けたエバは、何事もなかったかのようにキッドとルーの元に戻って来た。
いきなりのことでじっと成り行きを見守っていたキッドとルーは、エバがあまりに落ち着いていて、さあ早く小麦の袋を運び入れようじゃないかという表情に呆気に取られてしまっていた。
「騒がせてしまったようですまない。さあ、残りの小麦を運び入れよう。」
エバは2人に気を使って声を掛けると、荷台の袋に手を掛けた。
エバ達3人は全ての袋を運びこむと、エバはキッドとルーに相談し宿屋を紹介してもらった。
宿を確保したものの夕食にはまだ時間があったので、エバが体を動かしたいと言い、それにアレンティーやマリーウェザーも一緒に行くことになり、それではとキッドやルーが街の近くにある“じいさん岩”に案内することになったため、仕方なくマーリンも付いていくこととなった。
エバ達は大通りを抜けて街の北側の出口に来た。
荷車が2台は通れる大きさがあり、木製の観音開きの門だった。
門の内側に門番が2人木製の背もたれのないベンチに座っており、門の外には徴税人達が街に入ろうとする者の対応に追われていた。
キッドが門番に散歩で街の外に出ることを告げると、門番はエバ達を通してくれた。
エバ達5人は街から北へ続く道を歩き始めた。
エバとキッドを先頭にしてルー、マリーウェザー及びアレンティーが続き、最後尾をのろのろとマーリンが追いかけた。
しばらく行くと東に向かう分かれ道があり、エバ達は道幅が荷車が1台通れるほどの分かれ道に入った。
「この道はどこまで続いているんだ。」
「この先にいくつか農村があるんだが、そこに続いている。」
エバの問いかけにキッドが答えた。
「途中にこの辺りを治めている領主の屋敷もあるぞ。」
ルーが補足する。何だかルーの口調が上気づいていて、機嫌が良さそうだった。
「じいさん岩ってどんな岩なのかしら。」
マリーウェザーがルーに話しかけた。
「それは行って見てみた方がいいよ。あと、そこからの眺めが最高なんだ。」
ルーが楽しそうに答えた。
「そうなの。それは楽しみだわ。」
マリーウェザーはどんな景色が見られるんだろうとワクワクした。
旅をしていて一番の楽しみは、やはり見たこともない自然の風景が見られることだ。
それに旅は世界と自分の関係を正しく認識する助けになると兄のマーリンは言っていた。それは本当だと思う。
エルファの森に籠っていたら、世の中がこんなに争いに溢れ、飢えや病気でいつ命を落とすかも分からない世界だとは知らなかっただろうし、また、そんな世界に立ち向かおうとしている人達が少なからず存在することも知らなかっただろう。
唐突に襲ってきた戦争や疫病などの災厄に訳も分からず薙ぎ倒され、死ぬ運命であったかもしれない。
また、それに、兄マーリンは故郷の村では魔法には長けていたが変人扱いで居場所はなかったし、両親は行方不明で家は貧乏であったので、故郷にいてもこき使われるばかりで将来に希望もなかったから、マーリンが故郷を捨て旅に出ようと言った時には特に躊躇はなかった。
「ルーさんも楽しそうですね。」
ルーの楽しそうな表情に当てられて、マリーウェザーも楽しそうな口調で聞き返した。
「私にとっては特別な場所だから。」
ルーは目を細めると柔らかな眼差しでマリーウェザーを見た。
「それは俺にとってもそうさ。」
前を歩いていたキッドが顔だけをルーに向けながら声を掛けた。
そのやり取りを聞いていたエバは、キッド達が孤児で身寄りがない身であり、危険なライダーとして安く働かせられるため、ステインの速達屋に引き取られたのだと話していたことを思い出していた。
「マリーウェザーさんはずっと旅を続けているんですよね。出身はどこなんですか。」
ルーがマリーウェザーに訪ねた。
「グラダス半島って知ってる?その半島の西側にラジスの森という広大な森があるんだけど。出身と言えばそのラジスの森になるかな。」
「グラダス半島なんて初めて聞いた。どこにあるの。」
ルーは興奮した様子でマリーウェザーに訪ねた。
「青の帝国は分かるでしょう。その先にゼクス共和国があって、さらにその先にカルシファード候国という島国があって、そこから海を渡ったところにある半島がグラダス半島よ。」
「へぇ。凄いな。そんな世界があるなんて知らなかった。」
「でも、私達はゼクスとかカルシファードを経由して来たのではなくて、船でリアド大陸の南側を大陸に沿ってぐるっと周る、南周りの大陸一周航路で来たんだけどね。」
ステインの街を中心にそこに繋がる2、3の街の世界しか知らないルーにとっては、マリーウェザーの話は知らないことだらけで非常に魅力的だった。
自分が知らないだけで、この世界には自分の知らない人々や世界が想像できない程広大に存在しているのだ。
「グラダス半島はどんなところなの。」
「そうね。私が一番住み心地が良かったのは、鬼面都市バドッカね。街全体が鬼の顔になっているのよ。」
「何それ凄く面白い。目とか鼻とかどうなっているの。」
「目とか鼻とか口とかに皆住んでいて、周りを取り囲んでいる山々が顔の輪郭になっているのよ。私達は口に住んでたんだけど。」
「そうなんだ。」
「街には人間もいるけど、エルファもドワーフも沢山いるし、ミュルーンもいるのよ。」
「ミュルーンって何。」
「鳥のような顔と体をしているんだけど、凄くおしゃべりでお金にうるさいの。」
「何それ面白い。」
「街自体が新しくて、他の国から流れて来たような人達が多いの。私たちみたいな流れ者のエルファも多くて。エルファの裁縫師やドワーフの鍛冶師や細工師、ミュルーンの配達屋なんかいるのよ。」
キッドはルーの話し方が、普段の男のような口調ではなく、年頃の女性同士が楽しくおしゃべりしているような口調になっていることに気付き、嬉しい気持ちになった。
「そうかミュルーンは配達屋なのね。見てみたいわ。」
「バドッカは山肌に造られた街だから、目と鼻と口がそれぞれ高さが違うの。ミュルーンは空が飛べるからバドッカの配達業はミュルーンが独占しているわ。」
「空が飛べる配達屋なんて、そんなのが来たらライダーなんて廃業ね。」
「そうとも言えないわよ。」
少し後ろで2人の話を聞いていたアレンティーも話に入ってきた。
「実はミュルーンは長い距離は飛べないのよ。街の中ならともかく街と街の間を運ぶのであれば馬の方が速いと思うわ。」
「そうなんだ。それを聞いて安心したわ。」
アレンティーはルーにニコッとした表情を見せると続けた。
「それにミュルーンがライダーになったら、運んでいる間中ミュルーンのおしゃべりに付き合わなくちゃならなくて大変なことになるわよ。」
「私、仕事中は無駄口を聞かないことにしているのよ。やっぱりミュルーンよりもキッドの方が良さそうね。」
「おい。ミュルーンと俺を比べるなよ。大体ミュルーンは鳥なんだろ。なんで俺のライバルが鳥なんだよ。知らないよ。」
キッドの不貞腐れた態度にルーやマリーウェザー達の弾けるような笑い声が重なる。
幸せな時間だ。
この時エバとマーリンは同じことを思った。この幸せな時間を守るために自分達は戦っているのだ。
そして2人は分かっていた。自分達のような流れ者はいつどんな横暴な力によって理不尽に人生を奪われるかも知れない事を。
だから、エバとマーリンはこういう幸せな時間ほど、自分の中の警報が鳴り響く。自分達を脅かす脅威がどこかに顔を出してはいないか。そして、その脅威を事前に潰していくのは自分の仕事だと。
「あの丘の上に見える建物は何だ。」
エバは進行方向北側に見える丘の上に建物が建っていることに気付き、キッドに尋ねた。
「ああ、あれがこの辺りを治めている貴族の屋敷だよ。」
キッドがエバに答えた。すると後ろからマーリンが何となしに近づいて来るとキッドに尋ねた。
「キッド。さっきこの道の先に農村がいくつかあると言っていただろう。その農村のさらに先にエルファの森があるんじゃないか。」
「ああ、あるよ。ちょっと離れてるがな。行くのに4、5日かかると思う。」
それを聞いたマーリンは、コートの内側にいくつかついているポケットから黒い玉を取り出した。
「エバ、これを真上に高く投げてくれよ。」
「分かった。」
マーリンはエバに黒い玉を渡した。エバは玉を受け取ると、みんなから少し距離を取った。
「何で自分で投げないんだ。」
キッドは独り言のように呟いた。
「お兄様が投げると、上どころか地面に激突する恐れがあるからですわ。」
マリーウェザーがキッドの疑問に答えた。
「そういうことか。相当な運動オンチだな。」
「でも冗談なんでしょ。」
ルーが思わず口を出して来た。
「前にお兄様は、石を川に向かって全力で投げたら、なぜか目の前の河原の石に思いっきり石を叩きつけて、その石が跳ね返って来てびっくりして尻餅をついたことがある。」
アレンティーが笑顔でルーの疑問に答えてくれた。
「2人共。恥ずかしいからもう止めてちょうだい。お願いだから。」
マーリンが軽い口調でそういうと、ちょうどエバが黒い玉を真上に高く投げ上げた。黒い玉は一番高く上がった所で、なんと空中で停止した。
「玉が止まった。」
「本当だ。浮いてる。」
キッドとルーが驚きの声を上げた。
「お兄様が魔法を掛けたのですわ。」
「マーリンは魔法使いなんだ。」
アレンティーとエバが驚いている2人に説明した。
「みんな・・・ちょっと待っててね。」
マーリンはそういうとじっと黙りこんだ。
「魔法なんて初めて見た。」
「私も。」
キッドとルーはじっとしているマーリンの様子を窺った。
マーリンは、覗き込んでいるキッドとルーを見ながらも、どこかあらぬ方向も見ているような様子で、たまにぼそぼそと独り言をつぶやいていた。
「恥ずかしいから、じっと見ないでよ。」
キッドとルーにじっと覗きこまれて、さすがに恥ずかしくなってマーリンは言った。
「魔法使いって、杖をこう振って魔法をかけるんじゃないんだ。」
マーリンから顔を離したルーがマリーウェザーに尋ねた。
「杖とは限らないけど、手足や体を動かしたり、魔法の言葉を唱えたりするのが普通ね。」
「マーリンが異常なんだよ。普通は魔法を掛けてますよ、という感じで分かるのに、マーリンの場合全く分からない。普段からあまり口数が多い訳でもないし、運動オンチでじっとしていることも多いから、魔法を掛けているのかただ妄想に浸っている異常者なのかさっぱり分からない。」
マリーウェザーとエバがルーに説明する。
するとさすがにエバの説明に我慢がならなくなったのか、あらぬ方向を見ながらマーリンが口を開いた。
「あのね。魔法に集中しているからって、反論ぐらいできるんだからね。大体エバに異常者扱いされるのは非常に心外だよ。異常さでいけば僕は君には到底及ばない。」
「謙遜する必要はないさ。」
エバが肩をすくめる。
「いやいや、君には負けるさ大剣士殿。」
マーリンが答える。
「そんなことはないさ、大魔法使い殿。」
「いやいや格が違うよ、恐怖の剣王様。」
「本音を言えよ暗黒の魔法王。」
「じゃあ本音で言わせてもらうよ、リアドの殺戮王。」
「こっちも本音だ、闇の征服者。」
「破壊王。」
「変態エルファ。」
「変態だと、この百万人殺し。」
「数なんか覚えてねえよ。妹べったりの友達作れない陰湿エルファ。」
「私はそれで結構だ。」
エバとマーリンは別に興奮している様子でもなく、淡々と、ただリズムを楽しんでいるように言葉をやり取りしていた。
マリーウェザーとアレンティーは、いつものことというように聞き流している。
その様子を見ていたキッドとルーはお互いに顔を見合わせて笑った。
「みんな。ちょっと聞いてくれ。」
マーリンがじっとした状態のまま、皆に話しかけた。
「要はこの先に敵がいる。4人だ。シャロムの街へ馬車で向かっていたときに襲ってきた連中と目的は同じだろう。」
「分かったマーリン。詳しく教えてくれ。」
マーリンはエバに向かって頷くと話し始めた。
「この道はずっと雑草が生い茂った野原が続いているが、しばらく進んだところでゆるやかに左に曲がっている。その曲がっている内側に少し開けたところがあるんだが、そこに4人の男が座っている。」
「そいつらの武装は。」
マーリンの説明にエバが尋ねた。
「一番危険なのはクロスボウを持っている奴が1人いる。次に槍を持っているのが1人。残りの2人は剣を腰に提げている。」
「でどうするんだ。」
エバがさらに尋ねた。
「こちらから仕掛ける。この腰まで茂っている雑草の中を、ここから左回りで進んで行けば奴らの背後に出られる。完全な不意打ちになる。今の我々は圧倒的に有利な立場にある。」
「分かった。」
エバが簡潔に答えると、マリーウェザーもアレンティーも覚悟を決めた表情になった。
その様子を見てルーは、以前にアレンティーが言っていた、お兄様がそう言ったからという言葉を思い出して、そういうことかと納得していた。
「ちょっと待ってくれ。俺にはさっぱり分からないことだらけだ。大体、そいつらを避けて行けばいいだろう。」
キッドが分からないというように両手の平を挙げてマーリンとエバの間に割って入ってきた。
「キッドが分からないのは良く分かる。あいつらはあの丘の上に建っている館の領主に雇われている。例え一時的に避けてこのままじいさん岩にむかったとしても、奴らは報告のために領主の館に向かう。その時に鉢合わせとなる可能性が高い。」
マーリンがじっとしたままキッドに淡々と説明する。
「だったら、じいさん岩に行くのを止めれば良いだろう。」
「奴らは領主の館に報告したあと、シャロムの街の住処に戻るだろう。すると今度はシャロムの街で鉢合わせとなる可能性がある。」
「ちょっと待ってくれ。大体鉢合わせしたからといって、なぜ襲われると分かるんだ。」
「奴らが領主に言われているのは、エルファを生け捕りにしろということだ。また、それ以外については、いつもの獲物にすれば良いとも言われている。つまり金品を奪って殺害するなり人身売買するなりといったところだ。よって、私やマリーウェザーやアレンティーが奴らの目に留まれば、奴らはどこでも生け捕りにしようとするだろう。」
マーリンはずっと同じ調子で淡々とキッドの問いかけに答えた。
キッドはマーリンの言葉に唖然として声も出なかった。
マーリンは続けた。
「あとは戦略的な理由だ。この危機を避けたとして、結局後でご対面するとなった場合、今のようにこちらが圧倒的に有利な立場とならない可能性は高い。そうであれば、危険性が低い今こそ対処しておくべきだ。」
マーリンの説明を受けてキッドは黙り込んだ。確かに理屈は分かった。だがキッドは、胸の中がもやもやする感覚があり納得できなかった。
「納得できないのは分かる。全部マーリンの妄想だからな。」
エバがキッドの肩を叩きながら話しかけた。
そうだそれだ。キッドはなぜ胸の中がもやもやするのか理解した。それはエバ達がマーリンが話したことを何の疑いもなしに信じていることだ。
しかもマーリンが言っていることには何の証拠もないのに。
「妄想ではない。魔法だ。全く失礼だな。いつものことだが。」
マーリンが口を尖らせて反論する。
「キッド安心しろ。マーリンの妄想は当たる。俺が保証する。」
エバはまたキッドの肩をポンポンと叩いた。
そういうことかとキッドは思った。
エバはマーリンを信頼しているのだ。そしてこれまでもそうやって生き残ってきたのだろう。だったら、俺も信頼してみるしかなさそうだ。
「エバ。私は眼を操りながら行く。足元の注意がおろそかになるから、手を引っ張って先導してくれ。それから、キッドは私と一緒に、ルー、マリーウェザー、アレンティーは少し距離をおいて後からついてきなさい。」
「妹達も連れて行くのか。」
マーリンの指示にキッドが少し驚いた様子で聞いた。するとマリーウェザーがキッドの問いかけに答えた。
「私達は戦いであっても、いつもお兄様と一緒にいるって決めているの。」
「それに二度と後悔はしたくないし。」
マリーウェザーに続いてアレンティーも自分に言い聞かせるようにキッドに答えた。
「私も行くわ、キッド。」
ルーがキッドに向かって微笑んだ。
「それじゃ行くぞ。」
エバはマーリンの手を引きながら、農道から外れて背丈程まで茂った雑草の中を掻き分けながらゆっくり進み始めた。
エバ達はマーリンの指示に従って40分程ゆっくり茂みの中を進んでいた。
「この辺りで止まろう。」
マーリンは4人の野盗から30m程の距離のところまで来て全員に指示した。
4人の野盗達は少し開けた野原をうろうろしたりしていたものの、通りかかる地元の農民達に手を出すこともなく大人しくしていた。
今、その4人のうち2人は地面に転がっている倒木に座って、マーリン達にお尻を向けていた。
残りの2人は別の離れたところで地面にしゃがみ込み、何かの草をかじりながらおしゃべりをしていた。クロスボウと槍を持っているのは倒木に座っている野盗だった。
「エバ、キッド、状況を説明する。」
小声でマーリンはエバとキッドに話しかけた。
「この先20m程行くとこの茂みは終わる。そこから10m程先に2人の男がこちらに背を向けて倒木に座っている。1人がクロスボウで1人が槍だ。その座っている男達から見て右方向に7、8m行ったところに残りの2人がしゃがみ込んでいる。」
「状況は分かった。作戦は。」
エバが問いかける。
「私が茂みの出口辺りを魔法で雑草がざわつく音がしないように静かにしておくから、エバはその静かな空間から飛び出して4人を殺害してくれ。いつ飛び出すのかはエバに任せる。」
「分かった。」
「クロスボウを持っている奴は頭を残しておいてくれ。死ぬ前に聞きたいことがある。」
「分かった。じゃあ行くぜ。」
エバはこれまでどおりゆっくりと雑草を掻き分けながら進み始めた。
「俺は何をすればいいんだ。」
キッドがマーリンに尋ねた。
「私と一緒にエバの後ろからついて行って、成り行きを見守りましょう。でも10秒かからないと思いますよ。」
マーリンは何でもないというようにキッドに答えた。
エバはしばらく雑草を掻き分けて進んで行くと、不意に全く音がしない空間に入り込んだことに気付いた。
(そろそろ出るな。)
さらにゆっくり進むとちょっとした野原が見え、マーリンが言っていたように正面に倒木に座っている2人、右手にしゃがみ込んでいる2人、合わせて4人の野盗が確認できた。
(情報どおりだな。行くか。)
エバは全く音を立てずに雑草の中から掻き分け走り出すと、急に風の音が耳に戻ってきた。
「あっ、あれ。」
右手の2人のうちの一人がエバに気付いたが、良く分からない言葉を発しているうちに、エバは正面の二人の元に到達していた。
ビュッ
エバが剣を横に払うと、倒木に座っていた野盗の1人の首がまるで雑草のように刈り取られ、小さな放物線を描いて地面に落ちた。足元には撃つことができなかったクロスボウが置かれていた。
座っていた野盗の1人は、右手の仲間が変な声を出したのに気付き、ふと左側に顔を向けると、エバに刈られた生首がちょうど目の前を落ちて行くところだった。そして、その生首が視界から消えるとほぼ同時に、エバの剣が目前に迫っていた。
!!
何も言うこともなく、もう一人の野盗もエバの剣が目と脳を貫通し、そのまま頭蓋骨を破壊して剣先が頭の後ろから飛び出てしまった。
人間をバーベーキューにするために串刺しにしているような、そんな残酷な風景に野盗達も唖然としてしまった。一体俺達の目の前で何が起こっているのだろうか。こんな農村で何に巻き込まれてしまったのだろうか。
「悪魔だ。」
野盗の1人が思わず口走った。
エバは串刺しにした男から剣を引き抜くと、2人に向かって何となしに駆け寄った。
「くっ、来るな。」
慌てて2人は腰の剣を抜き、駆け寄るエバを待ち構えた。
しかし、次の瞬間また1人野盗の首が宙を飛んでいた。
見えない。というか何をしているのか分からない。
最後に残った野盗は、エバの動きが曲芸師か何かのようで、どうやって斬っているのか、いや、斬ろうとしている事の起こりも曖昧で良く分からなかった。
すると、自分の視界が大きな衝撃で見えなくなった。
エバは最後の4人目の野盗の首を落とすと、剣についた血糊を振るい、野盗の衣服で刃を拭い、鞘に収めた。
「10秒かかりませんでしたね。」
茂みから出てきて、様子を見ていたマーリンはキッドにいった。
キッドはエバの戦いを見てやはり唖然としていた。
以前にも1度見たことがあったが、人間技とは思えない、何か魔法で化かされているようなそんな戦いぶりに言葉も出なかった。
まず、エバがいつ斬りに行くのか全く分からない。殺意が全く感じられないし、斬るぞという雰囲気もないし、体の動きもおかしい。
いや全くおかしな動きはしていないのだけれども、斬るという動きをしていないのに、斬れている。そういう印象だ。
予備動作がないとか、歩いたり話したりするのと同じように斬るとか、もうそういう段階を超越している。まさに、今どうやって斬ったの?と手品でも見ているような印象だった。
「それでは、私は話を聞きに行くとしますか。」
マーリンはそういって歩いて行くと、転がっている生首を拾い上げ、倒木の上に置いた。
「死んでいるんじゃないのか。」キッドはいった。
「すぐには死なないんですよ。2つ3つなら話を聞けます。」
マーリンは生首にむかって呼びかけた。
「私はエルファだ。エルファを捕まえてどうするつもりだった。」
すると生首はマーリンの呼びかけに答えるように眼を開いたが、またすぐに瞼を閉じてしまった。だがマーリンはしばらく生首を見つめていた。
「どうだ。何か分かったか。」
剣を収めたエバが戻ってきた。
「だめでした。こいつも使われているだけの雑魚でした。」
マーリンは生首から手を離すと立ち上がった。
「そいつは残念だったな。」
そう言ってエバがふと目をやると、ちょうど雑草の中からルーやマリーウェザー達が出てきたところだった。
エバ達は野盗の死体を目立たないように後片付けを始めた。
「血液や体液が付着しないように、首に気を付けて。誤って体内に入ってしまうと病に感染する可能性がある。」
アレンティーがキッドとルーに向かって注意した。
「そんなことがあるのか。」
キッドがアレンティーに尋ねた。
「まだまだ世間には知られていませんが、病気にかかっている人間の体液などが誤って体内に入る、例えば、指に切り傷があって、その指で触ってしまう、するとその人間が侵されていた病が自分にも感染してしまうということがある。ちょうど皆手袋をしているし、腹から内臓が飛び出ている訳でもないからそんなに心配する必要はありませんが、気を付けておくことに越したことはありません。」
アレンティーが説明した。
「そんなことがあるなんて、知らなかった。」
キッドは感心してそういうと、ルーと並んで死体に向かった。
「物知りだな。アレンティー。」キッドがいった。
「そうだね。」ルーがいった。
幸いエバがきれいに殺してくれたおかげで、両腕と両足を持つようにすれば、首や頭から流れ出ている血液などが付着する恐れはなかった。
「ルー、足側を持ってくれるか。」
キッドは首のない死体の両腕を掴みながらいった。
「分かったわ。」
ルーは死体の両足を掴んだ。
キッドとルーは協力して死体を野原の端まで運んでいくと、勢いをつけて雑草の茂みの中に死体を投げ入れた。
マリーウェザーとアレンティーもエバと協力して3人で死体を運び、茂みの中に投げ入れた。
生首はエバが3つまとめて髪の毛を掴んで持ってくると、同じように茂みの中に投げ入れた。
マーリンは皆を見ながらじっとしていた。
全ての死体を茂みの中に投げ入れたところで、キッドはエバが空に投げ上げた黒い玉が、空中を飛んでこっちに向かってくるのを見つけた。
「黒い玉がこっちに飛んでくるぞ。」キッドがルーにいった。
「本当だ。」
キッドとルーがやっぱり不思議そうに注目していると、黒い玉は空の高いところからだんだん近づいてきて、とうとうキッド達の頭の上を通り過ぎた。
「おお。結構速い。」キッドが驚きの声をあげた。
「本当だ。」
玉は人が全力疾走するくらいの速さがあった。
黒い玉はマーリンの目の前まで飛んでくるとピタッと止まった。
マーリンはその玉を手に取ると、コートの内ポケットにしまった。
死体を片付けたエバ達はじいさん岩に向かって再出発した。
向かい始めた最初のとおりに、エバとキッドが先行し、マリーウェザー達を挟んで最後をのろのろとマーリンが追いかけた。
ルーは歩きながらマリーウェザーに尋ねた。
「マリーウェザーがいっていたでしょう。エバの残酷な戦い方に慣れてきたって。私も慣れてきたかも。」
「うん。やっぱり一緒に困難を乗り越えていると意外と慣れてくるのよね。一緒にというのが大事なんだと思う。」
マリーウェザーはルーの表情が落ち着いているように見えた。
「そうだね。辛い時に一緒にいることが大事だよね。」
ルーも心から共感した。
「ねえ。」
そこへアレンティーがルーに話しかけた。
「何。」
「正直に言うけど、慣れるのが早いと思う。」
アレンティーが淡々とルーにいった。
ルーは何と答えて良いか分からず少し頭の中で迷ってから答えた。
「そうなのかな。意外と私、丈夫なのかな。」
ルーはニコッとしていった。
「頑丈。少なくとも私よりは。」
アレンティーもニコッとしていった。
アレンティーは思った。その頑丈さは、これまで経験してきた辛い経験の積み重ねで得られたもの。ルーもこれまでいろいろな辛い経験をしてきたのだろうと。
またアレンティーはこうも思う。頑丈さを得ることと、辛い経験をすることは等しく同じ価値を持つのだろうかと。
「様々な困難に対処するために、知識はいくら持っていても持ちすぎるということはない。しかも頭に入れておけばかさばることもない。」
兄のマーリンはそう言っていた。
アレンティーもその兄の言葉に倣って、旅を続けながら様々な知識を吸収することに力を傾けてきた。それが辛い経験を避けることに繋がると信じて。
だが、エバがたくさんの人間を残酷に殺害する様を目の当たりにしたとき、どういう理屈でそれを理解すれば良いのか、どういう気持ちで心を整理すれば良いのか、全く分からなくなってしまった。
アレンティーの本能に強い衝撃が走る。本能が殺人という行為を忌避する。
エバに殺害されたたくさんの人々から流れ出た体液が悪臭を放ち、辺り一帯を地獄の様に変える。
アレンティーは一週間程、食事のときになると、においとかその様が蘇ってきて、まともに食事ができなかった。
このような本能に問いかける問題は知識でどうこうというものではなく、同様に本能に衝撃を受けるような経験を積み重ねることでしか慣れていかない。
この問題を整理するために、アレンティーは一週間程悩んだし、その後、決定的な出来事を経験することにもなった。
「言っとくけど、あんた達は今、兄を見殺しにしようとしているんだからね。あんた達も同じ人殺しだってこと、しっかり覚えとけよ!!」
シェリルに凄い剣幕で襟首を締め上げられ、怒鳴られたことを今でも鮮明に覚えている。
そんな経験をしたアレンティーは、ルーが慣れてきたという言葉を聞いて、これまでルーが積み重ねた経験も、相当に辛いこともあったのだろうと思った。
「アレンティーは一週間程かかったって言っていたよね。」
ルーはアレンティーに尋ねた。
「そう。人の命を奪うということを合理的にどう理解するのか。否定的な自分の本能にどう向き合うのか。それに時間がかかったわ。」
「難しいこと言うのね。」ルーはいった。
「ごめん。面倒なひとだと思った?」
アレンティはまたニコッとしていった。
「そんなことない。それより、私の方がよっぽど考えが足りてないと思う。マリーウェザーもそうだけど。比べると本当に私の方が子どもで、恥ずかしい。」
ルーはちょっとうつむき加減に独り言のようにいった。
「それは正確ではない。確かに私の方が知識はあるかもしれないが、ルーが考えが足りていないとは思わない。それよりもルーの経験に裏打ちされたその頑丈さは見事だ。」
アレンティーはルーを応援するつもりでそういった。
「誉められているんだよね。・・・ありがとう。」
アレンティーとルーがお互いに顔を見合わせて微笑んだ。
「あそこを左だ。」
キッドは先に見えてきた、左側に入る横道を指さすといった。
エバ達はその横道に入ると、丘に続いているゆるやかな斜面を進み始めた。
「そういえば、二人とも歳はいくつなの。」
ルーはマリーウェザーとアレンティーに尋ねた。
「えっと・・・今年で61歳かな。」
「えっ!!61歳。」
マリーウェザーの答えに、ルーが驚きのあまり歩くのを止めた。
「嘘だろ!」
前を歩いていたキッドも思わず振り返った。
「いや、本当。歳の話をすると驚かれることが多いんだけど、エルファは成長が遅くて、これでも若い方なんだけど。」
マリーウェザーがてへへという感じでルーに説明する。
「でも、61歳って・・・おばあちゃんか!」
ルーがマリーウェザーに突っ込みを入れる。
「アレンティーは。」
ルーがアレンティに尋ねた。
「私たちは双子だから、歳は同じ。」
アレンティーが答えた。
「じゃあ、マーリンは。」
今度はキッドがマリーウェザーに尋ねた。
「まあ、似たようなもんだ。」
キッドの質問にマーリンが答えた。
「おじいちゃんか!」
キッドもマーリンに突っ込みを入れた。
そのやり取りを聞いていたエバは思わず笑ってしまった。
「じゃあ3人はいつから旅を続けているの。もう何十年も旅を続けているっていうこと。」ルーが3人に尋ねた。
「旅を始めたのはおよそ3年前だ。」アレンティーがいった。
「そうなんだ。じゃあそれまでは何をしていたの。」
ルーが更に尋ねた。
「それまでは前に話したラジスの森で暮らしていたわ。」
マリーウェザーが答える。
「だいたい60年近くも。」
「そう、だいたい60年近くも。」
信じられない。ルーは黙り込むと、3人を理解しようと頭を巡らせた。
60年近くも森に暮らしていたのなら、わざわざ旅に出る必要もないのではないのか。
また、自分の方が子どもだと思っていたが、この歳の差ではしょうがない。
だいたい、私は60歳まで生きられるのか想像もできないし、恐らく60を迎える前に死んでしまうのではないかと思う。この3人は既にそれを超えて生きていることになる。
というかもう十分に歳を取ったので、老後の死に場所を見つけに旅に出たということだろうか。
「本当におばあちゃん。」
ルーがマリーウェザーに尋ねた。
「違うから。本当に違うから。」
マリーウェザーが強く否定する。
「周りもそうだから何の疑問もなく、のほほんと60年も生きて来てしまったの。旅に出て初めて分かったの。時間の流れが違うことに。だから変な人と思わないで。」
マリーウェザーが一生懸命に説明した。
「信じられないかもしれないが、妹達はエルファの社会では人間でいえば15歳程度。ちょうどルーと同じくらいの年齢なんだよ。妹も言っているように、エルファの社会ではそれが当たり前なので、何の疑問もなく生きていたのだよ。」
マーリンも補足する。そして、ルーに分かってもらおうと丁寧に説明を続けた。
「エルファの社会は円環といって、同じ毎日を延々と暮らしているようなものなんだ。人間から見ればつまらない生き方に見えると思うが、永遠に安寧とした暮らしを手に入れるためのエルファの知恵の結晶なのさ。その影響があるのかどうか判然としないが、エルファの心と体の成長は人間に比べて大きく遅くなっているんだ。」
そんなことがあるのか。ルーは驚きで興奮した頭で、これまでの説明をよく咀嚼しようと、マーリンが言ったことをゆっくり思い出していた。
「みんな歩きながら話そうぜ。」
エバが声を掛けると、一行は再びじいさん岩に向かって歩き始めた。
ルーは納得できず黙って考えていた。
マリーウェザーと自分が違う存在であることが分かると、いままで分かり合えたことが嘘のような気持ちになった。
いままでマリーウェザーと交わした会話は、そもそもお互いが置かれている前提条件が違っていたうえでのものだったのだ。
「面白くないか。」
エバがルーに声を掛けた。
「えっ。」
ルーは思わずエバを見た。
「こういう違いがさ。面白くないか。知らなかっただろ。驚きも感動もそういうの全部ひっくるめてさ、面白くないか。」
パッとルーの顔に明るさが戻った。
そうだ。私が知らなかっただけなのだ。
事実は変わってはいない。私が勝手にすねている前も後も、マリーウェザーは何一つ変わっていないではないか。
変わったのは私の方だ。
自分が知らないで話していて、マリーウェザーが知ったうえで話していて、そのことが後から分かったから、なんで事前に教えてくれなかったのか不満に思っている。
でもよく考えれば、後から知ったとしても事実が変わる訳ではないのだ。
自分は何て心が狭い人間なんだろう。
「面白い。凄く面白い。」
ルーはマリーウェザーを見た。
「面白いね、エルファ。」
「良かった。ルーに笑顔が戻って。」
そうだ。似ているところを見て安心する、同じ気持ちになって心地よくなる。でも違うところが出てきたら途端に拒否する。それではだめだ。
違うところが出てくれば、面白い。それで違いを認める。それでいいではないか。
さっきあれだけ協力して危機を乗り越えて、せっかく仲良くなったのに、ほんの少しの違いでそれを失ってしまったら、なんと愚かなことだろう。
「マリーウェザー、もっと旅の話が聞きたいな。私まだまだ何も知らないから。」
ルーはマリーウェザーにお願いした。
「私で良かったら何でも聞いて。」
マリーウェザーはルーに笑顔で答えた。
「じゃあ。」
ルーは歩きながら少し考えるとマリーウェザーに尋ねた。
「旅の間とかお金はどうしているの。」
ぶっ。
マリーウェザーは思わず吹き出してしまった。
「いきなり核心的なところに来たわね。」
マリーウェザーは少し考えてから話し始めた。

「今は、はっきり言うとお金に困っていない。そうは見えないかもしれないけど。でも旅を始めたときは大変だった。」
マリーウェザーは大変だった当時を思い出していた。
「お兄様と一緒にラジスの森を出た私達は、旅立つための資金を得るために、一番近くのターデンの街に向かったの。実は、エルファの森を出るときに薬を持ち出していたから、それを売ってお金にしようと思ったのね。」
「なるほどね。」
ルーはいった。
「何も知らなかった私達は、ちょうど立っていた市場の端の方で持っていた薬を売り始めたのね。ターデンの街はエルファと交流がある街だったから、エルファの薬だと言ったらあっという間に全部売れて、結構なお金になったのよ。」
「へー、やったわね。」ルーが感心したように頷いた。
「でもね、そこに凄い剣幕で男の人達がやって来て、目の前でひたすら怒鳴り続けるのよ、こんなに顔を近づけて大きな声で怒鳴るから本当に怖かったわ。言っている意味も分からないし。」
マリーウェザーが顔の前で両手の平の隙間を狭くして見せながら、顔が近かった様子を説明した。
「組合の人。」ルーが尋ねた。
「ううん、後から分かったんだけど、街を管理している役人だった。理解するのに時間がかかったんだけど、街の外の人間が市場で商売するのは禁止されていたのよ。おかげで薬の売り上げは全部没収されてしまって、私達は一文無しに戻ってしまった。」
「走って逃げちまえば良かったのさ。」
エバが茶々を入れた。
「その時はまだうぶだったから、そんなことは思いもつかなかったよ。」
当時を思い出しながら、マーリンはいった。
「いきなり一文無しになってしまった私達は、薬を勝手に持ち出してきたこともあって、エルファの森に戻る訳にもいかず、路頭に迷うことになってしまった。」
「最悪の状態だな。」キッドはいった。
「それでどうしたの。」
ルーが心配そうに尋ねた。
マリーウェザーがルーに頷くと話を続けた。
「他の街に行くことも考えたけど、それでは解決にならない。そこで、私達は人間社会を観察することにしたの。食べるものは他の乞食に混じって裕福な家々を回って、何とか食い繋いでいたわ。」
「乞食まではやったことないな。」
キッドが同情した様子でいった。
「商売人や行商人から話を聞いて回っているうちに、人間の街のことが色々分かってきたの。貴族とか組合とか。」
マリーウェザーの話をアレンティーが詳しく説明した。
「貴族が定めた様々なルールがあって、そのルールは街に住んでいる金払いの良い商売人に有利なものとなっている。また、職人たちは組合を作って貴族や商売人に対抗している。それはつまり、街というのは総じて、街の外の人間から街の中の人間を保護する性格を有している。」
アレンティの説明が終わると、マリーウェザーが話を続けた。
「とはいいつつも、街の人々は、日々の暮らしを快適にしてくれる何か新しいものを求めていることも分かった。」
「頑張ったんだね。」ルーはいった。
「ありがとう。そんなある日、サリカ神殿の施しを受けられることになって、サリカの施療院に1泊できることになったの。そこで初めて藁のベッドに寝たんだけど、匂いがきついのとノミが多くて、思わず魔法を使ってきれいにしてしまったの。」
「魔法ってそんなことができるの。」
ルーが驚いたようにいった。
「うん。できるんだけど、エルファの森で暮らしていたときは、木の上のハンモックで寝ていたから、匂いとかノミに悩まされることなんてなかったのよ。」
「ハンモックって何。」
ルーが分からない顔をして尋ねた。
「ハンモックというのは、ちょうどエルファを包み込める程の大きさの網を、木と木の間に綱で張ったもので、エルファは木の上に張ったハンモックで寝ている。」
アレンティーがルーに説明した。
「面白い。それに寝心地よさそう。」
ルーが好奇心一杯の目でいった。
「うん。だから藁のベッドに始めて寝て、その寝心地の悪さにびっくりしたんだけど、泊まった翌朝に3人でそのことを話していて、そうしたらお兄様が言ったの、これはいけるんじゃないかって。」
ルーはここまで話を聞いてピンと来た。
「ハンモックを売ったの。」
ルーは答えが分かったような顔をしていった。
「うーん、方向性は正解だけど、もっと簡単なことなの。藁のベッドに魔法をかけてきれいにして回ったのよ。」マリーウェザーはいった。
「あっ、なるほど。」
「なるほどね。」
ルーとキッドは感心したようにいった。
「まず最初にその街の貴族の家に行ったの。エルファの行商人です。エルファの伝統の技でベッドをノミと匂いから解放し、快適に眠れるようになりますよって。ただ、この街に留まっている間しか提供しないので決めるなら今決めてくださいって。」
「上手いこと言ったわね。」ルーがいった。
「だいたいお兄様が考えたんだけどね。それで、相手は最初不審がっていたんだけど、試しに1つのベッドで試してみませんか、お代は効果があってからで構いませんよってやったら、じゃあ試しに1つやってもらおうかという事になったの。」
「そうしたら?」
ルーが期待が膨らんだ表情で聞いた。
「大成功だった。翌日にもう一度伺ったら、素晴らしい、残りの全てのベッドをお願いするって。」
「やったね!」
ルーは自分のことのように喜んで、はしゃいだ表情になった。
「それで、お代の話になったときに、お兄様が吹っ掛けてね、どれも上等な格の高いベッドで、作業に苦労しましたって、ついては1ベッドにつき100ムーナいただきますって言ったの。そうしたら、文句を言われるどころか、逆にエルファの技は素晴らしいといって払ってくれたの、占めて600ムーナ。」
「凄い。一気にお金持ちになっちゃったね。」ルーがいった。
「600ムーナということはベッド6つということか。」キッドがいった。
「うん、そこでさらにお兄様が貴族に掛け合ったの、もう何日か街にいるつもりですが、その間だけ、街の人たちにもエルファの技を提供しても良いでしょうかって。」
「抜け目ないな。」エバがいった。
「そうしたら、いいでしょうって、許可してくれたの。」
「そうか、なるほど。」
ルーがうんうんと頷いた。
「その後にお兄様が貴族にいった言葉も面白いのよ。ありがとうございます、それではこちらも特別に、次回は半額の50ムーナで提供させていただきます。って。」
それを聞いたルーとキッドは可笑しくなって笑った。
「やっぱり闇の魔法使いに間違いはないな。」
エバがニヤニヤした笑顔でいった。
マーリンは反論はしないものの少し苦々しい顔をしていた。
「その後私達3人は、街の裕福そうな家を中心にベッドリフレという名前でベッドをきれいにして回ったの、お代はその家がお金持ちそうなら50ムーナ、庶民なら10ムーナ、その中間位なら30ムーナという具合で。」
「ベッドリフレのリフレって?」
キッドが尋ねた。
「お兄様が名付けたの。ベッドを元気にリフレッシュ。で、ベッドリフレ。」
アレンティーが答えた。
「可愛くて面白い。」
ルーは両手の指を組んで喜びながらまた笑った。
「結局全部でいくら位儲かったの。」ルーがいった。
「2,000ムーナ位だったと思う。」
「凄い。旅の資金としては十分ね。」
「本当に、ベッドに魔法を2つかけて、申し訳ないから、ちょっと小奇麗に整えているだけで、大したことはしていないのにね。」
マリーウェザーはそういうと、自分でも可笑しくなって笑ってしまった。
それにつられてルーとキッドも笑った。
するとアレンティーがいった。
「お兄様はエルファの伝統技術ですのでといって、家の人を部屋から追い出したり、あまり早く終わるのも怪しまれるからといって、部屋の中で休憩して時間調整したりしていた。」
アレンティーがそういうと、そこにいるみんなで笑った。
マーリンも思わず笑ってしまった。
ひとしきり笑いが収まった後、マーリンがルーに話しかけた。
「何か参考になったかな。」
「本当に面白かったし、参考になった。」
ルーは晴れやかな笑顔でそういった。
「まず街のルールを知ること、それから、その街が欲しがっているもの、足りないものを見つけて、街のルールをうまく利用して提供することができれば何とかなると思う。」
マーリンは自分の妹達に教えているようにルーにいった。
「何善人面してるんだよ、この詐欺師野郎。」
やっぱりエバが茶々を入れた。
「だから誤解するから止めろって、騙していないから!」
マーリンが必死に訴える。
しかし、そんな必死なマーリンをあえて無視するとエバはいった。
「あれかな、じいさん岩。」
一行が進んでいる丘の先に、独特の形をした岩がちょうど姿を現したところだった。
じいさん岩は人間の2倍ほどの高さがあり、丘から斜めに突き出すように立っていた。
丘をほぼ登りきったところにあるじいさん岩からは遮るものがなく、北は神聖王国の山脈群から南は帝国に続いている地平線を望むことができた。
西に傾き始めた日の光が辺り一帯を程よく照らし、遠くの風景をぼかして見せていた。
山脈群の白と青、森や茂みの緑、大地のベージュの色合いの美しさと、はるか遠くまで広がるスケールの大きさが単純に心に迫ってくる。
エバとキッドはじいさん岩によじ登ると岩に腰掛けた。
「素晴らしいでしょ。」
ルーがじいさん岩に寄り添うように立っているマリーウェザーにいった。
マリーウェザーはだまって頷くとしばらくその風景を眺めていた。
自然はこんなに広大で美しいのに、自分はなんてちっぽけなのだろう。
マリーウェザーは広大な自然に囲まれた小さな自分という風景が好きだった。
それは逆に自分自身が小さな存在であることを意識していることの裏返しだった。
マリーウェザーは兄のマーリンと旅に出たときには、まだ見たことのない世界に期待を膨らませていた。
しかし今となっては正直、ただ静かにこの美しい自然に寄り添っていたいというのがマリーウェザーの願いだった。
こうやって美しい自然の風景を眺めていると、その願いが叶った満足感に包まれている一方で、その裏側では、それは一時的な満足感であり、永遠にはそれが叶うことがないという現実に絶望感も生まれていた。
もともとエルファの森に兄と住んでいたときも裕福な生活ではなかったが、森が火事で焼けてしまったり、川が氾濫するなどして災害が森を襲うと、途端に食べ物がなくなってしまった。
災害の時のためにエルファの森では食べ物を蓄えてはいたが、絶対量が不足しているのと、自分達のようなはみだし者には十分に回してもらえず、とてもひもじい思いをした。
だから兄マーリンと旅に出たとき、まだ知らない世界に期待したのだ。
でも、旅をしてたくさんの国々、様々な街を巡ったが。結局どこに行っても同じ、天国などないのだと分かった。
雨が降らなかったり、逆に大雨で川が氾濫するなどして小麦が取れなくなると、街のサリカ神殿の前には、農村で食べるものがなくなり、食べ物を求めて来た人々で溢れかえった。
さらに体調が悪くなった人々が集まることで病気も広がり、死んでしまう人も出て、まさに地獄のような様相となる。
エルファでも人間でも、自然から生れ出たはずの人という存在は、なぜひっそりと自然に寄り添うだけの存在として生まれ出なかったのだろう。
生きるためには他の命でお腹を満たし続けなければならない。
それはとても醜い存在に思えた。
自分が望んで生まれて来た訳でもないのに、ただ生きるということがなぜこんなにも過酷なのだろうか。
こんな小さくて醜い自分など、この美しい自然に溶け込んで一体となり、消えてしまうことができればいいのに。
マリーウェザーは隣に立っているルーを見た。
それに気づいたルーが顔をこちらに向けたので、マリーウェザーは微笑んでみせた。
私の頭の中にこんな暗い気持ちがとぐろを巻いているなんて、誰も気づかない。
私は今、口元に微笑みを浮かべながら、本当に心地よさそうに、風景を眺めているのだから。
マリーウェザーは心の中で呟きながら、視線を風景に戻した。
「ソイル選王国のワーツィリヒの丘の風景に似ているわね。」
そんなマリ−ウェザーにアレンティーがいった。
「そうね。」
そう言われてみればそうだ。
こんな憂鬱な気持ちになったのもそのせいかもしれない。
ワーツィリヒの丘とは、ここから遥か東、グラダス半島のソイル選王国という国にある広大な丘の名前だ。
マリーウェザー達がワーツィリヒの丘を訪れたとき、ソイル選王国でも大きな川であるエイゼル川が洪水し、小麦がほとんど取れなくて大変なことになっていた。
「あの時は大変だった。でも地下はもっと大変だったけど。」
アレンティーがいった。
「そうね。」
そう。あの時は爬虫人の女性と一緒にワーツィリヒの丘から地下の爬虫人の帝国にすぐに潜ってしまったので、ソイル選王国では、街を2つ3つ通過したに過ぎなかった。
それでも、街の悲惨な状況は良く分かったし、治安も悪くなって街の中で襲われたりもして、通過するだけでも大変な思いをしたのだった。
“ナーシャ”
爬虫人の女性の名前だ。
とはいっても、爬虫人の言葉ではシューシューといった音になるらしいのだが。
爬虫人というのは、姿はトカゲのようであるが二本の足で歩き、独自の文化をもった生物だ。
ナーシャは魔法の秘薬によって、赤い髪と赤い瞳、真っ白な肌をした人間の姿をしていた。
ナーシャは爬虫人のお姫様を守る近衛兵であったが、人間の女性の姿に化けてお姫様の力になってくれる者を探して地上に出て来たのだ。
しかし、地上に出て来たものの、言葉も文化も違う地上の世界で途方に暮れていたところを、兄のマーリンが心配して声を掛けたのだった。
その縁をきっかけに、地下の爬虫人の帝国でお姫様のお手伝いをすることになったのだが、大変な思いもしたし命の危険もあったが、貴重な経験もでき、今となっては良い思い出だ。
今でも元気にしているだろうか。
マリーウェザーは知らないうちに穏やかな気持ちになっていることに気づいた。
(アレンティーありがとう。)
マリーウェザーは心の中でお礼をいった。
すると、マリーウェザーは以前シェリルに言われた言葉を思い出した。
「マリーウェザー、人はそんな高尚なものなんかじゃないのさ。食べるものがなくなっちまえば、空腹のあまり食べ物のことしか考えられなくなる。ロマンチックな考え何てほんの一かけらも浮かんではこないよ。」
シェリルはマリーウェザーの頭を撫でると続けた。
「今ここに私がいて、マリーウェザーがいる。それが全てで、それ以上の意味なんてないのさ。だから絶望する必要なんてないし、好きに生きていいんだよ。そもそも私達に意味なんてないんだから。」
シェリルからそう言われたとき心が震えた。
シェリルだけは私の心の中を見透かしていた。
だからシェリルに対しては素直な自分でいられるし心から尊敬している。
でもまだこの憂鬱な考えを吹っ切れる程、自分は大人にはなっていない。
まだしばらくはシェリルに頭を撫でてもらいたい。
マリーウェザーは早くシェリルに会いたいと心から思った。
「夕陽になるとさらにきれいなんだぜ。」
立てた膝に腕を乗せた格好のキッドが独り言のようにいった。
「そうか。」
エバはそういうと周りの風景に視線を移した。
いい場所だ。エバはそう思った。
「この岩がじいさん岩?」
アレンティーがルーに尋ねた。
「そう。」
ルーが答えた。
「おじいさんの要素がどこにあるのか分からないけど。」
アレンティーがいうとルーはくすくすと笑った。
「そうでしょ。でもビリーがね、このあたりがおじいさんに見えるんだって。この皴になっているあたりなんだけどね。」
そういうとルーは岩を指でなぞって丸を描いた。
「どこ。」
アレンティーはルーがなぞったところを近づいてよく見てみた。
しかし一向におじいさんの顔が見つからない。
「はははは。」
アレンティーの真剣な様子を見て、キッドが笑い始めた。
そしてルーも笑った。
「みつからないでしょ。」
ルーは笑いながらいった。
「この岩はね、最初にビリーがシャロムの街で聞いてきたの。おじいさんの形をした岩があるぞってね。」
ルーは遠くの風景に目を移した。
「1年半位前かな、あの時はまだお互いにライダーとして働き始めて間もないときだった。」
ルーはその時の様子を思い出しながら話し始めた。
「仕事も夕食も終わってこれから寝ようというときに、ビリーがこっそりみんなに提案したの。シャロムの丘におじいさんの形をした岩があるから、みんなで行ってみないかって。だけどその場では、機会があればねって話で本当に行くという感じではなかったんだけど。」
「へえ、そうだったんだ。」
マリ−ウェザーがいうと、ルーは頷いて話を続けた。
「しばらくして、たまたま仕事の日程でシャロムの街に全員揃う機会があったんだけど、ビリーが絶対に行こう、岩の顔が凄いらしい、見ないと絶対損するからって言い始めて。」
「この岩がか?」
エバがニヤニヤしながら尋ねると、ルーはクスクスと笑って続けた。
「それでみんなで来てみたんだけど、全くおじいさんの顔の形していないじゃない。それでみんなでどこにおじいさんの顔があるのか盛り上がってね、岩自体が鼻じゃないかとか、影がじいさんの顔になるんじゃないかとか言っていたけど、結局分からなくて、その時にビリーが言っていたのが、この皴のところがおじいさんの顔になっているんだって。」
ルーはさっきやったのと同じように岩を指でなぞって丸を描いた。
「どう見てもおじいさんには見えないけど。」
マリーウェザーがいうとルーは相槌を打って話を続けた。
「でもね、その後みんなで言い合ったの、おじいさんの顔は分からなかったけど、ここからの眺めは最高だねって。」
「ああ、そうか。」
エバが分かったようにそういうと、キッドがエバと目を合わせた。
ルーは話を続けた。
「その後、ビリーがじいさん岩の話を聞いたという店に行くことがあったんだけど、そうしたら、じいさんの形ではなくて、うちのじいさんも散歩に行っていた岩だったのよ。」
ルーがいい終わるとそこにいるみんなで笑った。
話していたルーも一緒に笑った。
「別にじいさんは岩には関係なかったの。ただのビリーの勘違い。街の人は夕陽の丘って呼んでいるんだって。」
「ビリーはいい奴なんだな。」
笑い終えたエバがいった。
「優しい奴なんだよ。あの頃はお互いのことがまだ良く分からなかったときだったから、分かり合えるきっかけを作ってくれた。」
キッドがエバにいった。
「ここには何度も来ているの。」
マリーウェザーがルーに尋ねた。
「何度もという訳じゃないけど、これで4回目、5回目ぐらいかな。仕事場で話しづらいことは、ここに来てみんなで相談するの。」
「そう、いい場所ね、ここは。」
傾き始めた陽の光がエバ達を照らした。
少し風が吹き始めた。
「そろそろ行きましょうか。」
マーリンはそう言うと元来た道を引き返し始めた。
「こっちじゃないのか。」
エバがじいさん岩から先に続いている道を親指で示しながらいった。
「そっちは領主の館に続いていますよ。」
「ああそうか。」
マーリンの返事にエバも納得し、すぐに引き返し始めた。
エバ達がシャロムの街に戻ったときは、太陽はほぼ落ちかけていた。
「遅くなってしまったね。」
ルーがみんなに声を掛けた。
既に北門は閉じており徴税人たちの姿も消えていた。
北門の外には街の中に入ることができない乞食達が、街の壁に寄り添うように座り込んでいた。
北門横にある小さな扉をキッドが叩くと、門番の男はエバ達を覚えてくれていたようで、その小さな扉を開けてくれた。
腰を屈めて小さな扉をくぐると南北に延びる大通りとそこに佇むたくさんの店を見ることができた。
たそがれ時を迎えた街は、あれだけ通りにいた大勢の人の姿はすっかりまばらとなり、通りに並んだ店も落とし戸を閉め、これから訪れる闇の世界に備えていた。
陽が落ちようとしているこの時間帯は、通りに佇む人の姿が黒く輪郭をぼやかして何とか見ることができ、それはまさに人影であり、誰そ彼(たそがれ)時という言葉どおりの情景が広がっていた。
この街の建物は土地を広く使った木製の平屋建てが多く、平屋を3つから4つの部屋に仕切り、太い木材で造られたアーチ屋根を被せていた。
建物に入ったすぐが店先兼仕事場であり、床は踏み固めた土間であるのが普通だった。
部屋の真ん中に湯を沸かしている暖炉があり、その暖炉の煙は屋根に設けられた煙突から逃がしていた。
落とし戸を閉めた家々では、仕事場の片づけを終わらせると暖炉の前に長テーブルを置き、そこに大判の布が掛けられ、これから軽い夕食が始まる時間である。
北門を最後にくぐり抜けたマーリンは門番に尋ねた。
「私はエルファですが、私のほかに今日この門をくぐったエルファを見かけませんでしたか?」
「知らねえな。この辺りはエルファはいねえから。」
門番の男は無精髭の生えた頬を左手で撫でながら答えた。
「そうですか。じゃあ、エルファを探している人が私みたいに声を掛けて来た、なんてことはありませんでしたか?」
男はハッとした表情を見せるとマーリンにいった。
「そういや、エルファと女を見なかったかと聞いてきた男達がいたな。てっきりあんた達のことだと思ったから北門から出て行ったといったが、俺の勘違いだったな。」
門番の男はそういうと、バツが悪そうに顔をしかめた。
「そうなんですか、何を勘違いされたんですか。」
マーリンは警戒されないよう、にこにこと話しかけた。
「いやなに、エルファと女を見なかったかと聞かれたんだよ。でも、エルファと聞いて俺はてっきりお前さん達のことだと思い込んじまって。」
「私はエルファだし、この方は女性ですからエルファと女で合っているのでは?」
マーリンが手でルーを示しながら門番に説明した。
「いや違うんだ。その男達がいっていたんだよ、馬を連れていると。」
「つまり私達は馬を連れていないから違うと。」
門番の男は視線を上に向けて考えるような素振りをみせた。
「まあ、そういうことかな。」
そう門番がいうのを聞いたマーリンはエバを見た。するとエバは分かったというように頷いた。
「そうですか。それでその男達は北門から出ていきましたか?」
「ああ、確か5人位だったと思うが、みんな北門から出て行ったよ。」
「その男達に、私達の人数は教えたのですか?」
「ああ、教えた。5人位だったと、言ったかな。」
「そうですか。ありがとう。教えてくれて助かりましたよ。」
マーリンは門番に向かってそういうと、エバ達は南北に延びる大通りを、今日泊まる宿屋のあるプチヘンリー通りに向かって歩き始めた。
「エバ、シェリルが来ていると思うか。」
マーリンがエバに聞いた。
「ああ、そんな気がする。」
マーリンは思案した。
エルファと女。そのエルファというのは領主が探している本命のエルファのことであろう。自分達のことではない。
女と言っているということは、この街に住んでいる女ではない女。そして、こういう厄介な問題に関わっている女。
そう考えるとその女は、シェリルではないかと思えてくるのだ。
マーリンが予測していたところでは、シェリルは青の帝国を一気に早馬を使って抜けてくるはずで、エバ達が徒歩で進んでいることを考慮すると、ここ2週間の間には合流することを見込んでいた。
そして、神聖王国ルークスに続く北門から出ていないということは、この街にいるはずだ。
馬を連れているというのは、女がシェリルであれば容易に説明がつく。
つまり、ライダーを雇って道案内をさせたのだろう。それにシェリルは一人では馬に乗れなかったはずだから。
だとすれば。
「同じ宿か。」
マーリンが呟いた。
「そうなのか?それなら探す手間が省けるな。」
その呟きを聞いたエバが、マーリンに向かってニッと笑顔を見せた。
「お兄様、何を話しているのですか?」
アレンティーがマーリンに尋ねた。
「ああ、そうだな。」
マーリンは一呼吸おいて続けた。
「確証はないがシェリルが追い付いたかもしれない。」
「シェリル姉さまが来ているのですか?」
マリーウェザーが胸の前で両手を合わせながら少し高めの声でいった。
「恐らくな。」
マーリンの返答にマリーウェザーは浮かれた様子でアレンティーの肩に触れた。
アレンティーはどんな表情で反応したら良いのか咄嗟に分からず無言のままでいた。
エバ達は宿のあるプチヘンリー通りを目指して、すっかり暗くなってしまった南北に延びるウェイン大通りを南に向かって歩いていた。
ちょうど左手にこの街で一番大きな教会であるサリカ大聖堂が大きな黒い影となってみえた。
「シェリルさんって、前に少し話してくれましたよね。」
ルーがマリーウェザーに聞いた。
「そうだったっけ。」
マリーウェザーはシェリルに会えるかもしれないことで、会ったら何を言おうか、シェリル姉さんは何を言うのかと考えていたため、ルーの問いかけに咄嗟に反応できなかった。
マリーウェザーはルーにシェリルについて何を話したのか正直思い出せなかったが、少し考えてから話し始めた。
「シェリル姉さんは、海賊で。」
「海賊で?」
ルーは聞き覚えのない言葉がマリーウェザーの口からでてきたので思わず聞き返した。
「そう紫の群島の周辺を荒らしている海賊で。しかも海賊の首領で。」
「海賊なんて本当にいるのね。」
マリーウェザーはルーの半信半疑な表情をチラッとみると続けた。
「たぶん、青の帝国からしたら極悪人なのかもしれないけど、だけど私にとっては憧れというか、人生の師匠というか。」
「人生の師匠。」
ルーは60年も生きているマリーウェザーに人生の師匠と言わしめるシェリルという女性に会ってみたいと思った。
「師匠ねえ。隊長って感じかな。俺にとっては。」
エバが歩きながら独り言のようにいった。
「人間の女性にしてはやりますね。」
マーリンがエバの言葉に続いた。
「強いのか、シェリルという人は。」
キッドがエバに聞いた。
「そうだな・・・強いね。俺は勝てる気がしないな。」
「どんな女なんだ。」
エバの言葉を聞いてキッドが分からないというように呟いた。
「まあ、会ってみれば分かるさ。それに、まだ会えると決まった訳でもないしな。」
エバ達はウェイン大通りを抜けファネリー大通りに入った。
ファネリー大通りに入ると街の南側に入ることになる。
この辺りはたくさんのパン屋が立ち並んでいるが、鎧戸を閉めてしまっている。
目指しているプチヘンリー通りはもう少し進んだところの左手側にあった。
「エバ、宿の前を誰か見張っているかもしれないな。」
プチヘンリー通りが見えて来たところでマーリンはエバにいった。
「いたら捕まえないとな。」
エバ達はファネリー大通りから左に折れ、プチヘンリー通りに入った。
プチヘンリー通りは通りの両側に宿屋が並んでいた。
宿屋の看板や軒先に赤黄緑の細長い布が足らされているのは、草原の国ゼクス共和国から来た旅人向けの宿屋だ。
看板に反りのある片刃の太刀が掲げられているのはカルシファード侯国から来た旅人向けの宿。
他にもグラダス半島から来た旅人向けの宿もあるし、黒い肌が特徴的な南国ザムーラ島からの旅人向けの宿もあった。
大抵はもともと世界を旅していた商人が、自分の出身国から来た旅人のために宿屋を営んでいることが多かった。
自分の口に合う料理を食べられるので、旅人は自国の出身者が営んでいる宿屋があればそこを選ぶことが多かった。
エバ達が目指している宿屋は、ライダーであるキッド達が、仕事が遅くなって一泊する時によく使っていた宿屋であった。
「あそこですね。」
通りの突き当り左側、荷車らしき黒い影が止まっている建物がその宿屋だ。
「表には・・・だれもいないな。」
エバがマーリンにいった。
「いや、通りの反対側の樽の陰に座っているやつがいるぞ。」
「本当か。」
マーリンにそう言われてエバがよく目を凝らしてみると、通りの反対側の宿屋の軒先に置かれた樽のようなものの陰から足のような黒い影が出ているのが分かった。
「あんなの良く分かったな。」
「ああ。」
マーリンはエバと一緒に旅をして分かったが、どうも人間とエルファでは夜のような暗いところでの物の見え方が違うようだ。
エバが暗くて判別できないという暗さでも、マーリンには灰色の濃淡で形の識別ができた。
今もマーリンには樽の陰から足が伸びている姿がはっきりと見えた。
「あれは大丈夫だろう。いつも座っている爺さんだと思う。」
キッドは二人にいった。
エバ達は宿屋の前に到着すると、エバは通りの反対側で壁にもたれ掛かって座っている男に近づくと、座り込んで男の顔を確認した。
顔を確認するとエバは皆のところに戻ってきた。
「どうだった。」
キッドはエバに聞いた。
「確かに、何か悪さをするには年より過ぎる。」
「それじゃあ入りますか。」
キッドは大きな両開きの扉の片側を開けると、中は揺ら揺らとした赤みのかかった明かりに照らされていた。
中に入ると、入った正面奥に数頭の馬が繋がれており、馬屋となっていた。
入口が両開きで大きい造りになっているのも馬を中に引き入れるためだ。
エバ達が乗ってきた荷車を曳いてきた馬もここに繋がれていた。
入って右側に目を移すと大きく開けた広間になっており、中央に暖炉が置かれ、それが建物の入り口から広間全体を炎独特の赤く揺らめいた光で照らしていた。
暖炉の周りを囲むように白い布が掛けられた細長いテーブルが置かれ、数人の男女がそのテーブルで食事をしているのが見えた。
キッドが広間の方に歩いて行った。
「ジェシーおばさん!」
キッドが大きな声で呼び掛けると、少し間があった後に広間に繋がっている部屋から女性が出て来た。
「キッドかい。」
少し目尻が下がった愛嬌のある眼差しの女性だった。
年は30代後半だろうか。
「遅かったね。ビリーが待っているよ。」
ジェシーはキッドにいった。
「ビリーが?」
キッドは分からないという顔で聞き返した。
「しかも女連れだよ。」
「本当か?」
「凄い美人で、しかも顔に刀傷があるんだよ。」
ジェシーが自分の左頬を左手の人差し指で撫でると刀傷の様子を示した。
キッドは、エバと顔を見合わせた。
「どこの部屋だい。」
キッドはこの宿にいくつかある部屋のどの部屋にビリーがいるのか尋ねた。
「えっと、奥から2番目の部屋だよ。」
キッドは奥に進もうとした。
「ちょっと待って。」
ジェシーがビリーを止めた。
「何だよ。」
「今日あんた達はここで泊りだからね。」
ジェシーはキッドとルーに向かっていった。
「えっ、そうなの。」
また不思議そうな顔でキッドはシェシーに聞き返した。
「ビリーがあんた達も泊っていくからって。」
ジェシーはキッドにいった。
「でも俺達、親父さんに何も言ってきてないし、宿代も払えないぜ。」
「さすがに親父さんに言っていないのはまずいよね。」
キッドが気まずそうにいうとルーも心配そうに続いた。
「親父さんには先に帰ったジミーが伝えてくれるはずだよ。ビリーがジミーにお願いしていたから。あと、宿代は美人の女の人が払ってくれるって。」
それを聞いたキッドはエバを見た。
「まあ、そういうことだろう。」
こういう手際のよさはシェリルらしいとエバは思った。
「奥の部屋に行こうじゃないか。」
エバはキッドを促し、広間を右回りに抜けると奥の部屋に通じるドアを開けた。
「夜食を食べるんだったら早くしてよ。こっちは片付けもあるんだから。」
ジェシーが広間から出ていこうとしているキッドに後ろから声を掛けた。
「分かったよ。」
キッドは振り返りもせずにそう返した。
廊下には壁にランプが1つついているのみで、ほぼ真っ暗な状況であったが、まっすぐ続いているだけであり、また右側にいくつかついている扉の隙間から薄明りが漏れているので、進むのに支障はなかった。
エバ達は廊下を進むと奥から2番目の扉の前に来た。
今日エバ達が泊まる予定だった部屋の隣の部屋だ。
扉の下の隙間から明かりが漏れている。
「開けるぞ。」
なぜかキッドはエバに扉を開ける予告をしてから扉を開けた。
扉を開けると、天井から吊るされたランプの明かりが、部屋の中をほのかに照らしていた。
部屋にはベッドが左右に3つずつ、合計6つあり、寝る前に脱いだ服を引っ掛けておく棒状の衣紋掛けがそれぞれのベッドの枕元に立っていた。
窓際には背もたれのないイスとテーブルが1つ、それから空の洗面桶が1つ壁に立て掛けられていた。
そして、入口から見て左側、窓際奥のベッドには、ランプの明かりで照らされた金髪が輝くような印象を放っている女性が腰掛けていた。
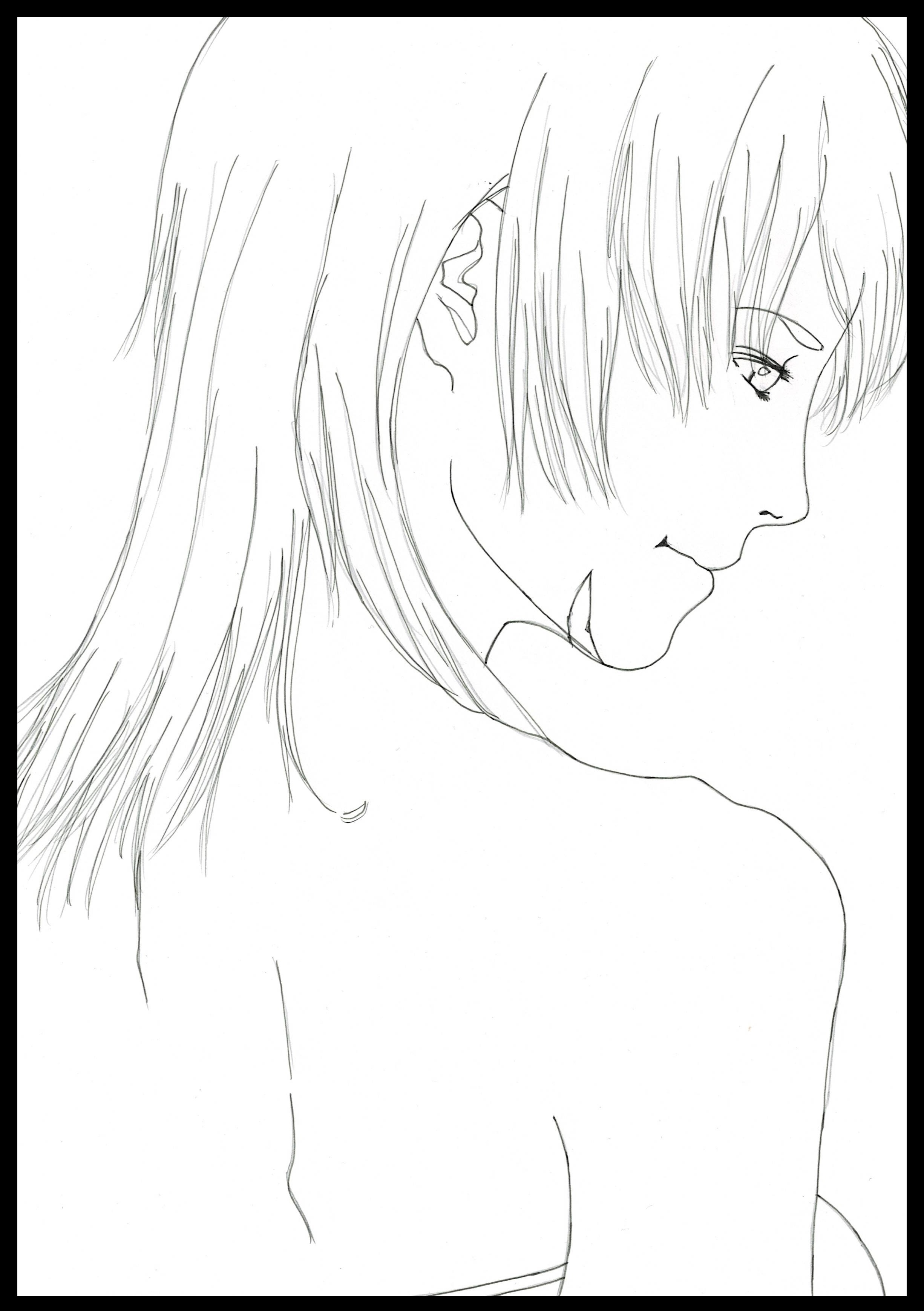
その女性が顔をこちらに向けると、碧い瞳がこちらを見つめた。
その碧い瞳は女性の白い肌と相まって清純で真っ直ぐな印象を与えていた。
女性の左の頬には薄く赤身のかかった大きな刀傷があったが、それが彼女の印象に力強さを与えていた。
キッドは女性と目が合った。
しかし気恥ずかしくなって自分から視線を外してしまった。
「どうしたんだい。早く中に入りなよ。」
その女性は少し首を傾け、はにかんでいるような表情でいった。
それでも部屋に入るのを躊躇っているキッドに、部屋の中にいるもう一人の人物が声を掛けた。
「キッド、遠慮してないで入って来いよ。」
キッドは聞き覚えのある声に普段の調子を取り戻した。
「別にお前に遠慮している訳じゃねえから。」
キッドは聞き覚えのある声の主、ビリーに向かっていった。
さっきの女性から反対側のベッドに座っていたビリーは、キッドの返事を聞くと左目をつむりウィンクして見せた。
後ろからエバがキッドの肩に手を置き中に入るように促すと、キッドはエバ達の邪魔にならないように部屋に入るとすぐに横に避けた。
キッドに続いてエバは部屋の中に入った。
「よう、シェリル。久しぶりだな。」
エバは真っ直ぐに窓際の方へ歩きながらシェリルに話しかけた。
「お前からこんな手紙を寄こしておいて、よく平然とそんなことをその口は。」
はにかんでいるような表情のままシェリルは目を細めると、嬉しそうにエバを見つめた。
「ああ、そこはすまん。悪かったよ。来てくれてありがとう。」
エバは窓際の椅子に座りながら笑顔でいった。
「当たり前だ。仲間だろ。」
シェリルは顔を上向きにすると偉そうに装っていった。
「まさか本当に来るとは。」
部屋に入ってきたマーリンがいった。
「久しぶりだな、マーリン。」
「よく無事に抜けて来られたな。」
青の帝国から賞金が掛けられているシェリルが、よくその帝国を抜けてこられたものだと感嘆した様子でマーリンはいった。
「反体制派の貴族に媚を売って、危うく広告塔に担がされるところだったぞ。」
シェリルは口をへの字に曲げて不満気な顔をした。
「大変だったな。」
エバがシェリルをなだめた。
「本当だよ。しかもその貴族がエロ親父で私を妻に迎えたいと言い出すし。」
「いや本当に大変だった。」
エバが大変だったを繰り返した。
「便宜を引き出すために、しおらしい女を演じたのが効きすぎてしまった。」
シェリルはがっくりと首を垂れると頭を左右に振った。
「まあ、無事にここまで来れたんだし、シェリルは上手くやったと思うよ。」
マーリンがシェリルをねぎらった。
その様子を見ていたビリーは、目の前のシェリルが、本当のシェリルなのだと思った。
そしてエバとシェリルとマーリンには古くからの繋がりがあるように感じた。
「シェリル姉さん。」
部屋に入ってきたマリーウェザーがシェリルに駆け寄った。
「マリーウェザー。元気にしていたかい。」
マリーウェザーはシェリルの横に座ると、シェリルはマリーウェザーの頭を撫でた。
マリーウェザーは嬉しそうに、てへへという感じで頭を撫でられていた。
「お久しぶりです、シェリルさん。お元気そうで何よりです。」
近くに来たアレンティーもシェリルに声を掛けた。
「アレンティー久し振り。また一緒に旅ができるな。」
「私も嬉しいです。」
アレンティーは知らないうちに嬉しくて体が緊張しているのを感じた。
「こっちにおいで。」
シェリルはアレンティーを引き寄せマリーウェザーとは反対側に座らせると、同じように頭を撫でた。
アレンティーは恥ずかし気に頭を撫でられていた。
「シェリルさん。」
ビリーがシェリルに声を掛けた。
「紹介しますよ。さっき話をしたこっちがキッドで、こっちがルー。」
エバ達が到着する前に、ビリーがシェリルに話して聞かせていたキッドとルーを紹介した。
「はじめまして、キッドです。」
キッドはシェリルに近づくと握手をした。
「ルーです。」
続いてルーも握手をした。
「シェリルだ。一人で旅をしていて、土地勘がなくて難儀をしていたがビリーには助けられた。優秀なライダーだな。」
「へへへ。」
誉められたビリーは鼻先を指で鳴らした。
「どうせエバ達も世話になったんだろう。今日は私が奢るから一緒に食事でもしよう。」
両手に抱えたマリーウェザーとアレンティーの長く伸びた耳を撫でながらシェリルはキッドに向かっていった。
「じゃあ、遠慮なくそうさせて貰います。」
シェリルはキッドのその言葉に頷くと、マーリンに顔を向けた。
「その前に、悪いけど手伝ってくれるか。」
「何を?」
「そこに寝ているエルファから話を聞いて欲しいんだ。」
マーリンは既に気づいていたが、シェリルの向かいのベッドにエルファの男が一人横になっていた。
そのエルファが身に付けている麻の衣服に施された赤や緑色の色とりどりの幾何学模様や、顔のペインティングからこのエルファが敵と戦うための部族であることがマーリンには分かった。
また、顔面や上半身に激しく殴打された跡がたくさん青く残っていた。
「意識は戻っているようだが、口の中、食道、肺、胃が傷ついているようで苦しんでいる。」
シェリルが状況を説明した。
「分かりました。まずは傷を治しましょう。」
「ただし、元気にさせ過ぎるな。」
シェリルが注文をつけた。
「分かりました。」
そういうとマーリンはマリーウェザーを見た。
「マリーウェザー、やってみなさい。」
「はい。お兄様。」
マリーウェザーはベッドから腰を上げると、体を横にしてうずくまり苦しんでいるエルファの側に立った。
「レスティリの粉薬がいいでしょう。ありますか?」
「はい、持っています。」
マリーウェザーはいつでもこの粉薬を取り出せるよう、腰のベルトに3つ括り付けていた。
「吐血していますから、シェリルの言ったとおり、口から肺、胃にかけて傷を治しましょう。」
「分かりました、お兄様。」
マリーウェザーはベルトに括り付けた小さな袋から紙で包んだ粉薬を取り出すと、指先で器用に紙の包みを破りながらエルファの上半身に振りかけた。
次に腰に提げていたアーモンドの形をした小さな盾を左手に持つと、胸の前に掲げた。
するとマリーウェザーは、両手足を柔らかく円のような軌跡で動かしながら、小川の流れるような不思議な言葉で囁くように歌うと、最後に横たえたエルファの上半身に盾を持ったまま両手をかざした。
振りかけた紛薬が、マリーウェザーがかざした両手を中心にして球の形に対流しているのが見えた。
すると、苦悶の表情で歪んだエルファの顔色がみるみるうちに血色を取り戻し、穏やかな表情となった。
気づいた時には球形の対流も消えていた。
「上手くいったみたいですね。ありがとうマリーウェザー。」
「どういたしまして。お兄様。」
横で見ていたキッド達はその不思議な光景に見入ってしまった。
「かっこいい、マリーウェザー。」
マリーウェザーの幻想的な姿にルーが感嘆の声を上げると、マリーウェザーはルーに向かって微笑んだ。
マーリンはシェリルを見た。
「それでは何を聞けば良いですか?」
シェリルはエバの座っているイスを取り上げると、横になっているエルファの側までもっていき、そのイスに腰掛けた。
「私が聞きたいことを言うから、マーリンが通訳して、答えを教えてくれ。」
シェリルがマーリンの目をじっと見つめて、分かったよなと無言で問いかけた。
「分かりました。ちょっと待ってください。」
マーリンはシェリルと目を合わせたまま一呼吸の間じっとしていた。
「大丈夫です。」
「分かった。それじゃあ、お前の名前、出身それから部族での役割を教えてくれ。」
マーリンが横になっているエルファにエルファ語で問いかけた。
しかし、エルファから反応はなかった。
マーリンは無反応のエルファを少しの間見つめていたが、その後シェリルを見ると言った。
「この街から東にある森のエルファだ。部族の名はプファイト。エルファの森を襲う敵と戦うのが役目の部族だ。部族での役割は部族の長、導き手と言われている。名前はロミタス。」
無反応だったエルファは、マーリンがロミタスという言葉を発すると閉じていた眼を開いた。
「なるほど。ロミタスというんだな。」
眼を開いたエルファに鋭い視線を送るとシェリルは質問を続けた。
「ロミタス。お前が人間に襲われていたのは、お前の身近な人が関係しているか。」
マーリンがさっきと同じようにエルファに問いかけると、ロミタスは一瞬マーリンを見たが、すぐに視線を外すと黙ってじっとしていた。
マーリンは同じようにロミタスを少しの間見つめると、シェリルを見ていった。
「関係している。」
「そうか。人か。」
シェリルは小さく溜息をつくと、目を合わさないようにしているロミタスに顔を近づけていった。
「そいつとお前の関係は。名前を教えろ。」
マーリンがロミタスに問いかけたが、ロミタスは緊張しているのか身じろぎもせずじっとしていた。
マーリンはまたロミタスを少しの間見つめると、シェリルの顔を見ていった。
「ロミタスの娘だ。名前はエイリス。」
ロミタスは猛獣のようなうなり声を上げ、シェリルに飛びかかろうとした。
しかし、勢いよくベッドから飛び出そうとしたロミタスの上半身は、目の前のシェリルにほんの少しも近づくことなく、そのまま激しくベッドに落下しただけだった。
ロミタスの足首はエバに握られていた。
飛びかかろうとしたロミタスをエバが引っ張り戻したのだ。
即座にエバは空いている左手で剣を抜き放つと、ロミタスの喉に剣先を当てた。
少しでも動けば、鋭利な刃が容易に喉笛を切り裂いてしまうだろう。
シェリルはちらっとエバを見て、すぐにロミタスに視線を戻した。
「今更いきがってるんじゃないよ。よく思い出すんだな、野盗に捕まってどんな情けない姿だったのか。まさか、それは想定どおりだったとでも言うのか。」
マーリンはシェリルの言葉をロミタスに伝えた。
ロミタスは黙ってシェリルを見ていた。
シェリルはロミタスを睨みつけるといった。
「あんなぼろきれの状態でどんな策を考えていたのか言ってみろよ。」
マーリンがロミタスに伝えるとロミタスはゆっくりと目を伏せた。
「お前は負けたんだよ。情けない。」
ロミタスは目を伏せてじっと聞いていた。
それを見ていたマーリンは、シェリルを見ると小さく頷いた。
少しの間沈黙があった。
「・・・私は負けた。娘を助け出すこともできず、成す術もなく、ただ運にすがるだけの情けない男になってしまった。お前の言うとおりだ。」
ロミタスは力なく肩を落とすといった。
「ヤドゥイカ子爵が関係しているな。」
シェリルが発したヤドゥイカという言葉を聞くと、ロミタスは驚いた顔でシェリルを見た。
シェリルは続けた。
「娘を人質にして何を要求されている。」
「エルファの森で栽培しているプファイトの実だ。だが私は断った。」
ロミタスは頭を左右に振った。
「ヤドゥイカ子爵はプファイトの実を何に使うつもりだ。」
「奴はプファイトの実を使って戦争に使う武器を作ろうとしている。」
ロミタスはシェリルの問いかけに素直に応じた。
「なるほどな。」
シェリルは上体を起こすと足を組み、軽く握った左手を頬に当て視線を下に落とすと、じっと考えているようだった。
少し間があった後、シェリルはロミタスを見ていった。
「ロミタス、お前が協力してくれるなら、私達はお前の娘を助けてやれるかもしれないぞ。」
マーリンがシェリルの言葉を伝えると、ロミタスはまた黙り込んでしまった。
そのロミタスの様子を見ていたマーリンは眉をしかめた。
そして、シェリルとエバにしかめた顔を向けるといった。
「エルファの軍隊がこの街に向かって来ているようだ。」
その言葉を聞くとシェリルは、軽く握ったこぶしを額にトントンと当てると、向かいのベッドに腰掛けているビリーに向かっていった。
「ビリー、悪い方の予想が当たってしまったな。」
ビリーはお手上げというように肩をすくめると両手の平を見せた。
「みんな食事にしよう。何か急にお腹が空いてきた。」
シェリルはそういって、イスから腰を上げると大きく伸びをした。
それから部屋の入口の方に歩き始めた。
「そうそう。」
シェリルは何か思い出したように歩みを止めた。
「ロミタス、お前もな。」
振り返ったシェリルはロミタスに人差し指を向けるとそういった。
それからみなに顔を向けるとシェリルは飛びっきりの笑顔を見せていった。
「安心しろ、策はある。」
エバ達が広間に戻ると、暖炉を取り囲むように置かれた長テーブルで食事をしていた最後の4人が席を立ち、ジェシーおばさんがテーブルの上に残った食器を片付けようとしているところだった。
「ジェシーおばさん、夜食頼むわ。」
ビリーが声を掛けた。
「分かったよ。ちょっと待ってな。」
ジェシーおばさんはビリーに笑顔を見せた。
シェリルは広間を見渡すとジェシーおばさんにいった。
「女将さん、テーブルを動かして使ってもいいかな。」
ジェシーおばさんは少し考えていった。
「別にいいよ。」
ジェシーおばさんはそういうと奥の部屋に引っ込んでいった。
「海賊流に豪快にやろう。そこのテーブルをこっちのテーブルに合わせて両側に座れるようにしよう。」
食事のときには、準備や片付けがやり易いよう、長テーブルの片側だけに座ることになっていたが、シェリルは2つのテーブルを合わせて両側に座れるよう指示した。
「でもそれだとテーブルの上まで暖炉の明かりが届かずに暗くなってしまいますよ。」
ビリーがシェリルにいった。
「それならランプを吊るせばいいだろう。」
シェリルが天井から伸びているランプフックを指さした。
「こんなところにランプフックがあったんだ。」
「今まで気づかなかったな。」
ビリーとキッドは顔を見合わせていった。
「普段は使っていないのさ。油だって安くはないからね。それじゃあ二人でテーブルを持ってきてくれないか。」
シェリルにいわれてビリーとキッドは長テーブルを運んで来ると、2つのテーブルを合わせて1つの大きなテーブルとした。
「ルー、悪いけどさっきの部屋からランプを持ってきてくれないか。」
「分かったわ。」
シェリルに言われてルーは部屋のランプを取りに行った。
「あらあら、テーブルをくっつけたのかい。」
ジェシーおばさんが木製のスプーン、皿代わりの固いパンを木製の盆に乗せてやって来た。
「どうやって置いたらいいかね。」
ジェシーおばさんはスプーンなどの置き場所が分からず戸惑った表情を浮かべた。
「女将さん、こちらが5人、そちらに4人座るから。」
シェリルが声をかけた。
「こっちが5人かい。」
ジェシーおばさんは戸惑った表情のままシェリルに聞き返した。
「女将さん、テーブルの上にまとめて置いてくれればいいよ。マリーウェザー、アレンティー、手伝ってやってくれないか。」
「分かったわ。」
ジェシーおばさんはテーブルの上にスプーンなどを置くと、マリーウェザーとアレンティーがそれを二人で適当に分け、テーブルの両側に並べ始めた。
その状況を見ていたエバとマーリンは顔を見合わせると、二人の間に挟んでいたロミタスの肩を叩き、3人で背もたれのない木製のイス5却を運ぼうと動き始めた。
「俺達も。」
キッドとビリーもイス運びを手伝おうとエバ達に近寄った。
いい感じだ。
シェリルはこの場の雰囲気が子気味よくまとまっている様子に満足した。
食事の準備をみんなで行う。
やはり人は何かを成したいという欲求があるし、皆で同じ目的に向かって、それぞれが成したことが連携し、一つの目的を達成したときの成功体験と一体感は、様々に降りかかる困難を全員で乗り切っていくのに必要なことだ。
そういう経験を重ね十分に成長した仲間は、緊急時において自分達が置かれている状況をそれぞれ自ら分析し、自分が果たすべき役割を誰が指示をせずとも自ら実行することが可能となり、個人の寄せ集めの域をはるかに超え、敵の出鼻をくじき、手も足も出させず一方的に制圧する強力な集団となる。
そこで必要なのは仲間を引っぱっていくリーダーの存在だ。
リーダーがまずそれぞれの行動を指示する、そしてその結果、失敗しようが成功しようがそこから反省すべき点を見つけ、皆で認識し、成長に繋げていく。
またリーダーは、集団の一員として行動し成長する機会を、仲間に提供しなければならない。
いまやっている食事の準備は、小さな機会であるがその一つだ。
大なり小なり様々な機会を提供し、繰り返し成長を促すことで、自然と仲間ひとりひとりが、ある状況によって仲間がどう動くか、その中で自分は何をすべきかを体に染み込ませ、瞬時に正しい選択ができるようになる。
ただし、いつ大きな困難が襲い掛かってくるか分からない中で、悠長に構えてはいられない。
だからどんな小さな機会でも、成長の機会があれば逃してはならないし、その機会を逃すことで集団が敗れるようなことがあれば、それはリーダーの責任だ。
「シェリルさん、ランプ持ってきました。」
ルーが部屋からランプを持って来た。
「ありがとうルー。それじゃあ、そのランプをランプフックに掛けてくれるかな。」
「分かりました。」
そうは言ったものの、天井から下がっているランプフックは、ルーが手を伸ばしてちょうど届かない程度の高さだった。
ルーは少し考えると、イスの上に乗ろうと右足を持ち上げた。
「ルー、ちょっと待った。」
シェリルはルーを制した。

「ごめんごめん。ルーだと椅子に乗らないと届かなかったな。私の指示がまずかった。だけどルーもちらっと思わなかったか?届かないな、どうしようかなって。」
シェリルはルーの瞳を優しく見つめながらいった。
ルーは図星をつかれて、少し気恥ずかしくなって、てへへという感じでごまかした。
「ははは、当たりだろう。でも、そういうときは一言言って欲しかったな。」
シェリルは少し口を尖らせた表情をした。
本当だ。
なんで一言言えなかったんだろう。なんで遠慮してしまったんだろう。
シェリルさんは私にランプを掛けろと言って。
だけど私の背では届かないなと思って、いっそマリーウェザーにでも頼めば届くのにと思ったけど、でも、そこでシェリルさんの指示が間違っていると言ったら、シェリルさんが嫌な気持ちになって、私は・・・。
そうだ。シェリルさんに嫌われるのが恐かったんだ。
ルーの顔に明るさが戻った。
言わなくちゃだめなんだ。伝えなくちゃだめなんだ。
シェリルさんは気づいて私に優しく伝えてくれた。
お互いに言える関係でないとだめなんだと。
だったら、私も伝えなければ、私の意志を。
私はこんな他愛のないことでへこたれたりなんかしないし、期待されているのならその期待に応えたい。
「シェリルさん、何言ってるんですか?」
そう言うとルーはマリーウェザーに向かって言った。
「マリーウェザー、悪いけどこのランプを掛けてくれない。背が届かないの。」
それを聞いたシェリルはとびっきりの笑顔を見せて言った。
「なんだ、これからは遠慮してやらないから、覚悟しておけよ。」
シェリルはルーの頭を優しく撫でた。
ルーは体中に嬉しさが溢れるのを感じた。
「それじゃあルー、エールを入れるコップを取って来てくれないか。」
シェリルはルーにいった。
「分かったわ。アレンティー、そこのお盆を持って一緒に来てくれない。」
「いいわよ。」
アレンティーは、エールがたっぷり入った土器のピッチャーをテーブルに置くと、お盆を持ってルーと一緒に奥の厨房に入って行った。
テーブルの上には、木製スプーンと皿代わりの固いパンが人数分、エールがたっぷりと入った土器のピッチャー、野菜と豆のポタージュが入った土器のボウルが2人に1つ、手洗い用の水が入った土器のボウルと水差しが3つ置かれていた。
そこへ奥の部屋からルー達が土器のコップを人数分持ってくるとテーブルに置いた。
「それじゃあ、そろそろ始めようか。」
そういうとシェリルは背もたれのない木製のイスに腰を掛けた。
シェリルを囲むようにマリーウェザー、アレンティー、ルー達女性陣が席についた。
残りの席にはロミタスを囲むようにエバ達男性陣が席についた。
自然に女性陣と男性陣で別れて座る形になった。
エバ達は席につくと隣同士、お互いに水差しの水を注いで貰いながら手を洗った。
濡れた手はテーブルに掛けられた大判の布で拭いた。
手を洗った後は、また隣同士、それぞれの土器のコップにエールを注ぎあった。
「それじゃあ、乾杯は海賊流でやろう。」
シェリルは自分のコップを掲げた。
「どうやってやるんだ。」
キッドがコップを持ちながらシェリルに聞いた。
「神様にお祈りした後に“ゴッソ”と掛け声を掛けるから、景気よくコップをぶつけて中のエールを溢れさせるんだ。」
「へえ面白いな。」
「面白い、やりましょう。」
キッドとルーはいった。
「それじゃ、みんなコップを掲げて。」
シェリルにそう言われて、皆がコップを掲げた。
ロミタスもマーリンに促されてコップを掲げた。
皆がコップを掲げるとシェリルは皆にいった。
「今日はどの神に祈るかな。」
シェリルは皆に問いかけた。
「どの神かな。」
エバがいった。
「そうですね。」
マーリンがいった。
キッド達はあっけにとられていた。
それというのも、キッド達はいつも食事のお祈りのときには、豊穣の神であるサリカ神に祈ることが決まっていて、どの神に祈るのかなどと考えたこともなかったからだ。
「サリカ神に祈るんじゃないの?」
驚いた様子のルーにシェリルは言った。
「力になってくれなかった神に祈る必要などないさ。ルーも考えてごらんよ、今日はどの神が力になってくれたかな。」
少しの間、皆が黙って考えているとエバがいった。
「思い出の神アルリアナはどうだ。今日ルーが案内してくれたじいさん岩は、いい思い出になった。それにアルリアナは季節と風の神でもある。じいさん岩からの眺めは最高だったし、いい風だった。」
「それはいい。」
マーリンが言った。
そしてキッド達も頷いた。
「よし分かった。エバ達はもちろん、私とビリーにも旅の思い出をくれたアルリアナに感謝を。」
シェリルの言葉に皆が同意した。
「それから、海賊の私を見逃して皆に会わせてくれた、間抜けなガヤンにも感謝を。」
シェリルの冗談に皆が思わず笑った。
「最後に、ごちそうとエールを我らに与えてくれた酒と料理の神リャノと、それから宿の女将さんに大きな感謝を。」
そういってシェリルは一同を見渡すといった。
「ゴッソ!」
そういうとシェリルは向かいに座っているルーのコップに勢いよく自分のコップをぶつけた。
するとカチンという音と共に、中のエールが勢いよくこぼれ落ちた。
「きゃあ。」
ルーがびっくりして小さく悲鳴を上げた。
シェリルはその様子を見て可笑しくて笑った。
「シェリルさん、やりましたね。」
ルーはそういうと隣のマリーウェザーに腹いせとばかりにコップをぶつけにかかった。
「何?負けないわよ。」
ルーとマリーウェザーのコップがぶつかった。
中のエールがこぼれ、泡が飛び散った。
そして、エバとシェリル、キッドとビリー、マーリンとロミタス、ルーとアレンティー、皆がそれぞれコップをぶつけあった。
しかし、それでも乾杯は終わらず、相手を替えては皆延々とコップをぶつけあい、乾杯を楽しんだ。
「楽しい。」
「これは楽しいな。ぶつける乾杯なんて初めてだ。」
キッドとビリーは何度目かの乾杯をした。
「海賊の乾杯ってこんな風にやるの。」
ルーがシェリルに聞いた。
「私がいた島では、一仕事終わって陸に戻ってきたら、山ほどのごちそうを囲んで豪快に乾杯するんだ。」
「料理を皆で囲んで食べるのも初めてだけど、こんな楽しい乾杯も初めてだわ。」
ルーが興奮した様子でシェリルにいった。
そこへジェシーおばさんが深さのある大皿を両手に1つずつ持って現れると、テーブルに置いた。
「どこに置いていいか分からないから、ここに置くよ。」
「ジェシーおばさん、これは何。」
ビリーが尋ねた。
「ニワトリのブルーエだよ。」
「俺の好きなやつだ。」
大皿の中には、すりつぶされた玉ねぎや根菜類と一緒に煮込まれた鶏肉が入っており、細かく砕いたパンでとろみが付けられ、塩と自家製のハーブ、それから香辛料の胡椒とマスタードで味付けがされていた。
「ルー、早くこっちに回してくれよ。」
ビリーがルーを急かした。
「ちょっと待ってよ。シェリルさん、海賊流ではこの皿はどうすればいいの?」
「料理は皆の真ん中に置いて、食べるのはそれぞれの好き勝手さ。」
「そうなんだ。じゃあ、一つはビリー達に回すね。」
そういうとルーは一皿をビリーに渡した。
ビリーは男性陣の真ん中に大皿を置くと言った。
「さあ、エバさんもキッドも、みんなで食べようぜ。」
ビリーは周りに声を掛けると、大皿からスプーンで鶏肉をすくい、皿代わりの固いパンにのせた。
ビリーを皮切りに、皆が大皿に手を伸ばした。
しかし、ロミタスだけは手を伸ばさずにいた。
そんなロミタスにマーリンは言った。
「食べてください。我々もあなたの協力が必要なんです。」
ロミタスは黙ったままどうして良いか分からない様子だった。
「貴方は確かに一度負けたけれども、たまたまとはいえ私達に出会った。もう一度誇りを取り戻す好機ではないですか?」
ロミタスはマーリンを見た。
「シェリルは合理的で正しい判断をします。また人間社会に詳しく鼻も利きます。エルファの私が言うんです。信じてみませんか。」
マーリンの言葉にロミタスは視線を落とし、顔を下に向けた。
少しの間そうしていたロミタスは、不意に顔を上げると硬い表情のまま大皿に手を伸ばした。
そうして皆が鶏肉を固いパンにのせると、それぞれ自分用の肉切ナイフを取り出し、それで鶏肉を切り出すと、手で摘まんで口に運んだ。
ルーは横で食べているビリーの食べる姿を見て、次に向かいのシェリルが食べる姿を見て、シェリルの食べ方が上品で綺麗だと思った。
「シェリルさん、食べ方が綺麗ですね。」
そう言われたシェリルは、ちらっとビリーの方を見てからルーに言った。
「ありがとう。一応、食べ方は気にしているんだよ。」
シェリルは、固いパンの上にのっている、ごろっとした鶏肉を左手の指先で押さえ、右手のナイフで器用に肉を切り分けると、押さえた左手でそのまま摘まんで口に運んだ。
シェリルの食べ方をルーは真似ようとしたものの、今いちどうしたら良いか分からなかった。
そんなルーを見てシェリルは言った。
「背中を丸めないようにするだけで上品に見えるようになるよ。それから。」
シェリルは左手の親指、人差し指、中指の3本の指先を合わせ、何か摘まむような形にした。
「右手はナイフ役と決めて、食べ物を掴むのはこの嘴の指で食べるようにすると綺麗に見えると思うよ。」
「なるほど。やってみます。」
ルーは早速背筋を伸ばすと、シェリルの真似をして左手を嘴の形にして肉を押さえると、右手のナイフで肉を切り分けにかかった。
「ナイフは軽く持って、肉は無理に切らないで、切れそうな方向に切るようにして。」
「はい。」
ルーは少し力が入ってしまったが、肉を切り分けると、嘴の左手で摘まむと口に運んだ。
「凄く良くなったと思うよ。」
シェリルはルーに向かってウィンクして見せた。
「ありがとう。シェリルさん。」
ルーはそう言ってから隣のビリーを見た。
ビリーは大きめの肉の塊を左手でがっちりと固定し、ナイフで真っ二つにすると、ナイフを持ったままの右手でむんずと肉を掴み口に放り込んだ。
さらにビリーはエールの入ったコップを左手で掴むと、ごくごくとエールを喉に流し込んだ。
右手も左手も持っていたナイフもコップも口の周りも肉の脂にまみれたビリーは満足そうに言った。
「最高だ!」
その姿を見て、シェリルとルーは可笑しくなって笑った。
もちろん、エバ達も一緒に笑った。
「ビリーには上品さは不要だったな。」
シェリルが言うとルーが続いた。
「良かった、あんな風にならなくて。」
ルーの言葉を聞いて、マリーウェザーとアレンティーも笑った。
そしてシェリルはルーに言った。
「ここの女将さんは料理が上手いな。塩加減がいい。やはり料理は塩だな。」
シェリルがジェシーおばさんを褒めると、ビリーが続いた。
「でしょう。ジェシーおばさんは世界一料理が上手いんだ。」
皆それぞれ鶏肉のブルーエを頬張った。
「どうですか、人間の料理は。」
マーリンはロミタスに聞いた。
「・・・悪くない。」
鶏肉にかじりつきながらロミタスはいった。
するとジェシーおばさんが2皿目の大皿を持って現れた。
「はいどうぞ、ここに置くね。」
ジェシーおばさんはテーブルの端、ちょうどアレンティーとマリーウェザーの前に大きな皿を2つ置いた。
「ありがとう女将さん。とっても美味しいです。」
シェリルが女将さんにいった。
「そうかい、嬉しいねえ。私もこんな豪勢に肉を使って料理をするのは久し振りだよ。」
ルーが大皿の一つを隣のビリーに手渡そうとした。
「ジェシーおばさん、これは何。」
ビリーが聞いた。
「豚肉のミルク煮だよ。」
「今度は豚だ。」
ビリーが嬉しそうに大皿を男性陣の中央に置いた。
大皿の中には、ミルクに細かくすり潰したリーキ、玉ねぎ、ブイヨンを加え、それで豚肉を煮込んだものに、塩、胡椒、マスタードで味が整えられ、パン粉でとろみがつけられていた。
「シェリルさん。」
アレンティーがシェリルにいった。
「何だい。」
「すいません。この料理代、シェリルさんが出してくれているんですよね。」
アレンティーが申し訳なさそうに言った。
「大丈夫、大丈夫。気にしなくていいから。」
シェリルが手をひらひらとさせながら言った。
すると、少し離れた席からエバが声を掛けた。
「大丈夫。シェリルだけに負担はさせない。ちゃんと俺とマーリンも負担するから。」
エバの言葉を聞いてマーリンも頷いた。
「それなら、俺達は・・・。」
キッドがエバに向かって言った。
「言ったろ、世話になったお礼だ。それに先輩風を吹かせたいという下心もある。遠慮せず受け取っておいてくれ。」
「そういうことなら、素直にいただきます。」
エバの言葉にキッドが素直に答えた。
「そういうことで、みんな、おいしくいただこうぜ。」
ビリーがミルク煮の皿に手を伸ばすと、続いて皆がそれぞれ大皿に手を伸ばし、豚肉のミルク煮を頬張った。
「うまい。」
ビリーが喜びの声を上げると、皆それぞれ同意した。
「シェリルさん。」
豚肉を飲み込んだルーがシェリルに話しかけた。
「何だい。」
「さっき乾杯した時にどの神に感謝するかって決めていたけれど、シェリルさんはどの神様の信者なんですか?。」
男なら10歳、女なら12歳を迎えると、主要な8大神の神殿で祝福を受けるのが普通だ。
どの神様に祝福を受けるかは、基本的に親の職業によって決まった。
農民であればサリカであり、商売人であればリャノ、戦士であればジェスタ、役人であればガヤンといった具合だ。
「私はリャノ神の信者だ。海賊としてやっていくなら、港湾管理組合に所属していなければ仕事もできないからね。」
「それはリャノに入信しないと港湾管理組合に入れないということ。」
ルーが分かっていない顔で聞いた。
「逆だね。私の生まれたオーデハーゲンでは、海運や漁師など海の産業が一番の産業でね、港湾管理組合は街で一番の金と権力を握っていた。オーデハーゲンにはリャノの大神殿があるんだけど、その神殿長は港湾管理組合の理事長が兼務することになっているのさ。」
「なるほど。」
ルーは少し難しい顔をして言った。
「つまりね、海運業や水産業が盛んだから、自然に海の神を信仰する者が多いということもあるけれど、海の産業で仕事をするには港湾管理組合に所属することは必須だし、その港湾管理組合と実質一体となっているリャノ神殿の信者になることも必須という訳さ。」
「そうなんだ。」
ルーはまたひとつ新たな世界を見た気がした。
「ルーの周りにも必ずあるはずだよ。まだルーが見えていないだけで、ルーの知らないところで金と人が蠢いている。」
「金と人。」
ルーが少し曇った顔をして言った。
「そう。私の街の話をすれば、そもそも神殿というのは神に参拝するための信者のための組織だろう。だけど、その神殿のやっていることは、信者から巻き上げた金を港湾管理組合に流していた。」
「そうなんだ。」
シェリルの話をルーだけでなく、周りのマリーウェザーやキッド達も耳を傾けていた。
「港湾管理組合は、組合員からの組合費だけでなく、さらに信者からのお布施も収入として得ていたことになる。別に海の産業に関わっているのは港湾管理組合だけじゃない、海運組合、漁業組合、造船組合、船員組合だってあるのに、神殿は信者から集めたお布施のほとんどを港湾管理組合に流していたんだ。」
シェリルはルーを見るといった。
「ルーはここまで聞いてどう思う。」
「どうって。」
ルーは少し考えると言った。
「不公平だと思う。」
シェリルは少し目を細めると言った。
「そうだね。じゃあ、もう少し話をしよう。」
そういうとシェリルは話を続けた。
「港湾管理組合でおいしい思いをしている理事長もそれを支えている人達も、ただ何もせずにそんなおいしい思いをしていたのだろうか。それは違う、彼らは自分達がおいしい思いができる体制を守るために必死で知恵を絞っていたし、金と人を巧みに使って、反対する者は仕事を奪い、投獄し、殺して排除していた。」
シェリルはエールを少し口に含むと続けた。
「さらに、その体制は少なくとも数世代は続いていたから、それこそ先人達からその努力は続けられてきたと言っていいだろう。」
シェリルは一旦そこで話を切るとルーを見た。
「だから私は不公平だとは思わない。いたって公平だ。」
ルーは、そう言われればそうかもしれないと思った。
シェリルが言うように相当な努力が払われているのだとすれば、それを上回る努力もなしに現状を変えようというのは、逆に不公平だろう。
「だから私はその体制を叩き壊した。」
「えっ、今何て。」
ルーは一瞬シェリルが何を言っているのか分からなかった。
「だから、私が叩き壊した。暴力という力で。」
シェリルの目が鋭くなった。
「やつらにその不公平さを維持する努力が認められるなら、私がそれを叩き壊す努力が認められるのはいたって公平だと思わないか。」
ルーは黙ってシェリルを見ていた。
「周りからは止められたよ。友人のガヤン神官からは街の秩序が崩壊するから止めろと言われた。でもその秩序って何だ。人が自分の有利なように金をばら撒いて勝手に作っただけじゃないか。そんな不公平な秩序を守れなどと、よくガヤンが言えたものだ。」
シェリルの目が優しさを取り戻した。
「ルー達はライダーだろう。すると、街の中での勢力からすれば弱小の部類だ。生きている中で不公平な扱いを受けることもあるだろう。ただ、勘違いしてはいけないのは、その不公平は絶対なものではなく、人が作り出したもので、それを変更する機会は我々にも与えられているし、その機会が与えられていることが公平ということなんだ。」
そういうと、シェリルは喉を潤すためにエールを口に含んだ。
ルーはこれまであまり公平とかそういうことを深く考えたことがなかった。
シェリルの話を聞いて、何となく分かった気がする。
不公平とは人から押し付けられたもの、だから、貴族に生まれたからとか、生まれ持って片腕がないとかは不公平に値しない。
そして、それを変更する努力をするかどうかは本人次第なのだ。
「一つ聞いてもいいですか。」
キッドがシェリルに言った。
「何だい。」
シェリルがキッドを見た。
「その・・・暴力で叩き壊したというのは、つまり・・・」
「ん。」
シェリルはキッドの真剣な目を見て、少し慌てた風を装って言った。
「待った待った!何か勘違いしてるんじゃないか。組合にカチコミかけたけど、首獲った訳じゃないから。」
それを聞いてキッドは分からない顔をした。
そこでエバがキッドに説明した。
「キッド。シェリルは組合で大暴れはしたけど、殺しはやっていないと言っている。」
「ああ、そうですよね。分かった、分かりました。」
それを聞いてキッドも少し慌てた調子で言った。
キッドの様子を見て安心したようにシェリルは続けた。
「確かにこちらも金と人を使って勝負する方法もあったが、街の有力者はことごとく買収されていて勝ち目はなかった。さらに、私は海賊だから、暴力という力はすぐに使える状態で持っていたし、相手よりも勝っていた。だから、相手の得意な土俵では戦わず、自分の得意な土俵で戦ったということが一つ。」
シェリルは人差し指を立ててキッドに示した。
「あとは、組合の幹部や買収された街の有力者達が、やつらの得意な人と金で反撃に出てくる可能性があるから、そんな気を起こさないよう、見せしめのためにもやるなら徹底的にやる必要があった。だから組合を襲撃し、殺しはしなかったが、反抗する者はその意思が失われるまで徹底的に痛めつけてやったし、理事長の前で高価なイスも絨毯も机も書類も金庫も壁も屋根も徹底的に破壊してやった。私達の機嫌を損ねたらどうなるか、そしてお前達ではそれを止めることができないことを思い知らせてやった。」
「そういうことか。」
そういったキッドは少し考えているようだった。
そしてシェリルはさらに続けた。
「でも、必要であれば人を殺すことに躊躇はしないよ。」
「そうなんですか。」
シェリルはキッドに優しい目を向けた。
「私もエバも1人の戦士として生きているから、相手の実力が上で敗れ、命を落としたとしても後悔はない。そういう覚悟を持って生きているつもりだ。だが、その実力というのは何だ?剣の腕前か?それだけではないだろう。例え剣の腕前で後れを取ったとしても、金でも人でも罠でも毒でも、己の命さえも、なんでもいいんだ。使えるものを全て総動員するんだ。そうして相手に敗れたのなら仕方がないし、後悔はない。そして、そうすることを縛るものは何もないし、それはお互いに全く公平といえる。」
キッドはシェリルの言葉に唾を飲み込んだ。
そして言った。
「覚悟が必要ということですか。」
「そうだ。忘れてはいけないことだ。我々が生きている世界は、実力を持っているものが、持っていないものから奪う弱肉強食の世界だ。そして、奪われてどんなに周りに泣きついても、同情はしてくれても誰も取り返してはくれない。奪われないように守るのは自分しかいない。」
シェリルは小さく息を吐いた。
「キッドにそうしろと言っている訳ではないが、お前達ライダーの仲間の中で、そういう視点で考えるリーダーが必要だとは思う。」

シェリルはキッドを正面から見つめた。
「期待しているからな。」
シェリルはそう言うとキッドに笑顔を向けた。
キッドはシェリルの言葉に圧倒されて、どう反応したら良いか迷っていた。
「シェリルさん。」
そこへビリーが声を掛けた。
「何だいビリー。」
「俺に期待するのを忘れてますよ。」
ビリーがここぞとばかりに得意気な顔でシェリルに言った。
「ぶっ、はははは。」
それを聞いたシェリルは思わず吹き出してしまった。
「確かにすっかり忘れていたよ。申し訳なかった。」
「すっかりはないでしょう。すっかりは。ひどいなぁシェリルさん。」
ビリーは大袈裟にすねて見せた。
「ごめんごめん。悪かったよ。機嫌を直してくれよ。なっ。」
シェリルが胸元で両手を合わせてビリーにお願いすると、ビリーはしてやったりという顔をして言った。
「それじゃあ代わりに、俺の自慢話を聞いてくださいよ。シェリルさん。」
それを聞いてシェリルはまた笑ってしまった。
「分かったよ、ビリー。ビリーがどんなにいい男か、私に教えてくれないか。」
シェリルはテーブルに頬杖をつくと、向かいに座っているビリーに向かって首を傾け、はにかんでいるように微笑んで見せた。
シェリルがビリーに独占されてしまったので、ごちそうを囲みながら周りはそれぞれで話を始めた。
「マリーウェザー、さっき魔法を掛けていたでしょう。かっこよかったなぁ。」
ルーがマリーウェザーに話しかけた。
「ありがとう。お兄様に比べたら大したことはないけど、私が貢献できることってやっぱり魔法かなって。」
マリーウェザーはルーに言った。
「魔法ってやっぱり難しいの。」
「難しく考えなければ、そんなでもないかな。ほら、農村でもサリカ神殿で魔法を教えていたりするでしょう。」
「それは知っているけど、魔法ってなんだか想像がつかないというか、どう考えればいいのか分からないというか。」
「うーん、そうね。」
ルーの言葉にマリーウェザーは、人差し指を立てた状態で少し考えこんだ。
するとアレンティーが言った。
「例えば、サリカ神殿では天気が分かる魔法を教えているわよ。一週間の天気が分かったら便利じゃない。」
「そうか。なるほど。」
ルーはアレンティーの言葉にうんうんと頷いた。
「そうね。便利なものを選んで学ぶのはいいかもね。でも、私の経験で言わせてもらうとたまたまというのが本当のところかも。」
「どういうこと。」
ルーはマリーウェザーに尋ねた。
「私は魔法をお兄様から学んだけど、自分で何を学ぶか決めるというよりは、お兄様からこれが便利だからって教えてもらったという感じで。お兄様も言っていたけど、優秀な先生に出会えるかどうかが一番重要だって言ってた。」
「そうなんだ。」
ルーが頷くと、その後にアレンティーも言った。
「確かに、さっき私が天気の魔法の話をしたけど、そもそもそのような魔法が存在することを知らなければ、何を学べば良いのか分からないわね。」
アレンティーの言葉を聞いてマリーウェザーは頷くと言った。
「それに、魔法って何が使えるのか秘密にすることが多いでしょう。何の魔法が使えるのかを教えることは手の内を教えることでもあるし。だから例えば、ルーみたいなライダーをしている人で、魔法を上手に使っている人がいたとして、それを見つけるのも大変だし、見つかったとして信頼関係を築いて魔法を教えて貰うっていうのは。」
ルーは少し考えると、難しい顔をして言った。
「つまり、たまたまということ。」
「私はそう思う。」
「そうなんだ。」
ルーは少し残念そうな顔をした。
するとアレンティーが言った。
「でも、その理由で魔法を否定するのは間違っている。マリーウェザーにとって魔法との関係がたまたまであるのなら、ルーも当然にたまたまの関係が期待できるはずだ。」
「えーっと、それはつまりどういうこと。」
ルーは両手を組むと首を傾げた。
「つまり・・・ルーが魔法への好奇心を持ち続ける中で、たまたま魔法との素敵な出会いがないとは、誰にも言えない。」
アレンティーはルーに微笑んだ。
そうか分かった。
少しも残念なことではないんだ。
逆に、今私はマリーウェザーとアレンティーと話をすることで、魔法というものと新たな出会いを経験しているのだ。
たまたま魔法との出会う機会が近づいた時に、その経験を糧として、その機会を引き寄せることや、正しい判断が出来るかもしれない。
ルーの中で魔法への好奇心が沸き上がった。
「アレンティーありがとう。私、もっと魔法について知りたいんだけど。」
ルーはマリーウェザーとアレンティーを見た。
「もちろん。私で良ければ何でも教えてあげる。」
マリーウェザーがニコッとしてそう言うと、アレンティーも頷いた。
「じゃあ、魔法ってどうやってやるの。というか、仕組みってあるの。」
ルーの質問にマリーウェザーとアレンティーが、分かり易くどう説明するか少しの間考えた。
「魔法の仕組みは会話に似ている。」
アレンティーがそう言った。
「会話?」
ルーが不思議そうな顔をする。
するとアレンティーの言葉に、マリーウェザーの頭の中で何かが繋がった。
マリーウェザーは言った。
「つまりね、例えば私がルーの悪口を言うとするでしょ、そうするとルーの心の中は、なんでそんな悪口を言うんだろうとか、私のことが嫌いになったのかなとか、不安で一杯になるでしょ。言葉って口から発することで、変化を与える力をもともと持っているの。」
「そうなんだ。」
「言霊って言葉があるでしょう。良い言葉を発すると良いことが起こり、悪い言葉を発すると悪いことが起こるということなんだけど、魔法の原理は正に言霊と一緒で、言葉を発することで、言葉の力で現実に変化を与えようというものなの。」
「そうか、魔法ってそういうことなんだ。凄く良く分かった。」
ルーの顔がぱあっと明るくなった。
「じゃあ、私が病気になってしまった人に早く治れ、早く治れと元気づけるのも魔法なのね。」
「確かにそうね。でも、言葉の中には言葉自体に強力な力を持った言葉があるの。早く治れと言った途端に、病気を治してしまう程に。」
「凄い。そんな言葉があるんだ。」
ルーの驚いた顔に、マリーウェザーが頷くと話を続けた。
「私やアレンティーはその強力な言葉を発することで魔法を掛けているのよ。」
魔法って凄い。
魔法のことを全く知らなかったルーは、新しい魔法の世界に胸が躍った。
「じゃあ、さっきマリーウェザーが魔法で怪我を治していたけど、薬の粉を振りかけたり、小さな盾を持ってダンスのようなかっこいい動きをしていたけど、あれは何。」
ルーの質問にアレンティーが答えた。
「実際に魔法をかけるには、言葉だけで魔法を成功させることは非常に難しい。」
「そうなんだ。」
アレンティーはルーに分かってもらおうと考えながら説明を始めた。
「まずあの粉はレスティリの葉を粉砕した薬の粉。触媒と言って、魔法を掛ける時に、その魔法に似たモノを使うことで、魔法が成功し易くなる。」
「触媒?」
アレンティーはルーの言葉に頷いた。
「例えば、農村とかで雨が降らなくなった時に行う雨乞の儀式。その儀式の中で、雷をまねて木槌で桶を打ち鳴らしたり、木の枝で水を撒いたりすることがある。それは何をしているのかというと、雨が降ることを真似ることで、雨が降ることを引き寄せ、魔法を成功し易くしている。そういう魔法を成功し易くしてくれるモノや事を触媒と呼ぶ。」
アレンティーの説明にマリーウェザーが補足に入った。
「レスティリの木は命の木と呼ばれていて、万病に効くエルファの薬としてよく用いられているものなの。私が撒いた粉は木の葉を乾燥し砕いて粉にしたもので、生命との繋がりがとても強い。その生命との繋がりの強さが、怪我を癒すという魔法が成功することを高めてくれているという訳。」
「なるほど。そうなんだ。」
ルーは腕を組んで大きく頷いた。
「次にマリーウェザーが手に持っていた小さな盾。魔法とは、形のない言葉を使って、形あるモノに変化を与えようというもの。だから、それには大きな力が必要となる。あの小さな盾には、言葉が持っている力を増幅する力が封じ込められている。」
「ほら、ルーも言っていたでしょう。魔法使いって、杖を振って魔法をかけるって。その魔法使いの杖にあたるのが、この小さな盾という訳。」
「そうか、杖だけど杖じゃないんだね。」
ルーが腕を組んだまま言った。
「最後はダンス。というかあの体の動きは言葉を表している。」
「へー、そうなんだ。ダンスが言葉ってどういうこと?」
「魔法の言葉とは、神がこの世界を創造する時に使用した言葉。その言葉を人が使う時には、非常に高度な正確さと繊細さが必要。口から発する言葉だけで使い分けることは不可能。さっき話した雨乞の儀式で言えば、祈りの言葉だけでなく木槌の叩く音に合わせて踊りを踊る。そうすることで、言葉に加えて体の動きがその正確さを補い、魔法が成功し易くなる。」
アレンティーの説明が終わると、マリーウェザーが補足のために続けた。
「さっきの私に置き換えると、傷を癒す魔法の言葉の中には、言葉だけでは正確に表現することが非常に難しい言葉がいくつも含まれているから、その言葉を正確に表現するために体の動きも加えることで、魔法が成功することを高めているという訳。実質、1つの言葉に1つの体の動きがあると言ってもいいくらい。」
「凄く良く分かった。ありがとう。魔法って凄いね。」
ルーは二人の一生懸命な説明に感激していた。
「でも、普通はここまで詳しく理解している人はいないと思う。」
アレンティーがルーに言った。
「そうなんだ。」
ルーの言葉にアレンティーは頷くと話を続けた。
「大抵の人は、こうやれば使えるという使い方を教わるだけで、魔法自体について具体的に理解している人はほとんどいない。」
アレンティーの言葉にマリーウェザーも続けた。
「そうだよね。以前に街のサリカ神殿の高司祭に魔法について聞いたことがあるんだけど、月の波動がどうとか言っていて、じゃあ、その波動というものが魔法をかける際の言葉とか身振りとかと具体的にどう関係しているのか聞いても、分かるような説明をしてくれなかったのよね。だから、今ならよっぽどルーの方が魔法に詳しくなっていると思うわ。」
ルーはアレンティーとマリーウェザーの説明をよく咀嚼するために人差し指をほっぺに当てて天井を見上げて少し考えていた。
「先生。1つ質問してもよろしいでしょうか。」
「何でしょうか?」
ルーの言葉にマリーウェザーが応えた。
「お兄さんのマーリンさんは、魔法の言葉を口にしている様子もないようなのですが、魔法が使えているようなのですが。」
ルーの言葉を聞いて、マリーウェザーは困ったような顔をして言った。
「正直、何でお兄様が魔法が使えるのか私には分からない。」
「高い可能性で、お兄様が普通ではないものと思われ、魔法を理解する上ではお兄様は参考にはならないものと思料。」
「そうなんだ・・・凄いんだね、お兄さんは。」
ルーの言葉にアレンティーは続けた。
「正に理解不能。故郷のラジスの森では変人扱いだった。」
「変人?あれっ、変態だったような?」
アレンティーの言葉にルーが聞き返した。
「変人。変態ではないと思う。なぜ変態が・・・。確かに妹の私達に固執している一面は見られる。」
「それが変態だからでは。」
「???」
ルーの指摘にアレンティーが分からないという顔をした。
「分かった分かった!」
マリーウェザーが胸の前で両手を合わせると何かを思い出した顔をして言った。
「エバさんが言ったのよ、妹べったりの変態だって。それよ。」
マリーウェザーの言葉にルーの顔が一気に明るくなった。
「思い出した、そうだそうだ。だからかぁ。分かってすっきりしたわ!」
マリーウェザーとルーのやり取りに、それでは結局変態なのでは、と心の中で思うアレンティーであった。
シェリルがビリーに独占されてしまったので、ごちそうを囲みながら周りはそれぞれで話を始めた。
キッドはシェリルが言ったことを思い出して一人考え込んでいた。
エバはそんなキッドを見て言った。
「気になるか、シェリルの言ったことが。」
キッドはエバにそう言われて、エバを横目でちらっと見ると視線を上に逸らした。
そして言った。
「どうですかね。俺がまだ子どもなのかもしれないけど、実際のところ良く分からないですね。」
「そうか。」
エバはキッドの言葉に軽く目をつぶって答えると、エールを少し口に含んだ。
「エバさんが勝てないと言っていた訳が分かった気がしますよ。」
キッドは独り言のように呟いた。
「そうか。」
エバとキッドは、固い皿代わりのパンに乗った豚肉をナイフで切り出すと口に運んだ。
二人は無言で顎を動かした。
エバは言った。
「シェリルは、初めて会った時からこんな感じだった。」
エバはそう言った。
「そうなんですか。」
キッドはエバの言葉の意味が良く分からなかった。
「あいつの過去に興味はないが、どうも小さい時から海賊の首領だったみたいだ。」
「小さい時から。」
エバはキッドに向かってニヤっとした。
「やっぱりリーダーも経験なんだ。リーダー業って言えばいいのか。たぶんこんなに小さな頃から人を指図して使ってたんだろうぜ。可愛くないよな。」
エバが左手でシェリルの小さかった頃の高さを示しながら言った。
「ははは。」
キッドは思わず可笑しくて笑った。
「リーダー業でキッドが敵う訳はないさ。」
エバの言葉にキッドも頷いた。
そしてお互いにエールを口に含んだ。
「エバさんはいつからシェリルさんと。」
エバは少し考えた。
そしてキッドを横目に見ながら言った。
「ちょうど俺が成人してからの付き合いだから、4年になるか。」
「ずっと旅をしてきたんですか。」
エバはどこを見るでもなく、テーブルに両腕を置いた格好でじっとしたまま言った。
「そうだな。出会ってからずっとだ。人数が増えたり減ったりはあったが、結局シェリルと俺とマーリンが残った。」
「エバさんは何で旅を。」
キッドがエバに尋ねると、エバはキッドをちらっと見て、そして言った。
「俺の話は前向きでも大した話でもないんだが。」
キッドはエバを見た。
エバは目を細めると続けた。
「俺にはどうしても妥協できないことがある。」
エバはキッドから目を逸らした。
「それを妥協して生きていくなんて俺には耐えられないんだ。」
エバはまっすぐに何かを見つめているようだった。
「一つの場所に留まれば周りに迷惑がかかる。あいつらなら俺を受け入れてくれる。」
そう言うとエバはキッドに視線を戻した。
「それに、」
エバはキッドに向かって笑みを浮かべた。
「一つの街にいたら、いつの間にかシェリルに支配されて、シェリルの街になっちまう。」
「ははは。」
キッドはエバの冗談に思わず笑った。
「いっ!」
エバがへんな声を出した。
「どうかしたんですか。」
キッドがエバに聞いた。
「いや、何でもない。」
エバは少し引きつった顔をしてそう言った。
「でも、シェリルさんなら支配されてもいいかな。」
キッドが軽く笑みを浮かべた。
「弱肉強食だぞ。」
「ははは。」
キッドはエバの冗談にまた笑った。
「うっ!」
エバがまたへんな声を出した。
「大丈夫ですか?」
キッドが心配そうに言う。
「大丈夫だが・・・隣に座ったのはまずかった。」
「?」
エバの言葉にキッドは分からないという表情をした。
二人はエールを口に運んだ。
「聞いてもいいですか?」
キッドはエバに話し掛けた。
エバは無言で目をつぶってみせた。
「エバさんはどうやって剣術を。」
来たか。エバはそう思った。
前からキッドの視線に自分の剣に憧れのようなものを感じていた。
男であれば暴力に対しての強さに憧れるのはエバは理解できた。
「俺の親父は傭兵だった。だから俺は物心着いた時から、親父が所属していた傭兵隊と一緒に旅をしていたんだが。剣術の基本は親父から教わった。」
「剣術の基本というのはどういうものなのですか。」
キッドがエバに聞いた。
「剣術と言ってもいろいろな種類がある。俺の流派はファイニア式の片手剣と盾を使う。」
「ファイニア式とは。」
「ファイニアというのは俺の生まれた国の名前だ。それぞれの国で軍事教科書が作られていて戦い方に特徴がある。ファイニアにはティアゴという片手剣と盾の達人がいたんだが、俺の親父は幸運にもティアゴの子孫から直接指導を受ける機会に恵まれた。」
「凄いですね。」
達人と聞いてキッドの目が輝いた。
「基本は打ち斬りと打ち突き。打ちというのは盾で打つこと。また、斬りは首、腕、足。突きは頭と胴に分かれる。」
エバは左右の手を軽く交互に突き出しながら説明した。
「盾で殴るんですか?」
「殴るというよりも、カウンターで打ち止めるように使う。相手の攻撃を軸を外して踏み込み、盾で右手を打ち止めておいて斬ったり、盾越しに刺したりという使い方だ。この基本稽古を日に3,000本を目標に行う。」
「3,000本ですか!」
キッドが驚いた様子で言った。
「大丈夫だ。斬りと突き、狙う部位もいろいろあるし、持ち手も入れ替えるから、やってれば3,000本はいく。日に3,000本がこなせるようになると自然と基礎体力もつく。」
エバは平然と言ってのけた。
やはりとんでもない人だとキッドは思った。
「基本稽古が終われば次は型をやる。」
「型ですか?」
エバは頷いて見せた。
「型は動きが決まっていて、決められたとおりに力を入れ、逆に力を抜き、正確に動く練習をする。それを何度も何度も繰り返す。」
「そうなんですか。」
「型は2人1組でも行う。これを対錬といって間合いや攻撃の間を身に着けるには効果的だ。俺はシェリルとよく稽古している。」
キッドはまだ合点がいっていないようだった。
「エバさん、いまいち型がどういうものか分からないんだが。」
「剣を稽古したことは。」
「自己流に練習したことはありますが、エバさんの話を聞くと、遊びみたいなものだと思います。」
「そうか。」
剣術の基礎的なところを、何の心得もなしに自力で習得することは非常に困難だった。
キッドは、強くなりたいのに方法が分からないのだと、エバには分かった。
「明日、少し教えてやろうか。」
「本当ですか。」
キッドが嬉しそうに言った。
エバが頷いて見せた。
「やった!ありがとうございます。」
するとそこへジェシーおばさんが3つ目の大皿を持って現れた。
「ジェシーおばさん、これは何。」
キッドの隣に座っているビリーが尋ねた。
「豚肉のローストだよ。」
大皿の中には、大きめの塊に切られた豚肉に細かく砕いたパンをまぶし、塩と自家製のハーブを振りかけたものを串に刺して焼いたものが、串から外されて入っていた。
「美味しそう。シェリルさん食べましょう。」
キッドは隣のビリーが楽しそうだなと思った。
エバとキッドは豚肉のローストを頬張った。
「美味いな。」
エバの言葉にキッドも頷いた。
肉を飲み込んだキッドが言った。
「エバさんが、こいつは強いと思った人っているんですか。」
「いる。」
エバは即座に答えた。
「1人だけ。負けはしなかったが、これは勝てないと思ったことが一度だけある。」
「そんな奴がいるんですね。」
キッドが驚いたような顔をした。
「知りたいか?」
「ぜひ。」
エバはエールを喉に流し込むと、空になったコップに土器のピッチャーからまたエールを注いだ。
「そいつは鉄壁のベルギルと呼ばれていた。」
エバは話し始めた。
「俺が親父と傭兵隊にいたときから噂だけは聞いたことがあった。ファイニアの隣の国、ソイル選王国の傭兵で、全身を分厚い鉄板で覆った大男で、どんな攻撃を喰らっても引くことがない、文字通り鉄壁だと言われていた。」
「かっこいいですね。」
エバは話を続けた。
「親父が戦死したのを機に俺は傭兵隊を離れて、バドッカという街でシェリルに会った。そしてシェリルとマーリンと一緒に旅を続ける中で、ソイル選王国に行ったことがあったんだが、そこでたまたま奴と戦う機会があった。」
エバはキッドを見てニヤッと笑みを浮かべた。
「どうでした。」
キッドは尋ねた。
「一目見てすぐに分かった。身長が2m20cmはあった。でかくて、鉄の鎧もごつくてまさに鉄壁だった。」
「凄い。」
キッドは少し興奮していた。
「持っている得物も凄くて、こんな大きな刃のついた巨大な斧だ。それを両手で持っていた。」
エバは長くて大きい斧の大きさを両手で示しながら言った。
「ビビッて戦う気も起きないですね。」
キッドの言葉にエバは頷くと続けた。
「全くだ。だが、当時の俺は自分の腕に自信があった。奴を転ばせれば勝てると思っていた。だから俺は“崩撃”という敵を転ばせてから両手で持った剣で突き刺すという型を使うことにした。だが、」
エバはキッドを見た。
「びっくりした。間を計って左手の盾で奴の斧を腕ごと封じ、同時に奴の右足を踏んで固定してから、盾で押し倒そうとしたんだが、びくとも動かなかった。そして次の瞬間、こっちが押し返されてしまい、即座に巨大な斧が振り下ろされた。」
キッドはエバを見ると、エバは笑っていた。
「後から一緒に酒を飲む機会があって、その時に聞いたんだが、ああいう時は脱力しているらしい。」
「脱力。力を抜いている。」
エバは何が嬉しいのかニヤニヤしていた。
「奴の戦術は単純だ。相打ち。武器を繰り出すときには、どうしても力を込める一瞬に全身が硬直する瞬間が必ず存在する。そこを狙う。」
「それだと敵の攻撃も喰らいますよね。」
「そこが奴の卓越したところだ。奴は攻撃的防御と言っていたが、俺が考えるに3つの技術を使っている。」
キッドはエバの話にわくわくした。
エバはキッドが興味を持っている様子を見て続けた。
「一つ目はわざわざ隙を作って攻撃を一定部位に誘導している。次に鎧の強度が強くなる箇所と角度で敵の攻撃が当たるようにしている。3つ目に相手の攻撃の衝撃が最大となる前に体を自らぶつけて攻撃を潰している。」
「なるほど。」
「俺はさらっと言っているが、実際にやるには相当な経験が必要だし、さらに奴は、その戦術をいかに敵に気づかせないように偶然的に見せるかに相当な注意を払っていた。」
キッドは黙ってエバの話を聞いていた。
「見た目の破壊的で圧倒的な印象と比べたら、戦術は非常に繊細で緻密だと思わないか。」
「そうですね。」
キッドは強さというものがおぼろげながら見えてきた気がした。
「俺は転ばせるのに失敗したので、次は、鎧に何度も衝撃を加えて変形させ、動きを止める戦術に切り替えた。だが、何度か奴の膝関節を打ったが、奴の動きが止まることはなかった。奴は足を狙われるのは慣れていて、さっき話した3つの戦術で俺の攻撃をことごとく潰していたんだ。」
「鎧を変形って、そういうことあるんですか、」
「板金鎧の関節部分は職人技で精密に作ってあるから、逆に鉄の棒を打ち付けて変形させることで動きを制限することができる。」
エバは自分の肘関節を動かして見せながら言った。
「でも相打ち狙いの相手に、よく無事でしたね。」
キッドがエバに言った。
「こっちも伊達に稽古を積んでいない。ティアゴ流は防御と攻撃を同時に行う。まともに奴に斧を振らせることはない。とはいえ、こちらの攻撃も奴に通じない。拮抗した状態だ。」
エバは一旦言葉を切ると、エールを一口、喉に流し込んだ。
「俺は正直、噂通りに、こいつは何度打ち込んでも倒せないんだと思うようになっていた。あとは、相手の斧を破壊して肉弾戦に持っていくしかないと考えた。ただ、それはやりたくなかった。」
「肉弾戦ですか。」
キッドが尋ねた。
「そうだ。斧を破壊したら、足に組み付いて、倒して、兜のヴァイザーを引き上げてナイフで止めを刺す。」
「なるほど。」
「だが、それをやったら、俺の剣は奴に通じなかったことを認めることになる。」
「どういうことですか。」
キッドはエバに言った。
「肉弾戦。それはもう剣術とは呼べない。鉄壁である奴に、俺はこれまで稽古を積み上げて来た剣術で勝利を得たかった。そうでなければ価値がないと思っていた。」
命の取り合いである戦い。シェリルの言葉で言えば、使えるものは何でも使えば良いはずなのに、自ら制限を加えている。それは合理的とは言えないのではないか。
ただ、その戦いにこだわる姿勢は、キッドにはとても清々しく思えた。
お互いに、純粋に戦いの技術を磨き上げて来た者同士だから、お互いに積み上げて来たものに敬意を表せるし、暗黙のうちに純粋に技術で勝負することに同意ができるのだろう。
「その後はどうなったんですか。」
「あとはぐだぐだの体力勝負だ。意地の張り合いだ。奴は俺に決定的な一撃を加えようと斧を振り下ろした。俺はとにかく奴の攻撃を抑えて剣を打ち込んだ。奴の胴に腕に足に。そして終わりは不意に訪れた。」
「どちらが勝ったんですが。」
エバは首を左右に振った。
「お互いに息が上がって、一旦距離を取って肩で息をしていた時、俺の中の闘争心が急に一気に消え失せた。俺はその場に立ち尽くした。奴もそれ以上攻めてこなかった。そして勝負は引き分けで終わった。」
エバが話し終えるとキッドも息を吐いた。
「凄い戦いでしたね。」
「俺が唯一勝てないと思った相手だ。」
エバとキッドは共にエールを口に運んだ。
「また戦いたいですか。」
エバはキッドを見て笑った。
「もう一度会いたい。今度は俺が勝つ。」
キッドは、エバもベルギルもかっこいいと思った。
それは2人が本当の戦士だからだ。
積み上げている稽古の量も、戦いに懸ける覚悟も、純粋で清々しい。
キッドはエバが大量殺人鬼には見えない理由が分かった気がした。
エバは普通の人間と住んでいる世界が違うのだ。エバは純粋な戦いの世界に生きている。
そして戦いに当然のように己の命を懸けていて、戦う相手にも同じ覚悟を求めている。
それはお互いに対等であるからだ。エバは戦う相手を上にも下にも見ていない。だから平然と人を殺せるのだろう。
「なんか・・・素敵ですね。戦いが終わったら一緒に一杯やったんですか。」
キッドが笑顔で聞いた。
「俺達は別に恨みつらみで戦っている訳じゃない、戦いがあるから戦っているだけで、戦いが終わればなんのわだかまりもない。」
キッドは自分はどうだろうと思った。
母親は自分を生んで死んだ。
父親は12歳の時に疫病で死んだ。
キッドは人買いに売られて、ある農家の奴隷となった。
奴隷が何となく嫌で金を盗んで飛び出した。
ステインの街に着いて、盗んできた金で自分の馬を1頭買った。
これから何かが変わる、変えてやる。
晴れやかな気持ちだった、まだ見えない未来に心が躍った。
今でも、何か変えてやるという気持ちは変わらない。
だが、エバやシェリルと出会って、もう少し正確に自分を見つめられそうな気がした。
俺がなんで奴隷が嫌で飛び出したのか。
何かを変えるというのは、具体的にどういうことなのだろうか。
生きるということをもっと真剣に考えなくてはいけない。
普段の日常に何となく流されていてはいけない。
そして、エバやベルギルと対等に肩を並べて話が出来る時が来たら、最高じゃないか。
キッドの胸の中で、何か心の芯のようなものが生まれた。
「目つきが変わったな。」
エバはキッドにそう言った。
「そうですか。」
キッドの顔は晴れやかだった。
「強くなりたいと思ったか。」
「強くなりたい。心からそう思います。」
「明日、時間は限られているが、強くなるために必要な基礎を体に教えてやる。基礎ができるようになればその先は、自分で探して行くこともできるだろう。」
キッドは自分が求めている強さが剣なのかどうか分からなかったが、エバから受ける指導が自分の人生に重要なものになるだろうと感じていた。
「じゃあ、明日の朝4時に宿屋の前に集合だ。」
「りょ、了解です。」
キッドは咄嗟に了解とは言ったものの。4時はまだ日が昇る相当前で、外はまだ真っ暗だ。
これはとんでもない指導になりそうだと、キッドは覚悟を決めた。
シェリルがビリーに独占されてしまったので、ごちそうを囲みながら周りはそれぞれで話を始めた。
「ロミタスさんの森はどれくらいの規模ですか。」
ロミタスはくすみがかった銀髪を編んで横にいくつか垂らしており、顔には赤色と緑色が特徴的なペインティングを施していて、年齢は160から200歳程度、人間では中年に当たる年齢であり、マーリンと比べればずっと年上に見えた。
マーリンは同じエルファであるロミタスから、この辺りのエルファの生活の様子を聞いてみたいと思っていた。
マーリンの言葉を聞いたロミタスは、横目でマーリンを見ると言った。
「あんたはお得意の魔法で俺の事を知っているようだが、俺はあんたの事を名前さえ教えて貰ってないぜ。」
「すいません。私は旅をしながら医術を研究している者です。マーリンと言います。」
マーリンはそう言って手を差し出したが、ロミタスは握ることはなかった。
マーリンは、自分が何者かを問われた場合には、医術の研究者と答えるようにしていた。
魔法使いだと言うと警戒されるからだ。
魔法使いというと、何者なのか分からない、何をするか分からないと思われ、どうしても警戒されてしまうのが常だった。
「魔法使いじゃないのか。」
「多少使えますが、大したものではありませんよ。」
ちょうどテーブルの反対側では、マーリンの妹達がルーに魔法の話をしていたのだが、その会話が断片的に聞こえてきた。
「ふーん。」
マーリンは頭を掻いた。
「どこの森の者だ。」
「以前はグラダス半島のサイスの森に住んでいましたが、旅に出た4年前に森は捨てました。」
「何か争いごとがあったのか。」
「いや、そういうことではなくて、研究のためです。」
マーリンは慌てた風を装ってそう答えた。
「まあいいか。・・・俺のいる森の規模は1万人程度だが、今年で下回った。」
ロミタスはマーリンを黙って一瞬見て、それからそう言った。
「減少傾向にありますか。」
「そうだな。」
渋い顔をしてロミタスはそう言った。それを聞いたマーリンは言った。
「どうやら、どこの森でもその傾向にあるようです。」
マーリンがそう言うと、ロミタスの渋い顔は驚いた顔に変わった。
顔に素直に出るんだな。マーリンは思った。
「それは本当か。」
「本当です。私は旅をしながらエルファに話を聞いて回っているのですが、グラダス半島のラジスの森でも、青の帝国の南にあるサイスの森でも、エルファの人口は減っています。」
「そうなのか。」
ロミタスはマーリンの話に衝撃を受けたようだった。
「若者の数が減っていませんか。」
「確かに減っている。」
「相対的に老人が増えている。」
「そうだな。」
ロミタスはエールの入った土器のコップを持ったままそう言った。
ロミタスは何か考えているようだった。
マーリンはロミタスに聞いた。
「森林開拓って知りませんか。」
ロミタスは分からない顔をした。
「何だ、それは。」
「荒れ地を開拓して森林にするんですよ。つまり、森林を増やすんです。」
「馬鹿な!そんなことをすれば人間や他種族と争うことになる。」
ロミタスが興奮した顔で言った。
エルファは円環といって、昨日も明日も永遠に安寧とした“今日”が続く生き方を目指しており、発展的な政策は否定されていた。
その為、人間や他種族と衝突することも避けるため、森を拡張することは厳に禁じられていた。
「そう思うのも仕方がないとは思いますが、実際にサイスの森で若いエルファから出た意見です。老人達に潰されたそうですが。」
サイスの森とは、世界の中心であると公言してはばからない青の帝国の南に位置し、リアド大陸で最大のエルファの居住地となっている森だった。
エルファの森では、森全体に関わる重要な問題については、権力を持った老人達による長老会議によって決められており、若者の意見が認められることは期待できなかった。
「サイスの森でそんな話が。知らなかった。」
ロミタスは動揺が顔に現れていた。
「エルファの寿命は円環によって、ここ千年の間で飛躍的に伸びてきました。今や長老達の中には400歳を超える方も出てきています。ロミタスさんの森ではどうですか。」
「そうだな、最長老は400歳に近い。」
「ただし、人口は年齢層が若くなるほど少なくなっている。一番人口の多い年齢層は240歳から300歳あたりではないですか。」
「確かにそうだ。」
「一番元気がある60歳から100歳の若者の人口は年々減り続けている。」
ロミタスは眉間に皴を寄せた。
「まあ、そうだな。」
ロミタスは若者の人口を正確に把握している訳ではなかったが、普段森を見ている印象では若者が減っていると感じていた。
「なんでだと思います。」
「それは・・・」
ロミタスは言い淀んだ。
何となく分かっている気がしたが、はっきりと言葉に出てこなかった。
「ロミタスさんは部族長ということでしたね、部族長は幹部の回り持ちですか?」
ロミタスはマーリンの問いかけに恐る恐る答えた。
「そうだが。」
「幹部の入れ替わりは?一番最近行われたのはいつでしたか。」
「そんなものはない。」
森に生きるエルファはたくさんの部族に分かれ、その部族が所有する森を管理していた。
部族の長である部族長は、部族の中の幹部達によって、おおよそ8年から12年周期で順番に交替する回り持ちとなっていた。
マーリンはその幹部達の交替があったのはいつだったかと聞いたのだが、少なくともロミタスが幹部になってから、新たに幹部に加わった者はいないし、その逆もない。
そもそも幹部は世襲であり、親から子へ受け継がれはするが、それ以外に交替となることがあるのかロミタスには分からなかった。
「別にロミタスさんの部族だけがという訳ではありませんよ。どこの森でもその傾向があります。」
マーリンは喉を湿らすためにエールを口に含んだ。
「あと、人手が不足しているのに、森も不足している自体が起こっている。」
ロミタスはマーリンの言っていることが理解できなかった。
「それは・・・どういうことだ。」
「森を育てているセローハマの部族の話です。部族の若者が少なくなったことで人手が足りず、荒れてしまう森が増えている一方で、部族の末端の身分が低い者はこき使われるばかりで、いつまでたっても自分の森が持てない。」
「何だって。」
森に生きるエルファはたくさんの部族に分かれ、その部族にはいくつか種類があったが、一番勢力の大きい部族がセローハマと呼ばれ、森を育て、食糧を集める部族であり、エルファの森にはセローハマの部族がたくさん存在した。
部族の中では明らかな身分の違いが存在し、身分が高い者から順番に、部族長を含む幹部、働き手を指揮する管理職、一番身分が低い末端の働き手に隔てられていた。
またその身分は上がることも下がることもなく、末端の働き手は死ぬまで働き手であったが、それはエルファが理想とする円環という生き方、つまり、それぞれの者が、それぞれの役割を、永遠に安寧と果たし続けるという生き方を維持するためには、必要なことと考えられていた。
部族の中で森を所有しているのは幹部であり、その幹部から、自分の森として割り当てを受けられるのは管理職までで、末端の働き手は他人の森で働くだけで自分の森を持つことはできなかった。
そもそも森のほぼ全域が、既におのおのの部族に割り当てられていて、新たに末端に与えられる森はない状況だった。
一方で、末端の働き手でも年寄りが増え、若い働き手が少なくなってしまい、荒れてしまう森が増えてしまっているのだ。
ロミタスにとっては、身分が変わらないことは当たり前のことであり、部族長がその役割を果たすために、末端の働き手に命令して働かせることは当たり前のことで、“身分が低い者はこき使われるばかり”だとか、“いつまでたっても自分の森が持てない。”などと言われたのはマーリンが初めてのことだったので、心に強い衝撃を受けた。
「だまって従ってはいるが、心の中ではそんな風に考えていたのだろうか。」
ロミタスは眉間に皴を寄せた。
ロミタスは森を守るプファイトという部族の部族長であったが、セローハマの部族と同じように身分に違いがあったし、身分が変わりがないという点も同じだった。
だが、森を外敵から守るという使命のために、一丸になっていると信じていた。
それが、例えば“隊長よりも俺の方が強いのに”とか“俺の方が戦いで活躍したのに”なんで末端の戦士なのか?そう不満をくすぶらせている者がいるかもしれないということか。
「何を考えているかなんて、外見で分かるものじゃないですよ。それに、部族長に聞かれても本音は言い難いでしょうし。」
外見なんて人の実力の少しも表しているものではない。
それは戦士であるロミタスは良く知っていたことだ。
どんなに恐ろしい大きな刃を持った敵であっても、首からいくつも髑髏をぶら下げていたとしても、問題はそいつがどれくらいの脅威となるのかだ。
それを冷静に見極めることが重要で、得てして外見というものは、自分を誇大に見せるか、あるいは逆に小さく目立たなくさせるための嘘だ。
しかし、ロミタスの末端の戦士達が、言葉には出さずとも不満を蓄積させているのだとしたら、それは、ロミタスが大人しく従っている外見に騙されてしまっていたことにならないか。
自分は外見には騙されないと慎重であったはずなのに。
マーリンは続けた。
「それだけではありません。年寄りの中には、ただ寝床から起きたり、歩いたりすることもままならくなって、常に誰かが面倒を見てあげる必要のある老人が増えています。その老人の面倒を、末端の働き手や“卑木”の若者にやらせようとしている。いや、実際にやらせているところもあります。」
「うむ。」
“卑木”とは末端である働き手のさらに下の身分の者達だ。人間の世界で言えば乞食が比較的近い。
老人の介護を末端の若者らにやらせる話は、ロミタスの森でも老人達の間でその動きが出てきていた。
エルファの寿命がまだ短かった時には、老人が老衰によって介護を必要とした時には、その子供は中年でまだ元気があった。
しかし、ここ千年の間に寿命が伸びてしまったことで、老人が老衰によって介護を必要した時には、その子供も年寄りになってしまっていて、老人介護をやろうにも自分の体も弱ってしまって十分に介護ができないのだ。
例えば、400歳に近い最長老の息子は300歳程度であったが、300歳とは人間でいえば80歳程度であり、老人が老人を介護する状況となっていた。
そこで介護をすることが大変なので、他人である末端の働き手や卑木の若者に介護をやらせようというのだ。
「私は森を捨てた身ですので、好きに言わせて貰うんですが。」
マーリンはロミタスを正面から見た。
「若者が減っているのは未来がないからですよ。」
マーリンの言葉をロミタスは無言で聞いていた。
「ここにいる人間の若者を見てください。キッドもルーもビリーも、未知の世界を自分の力で切り開いていこうときらきらしている。若者とは本来こういう姿をいうのではないですかね。」
マーリンは一旦そこで言葉を切った。
するとそこへジェシーおばさんが3つ目の大皿を持って現れた。
「ジェシーおばさん、これは何。」
向かいに座っているビリーが尋ねた。
「豚肉のローストだよ。」
「美味しそう。シェリルさん食べましょう。」
マーリン達の前にも大皿が置かれた。
隣に座っているエバとキッドがその大皿に手を伸ばす。
そしてマーリンとロミタスも豚肉のローストに手を伸ばした。
ロミタスは豚肉にかじりつき肉を引きちぎると、力強く噛み潰して飲み込んだ。
そして言った。
「それで森林開拓か。」
マーリンは頷いた。
「円環。永遠の今日。それは老人にこそふさわしい。若者には未来が必要です。未来とは未知の世界へ一歩踏み出すこと。未来とは計り知れない可能性を感じさせるもの。エルファの若者のどこに未来がありますか?」
マーリンはロミタスを見た。
「若者に老人介護をやらせているような生物が繁栄できると思いますか?エルファは、緩やかに滅びへの道を歩み始めているのではないですか。」
マーリンは、エルファの身分社会を心の底から辟易していた。
両親のいないマーリン達兄妹は、物心ついた時には、既に差別があった。
マーリン達兄妹は、末端である働き手のさらに下の身分である“卑木”とされていた。
マーリン達兄妹は食べ物を得るために、セローハマの部族の働き手に交じって働いていたが、食事の時間になると幹部らの子供から食べ物を恵んで貰っていた。
卑木はエルファの社会である円環の一員とは認められておらず、円環に寄生する者、卑しい者、未熟者と認識されており、いつ森を追い出されるか分からない身分であった。
そのため、幹部らの趣味で作られた無意味な礼儀作法があり、挨拶の仕方や話し方など、いちいち幹部らを持ち上げて、特別に扱うように命じられた。
例えば、話しかける時には申し訳なさそうに話しかける必要があった。
うっかり友人と話すように対等に話し掛けると、「礼儀がなっていない。」としつこく注意され、機嫌によっては食事がお預けになった。
部族で共同で使っている樹木を剪定するための農機具があり、効率よく使うために使い終わったら他の者が使えるように保管場所に戻しておくことになっていたが、ある幹部の妻が、自分の好きな時に作業ができるよう常に自分の手元に置いていた。
ある時、他の働き手と共にマーリンも作業しようとすると農機具が足らず、ちょうど幹部の妻は作業していなかったため、「空いているなら非効率なので貸してください。何で保管場所にすぐに戻さないのですか。」と言ったら、「礼儀がなっていない。二度と顔を見せるな。」と言われ、2週間程、森の外に追い出された。
だが、そのような扱いを受ける度に、ただでさえ無意味な礼儀作法が、時間がかかるばかりで、何の利点もないことが余計に感じられ、幹部らに対して畏敬の念などは浮かぶことはなく、自分を偉く見せようとする品性の低さばかりが感じられた。
食べ物を運んできた幹部らの子供の中には、自分にも親と同じように特別扱いするよう命令する者もいて、“食事を恵んでいただいて申し訳ありません。”“恵んでくれるあなたは神様です。”というような態度をしていないと「礼儀がなっていない。」と言われ、食事はお預けになることもあった。
幼かったマーリン兄妹は追い出されることはなく、食べ物にもありつけはしたが、働いたことの対価として食べ物を貰っているのではなく、追い出さずに置いてやっている、食べ物を恵んでやっているという扱いだった。
だから、災害が森を襲って食べ物が少なくなると、途端に施しはなくなって、食べられなくなった。
空腹で震える妹達を見て、マーリンはエルファの社会に絶望した。
こんな毎日が延々と続くのかと。
それが円環なのかと。
「確かにお前の言うこと、一理あるかも知れん。だが、お前の言う森林開拓を進めれば、必ず人間や他の生物と領地を掛けた争いに巻き込まれることになる。そこでたくさんの命を失うこととなろう。それが果たして本当に幸せと言えるかな。」
ロミタスはマーリンをチラッと見るとエールを口に含んだ。
マーリンも黙ってエールを口に含んだ。
ロミタスは続けた。
「それをよくよく考えたうえで、先人たちが選んだものが円環ということだろう。それに、どんなものも完璧というものはない、多少の犠牲は不可欠だ。例えば、卑木という最下層の者がいればこその円環と、考えることはできないか。」
確かに、卑木という最下層の身分があることで、末端の者達は、自分達よりもさらに下の者がいる。卑木よりはましな生活を送れている。そう溜飲を下げることができることも確かだった。
それを聞いてマーリンは言った。
「私は、妹達もですが、森に住んでいた頃は卑木でした。あなたには卑木がどのように思って生活しているかわからないでしょうから教えてあげますよ。円環なんて糞くらえ。ですよ。」
ロミタスはマーリンは見たが、マーリンはいたって冷静だった。
「あなたには分からないでしょう。幼い日に森から追い出され、何日も空腹に耐えながら、さ迷い歩いた時の気持ち。空腹と寒さに震える妹達を眺めていることしかできない時の気持ち。あまりの空腹のために誇りを捨てて、幹部に媚を売ってすり寄る時の気持ち。」
ロミタスにはどれも経験のないことばかりで、何と言っていいのか分からなかった。
マーリンは言った。
「ただ、私が言いたいのは、あなたに私の気持ちが分かって欲しいということではなくて、卑木だからと言って大人しくしていると思ったら、大きな間違いだということですよ。」
ロミタスには、マーリンが円環というエルファ社会に宣戦布告をしているように思えた。
「我々が生きている世界は、実力を持っているものが、持っていないものから奪う弱肉強食の世界だ。」
シェリルの言葉だ。だがシェリルはこうも言った。
「やつらにその不公平さを維持する努力が認められるなら、私がそれを叩き壊す努力が認められるのはいたって公平だと思わないか。」
そういうことだ。
世界は、変えようとする者と、変えさせないようにする者とのせめぎあいで創られていく。
円環という政策も、円環の外の敵との衝突を避けることには血筋を上げて来たが、結局、円環の中では不満が蓄積されていて、そのせめぎあいからは逃れることはできないということだ。
ロミタスの森でも、森林開拓を主張する若者が出て来るかも知れない。
その時に、ただ叩き潰せば良いとは、今のロミタスには考えられなかった。
そうではなく、円環はどのように変えていけるだろうかと、考えなければならない。
「それから、エルファの生き方である円環の素晴らしいところが、人間よりもはるかに長命であるところだと言われていますが、ただただ長く生き永らえることに、何の意味があるんですか。よっぽど尊厳のある死を選んだ方がましですよ。」
「何だと!お前の言っている尊厳のある死とはなんだ。」
ロミタスは円環の象徴ともいえるエルファの長命さを否定されたことが、自分を否定されたことのように感じた。
「尊厳のある死とは、自分が自分らしくいられるうちに、自ら死を選択することです。」
マーリンがエバとシェリルと旅をして、共に生きて、常に感じるのは、自分らしく生きたいということだ。
それができなければ生きている価値などない、死んだ方がまし。
そういう意思を、特に言葉で交わさなくても強く感じる。
そしてマーリンもその考えに共感している。
子どもの頃に過ごした円環の生活を一生続けるなら、死んだ方がまし。
マーリンは話を続けた。
「老衰によって体の至る所が壊れ、ついには死に至る。それは自然の死であって、エルファが尊い死として受け入れて来たものです。ですが、ロミタスさんの部族ではどうか分かりませんが、老衰によって次々に壊れていく所を、魔術を使って次々に治して、無理やり生き永らえさせていることが、最近は普通に見られるようになっています。」
確かにそれはある。ロミタスは思った。
ロミタスの住んでいる森でも、それは普通の事となっている。
円環によりエルファの寿命が伸びたことによって、レスティリが使う癒しの魔術は、体の至る所に不調を訴える高齢者に使われることが普通になっている。
ロミタスは単純に、年寄りがいつまでも元気でいられることが良いことだと勝手に思っていた。
ただそれが、自然に死に向かっている体を無理やりに、不自然に延命しているのだとしたら、自然の死を尊いとしてきたエルファの考えと矛盾することとなる。
年寄りに会えば、いつまでも元気でいてくださいと言葉をかけていたものだが、それは安易な言葉だったのだろうか。
「そうやって無理やりに生き永らえさせた結果、最近、頭がおかしくなってしまって、妻や家族が分からなくなってしまったり、目的も分からず森を徘徊したりする老人が見られるようになりました。」
「本当か、それは。」
ロミタスの問いにマーリンは頷いた。
実はロミタスの森でも、それは問題になっていた。
しかも頭がおかしくなってしまうと、レスティリの魔術でも治すことが出来なかった。
それが、自分の森だけではなく、他の森でも起こっている。
その事実にロミタスは衝撃を受けた。
「例えば、ロミタスさんが頭がおかしくなってしまって、家族や部族に迷惑を掛けるようになってしまうとしたらどうですか?それでも生きたいと思いますか。」
ロミタスはどう答えて良いか分からなかった。
ロミタスの様子を見てマーリンは言った。
「私だったら嫌ですね。死んだ方がましです。」
こいつは言い難いことをずばずばという奴だ。ロミタスは思った。
確かにマーリンの気持ちも分からないでもない。だがロミタスは、何か胸の中がもやもやとして、納得できないところがあった。
自ら死を選ぶことが果たして許されることなのだろうか。
命とは最も大切なものではないのだろうか。
マーリンはロミタスの様子を見た。
「納得できませんか。それは恐らく、命が一番大事だと勝手に思い込んでしまったためです。でも本当は分かっているはずなんですよ。自分の命など取るに足らないものだと。例えば・・・娘さんのエイリスさんのためなら命を投げ出すことも惜しくないと思いませんか。」
ロミタスは鋭い視線でマーリンを見た。
マーリンはその視線でロミタスの答えを読み取った。
「他にもありますよ。森を守る戦士のあなたは、森を守るためなら自分の命など惜しくないと思っていませんか?他人の子供であっても、自分が命を投げ出せば助かるとなれば、咄嗟に投げ出しはしないですか?自分の跡を継ぐであろう可愛い後輩のためならどうです?」
ロミタスは黙ってマーリンの言葉を聞いていた。
ロミタスは森を外敵から守る戦士の部族の長であった。
故に、森を守るためであれば命を懸けることは当然だと、疑ったことはなかったし、部下にもそう指導してきた。
おかしな話だ。
俺は既に自ら死を選ぶ覚悟をしていたし、それを部下にも強いていたというのに。
「以外でも何でもない。自分の命より大切なことは普通にあるんです。投げ出せるんですよ平然と、自分の命を。決められるんですよ、自分の死に際を。人にはあるんですよ、自分の死期を自ら決める権利が。」
ロミタスはマーリンの言葉の迫力に圧倒されてしまった。
この見た目やせ細った頼りなさそうな男は、一体どんな人生を送ってきたのだろうか。
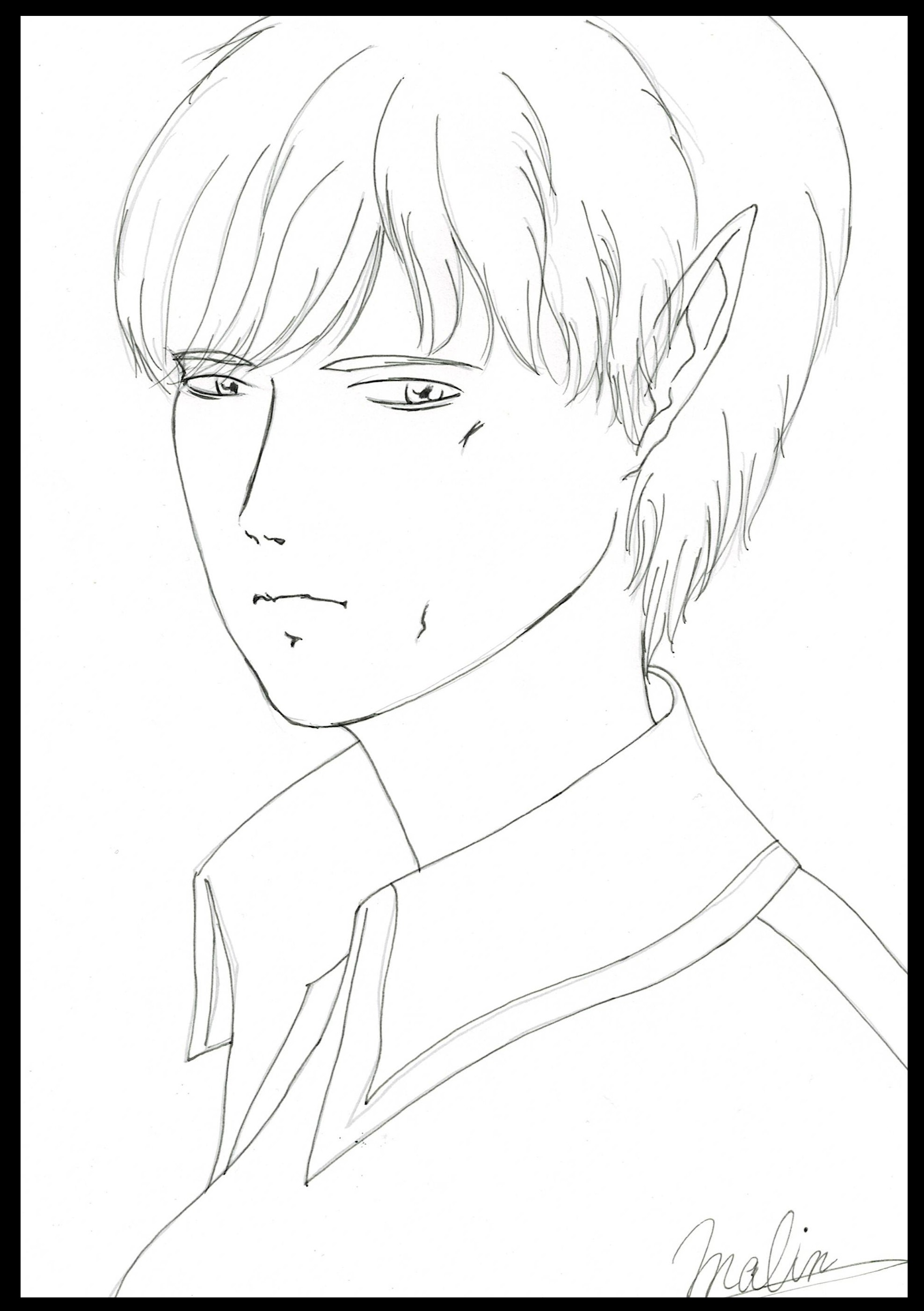
「それが尊厳のある死、か。」
ロミタスは、なぜか胸の中がすっきりした感覚を味わっていた。
マーリンの言葉は過激で胸に突き刺さる感じがしていたが、今はもうなくなっていた。
「私は、他人に迷惑をかけてまで生きたいとは思わない人に気付かせたい。自分の死に際を自分で決めること、自分らしく死ぬことは可能ではないですか、と。」
マーリンとロミタスは喉の渇きを潤すためエールを口に注いだ。
そしてお互いに豚肉のローストに手を伸ばした。
2人は黙って豚肉を味わった。
そしてロミタスは言った。
「ただ、そうは言っても自分でいつ死ぬか決めてくれと老人に言うのは難しくないか。」
「そうですね。だから初めは、老衰が原因であるのに無理やり延命させるための魔術の使用は止めて、体が自然に死の準備をするのを受け入れるようにして、あくまでも痛みや苦痛を取ることに魔術を使用する。そして、本人にも死を受け入れる心の整理をさせるようにしましょう。また、老人達に頭がおかしくなってしまった時に、生き永らえさせてほしいかどうか、聞いておくのが良いのではないでしょうか。」
「なるほど、だが死ぬときに苦しんで死ぬのでは、自ら死を選ぶのは難しいのではないか。」
「そこは魔術を使用して、まず眠らせて、次に痛みを感じさせないようにしたうえで、穏やかに生命力を奪って心肺停止させてしまうのが良いと思います。苦しまずに死ねるはずです。」
「ほう、いいねえそういうの。俺も頭がおかしくなった時は、そういうのがいいな。」
自分らしさを保ったままで、自分らしく、自分で死期を決める。
それは死というものに対して、前向きな考えだとロミタスは思った。
こうやって死というものについて、前向きに話せる機会というのは、これまでの人生の中ではなかったように思う。
親でも家族でも、こんな風に死について語る機会があっても良いかもしれんな。
ロミタスはそう思った。
「森を捨てたと言っていたが、それにしてはちょっと固執し過ぎじゃないか。」
マーリンはロミタスを見ると、ロミタスはニヤリと笑みを浮かべていた。
「それこそ森を捨てた私の勝手という奴ですよ。」
マーリンもニヤリと笑みを返した。
「他の森の話がいろいろ聞けてありがたかったよ。」
ロミタスはマーリンに右手を差し出した。
「それはこちらこそですよ。」
マーリンも右手を差し出すとお互いに手を握った。
この男、信頼してもよさそうだ。ロミタスはそう思った。
シェリルを独占したビリーは、得意の自慢話を始めた。
「シェリルさん。実は俺、ステインの夏の大市で、競技大会で優勝したことがあるんですよ。」
「へーっ、凄いじゃないか。どんな競技なんだ。」
ビリーが得意気に言うと、シェリルは瞳を大きくして笑顔を見せた。
ビリーは私を笑顔にしたいのだろう。
この目の前の青年は、周囲の人も幸せでないと自分も心から幸せを感じられない性分なのだろう。
だから自然に周りの人のために行動してしまう。
その性分は素敵で優しい。
この優しい青年のためならば、笑顔の1つや2つ提供するくらい安いものだ。
「それが凄いんですよ。パンの売り歩きなんですよ。」
「何だそれ!」
シェリルは両手の指を口元で合わせながら可笑しそうに笑った。
「びっくりでしょ。粉袋を運んだりとか、槍を投げたりとかそういうことじゃないんです。売り歩きですよ!聞いたことないでしょ。」
ビリーは両手を大袈裟に広げて見せながらそう言った。
「面白い。どうやって勝敗を決めるんだ。」
「それは当然売り上げですよ。」
ビリーは両腕を組んで見せた。
「順位は関係ないのか。」
「そうですね。関係ないですね。制限時間はありますけど。」
「なるほど。でも面白い競技だな。単純に力が強いとか速いとかではなくて、人としての総合的な力、人間力が問われる訳だ。」
シェリルが小さくうんうんと頷いた。
「へへへ。」
人間力なんて言われてビリーは嬉しそうな顔つきになった。
「どれくらい売ったんだ?」
「およそ300ムーナです。」
「300ムーナということは大体1,000個ぐらい売ったということか?凄いじゃないか。」
シェリルの顔が驚きでぱあっと明るくなった。
「1,000個って、この街の人口が3,000とか4,000とかだろう。ほとんどお前が売ったんじゃないか。」
「へへへ。」
シェリルの感心した様子にビリーは得意気だった。
「それに、普通に1人1人売り歩いていたのではその数は間に合わないだろう。制限時間もあるし。事前準備が大変だったんじゃないか。」
「そうなんですよ。シェリルさんなら分かってくれると思いました。」
「どんな工夫をしたのか教えてくれよ。」
そう言ってシェリルは少し目を細めてビリーを見つめた。するとビリーは少し照れてエールをグイっと喉に流し込んだ。
恐らく、私はビリーの好みの部類の女性に入るのだろう。シェリルはそう思った。
シェリルはもう少し幼い時代に、恋愛を経験したこともあった。
愛があれば何でも乗り越えられると思っていた時もあった。
愛というものが何なのかも分かっていなかったというのに。
だが今のシェリルは正直、恋愛に興味がなくなっていた。
ビリーに見透かされてしまうだろうか。
でもそれでも構わない。
嘘の自分を見せるよりは、ビリーに対して誠実であるはずだ。
「俺、ライダーなんでいろいろなところに顔を出すでしょう。普段から仲良くするようにしていたんで、競技に参加するって言ったら協力してくれることになって。」
ビリーは嬉しそうにそういった。
「なるほどな。」
ビリーの嬉しそうな顔に、シェリルも嬉しくなってしまった。
「特にいつも粉を運んでいるパン焼き職人の人達が、組合ごと俺に協力してくれることになって、一度に400個買ってくれることになったんです。」
優しいうえに、たくましい奴じゃないか。
若いのに生きていくセンスがある。
シェリルは自分より若い青年のたくましさに、心から嬉しさがこみあげて来た。
「凄いじゃないか。」
シェリルはビリーに向かって、心からの笑顔を向けた。
パン焼き職人組合と言えば、街で最大の規模であるのが普通だ。
パンの値段や品質は街に住む全ての人達に密接に関係するから、街を治める貴族とも直接的な繋がりのある組合であり、その組合を味方につけたという結果は、賞賛に値する。
ただ、ビリーの場合は打算的なものではなくて、普段から周囲の人々と仲良くしていて、困ったときは助けたり助け合ったりという関係から、地道に信頼関係を築いたものだろう。
そしてその人柄の良さが、この競技での協力を取り付けることに繋がったのだろう。
「ビリー、その結果は、お前が普段から積み重ねて来た、他人に対する思いやりを持った働きぶりの結果だよ。」
シェリルは一旦そこで言葉を切ると、改めてビリーを見つめて言った。
「お前の普段の働きぶりが想像できるよ。かっこいいじゃないか。」
シェリルはビリーに向かってまた笑顔を見せた。
ビリーはシェリルの笑顔に満足していた。
この話は自慢話で笑い話ではなかったのだが、シェリルの笑顔は本当の笑顔だと思えた。
心からのシェリルの笑顔が見たい。
そう思ったビリーだったが、図らずとも最初の自慢話で目標を達成することができた。
でも求めていたものと少し違う気がした。
「そんなに褒めてくれるのは、シェリルさんが初めてですよ。」
ビリーは照れながらそう言った。
シェリルとビリーはエールを少し口に注いだ。
「シェリルさん、もう一つあるんですよ。」
「まだあるのか?今度は何だ。」
シェリルは小さくクスっと笑った。
「俺の馬の話です。」
「馬って、ビリーが乗っていた馬のことか。」
「そうです。実はあの馬、俺が捕まえたんですよ。」
「捕まえるったって、どこかから逃げ出したのか?まさか野生馬な訳じゃないだろう。」
「1年前くらいですかね、ある日その馬がステインの街に現れたんですよ。でも馬の持ち主が分からなくて街で話題になっていたんですが、去勢もされていなくて、人見知りも酷くて暴れるので、街の役人は殺してしまおうかという話になっていたのですが、俺にはちょっと気になることがあって。」
シェリルがビリーを見ると、ビリーは目を伏せた。
「俺の街にシルバーグっていう結構な金持ちがいるんですが、その奥さんが若いのに旦那さんも息子さんも亡くされて一人で住んでいるんです。俺はたまたま配達先ということで仲が良くなって、たまに世間話をしていたりしたんですが、聞いたことがあったんです。息子さんが騎士見習いとして馬に乗って街を出て行ったという話を。」
「そうか。」
ビリーは伏せていた目を上げてシェリルを見た。
「その馬、たてがみと尻尾がクリームのように白かったので、その話をしたら、恐らくそうだろうと。気性が激しいことも息子さんが良く話していたそうですよ、気性の激しいこいつを乗りこなしてこそ一人前だと。馬の名前はシルブラウンなんですが。」
シェリルは顎に左手の親指と人差し指を添えると、合点がいったというように小さく頷いた。
「それでビリーに掴まえてくれって頼んだんだな。」
ビリーもシェリルの言葉に相槌を打った。
そして続けた。
「まず仲間達に協力をお願いして、それから親父さんに許可をもらって、街の役人に事情を話に行って。それから手分けして各組合やガヤンやらサリカ教会やら衛視やらを回ったんです。」
街で話題になっていた暴れ馬を掴まえる。
それは街の皆が興味の沸くことであったし、また、暴れ馬を掴まえる過程で、暴れた馬が街中を駆け回って迷惑をかけることも十分に考えられた。
そこで、事前に説明をして承知してもらうことは必要だったし、何かあったときに味方になってもらえることも期待してのことだった。
「サリカ教会にまで説明に行ったのはなぜだ。」
「サリカ教会には週末の礼拝にたくさん人が集まるじゃないですか、そこで、司祭様から一言伝えてもらえないかと思って。」
「なるほどな。説明したところで周りの反応はどうだった?協力的だったか。」
ビリーの顔色が明るくなった。
「シルバーグさんを心配している人が結構いて、みんな協力的で助かりました。」
それを聞いてシェリルも嬉しい気持ちになった。
シルバーグ夫人を個人的に心配している人もいたのだろうが、当然、ビリーの普段の優しさや人懐っこさ、意外と誠実なところが、ここでも役に立っていたのだろう。
「良かったな。お前のその行動力、尊敬するよ。それでどうやって掴まえたんだ。」
シェリルに尊敬すると言われて、ビリーは得意になった。
「乱暴なことをして脚を折ってしまったり傷つけてはいけない。仲間とも相談してとっておきの方法を思いついたんです。」
ビリーが得意気な様子でシェリルを見つめた。
「何だよ。もったいぶらないで教えろよ。」
「お友達作戦ですよ。」
「あ〜、そうか。なるほどね。」
シェリルはくるっとした瞳で笑顔を見せた。
「俺達はライダーなんで、自分の馬を持っているでしょう。餌の飼葉と自分の馬を引き連れて馬の所に行ったんです。そして馬の目の前に飼葉を置いて、自分の馬に食べさせた。そうしたらその馬も一緒に食べ始めたんですよ。」
シェリルは少し目を細めて、ビリーの話を聞いていた。
「あとは1週間かけて人間と馬との距離を縮めていったんですが、あの馬、俺の馬といい感じになってしまって、俺の馬は女の子なんですけど。」
「ははは。そうなんだ。」
「最後は俺達にくつわを付けさせてくれました。」
「やるじゃないか。結局、馬を街中で暴走させることなく掴まえることに、成功したという訳か。」
「へへっ。」
ビリーは得意気に鼻先を指で鳴らした。
「その後、その馬を連れてシルバーグ夫人の所に行ったんですが。」
「夫人はどうだった。」
ビリーはまた目を伏せた。
「泣いて喜んでいました。ありがとうって。」
「そうか。良くやったな。」
シェリルは目を伏せているビリーに向かってそう言った。
「今日俺が乗ってきた馬、それがシルブラウンで、シェリルさんが乗ってきた馬、それがシルブラウンの彼女、前は俺の馬だったプリモなんですよ。」
そういうとビリーは顔を上げると、笑顔でシェリルを見た。
「そうだったのか。どうりで私が何もしなくても、ビリーの後ろにちゃんとくっついて走る訳だ。」
シェリルもビリーにニコッとした。
「俺の恋はだめだったけど、馬同士は上手くいった・・・みたいな。」
ビリーは真顔になってシェリルにそう言った。
一瞬の間、シェリルとビリーの視線が交差した。
「馬だけに・・・。」
シェリルがぼそっとそう言った。
そしてシェリルとビリーは改めて顔を見合わせると、お互いにぷっと小さく吹き出した。
シェリルとビリーはお互いにエールを口に運んだ。
そして少し沈黙があった。
「でも、シルバーグ夫人はお前の気持ちに気付いたと思うよ。」
「そうですか。」
ビリーは疑っている風の視線をシェリルに送った。
「自分のためにそこまで手を尽くしてくれるんだから、好意を持っているんだろうということは察しがついているはずだ。」
「なるほど。」
「夫人の気持ちは正確に分からないが、ビリーに泣いてお礼を言った時に、お前から何かしらアプローチがあるかも知れないということは、考えていたんじゃないかと私は思う。」
するとそこへジェシーおばさんが3つ目の大皿を持って現れた。
ジェシーおばさんはテーブルの端に3つの大皿を置くと、ルーがビリーに大皿を手渡しした。
「ジェシーおばさん、これは何。」
ビリーがジェシーおばさんに尋ねた。
「豚肉のローストだよ。」
大皿の中には、大きめの塊に切られた豚肉に細かく砕いたパンをまぶし、塩と自家製のハーブを振りかけたものを串に刺して焼いたものが、串から外されて入っていた。
ビリーはルーから最初に受け取った1皿を隣のキッドの前に置き、次の皿をシェリルの前に置いた。
「美味しそう。シェリルさん食べましょう。」
ビリーとシェリルは大皿に手を伸ばした。
マリーウェザーは、魔法についてルーと話をしていたが、その話が一段落すると、ビリーとシェリルの話が気になってしようがなかった。
私だってシェリルと話がしたいのに。
しかもこのビリーという男、恋愛についてシェリルと話をしている。
私もシェリルと恋愛について話がしてみたいのに。
シェリルの恋人にでもなったつもりで、勘違いしているんじゃないだろうか。
私の方がずっとシェリルとの付き合いが長いのに、昨日今日出会ったような男が私とシェリルの間を邪魔するなんて、この状況は不公平だ。
この不公平さを正すのは私しかいない。
マリーウェザーは、自分とビリーの間に座っているルーの陰から、ビリーの様子を伺った。
ビリーは例の野性的な食べ方で、豚肉を満足そうに口に詰め込むと、シェリルに向かって美味しいことを表情で示しながら顎をゆっくりと動かしていた。
シェリルはビリーの大袈裟な表現に、小さく笑っていた。
二人の会話は途切れていた。
会話の主導権を奪う絶好の機会だ。
マリーウェザーは言った。
「さっきのシルバーグ夫人の話。私もシェリル姉さんと同じ考えだなぁ。」
するとシェリルがマリーウェザーに笑顔を向けた。
「マリーウェザーもそう思う?」
マリーウェザーは小さく頷くと続けた。
「まだビリーから声を掛けられるのを期待している、その可能性あるんじゃないのかなぁって。」
ビリーが慌てて肉を飲み込もうとして咳き込んだ。
「でも、さっきの話だと、夫人は亡くなった息子への未練がまだ大きく残っていると思ったのだけど。」
アレンティーも話に入ってきた。
「それはそれ、これはこれ。」
マリーウェザーがそう言うのを隣のルーは黙って見ていた。
ようやく肉を飲み込んだビリーが口を開いた。
「でも俺には言えなかったですよ。なんか、卑怯じゃないですか。弱みに付け込んでいるみたいで。」
ビリーが顔をしかめた。
「女心が分かってないなぁ。」
マリーウェザーがビリーを見下ろすような生意気な表情を見せた。
「夫人がビリーの告白を待っているという根拠はあるの?」
アレンティーはマリーウェザーに聞いた。
「女性の勘よ。」
マリーウェザーの生意気な表情を見て、シェリルは思わず吹き出してしまった。
マリーウェザーは可愛いな。そうシェリルは思った。
「マリーウェザーには悪いけど、そのような不確実な根拠では、信頼性を担保できない。」
アレンティーは眉をしかめた。
「あの・・・」
ようやくルーが声を出した。
周りがルーに注目する。
「好きとか嫌いとか理屈じゃないと思うんだよね、何となくというのかな。上手く言えないけど・・・感覚的なもの?」
それを聞いて周りの皆が頭を捻った。
少し沈黙があってビリーが言った。
「で、俺は聞いても言いわけ。というか聞いた方が言いわけ?」
ビリーが女性達に聞いた。
するとマリーウェザーがシェリルに向かって身を乗り出すと言った。
「シェリル姉さんはどう思います?」
すると、シェリルは前のめりになったマリーウェザーの頬に手の平で触れた。
だいぶふっくらとしたな。
シェリルはその柔らかい感触に安心感を覚えた。
シェリルはマリーウェザーにニコッとした。
初めてマリーウェザーの手首を握ったとき、シェリルは、その手首のあまりの細さに衝撃を受けた。
それはマーリン兄妹と初めて会って、間もないときのことだった。
そしてマリーウェザーは、自分が異常なまでに痩せ衰えてしまっていることに気付いていなかった。
異常なまでの細さと、そのことに全く気付かず、普通のことのように振る舞うマリーウェザーの違和感に、シェリルの心は大きな不安に包まれた。
幼い時に十分な栄養も摂れず、相当辛い経験を重ねて来たのだろうと、シェリルは胸が締め付けられる思いがした。
それでいて姉妹は、ほとんど笑うことがなかった。
話さない訳ではないのだが、嬉しかったり楽しかったりということを、顔の表情に表すことがほとんどなかった。
辛さをどうにか軽減しようと、辛いという感情を一旦忘れてしまう、自分から切り離してしまう技術を身に着けたのだろう。
なぜなら、辛い、嫌だという感情を表現したところで、その状況が改善される見込みなどないからだ。
周りが変えられないのなら、自分が変わればいい。
期待しても裏切られるのなら、初めから諦めてしまえばいい。
感情を忘れ、そのことについて考えることも止めてしまえば、自分は無敵だ。
どんな辛い環境でも生きていける。
だが、そうやって長い間自分の感情をないがしろにしてきたことで、今自分の感情がどのような状況であるのか、分からなくなってしまっていた。
しかし、マーリン兄妹は森を捨てた。
もう辛くて嫌な事ばかりの森の中ではないのだ。
姉妹は自分で自分の人生を決断し生き抜いていくためにも、これから自分の感情と向き合って行く。
シェリルが姉妹に会ったのは、まさにこれから時間をかけて、自分自身を取り戻していこうという矢先のことだった。
そんなとき姉妹は、悩みながらも、兄マーリンを合理的であるという理由で見殺しにしようとしてしまう。
恐らく、兄のマーリンが言って聞かせていたのだろう。
いざとなれば、自分達が助かるために兄は見捨てれば良いのだと。
しかし姉妹は本当にその選択をしようとした。
目の前にいる私に助けてとすがることもできなかった。
このままでは、この子達は取り返しのつかない罪を背負うことになる。
それがこの子達の人生に、一生黒い影を落とすことになろう。
シェリルはそう思った。
この姉妹にはまだ早すぎたのだ。
本当の自分の感情は今どのような状況であるのか。
兄の感情はどうなのか。
そして、本当に合理的な判断を下すには、その感情を抜きにして判断してはいけないのだということを。
そして後から事の重大さに気付いて、自分自身を呪うのだ。
なぜ私が生きているのかと。
だがシェリルは、この姉妹には希望もあると考えていた。
素直で純粋なのだ。
そして聞く耳を持っている。
時間をかければ必ず、自分で自分自身を救い出せるはずだ。
このまま悲惨な運命に落ちていくのを黙って見過ごすには、あまりにも惜しい。
確かにマーリンは命懸けで妹達を守るだろう。
だがマーリンに、妹達を感情豊かな女性として育てることを期待することは荷が重すぎた。
そもそもマーリンだって親の愛を知らないのだ。
だからシェリルは、マリーウェザーとアレンティーの母親役をすることに決めた。
シェリルはマリーウェザーの頬から手を離すと言った。
「私もマリーウェザーが言うように、それはそれ、これはこれだと思う。ただ、その夫人が用意している答えがビリーの意向に沿うものであるかどうか、私には判断できないな。」
シェリルは一旦そこで話を切った。
そしてマリーウェザーが自分の席に腰を下ろすと続けた。
「私も大した恋愛経験がある訳じゃないけど、私もマリーウェザーもアレンティーもルーも、同じ女性ではあるけれど、性が同一であるというだけで、考え方も好きなものも違う個別の存在だ、ということは同意してもらえるかな。」
シェリルはそういって周りを見渡すと、皆、それぞれ頷いた。
「恋愛も同じで、それぞれ求めるものが違って当然だと思うんだ。」
「そうか、なるほどね。」
マリーウェザーが言った。
「恋人に甘えたい人もいるだろうし、触れ合って安らぎを覚えたいという人もいるだろうし、楽しさを共有したいという人もいるだろうし、ただ単に異性がどういうものか知りたいからという人もいるだろう。じゃあ、夫人が何を求めていて、ビリーに対してどう考えているのか、それは夫人本人にしか分からないことじゃないか。」
シェリルのその言葉に、皆はそれぞれ自分は恋愛に何を求めているのかと考えて、その場は静かになった。
その様子を見てシェリルは目を細めた。
そして話を続けた。
「ただ、男と女の生き物としての性質は誰でも共通で持っているはずだ。それであれば皆で共感できるだろう?その話をしようじゃないか。」
シェリルの言葉に、皆良く分からない顔をした。
シェリルは人差し指を顎に当てると話し始めた。
「まずは男性について。男性は女性と比較して体格が大きく、力も強い。それは暴力に優れていることを意味している。それは、外敵から家族を守る。戦争から街を守る。逆に、食糧を奪うために街を襲うといった、人が生きるために必要な暴力を担うのに女性と比較して優れていると言える。」
「そういうことか。」
ビリーが合点がいった顔をした。
シェリルはその様子を見て話を続けた。
「もう一つの大きな違いは、男性は女性を妊娠させる。そして、その行為によって快感を覚える。また、おしっこみたいに定期的に排泄したい欲求がある。」
マリーウェザーもルーも興味津々な様子でシェリルの話を聞いていた。
「この2つの性質から、男とはどのような傾向を持っているでしょうか。」
シェリルはみんなに問いかけた。
「え〜っと・・・、暴れん坊でえっち?えっちな暴れん坊?」
マリーウェザーがそう言うと、シェリルもルーも思わず笑ってしまった。
「何か、可愛い言い方してるけど、馬鹿にされている気がするんだが。」
ビリーが顔をしかめながら笑った。
「暴力性と生殖性という2つの性質は、性質の強さ弱さはあるものの、男性が男性である以上は必ず持っている性質だ。例えば、暴力性が強くて生殖性も強い人の場合、マリーウェザーが言ったように、えっちな暴れん坊ということになる。」
シェリルが人差し指を立ててそう言った。
すると、アレンティーがシェリルの後に続いた。
「そういうことなら、組み合わせとしては、えっちな暴れん坊、ただの暴れん坊、ただのえっち、ただの大人しい人の4パターンということになるわね。」
アレンティーがそういうと、シェリル達はまた笑った。
「例えば・・・」
シェリルは隣に座っているエバを親指で示した。
「エバはただの暴れん坊。マーリンはただの大人しい人。ビリーは・・・ただのえっち。」
シェリルがそう言うと、女性達は本当に可笑しそうに笑った。
「俺はえっちだけじゃないですよ。アイもありますよ。愛も。」
ビリーは胸に手を当ててそう言った。
「じゃあ、ジェイは?」
ルーがビリーに言った。
「何?」
ビリーが分からない顔でルーに聞き返した。
「だからJ。」
「えっ、J?・・・エッチだけじゃなくて、アイもあるジェイ!」
ビリーが苦し紛れにそう言った。
ビリーのつまらない冗談に、また女性達は笑った。
一しきり笑いが収まると、シェリルまた話し始めた。
「だから、私達女性は男性の基本的な性質を理解して、例えば、安易に男性と2人きりの状況になることがないよう、注意しなければならない。」
シェリルを囲んだ女性達は、シェリルの話を聞いて皆頷いてた。
するとマリーウェザーは、頷いた後で少しの間黙って考えていると、不満そうな顔をしてシェリルに言った。
「でもそれって男性が悪いんじゃない。なんで女性が気を使わなきゃいけないの。不公平じゃない。」
「そうだね。」
シェリルはマリーウェザーに向かって微笑んだ。
「でもね、言って治せるのであれば、悪いと責めることもできるだろう。でも、男として持って生まれた性質が要因である以上、根本的に解決を図るには男性に男性であることを止めてもらうしかない。それは人が押し付けたものではなく、生まれ持ってのものだから不公平とは呼べないし、解決とはならない。じゃあ、根本的に解決ができないということは、どうすれば良いと思う?」
するとすぐにアレンティーが言った、。
「罰則を課せば良いのでは?女性に乱暴を働いたら、死刑とする。」
シェリルはアレンティーの言葉に頷いた。
「なるほどな。だが今でも罰則はあるし、それでもなお、なぜ男性は女性が嫌がっているのに乱暴を働くのか。それは自分が女性であったらという想像力が欠けていたり、男性として持っている2つの性質が強いことで正常な判断ができない状況になっていることが考えられる。そのような男性にとって、罰則は乱暴を思いとどまらせる抑止力にはならないだろう。」
「そんな男は俺が全て殺してやるさ。」
シェリルの隣に座っていたエバが突然そう言った。
「・・・」
あの時にエバと出会っていたら、海賊など投げ出して飛び出していたかもしれんな。
シェリルは黙ってエバを見つめた。

するとエバはシェリルに言った。
「シェリル・・・痴呆か?」
それを聞いてシェリルはエバの足をまた思いっきり踏みつけた。
「なんでここで痴呆とか、そういう言葉が出て来るんだよ。」
「いや、お前いつも忙しそうにしているから、若いのに老化が始まったんじゃないかって。」
エバは少し引きつった顔をしてそう言った。
「いらん心配だ。全く。」
シェリルはそう言うとマリーウェザー達に顔を向けた。
「これから話すのは、私が海賊の首領を務めていた時の話なんだが。」
シェリルは皆を見渡すと話し始めた。
「私は海賊の首領として、海賊達を纏め上げなくてはならかったが、そこでも男達の暴力性や生殖性の問題があった。街の人達に乱暴を働いたり、女性をレイプする事件が度々発生して、私の耳に入ってくる。私が首領になってから、同じ女性だからということもあって、その話は良く入ってくるようになった。だが、海賊がみんな乱暴を働くかというとそうではない、ただどうしても一定数そのような者が発生してしまう状況だった。」
シェリルは眉をひそめて困ったような顔をした。
「海賊をやるような男達は暴力性が強い者だらけだし、まともに教育を受けていないものだらけだから、厳しい罰則を設定しても、そもそも正常な判断ができないから効果は期待できなかったし、また、厳しく規則で押さえつけ、我慢に我慢を重ねさせたとしたら、不満や欲求が溜まりに溜まって、大爆発を起こすことも想定できた。」
女性達はシェリルの生々しい話にじっと聞き入っていた。
「そこで私は、売春婦の組合と相談して、売春婦のお姉さんに教育係をお願いすることにした。海賊達には定期的に売春婦のお姉さんの所に行ってもらって、サービスの最後に、無理やりえっちされるレイプという行為は、女性は嫌で悲しい気持ちになるのだと伝えてもらうことにした。」
シェリルは一息つくと、少しエールを口に含んだ。
「次にガヤンと相談して、体力が有り余っている乱暴者を街の衛視と一緒に、見回りに同行させることにした。そして、街中で暴力を働いている者を見つけたら、思う存分暴力を振るわせることで、海賊が暴れているのを海賊が取り締まるという仕組みを作った。そうやって、暴力性と生殖性の捌け口を作りながら、教育もさせつつ取り締まりをやらせて事件を減らすということをやった。」
シェリルの話に圧倒されて、誰も喋る者はいなかった。
「人には人という生き物として持っている性質、男として持っている性質、女として持っている性質があって、その性質がいかに愚かに見えることでも、まず、目の前の愚かな現実を認めなければならない。そして、その愚かさを前提としてどう対処するかを考えなければならない。人はもともと勘違いや、勝手な思い込みや、計算間違いをするし、嫉妬もするし嘘もつく。それを、人は正直で真面目で間違うこともなく、お互いに慈しみあい、助け合うものだと理想を前提に考えては、必ず無理が生じて破綻する。」
アレンティーはシェリルの言葉を正確に理解しようと頭の中で思い返していた。
私達は男性の性質を正しく理解したうえで、まずその性質がやむを得ない類のものだと認めなければならない。そして、その前提に立てば、正常に判断ができない恐れのある男性よりも、女性の方で対策を講じる。例えば、安易に男性と2人きりの状況になることがないよう注意を払う方が、自分の身を守る上では合理的で効果的ということか。
「なるほど。」
要するに、シェリルは、男性とお付き合いしたことのない私達に、男性と付き合う時には十分注意しなさいと教えたかったのだな。
アレンティーは小さく頷いた。
マリーウェザーはシェリルから海賊の頃の話や、男性についての話が聞けて満足だった。
これまでシェリルとは恋愛や男性について話をしたことはなかったから、これからはそのような話もし易くなったような気がする。
でも、シェリルは女性なのに男性の性質について詳しすぎるのではないか。
マリーウェザーはそこが無意識のうちに気になっていた。
どうやって男性のことを詳しく知ったのだろう。
マリーウェザーは疑問に思った。
そして、自分でもはっとすることに気付いた。
シェリル姉さんに男を教えた男がいた。
「シェリルさん、次は女性の性質の話をしようジェイ!」
ビリーがシェリルに向かってそう言った。
するとシェリルは、人差し指を顎に当てて少し考える素振りを見せると言った。
「女性の場合は、特にないけど。」
シェリルはぷいっとそっぽを向いた。
「いやいやいや、これだけ男のことを言いたい放題言っておいて、それはないでしょう。これから女性の話で盛り上がりましょう。」
するとシェリルはマリーウェザーに尋ねた。
「マリーウェザー、女性の性質って言われても特にないよね。」
するとマリーウェザーはシェリルの真似をして、人差し指を顎に当てて考える素振りを見せた。
「うーん、私も思いつかないな。女性は男性と違って特にないかも。」
マリーウェザーは顎に指を当てたままシェリルに向かってそう言った。
ビリーはこの状況にしてやられたという顔になった。
「アレンティーとルーはどう?」
シェリルは二人にも声を掛けた。
するとアレンティーとルーは顔を見合わせた。
そしてルーが人差し指を顎に向けて動かし始めると、アレンティーもはっとした様子で、人差し指を顎に当てた。
「私達もないかも。ねー。」
「ねー。」
ルーの相槌を追いかけるように、アレンティーも相槌を打った。
シェリルは二人の様子が可愛くて笑った。
その様子に、ビリーはしようがなくエバに顔を向けた。
「ちょっと、エバさん。何か言ってやってくださいよ。」
するとエバは肩をすくめると目を閉じて見せた。
「これがお前の知りたかった女性の性質ってやつさ。」
エバはビリーにそう言った。
ビリーは次にマーリンを見た。
「マーリンさん。」
するとマーリンは目だけをビリーに向けて、すねた様子で言った。
「俺はただの大人しい人だから。」
マーリンの言葉に女性達は思わず笑ってしまった。
ビリーはキッドにも顔を向けた。
キッドはまさか自分も巻き込まれるとは思ってもおらず、驚いた様子で左手の親指を自分に向け、2度ビリーの顔を見て確認した。
「えっと、」
キッドは何を言うべきか少し考えた。
「・・・弱肉強食?」
キッドがそう言うと、その言葉に皆が笑った。
「もう、ひどいですよシェリルさん。俺は凄く楽しみにしてたんですよ。それを皆で俺をいじめて、ひどいですよ。」
ビリーは大袈裟にすねて見せた。
「ごめんごめん。ちょっと意地悪が過ぎた。機嫌を直してくれよ。なっ。」
シェリルが胸元で両手を合わせてビリーにお願いすると、ビリーはしてやったりという顔をして言った。
「それじゃあ最後に、一つだけ教えてください。シェリルさん。」
それを聞いてシェリルは、これは最後にビリーにしてやられたのかなと思った。
「分かったよ、ビリー。ビリーは何が知りたいんだ。」
「シェリルさんは、今好きな人はいるんですか。」
するとその場は一気に静かになってしまった。
マリーウェザーはビリーの言葉に苛立ちを覚えた。
ビリーは何て無礼で、生意気な男なんだろうか。
シェリルが自分を好きになる可能性がほんの1%でもあると思っているのか。
自惚れるのもいい加減にしろ。
そんなことあり得ないことだし、私は絶対に認めない。
己の分というものをわきまえろ。
マリーウェザーは心の中でビリーを呪った。
そしてシェリルが何と言うのか、その言葉を待った。
当のシェリルは目を伏せると、そして言った。
「正直今は好きな人はいない。だけど好きになるつもりもない。」
シェリルの言葉を聞いて、マリーウェザーは心が躍った。
どうだ参ったか。
お前はシルバーグ夫人でも追っかけていればいいんだ。
「恋愛でひどい目にあったとか。」
ビリーが心配そうに言った。
「いや、違うんだ。何か、年老いた人のように思われるかもしれないけど、私は今持っている愛で十分満足してしまっていて。恋愛で心の隙間を埋め合わせたいという欲求が今はないんだ。」
ビリーはシェリルの言葉が理解できなかったが、もう一度確認するために尋ねた。
「もう持っているんですか。」
「ああ、私はもう持っている。それを失うのが恐ろしいくらいに。」
シェリルは穏やかな表情でビリーの顔を見た。
エバとマーリンは黙ってシェリルの言葉を聞いていた。
その場が静かになってしまった。
するとエバが思い出したようにシェリルに話し掛けた。
「売春婦で思い出した。実はシェリルに相談したいことがあったんだ。」
突然、場の空気とは全く関係のない展開に、皆言葉がなかった。
「相談って何を。」
シェリルがエバに聞いた。
「つまり、・・・売春婦のお姉さんに、」
「売春婦のお姉さんに?」
エバが言った言葉をシェリルが後から繰り返して言った。
「会いに行く。」
「会いに行く。」
「みたいな。」
「みたいな?」
二人は言い終わると一息の間お互いに顔を見合わせていた。
そしてシェリルは言った。
「会いに行くのは分かったけど。最後に言った、みたいな?が、分からなかった。」
「だろうな。」
エバは肩をすくめると目を閉じて見せた。
その様子を見たシェリルは小さく溜息をついた。
「分かった分かった。エバが分からないということが分かったから、何があったのか私に教えてくれないか。」
シェリルはテーブルに頬杖をつくと、今度は隣に座っているエバに向かって首を傾け、話を聞く準備をした。
エバは隣で頬杖をついているシェリルをちらっと見てから、視線を前に向けると話し始めた。
「この街に着いたとき、売春婦のお姉さんが男達に襲われていたんだが、そのお姉さんが凄くて、男のパンチを絡めとると、男を動けないように固定して顎を蹴り抜いた。」
「ほう。」
エバがシェリルの顔を見ると、シェリルはニヤリと口元に笑みを浮かべた。
シェリルの表情を見て、エバも思わずニヤリと笑みを浮かべた。
同じ武術家のシェリルなら、共感できるだろうとエバは思っていた。
「その後、残りの男達は俺が追い払ったんだが、そのお姉さんの格好がちょっとえっちだった。」
エバはそう言うと気が済んだようにエールを喉に流し込んだ。
すると不服そうにシェリルが言った。
「エバ。大事な事を言ってないだろうが。」
エバは少し考えるような素振りを見せたと思ったら、肩をすくめると目を閉じて見せた。
「あのなぁ、そのお姉さんに会いに来てくれって言われたんじゃないのか。」
シェリルの言葉を聞いたエバは、シェリルに向かってニヤリと笑みを見せると言った。
「全くだぜ。」
何を言っているんだか、こいつは。自分のことだろうが。
まあ、いつものことだが。
シェリルはエバのふざけた態度に思わず笑みを浮かべてしまった。
エバはいつもそうだ。
私を信頼しているからこそなんだろうが、問題が起こると自分のことでさえお構いなしに私に丸投げだ。
自分の人生なのに私に投げてしまって、どういう神経をしているんだろうか。
ただエバは、どんな状況になっても私の味方だ。
そこが可愛いから、許してしまうんだが。
シェリルはエバを見つめると言った。
「お前が言っていた、みたいな?が分かったよ。」

「えっ、今の会話で何か分かったんですか?」
横で聞いていたビリーが驚いた様子で言った。
「まあね。」
するとビリーだけでなく、マリーウェザーもルーもシェリルに注目していた。
シェリルは皆に分かるように説明を始めた。
「売春業というのは、個人で営業しているものもあるが、ある程度大きな街になるとアルリアナ信者によって運営されていることが多い。だからアルリアナ信者というと売春婦を想像してしまうだろうが、実はアルリアナ信者には踊り子もいて、大きな街では踊り子を派遣したり、劇場で披露していたりということをやっているんだ。」
「そうなんですか。でも、ステインの街でも、シャロムの街でも、踊り子は見かけないけど。」
ルーがシェリルの話を聞いて小首を傾げた。
ルーの様子にシェリルが人差し指を左右に振った。
「踊り子なんて商売は、金がたくさん集まる大きな街でないと成り立たない。この辺りの規模の街では無理だよ。」
「そっか。」
ルーが小さく頷いた。
「俺の生まれた国のファイニアには大きな劇場があって、アルリアナの踊り子も街でたくさん見かけた。」
エバがルーに話し掛けた。
「そうなんだ、見てみたいな。どんな踊りなの。」
ルーがエバに聞いた。
「アルリアナの踊りは迫力が凄い。舞台に出て来る踊り子の多さにも驚かされるが、舞台を目いっぱいに使って宙を舞うように跳躍する姿は圧巻だ。それにたくさんの踊り子達が打ち鳴らすタナクと呼ばれる楽器の音の迫力も凄い。何と表現すればいいのか分からないが。実際に見た方が早いだろう。」
エバがルーに笑顔を見せた。
「そうなんだ。見てみたいな。本当に。」
ルーは踊りの様子を想像して楽しい気持ちになった。
「ルー。私が持っているアーモンドの形をした小さな盾。これがタナクだよ。」
マリーウェザーが腰に提げているタナクを外すとルーに見せた。
「えー、そうだったんだ。魔法を掛ける時に使うやつでしょう。」
ルーが驚きと感動が混じった笑顔でマリーウェザーを見た。
マリーウェザーはルーにタナクを手渡した。
ルーは嬉しそうにタナクを手に取って、その感触を確かめた。
シェリルはその様子に微笑むと話しを続けた。
「実は、その踊りを基にした武術がアルリアナにはあるんだ。ダルケスというんだが、聞いたことはあるかな。」
シェリルは皆に聞いた。
「それなら知っている。以前ダルケスを見せてもらったことがあって、蹴り技が凄いんだ。」
キッドが得意そうに言った。
「そうか。どんな技だった?」
シェリルがキッドに聞いた。
「人の頭の上に乗せたリンゴを、跳び上がって蹴り落としたのが凄かったです。」
キッドがそう言うと、ビリーも思い出したように言った。
「そういえば俺も見たな。あれは確かに凄かった。掛け声が凄いんだ、アチャー!って。」
「そうだ。アチャー!が凄かった。」
キッドとビリーは顔を見合わせた。
「アチャー!」
「熱チャー!」
キッドがアチャーと繰り返し言うと、ビリーは熱い物でも触れたかのような素振りをしてそう言った。
ビリーのつまらない冗談に皆が笑った。
シェリルもビリーの冗談に小さく笑うと話を続けた。
「キッドの言ったとおり、ダルケスは跳躍からの華麗な足技が特徴的な武術で、派手で華やかだ。しかしお前達が見たのは実はダルケスの表向きの姿で、真のダルケスはエバが助けた娼婦が見せた姿なんだ。」
シェリルはキッドとビリーに向かって偉そうに装うとニヤリとした。
「そうなんですか。」
キッドが興味のある顔をしてシェリルに尋ねた。
「武術には、あまりに危険過ぎたり、手の内を隠しておく必要から、同じ技でも表と裏の2つの技の使い方が存在する。そして裏の使い方は、他人に見せてはいけないし、基本をしっかりと身に付け、実力のある者にしか教えられない。つまり、一つの技に使い方が2つあって、他人に見せても構わない表の使い方を陽法、真の使い方を陰法と呼ぶ。そして、ダルケスの陰法でよく見られるのが、相手を掴んで動けないように固定してから蹴りを入れるということなんだ。」
キッドは興味のある顔で黙ってシェリルの話を聞いていた。
するとエバもキッドに向かって言った。
「想像してもらえば分かると思うが、逃げる相手に蹴りを入れても衝撃は大して伝わらない。だが、壁に貼り付けにした相手の腹に蹴りをめり込ませれば内臓は破裂する。」
エバの補足説明が残酷過ぎて、キッドは何と言って良いのか分からなかった。
そんなキッドにエバは続けた。
「俺が助けたお姉さんも、敵のパンチを絡め取って相手を固定して蹴っている。これは陽法ではない、陰法。殺人技だ。ただ彼女は手加減をして相手を殺さなかった。俺の経験から言わせてもらえば、本来のあの技には続きがあって、相手の顎を蹴って脳震盪を起こさせた後、そのまま相手の頭を壁や地面に叩きつけて破壊するか、相手を地面に倒してから喉を踏み潰して破壊するかというところだと思う。」
エバの説明の恐ろしさに皆言葉がなかった。
ただシェリルだけは平気な顔をしていた。そしてエバに向かって言った。
「とは言っても、ダルケスで本当に恐ろしいのは九節鞭だろう。あれは短時間で容易に大量の人間を殺害する。」
「まあな。九節鞭の威力に比べたら、蹴りなんて情けの塊みたいなもんだ。」
はははは、と二人は笑った。
その様子に周りの皆は付いて行けなかった。
「ごめんごめん、話が逸れてしまったな。つまり、彼女はダルケスの陰法を伝授された相当な実力者で、少なくとも神官位を持っているはずだ。神官位はアルリアナ組織の中では中級管理職に当たるから、その彼女がえっちな服を着て営業をしているのは不自然だ。」
「全くだ。」
エバがシェリルの言葉に頷いた。
そんなエバの様子にシェリルは思わずフっと小さく笑うと話を続けた。
「他の可能性として、彼女が踊り子だという場合もあるが、踊り子ならもっと大きな街にいた方が仕事にありつけるだろう。どちらにしてもこの街の娼館で営業をしているのは不自然だ。エバが無意識に彼女に覚えた違和感。それが、みたいな?の正体だ。」
「さすがシェリルさん。」
ビリーは、シャロムの街に向かう途中で野盗を見事に出し抜いたシェリルを思い出していた。やはりシェリルには勝てそうにないなとビリーは思った。
ビリーの言葉に続いて、周りの皆も感心したように頷いた。
シェリルは改めてエバに顔を向けた。
「つまり、何か理由があって、やむを得ず彼女はここにいる。そういうことになるな。」
「そうか。」
シェリルの言葉を聞いてエバは少し考えこんだ。
シェリルは問題を惹きつける。
これまでも一緒に旅をしてきて、問題が起こると大抵シェリルが関わっている。
シェリルはやっかいな問題さえも惹きつけてしまう女なのだ。
そしてシェリルがこの街について、既にヤドゥイカ子爵やロミタスやエルファの軍隊といった問題が次々とシェリルの目の前に姿を現しているのだ。
そのシェリルが、娼婦のお姉さんには何か理由があると言っている。
するとエバは突然立ち上がった。
「ちょっと行ってくる。」
エバはそういうと出口に向かって歩き始めた。
「行ってらっしゃい。」
シェリルはエバに向かってそう言うと、エバは振り返り、シェリルに向かって手を振ると宿屋を出て行った。
エバが出て行った後、その場は静かになった。
するとそこへジェシーおばさんが4つ目の大皿を持って現れた。
ジェシーおばさんはテーブルの端に3つの大皿を置くと、ルーがビリーに大皿を手渡しした。
「ジェシーおばさん、これは何。」
ビリーがジェシーおばさんに尋ねた。
「野うさぎのスープだよ。」
大皿の中には、適当な大きさの塊に切られた野うさぎの肉を、細かくすり潰した玉ねぎ、人参などの根菜類を加え、煮込んだ後、ブイヨンとワインを加え、パン粉でとろみを出した後、香辛料で味を整えたものが入っていた。
ビリーはルーから最初に受け取った1皿を隣のキッドの前に置き、次の皿をシェリルの前に置いた。
「美味しそう。シェリルさん食べましょう。」
皆大皿に手を伸ばすと野うさぎのスープをそれぞれのスープ皿に注ぎ、スプーンで頬張った。
「行っちゃったね。」
ルーが野うさぎの肉を飲み込むと、とりあえずそう言った。
「エバはいつもあんな感じだ。引き留めるつもりもないしな。」
シェリルはそう言うと、スープをスプーンですくって口に運んだ。
「でも問題が起こると大抵エバさんが関わっていることが多いわね。」
アレンティーが誰に言うでもなくぼそっとそう言った。
それを聞いたシェリルが額に人差し指の指先をトントンと当てて目を伏せた。
それは分かっている。
エバは問題を引き当てる。
これまでも一緒に旅をしてきて、問題が起こると大抵エバが関わっている。
エバは、いわゆる引きの強い男なのだ。
「エバさんが助けたお姉さんだけど、最近この街に来たんじゃないかと思うんだよな。」
キッドもまた、独り言のように言った。
「どんな子なんだ。」
ビリーがキッドに尋ねた。
「銀髪で、短めの髪型で、瞳が大きくて可愛い感じ。」
「確かにそんな子、見たことないような気がするな。」
ビリーとキッドの様子を見て、ルーが目を細くすると、横目で2人を見て言った。
「さすが2人とも、よく知ってるのね。」
するとキッドとビリーはしまったという顔をした。
「いや、大体分かるじゃないか。狭い街なんだから。」
「それに俺達がそんな遊び金を持っていないことは、ルーだって分かるだろう。」
2人は身を守るために見事な連携を見せた。
「ふふ、分かったわ。」
ルーは2人の必死な姿を見て気が済んだので、許してあげた。
シェリルは、そんなキッド達の様子を眺めながら、エバがこれまで引き当てた様々な問題を思い出していた。
「シェリル姉さん。」
マリーウェザーがシェリルを見て小さく頷いた。
そしてシェリルはマーリンに向かって言った。
「マーリン。悪いけど、頼む。」
「そうだよな。」
マーリンはそう言うと、コートの内ポケットから黒い玉を取り出した。
「アレンティー、この黒い玉をそこの窓から外に出してくれませんか。」
「分かりました。お兄様。」
マーリンはアレンティーに黒い玉を手渡した。
「やっぱり心配だものね。」
マリーウェザーがシェリルとマーリンに微笑んだ。
「確かに心配だよな。」
シェリルがマーリンに尋ねた。
するとシェリルとマーリンは声を揃えると言った。
「エバに殺される人達がな。」
これがいつものお決まりの冗談なんだな。
ビリーは、息をぴったりと合せた二人の笑えない冗談に、引きつった笑顔を見せた。
「さて、そろそろロミタスから話を聞かせて貰おうか。」
次にシェリルはロミタスに顔を向けた。
ロミタスはシェリルの言葉が分からず、分からない顔をした。
「アレンティー悪いけど通訳をお願いしたいんだが。」
「分かりました。」
アレンティーは席を立つと、エバが居なくなって空いたシェリルの隣の席に腰を下ろした。
シェリルはアレンティーの肩に軽く触れるとニコッとした。
アレンティーもニコッとした。
そしてシェリルはロミタスを見た。
「まず私の意志を伝えておきたい。私はお前の娘を助けつつ、この街を守りたい。」
シェリルの言葉をアレンティーがロミタスに伝えた。
「俺は娘が助けられるなら可能な限り協力しよう。」
ロミタスは向かいに座っているマーリンを見ると、マーリンは、ロミタスの方を見ながら頷いたが、どこかあらぬ方向も見ているような様子で、たまにぼそぼそと独り言をつぶやいていた。
「娘がどこに囚われているか分かるか。」
シェリルはロミタスに尋ねた。
「それは分からないが、もともと俺は部下を2人連れて、3人で娘のエイリスに会うためヤドゥイカ子爵の屋敷に来ていた。そこで、子爵からプファイトの実で商売することを持ち掛けられた。プファイトの実を使って戦争に使う武器を作るのだと言っていた。」
ロミタスの言葉にシェリルは少し驚いた顔をした。
「ちょっと待って、娘さんはもともと人質に取られていたのか。」
「そうだ。ちょうど50年前、娘はエルファが人間に対して不可侵であることの証として子爵に差し出したのだ。」
「そうか、人質か。娘さんが不憫だな。娘さんは元気だったか。」
シェリルも眉をひそめた顔をしてそう言った。
「俺が商売を断ったせいで、娘には合わせて貰えなかった。」
ロミタスは視線を下に降ろした。
「子爵はお前を拘束して何に利用するつもりだったのだろう。」
「だた単に、俺では話にならないと思ったのだろう。」
シェリルは目を伏せているロミタスを見ていた。
「お前の替わりに話ができる奴がいるのか。」
「いるとは思うが結論は変わらないだろう。しかし、奴はそうは考えなかった。森の最高権力者である長老達に話をして、俺の替わりに話のできる者を寄こせと、俺の部下に言った。俺と俺の娘は交渉を有利に進めるための人質と考えたようだ。」
ロミタスは顔を歪めた。
娘が人質に取られているため抵抗もできず、交渉の材料として捕らわれてしまったこと、そのことで部族に迷惑を掛けてしまったこと、娘を助け出せなかったこと、それらの己の情けなさをロミタスは思い出したのだろう。
「話のできる替わりの者ではなく、エルファの軍隊が来たということは、人質は見捨てるという判断を長老達がしたということだな。」
「そういうことだ。それに、そうしてくれた方が心が軽くなる。」
「なるほどな。」
するとシェリルは、人差し指を顎に当てて考える素振りを見せた。
「ちょっといいですか。」
キッドがロミタスに向かって手を挙げた。
「ヤドゥイカ子爵の屋敷というのは、街の北側にある丘の上に建っている屋敷のことですか。」
「ああ、恐らくそうだと思う。」
キッドとロミタスの話を聞いて、シェリルは小首を傾げた。
「それは変だな。」
「何が変なんです。」
シェリルはキッドとロミタスを順番に見た。
「ふつう領主の屋敷なり城なりは、街の中にあるものだ。この街を守っている壁がいかに貧弱であったとしても、わざわざ攻めてくださいと街の外に屋敷を造って、そこに住む領主はいないだろう。見晴らしの良い丘の上に建っていることから考えると、元々は砦として使っていたところを屋敷にしたんじゃないか。つまり、エイリスは街にある子爵の本拠地である城なり屋敷なりに囚われていると考えた方が筋が通る。」
それを聞いたビリーがすぐに言った。。
「確かにシャロムの街の北西に領主の城がありますよ。」
ビリーの言葉にシェリルが小さく頷いた。
「エイリスが囚われているのは恐らくそこだな。」
すると、黙っていたルーが皆に向かって口を開いた。
「ねえねえ、話が戻ってしまうんだけど、エイリスさんが人間に対して不可侵であることの証というのはどういうことなの。」
するとルーの疑問にキッドが答えを説明した。
「それは俺も聞いたことがある、何でもこの街は過去に2度戦争を経験したたことがあったらしい。その時に、当時のこの街の領主は、街を守るために抵抗せずに敵の軍隊を通してやったと聞いたことがある。」
するとキッドの説明を聞いてロミタスが付け加えた。
「そうだ、今から18年前、南の青の帝国が神聖王国へ進撃したとき。それから、今から50年前、青の帝国よりも古いザノン王国が神聖王国へ進撃したときのことだ。私の娘のエイリスは、その2度の進撃の際に、人間に対して不可侵であることの証としての役目を果たしたのだ。」
ルーは2人の説明を聞いて少し考えてから、すまなさそうな顔をして言った。
「それは分かったけど、それは人間同士の戦争でしょう。なぜエルファが巻き込まれなければいけなかったの。」
ルーの言葉を聞いて、シェリルは目を細めると言った。
「この街とエルファの森は歩いて4、5日の距離しかない。敵の気持ちになってみると、この街を通って神聖王国へ進撃したとき、後方からエルファの軍隊に攻められたら厄介だと思わないか。」
「あっ、そうか。」
ルーの顔が分かった顔に変わった。
「おそらく子爵は、ただ通してやるだけではなく、エルファが不可侵であるという大きな手土産を用意しておくことで、敵の軍隊が要求する食糧やら戦費やら野蛮な行為から自分と街をいくらかでも守っていたのだろう。それにエルファとしても、人間達の争いに巻き込まれたくはないはずだ。エイリスは、エルファが人間に対して不可侵であることの証明であり、子爵が敵の軍隊との交渉を有利に進めるための材料でもあっただろう。そうして安心して神聖王国の厳しい冬山の懐深くに進撃した敵の軍隊は、極寒での戦いに慣れたスパイクスと呼ばれる神聖王国の勇猛な戦士達に、さんざんな敗北を喫することになった訳だ。」
「そうか、良く分かった。」
ルーは合点が言ったように頷いた。
「ただ、どうも引っ掛かるところがあるんだよな。」
シェリルがテーブルに肘をつくと、軽く握った左手を頬に当てそう言った。
「どうしたんですか。」
ビリーがシェリルに声を掛けた。
「おかしいと思わないか?ヤドゥイカ子爵はなぜエルファとの関係が悪くなる恐れがあることを進めようとする。しかもなぜ今なんだ。エルファが人間達の争いに巻き込まれることを嫌っていることは、昔から分かっているだろう。」
「シェリルさん。」
ビリーがここぞとばかりに得意気な顔をして声を掛けた。
「何?」
「今の子爵ですが、3年前に前代が亡くなって、その跡を弟が継いだらしいですよ。」
シェリルは少し驚いた顔でビリーを見て、その後にロミタスを見た。
「確かにそうだ。3年前に今の子爵に交替した。何でも、子爵を継ぐ前は、神聖王国の首都で高位な役人をしていたと言っていた。」
ロミタスは少しバツが悪そうにそう言った。
そういうことはちゃんと話しなさいよ。
シェリルは心の中でそう思った。
「なるほどな。人が替わったから方針転換があったんだ。ロミタス、子爵はこのプファイトの実の商売は何のために始めると言っていたんだ。」
シェリルは、ロミタスから細かく話を聞き出した方が良さそうだと思った。
「何のためか・・・奴は、金が必要だと言っていた。」
「ロミタスがだめだと言ったら、何と言っていた。」
「何でお前らのために上に面倒な説明をしなくちゃならないんだと言っていた。」
「上って何だ。子爵の上って。男爵か?」
ロミタスの言った言葉を聞いて、ビリーがキッドに分からない顔で尋ねた。
「それ下がってますから。男爵は子爵の下ですから。」
ロミタスの通訳をしていたアレンティーが突然突っ込みを入れた。
「うわ、びっくりした。そっちから来るとは予想外だったぜ。」
ビリーは大袈裟に驚いて見せた。
ロミタスは話を続けた。
「上が誰なのかは俺にも分からない。その後奴は、逆にどうしたら商売できるのかと聞いてきた。」
「ロミタスは何と言ったんだ。」
「俺は武器に使うのならだめだと言った。すると奴は、プファイトの実は武器には使わないと言い出し始めた。」
「何だそれ。」
キッドは呆れたように肩をすくめた。
「俺は、さっき武器に使うと言っていたのは何だと聞いたら、聞かなかったことにすればいいだろうと言った。」
「ふざけた野郎だな。」
ビリーが左手の拳を右手で撫でつけながら顔をしかめた。
ロミタスの顔の血流が多くなって赤みが増していた。
「なんか、子爵とか領主らしくないよね。なんでそんな他人の事のように言えるの?」
ルーも嫌な顔をした。
そんなビリーとルーの様子を見てから、シェリルはロミタスに尋ねた。
「なぜ商売を始めるのが今なのか、何か言っていなかったか。」
「それは聞いていないが、時間がない、至急だと言っていた。」
「それで結局、ロミタス以外の誰かを呼んで来いということになったんだな。」
「そうだ。こっちには人質がいる、立場が分かっているのかと。お前では話が進まない。話の出来る奴を連れてこい。でないと人質がどんどん増えることになるぞと。それから、早く首都に帰りたいと言っていた。」
「ふざけるなよ!むかつくぜ!」
「同じ人間だとは思えないぜ。」
キッドとビリーが悔しそうにそう言った。
自分とは考え方や価値観があまりにも違う。
なぜエルファが出来ないと言っているのに、無理やり自分の思い通りに従わせようとしているのだろうか。
そんなにお前は偉いというのか。
絶対に分かり合えない、自分達とは違う存在。
2人にはそう思えた。
シェリルはキッドとビリーの悔しそうな様子を見ていた。
「そうだな。・・・だが、同じ人間だ。ロミタス、お前良く我慢したな。」
「さすがに娘を人質に取られているからな。」
ロミタスは苦笑して見せた。
シェリルはロミタスが以外に我慢強いのに感心した。
そして、キッドやビリー達を見回すと言った。
「今の話で、子爵を支配している“上”という何者かがいるということが分かったな。つまり、子爵は使われている小者だ。プファイトの実の商売を成立させることで金が手に入るめどがあり、上からいついつまでに話をつけろと期限を切られているんだろう。そして、今まさに期限を迎えようとしていて、慌てて成立させようと躍起になっている。商売が成立すれば、上に面倒な説明をしなくても良くなる、そうしてそのうち、自分はお役御免となって子爵を辞めて首都に帰るという訳だ。」
皆はシェリルの説明を黙って聞いていた。
その様子を見てシェリルは話し始めた。
「子爵は海賊と違って十分に教育を受けているだろうし、教養もあるはずだ。なのに、我々でも愚かだと思う行動を取ってしまうのは何故だろうか。」
シェリルのその言葉に皆は頭を捻った。
すると、アレンティーが言った。
「子爵はあえて考えないようにしているだけなのでは。」
シェリルはアレンティーに微笑んだ。
「アレンティー、私もそう思う。」
シェリルはそう言うと、皆に話を続けた。
「さっきも言ったとおり子爵は、いついつまでに商売を成立させろということは命令されているが、エルファと関係を悪化させるなということは命令されていないのだと思う。だから、命令されていることを優先させて、命令されていないことはあえて考えない。そうしておけば、上から聞かれても、私は命令通りにやっただけですと言い訳ができるからな。」
「それは、この街がエルファの軍隊に襲われるかもしれないとしても、ですか。」
マリーウェザーがシェリルに聞いた。
「そうだとしてもだ。おそらく子爵は平然と開き直るだろう。私は命令に従っただけで悪くないとね。」
「何て恐ろしいんだろう。」
マリーウェザーが目を細めた。
「恐ろしいことは他にもある。こういう性質を持った人というのは、問題が起こっても面倒なことは上に説明しない。自分の持っている権限を利用して、自分よりも弱い奴らを叩くことで辻褄を合わせようとする。子爵が面倒な説明を上にしなくても済むように、エルファを叩いて辻褄を合わせようとしているように。こういう人達が街の運営に携わったらどうなるか。」
「どうなるんですか。」
キッドがシェリルに尋ねた。
「問題が解決されずに放置されるようになる。例えば、上の者が子爵に対して、昨年よりも街で使うお金を減らせと命令したとする。その後、古くなって危険な橋が見つかり、街を管理している役人が橋の再建が必要だと子爵に言って来たとする。その時に子爵はどうすると思う?」
「まさか、そのまま放置しておくとかないよね。」
マリーウェザーが恐る恐る言った。
「いや、正解だ。そのまま放置しておくだろう。なぜなら、子爵からすれば、命令されているのは金を減らすことであって、橋が崩壊して怪我人が出ることを事前に防ぐことではない。それに、橋を再建するには橋の実際の状況を確認することも必要だし、大きなお金が必要となるから、そのお金をどう工面するのか、できるだけ安く再建するためにどのような工夫をするのか、考えなければならないことが山ほどあるし、上に対して街で使うお金を減らせないという面倒な説明をする必要もある。しかし、この問題を放置しておくことにしてしまえば、お金を減らす目標を達成できるだけでなく、面倒なことは全てなくなる。街を管理している役人には金が無いから無理だとでも言っておけばよいだろう。実際に金を握っているのは子爵だから、ばれることもないし、もし、橋が壊れて怪我人が出たとしても、街の役人は金を握っている子爵に対して強く抗議はできないよ。結局犠牲になるのは怪我をした街の住人であり、上の者もその事実を知ることはない。もし上にばれたとしても、私は命令通りにやっただけですと言い逃れをすれば良い。」
シェリルの言葉にみな唖然としてしまった。
そんな人がいるのだろうか。
ルーはにわかに信じられない気持ちになっていた。
だが実在するからこそシェリルは言っているのだろう。
「ルーの周りにも必ずあるはずだよ。まだルーが見えていないだけで、ルーの知らないところで金と人が蠢いている。」
ルーはシェリルに言われた言葉を思い出していた。
とは言っても、本当だとすれば何と人とは情けない存在なんだろうか。
自分が楽をしたいから、本当は考えなければならないことを放棄してしまうなんて。
でも人にはやってはいけないことを見分けるための良心というものもあるはずだ。
「シェリルさん。良心が歯止めになって、子爵が思い直すという可能性はないの。」
ルーはシェリルに尋ねた。
そんなルーを見て、シェリルは穏やかに見つめた。
「良心に期待することだってできるさ。ただ、あえて考えないようにしてしまうという問題の根本は何かというと、楽がしたいという人としての性質だ。これは人として生まれ持ってのものだから根本的に解決ができない類の問題であり、実は我々だってその性質を持っている。さっき話していた男性の性質を考えた時と同じように、楽がしたいという怠慢性と良心という2つの性質があるとして、子爵の場合にはただの怠慢な人ということになるかな。だから私は、子爵が存在すること自体が悪だとは思っていないよ。私と同じ人間だ。」
一旦そこで話を切ると、シェリルは視線を鋭くさせた。
「ただし、子爵の怠慢が要因となって引き起こした問題については、子爵に責任を取って貰おうと私は思っている。」
シェリルの言葉を皆黙って聞いていた。
すると、マリーウェザーがシェリルに言った。
「子爵は上の命令に従っただけだと言い訳をするのではないかしら。」
シェリルはマリーウェザーを見ると目を細めた。
「そうだね。ただ、私は命令に従っただけだから責任は無いとは考えていないんだ。例えば、子爵が上の命令に従って、マリーウェザーのお兄さんのマーリンを殺したとする。そうして子爵が、私は命令されただけだから悪くないのでと言ってきたら、マリーウェザーはどう思う?」
「許せない。・・・エバにお願いして殺して貰う。」
マリーウェザーは珍しくキッとした視線でシェリルを見た。
マリーウェザーの表情を見てシェリルは微笑んだ。
「それが普通だ。人には感情があるんだ。子爵の言い訳などマリーウェザーの感情を押し止めておくことに1ミリの効果もありはしない。実際に手を下せば、その事実からは逃れることはできないし、マリーウェザーの強烈な感情からも逃れることはできないんだ。」
シェリルはマリーウェザーから周りの皆に視線を移した。
「命令しているのも自分と同じ人間だ。勘違いや思い込みをしていることも考えられるだろうし、命令に従わないという選択肢もあったはずだ。考えることをしようと思えば出来た筈なのに、あえて自分の意志でそれをしなかった。それは子爵の勝手な我儘だ。その我儘を我々に押し付けるというのであれば、我々だって自分の勝手な感情を正面からぶつけることは、至って公平だと私は思う。」
シェリルの言葉を皆は黙って聞いていた。
するとそこへジェシーおばさんが最後の大皿を持って現れた。
ジェシーおばさんはテーブルの端に3つの大皿を置くと、ルーがビリーに大皿を手渡しした。
「ジェシーおばさん、これは何。」
ビリーがジェシーおばさんに尋ねた。
「デザートの焼き菓子だよ。」
大皿の中には、小麦粉にミルクとブドウ汁を加えて練ったものに、干したブドウを加えて焼いた、四角形の焼き菓子が何枚も載っていた。
ビリーはルーから最初に受け取った1皿を隣のキッドの前に置き、次の皿をシェリルの前に置いた。
「美味しそう。シェリルさん食べましょう。」
皆大皿に手を伸ばすと焼き菓子を頬張った。
ロミタスは焼き菓子を頬張りながらマーリンが言っていた言葉を思い出していた。
「シェリルは合理的で正しい判断をします。また人間社会に詳しく鼻も利きます。エルファの私が言うんです。信じてみませんか。」
確かにそのようだ。
シェリルという女、信頼してもよさそうだ。
ロミタスはシェリルを見た。
するとシェリルは、両手で持った焼き菓子を頬張ってもぐもぐしていたところだった。
さっきまで威勢よく大口を叩いていた様子と、目の前でもぐもぐしている様子のギャップに、ロミタスは思わず苦笑してしまった。
シェリルは焼き菓子を飲み込むと言った。
「ごめんごめん。ちょっと静かになってしまったな。エイリスを確保してしまえば、問題の半分は解決するんだ。さっさと確保してしまうつもりだから安心しろ。」
シェリルはロミタスに笑顔を見せた。
「おーい。」
娼婦のお姉さんのところへ出掛けたエバを見守って、黙っていたマーリンがいきなり皆に声を掛けた。
皆がマーリンに注目する。
「エバの目の前にエルファの女性がいるんだが。」
「何だって!」
キッドとビリーは驚きの声を上げた。
そんな都合の良いことがあるのだろうか。
しかしマーリンは至って冷静だった。というより少し呆れているようにも見えた。
すると突然シェリルが立ち上がった。
「みんな行くぞ!エバのところに!」
「えっ、今から行くんですか?」
ビリーが驚いた顔でシェリルに尋ねた。
するとシェリルはビリーに笑顔を向けた。
「運命が動き始めている。そういう時は、乗り遅れちゃいけないんだ。」
そう言うとシェリルは、何がおかしいのか短くハハハっと笑った。
エバは宿屋を出ると、昼間助けた娼婦のお姉さんの店に向かって、宿屋に面したプチヘンリー通りを、街のメイン通りであるファネリー大通りに向かって歩き始めた。
通りの反対側の宿屋の軒先には、ここに到着した時に確認した爺さんが壁にもたれ掛かって座っていた。
じいさん岩から眺めた時にはあれだけ晴れ渡っていた空は、いつの間にか雲に覆われてしまい、この世界に7つもある月の全てを覆い隠していた。
月明かりがなく、また他に明かりも灯されていないため、暗さに慣れた目であっても足元に注意が必要な程であったが、それはこの時代のどこの街でも同じで、松明を灯しているのは、夜営をしている街の衛視の詰め所くらいであった。
だがエバは武術家であったから、目を塞いで剣を扱う訓練を積んでいたこともあり、一般人とは明らかに異なる次元で五感が優れていたので、特に不都合は感じなかった。
宿屋が立ち並ぶプチヘンリー通りを歩いていると、通り過ぎる宿屋の中から宿泊しているであろう旅人たちの囁くような雰囲気が感じ取れ、通りを満たしている空気もほのかに温かさを帯びていて、穏やかな夜だとエバは思った。
エバが向かっている店は、娼館にしては珍しくメイン通りであるファネリー大通りに面して建っていた。
エバは歩きながらふと首を回して周りを見渡した時に、何か見たことがあるものが視界の中に映り込んだことに気付き足を止めた。
エバは、広げた手をかざしながら周囲をゆっくりと見渡すと、黒い空を背景に紛れ込むようにして宙に浮かんでいる小さな黒い玉を見つけた。
マーリンだな。エバは思った。
心配して見に来たんだろう。
エバは正体が分かったので、また足を進めた。
エバはプチヘンリー通りからファネリー大通りに入った。
ファネリー大通りに入ると、そこはパン屋が集まった通りなのだが、そこから南へ歩を進めると飲食店が集まった通りとなった。
飲食店が店を閉めるのにはまだ早い時間だったから、飲食店の小さな窓に貼られた油紙は店の中でゆらめくランプの明かりを映していて、談笑する人達の声も漏れ聞こえて来た。
その飲食店通りを抜けると、目指している娼館はすぐのところにあった。
娼館は2階建てで、1階は土間ではなく床が貼られていた。
エバは数段の木製の階段を上がると娼館の扉の前に来た。
扉は大きな両開きの扉で意匠が施された立派なものであった。
エバは娼館にしてはえらく立派な扉だなと思った。
エバは扉の前に立つと、ふと扉の向こう側で、誰かが床に体重を掛けた、つまり誰かが立っているのが分かった。
エバは武術家としての習性で左手を腰の剣に手を添えると、右手で扉の右側の取っ手を掴み奥に押し開けた。
すると、開いた扉の向こう側に男が一人立っていた。
その男は両腕をだらんと垂らした格好でまっすぐ立っているだけだったが、エバにはその男の立ち方が武術的であることが分かった。
別に踵が上がっている訳ではないのだが、重心が前よりになっていて、目の前の不審者がどのような動きをするのか、待ち構えていることがエバには分かった。
エバはその男の顔を見た。
その男は目尻が少し上がった特徴的な眼差しをしていて、銀髪で雪のような白い肌で端正な顔つきをしていた。
エバと男の視線が交差した。
「昼間ソフィを助けてくれた剣士さんだね。」
すると通路の奥から一人の女性がエバに声を掛けて来た。この娼館の娼婦だろうとエバは思った。
その女性は男の横に立った。
「ミシェルさん、この剣士さんだよ。ソフィを助けてくれたのは。」
すると男の顔が緩んだ。
「どうぞ。」
男はそう言うと壁側に寄ってエバが通れるよう通路を開けた。
「ソフィに会いに来たんだろう、この階段を上って右手奥の突き当りだよ。」
女性は正面の階段を示すとそう言った。
エバは男の横を通り抜け、女性に目をつぶって挨拶をした。
「私が案内してあげるよ。」
女性はエバにそう言うと、先に立って階段を上がり始めた。
この娼館は宿屋としても営業しているようで、2階の通路の両側に扉が並んでいた。
エバは女性に付いて通路を右手に進んでいくと、通り過ぎる扉の奥から、談笑する男女の声が聞こえて少しどきどきした。
女性は突き当りの部屋につくと扉を叩いた。
「誰。」
扉の中から女性の声がした。
「私だよ。剣士さんをお連れしたよ。」
すると床を元気にタタっと歩く感触があった後、少し間があって、扉が奥に開いた。
「本当に来てくれたんだ。ありがとう。」
扉が開いた隙間から、銀髪に、ちょっと大きめな緑色の瞳をした女性が顔を出した。
昼間見た時と同じように、彼女の衣服はちょっと下着のような薄手のものだった。

「ソンドラ、案内してくれてありがとう。」
「お安い御用さ。」
エバを案内してくれた女性はソフィにそう言うと、来た通路を戻って行った。
「さあ、入って剣士さん。」
ソフィはそう言うとエバを部屋の中に招き入れた。
部屋の中には衣装箪笥が壁沿いに並び、反対側には天蓋の付いた大きなベッドが置かれており、部屋の中央には絨毯が敷かれ、その上に丸いテーブルと背もたれの付いたイスが3脚置かれていた。
どの家具も古いもののようであったが、細かな意匠が施されており、高価な品物であろうことがエバにも想像できた。
「どうぞ、その椅子に座って。」
エバは素直に椅子に腰かけた。
「ちょうど今日ルークス産のウェハースが手に入ったからお出しするわね。」
ソフィはそう言いながら、棚から焼き物のコップを2つ取り出すと、そこに赤ワインをコップの半分程注ぎ入れた。そして暖炉の火にかけられた鉄製のヤカンを手袋をはめた手で掴むとコップに湯を注ぎ、最後にオレンジを煮詰めて作られたシロップを少し垂らした。
ソフィは小さな木製のお盆に、そのコップを2つと紙で包まれたウェハースを手際よく載せると、エバが座っているテーブルまで運んだ。
ソフィはウェハースをテーブルの真ん中に置くと、コップの1つをエバの前に置いた。
「ありがとう。」
エバはそう言ってコップに触れると中身の温かさが伝わってきた。
ソフィはコップを手に取るとエバに持ち上げて見せた。
すると反射的にエバは自分のコップをソフィのコップにぶつけてしまった。
「きゃっ。」
ソフィは小さな声を上げると驚いた顔をした。
「すまん。つい海賊の癖が出てしまった。」
「あなた海賊なの?」
ソフィは少し驚いたように瞳を大きくして微笑んだ。
「いや、俺じゃなくて仲間がだ。」
「そうなの。なんというか・・・独特ね。」
「まあな。」
エバはそういって苦笑した。
「でも楽しいわね。どうやるの?」
「どうって、コップをぶつけるのさ。」
「もう一度やってみる?」
ソフィがコップを掲げた。
エバとソフィはお互いのコップを黙ってぶつけた。
するとエバが言った。
「悪い、忘れていた。ゴッソって言うんだった。」
エバの言葉を聞いてソフィは思わず吹き出してしまった。
「そうなんだ。じゃあ、もう一度やる?」
ソフィはまたコップを掲げた。
エバもコップを掲げると言った。
「ゴッソ。」
エバとソフィはお互いのコップをぶつけた。
そうしてエバはコップに軽く口を付けると、その様子を見たソフィもコップに口を付けた。
エバはこの飲み物が柑橘の風味が爽やかで美味しいと思った。
「おいしい。」
エバがそう言うと、ソフィは微笑んだ。
「良かった。私も好きなんだ。ウェハースもどうぞ。」
ソフィはエバに勧めた。
エバはウェハースに手を伸ばすと口に運んだ。
割れたウェハースのかけらが少しぽろぽろと絨毯の上に落ちた。
「悪い、かけらが少し落ちた。」
エバが少しすまなさそうに言った。
「気にしないで、後で掃除しておくから。」
ソフィがニコッとした。
雰囲気が落ち着いていて、居心地悪くないな。
エバは部屋に置かれた天蓋付きのベッドを眺めながらそう思った。
「昼間は助けてくれてありがとう。」
ソフィはエバに言った。
「お礼なら助けた時に言って貰った。」
エバの言葉にソフィはふと少し考えると言った。
「そんな、一言言っただけじゃ気が済まない。とはいっても大したおもてなしもできないけど。」
ソフィは視線を下に下ろした。
「いや、こういう雰囲気は好きだ。ありがとう。でも、俺は好きでやっていることだから気にしなくていいんだ。」
「そうなんだ。前向きなんだね。」
エバはソフィの意外な言葉に驚いた。
「そんなことを言われたのは初めてだ。」
ソフィは少し考える素振りを見せた。
「そうかな。前向きだと思うけど。」
ソフィはそういうとコップを両手で持って口元に当てた。
俺、前向きだったのかな。
エバはそう思いながらコップの飲み物を少し口に含んだ。
「名前、何て言うの?」
ソフィがエバに聞いた。
そう言えばまだ名乗っていなかったな。エバは思った。
「エバだ。」
「そうなんだ。エバって呼んでもいい?」
「ああ。」
「エバは傭兵をしているの?」
ソフィは両手でコップを胸元に持ったままそう言った。
「いや、無職だな。」
エバはあっさりとそう言った。
「えっ、無職なの。」
ソフィは思わずそう言って、それからどういう表情をしたら良いのかなと思った。
すると、その様子を見てエバは言った。
「大丈夫。本当に無職だから。」
エバがあまりにもあっけらかんとしているので、ソフィは思わず笑ってしまった。
「そうなのね。じゃあ、無職でぶらぶらしているの?」
「旅をしている。」
「旅?」
「そう、世界中を回る旅だ。」
ソフィはエバが言った世界中を回る旅という言葉に魅力を感じずには居られなかった。
それはソフィがいつも心の中で思い描いていたことだ。
この世界を自分の思うままに、自由に巡って、自分の目で見てみたい。
「そうなんだ、素敵ね。今はどこに向かっているの。」
「ルークスに向かっている。北国には行ったことがないんでね。」
「そうなんだ。でも、お金とか大丈夫なの?」
ソフィが聞くと、エバは肩をすくめると目を閉じて見せた。
「それを考えるのは俺の仕事じゃあない。シェリルの仕事だ。」
「シェリルって?」
ソフィが分からない顔をした。
「さっき言った俺の仲間さ。」
「海賊の?」
「そうだ。」
「そうなんだ。面白い。じゃあ、エバの仕事は何なの?」
ソフィは、エバが語る言葉が予想外で、新鮮で、もっとエバのことが知りたいと思った。
「俺の仕事は戦うことだ。シェリルを邪魔する奴と戦っている。」
「なんかシェリルさんに任せっきりみたいに聞こえるけど、それでいいの」
ソフィはエバの言葉が無責任に思えた。
「頭のいいシェリルが考えた方がいいに決まっている。まあ、適材適所だ。」
「じゃあ、シェリルが間違ったら。」
ソフィは思わず意地悪な口調でそう言ってしまった。
「シェリルなら間違ったらそれを認めて、その責任を果たすだろう。俺は戦うことしかできないから、その時に何の役にも立たないかもしれないが、側にいてやるぐらいのことはできるだろう。」
この人は自分のことをかっこよく見せようとか、そういうことがないんだな。自然体だ。自分のありのままをそのまま出している。
ソフィはこれまで男性というものを見てきた中で、男なんて助平で威張っていて、女を見下していて、その癖都合よく甘えてきて、本当に愚かな生き物だと思っていたから、目の前の剣士が威張ることも甘えることもなく、私が女性であることなど関係がないような態度が爽やかで、心地よさを感じていた。
そうして目の前の剣士は、シェリルという女性を心から信頼している。間違うとか間違わないとかは問題ではなく、そのままのシェリルを受け止める覚悟を決めている。
ソフィはシェリルのことが羨ましいと思った。
自分が憧れた剣士は、既に心から信頼している女性がいた。
強くてかっこよくて爽やかなこの剣士の心を、どうやってこんなにも強力に繋ぎ止めていられるのだろうか。
そして、なぜ私はそれを持っていないのだろう。
シェリルと私とは、同じ女性でありながら何が違っているのだろう。
「あんたはどうなんだ。ここで何をしている。」
すると今度は、エバがソフィに尋ねた。
「私は・・・何もしていないかな。」
ソフィは何故か心が重く凝り固まっていくような感覚を覚えた。
「何で。」
「何でって、」
ソフィは言葉に詰まってしまった。
私はどちらかと言えばすごく恵まれていると思う。
はっきり言って、働かなくとも衣食住には困らない。
この娼館にいるのも営業をするためではないし、それに正直なところ、働いている娼婦を見下していた。
言葉にはしなくとも、私はあなた達とは違うのだと。
そして私は他の人とは違う特別な存在なのではないか、何か特別な唯一のものが手に入るのではないか、漠然とそう思っていた。
でも、いつまで待ってもそうはならなかった。少なくとも、今この時までは。
確かに高価な服や毛織物やお菓子やワインが私のもとに届けられた。
だが、そのうちの一つとして、自分にとって特別な何かとは感じられなかった。
何かが足りないのに、その何かが分からない。この満たされない感覚。これはいったい何なのだろうか。
「・・・自分でも良く分からない。」
ソフィはそういうと目を伏せた。
「じゃあ、それでいいんじゃないか。」
「えっ。」
ソフィは目の前のエバを見た。
「いいんじゃないか、それで。武術と同じだろ。自分が弱いことをまず認めなければ、強くはなれない。」
ソフィはその言葉で肩から力が抜けた気がした。
エバの言葉に清々しさを感じて心地が良かった。
そうか、この人は武術家だったんだ。
心を無にして、自分のありのままを受け入れて、稽古に励む清々しさ。
この人から発散している爽やかさは、その清々しさだ。
そうして私も武術家だった。
ソフィはしばらく忘れていたその爽やかな感覚を思い出した。
「私もしてみたいな。世界中を回る旅を。」
ソフィはエバを見つめた。
「したらいいんじゃないか。」
「できるかな。」
「何か問題でもあるのか。」
エバの言葉を聞いてソフィは少し考える素振りを見せた。
「いろいろとあるかも。」
そう言うとソフィはまた目を伏せた。
「例えば、そこのベッドの下に隠れている人とかか。」
エバは天蓋付きのベッドに視線を送った。
「なんだ、気付いていたんだね。」
「まあな。」
エバは部屋に入るとすぐに気付いていた。
この部屋に自分とソフィ以外の人間大の大きさの何かが、床の上を蠢いていることを。
それは足の裏に伝わってくる僅かな床の軋みであったり、蠢いた時に発する小さな衣擦れの音だったり、空気に薄く含まれた埃っぽさであったりした。
ソフィは椅子から立ち上がってベッドまで歩いていくと、しゃがみこんでベッドを覆っている毛布を捲り上げた。
「エイリスさん、見つかってしまったよ。」
ソフィがそういうと、ベッドの下から、頭を抱え込むように折り畳まれていた女性が、ずりずりとお尻を先頭にして姿を現した。
その女性はベッドから出て来ても、そのままの格好でソフィに話し掛けた。
「ソフィさん。ベッドの下は隠れるところではありませんでしたよ。」
「ごめんなさい。咄嗟にここしか思いつかなくて。」
ソフィは半分に折り畳まれているような女性を開くように起こした。
「はぁぁぁ。」
体を起こした女性の頭には綿埃がくっついており、女性は目を瞑っていた。
「ごめんごめんごめん。」
ソフィは女性の頭を優しくはたいて埃を落とした。
その女性は目を開けた。
目尻の上がった細い目をしていて、ロミタスと目がそっくりだなとエバは思った。
痩せ過ぎという訳ではないのだが、とても体の線が細い女性だった。
くすみがかった銀髪を編んで横にいくつか垂らしており、その垂らした髪の間から長く尖った耳が伸びていた。
彼女はエルファだった。
「埃だけじゃないの。体が痒いの。」
「エイリスさん、本当にごめん。」
ソフィは今度はエイリスの服を優しくはたき始めた。
「結局見つかるんだったら隠れる必要はなかったし。私が必死に耐えているのにソフィは男と一緒にどこかに旅立とうとしているし。」
「ぅぅぅ、ごめん。」
エイリスは目を細くした。
「裏切り者。ついさっきまで2人で仲良くしていこうねって言っていたのに。」
ソフィは再度目を伏せた。
「弁解のしようがない。だって、・・・私は本当に旅立とうと思ってしまいました。」
素直に告白したソフィをエイリスは見下ろすように眺めた。
「嘘じゃないし、騙された訳でもないからしようがないか。ソフィには助けて貰った恩もあるし。」
エイリスはそう言うと、小さく息を吐いた。
2人の様子を眺めていたエバと、絨毯の上にへたり込んでいるエイリスは目が合った。
「親父さんと違って人間の言葉が話せるんだな。」
エバがそう言うとエイリスはきょとんとしていた。
「以前お会いしたことがあったかしら?」
エイリスはエバに尋ねた。
「親父さんの方にな。」
そう言うとエバは目を閉じて見せた。
「お父様のご友人?」
エイリスは少し驚いた顔をしてエバに聞いた。
「さっき会ったばかりだ。」
エバは肩をすくめて見せた。
エイリスはソフィに顔を向けると言った。
「面白い方ね。」
するとエイリスの言葉を聞いたエバは言った。
「2人でかくれんぼをする方が面白いと思うがな。」
そんなエバの態度を見て、エイリスはまたソフィに顔を向けると言った。
「やっぱり面白い。」
ソフィはそんなエイリスとエバを見て思わず笑ってしまった。
「エバ、エイリスのお父様とどこで会ったの?」
ソフィがエバに尋ねた。
「宿が同じで、さっき一緒に食事をしていたところだ。」
ソフィとエイリスは顔を見合わせると驚いた顔をした。
エバと出会ったことはなんて運命的なことなのだろうとソフィは思った。
するとエバは2人に向かって言った。
「ロミタスの話だと人質に取られていると聞いていたが。」
「実は城から逃げ出して来たの。本当に一昨日のことなの。」
ソフィがエバの方に身を乗り出した。
「そうか。じゃあ、いつから囚われていたんだ。」
「私は4年かな。でも、エイリスさんはもう何十年も捕まっていたんだよね。」
ソフィはエイリスを見た。
「もう今年で、50年になるかな。」
エイリスは目を伏せた。
「おばあちゃんか。」
エバがぼそっと言った。
「違うから、おばあちゃんじゃないから!」
エイリスは顔を上げると強く否定した。
そのやり取りを聞いてソフィはまた笑った。
そしてソフィはエバに言った。
「エバ、エイリスさんを助けて欲しいの。」
「俺に出来ることがあるのか。」
「エイリスさんをお父様と会わせてあげて。」
ソフィは真剣な目でエバを見つめた。
「それなら、親父さんはこっちに向かっているだろう。」
エバは思わずそう言ってしまった。
「そうなの?」
ソフィが不思議そうな顔をエバに向けた。
エバはソフィの顔を眺めながら少し考えると言った。
「・・・みたいな。」
「みたいな?。」
エバとソフィは一息の間お互いに顔を見合わせていた。
そしてソフィは言った。
「良く分からないけど、待っていれば良いっていうこと?」
「まあそういうことだ。」
「良く分からないけど、分かった。」
そう言って前のめりになった体を起こして、ソフィは椅子に座り直した。
エバも上体を起こすと、今度は横目でエイリスを見た。
「ただ、親父さんに会って、その後はどうするんだ。」
エバはエイリスにそう言うと、エイリスは一瞬ソフィの顔を見て、それからエバに向かって言った。
「私はエルファの森に帰ろうと思っています。」
「帰ってしまって良いのか。」
エイリスは視線を下の絨毯に向けた。そして話し始めた。
「先々代のジョン様、先代のカーター様、どちらにも大変良くしていただきました。私は丘の上に建てられた屋敷に住まわせていただいていて、そこからエルファの森を眺めることもできましたし、それに先代のカーター様はよく私を街に連れて行ってくれました。囚われの身ではありましたが、優しい心遣いがありましたし、エルファに対する敬意が感じられました。」
エイリスは昔を思い出したようで微笑んだ。
エバはその微笑みの中に、彼女が背負ってきた50年という年月の重さを感じ取っていた。
「ですが、3年前に先代のカーター様がお体を悪くしてお亡くなりになって、当代に替わってから、私は屋敷から城に移されました。城に閉じ込められ、故郷の森を見ることも、城の庭園に出ることも出来なくなり、まるで厄介者のように扱われるようになりました。」
「そうか。」
エバはそう言うと目を閉じた。
「それに当代はエルファのことを気にもかけていないご様子。だから私は、人質としての務めを果たす義理も責任も、もはやないと考えているのです。」
エバはエイリスの言葉を聞いて少し黙って考えた。そしてエイリスに顔を向けた。
「森に戻って居場所はあるのか。」
エイリスはエバに向かってニコッとした。
「お父様がいれば大丈夫でしょう。それに、私は植物を育てるのが好きなのです。森に居た時はよくセローハマの部族に混じって森のお世話をしていたんですよ。」
「花が好きだって言っていたわね。」
ソフィがエイリスにそう言うと、エイリスはソフィを見た。
「ええ、ジンチョウゲ、ノウゼンカズラ、キンモクセイ、サザンカ、四季ごとに季節を教えてくれる、花が咲く植物が好きで、どれも可愛くて生命の繋がりを感じられる。森に戻ったらまた植物のお世話をして、ただ静かな暮らしをしたい。」
エイリスには、こんな生き方がしたいという思いがあるんだ。
ソフィはエイリスが話す様子を見ていて、自分はどうだろうと思ってしまった。
エイリスを連れてヤドゥイカ子爵の城を抜け出したのは私だ。
その時には、行動力も意志もエイリスより私の方が強いものがあると思っていた。
私がエイリスを助けてあげなくてはと思っていた。
でも、ここに来て何だかそれが怪しくなってきた。
城の中を私に手を引かれていたとき、既にエイリスは森に帰った後のことまで考えていて、そして、その目途をつけていたのだろうか。
私はただエイリスを助けてあげたい一心で城を脱出した。
しかし、私にはその後どのように生きていこうという考えはなかった。
思い返してみると、これまで私の人生は流されてばかりだ。
言われるがままに色々な貴族の家を転々として、このシャロムの街に4年前に移り住んだ。
私は何をしているんだろう。
「そろそろ着いたみたいだ。」
エバがそう言った。
「本当。」
ソフィとエイリスが居ずまいを整えた。
暫く3人は静かに椅子に腰かけていた。
そして少し遅いかなとソフィとエイリスは何か言葉を発しようかと思ったときだった。
「来たな。」
エバがそう言うと、廊下を歩く足音と合わせて、軋んだ床が発するギシっという音が聞こえて来て、その音がエバ達のいる部屋の前まで来た。
そして扉を叩く音がした。
「誰。」
ソフィが声を掛けた。
「私だよ。エイリスさんのお父様をお連れしたよ。」
扉の外から先ほどエバを案内してくれたソンドラの声がした。
ソフィは少し緊張した表情でエイリスと顔を見合わせると、椅子から立ち上がった。
「ソンドラ、今開けるわね。」
ソフィが扉を引いて開けた。
「わっ!」
ソフィは驚いて思わず声を出してしまった。
というのも扉を開けた向こう側には、廊下一杯に8人もの人がひしめき合って立っていたからだ。
ソフィが誰に話し掛けて良いやら困惑していると、先頭に立っている痩せたエルファの男性がソフィに話し掛けた。
「どうも、私は旅をしながら医術を研究している者です。マーリンと言います。」
マーリンはそう言って手を差し出した。
ソフィは思わずその手を握ってしまった。
「こちらにエルファのエイリスさんがいらっしゃると聞いて伺いましたが。」
そういうとマーリンは奥に座っているエルファの女性を見た。
マーリンの視線を追ってソフィもエイリスを見た。
「エイリスは私です。」
エイリスは人間の言葉でそういうと、椅子から立ち上がり扉の方に振り向いて見せた。
振り向いたエイリスはマーリンの隣に立っているロミタスと目が合った。
ロミタスはエイリスと目が合うと頷いて見せた。
その様子を見たマーリンは言った。
「こちらはエイリスさんのお父様のロミタスさんです。少し中でお話をさせていただいてもよろしいですか?」
マーリンは隣に立っているロミタスをソフィに紹介し、微笑んで見せた。
「ど、どうぞ。」
ソフィはそう言うと扉を大きく開いた。
「それではお邪魔します。」
まずマーリンが扉をくぐって中に入った。
「失礼する。」
次にロミタスが部屋に入った。
ソフィはエイリスさんのお父様ということで、少しかしこまった態度をした。ただ、ソフィにはロミタスの言葉が分からなかったが、気にしないことにした。
そしてソフィは、ロミタスの後ろから現れた女性に目が止まった。
サラサラとした長い金髪に、少々切れ長の碧い目をした女性だった。
彼女の顔には大きな傷跡が左右の頬に一つずつあった。
特に、彼女の左頬の傷跡は大きく、首から顎を通って目の下辺りまで続いており、その形状から何か鋭利な刃物で切り付けられたことを想像させた。
しかし、その傷跡は彼女に不思議な魅力を与えていて、何か彼女の強さのようなものを発散させているようだった。
「こんな夜分に押しかけてしまってごめんなさい。」
その女性はそう言って微笑むと、扉をくぐってソフィの横を通り過ぎた。
この女性がシェリルだ。
ソフィは直感でそう思った。
「ごめんなさい。」
すると、シェリルにくっつくように色白のほっそりとした女性が2人続いた。
2人は背丈が同じで、猫を連想させる瞳も良く似ていた。
長く尖った耳が髪の間から伸びていて、2人はエルファの姉妹だと分かった。
「ごめんなさい。」
カウボーイ・ハットのつばをちょっと上に持ち上げながら、キッドはそう言ってソフィの横を通り過ぎた。
少し目尻が下がった目は優しい印象を与えるが、鼻筋の通った、整った顔立ちはなかなかの男前だ。
「ごめんなさい。」
次に小柄な女性がソフィの前でカウボーイ・ハットを脱ぐと、隠れていたブロンドの髪が溢れた。
ルーはソフィに向かって愛嬌のある笑顔を見せると部屋の中に入って行った。。
「ごめんなさぁい。」
そう言うとビリーはソフィの横を通りながらカウボーイ・ハットに指を当てると左目をつむりウィンクして見せた。
何なんだろう、この人達は。
何でこんなに気分が盛り上がっているんだろう。
そしてソフィはピンと来た。
こいつら酔っ払いだ。
廊下に立っているソンドラとソフィの目が合った。
ソンドラの目は、ソフィに大丈夫ですかと問いかけていた。
「ソンドラも中に入って。」
ソフィがそう言うと、ソンドラも扉をくぐり部屋の中に入った。
ソフィは扉を閉めた。
ソフィの部屋の中は人で溢れていた。
ソフィ1人であれば広すぎる程であるこの部屋も、11人も人が入ると足の踏み場もない状況だった。
「えっと、今飲み物をお出ししますね。」
ソフィは引き戸の中からコップを取り出し始めた。
「俺も手伝おう。」
エバはソフィの側に立つと、ソフィの取り出したコップを受け取ってテーブルに並べ始めた。
部屋の真ん中のイスには、エイリスとロミタスが座った。
ロミタスの隣に立っていたマーリンがエルファ語でエイリスに話し掛けた。
「あなたのお父様はヤドゥイカ子爵の命令で囚われていました。私達は、たまたま逃亡して傷ついたお父様を見つけて助けました。そして、たまたまここにエイリスさんがいることを知り、お父様をお連れしたのです。」
「本当なのですか?」
「本当だ。俺はお前に会えると聞いて子爵の屋敷に来たんだが、子爵に捕まってしまった。そして何とか逃げ出したんだが、追っ手に捕まって乱暴を受けた。その時彼女に助けられた。」
ロミタスはベッドに座っているシェリルを親指で示した。
「お父様、怪我は、お体は大丈夫なのですか。」
「ああ、ひどく乱暴を受けたが、この人達に治療してもらって今は大丈夫だ。」
「良かった、それでは皆さんはお父様の恩人なのですね。本当に、ありがとうございます。」
そう言うとエイリスはまずマーリンに頭を下げ、周りの皆に向かっても頭を下げた。
「困っている時はお互い様さ。」
床の絨毯で膝を抱えて座っているビリーが両手の平を見せながらそういった。
その言葉を聞いて、思わずシェリルはクスッと笑った。
お前ロミタスがリンチされているのに、放っておいて行こうとしていたじゃないか。
シェリルは心のなかでそう思った。
「でも、なぜお父様が捕まらなければならなかったのですか。」
エイリスは改めてロミタスを見て言った。
「子爵からエルファが持っているプファイトの実で商売することを持ち掛けられた。プファイトの実を使って戦争に使う武器を作るのだと言っていた。俺はその話を断った。そして子爵に拘束されたのだ。」
マーリン達がエルファ語で話している内容は、マリーウェザーとアレンティーが皆に通訳して教えていた。
すると両手を太腿に挟んだ格好でベッドに座っていたシェリルがエイリスに話し掛けた。
「エイリスさん、子爵はどうも誰かの命令で動いていたようなんだ。子爵に命令できるような人物に心当たりはないか。」
シェリルは目を鋭くさせた。
するとコップにワインを注いでいたソフィとエイリスは顔を見合わせた。そしてワインの入ったコップを持ったままソフィがシェリルに言った。
「それは恐らく、ボワロだわ。」
「何だって、」
シェリルとビリーが顔を見合わせた。
「ボワロよ。神聖王国の首都ルークスの豪商で、その代表をしているわ。」
ソフィはシェリルにそう言った。
するとエバはソフィが手に持ったままのコップを引き取ると、テーブルに置いた。
ソフィはエバにニコッとした。
「今の子爵を連れて来たのはボワロよ。子爵はボワロの奴隷みたいなものだわ。」
ソフィに続いてエイリスもそう言った。
「ボワロは見た目、どんな人物なんだ。」
シェリルはソフィに尋ねた。
「歳は40ぐらいかな。日に焼けて色黒で細身で、見た目はそれなりにかっこいいかな。短い顎髭がある。」
ソフィは自分の顎を手で撫でて見せた。
「シェリルさん、今日シャロムの街の入り口であった親父に間違いなさそうですね。」
「そうだな。」
ビリーがシェリルに話し掛けると、シェリルは頷いて見せた。
「でも性格は最悪。ケチだし、ねちねちと長い時間を掛けて嫌味を言うのが得意みたいね。顔を合わせたくもないわ。」
エイリスが嫌な物でも見るように顔をしかめた。
その言葉を聞いて、シェリルは昼間のボワロの様子を思い出していた。
シェリルの記憶では、ボワロは物知りで爽やかな印象しかなかった。
やっぱり見た目じゃ分からないものだな。
シェリルは一人で苦笑いした。
「やっぱりな、俺は最初に見た時からいけ好かない奴だと思っていたぜ。」
ビリーが顔をしかめてそう言った。
「そんな嫌な奴なのか。」
キッドがビリーに聞いた。
「ああ、やけに黒光りする顔をしていたぜ。」
「黒ピカか。」
「そうだな、黒ピカだ!」
ビリーが大きく頷いて見せた。
「だけどそれだけじゃない、いやらしいんだよ目つきが。シェリルさんをいやらしい目で見ててさ。」
ビリーが手を広げながら大袈裟に皆に説明した。
「何それ気持ち悪い。」
ルーが眉をひそめた。
「黒ピカで、エロピカか。」
「そうだ、黒ピカのエロピカだ。」
キッドとビリーが言い合った。
「見え見えなんだよ、あの野郎、シェリルさんに纏わりつきやがって、黒エロが。」
するとビリーの様子を横目で見ていたマリーウェザーがビリーに言った。
「でも、ビリーだって見え見えじゃない。」
マリーウェザーの言葉にビリーが驚いた顔をした。
「えっ、俺が、何で。」
「何でって、見てたら分かるわよ、シェリル姉さんに纏わりついて、エロビリー。」
マリーウェザーが目を細めた。
「でも俺黒くないし。ピカでもないし。」
「でもエロだし。」
そこへ2人の様子を見ていたシェリルが割って入った。
「マリーウェザー、男がエロなのはしようがないよ。ビリーが可哀想だ。」
するとシェリルの言葉にマリーウェザーはしゅんと静かになってしまった。
「皆さん、飲み物をどうぞ。」
ソフィがテーブルに並んだコップを示しながらそう言った。
「ありがとうございます。」
ルーがそう言ってコップを手に取った。
テーブルの側にいたマーリンやロミタスやルーが皆にコップを手渡した。
この部屋にいた皆にコップが行き渡った。
「シェリルさん、せっかくだから乾杯しましょう。」
ビリーがそう言うと、良く分からない顔をしているエイリスとソンドラ以外の皆が頷いた。
その様子を見てシェリルが皆に向けてコップを掲げた。
「こぼすのは悪いから、軽めでね。」
シェリルはそう言うとビリー達にニコッとした。
ビリーとキッドはシェリルの笑顔に素直に頷いた。
「それでは、ロミタスとエイリスの再会を祝して、それからここに集った我々の運命を祝して、またこの場に我々をいざなった出会いと別れを司るリャノ神に感謝を。」
そういってシェリルは一同を見渡した。
「ゴッソ!」
そう言うとシェリルは隣に座っているマリーウェザーに微笑んだ。
すると静かにしていたマリーウェザーもシェリル見ると微笑んで、コップを軽く合わせた。
ソフィは隣に立っているエバを見た。
「またやるか?」
エバがそう言ってコップを掲げて見せた。
ソフィはニコッとしてエバとコップを軽くぶつけ合った。
そして、皆がそれぞれコップをぶつけあった。
どうして良いか分からないエイリスに、向かいに座っていたロミタスはコップを差し出した。
「人間の乾杯もなかなか楽しいもんだ。」
そういうとロミタスはエイリスに向かって白い歯を見せた。
ロミタスとエイリスもコップを軽くぶつけ合った。
そして例のごとく、相手を替えては皆延々とコップをぶつけあい、乾杯を楽しんだ。
「美味いな、これ。」
コップに口をつけたキッドがそういってルーに顔を向けた。
「本当ね、オレンジの香りが爽やかだわ。」
ルーがキッドに微笑んで見せた。
「気に入って貰えて嬉しいわ。」
ソフィが笑顔を見せた。
「エイリスさん、ボワロの話に戻るんだが、ボワロはなんで子爵を奴隷のように扱えるんだろう。子爵はボワロに弱みを握られているのかな。」
シェリルは知らない風を装ってエイリスに尋ねた。
「子爵はボワロに大きな借金をしているの。大体半年に一度、借金の取り立てにこの街に来ていたようね。」
エイリスの言葉を聞いて、シェリルは想定どおりの回答だなと思った。
「なるほど。それは今から18年前、青の帝国が神聖王国に侵略したとき、敵から要求された戦費を調達するため当時の子爵がボワロから借金した、といったところかな。」
「ええまさにそうですわ。」
エイリスはシェリルの言葉に驚いた顔をした。
「もう一つ、当代の子爵を連れて来たのはボワロで、子爵はボワロの奴隷みたいなものとさっきおっしゃったけれども、本当に奴隷のような扱いなのか。」
「それは本当よ、ボワロは子爵をマックレと呼び捨てにしているし、子爵はボワロの命令を守ることを絶対と考えているようだわ。」
するとエイリスに続いてソフィも口を開いた。
「最近も、ボワロがこの街に到着するからって急に忙しそうにして、家令や執事や侍従長にまで八つ当たりして怒鳴り散らしていたのよ。ボワロに対するいいなり感は異常だわ。」
ソフィとエイリスの言葉を聞いたビリーが首を傾げた。
「領主が商人に奴隷みたいに扱われているっておかしくないか。そもそもエロピカが跡継ぎを連れて来たんだろう。それって、そもそも本物の跡継ぎなのかよ。」
するとキッドも頷いてビリーを見た。
「エルファと関係が悪化する事を何とも思っていなかったり、早く首都のルークスに帰りたいとか言っていることを考えると怪しいんじゃないか。」
「それって、つまりボワロが自分の都合が良い人物を子爵に仕立て上げているということ。」
ビリーとキッドとルーがそう言い合うと、その3人の言葉を聞いたソフィとエイリスが驚いた表情を見せた。
するとシェリルがエイリスにさらに尋ねた。
「前代の子爵にはご家族はいらっしゃらなかったのか。」
「奥様が1人いらっしゃったわ。」
「お子様は?」
「残念だけどできなかったようね。」
すると、エイリスの言葉を聞いてビリーとキッドとルーは、はっとした表情をするとまたお互いに顔を見合わせた。
「どうしたんだ。」
シェリルはビリーに鋭い視線を向けた。
「前代の子爵の奥さんですが、3年前に前代が亡くなってから、すぐに奥さんも亡くなったんです。それで街では噂になっていたんです、前代のことを追いかけて亡くなったんじゃないか、それほど仲が良かったんじゃないかって。」
するとビリーの言葉にエイリスが両手で口を押えた。
「奥様が亡くなったって本当ですか?」
「知らなかったのか。」
シェリルがエイリスに尋ねると、エイリスはシェリルを見て頷いた。
「前代の子爵がご存命の時には、私とソフィは奥様と一緒に、さきほどお話しした屋敷に住んでいたんです。そして、前代がお亡くなりになって、ボワロが当代の子爵を連れて来ると、私とソフィは屋敷から城に移されたんです。その時には奥様はまだお元気でいらっしゃった。その後私達は城に閉じ込められていましたから、奥様がどうなったか分からなかった。」
皆が黙ってエイリスを見ていた。
「奥様も花がお好きで、・・・良く私と一緒に・・・ごめんなさい。ちょっと、涙が出てきてしまって。」
そう言ってエイリスは指で目頭を押さえた。
「・・・奥様は成人してすぐの12歳で嫁いで来られたんですが、まだ表情に幼さが残っていて、その可愛げな姿を今でも良く覚えています。私も幼い時にこの街に連れてこられたので、奥様と自分を重ねてしまって、とても親近感が湧きました。それから10年以上もご一緒していたので、最後にお会いすることも出来ずに亡くなっていらっしゃったなんて。あまりに残念です。」
マーリンに通訳をして貰いながら、ロミタスも眉をひそめた。
「人間と共に生きる10年は、長いわね。」
エイリスは少し鼻をすすりながらそう言った。
エイリスの言葉に、誰も何も言うことはできなかった。
皆は改めて、エイリスの50年という月日の重みを感じていた。
「バークという男を知らないか。子爵の命令で動いているチンピラなんだが。」
シェリルはエイリスとソフィに尋ねた。
「知っているわ、よく子爵のところに金をせびりに来ていたから。バークは子爵の命令で汚れ仕事をしていたようね。」
ソフィがシェリルにそう言った。
「そのようだな。街のガヤン神官の話だと、その汚れ仕事で何度もバークはガヤンに掴まって牢にぶち込まれているようだ。そしてその度に、子爵が罰金を払ってバークを牢から出してやっている。」
シェリルはそう言って周りを見渡すと、エイリスもソフィもビリーもキッドもルーも皆シェリルを見ていた。
そしてシェリルは口を開いた。
「私も皆と同じことを考えているよ。エイリスさんを嫌な気持ちにさせてしまうだろうが。奥様は、ボワロが連れて来た偽物の子爵、マックレの命令でバークに殺されたのではないかと。」
シェリルはそう言ってエイリスを見た。
「いえ、大丈夫です。何となく、マックレは怪しい男だと気付いていました。」
そう言ってエイリスは落ち着いた表情でシェリルを見た。
「ソフィさんとエイリスさんを奥さんから引き剥がしたというのも、奥さんを殺すためと考えれば納得できるな。」
「それに子爵が偽物ということなら、奥様を平気で殺してしまうのも納得が行くわね。」
キッドとルーがそう言って顔を見合わせた。
「そうなると狙いは子爵の財産。結局金かよ。奥さんは金のために殺されたのかよ。」
ビリーは汚いものでも吐き捨てるようにそう言った。
「まあ、マックレが自分で言っているように、プファイトの実の商売も金が目的のようだから、ビリーの推測は当たっているんじゃないか。あと、殺されたのは奥さんだけではないと思う。前代の子爵や奥さんの近くにいた人達は殺されてしまった可能性が高いだろう。」
シェリルはビリーを横目で見ながらそう言った。
「確かに、マックレが子爵になると、前代の子爵に仕えていた家令も執事も解雇されてしまったようです。ですが、解雇ではなく殺されてしまったのかもしれないですね。」
エイリスが独り言のようにそう言った。
「恐い。」
ルーがそう言って目を伏せた。
「ああ、確かにな。」
キッドがルーの肩に手を乗せた。
すると今までロミタスに通訳をしていたアレンティーがシェリルに尋ねた。
「この街の領主が本物かどうかというのは、この街にとって重大な事件ではないのですか?それに、殺された人も複数いるというのであれば、この街のガヤンは気付かないものなのでしょうか。私には事の重大性のわりに、ガヤンを含め周りが誰も気づいていないことに違和感があるのですが。これはしようがないことなのでしょうか。」
ガヤンというのは正義と法の神であり、その神の教えを実践している信者達は、そのガヤンの法を犯す悪人を捕まえ、法の前で裁く権限を国王から与えられていた。
アレンティーの言葉に皆が口をつぐんだ。
確かに、事は重大であるように思うし、そもそも街の治安を守る仕組みはこの問題に対して機能しないのだろうか。
「アレンティー、私はアレンティーのそういうところが大好きなんだ。」
シェリルはそう言ってアレンティーに微笑んだ。
アレンティーは、シェリルは酔っぱらっているのかなと思いつつも、思わず嬉しい気持ちが込み上げてきて、視線を下に伏せた。
そんなアレンティーに向かってシェリルは言った。
「問題を考える時に、問題に近寄って目を凝らして細かく調べることは重要だが、問題から距離を置いて全体像を眺めることで、その問題がどのような傾向を持っているのかを把握することも重要だ。そして細かく調べた結果と、距離を置いて眺めて分かった傾向を重ね合わせて見て、矛盾が生じていないか検証してみることは大事な事だ。」
シェリルがそう言うと、アレンティーは顔を上げてシェリルを見た。
「ただ今回の問題は、ロミタスがもたらした子爵の情報、エイリスやソフィがもたらした城の中の情報、ビリーやキッドがもたらした街の情報を組み合わせることで、ようやく真相が見えてきたもので、実は我々がここで出会ったこと自体が奇跡的と言っていい。つまり、それらの情報を知り得ないガヤンに、真相まで到達することを期待するのは酷というものだろう。また死人が複数出ているとすれば、当然にガヤンの取り調べが行われたはずだが、マックレやバークがあらかじめ証人を用意しておけば、上手くすり抜けることは困難なことではないだろう。だとすれば、アレンティーが言ったガヤンが機能しなかった事実と矛盾は生じないと思う。」
シェリルがアレンティーに説明すると、アレンティーはシェリルを見て納得したように頷いた。
するとビリーが慌てた様子で立ち上がるとアレンティーに向かって人差し指を向けた。
「いや違うでしょ。アレンティー、遠慮しちゃいけないぜ。」
アレンティーは別に遠慮した訳ではなかったが、ビリーの勢いに思わず小さく頷いた。
するとビリーはシェリルに向かって身を乗り出した。
「シェリルさん、理屈じゃないんだぜ。今回のこの場合だ。エイリスさんや奥さんがやられた事を考えた場合だぜ。俺達でも気付いたようなことが、何で頭のいいガヤンの神官が分からないのか。死人が何人も出ているのだとしたら、細かく調べれば分かるはずだ。」
ビリーはシェリルに向かって一気にまくし立てた。
「シェリルさんも見た筈だ。ロミタスさんを助けて、捕まえたバークを引き連れてガヤンに行った時、奴らはのんびりと椅子に座って、暇つぶしにおしゃべりをしていたんだぜ。しかも、バークが何度も悪さをしているのに、罰金と引き換えにのうのうと牢から出してやっているんだぜ。その罰金はどこに行くんだ?奴らの懐の中だ!ガヤンは法律を使って悪い奴らをやっつけるのが仕事だろう、何でバークをやっつけないんだよ。」
ビリーの大演説が終わると、マリーウェザーが立ち上がった。
「そうだ、エロビリー、良く言った。亡くなった奥さんが可哀想。こんな悪い奴らがのうのうとのさばっているのに、放置しているガヤンは、私は許せない!」
マリーウェザーもビリーの勢いに負けない調子で宣言した。
予想外に意気投合したマリーウェザーの様子を見て、ビリーはあっけに取られていた。
「・・・エロはいらないんだけど。」
我に帰ったビリーがぼそっとそう言った。
シェリルは二人の力強い言葉に嬉しさが込み上げて来た。
何か成そうとする時に必要なのは強い感情だ。
その強い感情が行動するための力の源となる。
きっとこの二人はエイリスや奥さんのために、力強い活躍を見せてくれる筈だ。
もっとも、まだ奥さんが殺されたという証拠がある訳ではなく、確定した訳ではないのだが。
「ビリーとマリーウェザーの思いは十分私に伝わったよ。」
シェリルはビリーとマリーウェザーに微笑んだ。
「ただ、一つ話をしておきたいんだが、ガヤンは法律を破ったものを捕まえて、法律に従って処罰するのが仕事だ。では、ガヤンがとても優秀であったなら、奥さんは亡くならずに済んだだろうか。」
「そりゃ、ガヤンが使える奴だったなら奥さんは助かったはずだぜ。」
ビリーが先ほどの大演説の勢いのままにそう言った。
シェリルはビリーの言葉に頷いた。
「そうだな。だが、私はそうは思っていない。」
シェリルの言葉にビリーは思わずあっけに取られた顔をした。
「ええっ、だって、さっき俺の思いは分かるって言ったじゃないですか。」
ビリーがシェリルに残念そうな顔を向けた。
シェリルはそんなビリーに微笑んだ。
「だから、ビリーの思いは分かっているよ。私が話すのは思いとは少し違う話だ。」
シェリルは改めてビリーだけでなく、マリーウェザーやアレンティーやキッドやルーを見渡すと話を始めた。
「もう一度ガヤンの仕事を言わせて貰うと、ガヤンは法律を破ったものを捕まえることだ。すると、ガヤンが動き出す時には既に法律は破られた後ということになる。今回の奥さんの場合で言えば、ガヤンが動き出すのは奥さんが亡くなった後ということになるから、ガヤンが優秀であっても奥さんは亡くなっていただろうし、法律は奥さんの命を守ることはできない。」
「ええっ、そんな。」
ビリーがシェリルの言葉に頭を抱えた。
するとルーが心配そうにシェリルに尋ねた。
「ガヤンは悪い奴らを捕まえるのが仕事なんだよね?」
「そうだよ。だから、人が死んでから悪い奴らを捕まえるんだ。」
シェリルはそう言うと目を細めてルーを見た。
ルーは何と言って良いのか言葉を失ってしまった。
「シェリル姉さん、じゃあ人間は何のために法律を作っているの。法律は人間を守ってくれるものじゃないの。」
マリーウェザーがシェリルに尋ねた。
「法律というのは、簡単に言ってしまえばこの街に住みたかったら街の規則を守ってね、というものだ。人を殺したら罰金、払えなければ絞首刑。つまり、規則を破り悪いことをしたらその後で罰がある訳で、悪いことを事前に防ぐことはできない。」
「でも、罰を恐れて、悪いことをするのを思い止まる可能性があるのでは。」
アレンティーが小さく手を挙げながら、シェリルに向かってそう言った。
「法律の抑止力のことだね。だがそれには欠点がある。一つは、さっき話していた男性の性質と同じように、正常な判断ができない人間には抑止力は働かない。もう一つは、規則を破ったことがばれない自信がある人間、捕まらない自信がある人間には抑止力は働かない。今回のバークのように。」
「なるほど。」
アレンティーは小さく頷いた。
「そうか。」
ビリーもシェリルに向かって頷いて見せた。
シェリルは改めて皆を見渡すと言った。
「法律は人を守ってはくれない。法律は本気になった人に対しては無力だ。例えば、今目の前でまさにバークが奥さんを殺そうとしていたとしたら、奥さんの命を救えるのは誰だ、ガヤンか?法律か?」
シェリルが皆に問いかけた。
皆はじっとシェリルを見ていた。
シェリルは瞳を細めて視線を遠くに反らした。すると瞳は切れ長な印象に変わり物憂げさを醸し出した。
そして視線をそのままにしてシェリルは言った。
「私は奥さんを助けてあげたかったな。」
そう言ってシェリルは目を伏せた。
シェリルの様子を見て、皆ははっとして目を伏せた。
奥さんの命を狙っているのも人ならば、救うことができるのも人だった。
ガヤンでも、法律でもなく、奥さんの命を守ってあげられる誰かだった。
ビリーもマリーウェザーも黙って目を伏せた。
すると壁にもたれ掛かって腕を組んでいたエバが体を起こした。
「それは俺の仕事だ。」
突然エバがそう言った。
その言葉を聞いて皆がエバを見た。
「シェリル、俺に命令しろ。そのために俺はここにいる。」
そう言ってエバは肩をすくめると目を閉じて見せた。
シェリルはエバを見つめた。そして言った。
「そうだな。その時は、・・・エバに任せる。」
そう言うと、シェリルは黙ってコップを口に運び、飲み物を口に含んだ。
何だよ、エバの奴、かっこいいじゃないか。
シェリルはコップを口につけたままそう思った。

「シェリルさん。」
ソフィがシェリルに声を掛けた。
「教えてください。シェリルさんは何をしようとしているのですか。」
ソフィは真っ直ぐにシェリルを見た。
シェリルはソフィを正面から見据えた。
「私はエイリスとロミタスを助けたい。そして、マックレに真相を問いただし、その責任を果たしてもらおうと思っている。」
すると、シェリルの言葉を聞いたエイリスが椅子から立ち上がった。
「シェリルさん。私はマックレが何と言うのか、聞かずには森に戻れません。ご一緒させてください。」
エイリスはそう言うとシェリルを見た。
そしてシェリルも黙ってエイリスを見た。
シェリルとエイリスの視線が交差した。
ソフィはそんな二人の様子を見て、心の中で感情が高まるのを感じた。
そうだ思い出した。
言われるがままに色々な貴族の家を転々として、流されてばかりだった私の人生だったが、エイリスを助けたいと思った時、その時は内側から感情が溢れ出るように感じた。
そして、自分の意志で城を抜け出そうと思ったのだ。
そのとき私は気持ちが高ぶって、部屋のなかをうろうろしながら自分に言い聞かせた。
私は一人でエイリスの手を取って、この城を抜け出すのだと。
エイリスが奥様に自分を重ね合わせていたように。私は囚われの身であるエイリスに自分を重ねていたのだ。
だから、城から見張りの人間が急にいなくなった時、これなら城を抜け出せる。エイリスを助けられる。エイリスを助けたい。そう思った。
そして、城を抜け出した。エイリスと馬を1頭連れて。
私はこれまで自分のことが分からなかった。
自分が何がしたいのか。自分は何をしているのか。
自分に何かが足りないのに、その何かが分からない。満たされていない感覚だけがいつも胸の中にあった。
だが、少なくともエイリスを助けたいと私は自分の意志で思ったのだ。
そして、エイリスの手を引いて城の中を駆けたとき、私はすっかり忘れていた。高価な服や毛織物やお菓子やワインでも埋められなかった心の隙間を、自分に何かが足りていないという満たされていない感覚を。
そんなことはどうでも良くなっていた。
それなら、その気持ちを大事にしたい。
「じゃあ、それでいいんじゃないか。」
ソフィは、さっきエバから言われた言葉を思い出した。
私の人生は、そこからようやく始まるのかもしれない。
「シェリルさん。私もエイリスを助けたい。そして、事の真相を見定めたい。」
ソフィはそう言ってエイリスの隣に立つと、エイリスの細くて白い肩に手を置いた。
ソフィとエイリスが目を合わせた。
その様子を見てシェリルが目を細めた。
「純粋な人の意志ほど、キラキラと輝いて、これほど貴いものはない。」
シェリルは2人に微笑んだ。
シェリルはロミタスを見たが、ロミタスは片方の眉を器用に吊り上げて見せると、肩をすくめた。
「シェリルさん。」
ビリーがシェリルに声を掛けた。
シェリルはコップを両手で持ったままビリーを見た。
「俺もいますよ。ここに。」
そう言うとビリーはエバを真似て肩をすくめると目を閉じて見せた。
そのビリーの様子を見てシェリルは思わず声を出して笑ってしまった。
「シェリル姉さん。」
今度はマリーウェザーがシェリルに声を掛けた。
シェリルはマリーウェザーを見た。
「私もいるわ。」
マリーウェザーは肩をすくめてシェリルに微笑んだ。
そしてシェリルもマリーウェザーに微笑んだ。
「シェリル。」
今度はルーが声を掛けた。
「私達もいるよ。」
ルーが肩をすくめて見せると、アレンティーも真似をして肩をすくめて見せた。
二人の様子が可愛くてシェリルは笑顔を見せた。
そしてシェリルは最後にキッドを見た。
「もちろん俺も。」
キッドはカウボーイ・ハットのつばをちょっと上に持ち上げて見せた。
「お前たちがここにいることは良く分かったよ。」
シェリルは飛びっきりの笑顔を皆に向けた。
するとその様子を見て、エバは皆に言った。
「俺の真似をするのはいいが、歩きながらやると人にぶつかるから注意しろよ」
エバの言葉を聞いて部屋にいる皆で笑った。
「エバさん、もう真似することないと思うんで安心してください。」
ビリーがエバにそう言った。
「流行が飽きられるのは早いもんだな。」
そう言ってエバは肩をすくめると目を閉じて見せた。
エバのその様子にまた皆で笑った。
「おーい。」
今まで黙っていたマーリンがいきなり皆に声を掛けた。
皆がマーリンに注目する。
「何だい、マーリンさん。」
ビリーが声を掛けた。
「これからバークに会いにガヤンのところに行くぞ。」
「えっ、今から行くんですか?」
ビリーが驚いた顔でマーリンを見た。
「マックレをやっつける前に、まずは小者のバークを退治してやりましょう。」
マーリンはそう言って、座っているロミタスの肩を叩いた。
「そう言えば、忙しくてバークにお礼をするのを忘れていたな。」
マーリンとロミタスが目を合わせるとニヤリと笑った。
「お兄様が珍しく燃えている。」
アレンティーが独り言のようにつぶやいた。
「エルファが受けた屈辱は、エルファである我々が洗い流すのが筋というもの。シェリルに頼ってばかりという訳にはいかないでしょう。」
そう言ってマーリンはエイリスやロミタス、マリーウェザーとアレンティーを見た。
皆はマーリンの言葉に頷いて見せた。
放っておいてもシェリルはエイリスやロミタスのために勝手に考えて行動してくれるだろう。
でも、この問題はエルファの問題でもあるのだ。
シェリルに甘えてばかりではいけない。
シェリルは周りに弱音を吐くことをしないし、すがりつくこともしない。
だからシェリルを助けたいと思えば、自分から動かなければ。
エルファの私が引っ張らなければ。
マーリンは心の中で自分自身を引き締めた。
「エバ、シェリル、行くぞ。」
マーリンはエバとシェリルに声を掛けた。
するとシェリルとエバはそんなマーリンを少しの間眺めた。
そしてシェリルが眉をひそめた顔をした。
「マーリン、また少し痩せたんじゃない?」
シェリルがマーリンに言った。
「俺も思った。頬が凹んで、目つきも恐い。同じものを食べてるのに何でだろ。」
エバも不思議そうな顔をしてマーリンに言った。
「そんな事言われるために声を掛けたんじゃないわ!普通に、行きましょうとか言えんのかい!」
マーリンが珍しく鼻息を荒くして息巻いて見せた。
その様子を見て、マリーウェザーもアレンティーも、そして他の皆も声を出して笑った。
エバ達はソフィが居た娼館を出て、ガヤンの詰め所に向かって真っ暗な夜道を歩いていた。
ガヤンというのは正義と法の神であり、その神の教えを実践している信者達は、そのガヤンの法を犯す悪人を捕まえ、法の前で裁く権限を国王から与えられていた。
エバ達は、ロミタスを襲ったバークに話を聞くために、バークが牢に入れられているガヤンに向かっているところだった。
先頭を五感が優れているエバが、次にキッドとルー、ソフィとエイリスとソンドラ、ロミタスとマーリン、マリーウェザーとビリー、最後尾をアレンティーとシェリルが続いた。
ソフィとエイリスは、部屋に居た時の薄手の部屋着を着替えて、ふんわりとした長袖のチュニックの上に柔らかな皮でできた袖の無い上着のサーコートを重ね、腰を布のベルトで締めていたが、エイリスはさらに亜麻布のフードを被って顔を隠していた。
もう深夜の時間帯であり、大きな街であれば朝方まで開けている飲食店もあったが、小規模の大きさであるこのシャロムの街では、店を開けている飲食店は既になく、この時間帯に外を出歩いているのは、酒を飲み過ぎて自分が何処にいるのか分からなくなってしまった酔っ払いか、盗みを働くために建物の陰から陰を渡り歩いている盗人くらいのものであった。
目指しているガヤンの詰め所は、この街の中心を通っているファネリー大通りとウェイン大通りが交わる位置にあり、いわゆる街の中心にあった。
「壊れた荷車がある。」
先頭を歩くエバが皆に声を掛けると、足元に向けて親指を向けた。
エバの声に皆が頷いた。
月明かりもない夜道は本当に真っ暗で、道に広がった汚水、無造作に置かれた壊れた荷車、梯子、木材、建物から張り出した梁や階段などに度々注意が必要であった。
道に広がった汚水に足を滑らせて転倒し汚水にまみれてしまうのも大変な不幸だが、転倒した勢いのまま壊れた荷車などの固く角張ったところに体をぶつけてしまうと、打撲や骨折をしたり、頭をぶつけて死んでしまったという不幸な人の噂もあったから、エバの注意を皆は当たり前に真剣に聞いていた。
そうやって慎重に進んでいくと、通りの先にゆらめく明かりが見えて来た。
それはガヤンの詰め所の入り口に掲げられた松明の明かりだ。
近づいていくと、詰め所の入り口には日中にシェリルが訪れたときと同じように椅子にどかっと座って足を組み、周囲を眺めている男が一人いた。
「シェリルさん、ガヤンが間抜け面して座っていますよ。」
ビリーが振り返るとシェリルに声を掛けた。
シェリルは生意気そうな顔をしてそう言ったビリーの顔を見て、そして微笑んで見せると、人差し指を立てて見せた。
ビリーがその人差し指を見つめると、シェリルはその人差し指をビリーの頬に当てた。
「ビリー。これから事に当たろうという時に、侮ってはいけないぞ。その台詞は事が終わった時まで取っておくんだ。」
そう言うとシェリルは人差し指をビリーの頬から離した。
「そうですね。」
ビリーは嬉しそうにそう言った。
“チリーン”
すると、不意にシェリルの首輪につけられた鈴が鳴った。
その鈴の音に、ビリーだけでなくマリーウェザーとアレンティーも、シェリルを心配そうに見た。
先頭を歩いているエバも足を止めるとシェリルを見た。
「どうしたの?」
ソフィがエバに聞いた。
「シェリルの首輪につけられた紅い鈴は魔法の鈴で、危険が近づくと鳴って教えてくれる。」
「そうなんだ。」
ソフィがそう言って頷いた。
「シェリルさん。」
ビリーが声を掛けた。
シェリルは心配そうに見ているビリーとマリーウェザーとアレンティーの顔を順番に見て、そして微笑んだ。
「この危険は避けて通る訳にはいかないな。」
シェリルの言葉に皆は何も言えなかった。
するとマーリンがシェリルに聞いた。
「この危険は、シェリルが青の帝国から賞金が掛けられているということをガヤンが気付いた、という可能性も考えられるが、バークを引き取りに子爵が来ているという可能性も考えられるか。」
マーリンの言葉にシェリルは人差し指を顎に当てて少し考える素振りを見せた。
「うーん。」
しかしシェリルはマーリンが言った事とは別の事が思い浮かんだ。
ロミタスを助けた時に逃がした野盗が3人いたな。シェリルはそのことを思い出した。
マーリンの言葉を背中で聞いていたエバも、足を止めてふと考えた。
「うーん。」
ソフィを助けた時に逃げて行った男達がいたな。エバはそのことを思い出した。
「シェリルさん、大丈夫ですか。」
ビリーが心配そうにシェリルに尋ねた。
「大丈夫、大丈夫。」
シェリルはビリーに向かって手をひらひらさせると笑顔を向けた。
「行きましょう。」
マーリンが皆に声を掛けると、ガヤンの詰め所に向かって、エバ達はまた歩き出した。
すると、この先に繋がっているウェイン大通りから黒い人影が転げるように現れると、ガヤンの詰め所の前で倒れ込んだ。
倒れ込んだ人影は詰め所の前で座っているガヤンの男と何か話をしているようだった。
すると倒れ込んだ男が転がり出て来たのと同じ暗闇の中から、数人の人影が走り出て来ると、倒れ込んでいる男を取り囲んだ。
「シェリルさん、昼間も同じようなことがありましたね。」
ビリーがシェリルに声を掛けた。
「本当だな。」
そう言うとシェリルはビリーに苦笑して見せた。
そしてシェリルはエバの横まで歩いて行くと足を止めた。
「エバ。どうせお前だろう。」
シェリルがエバに声を掛けた。
「お前がそうやって声を掛けてくるときは、お前に心当たりがあるときだ。」
「うっ。」
思わぬエバの逆襲にシェリルは口をへの字にすると困った顔をしてエバを見上げた。
こいつ可愛い顔してこっち見やがって。エバはそう思いながら目を細めるとシェリルを見下ろした。
するとそんな二人にマーリンが後ろから近寄ってくると声を掛けた。
「あの取り囲まれている男、北門にいた門番だよ。」
エバは横に来たマーリンを見た。
「そうだっけ。」
エバがそう言うとマーリンは頷いて話を続けた。
「ほら、じいさん岩から戻ってきて北門をくぐった時に、エルファを探している人がいなかったかどうか、俺が門番のおじさんに聞いたじゃないか。」
エバが視線を前に戻しながら、うんうんと頷いた。
「そういえばいたな。あのおじさんか。」
「間違いない。」
エバとマーリンがお互いに合点がいったような顔をした。
「ふーん。」
そんな二人の様子をシェリルは横から見ていた。
「あのおじさんが言うには、馬を連れたエルファと女を探している男達がいて、心当たりがないかおじさんに聞いてきたらしい。」
マーリンがシェリルに説明した。
「ふーん、そうなんだ。馬、エルファ、女ねえ。」
シェリルは人差し指を顎に当てて少し考える素振りを見せた。
「馬、エルファ、女か。」
エバも腕を組むと空を見上げた。
「馬、エルファ、女。」
そんな二人につられてマーリンもつぶやいて見せた。
「私達のことだな、それは。はははは。」
「違いない。」
シェリルとエバとマーリンはそう言い合って笑った。
「エバ、行こう。皆はここで待っていてくれ。キッド、ビリー、万が一こっちに男達が寄ってくるようなことがあったら、けっして打ち倒そうと思うなよ。腰の剣を大袈裟に振って、近寄らせなければそれでいいから。頼んだぞ。」
シェリルがそう言うと、キッドとビリーが真剣な眼差しで頷いた。
そしてシェリルは振り返って歩き始めると、エバも黙って歩みを進めた。
2人が肩を並べて歩いていく後ろ姿を見て、ソフィは胸の中がもやもやとしているのに何か質量を感じさせるものが膨らんでいく感覚に戸惑った。
私も一緒に付いて行きたい。
ソフィは右手で左手首を撫でた。
実はソフィは、もしものために薄い金属板を縫い付けたバンドを、左手首と左足の脛に巻いていた。これがあれば、刃物を持った敵に対しても素手で立ち向かうことができた。
昼間エバに助けてもらったとき、同じ敵を撃退するという経験を共有して、一体感を感じた。
そして、それがとても心地良かった。
だから、同じ武術家として戦いを共有したい。もう一度エバと一体感を味わいたいと心が欲している。
でも、付いて行きたいと言葉にできなかった。
まだ、あの2人の間にはとても入り込めない。
「アレンティー、マリーウェザー。一応準備をしておきなさい。」
そう2人の妹に声を掛けると、マーリンは別に何でもないというようにエバ達の方に視線を移した。
エバは歩きながら視線を前に向けたまま独り言のようにシェリルに言った。
「女、子供という訳でもあるまいし。助けてやる必要はないだろうに。」
「まあ、話を聞いてやろうじゃないか。」
シェリルも視線は前を向いたまま、エバをなだめるような調子でそう応えた。
「男だったら自分の身は自分で守れよ。自分の身も守れないなら、どうやって女子供を守ってやれるんだ。」
「はいはい。お気に召していないことは理解しているつもりだよ。」
シェリルの言葉を聞いてエバは少しむっとした表情をすると、一瞬黙って考えた。そして言った。
「俺は、・・・いっぱしの大人の男の生き方に口を出すのも、出されるのも嫌いだ。」
エバは少し強い口調でそう言った。その口調から本当に嫌いなのだということが分かった。
するとシェリルも少し強い口調で返した。
「だからさ、口は女の私が出すから。エバは私の側に居てくれる為に、付いて来てくれているんだろ。違うのか。」

シェリルの生意気なその言葉に、エバは前を向いていた視線をシェリルに向けると、シェリルは首を少し傾け、はにかんでいるような表情でエバを見つめた。
またこれだ。エバは目を細めてシェリルを見た。
「お前、今どんな顔をして俺を見ているか自覚してないだろ。」
「あのなぁ、自分がどんな顔しているかなんて本人に分かる訳ないだろ。」
エバはシェリルの言葉に肩をすくめると目を閉じて見せた。
エバとシェリルがガヤンの詰め所に近付いていくと、倒れている男とそれを取り囲む5人の男達、それから椅子に座って眺めているガヤンの男が松明の明かりにゆらゆらと照らされて見えた。
「エバ、左側から頼む。」
「ああ。」
シェリルが独り言のようにつぶやくと、エバも前を向いたままぼそっと応えた。
シェリルは取り囲んでいる男達の配置を確認すると、男達を殺すとしたらどうやって殺すかシミュレーションを始めた。そしてすぐにその目途をつけた。
恐らくエバもシミュレーションを終了させているだろう。
「ガヤンが助けてくれると思ったら、大間違いでした!」
取り囲んでいる男の1人があざけるようにそう言うと、残りの男達がふざけた様子で笑った。
「おい、目の前で騒ぐな。」
椅子に座ったガヤンの男がそう言った。
シェリルはガヤンの男を知っていた。
昼間ロミタスを連れてここを訪れた時に話をした、ルードという名前の男だ。若いのにおでこが広いのが特徴的だった。
男達に取り囲まれて地面に倒れているのは中年の親父で、顔面を殴打されたのだろうか、鼻血を出していて、その血が服に飛び散っていた。
「何弱い者いじめしているんだ。」
シェリルが男達に声を掛けた。
「ああ。なんだ。」
シェリルにお尻を向けている男がそう言って、振り返った。
振り返った男はシェリルを見て目を大きくさせた。
「夜中にこんな可愛いお嬢ちゃんが何をしているのかな。俺に襲って欲しいのかな?」
男はわざと卑猥な顔をシェリルに向けた。
確かに、女一人で出歩くにはとても危険な時間帯だった。
「どうしても急ぎの用があってね。お前達は何をしているんだ。」
シェリルはそう声を掛けながら、振り返った男から見て左手側に立った。
エバは逆に男から見て右手側に足を止めた。
「だからさあ、お前馬鹿なの。俺が我慢してやっているのが分からないの。それともお前、俺に襲って欲しい痴女なの?」
そう言うと男達はわざと下品に笑った。
すると別の男がシェリルの前に立っている男に声を掛けた。
「おいゲーリー。この女だ。バークを殺したのは。」
するとシェリルの前に立っていたゲーリーという男は、声を掛けた男の方に顔を向けた。
「テッド、本当か。」
ゲーリーは後ろのテッドと呼ばれた男を見ると、テッドは頷いて見せた。
ゲーリーは信じられないといった表情でシェリルを見た。
すると、今度はテッドとは別の男がゲーリーに声を掛けた。
「ゲーリー、この男だ。リタを殺したのは。」
男の声掛けにゲーリーが顔を向けると、ゲーリーに声を掛けた男は顎でエバを示した。
「何だと。」
ゲーリーはそう言うと黙ってしまった。
「どうした?何をしていたのか話す気になったか?」
シェリルはゲーリーに声を掛けた。
「関係ねえよ。」
ゲーリーは小さくそう言った。
ゲーリーの目が泳いでいた。何か頭で考えながら迷っているようだ。
ここで決着をつけてしまうのが一番良いな。シェリルは思った。
こいつらは子爵の命令でロミタスを捕まえようとしていた奴らだ。ここで逃がしても、後から私達を襲ったり、倒れているおじさんが襲われたりするだろう。
ただ、ここで決着をつけるとなるとエバは殺してしまうだろうな。
エバは弱い者いじめをする者に容赦をしない。
弱い者いじめをするのであれば、当然反撃されて殺されることも覚悟してやっているのだと。だから殺されても文句は言えないのだと、エバはそう考えているのだ。
それに目の前の男はどうみても成人したいっぱしの男だ。
もし人として未熟なのだとしても、それは自己責任だとエバは考えるだろう。
だが、もしも・・・もしも、暴力沙汰は起こしたとしても、これまで人を殺した事がないということであれば、ここで人生を終わらせてしまうのは酷ではないか。
シェリルはゲーリーを睨みつけると、話し掛けた。
「お前さぁ、そうやって弱い者をいじめて、これまで何人も人を殺して来たんだろう?私も人を殺して来たから分かるのさ。あんたも同じ人殺しだってね。」
ゲーリーは黙ってシェリルの言葉を聞いていたが、シェリルが何を考えているのか分からず、相変わらず目を泳がせていた。
シェリルは続けて言った。
「同じ人殺しなら分かるだろう。確かにあんたの仲間は私に殺されたかもしれない。だが、あんたがこれまで弱い者をいじめて殺してきた人の数を考えてみろ、1人、2人、人が死ぬことが何だと言うんだ。大したことではないだろうが。」
シェリルはそう言いながら口元に笑みを浮かべて見せた。
ゲーリーは黙ってシェリルを見下ろしていた。そして何か考えているようだった。
そしてシェリルを見つめたまま口を開いた。
「この女、可愛い顔をしてとんでもない女だ。人殺しの匂いを嗅ぎ分ける魔女。」
ゲーリーはそう言って腰の剣に手を添えた。
「ああ、確かに俺も人殺しさ。それに相当なクズ人間さ。だが、あんたも相当なクズだな。」
そう言ってゲーリーが腰の剣を抜き放った。
だが、同じその瞬間に、シェリルは電光石火で腰の剣を引き抜くと、そのままゲーリーの喉元に斬り付けた。
ゲーリーは左手側から高速で迫るシェリルの剣に反応し、シェリルの剣を避けようと頭を逸らそうとした。
しかし同時にゲーリーは、右手側からも剣が高速で迫っていることを認識した。視界の端に高速で迫る剣が映ったのだ。
エバの剣だ。
シェリルが電光石火で斬り付けるのに、ほんの僅か、コンマ数秒遅れてエバも剣を斬り付けた。
シェリルの剣に反応してしまったゲーリーは、エバの剣に反応することができない。
結局ゲーリーは、前からシェリルの剣に、後ろからエバの剣に首を斬り裂かれた。
ゲーリーの首が小さな放物線を描いて宙を飛んだ。
雌雄剣。
この戦術はそう呼ばれている。
一方が先に相手に斬り付ける。そして、ほんの一瞬遅れてもう一方が斬り付ける。それを相手の左右に分かれて、しかも、相手の左右の視界のギリギリの位置からこれをやると、容易に斬られてしまう。
最初の攻撃に反応してしまうと、もう後の攻撃には反応できない。
そもそもエバとシェリルの斬撃は速すぎて、斬られるのを認識してから避けられるものではないから、先と後の両方の攻撃を認識したとしても、何もできずに斬られてしまうことも普通だった。
シェリルに反応すればエバが、エバに反応すればシェリルが。
さらに、必要であれば片方が足を、もう片方が頭という具合に上下に揺さぶりをかけることもできた。
これをやられると、相手が経験を積んだ戦士であったとしても、数秒も持たない。
もっとも、この戦術をやるには二人の連携が重要だったが、エバとシェリルの連携は完璧だった。
エバとシェリルの二人がゲーリーの前まで歩いてきた時、二人が左右に分かれて足を止めたのも、始めからこの戦術で殺すつもりであったからだ。
その事に気付けなかった時点で、ゲーリーの敗北は決まっていたと言って良かった。
ただそれは、武術家と一般人の違いでもあった。
武術家と一般人の違いで大きいのは、武術家は常に戦うことを想定しているということだ。
笑顔で話をしている時でも、目の前の相手と間合いを取り、襲い掛かって来た場合のことを想定しているし、街の通りを歩いている時であっても、こちらに歩いてくる人が襲い掛かって来た場合のことを想定している。
故に背後に人が立つことは、武術家はとても不安を感じることだった。
一般人から考えると頭がおかしいのではないかと思ってしまう程度であるが、それは武術家にとっては日常的な習性であって、自然なことであった。
なぜなら人は、想定していないことに対しては反応できずに停止してしまう性質があるからだ。
緊急時において、反応できずに停止してしまうということは死を意味する。
だから戦うことを想定することを習性としてしまう、自然に考えてしまう程度に身につけなければ自分の身を守ることはできないし、ましてや他人の命を守ることなどできやしないのだ。
シェリルはゲーリーの首を斬り裂くと、時計回りに歩みを進めて、ゲーリーの後ろに立っている男に斬り付けた。
ゲーリーの後ろに立っていた男は、呆気に取られてしまい、全く動くことができずにゲーリーと同じようにエバとシェリルの剣に首を斬り裂かれてしまった。
おそらく目の前のゲーリーの首が飛んだ状況を見て、頭が混乱してしまったのだろう。
まさかこんなにあっけなく、しかも一瞬で目の前に立っていた仲間の首が宙を飛んで、そして少しの猶予もなく、次の瞬間には自分が襲われることになるとは思ってもいなかったのだろう。
シェリルとエバは、そのまま時計回りに3人目、4人目も容易くその首を刎ねた。
最初にシェリルが剣を抜いてからまだ4秒しか経っていなかった。
そしてシェリルは、最後の5人目に向かって歩みを進めようとした。
シェリルは最後の5人目を知っていた。ロミタスをリンチしていた野盗の一人で、テッドという男だ。
テッドはエバ達を牽制するように、剣を前に突き出して持っていた。
「助けてくれ!」
すると突然、シェリルとエバの前に男が転がり出て来た。
シェリルとエバは足を止めた。
「助けてくれ。お願いだ。」
転がり出て来た男は、詰め所の軒先でイスに腰掛けていたルードという名前のガヤンの男だ。
「何のつもりだ。」
シェリルがルードに向かって言った。
「助けてやってくれ。俺の弟なんだ。」
シェリルはルードの言葉を聞くと小さくふっと息を吐いた。そして言った。
「だめだ。そいつは道中で私を襲った男だ。そして今また私を襲おうとした。ここで逃せば3度目がないとは言い切れない。」
私は、私の甘さのせいで大事なものを失う訳にはいかない。ここは妥協できない。シェリルはそう考えていた。
自分の甘さで、自分が命を落とすだけであれば構いやしない。それは自己責任だ。
だが、自分の甘さのせいでマリーウェザーやアレンティーに危害が及んだり、私と出会ってしまったばっかりにビリーにまで危害が及ぶようなことは絶対に許してはいけない。
しかも、ビリーはロミタスを助けた時に私と一緒にいたから、目の前にいる弟のテッドに顔を知られているのだ。
あんたが弟を大事に思っているように、私にも自分の命より大事なものがあるのだ。
ルードはシェリルの表情を見て、シェリルの決心が固いことを悟った。
ルードの表情はますます強張った。
ルードは慌てて後ろを振り返ると、後ろに立っている自分の弟を見た。
するとルードは、弟が持っている剣を奪い取ると、そのまま遠くに放り投げた。
そして次の瞬間、ルードは弟の顔面を殴り付けた。
兄に殴られたテッドは力なく後ろにひっくり返った。
次にルードは、ひっくり返った弟の腕を掴んで逆を取り、地面に抑え込んだ。
「あが!」
弟のテッドが痛みでうめき声を上げた。
ルードは弟のテッドを抑え込んだままシェリルを見上げた。そしてシェリルを睨みつけると叫ぶように大きな声で言った。
「この男は、傷害の罪でガヤンが捕らえた!お前達が手出しすることは、断じて許さん!!」
シェリルはテッドを少しの間黙って見下ろしていたが、静かに、だがはっきりと言った。
「だめだ。お前はさっき、弟がおじさんに暴力を振るっていたのを止めることもなく見逃してやっていただろう。今は私が目の前にいるからそんな態度を取っているが、いなくなれば弟を逃がしてしまうやもしれん。信用できない。」
だがシェリルの言葉を聞いてもルードは怯まなかった。
「手を出すというのなら、お前達も捕らえる。」
シェリルとルードは黙って睨み合った。
こいつは本気だ。シェリルは思った。
どちらも自分の命よりも大事なものを抱えて、一歩も引けない状況になっている。
このままでは斬り合いになる。そして、エバがルードを斬る。もちろん、地面に抑え込まれているテッドも。
だがシェリルは、ルードが目の前で見せている弟に対する純粋な思いに、心を揺さぶられずにはいられなかった。
どうせテッドが心から真っ当な人間に変わるなどということはないだろう。
こういう出来の悪い奴は、一生周りに迷惑を掛けながら生きていくんだろう。
でも、だからって何なんだ。
そうであったとしても、ルードの弟に対する純粋な思いは、けっして汚れない。
今目の前で見せているルードの純粋な思いが、何とかぎりぎり、テッドを道から転落させることなく人生を全うさせる。その可能性はゼロであるとはシェリルには言えない。
人の運命は、人と人との関わり合いの中で劇的に変化を繰り返していく。
現に今目の前で、先ほどまで悪さをする弟を見逃していた甘い兄が、弟に拳を振るっているではないか。
シェリルとテッドの関係だけであるなら、テッドはエバに斬られていただろうし、そんなことはテッドの自己責任だ。
だが、兄のルードが関わってきたことで運命は変わったのだ。
シェリルはルードに向かって言った。
「今のお前なら信用できる。だが、私が居なくなったら弟に甘さが出てしまうだろう。それはだめだ。私を信用させてくれ。そうしたら、この剣は収めてやる。」
シェリルの言葉をルードは黙って聞いていた。
「信用だと。そんなこと、どうやって。」
ルードはシェリルを黙って見て、それから周囲に目を泳がせながら必死に考えているようだった。そしてルードは改めてシェリル見ると言った。
「お前が海賊の首領で、賞金が掛かっていることは知っている。弟を見逃してくれたら、俺もお前を見逃す。」
ルードはシェリルの反応を窺った。
シェリルは目を細めると首を横に振った。
「残念だが、私は自分の賞金のことなんか気にしてはいない。その提案に乗る気はない。」
ルードは目を伏せると、また少しの間黙って考えた。そしてまたシェリルに向かって顔を上げると言った。
「弟がお前達に手出しできないよう、お前達がこの街を出るまでガヤンの牢に繋いでおく。」
シェリルの目つきが穏やかなものに変わった。
「なるほど、悪くない。後は、お前が心変わりしたとしても弟が牢から出られない工夫を考えてくれ。」
「それならその牢の鍵を、シェリルさん、あんたに預けよう。」
ガヤンの詰め所の入り口から、一人の男が姿を現した。
このガヤンの詰め所の責任者であるバクウェルという男だ。
バクウェルは入り口を出てこちらに歩いてくると、ルードに手に持っていたものを投げて渡した。
「ルード、その縄でテッドを縛っておけ。」
ルードはバクウェルから受け取った縄を手に取ると、テッドの手首に縄を掛け始めた。
「ごめんよルード兄。俺は、兄貴に迷惑をかけるつもりはなかったんだよ。こんなことになって、本当にごめんよ。」
テッドは涙を流していた。
「・・・うるさい。黙っていろ。」
そう言うとルードは、テッドの手首にぐるぐると縄を巻き付けた。
バクウェルはルードのその様子を確認して、そしてシェリルに向き直った。
「こういう時が来る事は分かっていたことなんだ。そう思いながらずるずると、俺も見逃していた。無関係のあんたを巻き込んでしまうとは。何とも面目がない。」
バクウェルはそう言ってシェリルに頭を下げた。
バクウェルの言葉を聞いてシェリルは言った。
「どうかな。それは、言い間違っているぞ。」
シェリルの言葉にバクウェルは分からない顔をシェリルに向けた。
「例えばあんたは、無関係だからといって街で無法に暴れている奴を放っておくのか。違うだろ。無関係だからというのは関係ない。」
バクウェルはシェリルの言葉を聞いて頭を掻いた。
「シェリル嬢、確かにそのとおりだな。逆に、無関係のあんたでなければ、俺やルードがテッドを見逃していたことを、それはおかしいと言うことはできなかっただろう。無関係というのは無関係だ。都合の良い言い訳だった。」
シェリルのバクウェルを見る目に優しさが現れた。
「いや、勘違いしないで欲しいんだが、私はルードを責めることはできないし、するつもりもない。ルードより私の方が優れているなんてことは、絶対にない。」
バクウェルはシェリルを興味深く見た。
シェリルは続けて言った。
「自分が大事にしている者に対して甘くなってしまうのは、大事にしていればいる程自然なことだ。ガヤンだからといってそんなことは関係ない、本質はただの人なんだからな。」
「うむ。」
バクウェルはシェリルの言葉を聞いて眉間に皴を寄せた。
「それに、一人の人を自分の思い通りに操るなんて、そんなことは絶対に無理だし、やってはいけないことだ。だから、兄であるルードに弟のテッドを品行方正な人間にしろとか、そんなことは口が裂けても言えないし、もしそうなってしまったら、テッドはテッドではなくなってしまうだろう。」
シェリルを見ていたバクウェルは視線を上向きに、真っ暗な空の方向に移した。
「私ができるのは、兄と弟の関係がおかしなことになってしまっているよと、兄弟に警告してあげることくらいだ。もっとも、テッドが私の大事にしている者に危害を加える可能性があるなら、悪いがテッドには死んでもらおうと思っている。」
バクウェルは真っ暗な空を見ながらシェリルに尋ねた。
「ならあんたは、なぜテッドを助けることにしたんだ。」
シェリルは言った。
「ルードに希望が見えたから。」
「そうか。」
バクウェルは視線を伏せると右手で顎を撫で回した。
情けない。バクウェルはそう思った。
このシェリルというお嬢さんは、ガヤンに心から失望しているし、期待などしていないのだということがバクウェルには分かった。
その証拠にシェリルは、テッドがこんな小悪党になってしまったことに対して、ガヤンがなぜ事前に防ぐことができなかったのか、などとガヤンの責任を責めることをしない。
あくまでもこれは兄と弟の個人の問題であると。
ガヤンなんぞに防ぐことなどできるものかと、諦めてしまっているのだ。
だが、それは事実だ。
俺はこれまでもルードとテッドを目の前で何度も見て来た。
それでこの様だ。
あげくにこんな可愛いお嬢さんから、お前なんか役に立たないのは当たり前だと、突き付けられてしまった。
バクウェルはガヤンとして働いてきたこれまでの実績を、全てシェリルに否定されてしまったように感じた。
だが後悔しても、もう遅いのだ。
バクウェルは顔を上げるとシェリルを見て言った。
「テッドは俺が責任をもってガヤンの牢に閉じ込めておく。そして、さっきも言ったとおり、牢の鍵はあんたに預けよう。」
バクウェルの言葉を聞いてシェリルは小さく頷くと、後ろに立っているエバを見た。
「気が済んだか。」
エバがシェリルに声を掛けた。
「まあね。」
するとエバは、シェリルに肩が触れ合う程まで近付いた。そして視線を前に向けたまま独り言のように言った。
「安心しろ。マリーウェザーもアレンティーも、テッドのようになりはしない。」
エバの言葉を聞いて、驚いた顔でシェリルは横に立っているエバの横顔を見上げた。
「一人で抱え込むな。俺もマーリンもいるだろ。」
シェリルはエバの顔を少しの間見つめると、そして言った。
「何勘違いしているんだ。お前の事が心配なんだろうが。」
シェリルの言葉を聞いて、エバは横目でシェリルの顔を見下ろすと、シェリルは首を少し傾け、はにかんでいるような表情でエバを見つめていた。
シェリルのそんな表情を見て、エバは肩をすくめると目を閉じて見せた。
エバ達はマーリン達と合流し、詰め所の前に転がっている死体の後片付けを始めた。
「その軒下のところに置いて、上から藁を被せておいてくれ。」
「了解。」
「あいよー。」
バクウェルの指示に、キッドとビリーが応えた。
「ビリーいいか。」
死体の両手を掴んだキッドが言った。
「オーケー。」
両脚を持ったビリーが応えた。
「せいの!」
そう言って二人は死体を持ち上げると、軒下まで運び始めた。
「エバ。」
ソフィがエバに声を掛けた。エバは顔を向けた。
「私も手伝うわ。」
ソフィはエバに向かって微笑んだ。
なかなか肝が据わった女だ。エバはそう思った。
「そうか。じゃあ、足側を頼む。」
エバとソフィは協力して死体を持ち上げようとした。
「ソフィ、止めてください。そんなことは私がやりますから。」
ソンドラがソフィを止めに入った。
するとソフィは、強い意志が込められた瞳でソンドラを見た。
「ソンドラこそ止めて。別に私はお姫様でも何でもないのよ。それを無理矢理お嬢様扱いして、滑稽だわ。」
ソンドラとソフィの視線が交差した。
「ソフィ、分かりました。」
ソンドラはそう言って引き下がった。
ソフィは変わった。ソンドラはそう思った。
今までは何をするにも曖昧で、“やりたい”とも“やりたくない“とも自分の意志を表に現すことはほとんどなかった。
しかし、先ほどの力強い瞳。そこにはソフィの強い意志があった。
いままでソフィの中でくすぶってきた何かが、ようやく形となって外に現れて来たのかもしれない。
ソンドラは心から嬉しさが込み上げて来るのを感じた。
マーリンとマリーウェザーとアレンティーとルーの4人も、それぞれが手足を1本ずつ持って協力して死体を運んでいた。
「お兄様が非力なのは理解していますが、もう少し力を込められないのですか?」
アレンティーの問いかけにマーリンが嫌そうな顔をした。
4人が運んでいる死体となったゲーリーは、結構な重量があった。
「それが、男なんだからという意味合いで言っているのであれば、性的差別だと言わせて貰おう。」
マーリンはまるで腰の曲がった老人のような、へっぴり腰の格好でそう言った。
「いいえ、年長者だからという意味合いです。」
アレンティーが言い返した。
「そうか、それは下から突き上げる類の新しい差別だと言っておこう。」
「もう、すぐそこまで運ぶだけなんだから、下らないこと言ってないでさっさと運ぼうよ。」
マリーウェザーが二人の会話を遮った。
「マリーウェザー、下らないことを言おうが言いまいが、運ぶ時間に大きな影響は与えないぞ。現に、私の腕は今、限界を迎える。」
そう言うと、マーリンの腕からゲーリーの腕がすっぽりと抜け落ちてしまった。
ゲーリーの上半身は地面に落ち、地面との間に発生した摩擦によってずりずりと抵抗が生じた。
「ちょっとお兄様、勝手に限界を迎えないでください。」
マリーウェザーが、ゲーリの右足を掴んだままマーリンに抗議した。
「さすがはお兄様。肉体的な能力に対する頼りなさは、半端ではない。」
アレンティーがマーリンを評価した。
「うむ、お前達の言い分は筋は悪くないんじゃないか。」
全く悪気のない様子でマーリンが頷いて見せた。
「ふふふ。」
マーリン兄妹のやり取りを見て、ルーは右手を掴んだまま笑いをこらえていた。
その様子を見ていたロミタスとエイリスも思わず笑ってしまった。
「どれ、俺が交代してやるとするかな。」
ロミタスはエイリスと顔を見合わせると、マーリンの所まで歩いて行き、マーリンと交代してやった。
「なるほど、つまり簡単に言うと、勘違いをして嘘を教えてしまったと、そういうことだな。」
死体を片付けた後、バクウェルはゲーリー達に乱暴されていた北門のおじさんから事情を聞いていた。
「エルファと女を見なかったかと、それで、馬も連れていると、そう聞かれたんだ。俺は勘違いをして出て行ったと言ってしまって、でも、だから謝ったんだ。戻ってきた時に。そうしたら怒って暴れ始めて。」
バクウェルは何度も同じことをおじさんに尋ねていた。
「なるほど。で、男達が北門を出て行ったのが夕刻で、戻ってきたのがついさっきの深夜でいいんだな。」
「ああ、隣町まで行って戻って来たらしい。」
「なるほど。で、おじさんは男達とはこれまで面識はないんだな。」
「門番なんで見かけたことはこれまでもあったけど、それだけのことだ。」
ガヤンの詰め所の執務室は、バクウェルと北門のおじさんだけでなく、エバ達大勢もいるため、足の踏み場もない状況になってしまっていた。
「分かりました。それではもう大丈夫でしょう。安心してお帰りください。」
バクウェルはそう言うと門番のおじさんを帰らせた。
そしてバクウェルは席に座り直すと、改めてシェリルに言った。
「少し見ないうちに、仲間を増やしましたな。シェリル嬢。」
「まあね。」
シェリルは苦笑して見せた。
「それで、・・・確認したいのですが、・・・奥にいるあなた。」
バクウェルは執務室の隅でロミタスの隣に立っているエイリスを手で示した。
「あなたは、エルファの姫君のエイリス様ではないですか。」
バクウェルがエイリスに尋ねた。
「確かに、私はエイリスです。」
エルファの森にお姫様という概念はないのだけれど。エイリスはそう思ったが、この街ではお姫様と言っておいた方が街の人の理解が早かったので、もうそのことに対して何も言うつもりはなかった。
「どうされたんですか?どうしてこんなところに。」
「バクウェル、エイリスを知っているのか。」
シェリルはバクウェルに尋ねた。
「もう3、4年程前だと思いますが、先代子爵のカーター様とご一緒にいるところを街で拝見しました。」
「エイリスは街でヤドゥイカ子爵とはぐれてしまったらしいんだ。明日子爵のところに連れて行くつもりだ。」
「そうなんですか。」
シェリルの言った言葉を確認するように、バクウェルはエイリスに尋ねた。
「そうなんです。」
エイリスは微笑んで見せた。
バクウェルは少しの間黙っていた。
「それで、シェリル嬢はガヤンに何の御用でしたか。」
気を取り直した様子で両手の指を組みなおすと、バクウェルはシェリルに尋ねた。
「実はバークに話があって来たんだ。」
「何かありましたか。」
「いやなに、バークに暴行を受けていたエルファがバークに持ち物を取られたかもしれないんだ。」
「なるほど。そちらのエルファの御仁ですな。」
バクウェルが視線を向けると、ロミタスは小さく頷いて見せた。
「シェリル嬢、そちらのエルファの御仁はどのような方か分かりましたか?重要人物でしたか。」
シェリルは軽く首を横に振って見せた。
「いや、それがまだ教えてくれないんだ。まずは失くしてしまった何かを見つけてあげなければ。」
「そうですか。」
バクウェルはまた、少しの間黙って何か考えているようだった。
「それじゃあ、バークに合わせて貰えないか。」
シェリルがバクウェルに切り出した。
「いいですよ。」
バクウェルはそう言うと、立ち上がるために上半身を起こした。
するとバクウェルは、何か思い出した様子でシェリルに言った。
「そういえば、シェリル嬢。ヤドゥイカ子爵がエイリス様を捜しているようですよ。何でも城から急に姿が消えてしまったとか。」
バクウェルはそういうとシェリルの顔を見た。
バクウェルの言葉に、この場が一瞬にして緊張感に包まれた。
だがシェリルはバクウェルの言葉を聞いても表情を変えることはなかった。
そして言った。
「何だ知っていたのか。だから言ったじゃないか、エイリスを知っているのかと。私はあえて言わなかったのに。」
「どういうことですか。」
バクウェルはシェリルの顔を見ていた。
「エイリスと子爵の間にも色々と事情はあるということだよ。それをわざわざエイリスの口から言わせるなんて野暮だとは思わないか。」
「ほう。」
バクウェルはそのまましばらくシェリルの顔を見ていた。
バクウェルとシェリルの視線が交差した。
だが、バクウェルは何か決心した表情で立ち上がった。
「確かに私が野暮だったようですな。それではバークの入っている牢に行きましょうか。」
バクウェルが先頭に立って、今いる執務室から取調室、談話室を抜け、宿直室、備品庫の扉を横に見ながら進むと、奥に5つ、牢が並んでいるのが見えた。
牢の扉は木製で、補強のため鉄の板が横向きに2本取り付けられ、小さなのぞき窓が一つ付いていた。
バクウェルはどんどん奥に進んだ。
途中、シェリルはルードとテッドが入っている牢を通り過ぎた。
のぞき窓から見た様子では、どうやらルードはテッドと話をしているようだった。
「ここです。」
バクウェルは一番奥の牢の前で立ち止まった。
バクウェルはのぞき窓から中を確認すると、鍵を開けた。
「奴は横になっています。」
するとマーリンが後ろから出て来ると、のぞき窓を覗いて中を確認した。そして、ロミタスやエイリス、マリーウェザー、アレンティーを見て頷いて見せた。
マーリンは扉に手を掛けると奥に押し開けた。
そしてマーリンが牢に入った。続いてロミタスが入り、エイリスが入ろうとしたときだった。
「私も入りましょう。」
バクウェルがエイリスに声を掛けた。
バクウェルに声を掛けられたエイリスはロミタスを見た。
その様子を見て、ロミタスは言葉は分からなくても状況を理解した。
ロミタスはバクウェルの目の前に戻って来ると、顔を近づけて言った。
「エルファの大切な物をお前に見せる訳にはいかない。」
ロミタスはバクウェルを睨みつけた。
「ダメだと言っています。大切な物なので。」
エイリスはバクウェルにそう言った。
しようがなくバクウェルは引き下がった。
「この者は、エルファの護衛です。一緒に入らせて貰います。」
エイリスはそう言うと、マリーウェザー、アレンティー、ルー、キッド、ビリーを招き入れた。
その様子を納得がいかない様子でバクウェルは見ていた。
「私も手が出せない強力な護衛だ。諦めてくれ。」
シェリルはバクウェルにそう言うと、肩をすくめて見せた。
最後に牢に入ろうとしたエイリスは、ソフィに向かって軽く手を挙げて見せた。
それを見てソフィも軽く手を挙げて応えた。
「大丈夫。危険はないんだ。若い奴を信じよう。」
エバはソフィに声を掛けた。
「そうね。」
ソフィはエバに微笑んで見せた。
マーリンとロミタス達は、全員が牢の中に入ると扉を閉めた。
「もう大丈夫ですよ。」
マーリンはエルファ語でロミタス達に言った。マーリンの言葉を聞いたマリーウェザーとアレンティーはキッド達にひそひそと囁いて伝えた。
「扉の外には声が聞こえないのか。」
ロミタスがエルファ語でマーリンに尋ねた。
「普通に会話している分には聞こえないはずです。」
マーリンは魔法で扉の前の空間を音がしない静かな空間にした。
「便利だな。・・・確か医術を研究していると言っていなかったか。」
「そうですよ。医術が本業です。」
「まだ言うか。」
マーリンはキッドに近付くと、肩を叩いて小さな声で言った。
「それでは段取りのとおりに始めましょう。」
キッドは頷くと、部屋の隅で両手を縛られ横になっているバークに向かって声を掛けた。
「起きろバーク。」
バークはキッドの呼び掛けにゆっくりと目を開けた。
のろのろとしたバークの様子を見てビリーが言った。
「コラァ!さっさと起きろ!。将軍様の御前であるぞ。」
ビリーの大声にびっくりしたバークが芋虫のような恰好のまま後ずさった。
そして目を見開いて周囲を見渡した。
バークの目の前には、ちょうど扉を隠すようにロミタスとエイリスが立ち、その両側にマリーウェザーとアレンティーが控え、一番手前にマーリンが立っていた。
そして、バークの周りをキッドとビリーとルーが囲んだ。
「ほう、結構驚いとるな。俺がロミタスとは分からないかも知れんが。」
ロミタスが独り言のようにエルファ語で言った。
するとロミタスが喋り終えるのに合わせてルーが言った。
「私は、討伐軍の指揮官。そしてこの街の領主であるロミタス将軍だ。」
「・・・」
どうやらロミタスが喋ったエルファ語を、ルーが人間の言葉に通訳しているようだ。
バークはルーの言っている意味が分からずきょとんとしていた。
「私がマーリンということは当然分からないでしょうが。」
マーリンもエルファ語で独り言のように言った。
するとマーリンが喋り終えるのに合わせてまたルーが言った。
「私は、エルファ軍の軍師マーリンである。控えおろう!」
バークは驚いた目をきょろきょろとさせていた。
「ごほ、ごほ。」
ビリーが口を押えながら大きく咳払いをした。
「えっと、次は私がエイリスを紹介するために喋る番ね。言葉が分からない筈なのに少し緊張するわね。上手くできるかしら。」
マリーウェザーがバークに顔を向けて独り言のようにつぶやいた。
すると、マリーウェザーが喋り終えるのに合わせてまたルーが言った。
「そして、この方がエルファ国の王女、エイリス王女だ。この街は既にエルファ軍によって占領された。お前達は負けたのだ。」
ルーが喋り終えると、ルーの隣に立っていたマリーウェザーがルーの耳に口元をあてて人間の言葉で囁いた。
「無理に言葉の長さを合わせなくても大丈夫だよ。」
するとルーはマリーウェザーを見て黙って頷いた。
様子を窺っていたバークは、目の前に並んでいる人の中で唯一知っているエイリスに向かって尋ねた。
「何を言っているんだ。エイリス、これはどういうことだ。」
エイリスはソフィと一緒に城に閉じ込められて暮らしていた時、バークがよく子爵のところに金をせびりに来ていたのでバークのことを知っていた。
「バーク、あなたが信じようが信じまいが関係ありません。ただし、目の前で起こっていること、これは夢ではありませんよ。」
エイリスが人間の言葉でバークに言った。
バークは黙っていた。
「まだ分かんねえのか?この街はエルファ達に占領されたんだよ。」
ビリーがバークに呆れた様子で言った。
「俺達はエルファ側に着いたのさ。」
キッドも続けてそう言った。
バークは呆気に取られていた。そして独り言のように言った。
「馬鹿な。」
するとバークに向かってビリーが言った。
「馬鹿はお前だ、バーク。将軍様の顔をよく見て見ろ。見た覚えがあるだろうが。」
バークは改めてロミタスの顔を見ると目を見開いた。
「お前は、あの時の。」
バークが驚いた様子でそう言った。
「そろそろかな。」
ロミタスが独り言のように言った。
「まだです。私が合図してからです。」
ロミタスの隣に立っていたアレンティーがすぐにそう言った。
するとビリーはバークに近付くと、バークを上から見下ろして言った。
「よくも将軍様をリンチにして、死ぬ程の大怪我を負わせてくれたな。」
バークの顔から血の気が引いて顔が青くなっていた。
「死ぬ程の大怪我なんて、殺すつもりなんかなかったんだ。」
バークをあえて無視するとビリーは言った。
「将軍様は戦争犯罪人を捜している。一つは将軍様をリンチにした奴を、そしてもう一つは子爵の奥様を殺した奴を。」
バークはビリーの言葉を聞いて黙り込んだ。
「バーク、あなたがやったんですね。将軍様に暴力を振るったのも、子爵の奥様を殺したのも。」
エイリスがバークに言った。
「違う!違うんだ。俺じゃないんだ!」
バークは必死になって言い訳を考えているようだった。
そんなバークの様子を見て、ビリーとキッドは顔を見合わせると、後ろのアレンティーを見た。
アレンティーは小さく頷くとロミタスに言った。
「出番です。」
「良し。」
ロミタスはアレンティーに頷いて見せると、ゆっくりとバークに近付いた。
「マーリンよ、バークに礼をする機会を与えてくれたこと、心から感謝する。」
そういうとロミタスはバークにおもむろに近づくと、右足を大きく後ろに引き上げた。そしてその右足を勢いよく振り下ろすとバークの腹を激しく蹴り上げた。
ロミタスの蹴りはバークの腹にめり込んだ。
「あがっ!」
バークは大きな呻き声を上げると、ロミタスから少しでも離れるように、反対向きに転がってロミタスに背を向けると足を抱え込んで縮こまった。
その様子を扉の小さなのぞき窓から見ていたバクウェルが言った。
「おい、大丈夫か。」
「ああ、あれは見せキックだ。」
不安そうなバクウェルにエバがそう言った。
「そうね、あんな蹴り方は見せキックだわ。」
ソフィも納得した素振りでそう言って見せた。
「見せキック。」
バクウェルが分からない顔をした。
「つまり、演技よ。」
ソフィが見せキックについて説明した。
「演技。」
「ダルケスではあんな蹴り技は使わないわ。素人が使う見せキックよ。その証拠に激しく蹴ったように見えるけど音がしていないでしょう。大袈裟に痛いふりをしているだけよ。」
ダルケスというのは、華麗な蹴り技が特徴的な武術の一つで、ソフィはダルケスの使い手だった。
ソフィは大したことではないというように、バクウェルに肩をすくめてみせた。
ソフィのその姿がまるでエバの真似をしているようだった。
するとソフィは、肩をすくめた格好でエバを見ると、ニコッとした。
エバは肩をすくめると目を閉じて見せた。
「どうした、1発蹴っただけでもう降参か?俺には何発も蹴りを入れていたくせにか?」
ロミタスは背を向けて縮こまっているバークを見下ろしてエルファ語でそう言った。
するとロミタスが喋り終えるのに合わせてルーが人間の言葉で言った。
「バークは有罪。バークは生きたまま狼の餌とする。」
ルーがそう言うと、ビリーとキッドが続けて言った。
「どうやら判決が出たな。」
「おー怖い、狼に生きたまま内臓を喰われるがいい。」
キッドとビリーが憐れむような表情でバークを見た。
「ちょっと、待ってくれ。子爵は、ヤドゥイカ子爵は捕まったのか。」
バークは痛みをこらえながらキッドに聞いた。
「何で子爵が捕まるんだ。子爵はお前が悪いと言っていた。だからお前を捕まえに来たんだ。」
「違う。俺じゃない。子爵だ。悪いのは子爵なんだ。」
「そんなの口で言うのは誰でも言える。信用できるか。」
ビリーがバークを一蹴した。
「証拠がある。証拠が・・・でかい証拠があるんだよ!」
バークのその言葉を聞いて、キッドとビリーは顔を見合わせた。
ビリーは近くのマリーウェザーに近付いて耳に囁いた。
「第2段階に行く時分か?」
マリーウェザーはビリーの言葉を聞くと、マーリンに近付いて耳に囁いた。
「第2段階に進めますか?お兄様。」
「うむ。」
マーリンはマリーウェザーの言葉を聞くと、ロミタスとエイリスを見た。
「言葉が分からなくてあれなんだが、上手くいっているのか。」
ロミタスがマーリンにエルファ語で尋ねた。
「ええ、ほとんど即興劇なのに、本当にみんな上手くやっていますよ。これから第2段階に進めようと思います。エイリスさん、お願いしますね。」
マーリンのその言葉にロミタスとエイリスは頷いて見せた。
するとマーリンはコートの内側にいくつもついているポケットから木の枝を何本か取り出すとマリーウェザーに手渡した。
マリーウェザーは次にルーに木の枝を渡しながら囁いた。
「嘘発見器を使うわよ。」
ルーは頷くとバークに顔を向けると言った。
「バークが嘘をつくかも知れないので、嘘発見器を使います。」
ルーはそう言うと、持っている木の枝を皆が良く見えるように腕を伸ばして差し出して見せた。
「これはエルファの国で使われている最新の嘘発見器です。これをバークの耳の穴と鼻の穴に挿しなさい。」
キッドとビリーはルーから木の枝を受け取ると、嫌がるバークの耳の穴と鼻の穴に小枝を差し込んだ。
「や、やめろ!ふっ、ふが。」
バークの耳の穴と鼻の穴から小枝が飛び出していた。
「ごほ、ごほ、ごほ。」
ビリーとキッドが口を押えながら大きく咳払いをした。
マリーウェザーはまたルーに近付いて囁くように耳打ちした。
ルーはマリーウェザーの話を聞き終えるとバークに向かって言った。
「バークに挿したその枝は、エルファの国に生えているウソの木の枝だ。ウソの木は人がついた嘘を見分ける力を持っている。」
あれは医術に使うレスティリという薬木の枝だ。アレンティーはそう思ってマリーウェザーを見ると、マリーウェザーも目でウソの木なんて知らないと言っていた。
ルーはバークに続けて言った。
「バークが嘘をついたら、バークに刺さっている枝が嘘を感知してマーリン軍師が持っているその枝に伝える。すると、その枝が左右に大きく揺れる。」
ルーがそう言うと、マーリンは自分が持っている枝を左右にぶらぶらと揺らして見せた。
「つまり、マーリン軍師の持っている枝が左右に揺れたら、お前は嘘をついているということだ。」
ビリーがバークに言った。
「おい、ちょっと、あれは何をやっているんだ。」
バクウェルがシェリルに声を掛けた。
「ああ、あれね。エルファの医術だよ。」
「医術?」
「エルファは森の植物を使って高度な医術を使うんだ。恐らくバークが大切な品物を飲み込んでしまったとかで、やっているんだろう。」
「飲み込みか。」
シェリルは頷いて見せた。泥棒が高価な宝石などを隠すために、飲み込んで体の中に隠すことは話としてよく聞くことだった。
「エイリスから聞いたことがあるわ。エルファの森ではよくやっているみたいね。」
ソフィが聞いた話を思い出した様子でそう言った。
「ごほ、ごほ。」
エバが思わず咳払いをした。
バクウェルの表情が少し疑っているような様子に変わった。
「ふーん、やはり人間とエルファでは文化が違うね。まあ、バークに手こずっているんだろ。大したことではないさ。」
シェリルは何でもないというようにバクウェルにそう言った。
バクウェルも仕方がなく様子を見ることにした。
牢の中のバークは、鼻と耳から枝が飛び出たまま黙っていた。
「エイリスさん。」
キッドが扉の前で立っているエイリスに声を掛けた。
エイリスはキッドの言葉に頷くと前に進み出た。
エイリスはそのままバークの前に来ると言った。
「あなたが奥様を殺したのですね。」
エイリスが真剣な眼差しでそう言った。
「・・・違う。俺じゃない。」
バークが言ったその言葉を聞いて、エイリスはマーリンを見た。
するとマーリンが左手で持っていた小枝が激しく左右に揺れた。
「ああ、やはりそうだったのですね。」
エイリスは両手で口元を覆うと目を閉じた。そうしてまた閉じた目を開けるとエイリスは口元を覆ったまま。天井を見上げた。
「俺は違うって言ってるだろ。こんなの、インチキだ!」
バークは言った。
「あなた、」
突然アレンティーが人間の言葉でバークに話し掛けた。
「あなた北国の首都ルークスから来たんでしょう。違いますか?」
「何を言って。」
バークが呆気に取られてそう言った。
アレンティーは兄マーリンの持っている小枝を見た。小枝は微動だにしなかった。
「どうやらそのようね。」
バークは驚きで言葉もなかった。
「バークさん、あなたにも兄弟はいるでしょう?」
アレンティーがまたバークに尋ねた。
「・・・。」
バークは何も言わず黙っていた。
アレンティーは兄マーリンを見た。すると小枝は動くことはなかった。
「そう、兄弟がいるのですね。では、兄弟は男ですね。」
バークは驚きで呆気に取られていた。
アレンティーはマーリンの小枝が大きく揺れていることを確認した。
「おや、女性でしたか。それではその女性は年上ですね。」
そう言うとアレンティーは、マーリンの持っている小枝が動いていないことを確認した。
「そう、お姉さまがいらっしゃるようですね。ルークスにお住まいということでいいですか。」
「やめろ!姉さんは関係ないだろう!」
バークが必死な形相でそう言った。
そんなバークを見て、アレンティーは言った。
「ウソの木は、あなたの言った言葉から嘘を感知するような、そんな安っぽい物ではありません。あなたが何を言おうが言いまいが、心の動きを感知しているのです。あなたは今、丸裸で私達の前に居る。インチキはあなたの方です。」
アレンティーがバークにそう宣言した。
バークは何も言うことはできなかった。
「バーク、何で殺したのですか。何で奥様を殺したのですか。」
エイリスはバークを見下ろしてそう言った。
「子爵が殺せと言ったんだ。しようがなかったんだ。」
バークは目を伏せてそう言った。
マーリンの持っている小枝は動かなかった。
「子爵が悪いと言うのですか。あなたは悪くないと。」
「そうだ。」
バークはそう言った。マーリンの持っている小枝は動かなかった。
エイリスは言葉を失ってしまった。
「子爵の言うことに逆らったら、あなたは子爵に殺されるのですか?」
突然ルーがバークに尋ねた。
「・・・殺されるということはないと思う。」
バークは視線を伏せたままそう言った。
「それじゃあ、あなたが奥様を殺そうとしたとき、奥様はあなたを殺そうとしたのですか。」
「・・・たぶん違うと思う。」
「なら、あなたが奥様を殺そうとしたとき、奥様はあなたに私を殺して欲しいとお願いをしたのですか。」
「・・・そんなことは、していない。」
「なら、あなたが奥様を殺そうとしたとき、奥様は助けて欲しいとあなたにお願いしたのではないのですか。」
「・・・。」
バークは黙っていた。マーリンの持っている小枝は動かなかった。
するとルーの瞳から急に涙が溢れた。
「じゃあ、何であなたは奥様を殺してしまったの?殺す必要はなかったじゃない。奥様を殺さなくても、あなたの命が脅かされる訳でも、何でもなかったじゃない。」
ルーは感情が溢れて涙が止まらなかった。
「奥様は助けて欲しいと言った。もっと生きたいと言った。そんな奥様の命を奪う権利はあなたには何もなかったのに。それなのにあなたは奥様を殺した。」
ルーは下を向いて目を合わせることもできないバークを激しく睨んだ。
「どこが子爵のせいなのよ。全部自分のせいじゃない。あなたは本当の人殺しだわ!」
そう言って泣いているルーをエイリスが抱きしめた。
「ありがとう。私も同じ気持ちよ。ありがとう。」
ルーとエイリスの様子を見たビリーは天井を見上げて涙を堪えた。そして、バークの側にしゃがみ込むとバークの髪の毛を掴んで顔を起こした。
ビリーはバークを睨みつけると言った。
「さっき言っていた“でかい証拠”というのは何だ。正直に言わないと、この鼻から出ている枝を脳味噌に叩きこむぞ。」
バークは少しの間ビリーを見つめると言った。
「俺はもうどのみち処刑決定だ。言うかよ。」
バークはビリーにそう言った。
「何だとこの野郎!」
ビリーが怒りに任せてそう言った時だった。その瞬間、キッドがバークの頭をぶん殴った。
「お前の姉さんをぶっ殺すって言ってるのが分からないのか。」
キッドはバークを見下ろしてそう言った。
キッドはシェリルの言っていた言葉が頭に浮かんだ。
男性は人が生きるために必要な暴力を担うのに女性と比較して優れている。
今がその暴力を担う時だ。
「お前がやったのと同じことをやってやるよ。」
キッドはそう言ってバークに馬乗りになると、何度もバークをぶん殴った。
キッドはエバの気持ちがまた少し理解できた気がした。
暴力を振るう罪は男が背負えばいい。泣いている女には背負わせたくはない。
バークの鼻の穴と耳の穴に差し込まれた小枝は、殴られた衝撃で弾け飛んだ。
「分かった。言うから止めてくれ。」
バークは頭をふらふらさせながらそう言った。
キッドは殴るのを止めた。
そして少しの間バークは黙っていたが、とうとう口を開いた。
「俺は北の神聖王国の首都ルークスから今の子爵と一緒にこの街に来た。今の子爵は偽物だ。マックレというルークスの元高級役人さ。前代の子爵の弟でも何でもない。」
「やはりそうか。」
ビリーはそう言って歯を食いしばった。
「俺が戦争犯罪人で処刑されるのに、マックレが助かるなんて納得いかねえ。」
バークはうつろな目で天井を見上げながらそう言った。
少しの間ぼんやりと天井を見上げていたバークは、馬乗りになっているキッドを見てまた口を開いた。
「それからもう一人道連れにしたい奴がいる。」
「誰だ。」
「ボアロという大金持ちだ。そもそもマックレと俺は、ボアロに誘われてこの街に来たんだからな。」
「そのボアロって奴はどこにいる。」
ビリーがバークに尋ねた。
「ちょうど今この街に来ているはずだ。マックレと一緒に子爵の城にいるだろう。」
バークは目だけをビリーに向けるとそう言った。
「だが、マックレとボアロが口裏を合わせてお前が嘘をついていると言ったらどうする。逃げられちまうだろ。」
キッドがバークにそう尋ねた。
「馬鹿だな、そんなのルークスに行けばマックレを知っている奴は何人もいる。お前を知っている奴を連れてきてやろうかと脅してやればいちころさ。」
バークはそう言って目を瞑った。
「なるほどな。」
「頼んだぜ。俺だけ地獄行きなんて絶対ありえねえからな。それから、姉さんには手を出すな。殺すぞ。」
バークは目を瞑ったままそう言った。
「いい気になってんじゃねえよ。だが、このまま大人しく地獄に行くっていうのなら手を出さないでいてやる。」
キッドはそう言って、立ち上がった。
そしてマーリン達は牢を出るために、牢の入り口の扉を開けた。
「くそっ、どこで間違ってこんなことになっちまってよ。」
小さな声でバークはそう言うと、静かにむせび泣いた。
牢の扉が開くとマーリン達が出て来た。
「どうだった。」
シェリルがマーリンに尋ねた。
「想定どおりでしたよ。それに、ビリーとキッドとルーが大活躍してくれました。」
「そうか。」
シェリルはルーを見た。
「ありがとう、ルー。」
ルーはシェリルの顔を見て、何か言おうとして、でも言えなくて、少し間があって、そしてようやく言った。
「シェリルさんがやろうとしていることが大事なことなんだって、ようやく分かった気がして。」
シェリルはルーの頬に手で触れた。
「とても難しい事だね。他人の気持ちと同じ気持ちを共有するというのは。そもそも自分は他人ではないから、全く同じ気持ちになるということは不可能だ。」
シェリルは目を細めてルーを見た。
「でも、エイリスの気持ちに触れ、奥様の気持ちを考えて、エイリスと同じ気持ちを共有することができたとき、本当に心から助けてあげたいと思うことができた。そういうことじゃないのかな。」
シェリルはルーに微笑んだ。
「相手の気持ちを考えて、同じ気持ちを共有する。すると、高く分厚く立ちはだかっていたはずの無関係という壁は、一瞬にして消え去る。ルーとエイリスの間を隔てていた壁が、一瞬にして消え去ってしまったように。」
「シェリルさん。」
「誰かの特別な存在になることって、同じ気持ちを共有できれば、そんなに難しいことではないんだよ。結局のところ問題は、自分自身の心なんだね。」
「うん、分かった。」
「ルー。」
マリーウェザーがルーに声を掛けた。
「私もルーと同じ気持ちよ。もし、ルーが言わなかったら私が言っていたわ。」
「本当。」
マリーウェザーは頷いて見せた。
「そうよ、だって私は、命令に従ったからって責任は無いとは考えていないからね。」
マリーウェザーがシェリルの口調を真似てそう言った。
シェリルもルーも思わず笑ってしまった。
すると控えめに立っていたアレンティーがルーに言った。
「ルー、説得が凄かった。論理性に感情が上手く融合していて見事だった。」
アレンティーはそう言って少し口をすぼめると親指を立てて見せた。
アレンティーもこんなおどけた顔をしたりするんだ。ルーはそう思った。
「アレンティーだって、ウソの木の説明がかっこよかったよ。」
ルーの言葉にアレンティーは照れて少し下を向いた。
「あれは、お兄様の事をインチキ呼ばわりするから、つい言ってしまった。でも、本当はウソの木なんてエルファの森には生えていない。」
そういってアレンティーはルーにニコッとした。
「ふふ、そんなことだろうと思ってた。」
ルーもアレンティーを見てニコッとした。
シェリルはそんな3人の元気な様子を見て、安心して思わず笑顔になった。
「大丈夫か。」
エバはキッドとビリーに声を掛けた。
さすがに二人の表情には疲れが現れていた。
でもビリーは笑った。
「俺がやっつけてやりましたよ。」
「そうか。」
エバは口元を緩めると目を閉じて見せた。
「エバさん。」
キッドが声を掛けた。
エバは目を開けてキッドを見た。
「やっぱり、俺も男なんだなって、思い知りました。」
キッドはエバにそう言った。
するとエバは少しの間キッドを見ていて、そして言った。
「キッドが見せたその本気が、男の強さの原点。持って生まれた男の性質って奴さ。」
エバはそう言うと、キッドの肩をポンポンと叩いた。
「エイリス」
ソフィがエイリスに声を掛けた。
「ソフィ。」
エイリスはソフィに応えた。
ソフィにはエイリスの白い顔が余計に白く見えた。
「大丈夫。」
ソフィはエイリスを気遣った。
「私の事?」
エイリスは、ソフィがまず奥様の事を聞くのではないかと思っていたので、自分の事を聞かれたのかどうか聞き返した。
「そうよ。」
ソフィは当たり前の事のようにそう言った。
「大丈夫よ。」
エイリスは力なく微笑んで見せた。
「でも凄く顔が白いわよ。」
「そんなに白い。」
エイリスは頬に指を当てた。
「ええ、あの時の奥様みたい。」
「あの時って、あの蛇の時?止めてよ。」
エイリスがソフィの肩を叩いた。
それはエイリスとソフィと奥様が、この街の北側にあるじいさん岩の丘に建っている屋敷に住んでいた時の話。
ある日の朝、奥様の部屋に小さな蛇が迷い込んだことがあった。
奥様が甲高い叫び声を上げて、ソフィが駆け付けたのだが、ソフィにもどうすることができずに二人でベッドの上に避難して、床で蠢く蛇を見ながらキャーキャー大騒ぎしていた。
するとそこへ、一番華奢で蛇なんて触れそうもないエイリスが部屋に入ってくると、エイ!と少し甲高い声で気合を入れると、絨毯の上を這っていたヘビの頭を鷲掴みにしたのだ。
そしてエイリスは鷲掴みにした蛇の頭を、わざわざ二人の側まで寄って来て見せながらこう言った。
「小さくてまだ子供よ、食べられないわ。」
その時の奥様がエイリスを見つめる顔が、血の気が失せてしまって本当に白かった。
「あの時は私も本当にびっくりしたわ。」
ソフィが笑顔でそう言った。
「ふふ、エルファのお姫様の正体がばれてしまったわね。」
エイリスも微笑んでそう言った。
その事件以来3人は、持ち前のお転婆振りを遠慮なく露わにして、人目につかないようにこっそりと、屋敷周辺の林や丘を歩いて巡った。
先代のヤドゥイカ子爵のカーター様は寛大で、3人の好きにすることを見逃してくれた。
自由は制限されていたけれど、3人で過ごした日々は幸せだった。
エイリスは知らないうちに穏やかな気持ちを取り戻していた。
エイリスの顔色も良くなっていた。
「私達、奥様の分まで、前に進んでいこう。」
ソフィがエイリスにそう言ってニコッとした。
「そうね、そう思うわ。」
エイリスもソフィにニコッとした。
少し離れたところで、バクウェルはエバ達の様子を黙って見ていた。
バクウェルの様子に気付いたマーリンはバクウェルに近付いた。
「とりあえず今日は終わりました。」
マーリンがバクウェルに話し掛けた。
人間の言葉が話せるエルファがいたのか。バクウェルはそう思った。
「どうでした。大事なものは見つかりましたか。」
バクウェルはマーリンに尋ねた。
「いや、それがだめでした。なかなかしぶといですね。」
「そうですか、だめでしたか。」
それにしては、こいつらが醸し出しているやってやったという雰囲気は何なんだ。バクウェルはエバ達の様子を見てそう思った。
やはりおかしい。
こんな夜中に、こんな大勢で来たということは、それだけ緊急で重要なことなのだ。
こんなにもエルファが多くいて、その中にヤドゥイカ子爵が捜索しているエイリス様もいる。そしてバークに暴行を受けていたエルファの男は、元気な様子でエイリスの側に立っていて、しかもとても親しいようだ。
何かヤドゥイカ子爵に関して重要な事が起ころうとしているのではないか。
そしてそれにはエルファが関係している。
だが、シェリルは私に情報を一つも与えるつもりはないようだ。
今日の夕刻、シェリルがバークを馬に引きずらせて連れて来た時は、何か分かったら連絡すると言っていた。
だから俺だって、俺なりにこの問題を考えていて、明日の午後、子爵に話を聞くため城に伺う約束も取り付けたのだ。
すると、ヤドゥイカ子爵が急に姿を消してしまったエイリス様を捜索しているというではないか。
事が動き始めた。そう思った。
だからシェリルの連絡を待っていたのに。
それがどうだ、シェリルは手の平を返したように何も言わなくなった。
いや、言葉は話しているが、本当のことは何もない。
始めから俺を利用することだけを考えていて、俺に利用価値がなくなったということか。
お役御免ということか。
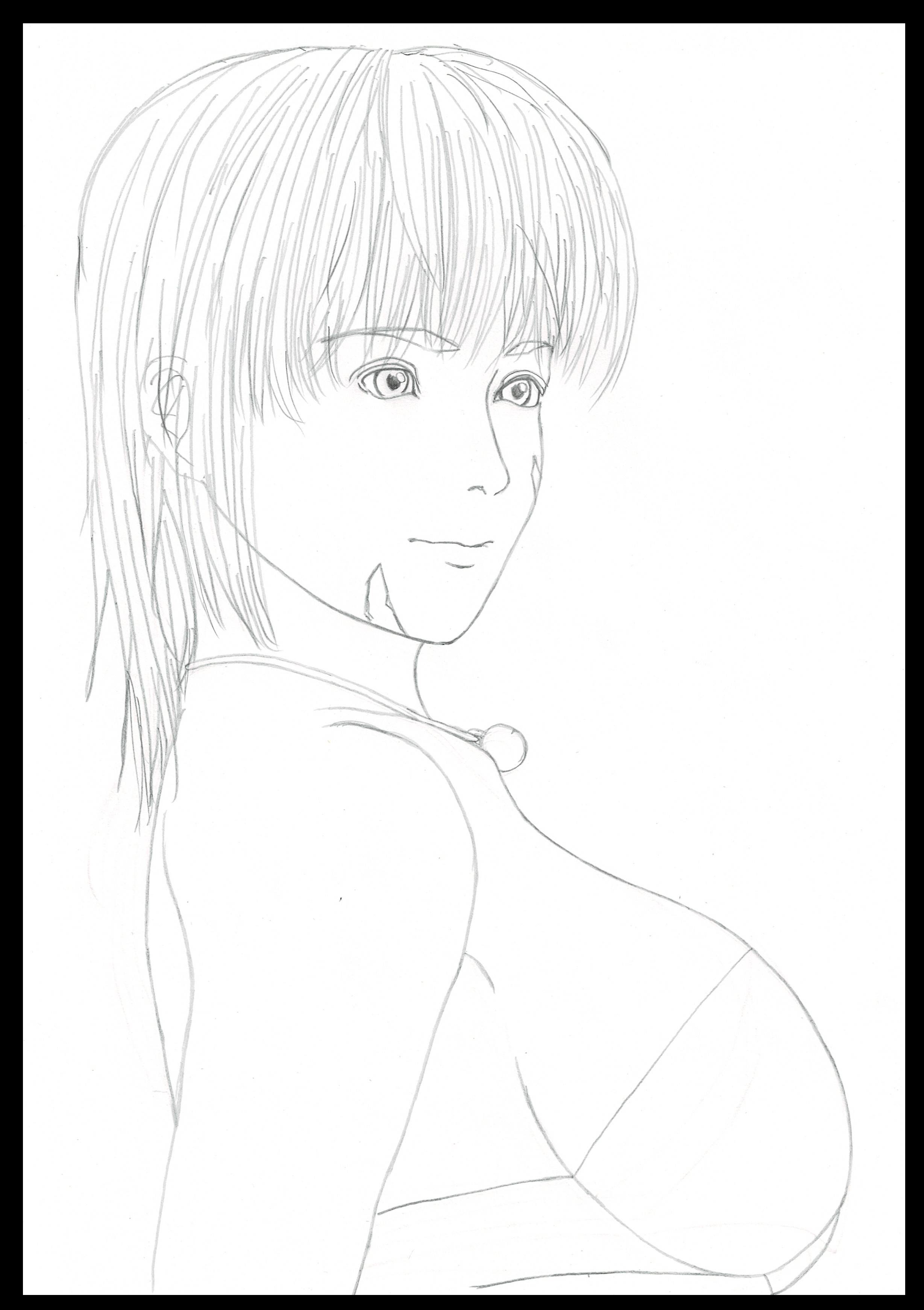
「バクウェル、ありがとう。邪魔をしたな。」
シェリルがバクウェルに声を掛けた。
「残念だったな、大事なものが何かは知らんが。」
「また伺うよ。」
「そちらのエルファの御仁がどのような方か分かれば教えてください。それから、これがテッドの牢の鍵です。」
「ああ、分かった。」
シェリルはようやく笑顔を見せると、バクウェルから鍵を受け取った。そして皆に行くぞと目配せすると、さっさと詰所から出て行った。
このまま行かせていいのか?バクウェルはそう思った。
確かに俺は清廉潔白なガヤンなどではない。
金を受け取ることだってあるし、仲が良い者は見逃してやることもある。
そうさ、尊敬されるガヤンではないさ。
だが、それでもこの街を20年以上も守って来たんだ。
それを、その全てを、こんなお嬢さんに否定されてしまって、それで黙って行かせるのか。
きっと、あのお嬢さんは分かっているのだ。
ガヤンが抱えている矛盾も、その仕事の辛さも。
分かっていてガヤンに失望しているのだ。
ガヤンなんぞに防ぐことなどできるものかと、諦めてしまっているのだ。
だから、余計に悔しい。
ふざけるなよ!俺だって、やる時はやるのだ!
「うおおおおおおお!」
突然バクウェルが大きな唸り声を上げたのでシェリル達は振り向いた。
すると、バクウェルは両肩を怒らせながらずんずんと歩いてくると、シェリルの目の前で止まった。
そして、シェリルの腕をがっしり掴むと詰め所の方に引っ張って行こうとした。
「おい、ちょっと、痛い。」
シェリルが抵抗するとバクウェルは振り向いて言った。
「このまま行かせられるか!」
シェリルは腕を内側から半円を描くように動かすと、バクウェルの掴んでいた腕はすんなりと外れた。
「どういうことだ。」
「どういうことだだって、それはこっちの台詞だ。こんな、こんな嘘ばかりの茶番で納得できるか。」
シェリルはだまってバクウェルを見つめていた。
バクウェルは続けた。
「お前だって言っていたじゃないか、何か分かったら連絡すると。それがどうした、まだ何も分かっていないだと、どうみても分かっているだろう。」
バクウェルはエイリスの横に立っているロミタスを手で示した。
「俺が愚かなのは認める。だが、これでも、この街を守って来たんだ。そこはお前にだって負けるつもりはない。」
シェリルはバクウェルの必死な姿を見て考えていた。
ガヤンであるバクウェル達に、本当のことは話すな。
シェリルはガヤンに向かう道すがら、皆にそう指示した。
ガヤンという組織は国王の直轄組織であり、地方領主からは独立した存在だ。
とはいいつつも、領主と結びつくガヤンは多い、というか普通と言ってもいい。
ガヤンが違法者から徴収した罰金は、半分を国王に、4割をガヤンの運営費に、そして残りの1割を協力金として領主に渡すのが一般的だった。その替わりに領主は、領内でガヤンが独自に活動することに寛容だった。
だから、ガヤンであるバクウェル達に話したことによって、その情報を裏で子爵に渡されてしまったり、バクウェル達が子爵と手を組んで障害となることは回避しなければならない。
しかも、シェリル達は奥様を殺した罪で子爵を勝手に断罪しようとしているのだ。
法に基づいて処罰するバクウェルがそのことを知ったら、どうすれば良いのかと、バクウェル自身が苦しむだけだろう。つまり、答えは出ているのだ。
しかしシェリルは、何か胸の中に詰まったような感覚に戸惑っていた。
シェリルの言葉を信じて待っていたバクウェルを裏切ってしまうことが、街を守りたいという純粋なバクウェルの思いを裏切ってしまうことが、それが本当に最良の選択なのだろうか。
するとシェリルの目の前に突然エバが出て来た。
「分かった。だが一つ条件がある。俺達の話を聞いた後で、やっぱり聞かなかったことにするというのは無しだ。その時は俺が、お前を斬る。」
エバはバクウェルに向かってそう言った。
バクウェルは目の前に立ったエバの顔を見た。
若い、そして内気で大人しそうな男だ。何の圧力も凄味も感じられない。バクウェルはそう思った。
だが、バクウェルは見ていた。この男はあっという間に4人の男の首を刎ねた男だ。
だからこそ、目の前のエバが不気味だった。
バクウェルとエバの視線が交差した。
「どうした、分かったか。それとも止めるか。」
バクウェルは唾を飲み込んだ。そして言った。
「分かった。話の内容が俺にとって都合が悪くても、お前達の邪魔にはならないと約束しよう。」
バクウェルの言葉を聞いて、エバは後ろに立っているシェリルを見ると言った。
「だそうだ。」
エバはシェリルに向かってそう言うと、肩をすくめると目を閉じて見せた。
シェリルは、そんなエバを目を細めて見て、それからエバに微笑んだ。
「だそうだ、じゃねえよ。」
エバ達は、バクウェルが知りたがっていた現状を説明してあげると、ガヤンの詰め所を出て、宿屋に向かって歩いていた。
エイリスとソフィも一緒だった。
明日一緒に行動するから、一緒の宿に泊まった方が都合が良いだろうということになった。
ただ、ソンドラは娼館に帰ると言った。
そこでみんなで娼館を経由して、ソンドラを送ってから宿に帰ることにした。とは言っても、それで特に遠回りになるということでもなかった。
また、宿の部屋の人数は6人部屋だったから、もし全員が宿に泊まるとなると、女性1人が男部屋に入ることになるから、もしかしたらソンドラはそこを気にしたのかも知れなかった。
「それじゃソフィ、おやすみなさい。」
「おやすみなさい、ソンドラ。」
ソンドラはソフィと挨拶をすると娼館の中に入って行った。
ソンドラを送った一行は宿に向かって歩き始めた。
「ふふ。」
歩きながらマリーウェザーは、突然思い出したように吹き出した。
「何笑っているの。」
ルーがマリーウェザーに言った。
「ごめん。ルーの顔見ていたら思い出しちゃって、だって、ルーったらいきなり“控えおろう!”なんて言うんだもの。」
マリーウェザーのその言葉を聞いて、途端にビリーも笑い始めた。
「控えおろうなんて、どこの国の言葉だよ。」
ビリーがこらえ切れない様子でそう言った。
「だって、マーリンさんが言った言葉と同じくらいの長さにしなくちゃって、何か言わなくちゃ怪しまれるかもって思ったんだもの。」
ルーが口を尖らせてそう言った。
「ああ、そういうことか。でも、なんで控えおろうなんだ。」
ビリーの言葉にルーは少し頭を捻ると言った。
「将軍様だから?」
ルーはビリーにそう言った。
「そうなの?」
ビリーが不思議そうな顔をした。
「だけど、ウソの木には参ったな。」
キッドが歩きながら頭の後ろで手を組んだ格好でそう言った。
「ああ、俺も笑いを堪えるのに必死だったぜ。」
ビリーもにやけた顔でそう言った。
「でも、バークがウソの木をインチキ呼ばわりした時はちょっと厄介だったな。」
キッドがビリーにそう言った。
「確かに、あれはやばかった。」
ビリーが頷いて見せた。
「アレンティーがゴツンとお仕置きしてくれたおかげよね。」
ルーがアレンティーにそう声を掛けた。
「助かったぜ、アレンティー」
ビリーがアレンティーに向かって片目を瞑って見せた。
「そんな。」
アレンティーが控えめに喜んだ。
「いや、本当にアレンティーがいなかったら大変なことになっていたぜ。」
「そうそう、もしアレンティーがいなかったら。」
そう言ってキッドとビリーは少しの間想像を巡らせた。
「もしアレンティーがいなかったら、バークのケツに枝挿してたな。」
キッドがにやけた顔でそう言うと、ビリーが下品に笑った。
「なら俺は前のソーセージの方にも枝挿してたな。」
続けてビリーがそう言うと、二人は声を上げて可笑しそうに笑った。
「もう、止めてよ。」
「汚い。」
「ばっちい。」
「私の頭の中を汚さないで。」
女性たちが次々と非難の声を上げる中、キッドとビリーは満足そうにさらに大きな声で笑った。
若者達は、一仕事やり終えた爽やかな達成感を味わっていた。
「あのさ。」
シェリルがエバに話し掛けた。
「ん。」
「最後のあれは、私に任せておけば良かっただろ。なんでわざわざ私の前に出て来たんだよ。」
「さあな。」
エバはとぼけて見せた。
「大体、ガヤンを巻き込んでどうするんだ。今頃バクウェルは頭を抱えているぞ。」
シェリルはキッド達を眺めながら独り言のように呟いた。
「いいんじゃねえの。」
「ん。」
シェリルはエバの顔を見た。
「頭を抱え込みたかったんだろ、あいつが。お望みどおりだ。」
エバは真っ直ぐ前を見ていた。
シェリルはエバの言葉を聞いて、一息の間エバの横顔を見た。そして前を向いた。
「そんな奴がいるか。」
シェリルが決めつけたようにそう言った。
「いるだろう。」
そう言って、エバは思わず“シェリルお前だ”と心の中で思ったが、ここで言ってしまっては元も子もないと思って言わなかった。
「どこに。」
「さあな。」
エバはまたとぼけて見せた。
「なんだそれ。」
シェリルは肩をすくめると両手の平を見せた。
エバ達は宿屋までもうすぐそこまでのところに来ていた。
エバ達の長い1日がそろそろ終わりを迎えようとしていた。
ガヤンの詰め所から宿に戻ったエバ達は、宿の玄関に鍵が掛けられていることを確認すると、ビリーの案内で裏口に周った。
ビリーは、裏口のすぐ隣にある窓に取り付けられた木製の鎧戸を、ゴンゴンと叩いた。
ビリーが何度か鎧戸を叩くと中から声があった。
「誰だ。」
「ビリーだよ。扉を開けてくれよ。」
ビリーがそう言ってから少し時間があって、裏口の扉が開いた。
「どうしたビリー、遅いじゃないか。」
開いた裏口から、顎髭がもじゃもじゃとした中年のおじさんが顔を見せた。
「急な用があったんだよ。」
ビリーがそう言うと、もじゃもじゃのおじさんは眠そうにあくびをしてから、ビリーに手招きした。
「使用人のトロマおじさん。」
ビリーはシェリルにそう言うと、裏口をくぐって中に入った。
そしてビリーに続いて、エバ達は順番に裏口をくぐった。
「ありがとう、トロマおじさん。」
中に入ったシェリルがおじさんにそう言うと、おじさんは眠そうだが、それでも優しい顔つきで頷いた。
エバ達が全員中に入ると、トロマおじさんは裏口の扉に閂を掛け、裏口のすぐ隣にある自分の部屋に入って行った。
エバ達は、真っ暗な宿の中を進んで、自分達の部屋に向かった。
キッドもビリーも宿の構造を良く知っていたので、進むのに困ることはなかった。
エバ達は、部屋の前に辿り着くとお互いにお休みと言い合って、男性と女性に分かれて部屋に入った。
「やっぱりちょっと、このままじゃ不便ね。」
女性達は適当に自分のベッドを決めて腰掛けたが、油紙の貼られた小さな窓があるものの、あまりの暗さに荷物の整理もできなかった。
「悪いけど,ルー、ランプに火を灯せないかな。」
シェリルはルーにお願いした。
「広間の暖炉に火が残っているかもしれないから、行ってくるわ。」
ルーは天井に吊るされたランプを取ろうとしたが、それこそ暗くて良く分からなかった。
「私が取ってあげる。」
マリーウェザーがベッドから腰を上げた。
「マリーウェザー、見えるの?」
ルーはマリーウェザーの黒い影に尋ねた。
「ふふ、実はエルファは夜でも結構見えてるのよ。」
「へー、そうなんだ。どれくらい見えてるの。」
ルーは驚いた様子で近くに寄ってきた黒い固まりのマリーウェザーに聞いた。
「そうね。」
そういうとルーはマリーウェザーの手が自分の頬に触れたのを感じた。
「ここがルーのほっぺで、ここがルーの鼻。」
マリーウェザーは軽くルーの鼻を摘まんだ。
「凄く見えてるやん。」
ルーがそう言って笑った。
マリーウェザーは天井から吊るされたランプを取った。
「一緒に行こう。」
「うん。」
ルーとマリーウェザーは一緒に部屋の扉を開けて廊下に出た。
2人は廊下の突き当りの扉を開けて広間に出ると、暖炉の火は落とされていたものの、まだくすぶっている薪が残っていたので、マリーウェザーがはさみのような鉄製の火箸で薪を摘まんで、ルーがランプを近づけて火を点けた。
この暖炉は、壁を隔てて厨房と兼用となっており、厨房側の大きな鍋には、まだたくさんお湯が入っているのをルーは見つけた。
2人はランプを持って部屋に戻った。
「ただいま。」
「おかえり。」
部屋に戻ると、マリーウェザーはルーからランプを受け取ると、天井から下がっているフックに吊るした。
「やっぱりランプがあると全然違うね。」
皆ベッドに腰掛けながらランプの明かりを見ていた。
「この宿屋は大丈夫だけど、ランプの下にベッドを置いている宿屋もあるんだよ。」
シェリルが両手を太腿に挟んだ格好で、ランプを見ながらそう言った。
ランプにはガラスの覆いはついていなかったので、何かの拍子で転倒したりすると火事になる恐れがあった。
この時代の街の建物は、煙突や暖炉は石を積んで造られていたものの、建物自体は木造で、壁も土壁であるのが普通だった。
さらに、建物同士が同じ壁を共有していて、たくさん連なった建物が大きな1つの建物のような状況であったので、火事になって火の勢いが大きくなってしまうと、燃え尽きるまで手の付けようがないということが良くあった。
ただこの部屋の場合は、ランプフックの下には誰のベッドも被っていなかった。
「そんな宿屋があるの。」
ルーがシェリルに驚いた顔を向けた。
「あるよー。ねえ、マリーウェザー。」
シェリルが自分のベッドに腰掛けようとしていたマリーウェザーに言った。
「あるある。結構みんなうっかりなんだよね。」
マリーウェザーはそういいながらベッドに腰掛けて足をぶらぶらさせた。
「うっかりだなんて、そんな悠長な話ではないでしょう。」
ルーが信じられないという表情をしてそう言った。
ルーが真剣なのも無理はない。
火事は、洪水や地震という自然災害と同じで、どうしようもないもの、誰にも責任はないものと考えられてはいたが、もし、誰かが火を点けたとなれば、魔女や悪魔に憑りつかれてしまった人と同じように、公開で火あぶりの刑に処せられる程の重罪だった。
「本当ね。街に住んでいるのに火の扱いがうっかりだなんて信じられない。」
ソフィはルーの言葉に頷くとそう言った。
「だけどね、うっかりは普通にあるよ。」
シェリルがそう言ってルーとソフィを見た。
「誰も火を点けてやろうと思ってうっかりしている訳ではなく、例えば、女将さんはしっかり者でも使用人がうっかりしてしまったり、子どもが遊んでいる間に動かしてしまったり、掃除のために少しの間と思って動かして忘れてしまったりと、まあいろいろと考えられる訳だ。」
シェリルがそう言って苦笑いをルーとソフィに向けた。
「人間だからね、うっかりを失くすことは不可能さ。それに、自分で気付かないからこそ、うっかり何だからね。」
「そっか。」
ルーがそう言って頷いた。
「そんなうっかり者の人間であるのに、火は絶やさないように常に身近なところにいくらでもあるだろう。しかも何の覆いもされずに。これで火事にならない方がおかしい位だ。」
シェリルの言葉を聞いてソフィは、何だかシェリルが火事を防ぐつもりがないように感じて心が苛ついた。
「街が燃えてしまってもしようがない。そういうこと?」
ソフィはシェリルに意地悪な口調で言った。
「ソフィはそう思うかい。」
シェリルは逆にソフィに聞き返した。
「まさか。」
「なら私と一緒だね。」
ソフィはシェリルが何を言っているのか分からなかった。
「人のうっかりを失くすことはできない。でも、身近な火を絶やすわけにはいかない。そんな状況で火事を防ぐにはどうすれば良いと思う。うっかりしてしまった人を信じられないと拒否すれば、なくなるのかな?」
なるほど。
ソフィはシェリルを見て頷いた。
するとシェリルはアレンティーに顔を向けた。
「アレンティー、例えば、アレンティーが宿に泊まろうとして部屋のベッドの上にランプがかかっていたらどうするかな。」
アレンティーはシェリルを見つめながら少しの間考えると言った。
「やっぱり、まずベッドをランプにかからないように動かして、それから宿の女将さんに危ないのでベッドを動かしましたと伝える。」
シェリルはアレンティーにニコッとした。
「うん、私もそうする。」
そう言ってシェリルは次にソフィを見た。
「ソフィもアレンティーと同じ考えじゃないか。」
「そうね。私もそうすると思うわ。」
ソフィはシェリルに軽く頷いて見せた。
「じゃあ、私と一緒だね。」
シェリルはソフィにニコッとした。
シェリルが微笑む顔を見て、なぜかソフィは胸の中がほんわかと温かくなる感じがした。
「うっかりするなんて、けしからん!そう言って女将さんを叱りつけるのも選択肢の一つではあるけれど、その後、何かの理由でベッドを動かすのを忘れられてしまったら、火事を防ぐことにはならないし、そうしたら、また女将さんを呼び付けて叱りつけないといけないだろう。それってお互いに気分が悪いよ。それよりも、自分ができるのであれば先にベッドを動かしてしまう方が、火事を確実に防ぐことになる。それに・・・、」
シェリルはそこで一旦話を切ると、皆を見渡して、そして言った。
「その方が、上品でかっこいい女性だと思わないか。」
シェリルがそう言うと、ルーもマリーウェザーもアレンティーも笑って頷いた。
シェリルは皆の笑顔に目を細めると続けた。
「私は別に、何でも自分が気付いたらやるべきだとか、自分ができないことでもやるべきだとか言っている訳ではないよ。人の命を守るためだとか、目の前の危険を放っておいたら大変なことになるかもしれない。その時こそ、誰かがやるのではなくて、自分がやる。誰かが守るのではなくて、みんなで守るんだ。」
ソフィはシェリルの言葉に頷くと、シェリルに向かって言った。
「私もただのうっかり者だったわ。ごめんなさいね、シェリル。」
シェリルはソフィの言葉を聞くと笑顔を見せた。
「なら私と一緒だね。」
シェリルとソフィは顔を見合わせるとふふっと小さく笑った。
「ねえねえ。」
するとマリーウェザーがシェリルやルーに声を掛けた。
「寝る前にベッドを魔法で綺麗にしようと思うんだけど。みんなもやって欲しい?それとも、やって欲しくない人いる?」
マリーウェザーがそう言うと、ルーが目を輝かせてマリーウェザーを見た。
「それってもしかして“ベッドリフレ“。」
ルーが尋ねるとマリーウェザーが笑顔で頷いて見せた。
ベッドリフレとは、エルファの森を旅立ったマーリン兄妹が、旅に必要な資金を稼ぐために考え出した商売の名前だ。藁のベッドをノミと匂いから解放し、快適に眠れるようにするもので、ベッドを元気にリフレッシュ。で、ベッドリフレとマーリンに名付けられた。
「嬉しい。絶対見たい!寝てみたい!」
ルーが浮かれてわくわくした様子でそう言った。
「ベッドリフレって何?」
ソフィがシェリルに尋ねた。
「エルファの伝統の技でベッドを綺麗にしてくれるのさ。ダニもノミもいなくなるよ。」
シェリルの説明を聞いてソフィは瞳を大きくさせた。
「そんなことができるの!凄い。マリーウェザー、私のベッドもお願いできないかしら。」
ソフィはマリーウェザーに両手を合わせてお願いした。
「マリーウェザー、私のベッドもお願い。」
シェリルもマリーウェザーにお願いした。
「任せて、お安い御用だわ。だけど、アレンティーにも手伝って貰うからね。」
マリーウェザーがそう言うと、シェリルとソフィはアレンティーを見た。
「アレンティー、お願いします!」
アレンティーは恥ずかしそうに微笑んだ。
「大丈夫。私とマリーウェザーでやれば難しくないから。」
アレンティーはそう言うと、床に置いてあった自分の背負い袋を膝の上に置くと、何かを探し始めた。
同じようにマリーウェザーも自分の背負い袋の中を探し始めた。
「ねえ、どうやってやるの。」
ルーが自分のベッドから立ち上がって、マリーウェザーのベッドまで来ると横に座った。
「私が使うのは燻製の魔法。」
「燻製?」
ルーが好奇心一杯の目でマリーウェザーに聞いた。
マリーウェザーはちらっとルーを見て、また背負い袋の中を探った。
「本当に燻製にする訳じゃないけどね。あったあった。」
そういうとマリーウェザーは、小さな袋と黄銅色をした金属のスプーンを取り出した。
するとそこへアレンティーもやって来た。
ルーがアレンティーを見ると、アレンティーは大きな葉っぱを手に持っていた。
「アレンティーは葉っぱを使うの?」
ルーがアレンティーに聞いた。
「私が使う魔法は蒸し焼きの魔法だから、バナナの葉を使う。」
ルーが瞳を大きくさせた。
「面白い。二人とも違う魔法を使うんだね。」
「たぶん結果は同じ。だけど、私は蒸し焼きの魔法の方が言葉の発音が優しくて好き。」
アレンティーが大きなバナナの葉から半分顔を覗かせながらそう言った。
「そうなんだ。面白いな。」
ルーが笑顔でそう言った。
「私から先に始めていい?」
マリーウェザーがアレンティーに聞くと、アレンティーは小さく頷いた。
するとマリーウェザーは、小さな袋の中から木のおが屑を摘まみ出すと、スプーンの上に乗せた。
「このおが屑はね、エルファの森にあるりんごの木のおが屑なの。」
そう言ってマリーウェザーはおが屑を乗せたスプーンを自分のベッドの上に置いた。
「燻製の魔法は、もともとはエルファの森で豊かな収穫を祝う収穫祭が元になっているの。森の神様に捧げるお供え物がいつまで経っても腐ることがなくて、それが元になって燻製の魔法が生まれたんだって。」
「へー、そうなんだ。」
ルーが感心したように頷いた。
「知ってた?」
マリーウェザーの話を聞いて、感心した様子のソフィがエイリスに聞いた。
「知らない。」
エイリスが答えた。
「だよね。」
ソフィが何気なくそう言った。
「だよね?」
エイリスがそう言って器用に片方の眉を吊り上げると、細めた目でソフィを見た。
「いやいやいや、違うよ。その“だよね”じゃなくて、“一緒だよね”のだよね。」
ソフィが慌ててそう言った。
「あー、そうだよねえ。私に匹敵する程のお転婆娘のソフィが、自分の事を差し置いて“だよね”はないよね。」
エイリスが偉そうに装うとそう言った。
「だよねえ。」
ソフィがそう言って苦笑いした。
「それじゃあ、魔法を掛けてみるね。」
マリーウェザーはルーに向かってそう言うと、アーモンドの形をした小さな盾“タナク”を胸の前に掲げた。魔法を掛けるのに必要な魔法の杖にあたるのが、この小さな盾“タナク”だった。
するとマリーウェザーは、ロミタスの傷を魔法で癒した時と同じように、両手足を柔らかく円のような軌跡で動かしながら、小川の流れるように、囁くように歌った。
「・・・サセヤサセヤ、ノシス、スズイセソ、シヨマエサ、ノモス、スビナサ、ニゼサワサワ・・・」
マリーウェザーの側にいたルーには、マリーウェーザーがそんな風に歌っているように聞こえた。
するとベッドの至る所から白い煙が立ちのぼり始め、その煙がベッドを包み込みんだ。
そしてマリーウェザーが持っていた盾でその煙に触れると、ベッドを包み込んでいた煙は一片にふわっと消えてしまった。
「はい、できた。」
マリーウェザーはルーに向かって首を傾げるとおどけた表情をした。
「面白い、素敵。もうできたの。」
ルーが目をキラキラさせて目の前のベッドを触った。
「もう綺麗になっているわよ。ちょっと薪でいぶしたような匂いがするけど。」
マリーウェザーがそういうと、ルーはベッドに鼻を近づけてベッドの匂いを嗅いだ。
「本当だ。煙の臭いがする。でも、気にはならないわね。」
普段から薪を燃やして暖を取ったり料理をしたりしているので、ルーには煙の臭いは気にならなかった。
「次は私。」
アレンティーはルーにそう言うと、違うベッドの上にバナナの葉を置いた。
「この蒸し焼きの魔法は、ここから遥か南の海に浮かぶザムーラ島に行った時に、現地の精霊使いの人から教えて貰った。ザムーラ島では芋をバナナの皮に包んで蒸し焼きにして食べていて。その蒸し焼きにする時に、料理をする女性達がおいしくなれ、おいしくなれと歌を歌っておまじないを掛ける。それが元になってこの蒸し焼きの魔法が生まれたらしい。」
アレンティーは側に来たルーにそう説明すると、左腕にいくつか着けている金色の丸い腕輪を右手で摩ると、両手を自分の頭の上で交差させた。
そして左腕をぶるんと勢いよく震わせると、付けている丸い腕輪がぶつかり合って、楽器のようにシャランと音を立てた。
アレンティーはその場でくるくると回りながら、両手を伸びやかに広げるように動かすと高い声で囁くように歌った。
「・・・マカシキカバー、セカン、サマサマナビク、クモノ、サマサマエカ、アパアパ・・・」
アレンティーの側に来たルーには、アレンティーがそんな風に歌っているように聞こえた。
するとベッドのシーツがだんだん膨らみ始め、まるでお湯でも沸かしているようなシュッ、シュッという音がベッドから鳴り始めた。
そしてアレンティーが、ぷっくりと膨らんだシーツに腕輪の着いた左手で触れると、ポンという音がして、シーツは一片にしぼんで元に戻った。
「はい、おしまい。」
アレンティーはそう言ってルーに向かって首を傾げると、最後に両腕を互いにぶつけてシャンと腕輪を鳴らした。
「凄い!何て素敵なの!」
ルーはアレンティーが踊り子か何かのようで、また、南の国を想像させる異国情緒の溢れる歌と踊りに心を奪われてしまった。
それに静かで控えめなアレンティーと、その異国情緒溢れる踊りとのギャップがさらにその魅力を高めていた。
「まるで外国に行ったような気分だわ。どこの国だっけ?」
ルーがアレンティーに笑顔を見せた。
「ここから遥か南の海に浮かぶザムーラ島。この魔法は高い発声と、言葉の発音が優しい気持ちになるので好き。」
アレンティーもルーに笑顔を見せた。
「本当に、発音が優しい感じで可愛いわね。」
エイリスがソフィに言った。
「同じ効果の魔法でも、地域の文化の違いによって魔法の言葉も、掛け方も全く違うのね。面白いわ。」
ソフィが感心したように頷いた。
するとマリーウェザーがソフィに顔を向けた。
「面白いでしょ。例えば、明日の天気を知る魔法も、地域によっていろいろやり方があるのよ。」
マリーウェザーがそう言うと、ルーが分かった顔で手を挙げた。
「知ってる。明日の天気はなあに、でしょう。」
ルーはそう言いながら右手をくるっくるっと回した。
すると、ルーを見て不思議そうにマリーウェザーが言った。
「明日の天気はなあに、というのは凄く良く分かるんだけど、その、右手のくるっくるっというのはなあに?」
するとルーが驚いた顔をした。
「えっ、ソーセージを焼いているんだけど。何で。」
ルーがまた右手をくるっくるっと回しながらそう言った。
「えー、それってソーセージを焼いているの、可笑しい!」
マリーウェザーが笑顔でルーを真似てくるっくるっとした。
「あっ、それソーセージを焼いていたんだね。」
横で見ていたソフィも笑顔でそう言った。
「えー、もしかして解るのは私だけなの。」
ルーも笑顔でそう言った。
「ねえ、ソーセージを焼いてどうやって天気が分かるの。」
アレンティーが笑顔でルーに尋ねた。
「焼いて、パキッと皮が裂けちゃったら雨、裂けなかったら晴れ。」
「へーっ、面白い。じゃあ、ポンって弾けちゃったら?」
マリーウェザーがルーに聞いた。
「嵐かな。」
ルーが少し首を傾(かし)げてそう言った。
「わあ、とても危険なソーセージだ。」
マリーウェザーがそういうと、みんな可笑しそうに声を出して笑った。
ルーも一緒に笑った。
「でもね、安心して。」
笑い終わったルーは、そう言って皆を見渡した。
「嵐が出たらね、食べちゃえばいいから。」
ルーは皆にそう言った。
「そうか、食べちゃえば無かったことになるんだ。」
マリーウェザーがそう言って小さく頷いた。
「でも、それだと晴れになるまで焼いて食べれば良いのでは。」
アレンティーが静かにそう言った。
「それは・・・、もう魔法ではなくて、ただの食いしん坊ね。」
エイリスがそういうと、また皆で可笑しそうに笑った。
「ねえ、みんな大事な事を忘れてるだろ。ベッドは6つあるんだから、マリーウェザーとアレンティーに残りの4つも綺麗にして貰おうよ。」
シェリルが笑顔で皆に言った。
「本当だ、すっかり忘れていたわ。」
ルーはそう言うとてへへという表情をした。
「それでは、さっさと終わらせてしまいましょう。」
「そうね。」
マリーウェザーとアレンティーはそう言うと、手分けして残りの4つのベッドに魔法を掛けて回った。
魔法を掛けること自体は、ものの数秒で終わるから、マリーウェザーとアレンティーの二人はあっという間に4つのベッドに魔法を掛けた。
「アレンティー、ありがとう。」
「ありがとう、マリーウェザー。」
「ありがとう、こんなに寝るのが楽しみなのは生まれて初めてだわ。」
皆はマリーウェザーとアレンティーにお礼を言った。
「どういたしまして。」
マリーウェザーとアレンティーは皆にニコッとした。
「ちょっとエバさん、隣の部屋が凄く楽しそうなんですけど。」
既にランプの消えた真っ暗な部屋で、裸でシーツにくるまっているビリーは、隣に寝ているであろうエバに声を掛けた。
しかし、特にエバから返事はなかった。
隣の部屋を隔てている壁は土壁でできていて、隣の部屋の話声が良く聞こえた。
「何でこんな深夜なのに、女性達は楽しそうにはしゃいでいるんですかね。」
懲りずにビリーがエバに声を掛けた。
すると少し間があって、エバが横になったままビリーに言った。
「お前がはしゃぎたいということは分かったが・・・、ビリー悪いが、俺はお前とどうやってはしゃいだらいいのか想像がつかないんだ。」
エバがそう言うと、ビリーを挟んでエバの反対側で寝ていたキッドが思わず笑い声を上げた。
「ちょっとエバさん、何で俺がエバさんとはしゃぐんですか。俺だって想像つかないですよ。」
「そうか。じゃあ寝るか。」
エバはそう言うと、シーツを引き寄せて目を瞑った。
「ああもう、俺は隣の部屋に行きたいんだ。」
「おいビリー、諦めて寝ろ。」
キッドがそう言うと、ビリーは寝返るとキッドの方を向いた。
「お前だってルーの所に行きたいだろ。」
ビリーはキッドをからかうように言った。
キッドは目を瞑ったまま少し考えると言った。
「いや、別に行きたいとは思わん。」
「嘘だろ、何でだよ。」
ビリーが疑っている口調でそう言った。
「真っ暗で何も見えん。」
キッドの言葉を聞いたビリーはその言葉に驚いた。
「お前エロだな。しかも完全に俺を超えている。何て羨ましい奴。」
キッドは思わず目を開けた。
「勘違いするなって、そういう意味じゃない。」
キッドが疑いを晴らそうと強い口調で言った。
「いや、言い訳はいい。」
するとビリーの言葉を聞いて向かいに寝ているマーリンが尋ねた。
「ビリー、やっぱりシェリルの事が気に入っているのか。」
「シェリルさん、好きです。一緒のベッドに入りたいです。」
「変態か。」
キッドがビリーにそう言った。
「変態でいいです。どうせ俺はただのえっちな人なんで。」
ビリーがそう言うと、キッドは呆れて掛ける言葉もなくなった。
「どこがいいんだ。シェリルの。」
マーリンが尋ねた。
「どこがって・・・全部です。」
「分かった。見た目だろ。」
マーリンがそう言った。
「そうだな、見た目だ、見た目。」
エバも決めつけたようにそう言った。
「見た目だけじゃないですよ。」
ビリーが強い口調でそう言った。
「じゃあ、他に何があるんだ。」
マーリンが聞いた。
「やわらかそうだし。触ったら。」
「そりゃ肉と脂肪でできているんだ。触ったら柔らかいだろう。」
エバが茶化した。
「そういうことじゃないですよ。」
「重症だなこれは。」
マーリンが言った。
「はっきり言っといてやるけど、諦めた方がいい。」
エバがビリーにそう言った。
「何で。」
ビリーが不満そうな声で言った。
「シェリルには娘が2人いる。」
「ええっ!本当ですか。」
ビリーが驚いた様子で飛び起きた。
「ああ。」
エバはそう言って飛び起きたビリーに顔を向けると続けて言った。
「シェリルと一緒になるとしたら、まずは娘に父親と認められる必要があるな。」
「その2人の娘さんは今どこにいるんですか。」
エバはもう飽きたという様子で、シーツにくるまった。
「隣にいるだろう。」
エバは目を瞑ってそう言った。
「隣に!」
ビリーは訳が分からない顔をした。
「そうだ。だから諦めて寝ろ。」
エバはそう言って眠りに入った。
マリーウェザーとアレンティーが魔法を掛け終わると、女性達は寝る支度を始めようと自分のベッドに腰掛けた。
するとシェリルは、マリーウェザーとアレンティーに向かって言った。
「マリーウェザー、アレンティー。ついでという訳でもないんだけど、髪を洗いっこしないか。」
シェリルが自分の髪の毛を引っぱって鼻に持っていくと、くんくんと匂いを嗅いだ。
「うん。いいわよ、やりましょう。」
「私も大丈夫。」
マリーウェザーとアレンティーはそう言って頷いた。
「みんなもどう?」
シェリルはルーやソフィやエイリスにも声を掛けた。
「私はいいかな。眠くなっちゃった。」
ルーは眠いことを思い出したように片目を擦って見せた。
「私も先に休ませて貰うわね。」
エイリスは履いていた靴を脱ぎながらそう言った。
ソフィもベッドに腰掛けると履いていた靴を脱ぎ始めた。
「それじゃあ、私達3人でやろうか。まずは厨房からお湯をいただいて来よう。」
シェリルがそう言うと、マリーウェザーが何か思い出したような顔をした。
「さっきランプに明かりを灯しに行った時に、大きな鍋にお湯がたくさんあったわ。」
「なら好都合だね。」
シェリルとマリーウェザーとアレンティーの3人は厨房に行くと、大きな鍋から水差しにたっぷりと湯を入れると部屋に戻って来た。
そして3人はそれぞれ自分の荷物から愛用のブラシを取り出した。
ルーやソフィやエイリスはもう寝てしまったようだった。
「まず私がマリーウェザーの髪をとかしてあげるよ。」
シェリルがマリーウェザーにそう言った。
「じゃあ、アレンティーは私がとかしてあげる。」
マリーウェザーがアレンティーに言った。
アレンティーは分かった表情で頷いた。
シェリルとマリーウェザーとアレンティーの3人は一つのベッドに横に並んで座った。
シェリルはマリーウェザーからブラシを受け取ると、マリーウェザーの髪を手に取った。
この時代、髪はまれにしか洗うことはなかったが、シェリルはベタつきや匂いが我慢できずに、週に何回かお湯で髪を洗っていた。
「相変わらずマリーウェザーの髪の毛は、猫の毛みたいに癖っ毛だね。」
シェリルはマリーウェザーの頭にブラシをあてると、髪の根本から汚れを掻きだすようにブラシを動かした。
「私はシェリル姉さんみたいにまっすぐでさらっとした髪の毛がいいんだけど。」
マリーウェザーもアレンティーの頭にブラシをあてながらそういった。
「私も。」
髪をとかして貰っているアレンティーがそう言った。
「2人ともとっても可愛いけど、そんなに気になるなら魔法を掛けてあげるよ。」
そういうとマリーウェザーとアレンティーはふふっと小さく笑った。
「シェリル姉さんも魔法が使えるなんて知らなかったわ。」
「知らなかった?使えるのよ、私も。」
そう言うとシェリルはマリーウェザーの頭を左手で優しく撫でた。
「まっすぐになあれ、まっすぐになあれ、まっすぐで素直で優しくなあれ。」
マリーウェザーは黙ってシェリルに頭を撫でられていた。
「どう?私の癖っ毛まっすぐになった?」
マリーウェザーが振り向いてシェリルを見た。
「凄くまっすぐになってる。」
シェリルは瞳を大きさせると笑顔でマリーウェザーを見た。
「本当?嘘でしょう。」
マリーウェザーは笑顔でシェリルにそう言った。
「じゃあアレンティーにも魔法を掛けてみるね。」
シェリルはそう言って今度はアレンティーの横に座ると、アレンティーの頭にブラシをあてると、髪の根本から汚れを掻きだすようにブラシを動かした。
それからマリーウェザーと同じように左手でアレンティーの頭を優しく撫でた。
「まっすぐになあれ、まっすぐになあれ、まっすぐで素直で優しくなあれ。」
アレンティーも黙ってシェリルに頭を撫でられていた。
「はい、アレンティーにも魔法を掛けたよ。」
アレンティーはシェリルを見た。
「どう、まっすぐになった?」
アレンティーがシェリルに聞いた。
「凄くまっすぐになった。2人ともまっすぐで素直で優しくなった!」
シェリルはそう言うと、マリーウェザーとアレンティーをまとめて抱きしめた。
「何それ、自分が魔法に掛かってるじゃない。」
「わあ。」
マリーウェザーとアレンティーが笑いながらそう言った。
シェリルは2人を抱きしめると、2人の温かな体温を確かめた。
体にしっかりお肉がついていることも確かめた。
そして2人の体から土の匂いや薪の燃えた匂いがすることを確かめた。
2人の心臓が一生懸命に鼓動していることが、肺がしっかりと新鮮な空気を取り込んでいることが、お腹が元気にぐぅっと活動していることが、シェリルにはとても嬉しかった。
ただただ、この2つの命が生命力に溢れていることが、なぜこんなにも愛しいのだろう。
この時代、子どもが健康に成人を迎えられるのは本当に幸運なことだった。
そもそも出産の時に、産道が広がらず赤ん坊が出て来ることができなかったり、出て来るまでに衰弱してしまい死んでしまうことは良くあったし、未熟であったり生まれた時から異常があったりで死んでしまうこともあった。
無事に生まれて来たとしても、洪水や逆に雨が十分に降らずに食べるものがなくなってしまうと、体力が落ちてしまった人々の間で謎の病気が流行りだし、そうやって流行が始まってしまうと、体力のない子どもは本当にあっけなく死んでいった。
その他にも、戦争が起こって街や村が侵略されると、両親を失ってしまって孤児となってしまって、乞食となったり、人身売買で奴隷として売られてしまったりした。
このシャロムの街の中にも、乞食をしている子供は何人も見ることができるし、街の中に入れず街の壁に寄り掛かるように座っている乞食の中にも子どもの姿があった。
そういう子ども達は、栄養が不足して体を悪くしてしまい、大抵長くは生きられなかったし、また普通に街や村の中で生活していれば無償でサリカ神殿で教えて貰えるはずの、読み書きや簡単な算数もできないから、単純労働しかできなかった。
シェリルは8歳の時に父親が行方不明になって、成り行きで父親の後を継いで海賊の首領となった。
その首領をしていた時に、シェリルが挑戦して絶望したことがあった。
それは街の裕福な人達から食べ物を暴力で奪い取って、子どもを含め食べることに困窮している人達に分け与えようとしたのだ。
そしてシェリルは思い知った。
シェリルが海賊の取り巻きを連れて街の領主に押し入ったとき、領主は自分の蔵を開けて見せてくれた。
そこには、困窮している人達を食わせてやる程の食糧は無かった。
せいぜい、領主を含め城に住んでいる兵士達が数ケ月持ちこたえる程度の食糧しかない。
困窮している人達に食糧を配れば、1ケ月も持たずになくなってしまうだろう。
つまり、そもそも街には街の住民全ての腹を満たせる程の食糧はなかったのだ。
限られた食料を奪い合うしかない。
実力のあるものが食糧を奪って、自分の大切な者に与える。
それがシェリルの住んでいる世界の現実。
その現実にシェリルは絶望した。
誰か悪い人間がいるのではない。人間が望んでいなくても、この世界が人間に奪い合うことを強制していたのだ。
餓えた子どもの腹を満たしてやることは、そんな簡単な事ではない。
両親のいないマーリン達3人の兄妹が、なんとか成人を迎えられたのは本当に奇跡的なことだ。
シェリルはマーリン兄妹と一緒に旅をして3年が経つが、マリーウェザーとアレンティーにはしっかりと食べさせて来たつもりだ。
だから、マリーウェザーとアレンティーの2つの命が生命力に溢れていることは、シェリルにとってとても愛おしいことだった。
「じゃあ次はシェリル姉さんの髪をとかしてあげる。」
マリーウェザーはそう言うと、シェリルのブラシを手に取った。
「ありがとう。今日は汗を掻いたし、髪が気になっていたんだよ。」
マリーウェザーはシェリルにして貰ったのと同じように、シェリルの頭にブラシをあてると、髪の根本から汚れを掻きだすようにブラシを動かした。
「ブラシは森ブタさんの毛でできたものが一番感触がいいね。さすがエルファの職人だ。」
3人が使っているブラシは、ここから遥か東、グラダス半島にあるバドッカという街で、エルファの職人から購入したものだ。
木製の櫛よりも痛くないし感触が良く、汚れ落ちも良い気がした。
「じゃあ、お湯で汚れを流そう。最初はマリーウェザーからね。」
3人はブラシを掛け終わると、部屋にあった桶を床に置いて、水差しに入れて来たお湯で交代して頭を流した。
流し終わって桶にたまったお湯は、その都度窓から捨てた。
「う〜ん、最高に気持ちいい。1日の汚れが洗い流される、そんな心地よさだね。」
アレンティーにお湯で頭を流して貰いながら、シェリルは満足そうにそう言った。
お湯で流し終わったら、亜麻でできたリネンの布をあてて髪の水気を吸い取った。
「さっぱりしたね。」
3人は指で軽く髪を整えると、扇子を開いてパタパタと髪を乾かし始めた。
そして3人で黙ってしばらくパタパタと髪を乾かしていた。
するとマリーウェザーが何気なくシェリルに聞いた。
「シェリル姉さんは、今までお父様に会いに行っていたんだよね。」
マリーウェザーの言葉に一瞬シェリルは視線を下に向けると一点を見つめた。そして言った。
「うん。そうだね。」
シェリルは、今日エバ達と合流するまでのおよそ4ケ月の間、エバやマーリン兄妹と別れて海賊達と一緒に行動していた。
それはシェリルが8歳の時に行方不明になった親父が見つかったからだ。
シェリルが海賊の首領をしていたオーデハーゲンの街、そしてその街のある紫の群島地域。
その紫の群島地域の最南端。壁のような大きな岩の板が立ち並ぶ断崖絶壁の誰も住んでいない筈の海域。
そこに往来する船があって、その船にシェリルの親父さんが乗船していたのだ。
そこで、誰もいない地域を往来する怪しい船が何をしているのか、そしてシェリルの親父さんが本当にいるのかどうか、シェリルのかつての部下だったオーデハーゲンの海賊達が船を出すことになった。
シェリルはかつての部下だった海賊達に誘われ、果たして親父が本物の親父かどうか、その船に乗って確かめに行ったのだった。
「それで、シェリル姉さんはお父様と会えたの。」
扇子でパタパタと扇ぎながらマリーウェザーは目を伏せてそう聞いた。
「親父には会えたよ。」
シェリルも目を伏せてそう言った。
「どうだった。」
マリーウェザーが目を伏せたまま尋ねた。
「そうだな、親父は親父だったな。」
シェリルはそう言った。
「会えて良かったね。」
マリーウェザーはそう言って一息置くと、続けた。
「でも、黙って出て行くことないじゃない。」
マリーウェザーは目を伏せたままそう言った。
シェリルもマリーウェザーを見ることができなかった。
アレンティーも下を向いて黙って聞いていた。
「ごめん。私の親父の事で迷惑は掛けられないと思った。」
「何で?」
「えっ。」
「何で迷惑を掛けたらいけないの。」
「それは。」
マリーウェザーの問い掛けに、シェリルは言葉が詰まった。
「私は迷惑を掛けて欲しかったよ。」
マリーウェザーはそう言った。
「でも、迷惑だけじゃないんだ。私は、私のせいで2人に辛い思いをさせたくないと思ったんだ。」
シェリルがまた目を伏せるとそう言った。
「いいじゃない、辛くなれば。」
「えっ。」
シェリルはマリーウェザーを見た。
「辛いってことはさ、それだけ大好きって事じゃないのかな?」

そう言ったマリーウェザーの瞳が涙で潤んでいるのを見て、シェリルははっとした。
「もし、もしもの話だけどさ、出て行ったままシェリルが死んじゃったらさ、どうするつもりだったんだよ。もう会えないじゃん。」
マリーウェザーは目を伏せたままそう言って、涙がポロポロとベッドのシーツに落ちた。
「言ってよシェリル。一人で抱え込まないでさ、言ってよ。」
マリーウェザーの言葉に、アレンティーも口を開いた。
「私もマリーウェザーの言うことに賛成。私はシェリルの言うことをきちんと理解できるつもりでいる。」
「どうやったらシェリルは私の事を信じてくれるのかな。」
シェリルは胸が締め付けられる思いがした。
シェリルは2人を抱きしめた。
私は愚かだ。
自分が悲劇のヒロインにでもなったつもりで、自分の父親との関係は自分で清算すると決意を固めた。
エバやマーリン兄妹には自分の個人の事で迷惑は掛けられない、そう思った。
それに、これまで一番大事にしてきたマリーウェザーとアレンティーがいるのに、私個人の問題を一番に優先させてしまうことに罪悪感があった。
だから、私のせいで2人にはできるだけ辛い思いはさせたくない、そう思った。
そして夜中にこっそりと一人で旅立つことにした。
でもまさか、それが2人の気持ちを傷つけてしまっていたなんて。
エバにも言われた。一人で抱え込むなって。
言われて分かった気になって、結局分かっていやしなくて、マリーウェザーの涙を見てやっと気づいた。
私だって、マリーウェザーやアレンティーが辛い時があれば、その気持ちを共有したい。
そして少しでも力になってあげたい。そう思う。
なら、マリーウェザーやアレンティーだって同じだった。
つまり、私の事を大切に思っていてくれていたんだ。
シェリルは2人を抱きしめたまま、目頭が熱くなるのを感じた。
「これからはちゃんと2人に言うから。ごめんね。」
シェリルは2人の耳元でそう言った。
大事にしているならしている程、同じくらい、きちんと気持ちを伝えなければだめなんだな。
大事にしているから黙っていても伝わるだろう、そんなのは自分の甘えなんだ。
「それじゃあ、そろそろ寝ようか。」
シェリルは明るい声に切り替えると2人にそう言った。
マリーウェザーは少し鼻をすすって立ち上がると、天井から吊るされたランプに手を掛けた。
「じゃあ、私がランプを消すわ。」
シェリルは靴を脱いでベッドに上がると、着ている服を脱いでベッドの側に立っている棒状の衣紋掛けに掛けた。そして下着姿でシーツに潜り込んだ。
「ありがとうマリーウェザー、私は大丈夫だよ。」
シェリルがマリーウェザーにそう言った。
「マリーウェザー、私もオーケーだよ。」
シェリルに続いてアレンティーがそう言った。
「それじゃあ消すね。」
マリーウェザーがそう言って、ランプの火を吹き消した。
すると部屋の中は真っ暗になった。
シェリルは潜り込んだシーツの中で最後の下着を脱ぐと、枕の下に潜り込ませた。
そして裸で膝を抱え込むように丸くなった恰好でシーツにくるまると目を閉じた。
シェリルはなぜか幸せな気持ちだった。
血が繋がっていなくたって、本当の母親でなくたって、私は絶対にできる。もっと2人に愛を注いであげられる。シェリルは心の中で強くそう思った。
そうして小さな声でふふっと笑みを浮かべると、まどろんで意識が曖昧となって眠りの世界に入って行った。
エバ達がベッドに入ってからどれ位経っただろう。
シャロムの街を覆っていた真っ暗な闇が、だんだんとその黒さを薄らぎ始めた。
まだまだ太陽は見えない。
だが東の空の果てに隠れている太陽の光が空を反射して拡散し、真っ暗な暗闇を薄め始めていた。
そうしてだんだんと東の空に白い靄が掛かり始める。
夜明けを知らせる鐘が鳴らされるにはもうしばらく時間が必要だ。
しかし特に早起きの女中は、冷たい水をたっぷりと汲むため、手に桶を持って街の共用井戸に歩いて行く。
そんな女中の姿が黒く輪郭をぼやかして何とか見ることができ、それはまさに人影であり、彼は誰(かはたれ)時という言葉どおりの情景が広がっていた。
ソフィは、ふと部屋の扉の外で物音がしたのに気づいて目を覚ました。
清潔なベッドでの目覚めはとても気分が良かった。
油紙の貼られた小さな窓を見ると、外は大分白じんで来たのが分かった。
枕の下に入れた下着を手に取ると、ソフィはシーツの中で下着を身に着けた。
素足で靴を履いて、部屋の扉を少し開けてみると、部屋の前にたっぷりと水が入った水差しが置かれていた。
ソフィはその水差しを取って扉を閉めると、窓際に立て掛けられた洗面桶を取りに行った。
せっかく窓際に行ったので、大きな窓の鎧戸を少し開けてみた。
もう外は大分明るくなっていた。宿屋の前の通りを見ることができる。
そしてふと通りの先に目をやると、少し通りが広くなったところでエバが立っているのを見つけた。
そしてエバの近くにキッドがいるのも見つけた。
キッドは木でできた剣と盾を手に持って同じ動作を繰り返していた。
私も行ってみようとソフィは思った。
ソフィは鎧戸を閉めると、洗面桶に水を注いで冷たい水で顔を洗った。
自分の手提げ袋から亜麻でできたリネンの布を取り出し水を拭き取ると、鎧戸を開けて桶の水を捨てた。
そしてベッドに移動すると、ブラシを取り出して髪をとかした。
衣紋掛けから長い靴下を取って、足に履いてガーターで留めた。
それからふんわりとした長袖のチュニックを被ると腰を布のベルトで締めた。
ソフィは靴を履くとベッドから立ち上がった。
最後に柔らかな皮でできた袖の無い上着のサーコートを羽織ると、ソフィは部屋の扉を開けた。
すると夜明けを知らせるサリカ大聖堂の鐘の音がちょうど聞こえてきた。
廊下を通って広間に出ると、暖炉にはもう火が入っていて、大きな鍋で湯を沸かしていた。
広間をトロマおじさんが箒で掃いて掃除していた。
「おはようトロマおじさん。」
ソフィがそう言うと、トロマおじさんが曲がった腰を伸ばしてソフィを見た。
「おはようございます。お嬢さん。」
トロマおじさんはニコッとした。
ソフィはトロマおじさんの横を通り過ぎると、掃除のために開けられている宿の扉から外に出た。
そして、通りの先の少し広くなったところに立っているエバの方に歩いて行った。
「辛いか。辛かったら遠慮なく声を出せ。自分を奮い立たせろ。」
エバはキッドに声を掛けた。
「へぁ。」
キッドは声にならない声を上げた。
もう腕にも足にも力が入らない。
ただ何とか形だけ、盾を持っている右手を動かしながら、一歩前に踏み出して、左手に持った剣を振り、そして元の姿勢に戻る。
キッドはこの2時間の間、エバの号令で100回剣を振って少し休憩し、剣と盾を持っている手を替えて100回振って少し休憩し、を繰り返していた。
手も足も含め全身の筋肉が疲労し、回復が追い付かず熱を持ち炎症を起こしている。
その炎症を抑えるため、体を冷やそうと大量の汗が流れ出る。
額から流れ出た汗が頬を伝って顎先から地面に滴り落ちる。
こんなにも大量の汗を掻いたのは、キッドの人生の中でも生まれて初めてのことだった。
500回を過ぎたあたりから、盾を持っている腕を上げようとすると力が入らなくなった。
だがエバは力が入らなくなっても問題ないと言った。
「体は疲労で悲鳴を上げるだろうが、無視しておいて大丈夫だ。人間の体はそんなにやわじゃない。今はとにかく止めずに動き続けることが大事だ。」
500回から1,000回の間は、声を出して気合を入れることで体を興奮状態にし、神経を麻痺させることで疲れを軽減させることができた。
だが、1,000回を超えたあたりからその効果も消えてしまって、あとはただひたすらに耐えるだけだ。
「何とか2,000回まで行こう。」
エバはそう言った。
あと1,000回。ひたすら耐えるだけの1,000回。
だがエバは、これを3,000回こなすという。
変態だ。キッドはそう思った。
「よし、少し休憩しよう。」
エバはそう言った。
キッドは地面にへたり込んだ。
あと残り400。
「辛いか。」
エバがキッドに聞いた。
キッドは黙って頷いた。
「それならいい感じだ。」
エバはニヤリとした。
キッドには何がいい感じなのかさっぱり分からなかった。
すると、エバがキッドの表情からそれを察したのか説明を始めた。
「キッドが辛いと感じている時、お前の手や足や体は、何とかこの辛さを軽減しようと必死で対策を図っている。」
「俺の体が。」
キッドが不思議そうな顔をしてそう言うと、エバは頷いて説明を続けた。
「どうやったら辛さを軽減できるか。それは、まずは余計な力を使わず、最低限の力だけ使うようにすることだ。次に無駄な動きをしないよう、最低限の動きだけをすることだ。そしてなるべくたくさんの筋肉に負担を分散することだ。」
なるほど。キッドは小さく頷いた。
エバは説明を続けた。
「お前がただただ辛さに耐えて、1回、また1回と基本動作を繰り返している時、お前が何も命令をせずとも、お前の手や足や体は、辛さを軽減させようとお互いに試行錯誤や調整を繰り返している。余計な力を使わなくて済むよう、力の出し具合を調整している。無駄な動きをしないよう、1つ1つの動きを正確に記憶するよう刻み込んでいる。手や足や体の連携が無駄なく行われるよう、お互いに調整を図っている。」
「俺の体の中でそんなことが。」
キッドは驚いた表情でそう言った。
「その結果、」
そう言うとエバは、立っている状態から一瞬で鞘から剣を引き抜き斬り付け、そして元の立っている状態に戻った。
無駄がない。無理がない。滑らかで、そして速い。キッドはエバの動きを見てそう思った。
「こんな風に、人が自然に呼吸するのと同じように、斬ることができるようになる。」
エバはキッドを見た。
「知らなかったか?自分の体の話だぞ。」
エバはそう言って自分の胸をポンポンと叩いた。
「俺の体の中でそんなことが起こっているなんて。」
キッドは驚きと感動で思わず自分の胸に手を当てた。
「だが体というのは、俺やキッドと同じ怠け者で、辛い状態に追い詰めてやらないと仕事をしないんだ。」
エバはそういうとキッドに笑顔を見せた。
「面白いだろ。」
なるほど、そういうことか。キッドはエバの言っていることを理解した。
エバが俺に指導しているように、俺は自分の体を指導して、鍛えてやらなければならない訳だ。
「人間みたいですね。」
キッドが笑顔でエバにそう言った。
「そうだ。人間みたいなんだ。ん?というか人間だよな俺達。」
エバがそう言うと2人で声を出して笑った。
「人間らしいといえば全くそうなんだが、体は人間と同じで、しばらく稽古を怠けてしまうと、せっかく身に付けた技術を忘れてしまう。だから稽古は日々続ける必要があって、体が忘れないように維持しなければならない。」
「分かりました。」
キッドがエバにそう言うと、エバは満足そうに頷いて言った。
「じゃあ最後の400回。行くか。」
「はい。」
とは言ったものの、体が辛い事には変わりはないキッドは、絞り切った気力をさらに絞ってゆっくりと立ち上がった。
「頑張っているのね。キッド。」
横で離れて見ていたソフィが話し掛けて来た。
エバとキッドはソフィを見た。
「頑張って、基本稽古は辛いのが当り前よ。でも、エバも言っているとおり、あなたの体は絶対にあなたを裏切らないから。」
「はい。」
キッドは力なくそう言って苦笑いを浮かべた。
「私も久し振りに型の稽古でもしようかな。」
ソフィはそういって、エバ達から距離を取った。
「最後の400回は足を斬る。」
エバが説明を始めた。
「足と言っても狙うのは膝の裏側だ。だが、人間は足を斬られると反射的に足を持ち上げて逃げる。こんな風に。」
そう言ってエバはひょいと右足の膝を曲げると足を持ち上げて見せた。
「だから足を斬る時は逃げられないように下から斜めに斬り上げる。」
エバは一歩踏み込んだ体制から、右手に持った剣を鎌で草でも刈り取るように斜めに斬り上げた。
「ここで注意するのは足の向きだ。」
エバは自身の右足を示した。
「足を斬る時には下から斜めに斬り上げるために体にひねりが加わる。だから、一歩踏み出した右足は大きく内側に向けて置かなければ、逃げる足を追いかけて斬り上げることができない。何度も言っているが、足先が向く方向でその後の体の動きが決まる。重要なことだ。」
「はい。」
「それじゃあ軽く5回、やってみよう。」
「はい。」
キッドの残り400回が始まった。
キッドを見ていたソフィは自分も体がうずうずしてしまい、型の稽古を始めることにした。
ソフィはダルケスという華麗な蹴り技が特徴的な武術の使い手だった。
始めたのは“踏破四方”という型だ。
この型は、相手が槍などの長い武器で襲い掛かって来た時の戦い方を示していて、女性らしい柔らかな動きだけでなく、敵の槍を踵で踏み折るという豪快な動きもあって、ソフィは気に入っていた。
ソフィは足を結んで真っ直ぐに立つと、両腕を真上に伸ばしながら息を吸い込んだ。
そしてゆっくり息を吐きながら開いた両手を下に降ろすと、両手を腰の高さでハの字に構えた。この構えが型を始める時の最初の構えだった。
ソフィは型を始めた。
まずは正面から敵が槍で突いてくる。
ソフィはそれを左斜め前に踏み出し敵の攻撃から軸を外す。同時に左腕の前腕部分を槍に沿うように当てる。力を入れる必要はない。致命傷にならないように槍をそっと内側に外すだけだ。
両腕の前腕を槍に沿わせたまま、ソフィは横に滑るように2歩移動する。するともう敵の目の前だ。
ソフィは右手で敵の右手首を掴むと、左の肘で敵の顔面に肘を入れる。
だがこの肘はフェイントで、一瞬相手の視界を奪うのが目的だ。
ソフィは今度は手を入れ替えて、左手で右手を抑えると、右手で敵の髪を掴み、自分の右足を敵の右足の裏に差し入れて倒すと、倒れる勢いのまま敵の頭を地面に叩きつけた。
これで正面の敵を倒した。
次はソフィの後方から敵が槍を突いてくる。
ソフィは右足を左前に踏み出しながらくるっと左側に体を回転させ転身し、敵の攻撃から軸を外した。と同時に、左腕の前腕部分を槍に沿うように当てる。
両腕の前腕を槍に沿わせたまま、ソフィは1歩踏み出すと、両手で槍を下に抑え込み、左足で槍を踏み折った。
そしてまた両腕の前腕を槍に沿わせたままさらに1歩踏み出すと、敵は正面となる。
ソフィは敵の目の前で体を回転させ転身し背中を見せると、敵の右手を自分の右脇に挟み込み、自分の左手で敵の右手首を掴んで逆を取る。
だがこの腕関節技はフェイントで、一瞬痛みで相手の注意を逸らすのが目的だ。
ソフィはすぐに腕関節技を外し相手の右腕を肩に担ぐと、敵を背負い投げで前に投げ捨てた。
そして敵の右手を掴んだまま、すぐに右足を引き寄せ、左足を持ち上げると敵の喉を踏み潰した。
これで背後の敵を倒した。
次は左手から左足元を狙って槍で払ってくる。それをソフィは左脛で受け流した。
一つ一つの技はとても残酷だったが、ソフィは無心に体を動かすことが心地良かった。
型は、ダルケスという武術に携わってきた過去の達人たちが残した、戦いの記憶だ。
過去の達人たちが実戦で有効だった技にさらに磨きをかけ、無駄を削ぎ落し、最短の時間で人を殺せるように作られている。
型を稽古することで過去の達人たちの記憶に触れ、ダルケスという武術の悠久の時の流れを感じることができる。
また型を稽古することで、安全に戦い方を経験することができた。
実際にたくさんの実戦を経験することは非常に危険が伴い、命がいくつあっても足りはしないが、型であれば、安全にたくさんの経験を積むことができる。
特に実際に2人で攻守に分かれて型を稽古する“対錬”は、実戦における間合いや攻撃に移る間を学ぶのには最適だった。
過去に居たたくさんの達人たちが、自分と同じように大地を踏み締め、型を稽古する姿がソフィの脳裏によぎる。
ソフィは型の稽古をすると、その技が持っている残酷な性質にもかかわらず、とても厳(おごそ)かな気持ちになった。
ソフィは最後の4人目の敵を倒すと、両腕を真上に伸ばしながら息を吸い込んだ。
そしてゆっくり息を吐きながら開いた両手を下に降ろすと、両手を腰の高さでハの字に構えた。
最後にソフィは両手を自然に体の横に持ってくると型は終わった。
ソフィはゆっくりと呼吸をして息を整えると、横を見た。
まだキッドの基本稽古は続いている。
基本稽古は文字どおり、武術の基本だ。
基本動作がどれだけ熟練しているかによって、当然、型の水準も威力も全く違ったものとなる。
ソフィはキッドが終わるのにまだ時間がかかりそうなので、今度は“跳山八世路”の型を始めた。
この型は、相手が剣やナイフなどの刃物で襲い掛かって来た時の戦い方を示していて、接近してからの打撃や腕関節技に加え、柔軟性を利用した膝蹴りや上段蹴りの動きもあって、これもソフィは気に入っていた。
ソフィがエバと初めて会った時、ソフィに殴りかかって来た男の腕を絡め取って顎を蹴り抜いたのも、この型を使ったものだ。
ソフィは足を結んで真っ直ぐに立つと、両腕を真上に伸ばしながら息を吸い込んだ。
そしてゆっくり息を吐きながら型を始める最初の構えを取った。
ソフィは型を始めた。
キッドはようやく基本稽古を終え、気が済むまで水をガブガブと飲むと、地面にへたり込んで休憩していた。
エバとキッドは横で型の稽古を続けているソフィを見ていた。
キッドにはソフィが何をしているのか分からなかったが、その地面を滑るように移動する独特の動きと、時々出て来る膝蹴りや蹴り技がかっこいいと思って見ていた。
エバにはソフィの動きの一つ一つが、おおよそ何をしているのか見当がついた。
そして2人は、ソフィが空を蹴り上げるように上段を蹴ると、靴下を履いた真っ白な足が、ソフィが着ているチュニックの裾から空に向かって伸び上がって出て来て、少しえっちだなと思って見ていた。
「うんっ、そろそろこっちも型をやるぞ。」
エバがそう言うと、キッドものろのろと立ち上がった。
「お願いします。」
エバは立ち上がったキッドに言った。
「型は、過去の達人たちが残してくれた、戦い方を教えてくれるものだ。俺は傭兵をしていたことがあったが、実戦経験を重ねている戦士はやはり手強い。じゃあだからといって、基本を覚えたばかりのキッドを実戦を学んで来いと言って戦場に放り込んだら、学ぶどころか生きて戻っては来ないだろう。型は実戦に行かずとも、実際に戦いとなった時にどのように戦えば良いのかを教えてくれる。今は亡き達人たちが残した戦いの記憶と呼べるものであり、経験と知恵と工夫の詰まった武術の財産だ。」
エバはそう言うとソフィを親指で示した。
「あれは、華麗な蹴り技が特徴的な武術、ダルケスという武術の型だ。キッドには何をしているのか分からないかもしれないが、実戦になった場合、ソフィは今やっている型の動きで敵と戦う。」
エバの言葉を聞いて、キッドが少し驚いた顔になった。
「あの動きでそのまま戦えるのですか。」
キッドにはソフィの動きが戦いにそのまま使えるようには思えなかった。
「省略されているところがあるから、完全にそのままという訳ではないが。あれを喰らったら確実に死ぬだろう。」
エバはそう言ってニヤリと笑みを浮かべた。
「また、以前にシェリルが話をしたと思うが、技の使い方には一般の人向け、表向きの陽法と、本来の使い方、殺人技である陰法の二つの使い方がある。つまり、型の使い方も陽法と陰法の2つの使い方があることになるんだが、残念ながら今のキッドに殺人技である陰法を指導する訳にはいかない。」
「だめですか。」
「だめだ。」
キッドは少し残念な表情になった。
「だが、陽法でも十分に戦い方の基礎は学べるし、今のキッドにはそれで十分だろう。」
エバがキッドをなだめるような調子でそう言った。
「じゃあ教えていくぞ、俺が教えるのは“四つの塔”だ。この型は、俺が身に付けているティアゴ流剣術の基礎と呼べる型で、軸を外し、接敵し、相手の防御を破って斬るという一連の流れを修得する。」
そう言ってエバはキッドを真っ直ぐに立たせると、肩幅に足を開かせた。
「型の最初はここから始まる。最初は分かり易いように俺が敵役をやる。」
そう言ってエバはキッドから2m半程離れると、木剣をキッドに向けた。
エバの木剣はぎりぎりキッドの鼻に触れるか触れないかの距離だ。
「キッド、この距離だ。この距離が剣の間合いだ。これ以上近付くことを死線を越えるといい、お互いに命を失う危険がある。良く覚えておくんだ、死なない事だけを考えるなら、この距離から中に入らなければいい。」
キッドは鼻の先にあるエバの剣を見て頷いた。
「命を落としてしまう奴は、自分が気付かないうちにうっかりと、この死線を越えてしまっている。だから普段からこの死線を意識しろ。街の通りを何気なく歩いている時でも、軽く人と挨拶をする時でも、自分が今死線の中にいるのか、それとも外にいるのか、それを意識するんだ。」
「分かりました。」
そう言ってエバは右足を一歩踏み出してキッドに向かって木剣で突きを放った。
エバの木剣はキッドの顔の右側をかすめた。
「敵が右手に持った剣で顔面に突きを放ってくる。それをお前は左足を斜め左に踏み出しながら盾で打ち外す。キッド、左足を踏み出してみろ。」
キッドは伸びているエバの木剣を避けて、左足を斜めに踏み出した。
「キッド、左足の向きを少し内側に向けろ。」
そう言われてキッドは左足の向きを少しだけ内側に向けた。
「左手で持った盾で俺の剣を打ち外してみろ。」
キッドは左手で持った盾でエバの剣を打った。
思いのほか力が入ってしまって、カツンという木と木がぶつかる子気味良い音がした。
「力を入れ過ぎだ。そんなに力をこめては動きが遅くなる。敵の速い突きに対応できない。力は入れなくていい。ただ、相手の剣に盾をぶつけて押しやる感じだ。」
「はい。」
「最後に右手で持っている剣で相手の喉を突く。盾を持っている左手の上を交差するように右手を突き出して、敵の喉を突く。」
キッドはエバから言われたとおりに右手でエバの喉を突いた。
キッドの木剣が軽くエバの喉に触れた。
「狙う個所はもう少し下だ。ちょうど喉の根本、三角に窪んでいるところだ。ここは頭と違って動きが少ないから狙い易く、剣もスッと入って行く。」
エバはそう言って、キッドの剣を少し右手で下に下げると自分の首の根本に当てた。
「それから、実際には盾で相手の剣を打ち外すのと、右手で突きを放つのはほぼ同時だ。じゃあ、一連の動きを一人で軽く5回やってみよう。」
「はい。」
キッドのこれまでの人生の中で、ここまで肉体的にも精神的にも追い詰められ、また中身の詰まった指導を受けたのは初めてだった。
キッドは生まれた農村で、サリカ神殿で読み書きと簡単な算術を習った。
それ以来、キッドが先生に付いて指導を受けるなどという機会はなかった。
そのあとはもう、親父と一緒に畑仕事に就いた。
子供は10歳になると、大人と一緒に畑仕事に出るのが普通だったが、キッドも同様に10歳になると牛に犂(すき)を取り付け、親父と一緒に畑仕事に出た。
親父からは耕作や家畜の世話、干し草づくりや刈り取り、落穂拾いなど様々な事を学んだが、指導ではなく、生きるための労働だった。
親父は自分の土地を持っていなかったから、生活すること自体が過酷で辛かった。
その過酷な親父との生活も長くは続かなかった。
キッドが12歳の時に親父は死んだ。
キッドはいまでも鮮明に覚えていた。親父が死んだ時の事を。
親父は村で流行した謎の感染症で死んだ。
親父は高熱を出して藁の寝床から起き上がれなくなると、あっという間に衰弱して、最後は意識もなくなってしまい、そして死んだ。
親父は意識がなくなる前の日に、朦朧とした様子で俺に言った。
「お前を1人にする訳にはいかないのに。」
親父はそう言って涙を流していた。
ただ、その時はなぜかキッドは涙が出なかった。
親父が死ぬと、キッドは人買いに売られて、ある農家の奴隷となった。
奴隷が何となく嫌で金を盗んで飛び出した。
ステインの街に着いて、盗んできた金で自分の馬を1頭買った。
そしてライダーとして働き始めてルーに出会った。
ルーに出会って、ルーの懸命に生きる姿が愛しいと思った。力になってあげたいと思った。守りたいと思った。
これから何かが変わる、変えてやる。そう思っていた。
だが、そんな風に思っていた矢先、キッドはある夢を見た。
夢の中でキッドはベッドで横になっていた。
ベッドの脇にはルーが椅子に座っていて、心配そうにキッドを見ていた。
すると夢の中のキッドは言った。
「お前を1人にする訳にはいかないのに。」
キッドはそう言って涙を流した。
すると、夢の中のルーはキッドを見て涙を流した。
キッドは死んで、ルーは人買いに売られて、奴隷となった。
その瞬間、キッドはハッとして目を覚ました。
何だこれは。
俺は好きな人を守ることさえもできないのか!
大切な人を不幸にすることしかできないのか!
俺には何かを変えることなんてできないのか!
悔しかった。そしてあまりの己の無力さに涙が流れた。
そしてやっと気付いた。親父がどれだけ無念な気持ちを抱えて死んでいったのかを。
だが分かって怖くなった。
自分も親父のようになってしまうのではないかと。
だからキッドは思った。
強くなりたい。絶対的に強く。何にも負けない強さを。
今の自分には、強さと呼べるものなんて何もない。
キッドはただただ強くなりたいと思った。強くなるというのがどういうことなのか、分かっていなかったというのに。
そんな時だった、キッドがエバに出会ったのは。
エバはあっという間に何人もの人の首を刎ねてしまった。
それは圧倒的であった。一方的であった。
キッドにはその光景が自分の求めていた強さだと感じた。
そのエバが剣術の指導をしてくれるという。
エバの強さの秘密が手に入る。自分も同じ強さが手に入るかもしれない。
嬉しくて心が躍った。
「キッド、それでは斬れないぞ。」
エバの指導は続いている。
「剣で斬る時には、刃の細くなった先の方の剣先を使う。だから当然、敵を斬る時にはその剣先をあてる。」
「はい。」
「斬るためには、剣をあてた後に引かなくてはいけない。基本稽古の動きを思い出せ。」
「はい。」
エバの指導は具体的で曖昧なところがなかった。
エバの強さは、人が本来持っていた力を引き出したものだった。
先人達の残した型から、戦い方と知恵と工夫を学んだものだった。
そして、それをひたすら継続することだった。
何か超人的なことでも、不思議な力でもなかった。
分かってしまえば納得がいった。
だが、教えて貰わなければ分からなかっただろう。
何をどうしたら良いのかも分からない自分に気付くこともなく、ただ漠然と強さの妄想に憑りつかれたままだっただろう。
するとキッドは、ふと動くのをやめた。
そしてエバに向かって言った。
「エバさん。何で俺なんかにこんなに熱心に教えてくれるんですか。俺なんか、大した人間じゃないのに・・・、何で・・・。」
キッドはそう言って、うつむいて地面を見た。目から涙がこぼれた。
エバはそんなキッドを黙って見た。そして目を閉じた。そして言った。
「俺にだって生きている中で辛いこともあった。だから、お前にだってあったんだろう。」
エバは目を開けると、うつむいているキッドを目を細めて見下ろした。。
「今のお前が大した人間ではないとして、じゃあ、これからはどうなんだ。これからも大した人間ではないままでいるつもりか。」
エバはキッドに近寄ると肩をぽんぽんと叩いた。
「キッド、顔を上げろ、前を見ろ。お前は強くなれる。これから強くなれるんだ。だから俺は教えている。」
キッドは顔を上げるとエバを見た。
「俺にできるのはそれくらいだが、それじゃダメか?」
エバはそう言ってニヤリと笑みを浮かべた。
キッドはまた涙が溢れてきてしまった。
エバの優しさが心に染みた。
「キッド、強くなれ。強さの妄想に惑わされるな。本当に強くなれ。」
俺だって強くなれるんだ。
キッドは腕で顔を抑えると目からまた涙がこぼれた。
さっきあれだけ死ぬ程汗を掻いたのに、俺の体には、まだこんなにも水で溢れていたとは。
「さあ、もう少しやるぞ。」
エバが言った。
「はい。」
キッドは型の稽古を続けた。
するとそこに、目を覚ましたシェリルがやって来ると、ソフィに声を掛けた。
「やあ、朝から頑張っているじゃないか。」
ソフィはシェリルを見た。
「やっぱりいいわね。朝は空気も澄んでいて。稽古をすると爽やかな気持ちになる。」
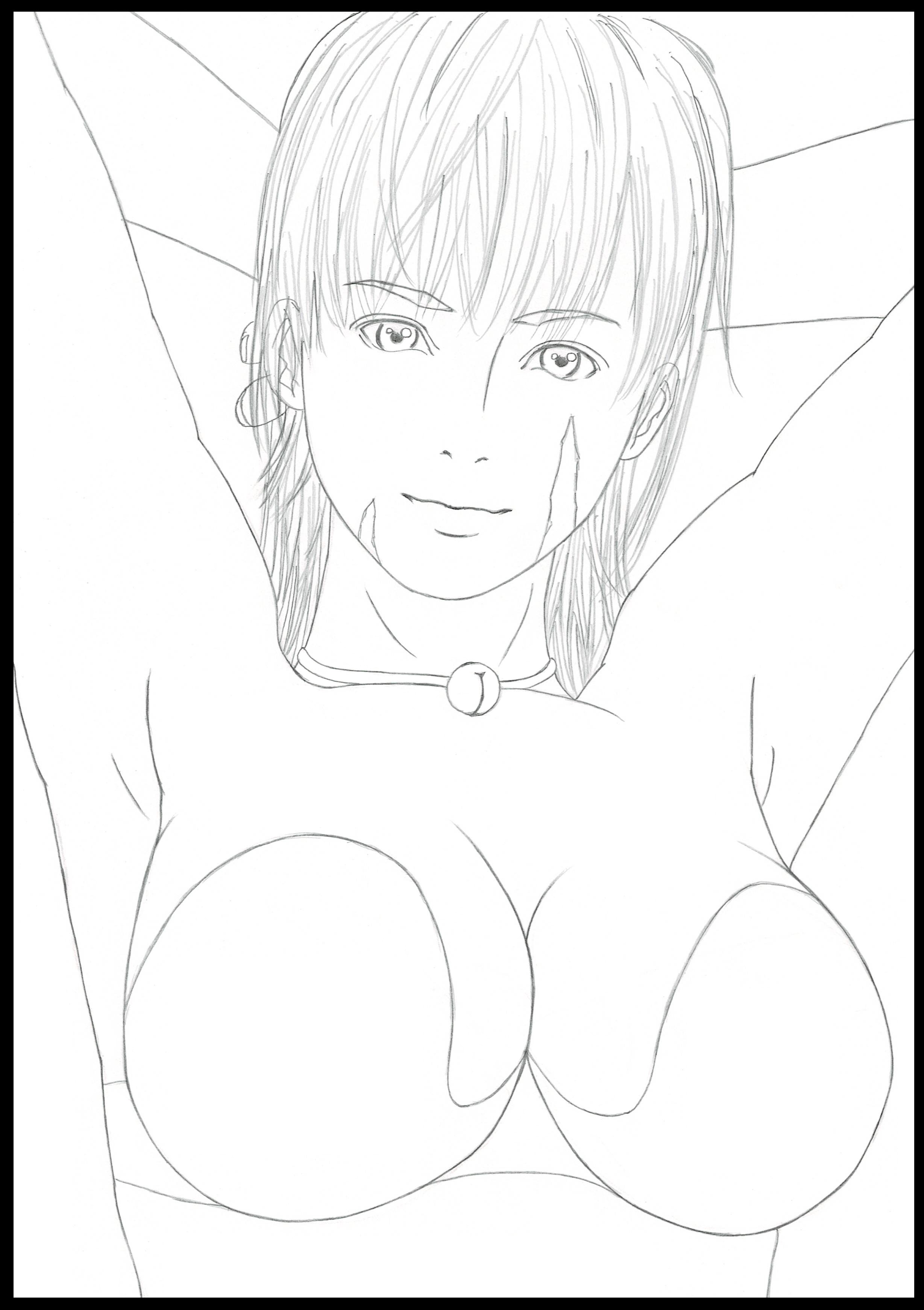
「いいな。私も爽やかな気持ちに、なりたい。」
シェリルはそう言って大きく背伸びをした。
シェリルとソフィはしばらくキッドの型を眺めていた。
「結構形になっているね。」
シェリルがそう言った。
「基本稽古2,000回こなしたらしいわよ。」
「ほう。」
シェリルは満足そうにそう言った。
「エバは以外に教えるのが上手いのね。」
ソフィが言った。
「あいつは剣術だけは情熱が群を抜いているからな。まあ、見た目は冴えた感じではないが。」
シェリルがそう言った。
「そうかな。爽やかでかっこいいと思うけど。」
ソフィがそう言った。
「えっ。」
シェリルが思わずそう言った。
「えっ?」
シェリルの言葉にソフィがそう言った。
二人はそう言うとまた黙ってキッドの型を眺めた。
「おーい、シェリル嬢。」
遠くからシェリルを呼ぶ声が聞こえた。
シェリルは声のする方に顔を向けると、ガヤンの詰め所の責任者であるバクウェルとその部下のルードが急ぎ足でこっちに向かって来た。
何か事が起こったのだろう。
「どうした?エルファの軍隊が姿を現したか?」
シェリルがバクウェルに尋ねると、バクウェルは大きく頷いた。
「街の丘の向こうにエルファの軍隊が姿を現した。恐らく500程だ。」
バクウェルはシェリルのすぐ横に来た。
「昨日あれからいろいろ考えたんだ。打ち合わせがしたい。良いか?」
バクウェルは真剣な眼差しでそう言った。
「分かった、中で話そう。これから軽くパンでもかじろうと思っていたんだ。」
シェリルはそう言うと、バクウェルの肩を叩いて、宿屋の方に向かって歩き出した。
窓から日の光が差し込んでいる。
その窓には、この時代には珍しくガラスがはめられていて、朝焼けの光を部屋の中に差し込ませていた。
この部屋の中央には、人が3人は並んで寝られるような天蓋の付いた大きなベッドが置いてあった。
そのベッドの上に、両腕を頭の後ろで組んで、天井をじっと見つめている男が横たわっていた。
朝の静かなこの時間は、考えを深めるのにちょうど良い。男はそう思っていた。
男は、睡眠は無駄な時間だと思っていた。
時間こそ無慈悲で支配できないものはない。
どんなに金を積んでも、どんな権力者、たとえ国王であっても支配できないもの。それが時間だ。
時間だけは自分を特別扱いしてくれない。男の周りにいる貧乏人どもと同じように扱われる。
男にはそれが我慢ならなかった。
だから男は、逆に周りの貧乏人どもよりも一瞬一瞬を有効に効率的に使うことを心に誓っていた。そして、少しでも有効に時間を使うために、ごく短い睡眠で体の健康を維持する方法を模索してきた。
男の睡眠時間は3時間だ。
それ以外のほとんどの時間を、男は、自分を取り巻く様々な問題を深く、より深く考えることに費やしていた。
男にはたくさんの敵が存在した。
男が金を奪い取った者どもや、男の持っている金を狙っている者どもが、男の周りにはたくさん存在した。
そのたくさんいる敵のはるか上を行き、敵を出し抜き、敵を完膚なきまでに叩きのめすためには、敵よりも深い考え、敵よりも深い洞察こそが唯一の武器となり、それ以外に武器はなかった。
だから、敵が酒を飲み同じ貧乏人共と傷を舐め合っている時間こそ、ぐうたらと惰眠を貪っている時間こそ、男はさまざまな考えを張り巡らせるのだ。
男はじっと天井を見つめていた。
すると、部屋の入口の扉の向こう側から女性の声がした。
「ボワロ将軍、エルファの軍隊が街の北の丘を越えたあたりに現れたそうです。」
「・・・そうか。」
ボワロ将軍と呼ばれたその男は、身動き一つせずにそう言ってまた少しの間天井を見ていた。
ボワロは軍人ではなく商人であったが、自分を軍隊の将軍になぞらえて、部下にそう呼ばせていた。
ボワロは枕の下から下着を取ると、ゆっくりと身に付けた。
そしてベッドから立ち上がると朝陽の差し込む窓の前に立った。
日の光が眩しい。
この世界は実に公平だ。
この朝陽も、金持ちにも貧乏人にも、善人にも悪人にも同じように降り注ぐ。
もちろん、俺は悪人の方だ。
悪いことをすれば天罰が下る。
そんなのはただの迷信だ。
現に俺はこれまでに天罰が下ったことなど一度もないし、逆に俺の怒りを買って殺されてしまった人間は数え切れないほどいる。
恐らく神は、俺のようなちっぽけな存在など気にも留めてはいないのだろう。
だったら気兼ねする必要はない。欲望のままに生きれば良いのだ。
拘束するものは何もない。
人は一人では生きられないだと。
そんなことはとっくに分かっている。
だからこそ利用するのだ。他人を。
それで他人が死んだって構いやしない。
それは逆に、俺が他人よりも上手(うわて)を行った、ただそれだけのことだ。
死にたくなければ俺の上を行けば良いだけの事。
「おい、着るものを。」
ボワロがそう言うと、扉が開いて女性が2人、部屋の中に入って来た。
女性達はボワロの身の回りの世話をする侍従だ。
女性は2人とも目を伏せて、決してボワロとは目を合わせようとしなかった。
ボワロを恐れているのだ。
ボワロは気分が良かった。
馬鹿な者どもだ。生きる意味を自分の頭で考えようとしない阿保ども。
黙って従っていれば、自分が悪いことをしなければ、慈悲を与えて貰える。そう思っているのだろう。
そういう考えは反吐が出る。
そうやって一生、恐れて、媚びへつらって、それなのに裏切られて、生きていれば良いのだ。
ボワロは2人の女性に服を着せてもらいながら、どうやってこの2人に効果的に絶望を味合わせてやるかを考えて、ほくそ笑んだ。
するとボワロは、なぜか昨日の昼間、シャロムの街の入り口で出会ったシェリルの事を思い出した。

可愛らしい顔をしていたが、顔に刀傷をつけていて、威勢の良い女だった。
男に対しても堂々としていて、爽やかだった。
しかも傑作だったのは、女が足で踏みつけていたのがバークだったことだ。
バークは愚かな男だと思ってはいたが、女に足蹴にされているとは。
痛快で気分が良かった。
ボワロはシェリルの事が気に入った。
はっきりと分からないが、シェリルには自分と共通する何かがあるように感じた。
ボワロはシェリルを食事に誘ったが、断られてしまった。
女性を建前ではなく、本気で食事に誘うなどというのは、ボワロの人生の中で初めてのことだった。
あの後シェリルはガヤンの詰め所に行ったのだろう。
そしてバークはガヤンの牢に入れられているのだろう。
いい気味だ。
しばらくそのまま牢に入れられているがいい。
次に出て来る時は、絞首刑だ!
ボワロは2人の女性に腰を布のベルトで締めてもらっていたが、そのかいがいしい姿に苛立ちを覚えた。
「もういい、離れろ。俺に触れるな!マントを寄こせ。」
ボワロはマントを受け取ると、わざと汚いものでも見るように女性を見下ろした。
同じ女性でもえらい違いだ。
ボワロはマントを羽織りながらベッドのある寝室を出ると、隣の執務室に入った。
ボワロは執務室の背もたれの付いたクッションの厚い布張りの椅子に腰を掛けると足を組んだ。
シェリルの事は残念だったが、さて、次の事を考えよう。
ボワロは執務室の壁に掛けられた顔料と卵黄を混ぜあわせた絵の具で描かれたテンペラ画に目をやると、考えを深めるためにじっと絵画をみつめた。
絵画には合戦の様子が描かれていた。
ボワロはこの絵画を気に入っていて、考え事をする時はこの絵画を眺めることが多かった。
ボワロは商人として旅をする間もこの絵画を持ち歩いていた。
「ボワロ将軍」
執務室の入り口の扉の向こう側から男性の声がした。
「何だ。」
「子爵のマックレ様がお越しいただきたいということです。」
「どうした。」
「現れたエルファの軍隊のことでご相談があるそうです。騎士たちも集まっております。」
「ふん。」
ボワロは椅子から立ち上がると部屋の入口に向かって歩き始めた。
ボワロは入り口の扉を開けると、隣の応接室に入った。
入り口の扉のすぐ横に、男の侍従が目を伏せて立っていた。
ボワロは男の侍従には構わず応接室を大股で一気に抜けると、反対側の扉を開けた。
そこは領主の謁見の間。大きな広間であった。
ボワロが扉を開けると、ざわざわとしていた広間は一気に静かになった。
「どうしましたか、閣下。」
ボワロはそう言うと広間の一段高くなったところに据えられた大きな椅子に座っているマックレに向かって歩いて行った。
マックレの前には、9名の騎士たちがマックレに詰め寄る格好で立っていた。
この騎士達は、自分の領地を持たない城に仕える騎士達だ。
ボワロはそのマックレと騎士どもの間に立った。
ボワロは騎士どもの中で、正面に立っている大柄な男を睨みつけた。
すると、ボワロが睨みつけた大柄な男も、顔の中心に向かって深い皴をいくつも作ると、ボワロを睨んだ。
すると椅子に座ったマックレが口を開いた。
「今朝方、街の北側にある丘の上に建っている屋敷の兵士から連絡が入った。北の丘を下ったところでエルファの軍隊が駐留しているそうだ。数は500程。」
マックレがそう言うと、その場は静かになった。
「エルファの目的は何か?」
ボワロは誰に向かってというでもなく、その場にいる皆に問いかけた。
その問い掛けに答えるものは誰もいなかった。
すると騎士どもの中で、正面に立っている大柄な男がマックレに言った。
「閣下、最近エルファの使者を招いて交渉事をされていたと聞きましたが、上手く行かなかったやに聞きました。それが原因ではないか。」
マックレは肘を椅子の肘掛けに乗せ、その乗せた手で顔を支えると困った様子で言った。
「エルファが育てている農産物を物々交換しようと持ち掛けただけだ。それよりも城に幽閉していたエルファの姫君のエイリスが城から逃亡したであろう。貴卿らが逃がしてしまったことが要因であろう。」
マックレがそう言うと、大柄な男は顔色を変えた。
ここで負ければ、エルファと争いとなった責任を押し付けられてしまう。
絶対に負けられない。
大柄な男は心を強く持ち直すと口を開いた。
「恐れながらその可能性は低い、姫君が逃げ出したのはつい一昨日の話。関係があったとして、エルファの軍隊がこのシャロムの街に到達するのが早過ぎる。」
大柄な男は強い口調でそう言った。
「そんなことは問題ではない。エルファの姫君が逃亡したのは身の危険を感じてこの街から離れたのであろう。逆に、姫君がこの街を離れ、戦いに巻き込まれる可能性がなくなったから、それに合わせてエルファの軍隊が到達したのではないか。であれば、貴卿らが逃亡を許してしまったせいでエルファの軍隊が現れたと言って良い。さらに我々は姫君という人質も失ったのだ。貴卿らの責任は重い。」
マックレは詰まらないことでも話すように大柄な男にそう言った。
自分の失敗であることは悟られてはいけない。マックレは何でもないというような表情をしながら、頭の中では高速で考えを張り巡らし、この場の展開に備えていた。
だいたい期間限定で領主をやっているだけなのだ。
領主をやっている間だけ、なるべく何もしないで平穏に過ごすのが良いのだ。
面倒な仕事を押し付けられるのはごめんだ。
すると、一人の騎士が、大柄な男に後ろから近付いて何か耳打ちした。
大柄な男はマックレに向かって言った。
「閣下、そもそもエルファの軍隊がこの街に姿を現すことになったきっかけ、原因、そちらの方が重大なのです。一番重いのです。その原因として考えられるのは閣下が進めていた交渉の失敗、これしか思い当たらんのです。」
すると、マックレの横に控えていた家令がマックレに近付くと何か耳打ちをした。
そしてマックレは口を開いた。
「口を慎め。失敗ではない、まだ交渉途中だ。それに我はボワロ将軍の勧めで、言われたとおりに進めていただけなのだ。交渉の責任はボワロ将軍にある。」
なるほど。いつものことか。ボワロは思った。
相変わらずこいつらの頭の中にあるのは、自分がいかに楽をするかというその1点のみだ。
街の市民の安全とか、街の平穏であるとか、街の価値を守るとか、そんなことは結局自分が楽をすることに比べたら、2の次、3の次なのだ。
それよりも、自分が楽をするため、責任の押し付け合いであるこの場での戦いに全力を投入している。
マックレと家令は、この城、それからこの街や領地の経営をやっている、言わば金を握っている者達。
そして騎士らは、この城と街を防衛するための武力を行使する者達だ。
城の機能は、この2つの者達によって維持されている。
騎士らは武力を持っているから、その武力でマックレ達経営者に圧力を掛け、自分らの言うことを聞かせられるかと言えばそうではなく、騎士らは領主に叙任され、騎士である地位を手に入れた者達であり、騎士らは領主に叙任される際に、法と契約を象徴するガヤン神の前で領主に付き従うことの誓いを立て、その誓いに嘘偽りがないことを宣誓しているのだ。
よって、その誓いを破ることは騎士としての地位を失うだけでなく、己自身の価値を大きく貶(おとし)め、剣を汚した騎士、騎士の面汚しとしての不名誉を背負うこととなり、もう二度と騎士という上位階級の地位を得る道が閉ざされることを意味していた。
では、騎士らが領主に何でも素直に付き従っているのかと言えばそうではなく、今目の前で起こっているように、騎士らは金にならない戦いに出ることは強硬に抵抗した。
エルファの軍隊と戦ったところで、身代金も略奪品も得られるとは考えにくい。
逆に下手をしてエルファに捕らえられでもしたら、どのような扱いを受けるのか想像できない。
故に、騎士らはエルファの軍隊と戦うことは絶対に避けねばならないと考えているのだろう。
「ふん。」
ボワロは低い声で唸ると腕を組んだ。
この城と街を防衛するための騎士であれば、どのように城と街を守るのか、戦いに市民を動員する必要があるか、なるべく市民の犠牲を出さないようにするにはどうしたら良いか心配しそうなものだが、こいつらときたら、本来騎士として何を考えるべきかということは全く頭になく、どうやって自分が戦わずに済ませるか、それしか頭にないのだ。
こいつは騎士失格だ。
ではマックレの方はどうか。
マックレは指示したことしかやらない男だ。
もともと俺が爵位を取得するまでの間という約束で領主役を引き受けている。
この街に何の思い入れもない、よそから期間限定でこの街に来たのだ。
だったら期間が過ぎるまで何もしないのが得策なのだ。
だからやる事を与えてやった。エルファと商売の話を纏めろと。
だが、やる気がないこともあって、期限に追われて強硬な手段を取って失敗したのだろう。
だが自分が下手をこいたと言えば、後始末を押し付けられると思って、ばれないように、かつ面倒な事をしなくて済むように、必死に立ち回っているのだろう。
なるほどな。
領主であれば、自分が治めている街が荒らされて、街の価値が毀損(きそん)してしまったり、毀損してしまった街の復興にかかる経費を考えたり、次に開かれる大市の開催が出来なくなるかもしれないとか、命を失う市民が出るかもしれないと心配したりしそうなものだが、こいつらときたら、本来領主として何を考えるべきかということは全く頭になく、自分がいかに楽をするか、それしか頭にないのだ。
こいつは領主失格だ。
しかもこいつらがやっている責任の押し付け合いを見ろ、こんな狭い城の中の世界だというのに、何を必死になっているのか。
2人だけではない、マックレに従っている家令も、大柄な男以外の8人の騎士らも、誰も2人に対しておかしいと言う者はいない。
何も今日だけではない。これまで何度も見て来た光景だ。
こいつらと来たら。小さい、あまりにも器の小さい男達だ。
こいつらに価値があるとすれば、私に利用されるという、そのことだけだ。
お前らに存在価値を与えてやるためにも、存分に利用してやらなばなるまい。
ボワロは大柄な男を睨むと言った。
「貴卿は戦いの準備を始めよ。そして北の丘にあるヤドゥイカ砦で守りを固めるが良かろう。」
ボワロの言葉を聞いた大柄な男が、口を開けたまま動きを止めた。
ボワロの言った言葉がすぐに分からなかったようだ。
大柄な男は一瞬後ろにいる騎士らを見て、もとに戻ると言った。
「ボワロ将軍。いつ戦うことが決まったのだ。そんな話はしていなかったであろう。」
大柄な男は良く分からないという顔をした。
「貴卿らは戦うことが仕事であろう。違うのか。それとも何か理由があるのか。」
「ボワロ将軍。貴卿も聞いていたであろう。エルファの軍隊がこの街に攻めて来たのは、閣下の交渉が失敗したせいであるのだ。我ら騎士らの責任ではないのだ。」
「そうか。で、」
「で・・・、そもそも我らは戦力で負けておるのだ、ヤドゥイカ砦は使われなくなって久しく、閉鎖されている塔もある。それに武器も食料も置いてはいない。さらにこの街を守っている壁は貧弱で頼りにならん。だが、領内から援軍が到着するまでこの城に立て籠もれば、勝機は見える。わざわざヤドゥイカ砦にのこのこと出て行くなど、狂っておるとしか思えん。そんな戦いに、我らは絶対に出向きはせん!」
大柄な男は、周りを取り囲んでいる騎士たちを代表してそう言っているようだった。
大柄な男はじわりとボワロににじり寄った。
そして言った。
「そもそも騎士に叙せられてもいない、一介の商人でしかないお前が将軍だと。片腹痛いわ!」
大柄な男はボワロと顔がくっついてしまう程に近づいてそう言った。
しかしボワロは全く怯む様子も見せずに静かに言った。
「それだけか。」
「何?」
「理由はそれだけかと聞いておるのだ。」
大柄な男はボワロの言葉に、何と言えば良いのか戸惑った表情をした。
するとボワロは、猛獣が獲物に襲い掛かるような表情に豹変すると大きな唸り声を上げた。
「この、ど阿保おおおおおおおぅ!!」
大柄な男は、ボワロの声があまりに大きいので、思わず怯んでしまった。
「卿らが騎士に叙せられた時の誓いの言葉を忘れたか!卿らが城に籠(こも)ったら街の人々はどうなるか。それが歴代、街の人々に寄り添い、平和を守って来たヤドゥイカの騎士か?卿らが誓った勇気とはそんなものか!この、たわけがぁ!」
ボワロの言葉に、騎士たちは一瞬で猛獣に睨まれた家畜のように身を縮めた。
「大体、この街の壁が貧弱なものであることは、昨今分かったことではないであろうが。それであるのに、何の策も施さずに惰眠を貪って来たのは卿らであろう。それを差し置いて、敵に責められた途端何の策もなく城に逃げ込むとは、それでも卿らは誇りある騎士か!」
ボワロの前に並んだ騎士たちは下を向き、その目から抵抗する意思が失われていた。
だが、ボワロの正面に立っている大柄な男だけは、最後のあがきを見せた。
「貴卿は我らに死ねと言っておるのか。」
するとボワロは大柄な男が腰に提げている剣におもむろに手を掛けると、一気に剣を引き抜き、床に叩きつけた。
「戦わぬ騎士などもう騎士ではないわ!騎士でない者に剣などいらぬ!」
そしてボワロは大柄な男の顔を鷲掴みにすると、自分の息を吹きかけて言った。
「有事に活躍することを期待して、閣下は貴卿に高い給料を与えておったのに、見事に閣下の期待を裏切りおって。卿はもうよい。裏切り者という不名誉を連れて城から出て行くが良かろう。その代わり、騎士である貴卿にこれまで支払った給料は無駄であったのだから、馬も武具も家族も質に入れて返して貰うからな。」
「な、何だと!」
ボワロの言葉に大柄な男は唸った。そして黙り込んだ。
ボワロは大柄な男の顔を掴んでいた手を離すと、他の騎士らを見渡した。
「他に何か言いたいことがあるか!」
大柄な男も含め、騎士らは大人しくなった。
「この愚か者どもが、分ったらさっさと戦いの準備に入らんか!」
ボワロの言葉に、騎士らはさっと踵(きびす)を返すと広間から出て行った。
大柄な男だけは黙ってその場に立ち尽くしていた。
最後に出て行った騎士が、広間の扉を閉めると、大柄な男はボワロに話し掛けた。
「ボワロ将軍。貴卿の言い分は良く分かった。我も貴卿の言うとおり戦おうと思う。」
ボワロは黙って男を見ていた。
「ボワロ将軍、わしにも騎士らをまとめるという立場があるのだ、そこは分かるであろう。それにわしは城仕えの騎士であるし、年齢も重ねておる。いまさら首になって、誰か新しい領主に仕えるというのも難しいからな。」
この男は戦うのも嫌だし、この城から出て行くのも嫌だという訳だ。
汚(きたな)らしい。何と汚らしい男か。
この男は人間ではない。汚物だ。
だが俺は、どんな糞のような人間でさえも利用する。この世界に存在する全ての人を俺は利用するのだ。
するとボワロは目つきを緩めると大柄な男に向かって言った。
「分かっている。分かっている。」
ここが大事だ。
ここで優しい言葉を掛けておけば、自分の事を大切に思ってくれていると勝手に勘違いして、俺の役に立ってくれるだろう。
人を利用する時に重要なのは、厳しくこき使いつつ、良い頃合いを見計らって優しい言葉を掛けたり、少し金を渡したりすることだ。
すると相手は自分の事を大事に考えてくれていると勝手に勘違いして、役に立ってくれる。
馬鹿な奴だ。自分が利用されているだけとは疑いもしない。
少しの労力や金で、死ぬまでこき使う。
これが大事なのだ。
「貴卿でなければ騎士らはまとまらん。頼んだぞ。」
「承知した。」
大柄な男は満足そうに唇の片側を吊り上げると、さっと踵(きびす)を返すと広間から出て行った。
騎士らが街の外にある砦で戦えば、街が戦場となることはない。
この街は近いうちに俺のものになるのだ、街を壊されたらこの街の価値が下がってしまう。それに街の修復にも金がかかる。
よっぽど騎士らが戦死してくれた方がましだ。
戦死すれば、もっと若くて給料の安い騎士を新たに雇いなおせば良い。
また、騎士らがエルファとの戦いに負けてこの街に帰ってきたら、騎士らの給料を減らす良い口実にもなる。
良い事づくめだ。
大柄な男の騎士が、広間を出て扉を閉めると、ボワロはマックレに話し掛けた。
「これでまた借りが一つ増えたな。どうやって返すつもりだ。」
マックレは何も言えなかった。
「このエルファとの戦いも、お前がエルファとの交渉を失敗したせいなのだからな。」
するとマックレは椅子から立ち上がると、ボワロの前に膝を突いた。
「失敗などしておりません。昨日ご報告申しましたとおり、まだ交渉している最中でありまして、私はボワロ将軍のご命令のとおり絶対に商売を成立させるよう最優先に取り組んでおります。想定外であったのは、騎士らが城に幽閉していたエルファの姫君のエイリスを、城から逃がしてしまったことです。人質を失ってしまったことで我々は交渉において不利となります。商売を成立させることは相当に困難です。」
マックレはボワロを真っ直ぐに見てそう言った。
相変わらず芝居が上手いな。ボワロはマックレを見てそう思った。
「昨日の報告ではまだ交渉途中だと言っていたが、困難とはどういうことだ。俺は必ず商売を成立させろと指示したのだが。」
「ですので、先ほど申しましたとおり、騎士らのせいで人質であるエルファの姫君のエイリスを失ってしまったことで、商売の成立は困難となってしまったのです。」
マックレは頭を下げたままそう言った。
だが、マックレの言葉を聞いたボワロは、表情を豹変させた。
「馬鹿かお前は!お前が人質を取るような真似をすることなど、私が想定していなかったとでも思ったか!エルファと争いになることも初めから分かっておったわ。分かった上で言っていたのだ。必ず成立させろと!」
ボワロの言葉を聞いて、マックレは口を開けたままじっとボワロを見上げた。
唖然としているマックレに向かってボワロは続けた。
「お前はわざと気付かない振りをしていただけだ。そして人質がいなくなったことで商売を成立させるつもりもなくなったという訳だ。騎士らのおかげでいい口実ができたと思っているのであろう。つまり、お前は私を騙そうとしていたということだ!」
ボワロが激しく睨みつけると、マックレは力なく頭を垂れた。
「お前が俺を騙そうとするなら、俺は一切力を貸さない。この戦争はお前の責任なのだからな。お前の責任で何とかするのだな。」
「そんな、申し訳ありません。私が悪うございました。申し訳ございません。」
マックレはボワロの足に取りついて、何とかボワロに慈悲をかけてもらおうと、すがりついた。
そのマックレの姿をボワロは心の中で笑って見ていた。
馬鹿な男だ。
マックレを追い詰めれば、エルファとの交渉で手段を選ばず、強硬な姿勢で臨むことは想定していたことだ。
曖昧な態度をしてマックレを油断させておいて、急きょ1ケ月前になって期限までに必ず成立させるように圧力をかけた。
エルファと親しい関係者がいる訳でもないマックレが、1ケ月で商売をまとめるなど不可能だ。
それに今回の商売は、エルファが森で栽培しているプファイトの実を、人間同士の戦争の武器に使うというのだ。
エルファが同意などするはずもないし、それを強要すればそれだけで戦争になってもおかしくはない。
その商売を考えたのは誰だ。
俺だ。
ボワロは自分の足に取りつくマックレを満足そうに眺めた。
さて、そろそろマックレに飴を与える頃合いだな。
するとボワロは目つきを緩めるとマックレに向かって言った。
「分かっている。分かっている。」
その言葉を聞いて、マックレは顔を上げてボワロを見た。
「お前しかいないのだ。これをやり遂げられるのは。」
「ボワロ将軍。」
「俺は爵位を金で手に入れる見込みが付いた。後は実績が必要なのだ。それがこの商売だ。そして、この商売が成立したら、お前もその実績と金を持って首都のルークスに戻れるのだ。お前が首になった高級役人に戻れるのだ。だから、必ず成立させろと言っている。」
ボワロの言葉に、マックレは力なく頭を垂れた。
マックレは少しの間下を向いて黙っていた。そして下を向いたまま言った。
「申し訳ありませんでした。ボワロ将軍。では、私はこれから何をすればよろしいでしょうか。」
ボワロは満足そうに頷いて見せた。
「よし。ではまず、領内の騎士らに召集を掛けるのだ。これは速やかに行うのだ。次に、同盟に基づいて諸侯に援軍を要請するのだ。エルファどもにこちらの本気を見せてやらねばならん。それから書状には、エルファ軍の数は2,000だと書いておけ。エルファ軍も増援があるかもしれんからな。」
ボワロはマックレに手を差し出すと、マックレを立たせてやった。
「承知いたしました。早速取り掛かります。」
「うむ。」
そういうとボワロは、満足そうに頷いて、自分の応接室への扉を開けて、部屋に入った。
応接室の中には男の侍従が目を伏せて立っていた。
するとボワロは応接室をさっさと抜けて、さらに隣にある自分の執務室に入ると、執務室の背もたれの付いたクッションの厚い布張りの椅子に腰を掛け、足を組んだ。
そして椅子に座って天井を見ていたボワロは、急に我慢できなくなった様子で笑い始めた。
「ははははは。」
ボワロは左手で顔を覆った。
これで戦争になる。
戦争になれば人も食料も武器も必要となる。その金額は巨額だ。
しかも、同盟を結んでいる諸侯でも人と食料と武器が必要となる。
その人と食料と武器を取り扱うのは誰か?
俺だ。
「ははははは。」
ボワロは儲けの金額のあまりの大きさに笑いを堪(こら)えることができなかった。
実に可笑しい。そして愉快だ。
全く、私の思い通りに事が運んでいく。
勝ち負けは問題ではないのだ。
戦争になりさえすればそれで良いのだ。
そして戦争責任は領主のマックレに取って貰う。
ちょうど首都のルークスに帰りたいのだから、希望通り死体となって帰してやれば良いだろう。
馬鹿な男だ。俺に利用されていることは分かっているだろうに。それなのにコロッと騙される。
そんな甘さだから高級役人も首になるのだ。
まあ安心しろ、地獄への道連れにバークも付けてやる。
バークはガヤンに拘束されているから、逃げられることもないし安心だ。
そして戦争が一段落したところで、このシャロムの街と周辺の領地一帯は、俺がいただく。
新しい領主としてエルファとの交渉も進める。
それに必要な準備はこの3年の間にもう全て終わっているのだ。
エバ達は、宿の広間で昨夜のようにテーブルを2つくっつけると、固くなったパン、チーズ、焼いたソーセージ、豆のスープを食べていた。
この時代、朝食を取る習慣はないのだが、シェリルがジェシーおばさんに頼んで特別に用意して貰ったのだ。
特に、朝の稽古で腹を空かせたキッドは、何日も何も食べていなかったかのように、固いパンをじゃぶじゃぶと豆のスープに浸すと、次々と腹に飲み込んでいた。
「凄い食欲だな。」
向かいに座ったバクウェルが驚いた様子でそう言った。
「体が欲しているんだ。疲れを回復するためにも、体を強く作り替えるためにも食べなければならないからな。」
エバがそう説明した。
「みんなも食べておいてくれ。恐らく、この後は夜まで食べられないだろうからな。」
シェリルはそう言うと、テーブルを囲んで座っている皆に向かってそう言った。
テーブルには、エバ、シェリル、マーリン、マリーウェザー、アレンティー、キッド、ルー、ビリー、ロミタス、エイリス、ソフィ、それから娼館から駆け付けたソンドラ、ガヤンの責任者バクウェル、その部下のルードを含め全員が揃っていた。
皆は固いパンをちぎって豆のスープに浸してふやかすと、口に運んで食べた。
「シェリル嬢。そろそろ話をさせて貰っても良いかな。」
ガヤンの詰め所から先ほど駆け付けたバクウェルが、眉毛を上に引き上げてシェリルを見た。
「うん、その前に、ガヤンとしてのバクウェルではなく、一人の人間としてのバクウェルがどう思っているのか、聞いてもいいかい。」
シェリルはそう言ってバクウェルを見た。
凛々しい顔をしている。バクウェルはシェリルを見てそう思った。
「承知した。」
バクウェルはそう言って頷いた。
「領主マックレをどう思う。」
シェリルはそう言ってバクウェルの方に身を乗り出した。
シェリルの問い掛けに、バクウェルはシェリルを見つめたままじっと考えていた。
「そうだな・・・。真相を問いただしたうえで、領主を辞めて貰う。」
「マックレは前代子爵の奥さんを殺した男だぞ。」
シェリルが鋭い視線を送ると、バクウェルは目を閉じて眉間に皴を寄せた。
「そうだな。辞めて貰うだけでは足りないな。」
「捕まえるのか。捕まえたって、罰金を払えば済むことだろう。」
バクウェルは眉間に皴を寄せたまま黙っていた。
「偽物の領主のくせに、エルファの姫君であるエイリスを幽閉し自由を奪ってきた。」
バクウェルは目を閉じたまま何度も頷いた。
「例えば、もしも、殺された前代子爵の奥さんが自分の奥さんだったとしたら、幽閉されたエイリスが自分の娘だったとしたら、どうだ。」
シェリルは目を閉じているバクウェルが何を言うのか見守っていた。
するとバクウェルは右手で額を抑えるとぼそっと言った。
「ぶっ殺してるだろうな。」
シェリルはその言葉を聞くと、バクウェルの方に身を乗り出した体をゆっくりと起こした。
「良く分かったよバクウェル。じゃあ、ガヤンとしてのバクウェルの話を聞こう。」
バクウェルは右手で自分の額の汗を拭うと、土器のコップに入った水を一気に飲んだ。
そして咳払いをすると、改めてシェリルを見て、話しを始めた。
「マックレには今日の午後会いに行く約束をしていたが、そこまで待っている必要はない。ここにいる全員でさっさと乗り込めば良い。そして、マックレをガヤンの我々が捕まえる。」
「捕まえてどうするんだ。」
ビリーがバクウェルに向かって疑うような視線を送った。
「普通に考えれば、殺人の罪で絞首刑にかける。」
「それじゃあ罰金を払ってすぐに出てきちまうだろうがよ。」
ビリーが吐き捨てるようにそう言った。
ガヤンは信用できない。ビリーの顔にはその思いが表情に現れていた。
「分かっている。そこでエルファとの戦争を引き起こした戦争犯罪人として捕らえる。」
「戦争犯罪人か。」
キッドが静かにそう言った。
「だめだ。戦争にはさせない。」
突然エバがそう言った。
「そうだな、戦争には絶対にさせない。だから、起こってもいない戦争で戦争犯罪人には問えない。」
シェリルはエバを見ながらそう言った。
「エルファとの戦いを今から止めようと言うのか。」
バクウェルが驚いた様子で尋ねた。
「当たり前だ。もし戦争になれば、エイリスはもう2度とこの街に来ることは出来なくなる。」
シェリルはそう言ってバクウェルを見ると首を横に振った。
マーリンはエルファ語で目の前で起こっているやりとりをロミタスに通訳していた。
ロミタスは、今でこそマックレに捕らわれてしまい一人でこの場にいるものの、森ではプファイトという森を守る部族の部族長を務めていた。
だからロミタスは、エルファの軍隊についてシェリルやバクウェルがどのように考えているのか注意深く窺っていた。
そのロミタスの娘であるエイリスも、穏やかにシェリルの様子を見守っていた。
するとバクウェルの隣で黙って座っていたルードが口を開いた。
「シェリル嬢。ただ、戦争犯罪人となれば極刑は免れなくなる。つまり、金で免れるということはできなくなるのだ。」
「だめだ。戦争は起こさせない。」
シェリルはルードに向かってはっきりとそう言った。
ロミタスはマーリンから説明を聞くと腕を組んでシェリルを黙って見つめた。
「そうか。これが一番我々の中で有力案だったんだが。」
バクウェルは小さくため息をつくと頭を掻いた。
そして、改めてシェリルに顔を向けた。
「それなら、偽物の子爵として王宮を侮辱した不敬罪であるとか、国の秩序を乱した内乱罪として王宮裁判にかけるのはどうだ。どちらも重罪で極刑は免れない。」
すると話を聞いていたソフィが口を開いた。
「王宮裁判は、王宮の裁判官が地方を定期的に巡回して裁判をやるものよ。このシャロムは首都のルークスからかなり離れているから、この街に裁判官が来るのは年末になってしまうわ。」
「それは待っていられないわね。」
ソフィとエイリスは顔を見合わせた。
王宮裁判とは、国王がその威信を国の隅々にまで行き渡らせるため、王宮に対する重大な犯罪について、国王から任命された王宮の裁判官が国中を回って、直々に判決を下すものだった。
ソフィは良くそんなことを知っているな。シェリルはソフィを横目で見ながらそう思った。
シェリルは口を開いた。
「不敬罪と言っても国王を侮辱した訳ではないし、内乱罪にしてもどのような被害があったと言うつもりだ。」
シェリルは、軽く握った左手を頬に当て考えるような素振りを見せるとそう尋ねた。
「それは我々に任せて欲しい。」
バクウェルはそう言って、テーブルの上に両手の肘をついて指を組むと、その組んだ両手越しにシェリルを見た。
「どういう意味だ。」
怪訝そうな表情をしたシェリルがそう言うと、バクウェルがちらっと横に座っているルードを見た。すると部下のルードはバクウェルに頷いて見せた。
バクウェルは意を決したように話し始めた。
「マックレは極刑に値する重罪人だ。であれば、極刑に科すという結果が同じであれば、方法が異なってもやむを得ない。我々なら上手くやってみせる。」
バクウェルは自分でそう言いながら、額に汗が浮かんでいた。
バクウェルがそう言い終わると、その場は一気に静かになった。
その場にいる皆が、バクウェルの言葉の意味を考えていた。
シェリルはじっとバクウェルの目を見た。
バクウェルの額に浮かんでいた汗が、重力に負けて顔を伝って流れた。
バクウェルはシェリルの目を見ることができずに、思わず目を伏せた。
するとシェリルは大きく息を吐くと、首を横に何度も振った。
「だめだ。お前、自分で言っていて苦しんでいるじゃないか。そんなのはだめだ。」
シェリルの言葉を聞いて、バクウェルはなぜかほっとした気持ちで頭を垂れた。
「起こってもいない犯罪人に仕立て上げるなんて冤罪じゃないか。お前は自分の心に嘘をつくと言うのか。本当はやりたくないことを、自分に嘘をついて無理やりやるというのか。」
「自分の心に嘘を付いたら、奴隷と一緒だぜ。」
キッドが静かにそう言った。
「そうだ。奴隷は人間とは呼べない。ただの道具だよ。道具ならいくら乱暴に扱っても良いし。壊れたら捨てればいい。」
奴隷という言葉を聞いて、バクウェルは顔を上げた。
シェリルは顔を上げたバクウェルの目を見て言った。
「昨日私の手を強く握った時の、ガヤンであるお前の純粋な意思。それがとても大切なことなんだ。それを汚すようなことは絶対にだめだ。自分から人間をやめるなんて言うな。そんなことは、私が許さないぞ!」
シェリルの力強い意思と言葉とその生命力に、バクウェルは完全に参ってしまった。
このお嬢さんは凄い。
何で関係のない俺なんかにこんなに一生懸命になれるのだろう。
何で大したことのない俺なんかを、ここまで大切に考えてくれるのだろう。
俺の方がよっぽど年上であるのに、何でこうもずけずけと遠慮もなしに人の人生に口出しできるのだろう。
だが、これで確信した。このお嬢さんは絶対に信頼できる。俺を絶対に裏切らない。
そうであるなら俺は、お嬢さんの期待に絶対に応えるべきだ。
見てろよ、ここからガヤンの底力を見せてやる。
「分かった。よく分かった。試すようなことをして済まない。ちゃんともう一つあるんだ。もう一つ考えて来た。だが、この方法はとても危険が伴う。」
バクウェルは両手の平を広げて見せると、シェリルを落ち着かせようとした。
それから、改めてバクウェルは両手をテーブルの上に置くと話し始めた。
「ガヤンが国王から与えられている権限の中で、唯一、領主にさえも実力行使が可能な方法がある。」
「もともと実力行使するつもりだったんだ。問題ない。」
そう言うとシェリルは手をひらひらとさせた。
バクウェルは頷くと話を続けた。
「反逆罪だ。国王の利益を大きく害した者を罰する。」
反逆罪という言葉を聞いて、その場は静かになった。
キッドとルーは顔を見合わせて分からないという表情をした。
「反逆罪は重罪の中でも相当に重い罪だわ。」
ソフィが呟くようにそう言った。
「バクウェル。今回の場合、大きく害した国王の利益とは何か。」
シェリルがバクウェルに尋ねた。
「3年間もの間、ヤドゥイカ子爵の継承者であるとして国王を欺き、私利私欲のために領主の地位を利用し、国王が得るはずだった領地からの収入を領得した。」
バクウェルは即座に答えた。
「なるほど、だが国王が得るはずだった領地からの収入を領得したとなぜ言える?」
「前代の子爵が亡くなって、その領地を相続する者が決定するまでの間。つまり、領地を相続する者が空白である期間は、その領地にかかる収入は国王が得ることとなっている。」
バクウェルはまたシェリルの問いに即座に答えた。
「なるほど。良く調べたな。反逆罪なんて扱ったことないんじゃないか。」
シェリルは、バクウェルの表情が何か迷いが消えたような、すっきりした表情になったと感じた。
「今から18年前、南の青の帝国が神聖王国へ進撃したとき。この街の騎士らの中で反逆罪に問われた案件がたまたま残っていた。重大な案件だから、代々のガヤン達が古文書として残しておいてくれたんだろう。」
「18年前か、そんな古い文書良く見つけたな。時間がかかったろう。」
シェリルは感心したようにそう言った。
「ルードが見つけたんだ。」
「おかげで、ガヤンの書庫にある文書にはかなり詳しくなりましたよ。」
ルードは恥ずかしそうに笑顔を見せた。
すると、シェリルが何かに気が付いた様子でまたバクウェルに尋ねた。
「マックレだけでなく、ボワロも反逆行為を手助けしたとして罪に問えるか?」
「問題ない。マックレを連れて来たのはボワロだ。手助けしたという幇助ではなく、どちらも反逆罪として排除できる。」
バクウェルが答えた。
「手続きはどう?反逆罪は通例、王宮裁判にかける必要があるでしょう。」
すると今度はソフィがバクウェルに尋ねた。
良く知っているな。バクウェルはそう思って感心した様子でソフィを見た。
「確かに、反逆罪は通例王宮裁判で判決される罪であり、実力行使するのであれば国王の承認が必要となる。だが、大きな危険が迫っている場合などであれば、ガヤンには緊急執行が認められている。」
バクウェルがソフィに説明した。
「今回のマックレの件は、大きな危険が迫っている場合と言えるかな。」
さらにシェリルがバクウェルに詰め寄った。
「放置すれば、その分国王の利益が失われれる。また、マックレらに財産を隠匿する隙を与えることにもなる。可能な限り速やかに執行すべきだと言える。」
バクウェルが答えるとルードが補足するために続いた。
「18年前の案件でも、青の帝国と通じた騎士らが財産を隠匿、あるいは敵国に移送してしまう可能性があるとして緊急執行している。今回も同じ理屈でいける。」
「なるほど。」
感心した様子でシェリルは頷いて見せた。
「だが手続きとして、違法行為が行われた事実を証明する書類を整えておく必要がある。」
バクウェルがそう言うと、またルードが補足するために続いた。
「まず、違法行為が行われたことを確認した者が必要となる。それから反逆罪の場合、法と契約の神であるガヤン神の前で、その事実を証明する12人の証人が必要となる。」
ルードがそう言い終わると、バクウェルがこの場にいる皆を見渡した。
「この場には、ちょうど12人の人がいる。」
バクウェルはそう言って少し笑みを見せた。
「なるほど。」
この場のやりとりを聞いていたビリーは、納得したように頷いた。
シェリルとソフィが、まるで悪い奴を尋問でもしているように次々と繰り出す質問に、バクウェルは見事に答え切ってみせた。
ビリーは、ガヤンであるバクウェルらが細かなことまで調べて、良く考えた上でこの場に来ているのだと思って、ガヤンを見直していた。
「まだだ、この方法はとても危険が伴うと言っていた筈だ。」
エバが独り言のようにそう言った。
その言葉にバクウェルは頷くと、この場にいる皆に向かって説明を始めた。
「領主に対して実力行使するということは、城を守っている騎士らを敵に回す可能性がある。もし騎士らを敵に回すことになれば、悪いが、ガヤンには騎士らに対抗するだけの戦力はない。」
「騎士か。こりゃやばいな。そもそも城に入れるのか。」
ビリーが眉をひそめた。
「それなら、エイリス様にご協力いただくのが良いと思う。エイリス様を保護したので受け渡すとすれば、暴力沙汰にはならないだろう。」
バクウェルが言い終わるとルードが続いた。
「反逆罪に問うのはマックレとボワロで、騎士らではない。だから基本的には騎士らを敵に回すことはない。だがマックレを排除する時になって、騎士らがどのような行動に出て来るのかが判然としない。」
「それなら心配ない。言ったろ、もともと実力行使するつもりだったって。そういう暴力沙汰はエバと私に任せて貰えばいいんだよ。」
シェリルは何でもないというように手をひらひらさせてそう言った。
それからシェリルは、改めてバクウェルとルードを見た。
「バクウェル、ルード、お疲れ様。良くやったな。徹夜だったんだろ。ありがとう。」
シェリルはとびっきりの笑顔をバクウェルに見せると、右手を差し出した。
バクウェルはシェリルの右手を握った。
シェリルの手は白くて、すべすべしていた。
シェリルの笑顔が輝いて見えた。
頑張って仕事して良かったな。バクウェルはシェリルの笑顔を見てそう思った。
疲れが一遍に吹き飛ぶ気がした。
「シェリル嬢、私も頑張ったんですよ。」
ルードがシェリルにそう主張した。
「ごめんごめん。ありがとう、ルード。」
シェリルは空いている左手をルードに差し出した。
ルードは両手でシェリルの手を握った。
「何だか、この状況は情けないわね。」
ルーがそう言って苦笑いした。
「男なんて単純さ。この程度で以外と頑張れるもんだ。」
ビリーがルーに分かったような顔をしてそう言った。
「それ、ビリーだからでしょ。」
ルーがビリーに疑いの目を向けた。
「なぬ?・・・そうかもしれないけどさ。」
ビリーがすねたような表情でそう言った。
「まあでも、憧れている人と握手すると嬉しくなるのは、男も女も一緒だろ。そう言う事なんじゃねえの。」
キッドがルーにそう言った。
「そっか、そう言われると納得。」
ルーはそう言って頷いた。
「俺も頑張ろう。」
ビリーが独り言のようにそう言った。
「では、早速皆さん、この書状に証人として署名を。正、副、控えとありますから3枚ともに。」
ルードは床に置いた袋から大きな羊皮紙を3枚、羽ペン、インクを取り出すと、テーブルに置き始めた。
「早いな。」
キッドが驚いて思わず笑顔になった。
「昨日見た時はさぼっていたけどな。」
「やればできるのね。」
ビリーとルーが笑顔で顔を見合わせた。
ルードはその会話を聞いても意味が分からなかったので、放っておくことにした。
「それから、違法行為を確認した者は誰にしますか。」
ルードは皆を見渡した。
「それなら私がなりましょう。」
ソフィがルードに向かって手を挙げた。
「ソフィ、わざわざソフィがならなくても良いのでは。」
ソンドラがソフィに思い止まるように声を掛けた。
「反逆罪であれば、この書状は王宮に送られることになるでしょう。それなら好都合というものです。」
「良いのですか。」
ソンドラはソフィに念を押した。
ソフィは頷いた。
「これまで私は存在を消して生きてきました。でももう止めにします。私は勝手に生きます。私は奴隷は嫌ですから。」
ソフィはソンドラに笑顔を向けた。
遂にその時が来たのか。ソンドラは思った。
ソンドラにとってはどちらでも良かった。ソフィが納得できるのなら。
奴隷のように自由はないが衣食住に困らない生活か、それとも自由はあるが様々な困難を乗り越えて、衣食住を自分で手に入れなければならない生活か。
どちらでも、ソフィが納得できるのであればそれで良い。
ただそれは、ソフィの意思で決められなければならない。
そして今、ソフィはその意思を示した。ソフィは奴隷ではなく自由を選んだのだ。
喜ばしい事だ。
だがソフィが自由でいることを喜ばない連中が、鎖で縛り付けようとソフィをつけ狙うだろう。
ソフィは生き残ることができるだろうか。
長い間ソフィを見守って来たソンドラは、嬉しいのか悲しいのか良く分からなくなってしまった。
「それではソフィ嬢、こちらに署名をお願いします。」
するとソフィは首を横に振った。
「私は最後に署名します。」
「じゃあみんな、そっちから時計回りに順番に署名して、それからパンとかソーセージとか食べて片付けてしまおう。」
シェリルがそう言うと、皆は順番に署名しながら、残っている固くなったパン、チーズ、ソーセージ、豆のスープを食べてすっかり片付けた。
「ソフィさん、これは・・・合っているのですか。」
ルードは最後に署名したソフィの署名を見て、ソフィに尋ねた。
どう見てもソフィとは読めなかったからだ。
「合っていますよ。ソフィは愛称なので。」
何でもないというように、ソフィはそう言った。
「ちょっと、みんな聞いてくれないか。」
シェリルはそう言って皆に声を掛けた。
「昨日バクウェルにも話をして、みんなも聞いていたと思うんだが、マックレはボワロの命令で動いていて、エルファと争いになることをあえて自分では考えないようにしていた。その結果、エルファとの関係を悪化させてしまった。マックレは期間限定で領主役を務めているに過ぎないから、言われた事だけをやっていた方が楽だし、怒られないからね。だから私は、マックレの怠慢が要因となって引き起こした問題については、マックレに責任を取って貰おうと考えていた。」
シェリルはそう言って、マリウェザーとアレンティーとルーを見ると、三人はシェリルに向かって頷いた。
「それからもう一つ、マックレがバークに指示して前代子爵の奥様を殺害したことだ。これも私はマックレに真相を問いただし、その責任を果たしてもらおうと考えていた。」
シェリルはそう言って、ソフィとエイリスを見ると、二人はシェリルに向かって分かったというように頷いた。
するとシェリルは視線を下に伏せた。
「何か違和感があったんだ。みんなも感じないか?私はマックレをやっつけることばかり話していて、ボワロが出て来ていないじゃないか。」
シェリルは自分に言い聞かせるように続けた。
「マックレを裏で操っているのはボワロだろう。だから私達は、今起きている問題について表のマックレだけでなく、裏のボワロにとってどのような意味があるのかを考えなくてはならないし、マックレだけでなくボワロもやっつけなくては意味がない。」
シェリルはそう言うと、この場にいる皆を見渡した。
「そこでエルファにとって、この街にとって、最悪の事態とは何かを考えてみる。私は戦争だと思う。エルファの軍隊が姿を現したことを引き金として、人間とエルファが戦争になることだ。そうは思わないか。」
シェリルはそう言って顔を上げると、ここにいる皆を見渡した。
すると皆も納得したようにそれぞれ小さく頷いた。
「同じように最悪の事態を考えるなら、ボワロはとても賢くて、思慮深い男だと仮定してみる。もちろんマックレの性質を良く理解していて、マックレがエルファと争いを起こすことなど初めから分かっている。分かっていてマックレを操っていたとしたら、それは、ボワロが初めから戦争を起こすことが目的だったと考えられないか。」
シェリルはそう言って、鋭い目つきで皆を見た。
「戦争となることがボワロにとってどんな利益があるのか、それはちょっと分からない。だが、既にエルファの軍隊はこの街に姿を現してしまっている。」
「つまり、今の状況はボワロの思い通りに進んでいて、このままボワロの悪だくみにはまってエルファと人間で戦争になるということ。」
マリーウェザーが眉をひそめた顔をしてそう言った。
「可能性があるということ。でも、それを否定する材料を私達は持ち合わせていない。」
アレンティーがマリーウェザーにそう説明した。
「である以上、最悪の事態を回避することをまず考えるべきという事か。」
キッドがそう言って右手で顎を触った。
シェリルはこれからこの仲間で行動する前に、皆が同じ程度にこの問題を理解する必要があると考えていた。
シェリルはこの場にいる皆を見渡すと口を開いた。
「行動する前に良く考えてから行動しなければいけない。だから、順序立てて考えて行こう。」
シェリルは皆が頷くのを確認すると話を続けた。
「考える要素としては3つある。一つはマックレとボワロ、2つ目はエルファの軍隊、3つ目は我々だ。まずはボワロとマックレについて考えよう。彼らは戦争を起こすために何をしようとするかな。」
「戦いの準備をするんじゃない。」
マリーウェザーが言った。
「ボワロとマックレが戦いに出て来るかな?」
シェリルがマリーウェザーを細めた目で見た。
「確かに出て来る訳ないか。」
「普通に考えれば、城にいる騎士らが戦いの準備を始めるだろうな。」
エバはマリーウェザーを優しい目で見た。
「そうか。」
「あとは民兵だな。」
エバが言った。
「そうか、街の男達に動員がかかるんだ。」
ビリーが分かった顔をエバに向けた。
「そうだ。街を防衛するには昼夜を問わず見張りを立たせる必要がある。城に仕えている騎士だけでは兵員が不足するからな。あとは、隣の領主に援軍を依頼するというところか。」
「援軍ですか。」
キッドがエバに尋ねた。
「そうだ。エルファ軍は500程度だ。街を守っている壁が頑丈なものであれば、援軍を要請する必要はない。エルファ軍の食糧が尽きて諦めて帰るまで、この街の衛兵だけで何とかできるだろう。だが、この街を守っている壁は脆弱だ。すると、エルファ軍が街の中に入ってしまう可能性が高い。そうなると、エルファ軍は食糧を現地調達できるから戦いが長期化するだろう。その場合、援軍を持って包囲し、一気に殲滅するのは作戦としてはありだ。」
「なるほど。でも、それはだめだわ。」
「ああ。エルファが死んで、街もぐちゃぐちゃになる。」
エバの説明を聞いて、ルーとキッドが顔を見合わせてそう言った。
「だからエルファの軍隊を何とかすべきだろう。もしものときには俺が排除する。戦争には絶対にさせない。」
「ちょっと、500人ですよ。無理ですよ。」
キッドがエバに言った。
「無理とか無理でないとか、俺には関係ない。それは俺がやるべきことだ。」
エバはキッドを強い意思を込めた目で見た。
「戦争は、結局弱い奴らが犠牲になる。兵士はいい。もともと戦うためにいるんだから。勝手に戦って勝手に死ねばいい。だが、結局戦争に勝った方の兵士は、給料を現地調達する。財産も女も子供も全て奪っていく。戦争は弱い者いじめでしかない。」
エバは両腕を組むと目を閉じた。
「俺は傭兵をやっていた時に侵略戦争に参加したことがあるが、戦争に勝った兵士どもの醜い姿を目の前で見た。戦争に勝った兵士どもは、当たり前のように家々に押し入り、金になりそうな物は全て奪い去った。金目の物がなければ女や子供を奴隷として売り払うために捕まえた。特に見立ての良い女は売春婦として高く売れるらしい。性欲に餓えていれば女をレイプし、最後に建物に火を放つ。その時の俺は茫然としてしまって、何もしてやることができなかった。今思えば、例え一緒に戦った仲間だったとしても、全て殺してしまえば良かった。」
エバはそう言ってギリギリと奥歯を噛んだ。
同じ人間のすることとは思えない。
エバの言葉にこの場にいる誰も何も言うことができなかった。
キッドは初めて、エバの目に強烈な殺意が宿っているのを見た。
人の首を斬り落とす時でさえ、少しの表情も変えることはないというのに。
するとシェリルは、キッドとビリーを見ると口を開いた。
「少し考えれば分かるはずだ。自分の大切な人が同じことをされたらどうか、自分の子どもが同じことをされたらどうか。考えればやってはいけないことだと分る筈なのに、考えることを放棄した者達。戦争だから当たり前だと、勝手に思い込んでいる愚かな者達。同じ人間であるのに欲望のままに同じ人間を傷つける。それは相手を自分と同じ人間として見ていないから平気に傷つけることができるのだ。だったら、逆にそんな奴らを人間扱いしてやる必要はない。ただの餓えた獣だよ。獣なら、一匹残らず駆逐してやればいい。」
キッドとビリーを見つめるシェリルの目から、お前達は絶対にそんなことはするなよ、というシェリルの思いが伝わって来た。
「シェリルさん。俺達は絶対にそんなことはしないよ。」
「そうさ。絶対にするもんか。」
キッドとビリーはシェリルを力強い目で見つめた。
シェリルは安心したように目つきを緩めた。
エバは目を開けると決意を込めた目で宙を見た。
「戦争だけは絶対に許せない。500人がどうした。1人1秒として8分とちょっとだ。」
エバはシェリルとマーリンを見た。
「シェリル、マーリン、その時は力を貸してくれ。」
マーリンはロミタスにエバの言葉を通訳していた。
ロミタスは、森ではプファイトという森を守る部族の部族長を務めていた。
つまり、この街に姿を現したエルファの軍隊は、つい先日まで部下であった者達なのだ。
エバが言っているとおり、戦争になどするべきではないし、部下たちがボワロの罠にかかろうとしているのであれば、部下の命は俺が守ってやらなければならない。
ロミタスは一度頷くとエバに向かって言った。
「エバ。お前の心配していることは良く分かった。だが安心しろ。俺は絶対に戦争にはさせない。」
「エバ、エルファの軍隊は略奪に来たのではない。話をすればきっと分かるはずだ。」
マーリンもエバにそう言った。
「そうだな、分かった。」
エバはそう言って、両腕を組むと目を閉じた。
「私も絶対に戦争にはさせない。」
シェリルはそう言って、マリーウェザーとアレンティーを見た。
マリーウェザーとアレンティーもシェリルを見て頷いた。
シェリルは私達のためにも、エルファと人間が戦争することを止めようとしているのだ。アレンティーはシェリルに向かって頷きながらそう思った。
「じゃあ、次はエルファの軍隊がどう動くか考えてみよう。」
シェリルがそう言ってこの場を仕切り直した。
「一旦軍隊として進撃した以上、大人しく手ぶらで森に帰るとは思えない。どこで暴れて、どんな手柄を持ち帰ろうとしているのか。ロミタス、何か分からないか。」
シェリルはロミタスに尋ねた。
マーリンがロミタスにシェリルの言葉を伝えた。
ロミタスは両腕を組んで少しの間黙って考えていた。
するとエイリスが口を開いた。
「森の最高権力者である長老たちは、人間と付き合うのは止めようと考えているのだと思うわ。だから、もう2度と関わるなと人間達に決意を伝えに来たのではないかしら。」
エイリスの言葉を聞いたロミタスは頷くと皆に顔を向けた。
「あとは、エイリスが人質に取られていたのと同じように、人間がエルファに敵対しないことを保証するため、人質を要求しに来たのではないか。だが、あくまでも脅しのための軍隊であって、実際に人間と戦火を交えようとは考えていないのではないかと思う。」
ロミタスがエルファ語で言った言葉をマーリンが皆に説明した。
「なるほどな。」
シェリルが人差し指を顎に当てると小さく頷いた。
「よし、じゃあマックレとボワロ、エルファの軍隊が何をするかを考えたところで、次に我々は何をするか考えよう。」
シェリルが皆にそう言った。
するとシェリルは視線を伏せると少しの間黙ってじっと考えた。
そしてシェリルは顔を上げてまたロミタスを見た。
「さっき、ロミタスが話してくれたように、エルファ軍は人間と血みどろの戦いをやりたい訳ではないと思うんだ。だったら、このまま進撃すれば人間達の罠にはまってエルファにとってより大きな痛手を負うことになる、だから進撃するのを止めた。こういう説明であれば、エルファの軍隊が何もせずに大人しく森に帰ったとしても、森にいるエルファの偉い人達も納得してくれるんじゃないかな。」
シェリルはロミタスに尋ねた。
「エルファは好戦的な生き物ではない。その理由なら全く問題ないように思えるが。」
ロミタスの言葉を聞いて、シェリルは納得したように頷いた。けれどまた視線を伏せると顎に当てた人差し指をトントンと動かした。
「でも、それだけでいいのかなって思うんだよな。大人しく引き下がるだけで。」
シェリルは独り言のようにそう言った。
「どういうこと。」
マリーウェザーが分からない顔をした。
「結局、エルファ軍の姿は既に街の人々に見られてしまっている訳だろう。エルファ軍が姿を消したからといって、ボワロが大人しく諦めるかな、と思ってさ。」
シェリルはマリーウェザーと目を合わせた。
「そうか、結局エルファ軍が帰ったとしても、ボワロがエルファ軍は森に隠れているだけだとか言い掛かりをつけて戦争を続けようとするかも知れないということか。」
キッドが顎に右手を触れたままそう言った。
「だったらいっそのこと、街の人達に洗いざらい話をすればいいじゃねえか。」
ビリーがシェリルを見た。
「何て言うんだ?」
シェリルがビリーに首を傾げて見せた。
「街の人達を中央の広場に集めて、エルファの軍隊が来ているのはマックレがエルファを人質に取ったからで、そのせいでエルファは怒っているんだって。そう話をすれば。」
ビリーがそう言い終わると、シェリルはかぶりを振った。
「うーん、だめだめ。それだとエルファの軍隊が現れたのは、やっぱり人間と争うためにこの街に来たとなってしまうだろ。この世界は私達みたいにお人よしの人間ばかりではないんだ。エルファの軍隊が人間と争うために来たという事実だけを悪用して、戦争を起こそうと考える悪い奴が出て来るかも知れない。そういう悪いことを考える人間がどこにいるか分からないし、どのように利用されるかも分からない。もしかしたら国王が利用するかもしれない。私はそれが恐いんだ。」
するとルーが何か良いことを閃いたように瞳を輝かせた。
「それなら、エルファの軍隊が現れたのは争うためじゃないことにすればいいんじゃない。」
「どういうこと。」
マリーウェザーがルーに尋ねた。
「例えば、エルファが現れたのは、大勢でピクニックに来ていただけとか。」
ルーがそう言うと、思わずこの場にいる皆は声を出して笑った。
「500人でピクニックか。でも、そういう何か楽しいことを理由にするという訳だな。そういう発想がいいかもな。」
ビリーが笑顔でそう言った。
「人が集まって楽しいことね。お祭りとか。」
アレンティーはそう言ってシェリルに笑顔を向けた。シェリルも笑顔でアレンティーを見た。
「エルファにはお祭りとかあるの?」
ソフィがエイリスに尋ねた。
「収穫祭とか緑の月の復活祭とか、お祭りは年に何回かあるけど、何で森の外に出て来て、しかも人間達の見えるところでお祭りをやるのか理由が難しいわね。」
「エルファの軍隊は武器を持っている。お祭りという感じではないな。」
ロミタスがそう言って苦笑した。
「そうか。良い案だと思ったんだけどな。」
ルーはそう言うとてへへという表情をした。
「そんなことないよ、ルーのお陰で発想が広がった。きっといい考えが出るよ。」
シェリルはルーに笑顔を向けた。
「ならこれはどうだ。エルファの軍隊は、人間達を守るために姿を現した。」
キッドが静かにそう言った。
「えっと、どういうこと?」
マリーウェザーが分からない顔をした。
「そうだな。例えば、エルファが何か悪い奴らに襲われていて、その悪い奴らが人間達にも危害を加えるかもしれない。そこでエルファの軍隊が悪い奴らから人間達を守るために森から出て来た。とか。」
「おお。」
この場にいる皆が感心の声を上げた。
「それはいいんじゃないか。」
マーリンが頷いた。
「でも悪い奴らって何だろうな。」
ビリーがマリーウェザーに尋ねた。
「エルファの森で悪い奴と言っても・・・、樹木を枯らしてしまうカイガラムシとか。」
マリーウェザーもそう言って首を傾げた。
「何だそれ。もっと凄いのじゃないと500人の理由にならないだろ。」
ビリーが呆れたように両手の平を見せた。
するとマリーウェザーが何か良いことを閃いたように瞳を輝かせた。
「だったら悪魔でいいんじゃない?エルファの森は恐ろしい悪魔に襲われているのよ。」
「突拍子もなく凄いの来たな。」
ビリーが思わず笑顔になった。
「どんな悪魔だよ。」
キッドがマリーウェザーに尋ねた。
「熊よりも大きくて、狼よりも鋭い牙を持っていて、頭が蛇みたいで、剛毛な足で蛙みたいにピョンピョン跳ねる。」
なぜかマリーウェザーは両手の平を頭の上に乗せると、ウサギの耳を真似てぴょこぴょこと動かした。
「何か凄い物が頭の中に出来上がっているみたいだな、それは。」
ビリーが苦笑いを見せた。
するとアレンティーが控えめに口を開いた。
「その悪魔はエルファの森の外からやって来て、エルファの森を荒らし始めた。エルファ達は悪魔をやっつけるために戦った。だが、傷を負った悪魔は森の中を逃げ回っていて、このシャロムの街の方角に逃げてしまった。エルファの軍隊は、逃げ回っている悪魔からこの街を守っているのだ。」
「凄い、何かの物語みたい。続きが楽しみ。」
ルーが瞳を輝かせた。
「いいじゃないか。それならエルファの軍隊は、人間達に感謝されることはあっても、戦争の理由にされることはないな。」
シェリルが皆に笑顔を向けた。
「エルファは実際に悪魔と戦ってきた歴史があるから、あながち全くありえない話ということでもないのよ。」
エイリスがルーに説明した。
「へー、そうなんだ。悪魔なんて本当にいるんだね。」
ルーが驚いた顔をした。
するとソフィが何か気付いたのかはっとした表情をした。
「でも、それなら早くしないとエルファが進撃を開始してしまうかも。」
ソフィが心配そうな表情になった。
「そうか、早くしないと。まずはエルファが動き出す前に説得しないとだめだな。」
ビリーはそう言ってソフィと顔を見合わせた。
「ロミタス、エイリス。エルファを説得するのはお願いしてもいいか。」
シェリルがロミタスとエイリスを見た。
「任せておけ。」
「やってみるわ。」
ロミタスとエイリスは頷いて見せた。
「それから市政長官に話をしに行こう。」
「市政長官ですか。」
シェリルの言葉にビリーが分からない顔をした。
「なるほどね。」
ソフィだけはシェリルの言葉に頷いていた。
「市政長官は、街の開門時間や衛兵などの街の運営管理を行っていて、街のお金を握っている役人なんだが、緊急時に騎士の要請を受けて民兵の動員を承認するのは市政長官なんだ。この街にもいるだろう。」
シェリルはバクウェルに尋ねた。
「そうだな。間違いない。」
バクウェルは頷いた。
「そうか、てっきり衛兵隊長かと思ったぜ。」
ビリーがそう言って腕を組んだ。
「実際に動員をかけるのは衛兵たちさ。でも、民兵を動員するとなれば、民兵を維持するための武器や食料が必要となる。それには金がかかるから、動員を承認するのは市政長官なんだ。衛兵隊長は市政長官の同意がないと動けない。市政長官が金は出さないと言ったら終わりだからな。この世の中、結局金を握っている人が裏で操っているんだよ。だから表の衛兵隊ではなく、裏で操っている市政長官を何とかする必要があるのさ。」
シェリルがビリーに説明した。
「なるほどね、さすがシェリルさんだ。」
ビリーが感心した様子で頷いた。
「市政長官に会って、エルファは無害だし、民兵を動員する必要もないと吹き込んでおこう。市政長官は無駄なお金を使いたくないから、話を聞いてくれるはずだ。バクウェル、市政長官に繋いでくれないか。」
「それなら大丈夫だろう。承知した。」
バクウェルはシェリルと顔を見合わせると頷いて見せた。
「そういうことなら、街の組合を回って、エルファは安心だと言って回るのはどうだ。」
ビリーが良い事を思いついたように皆に提案した。
「それはいい考えだな。皆で手分けして主な組合を回ることにしよう。どうかな?」
シェリルがそう言うと、皆も同意して頷いた。

「あとは・・・、ボワロとマックレが諸侯に援軍を要請するのはどう対処しようか。」
忘れていたことを皆に思い出させるかのように、マーリンが皆に問い掛けた。
「援軍を要請するとなれば、城から伝令が諸侯に向かって走ることになるだろう。だが、その伝令を捕まえるのはちょっと難しいだろう。」
エバが言った。
「そうね。それはボワロとマックレをやっつけてから、もう一度伝令を走らせるしか方法がないかもしれないわね。さっきの書状は誤りでしたって。」
ソフィがそう言うと、エバは目を開けてソフィと顔を見合わせた。
「そうだな。それは事が終わってから対処することにしよう。」
シェリルはそう言うと、机をバンと叩いて立ち上がった。そして皆を見渡した。
「みんな、出掛ける準備をしようじゃないか。まずはエルファの軍隊だ。次に市政長官、そして組合を回って、最後にマックレとボワロのところに乗り込もう。キッド、ビリー、ルー、ライダーとして道案内をお願いできないか。」
シェリルは真っ直ぐにキッド、ビリー、ルーを見た。
「任せてください。」
キッドはカウボーイ・ハットのつばをちょっと上に持ち上げるとそう言った。
「よっしゃぁ、やったるぜ。」
ビリーが立ち上がると気合を入れた。
「おー!」
ルーもビリーにつられて思わずそう言って立ち上がった。
するとルーの様子を見たアレンティーが静かに言った。
「ルーのやる気が凄い。」
アレンティーにそう言われて、急に恥ずかしくなったのか、ルーが慌てて椅子に座った。
その慌てたルーの様子を見て、その場にいる皆で声を出して笑った。
「もう、思わずビリーにつられてしまったじゃない。」
ルーはてへへという表情をすると、自分も可笑しくなって皆と一緒に笑った。
シャロムの街を朝陽が照らしている。
このシャロムの街は、街の真ん中を大きな通りが1本通っている。
その大通りは南側をファネリー大通り、北側をウェイン大通りと名前がつけられていた。
大通りは、馬車が4台並んで走ることが出来る程道幅があった。
大通りの両側には木造の商店が並んでいる。
この辺りの建物は土地を広く使った木製の平屋建てが多く、平屋を3つから4つの部屋に仕切り、太い木材で造られたアーチ屋根を被せていた。
そのウェイン大通りを、5頭の馬に囲まれた1台の馬車が速足で進んでいた。
エバ達であった。
宿屋を出たエバ達は、ソフィとエイリスが城から逃げ出した時に持ち出した馬を取りに娼館に向かった。そして次にガヤンの詰め所に行くと、バクウェルとルードはガヤンで持っている馬2頭を引き出した。
バクウェルとルードはこの街のガヤン神官だ。
ガヤンというのは正義と法の神であり、その神の教えを実践している信者達は、そのガヤンの法を犯す悪人を捕まえ、法の前で裁く権限を国王から与えられていた。
そしてエバ達は、エルファの軍隊が駐留している北の丘を越えた平原を目指して、まずはこの街の北門に向かってウェイン大通りを北に進んでいた。
マーリン兄妹とロミタスは馬車に乗っていた。
昨日キッド達が、隣のステインの街から小麦を運ぶのに使った荷車があったが、荷車で人を運ぶという訳にもいかないので、宿屋の納屋にしまっていた馬車に切り替えたのだった。
「シェリルさん。あれが領主の城ですよ。」
ビリーは手綱を握ったまま、顎で領主の城の方向を示しながら、前に乗っているシェリルに声を掛けた。シェリルはビリーと同じ馬に乗っているのだ。
「ふーん、あれか。」
ビリーが示した先に、城を取り囲んでいる濠(ほり)と城壁、それからその奥に佇んでいる城とそれから特徴的な塔がいくつか見えた。
ビリーとシェリルが乗っている馬は、シャロムの街で暴れていたところを、ビリー達が見事に生け捕りにした馬で、名前をシルブラウンと言った。
そのシルブラウンにはプリモという彼女がいるのだが、横に並んでいるキッドがその手綱を握っている。
ビリーはシェリルとくっついてしまう位に距離が近いのでとても満足していた。
エバ達は速足で城の前を通過しようとしていた。
「あの城から逃げ出して来たのか。」
馬車の御者台に座っていたエバは、ちょうど隣を進んでいたソフィに話し掛けた。
「そうね。」
ソフィが城に目をやりながら応えた。
「二人でか。」
「ええ、そうよ。」
エバの問い掛けに、今度はソフィの前に座っているエイリスが応えた。
ソフィとエイリスの二人は同じ馬に乗っていた。手綱はソフィが握っている。
二人はつい先日まで、偽物の領主マックレによってあの城に捕らわれていたのだ。
「たくましいな。」
エバがそう言って肩をすくめて見せた。
するとソフィが小さくふふっと笑った。
「何笑っているの?」
エイリスが後ろに座っているソフィに聞いた。
「何でもない、ただの思い出し笑い。」
「ふーん。」
すると少し間があって、エイリスが何かを思い出したように振り返ってソフィを見た。
「ちょっと、やめてよ。あれはソフィが悪いんだからね。」
ソフィが笑顔のまま、エイリスをなだめるように手綱を握っていない左手を上げて手のひらを見せた。
「分かってる分かってる。言わないから。」
ソフィがそう言うと、エイリスは前に向き直った。
「それにしてもよく脱出できましたね。本当に無事で良かった。」
ソンドラが二人に話し掛けた。
ソンドラは、ソフィとエイリスが城から逃げ出して駆け込んだ娼館で、2人を助けてかくまってくれた娼婦だ。
ソンドラはルードが手綱を握る馬に乗っていた。
「ソフィはお転婆で男の子みたいだもの。」
エイリスが言った。
「あら、エイリスこそ野生児という感じじゃない。私の方が負けるわ。」
ソフィがそう言った。
「二人ともやめてくれ。」
エバが二人の会話に割って入った。
「あら、どうして?」
ソフィが笑顔でエバに尋ねた。
「どっちも同じだ。」
エバのその言葉にソフィが表情を一変させた。
「同じじゃないわよ。失礼ね。」
するとすぐにエイリスが続いた。
「そうよ、私に失礼だわ。」
「違うから、私だから。」
ソフィがすぐに訂正した。
二人の様子に、エバは肩をすくめると目を閉じて見せた。
すると城の方向を見ていたシェリルが何かに気付いた。
「ちょっと止まってくれないか。」
シェリルが後ろのビリーに声を掛けた。
先頭を進んでいたビリーが左手を上げて、後ろから付いて来る皆に止まる合図をした。
シェリルは後ろに顔を向けるとエバを見た。
「城の出入り口のところに、大きく紋章の入った上着を着た一団が見えた。」
シェリルはそう言って、顎で城の出入り口を示した。
ビリーは馬の横腹を軽く蹴ると、シェリルがエバと話が出来るように、馬車の御者台に座っているエバの近くに馬を寄せた。
「エバ、見えたか。」
「ああ、あれは伝令だな。」
その一団は騎士のような紋章入りの上着を着て、その上からお揃いの草色のマントを羽織って馬に乗っていた。
しかし、携帯している武器が護身用の短剣のみであったり、また、騎士であれば身の回りの世話をさせるための従士を連れているはずだが、目の前の一団は従士を連れていなかった。
「都合が良いと言えば良いのか、ちょうどこれから出掛けようというところか。」
エバが城の出入り口を眺めながらそう言った。
「よし、出て来たところを捕まえて伝令が持っている書状を回収しよう。これで領主のマックレやボワロが何をしようとしているのか分かるはずだし、諸侯にエルファ軍と戦うための援軍を要請するつもりなら、それを阻止できるかもしれない。」
シェリルはそう言うと、面白いいたずらを思いついた少年のように、ニヤリとした笑顔を皆に向けた。
「伝令が自然に自分から書状を渡すようにしてやろう。」
そのシェリルの笑顔を見てビリーは苦笑いをした。するとその瞬間、ビリーはピンと来た。
「シェリルさん。それ、俺に任せてくださいよ。」
ビリーの言葉を聞いて、シェリルははビリーを見た。
「私の考えていることがばれてしまったかな?」
シェリルはビリーに笑顔を向けた。
「はは。シェリルさんの事が少しは分かって来たかな。」
ビリーはシェリルに左目をつむりウィンクして見せた。
「なら、私は馬から降りた方が見た目がいいな。」
「そうですね。お願いします。」
シェリルは馬から降りると、皆に向かって言った。
「ちょっと行ってくる。皆はここで待っていてくれ。」
シェリルはそう言うと、馬に乗ったビリーと一緒に城の入り口に向かって歩いて行った。
「まずは伝令に私達は無害であることを印象付けるんだ。相手の気持ちになって考えることを忘れないように。」
シェリルはビリーに付き従う従者のように寄り添いながら、ビリーに声を掛けた。
「了解。」
ビリーは頷いた。
「私達はエルファが無害であることを、この街の人々に伝えに来たエルファの使節団ということにしておこう。」
「了解。」
城の周りには水が貼られていない空濠(からぼり)があって、城の入り口には跳ね橋が架けられていて、城の出入り口と街の大通りとを繋いでいた。
ビリーとシェリルは、城の入り口から伸びている跳ね橋をちょうど渡ったところで伝令たちを待っていた。
まだ朝早い時間だというのに城の門は空いていて、1台の馬車が跳ね橋を渡っていた。城の入り口を入った中庭にも数台の馬車が止まっているのが見えた。
恐らく、朝食や1日のうちで一番豪勢な食事となる正餐(昼食)のためのパン、野菜や豆類などの食材、ワインを運び入れているのだろう。
「今日は天気が良いね。雲も無いし。朝陽が眩しい。」
シェリルは眩しそうに目を細めて朝陽を見た。

「朝陽が好きですか。」
「好きだよ。私は、自然が生まれたままに持っている、そのままの美しさが好きなんだ。」
シェリルはそう言って、手のひらを朝陽にかざして見た。
ビリーは、ついそんなシェリルの姿に見入ってしまった。
シェリルの髪が太陽の光を受けて艶(つや)めいて見えた。
するとビリーは、今この瞬間、シェリルと二人きりの状況であることに気付いた。
今エバ達は全員で14人。
この仲間たちと一緒に行動する中で、シェリルと二人きりの状況になることは今後果たしてあるだろうか。
今のこの状況は、ひょっとすると二度と訪れないかもしれない。
ビリーはシェリルを眺めながら、口の中が乾いて来るのを感じた。
ビリーは過去に、好きになった女性に思いを伝えられなかったことがあった。
好きになった女性は未亡人でシルバーグ夫人といった。
夫人は一人息子も亡くしてしまって一人で住んでいた。
その亡くなった一人息子が大事にしていた馬が、なぜかこの街に戻って来て、街で暴れていたのだ。
ビリーはシルバーグ夫人のために、その暴れ馬を見事に掴まえて見せたのだ。
その暴れ馬というのが、今ビリーが乗っている馬、シルブラウンだ。
シルブラウンを夫人に見せた時、夫人は泣いて喜んでいた。
その泣いている夫人の姿を見た時、ビリーは自分の思いを伝えることが出来なかった。
夫人が弱っているところに付け入るようで卑怯だと思ったのだ。
だがその話を聞いたシェリルは言った。
それはそれ、これはこれ。
夫人は、ビリーから何かしらアプローチがあるかも知れないということを考えていたのではないかと。
自分の心臓の鼓動がとても大きく感じた。
ビリーはさっと馬から降りるとシェリルを見た。
「どうしたんだ?」
シェリルが首を傾げてビリーを見上げた。
ビリーは乾いた唾を飲み込むとシェリルをじっと見た。
そのビリーの表情を見て、シェリルも何も言えずにだまってビリーを見上げた。
ビリーは覚悟を決めると口を開いた。
「シェリルさん、好きです。」
とうとうその時が来たか。シェリルはそう思った。
ビリーが好意を持っていることは分かっていた。
だからその答えも既に用意している。
ただその前に、少し聞いておきたいことがシェリルにはあった。
「ありがとう、嬉しいよ。でも、私に好きだと告白したとして、ビリーは何がしたいんだい。何かやりたいことがあるの?」
「やりたいこと?・・・えっと、俺はただ、好きだからその気持ちを伝えただけなんだけど。」
ビリーは困った表情をしてそう言った。
「なるほど、それだけでいいんだな。じゃあ、私もビリーの事が好きだよ。これで満足かい。」
そう言ってシェリルはビリーに笑顔を向けた。
「えっと・・・、そういうのじゃなくて。」
シェリルの笑顔に、ビリーは頭を掻いた。
「じゃあ、どういうの?」
「そうだな、・・・俺は、シェリルさんにとってもっと特別な存在になりたいです。」
ビリーの言葉に、シェリルは小さく頷いて見せると口を開いた。
「今でも充分に特別な存在だよ。現にこうして、すぐ側にいて、同じ人生を共有しているじゃないか。私と一緒に居てくれているんだろ。それではだめなのかな?ビリーがあえて告白する意味ってあるのかな?」
「俺が告白する意味。」
シェリルにそう言われて、ビリーは良く分からなくなってしまった。
俺は、シェリルさんを助けたい、守りたい、大切にしたい、そう思っている。
でも、それって告白しないとできないことなのか?
別にそうではない。
今シェリルさんの隣に俺が立っているのは、シェリルさんの力になりたいという気持ちからここに立っているのだ。
別に告白しなくたって、俺はシェリルさんの力になることはできるんだ。
だったらさっき、俺がシェリルさんに好きだと告白したのは、ただ好きだと言う気持ちを伝えたかったから、それだけだったのだろうか。
いや、違う。
それだけでは納得できない。
俺は、何のために告白したんだ!
「分からないかな?」
シェリルは悩んでいるビリーを見て微笑んだ。
するとシェリルは、伝令の一団がゆっくりと城の出入り口を出て、跳ね橋に向かって進み始めたのを確認した。
そのシェリルの視線に気付いたビリーも、その一団の方に目をやった。
ビリーは答えを見つけられるかな。ゆっくり進み始めた一団を眺めながらシェリルは思った。
ビリーの答えが出た時、その時が、私がビリーの告白に答える時だ。
しかし、今この場で決着してしまうのは良いことではない。
これからビリーも含めて仲間たち皆で乗り越えていかなければならない問題がたくさんあるのだ。
その時に仲間たちの間がぎくしゃくした関係となってしまうのは避けなければならない。
それに、ビリーの純粋な気持ちを大切にしたい。
だから、決着するにしても綺麗な形で決着させたい。
シェリルは少し微笑んだ表情のまま、悩んでいるビリーに視線を移すと口を開いた。
「お互いに、この答えは今抱えている問題を解決してからにしよう。私も告白に対する答えを考えておくから、ビリーも告白した意味を考えておいてくれないか。」
シェリルはそう言うと、ビリーの表情を伺った。
けれどビリーは、そのシェリルの言葉を聞いても表情を緩めなかった。
やはり、シェリルさんは一筋縄にはいかないな。ビリーはそう思った。
まさか、好きだと告白したらこのような反撃を喰らうとは思ってもみなかった。完全にシェリルさんに手玉にとられてしまっている。
きっと、シェリルさんはどんな終幕を迎えるのかまで、既に考えているんだろう。
つまり、俺は振られて終わるのだ。
しかも、俺が必要以上に傷付かないよう心配りまでされてしまって。
情けねえ。
そんな俺は絶対に情けねえ。
このままシェリルさんの想定どおりに進ませるものか。
何とか一矢だけでも報いてやりたい。
どんなことでもいい。シェリルさんの想定の上を行かなければ。
するとビリーの視界の端に、伝令の一団が映った。
伝令の一団がゆっくりと跳ね橋を進み始めていた。もうあまり時間がない。
ビリーはシェリルを見つめると言った。
「好きな人はいない。だけど好きになるつもりもない。・・・シェリルさん昨日の夜、そう言いましたよね。」
ビリーのその言葉に、シェリルは目を細くしてビリーを見た。
「俺覚えてますから、分かっているつもりですから。でもシェリルさん、俺がその運命、変えていいですか。」
ビリーの言葉にシェリルは少し驚いた表情をした。
「運命を変える?ビリーが?」
「ええ、俺が。」
ビリーはそう言ってシェリルを見た。
シェリルはビリーの言葉が良く分からないという表情をした。そしてビリーに尋ねた。
「・・・どうやって?」
「それは、・・・シェリルさん、結婚してください!!」
ビリーの言葉に、思わずシェリルは瞳を大きくさせてビリーを見た。
「!!。いきなりそんな・・・お前、勢いだけで言っているだろう。そんなの無理だ。」
そう言ったものの、シェリルはビリーの勢いに押され、思わず少し後ずさりしてしまった。
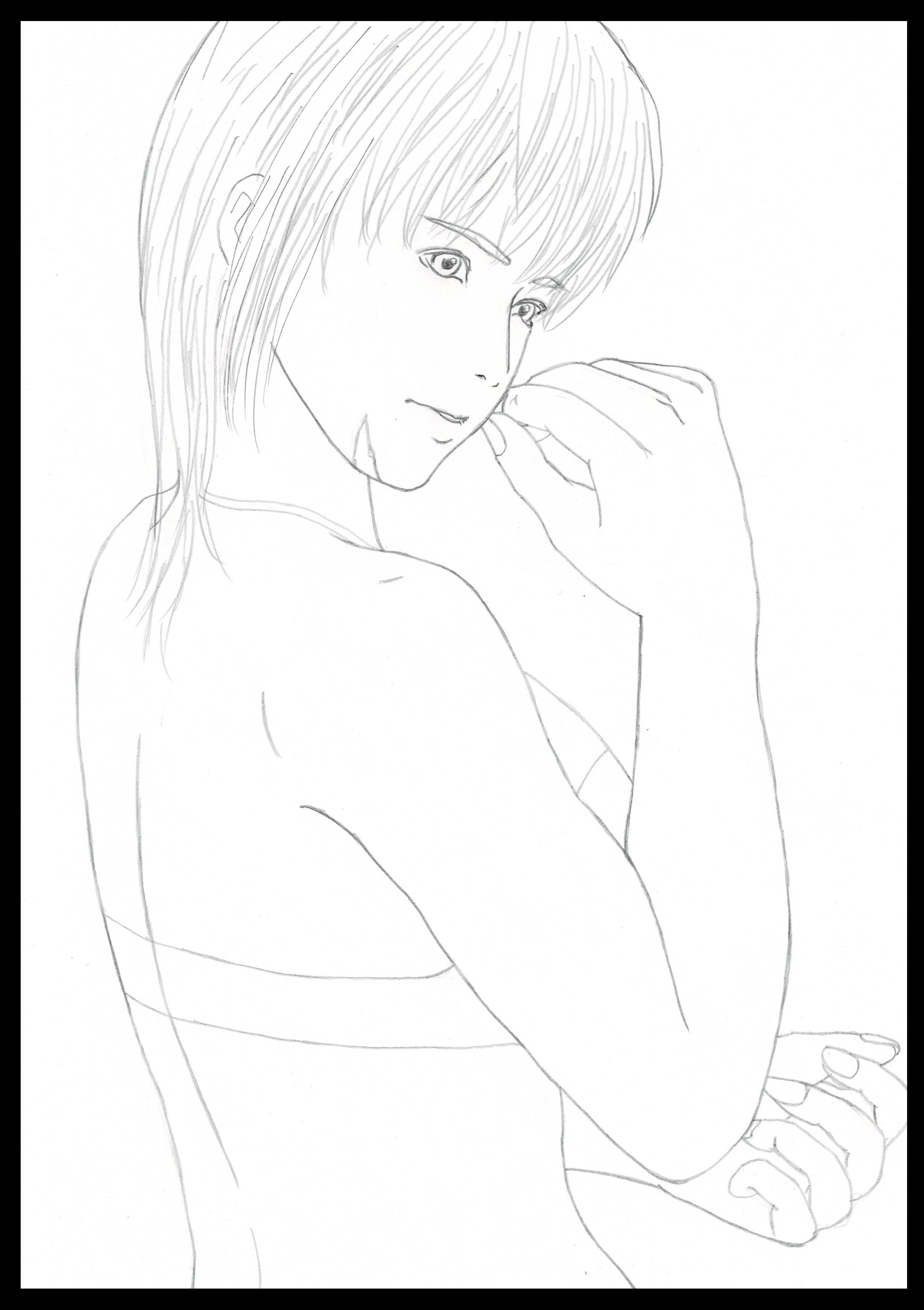
ビリーはそれを見逃さなかった。ビリーはシェリルに近付くと、さらに攻勢に出た。
「そりゃあ勢いで言っているに決まっているじゃないですか。こっちは時間もないんですよ。でも、勢いだとなぜ無理なんです。勢いで結婚したらだめなんですか?なぜ無理なのか、俺を説得してくださいよ。」
やられたな。シェリルは思った。
完全な不意打ちだ。
私の思ったとおりにはさせないぞ、と。そういうことか。
「俺、シェリルさんに2人娘がいても構わないので。何なら2人息子がいると言われても驚かないので。」
真っ直ぐな視線をシェリルに向けながら、ビリーはそう言った。
シェリルは、そんなビリーを眺めていた。
自分で何を言っているのか分かっているのか。勢いだけで、言っていることは無茶苦茶だ。
でも、こいつ本気なんだな。
シェリルはそう思った。
そしてそう思った途端、シェリルは胸が強く締め付けられて苦しくなった。
ビリーの純粋な気持ちを大切にしたいだとか、綺麗な形で決着させたいだとか。
私は高慢で打算的で嫌な女だ。
シェリルはビリーの視線を受け止めることができずに目を伏せた。
いつからだろう。恋で胸がときめくとか、そういう感覚を失ってしまったのは。
シェリルはもう少し幼い時代に恋愛を経験したこともあったが、もうその感覚を失ってしまって何年も経っている。
だがビリーは、恋愛をすっ飛ばして私と運命を共にしたいのだと言う。
だがそれはだめだ。
性格は優しい。
たくましさもある。
五体も健康。
上背もあって、結構良い顔をしている。
そんな好青年を、ときめきを枯らしてしまった私の側に置いて、愛だけを貢がせるようなことをすれば、それこそ、若い翼をもぎ取ってしまうことになるだろう。
ビリーには恋愛経験をしてもらって、その延長で愛する伴侶を決めて貰いたい。
だが、今のビリーにこんな話をしたところで納得しやしないだろう。
ビリーがいくら抵抗しようとも、私は、嫌な女でなくてはならない。
シェリルは、伏せていた瞳を開けてビリーに向けると言った。
「分ったよ。もう一度考え直すから。事が終わったら必ず返答するから、約束する。」
そう言って、シェリルはビリーに少し微笑んで見せた。
ビリーも安心したのかシェリルに向かって笑顔を向けた。
「ビリー、来たみたいだね。」
シェリルが跳ね橋を渡り終えた伝令の一団を顎で示した。
城の入り口から伸びる跳ね橋を、馬に乗ってゆっくりと進む5人の伝令が渡り終えようとしていた。
「行きましょう!」
ビリーはさっと馬に跨ると、シェリルに左目をつむりウィンクして見せた。
全く、人の気も知らないで。それにしてもビリーの奴、気持ちの切り替えが早いな。
シェリルはそう思って思わず苦笑いした。
シェリルとビリーはゆっくりと伝令の一団に近付いて行った。
するとビリーが伝令たちに声を掛けた。
「城の使者殿、お初にお目にかかります。私はエルファの使節団で案内役をしている者です。」
伝令たちは、エルファという言葉を聞くと怪訝そうな顔をした。
「いや、声を掛けたのは本当にたまたまで、通りかかったら姿が見えたので。使節団の代表があなたたちの事を心配して、一言お伝えするようにということで。」
ビリーは淡々と命令どおりに話している風を装ってそう言った。
伝令たちはビリーの言葉を怪しんでいるものの、心配事とは何なのか気になっているようだった。
「エルファの使節団と言ったか。」
ビリーに一番近い伝令の男がそう尋ねた。
「ええ、これから市政長官のところに伺って、もちろんこの城の城主にも本日お連れする予定です。」
ビリーはそう言って、4頭の馬に囲まれたエバ達のいる馬車を手で示した。
「それは本当か。」
伝令の一人が驚いた顔を見せた。
「お前は何だ?お前も案内役なのか。」
伝令たちの一人がシェリルに声を掛けた。
「はい。案内役であるビリー殿の従者をしております。」
シェリルがいつもの威勢の良さは隠して、大人しい風を装ってそう言った。
「可愛い顔をしているじゃないか。どうだ、俺たちの従者にならないか。食べ物には困らないぞ。」
伝令の男が下心を出した。
「そりゃあいい。俺たちの世話をしてくれよ、たっぷりと。」
別の伝令の男がそういうと、伝令たちは可笑しそうに笑った。
「まあ、それは良いとして、代表が心配されているのはあなた方のことなんですよ。」
ビリーの言葉に、伝令たちはつまらないものでも見るようにビリーを見た。
そしてお互いに顔を見合わせると、しようがないという様子で、ビリーに一番近い伝令の男が尋ねてきた。
「何が心配なのだ。」
ビリーは頷いて見せると話しを始めた。
「我々エルファの使節団は、この街の人達を安心させるために来ているんです。実は、北の丘の向こうに現れたエルファの軍隊は、この街を守るために来ているんですよ。」
「何だって。」
伝令たちは皆驚いた顔を見せた。
するとシェリルもビリーの話を補足するため口を開いた。
「何でもエルファの森で悪魔が出たらしい。その悪魔が森の中を逃げ回っていて、エルファはこの街に悪魔が入ることがないように守ってくれているんだ。」
ビリーはシェリルを見て頷いて見せると、伝令たちを見た。
「この城の城主もその事を知らないから、エルファの軍隊が街を襲いに来たのではないかと勘違いされていると思うのです。まあ、後から城主には我々からちゃんと説明しますが。」
すると、ビリーの言葉を聞いて、ビリーに一番近い伝令の男が頷いた。
「そうか、なるほど。それは知らなかった・・・、それで、使節団の代表が心配している事とは何なのだ。」
「もしかしたら、使者殿はこれから諸侯を回って兵士を派遣するよう要請して回るのではないですか。」
ビリーがそう言うと、伝令たちが少しざわついた様子を見せた。
城主から賜った使命は他人に知られてはならない、機密事項だからだ。
だがビリーに一番近い伝令の男は、後ろにいる伝令たちを制した。そしてビリーに口を開いた。
「いかにも。これから領内と周辺の諸侯を回る予定だ。」
緊急事態であり、ばれているのであれば隠してもしようがない、伝令の男はそう考えたようだった。
伝令の言葉を聞いたビリーは、分かっていたというように、シェリルと顔を見合わせるとお互いに頷いて見せた。
そしてまた伝令に顔を向けると言った。
「そうだとすると、せっかく諸侯を回っても無駄になりますよ。いや、無駄になるどころか、もう一度諸侯をお詫びして回る羽目になる。」
伝令たちは眉をひそめた。
「どういうことだ。」
「この城の城主が兵士を集めているのは、エルファと戦いになったときのためだ。だがエルファと戦いになることはない。エルファはこの街を守っているのだから。当然、兵士を集める必要はない。使者殿が諸侯を回って兵士を要請して帰ってきたら、今度はそれは間違いでしたというお詫びをするために、もう一度諸侯を回らなければならなくなる。」
伝令たちは険しい顔をしてビリーの説明を真剣に聞いていた。
ビリーの説明が終わると、伝令たちは黙ってしまった。
様子を見ていたシェリルは、もう一押ししておこうと自分も口を開いた。
「お詫びで済めば良いが、もしお詫びが間に合わずに兵士を派遣してしまったら、この城の城主の責任問題になってしまうだろうし、賠償金を請求されることもあり得るだろうな。その時に伝令のあなた達が、この城の城主とか諸侯の領主から、とばっちりを受けなければ良いけれどね。」
シェリルが何でもないというような表情でそう言った。
領主の言葉を代行して伝える伝令は、普通であれば丁重に扱われるのだが、領主同士が敵対してしまったり、伝える内容が都合が悪い事であったりすると、伝令が失礼な事をしたとして書状を受け取って貰えなかったり、持って来た書状を食べろといじめられたりした。
ひどい場合、拘束され尋問を受けたり、殺害されてそもそも伝令など来なかったことにされるという噂もあった。
「まさかな。」
シェリルの言葉に伝令たちは顔を青くした。
ビリーが伝令たちをなだめるように両手を挙げて手の平を見せた。
「いや、別に使者殿が良ければそれで良いのです。ただ、使節団の代表が良い提案があると言っていまして。」
「何だ、その良い提案とは?」
ビリーに一番近い伝令の男が真顔で尋ねた。
ビリーは両手を挙げたまま小さく頷くと説明を始めた。
「それはこうです。まずは使者殿が持っている書状を我々で一時的に預かる。そして、後ほど使節団の代表がこの城の城主に説明します。エルファの軍隊はこの街を守るために来ているのだと。するとこの城の城主は顔を青くするでしょう。しまった、諸侯に兵士を要請してしまったとね。そこで我々が預かっておいた書状を出す。ここにありますから大丈夫ですと。するとこの城の城主も安心すると、こういう訳です。」
ビリーの説明が終わると、シェリルが続いた。
「城主の為を思ってやるのだから使者殿が責められる道理はないし、使者殿も二度も諸侯を回る必要もなくなる。それに、諸侯にとっても誤った情報で兵士を派遣してしまうこともなくなる。誰にとっても良い事だ。それに使節団には、エルファの姫君のエイリス様もいらっしゃる。」
「何だと、それは本当か。行方が分からなくなっていると聞いていたが。」
伝令たちは驚いた表情をした。
「本当だ。あちらにいらっしゃる。」
シェリルが、4頭の馬に囲まれたエバ達のいる馬車の方向を手で示した。
「さてどうするか。代表は忙しいので決めるなら今すぐに決めて貰わないといけないが。」
ビリーが時間がない風を装って、少しイライラした様子を見せた。
「どうするか。」
ビリーに一番近い伝令の男が仲間の伝令に尋ねた。
「どうしようか。ただ、このまま諸侯を回るのは危険だろう。」
「かと言ってどうする。」
すると伝令の中の一人が、顔をしかめると強い口調で言った。
「馬鹿か、書状を渡すというのは無理だろう。伝令を首になるどころか下手をすると処刑されるぞ。」
伝令たちの間に流れる空気が一気に緊張感を増した。
その事に気付いてすかさずビリーが打ち消しに入った。
「だからそれは大丈夫だ。我々から書状を渡すように提案したのだと、使節団の代表からこの城の城主に説明するのだから問題にはならない。」
だが、処刑という言葉が出たことで慎重になった伝令たちは、分かったとは言わずに黙り込んだ。
このまま諸侯を回るのは嫌だが、書状を渡すのも嫌だという訳だ。何か策がないかと考えているに違いない。
すると伝令の一人がビリーに向かって言った。
「お前から城主殿に説明してくれないか。」
それはつまり、ビリーが城主に会って、諸侯に伝令を向かわせることは無駄になると説明してくれと、こういう訳だった。
「はあ!」
伝令たちの無責任な態度に、さすがのビリーも唖然としてしまった。
すると別の伝令も頷きながら口を開いた。
「確かに、エルファの事情が分からない我々から城主殿に説明するよりも説得力がある。城主殿からエルファの事情を聞かれても、我々は分からないからな。」
その伝令の言葉に他の伝令たちもうんうん、そうだと頷いていた。
伝令たちがビリーに見えない圧力をかけた。
「ちょっと待ってくれ、俺はただの案内役。この城の城主が会ってくれる訳ないだろう。」
ビリーは慌てた様子でそう言った。
しかしビリーに一番近い伝令の男は落ち着いた様子だった。
「城主殿には俺が口を聞いてやろう。さっそく行こうじゃないか。」
どうする。どうする。ビリーは高速で考えた。
ふざけるな、何で俺が説明することになるんだ。
伝令というのはこういう奴らなのか?
城に仕える人がこんな無責任なことでいいのか?
だがこうなってしまった以上、時間がないからと言って退散するしかないか。
書状を入手することはできないがしようがないか。
そこでビリーはシェリルを見た。
するとシェリルもビリーの様子を見つめていた。
二人の視線が交差した。
シェリルはビリーを安心させようと、一度頷いてからニヤリと微笑んだ。
こいつらいじめてやる。シェリルはそう思った。
この城の城主には尻尾を振って、立場の弱いビリーには嫌な仕事を押し付ける。
そんな伝令たちをシェリルは許せなくなった。
今の状況から、こいつらの普段の仕事の様子も窺えた。
自分より下の立場の人間に仕事を押し付けるのが、日常になっているのだろう。
一度思い知らせてやる必要がある。
可愛いビリーをいじめた落とし前は、つけさせなければならない。
シェリルはビリーと伝令の間に割って入った。
ビリーと伝令は、シェリルが何をするのかと思わず静かになった。
するとシェリルは両腕を組むと伝令を睨みつけた。
「とっとと失せろ、恥知らずが。」
この場が一気に静かになった。
「この女、何を言っているんだ。」
伝令の一人が口元に笑みを浮かべながら、ふざけた調子でそう言った。
「2回言わないと分からないのか、とっとと失せろと言ったんだ。」
伝令たちの顔から笑みが消えた。
「思い知らせてやる。」
伝令の男が片足を上げて馬から降りようとすると、ちょうどシェリルにお尻をむける形になった。
馬鹿な奴。思い知らせてやると言っておきながら、敵にお尻を向けるやつがあるか。シェリルはそう思った。
するとシェリルは、スッと伝令の男のお尻に剣先を当てると、鋭い切っ先は容易に衣服を斬り裂いてお尻に刺さった。
「ぎゃ!」
伝令の男は驚いて跳び上がり、地面に転がった。
シェリルは地面に転がった男の頬に切っ先を当てた。
「ひい!」
男の顔は、シェリルの剣と地面に挟まれて動けなくなった。動けば剣が頬に突き刺さってしまう。
シェリルは転がった伝令を見下ろした。
「思い知らせてやると言ったな。私をどうするつもりだったのだ。言ってみろ。」
転がった伝令はじっと黙っていた。
「言えと言っているのが分からないのか。いや、分からない訳はないか。つまり、頬を串刺しにして欲しいと暗に言っているのだな。」
シェリルは切っ先をスッと下した。すると、切っ先は頬を斬り裂いて血を滲ませた。
「あああああ!止めてくれ、お願いだ。止めてくれ。」
「頼む、許してやってくれ。」
周りの伝令も慌てた様子で口々にそう言った。
だがシェリルは剣を抜かなかった。
そして伝令たちを見渡した。
その時、シェリルは伝令たちの後ろにエバが何となしに立っているのを確認した。
シェリルは心の中でクスッと笑った。
そして改めて気持ちを引き締めると、伝令たちに向かって言った。
「言ったはずだぞ、書状の回収は城主の為を思ってやるのだと。それが何だ!お前たちときたら、説明が面倒だとか、書状は渡すのはだめだとか、でも諸侯を回るのは嫌だとか、全部自分の都合ばかり、城主の事などこれっぽっちも考えていやしないじゃないか。恥ずかしいと思わないのか。」
伝令たちは、シェリルの思いがけない言葉に唖然とした様子だった。
「伝令の仕事だって城主から任された大切な仕事だろう。書状を届けられない時に、その理由を城主に説明するのもお前たちの大切な仕事だろうが。それを容易に投げ出して、お前たちは城主から任された伝令としての誇りはないのか。」
シェリルにそう言われて、伝令たちは何も言えずに黙っていた。
その伝令たちの様子にシェリルは小さく溜め息をついた。
「こっちは今日中に回らないといけないところ、やらないといけないことが山ほどあるんだ。別に私達は城主がどうなろうと構いやしない、協力しないのならそれで構わない、勝手に困れば良いだろう。」
シェリルは少しの間困っている伝令たちを眺めていたが、それから何か気付いた様子でまた口を開いた。
「それから悪いけど、今この場でお前たちと話をしたやり取りは、使節団の代表がこの城の城主とお会いした時に報告させて貰うから。こっちは城主のことを思って親切心で提案したが、伝令は城主の事よりも自分の都合ばかりで協力しなかったと報告させて貰う。」
「おい待て!何でわざわざそんなことを言うんだ!」
シェリルの目の前にいる伝令の男が慌てた様子で尋ねた。
「分からないのか?我々だって自分の身は守らないといけない。この城の城主と周辺の諸侯との関係が悪化した時に、我々のせいにされたら困るからね。我々は関係悪化とならないよう防ごうとしたが、伝令が協力しなかったのでできなかったと城主に説明するし、必要であれば諸侯にも説明に回る。」
凄いな。あっという間に形勢が逆転してしまった。シェリルを見つめながらビリーはそう思った。
「じゃあ、そういうことなんで、俺たちはもう行きますから、勝手に困ってください。」
ビリーはそう言うと、シェリルに向かって顎で行こうと促した。
シェリルは足元で寝転がっている男から剣を引き抜くと、ビリーの後を追いかけようと後ろを振り返ろうとした。
「待ってくれ。本当に、我々伝令は悪くないのだと、城主殿に進言して貰えるのだな。」
伝令のその言葉に、振り返ろうとしていたシェリルはゆっくりと元に戻った。
「しつこいな。そうだと言っているだろう。」
もう飽きたという様子でシェリルは言った。
「分かった。お前達を信じよう。」
伝令のその言葉に、シェリルとビリーは肩をすくめて両手の平をみせると、やれやれと顔を見合わせた。
それから改めてシェリルは伝令に向き直ると言った。
「じゃあ持っている書状を我々で預かろうと思うが、書状の保管に保管料がかかるから。」
シェリルが何となしに伝令たちにそう言った。
「金を取るのか。」
伝令が怪訝そうな顔をした。
「別に好きで取る訳じゃなくて、大事な書状だから管理に必要な保管料がかかる。1人5ムーナだ。」
「何だと!」
伝令たちは驚いた顔をして、次に嫌そうに顔をしかめた。
「だから言っているだろう。嫌なら別にいいよ。勝手に困れば。」
少しの間伝令たちは、どうするどうすると言い合っていたが、先頭の1人が意を決したようにシェリルに言った。
「分かった、だが・・・、5ムーナは高くないか。」
その言葉にシェリルは片方の口元を引き上げてニヤリとした。
「なら、私が口を利いてやろうか?私の馴染の業者なら3ムーナになる。」
「初めからそう言え!強欲女が。」
伝令がそう言って馬の上からシェリルを汚いものでも見るように見下ろした。女を馬鹿にしている気持ちが言葉に出てしまったようだ。
その言葉を聞いたシェリルは伝令の男を睨みつけた。
「何だその態度は、口利きの話は無しだ。5ムーナだ。」
シェリルの言葉を聞いた伝令の男は驚いた様子で少しの間黙り込んだ。
そしてバツが悪そうにシェリルに小さな声で言った。
「悪かった。」
「何?聞こえないが。」
伝令の男は声を大きくした。
「悪かったと言っている。」
するとシェリルは右手を差し出すと親指を地面に向けて見せた。
「降りろ。」
そう言われた伝令の男は意味が分からずに唖然とした。
「お詫びするのに、馬に乗って高いところからお詫びするなんて、どれだけ失礼を重ねたら気が済むんだ。お前たち、本当に城に仕えているのか?馬から降りろ!」
そう言われた伝令の男はすごすごと馬から降りた。
そしてシェリルの前に立つとまたバツが悪そうにシェリルに言った。
「悪かった。」
「だめだ。」
シェリルはかぶりを振った。
「何だ?」
伝令の男は、もう勘弁してくれと大袈裟に困った表情をした。
だがシェリルは表情を緩めてやらなかった。
何だ。さっきまで偉そうにして女を馬鹿にするような態度を取っていたくせに、形勢が不利となった途端に女に甘えて来るなんて。お前みたいな奴、甘えさせてやるものか。シェリルは伝令の男を見てそう思った。
シェリルは目を細めた。
「そんなのじゃだめだ。一つ、嫌な仕事を我々に押し付けようとした。二つ、私に暴力を振るおうとした。三つ、強欲女と罵った。四つ、高いところから失礼なお詫びをした。お前らの重ねた数々の非礼、そんな謝罪で納得できるか。お前、いくつだ?私より年上に見えるが、いい年になってそんなことも分からないのか?自分の頭で、丁寧で深いお詫びの方法を考えてみろ。」
「・・・。」
伝令の男は抵抗する気も失くして黙って立ち尽くしていた。
シェリルは細めた目で伝令の男を見ていたが、男が黙って動かないので、しようがなく口を開いた。
「分からないのか。しようがないな。じゃあお詫びの仕方を教えてあげるよ。いつも尻尾を振っているこの城の城主にお詫びする時はどうやっているんだ?それと同じやり方で我々にお詫びすればいいのじゃないか。」
少しの間伝令の男は黙ってじっと立っていた。
すると、伝令の男はゆっくりと地面に片膝を突くと、シェリルに対して頭を垂れた。
「申し訳ありませんでした。」
「分かった、許す。じゃあ、一人3ムーナずつ貰うから。」
シェリルはあっさりとそう言って、伝令たちから順番に金を徴収し始めた。
シェリルさんはやっぱり凄いな。シェリルの様子を眺めながらビリーはそう思った。
本当に、シェリルさんが敵じゃなくて良かった。
けれど、シェリルさんと結婚したら完全に尻に敷かれるな。
しかし、シェリルさんのお尻に敷かれるならいいか。
きっと、シェリルさんのお尻を触ったら柔らかそうだし。
ビリーはそう思って一人で苦笑いしていた。
「ビリー、お金はいただいたよ。」
シェリルは一人で苦笑いしているビリーを不思議そうに見た。
「分かりました。では、使節団の代表がすぐ近くにいますのでお連れします。こちらへどうぞ。」
ビリーはそう言うと、伝令たちをエバ達のいる馬車まで案内するため、先頭になって馬を歩かせた。
エバ達のいる馬車がだんだんと近付いて来ると、馬車の向こう側にソフィとエイリスの二人が馬に乗っている姿が見えた。手綱を握っているのはソフィだ。
「おお、これはエイリス姫。」
先頭の伝令がエイリスに声を掛けた。
「いかにも、私はエイリスです。」
エイリスが馴れた様子で、伝令に微笑んで見せた。
エイリス姫の姿を見て、伝令はうんうんと納得したように頷いた。
どうやら伝令たちは、ビリーの話を信じたようだ。
ビリーは自分の馬シルブラウンの歩みを止めると、伝令たちに止まるよう手を挙げた。
「エルファの使節団の代表はこの馬車にいらっしゃいます。」
ビリーがそう言うと、いつの間にか馬車の近くに来ていたシェリルが馬車の扉を開けた。
すると、扉に一番近い席に座っていたロミタスが開いた扉から顔を見せた。
馬車の中には、ロミタスの他にマーリンとマリーウェザーとアレンティーがいた。
馬車は4人乗りだった。
「何だ?こいつら。」
ロミタスは伝令たちを見るとエルファ語でそう言った。
すると、すかさずビリーがマーリンにウィンクして見せた。
するとマーリンは表情を変えることもなく人間の言葉で言った。
「大儀である。ロミタス将軍はそうおっしゃっております。」
伝令たちは、手綱を握っていない右手を胸の前に置くと軽く頭を下げた。
「使節団の代表は将軍なのか?」
頭を上げた伝令たちの1人がビリーに尋ねた。
「ええ、代表はエルファ軍の指揮官、将軍であらせられます。」
伝令たちはおおっと驚きの声を上げた。
「それでは書状をお預かりいたします。」
ビリーがそう言うと、シェリルは伝令たちから書状を受け取って回った。
シェリルは全ての伝令から書状を受け取ると、馬車に乗せた。
「よろしく頼みます。将軍殿。」
先頭にいた伝令がロミタスに向かって軽く頭を下げた。
「何を言っているんだ、こいつらは。」
ロミタスはエルファ語でそう言うとマーリンを見た。
するとマーリンは人間の言葉で伝令に向かって言った。
「良い決断である。ロミタス将軍はそうおっしゃっております。」
マーリンの言葉に先頭にいた伝令の男は頷いた。
シェリルが馬車の扉を閉めた。
ビリーが何か気付いた風に伝令たちに向かって言った。
「使節団の代表をこの城の城主にお連れするのは夕刻になるので、使者殿はそれまでどこか時間を潰していてください。我々がこの城の城主に会う前に使者殿が城主と顔を合わせてしまうと、面倒なことになりますので。」
「そうだな。そうさせて貰おう。」
すると、伝令たちの1人が思い出したように言った。
「そう言えば、騎士殿が衛兵隊長のところに行ったようだが、これはどうしようもないな。」
そう言った伝令は顔をしかめた。
「そうなのか。何をしに行ったのだろう。」
シェリルがその伝令の男に尋ねた。
「恐らくエルファの軍隊が現れたので、街の男達を動員する話をしに行ったのだろう。」
「ふうん。そうか。」
シェリルは分かったように頷いた。
「それでは、我々はこれで失礼します。」
ビリーはそういうと、馬の上からシェリルに右手を差し出した。
シェリルがビリーの右手を握ると、ビリーはシェリルを引き上げて自分の前にシェリルを座らせた。
それからビリーはもう一度右手を挙げると、今度はエバ達に出発の合図をした。
エバ達は進み始めた。
伝令たちは散り散りになって、通りの奥に消えて行った。
「ビリー。」
少し経って、シェリルは後ろに座っているビリーに声を掛けると、小さな袋を手渡した。
「これはさっきの。」
ビリーが袋を握って感触を確かめると、じゃらじゃらとした金属の手触りがした。
さっきシェリルが伝令たちから徴収した金だ。
「馴染の業者さんに大切な書状の保管をお願いしようと思ってね。馴染の業者さん、しっかり頼むよ。」
シェリルは、後ろにいるビリーに顔だけを向けると、まさにいたずら大成功といった感じでニヤリと笑った。
「ははははは。」
ビリーは可笑しくて声を出して笑った。
そのビリーの様子を見て満足したのか、シェリルはとびっきりの笑顔をビリーに向けた。
「終わったらその金で、またみんなで美味しいものでも食べよう。」
「何て書いてあるんだ。」
ロミタスは隣で書状を読んでいるマーリンに向かって尋ねた。
「まあ要するに、兵士を派遣してくれと書いてあります。あと、エルファの軍隊は2,000だと書いてあります。」
マーリンは書状に一通り目を通すと、取り囲んでいる皆を見渡した。
エバ達は、伝令から回収した書状の中身を確認するために、馬車を止めてマーリンに書状を確認して貰っていたのだ。
「2,000だと。我がエルファ軍は500だぞ。4倍ではないか。」
ロミタスがそう言って顔をしかめた。
「この書状何通あるの?ざっと30通以上あるわね。」
マリーウェザーが馬車の中に置かれた書状の束を数えてそう言った。
「マリーウェザー、ちょっと見せて。」
ソフィがそう言うと、マリーウェザーから書状の束を受け取った。
「領内の騎士らに宛てたものと、周辺の諸侯に宛てたものね。」
ソフィは書状を1つ1つ確認しながら、確認した書状をエバに1つ1つ渡した。
なぜかエバは黙って書状の束を受け取り続けた。
「これは、配って回る伝令の人たちも大変ね。」
そう言ってマリーウェザーがマーリンを見ると、マーリンは大袈裟に口をへの字に結ぶと目を大きくさせた。
「でも、書状を回収できたのは本当に幸運だったわね。それにしても、ボワロは戦争する気が満々ね。この書状の数を考えると、恐らく召集される兵士の数は1万にもなる。」
ソフィがそう言ってエイリスを見た。
「ちょっと、それは兵士の数が多すぎない?1万って。森のエルファの人口が1万位なのだけど。エルファを殲滅するつもりなの。」
エイリスが眉をしかめるとそう抗議した。
「確かに多過ぎる。だが、書状の数から考えるとそれくらいの人数にはなりそうだな。」
エバが2人にそう言った。
「とにかく、戦争することが敵の狙いであるのなら、何としてもエルファ軍を止めなければ。」
ソフィはエイリスにそう言うと、エイリスも頷いて見せた。
「どうします?予定通りエルファ軍の駐留している丘に向かいますか。」
ビリーがシェリルに尋ねた。
「うーん。」
するとシェリルは、人差し指を顎に当てて少し考える素振りを見せると言った。
「城の騎士が衛兵隊長のところに向かったと、さっき伝令が話していただろう。動員の話が気になるんだ。先に市政長官のところに行きたいんだがどうかな。」
シェリルはそう言って皆を見渡した。
「特に異論はないが。」
マーリンはシェリルにそう言うと、次に隣のロミタスにエルファ語で通訳した。
「人間世界の事はお前達を信頼している。ここは任せる。」
ロミタスのその言葉を聞いたマーリンはシェリルに頷いて見せた。
「ありがとう。」
シェリルはロミタスに笑顔を見せた。
「行くならさっさと行ってしまいましょう。私はエルファ軍の方が心配だわ。」
ソフィが皆を促した。
「案内できるか。」
シェリルがビリーに尋ねた。
「もちろん。」
ビリーがそう言うと、皆はそれぞれ自分の馬に戻ろうとした。
「ちょっと待ってくれ。」
ロミタスが皆に声を掛けた。
「悪いが、馬に乗せてくれないか。」
マーリンがロミタスの言葉を皆に伝えた。
「どうも馬車は乗り心地が悪くてな。」
この時代、馬車に地面からの衝撃を吸収するバネがついていないため、座席には衝撃を吸収するため厚いクッションが置かれていたが、道の舗装が十分でないこともあって、走行時のガタガタという音と衝撃は相当なものだった。
だがロミタスの場合、狭い閉鎖的な馬車という空間がどうにも性に合わなかった。
「じゃあ、俺の馬に乗ってください。」
キッドがそう言って手綱を引くと馬の向きを変えた。
「キッドはどうするんだ。」
ビリーが声を掛けた。
「そうだな。ルー、交代しよう。俺が御者台に座るから、ルーは馬車に乗ってくれないか。」
キッドが馬車の御者台に座っているルーに向かって右手を挙げた。
「分かったわ。」
キッドは馬車に馬を寄せると、馬車を降りたロミタスはキッドの馬に跨った。
「慣れてますね。」
キッドがそう言うと、ロミタスは言葉は分からなかったが何となく理解して片方の眉を器用に吊り上げて見せると、ニヤリとした笑顔を見せた。
それからキッドは馬車の御者台に座っているルーと交代した。
御者台を降りたルーは馬車の扉を開けた。
「ただいま。」
「お帰りなさい。」
ルーが馬車に乗り込むと、マリーウェザーとアレンティーがそう言って迎えた。
「行きましょう。」
ビリーが左手を上げて皆に合図すると、エバ達は馬を進めた。
馬車に乗っているマリーウェザーは窓から外に目をやった。
お城がだんだんと遠ざかっていく。
太陽に照らされたいくつもの塔が輝いているように見えた。
人が作ったものではあるけれど、その姿は美しく見えた。
人間の街には、豊穣の神サリカ神の大聖堂が必ずあって、その街を象徴する建物となっていたが、やはり城は、それを上回る街の象徴としてその存在感を現している。
この街にいる偽物の領主マックレとボワロはあの城にいて、この街を見下ろしているのだろうか。
するとマリーウェザーは、斜め向かい側に座っているルーが窓の外を眺めている様子を見て声を掛けた。
「ルー、どうしたの。」
「えっ、何。」
ルーは振り返ってきょとんとした顔をした。
「ルーは何を見ているのかなと思って。」
確かに、マリーウェザーとは反対側に座っているルーの座席からは、お城もサリカ大聖堂も見えないし、特に見るものも無い様子だった。
「うーん。実はちょっと考え事をしていて。」
「どうかしたの。」
アレンティーもルーを見た。
「市政長官のところか、と思って。」
「これから行く所でしょ。」
ルーは頷いた。
「なんで?」
マリーウェザーが尋ねると、ルーは少し黙って考えていて、そして口を開いた。
「私はサリカの孤児院で育ったんだけど、同じ孤児院にいた友達のベッキーが市政長官の屋敷で小間使いとして働いているの。」
「そうなんだ。ベッキーは元気なの?」
「元気だと思うけど。」
「けど。」
「最近顔を合わせてないから。」
「じゃあ、顔を合わせなければいいってこと。」
マリーウェザーが顔を傾げてルーを見た。
「うーん、ごめん。違う。何かもやもやするの。」
ルーがかぶりを振って一度視線を外に向けた。
マリーウェザーとアレンティーとマーリンは顔を見合わせると、少しの間黙ってルーの様子を見守った。
ドン!
突然馬車が大きく跳ねた。
「きゃあ!」
馬車が上下に大きく揺れて、マリーウェザーはアレンティーの方に倒れ込んだ。
マーリンはひっくり返って倒れてしまった。
ルーは窓枠にしがみついて耐えた。
「マリーウェザー、大丈夫。」
「びっくりした、すっごく揺れたね。」
ルーは反対側に座っていたはずのマーリンを見た。
マーリンは座席から落ちた格好のままで皆を見上げると、落ち着いた様子で言った。
「みんな、大丈夫か?」
そんなマーリンの様子を見て3人は声を出して笑った。
「何が大丈夫か、よ。お兄様が一番大丈夫じゃないじゃない。」
マリーウェザーとルーが笑いながらマーリンに手を差し出した。
マーリンは2人に引き上げて貰って座席に座り直した。
「悪い悪い、大丈夫だったか?」
御者台に座っているキッドが声を掛けて来た。
「ちょっと、ちゃんと運転してよね。」
ルーが窓から顔を出してキッドに言った。
キッドはルーに了解というように右手を上げて答えた。
ルーは座席に座り直すと、改めてマリーウェザーを見た。
「ベッキーはね、いじめられているんだよね。」
「そうなんだ。」
「そうなの。でも、今まではそんなことは良くある事と思っていたのだけど。シェリルさんと出会って、今思うと何だがもやもやする。」
「良くある事じゃないという事?」
アレンティーが静かにそう言った。
「うーん、しようがないと思っていたけど、そうじゃない事なのかも。」
ルーはそう言うと視線を伏せた。
「なるほどね、それでルーはどうしたいの。」
マリーウェザーはそう言って両腕を組んだ。
「どうしたいんだろう。」
ルーは下を向いたまま頭を左右に振った。
「分からないの?」
「分からない。もやもやする。どうしたらいいんだろう。」
ルーはそう言って、両腕を前に伸ばすとうーっと体を伸ばした。
すると突然マーリンが両手を上げてみんなの注目を集めた。
「どうしたら良いか分からない時は、まず、逆に絶対にしたくないことから考えることをお勧めするよ。」
「そうか、なるほど。」
ルーが小さく頷いた。
「例えば、ベッキーがいじめられているのを、見て見ぬ振りをするというのはどう。」
マリーウェザーが尋ねた。
「それは絶対にしたくない。」
ルーが大きく首を左右に振った。
「そう。なら、見てはいるけど何もしない、というのは。」
「それもしたくない。」
「ということは何かしてあげたいと思っている。だったら、助けてあげたら。いじめている奴をみんなでやっつけるというのはどう?」
マリーウェザーが人差し指を立てるとルーにそう提案した。
「うーん、それはどうなんだろう。」
ルーは両腕を組むと、体を後ろに倒して座席に寄り掛かった。
「ということは、何かしたいけど、やっつけることまではしたくない。その中間あたりのことをしたい、ということね。」
アレンティーがルーの心境をまとめると説明した。
「でも、何で助けてあげるのがだめなの。」
マリーウェザーがルーに尋ねた。
「そこが良く分からない。どう考えればいいのかな。」
座席に寄り掛かったままルーが呟いた。
「シェリル姉さんだったら何て言うかな。」
マリーウェザーもふとそう呟いた。
すると様子を見ていたマーリンがまた両手を挙げた。
「そうだな・・・、いじめられているというのは命の危険があるのかな。」
マーリンがルーに尋ねた。
「それはないかな。」
「お給料が減らされたりとか。」
「お給料はちゃんと貰えているみたい。」
「なるほどな。」
マーリンはルーに大きく頷いて見せた。
そして言った。
「命の危険もなく生活を脅かされている訳でもない。であるなら、あとはベッキーがどうしたいのか、ではないかな。」
マーリンは人差し指を立ててルーにそう言った。
すると、その様子を見てマリーウェザーはくすっと小さく笑った。
「もしかしてシェリル姉さんの物真似なの?」
マーリンは黙ったまま、今度は真顔でマリーウェザーを見た。
「お兄様、努力は認めますが、シェリルに似てはいないです。」
アレンティーが静かにそう言った。
アレンティーにそう言われて、マーリンはすごすごと座席に座り直した。
「ありがとう妹よ。私も今、やったことを後悔しているよ。」
そう言ったマーリンの様子を見てまた3人は笑った。
笑い終わったルーがまた話を始めた。
「そっか、この問題はベッキーがどうしたいのかということなんだね。そもそも私が口を出す問題ではないんだ。だから私は、いじめている奴をやっつけるのは違うと思ったのだと思う。ベッキーが自分で何とかしないといけないんだ。」
ルーの顔が少しすっきりした顔つきになった。
「でも、もやもやしているのはルーの気持ちの問題ではないの?」
「そうだよ、ルーは何かしてあげたいと思っているんでしょ。もやもやしているルーの気持ちはどうするんだよ。」
アレンティーとマリーウェザーがルーにそう言った。
「でも、私のもやもやでベッキーに迷惑を掛けるのは気が引けるよ。」
ルーのその言葉を聞いて、マリーウェザーは口を尖らせた。
ここにも一人で迷惑とか迷惑でないとか勝手に決めている人がいる。マリーウェザーはそう思った。
シェリルがそうだ。
シェリルは行方不明になっていた父親に会いに行った。
けれど、私達には自分の個人の事で迷惑は掛けられないと勝手に思って、夜中にこっそりと一人で旅立ってしまったのだ。
朝起きてその事を知ったとき、マリーウェザーはシェリルが自分の事を信じてくれていないのだと思った。
シェリルは私の気持ちを全然分かっていない。そう思ってとても悲しかった。
辛いことも一緒に共有したい、私はそれくらいシェリルが大好きだし、覚悟だってあるんだから!
マリーウェザーはルーを見た。
「それは違うよ。少なくとも、私は違うよ。大事に思ってくれるのは嬉しいけど、その気持ちをちゃんと教えてよ。もやもやしているなら、もやもやしているってちゃんと言ってよ。迷惑とか迷惑でないとか、一人だけで勝手に決めるのは違うと思う。」
マリーウェザーは力を込めてルーを見た。
「そっか。でも、ベッキーは諦めていると思うんだよね。」
ルーは何となく下を向いてそう言った。
「諦めているのはルーの方じゃないのかな。ちゃんと話したことあるの?そりゃ、友達の人生は友達の人生。だから、乗り越えるのは友達自身の力でなくちゃいけないよね。でも、それが分かった上で応援してあげるのは、いけない事なのかな。」
ルーは顔を上げてマリーウェザーを見た。
「そっか、分かった。でも、ちょっと一人で考えさせて貰っていい。」
「どうぞ、どうぞ。」
マーリンはこの場を仕切り直すようにそう言った。
ルーは馬車の外の風景に目をやると一人で考え始めた。
小間使いのベッキーは、使用人のモーリーにいじめられていた。
でもルーは、そんなことは良くあることと考えていた。
街で世間話をすれば、よく聞く話だと。
それに私もベッキーも親がいないし。一人でお金を稼いで生きていかなければいけない。
しかも私もベッキーも孤児院にまだ弟たちがいる。
生活が安定したら、弟たちとも一緒に生活がしたいと思っている。
だからいじめになんて負けていられない。
絶対に耐えてみせる。そういう気持ちは持っている。
お互いに頑張ろうね。そう言い合って、慰め合って来た。
でもシェリルさんと出会って、耐えているだけでいいのかな、慰め合っているだけでいいのかなって思い始めている。
戦うという選択肢は良い選択なのだろうか。
分からない。
戦った結果仕事を失ってしまうとしたら、戦う意味はあるのだろうか。
でも、マリーウェザーが言うように一人でもやもやしているよりも、もやもやしているということをベッキーに伝えるのは悪い事ではないと思う。
ルーはマリーウェザー達を見た。
「市政長官のお屋敷についたら、ベッキーに気持ちを伝えてみる。」
「いいんじゃない、私も一緒に応援するから。」
マリーウェザーが嬉しそうに両手の平を合わせてそう言った。
「私も。」
アレンティーも続いた。
「ありがとう。」
ルーはそう言うと馬車の扉に手を掛けた。
「ちょっと、どこ行くの!馬車は動いているでしょ。」
マリーウェザーが慌ててルーを止めようとするように手を伸ばした。
するとルーは振り向いてマリーウェザーを見るとニヤリと笑った。
「ちょっとシェリルに話をしてくるわ。」
そう言うとルーは馬車の扉を開け、体を馬車の外にのり出すと、屋根に付けられた捕まり棒にぶら下がった。
そしてぶら下がったまま、中にいるマリーウェザーやアレンティーにニコッとすると、パっと馬車から飛び降り、同時に器用に馬車の扉を閉めた。
ルーは着地するとそのまま走って先を進んでいるシェリルのところに向かった。
「市政長官はどんな人物なんだろう?」
シェリルは横に並んで馬を進めているバクウェルを見た。
シェリルはビリーが手綱を握る馬、シルバーグに一緒に乗っていた。
「ミンチン市政長官だな。話をしたことはほとんどないのだが、まだ市政長官に就任してから1年経っていない。この街で初めての女性の市政長官だ。」
「何!女性の市政長官だって、嘘だろう。あり得ないよ。」
シェリルは瞳を大きくすると驚いた表情を見せた。
「本当ね、女性の市政長官なんて私も初めて聞いたわ。ソンドラは聞いたことある。」
近くで聞いていたソフィが驚いた様子でソンドラに尋ねた。
「そうだね。市政長官になってからよく街で見かけるようになったよ。」
ルードと同じ馬に乗っているソンドラが答えた。
「市政長官になる前は街の役人を勤めていましたよ。」
バクウェルの部下であるルードも、シェリルの方に馬を寄せると話し掛けて来た。
「街の役人を女性が勤めるのも凄いよ。」
シェリルは感心したように頷いた。
この時代、女性は街の運営や管理をする役人になるということはできなかったし、さらに役人の中で要職に就くなどということは考えられない事だった。
「中流の商家の生まれで、街の役人を務めていたが抜擢されて市政長官になった。」
「父親も娘も、相当権力が好きみたいですね。」
バクウェルとルードの説明を聞いて、シェリルの表情が苦笑いに変わった。
「抜擢というよりも、要するに親のコネか。」
シェリルがバクウェルに尋ねた。
「確かにそれもあるが、さらにこの街の有力者たちからの推薦もあったらしい。」
「地位を奪い取ったのか、それは凄いな。」
「まあ、そういう事なんだろうな。」
街の経営は、限られた大金持ちの市民らによって握られていた。
領主は、年に一度財産に応じた税金を払うことを条件に、市民が自ら街の経営に携わることを許可していた。
しかし、その経営に携わるのは大金持ちの市民らによって独占されており、特に高級役人である市政長官、司法長官、衛兵隊長、大市監督官は、この街で名門と呼ばれている8つの一族によって1年ごとの回り持ちとなっていた。
その中でも、市民から税金を徴収し、その金の使い道を管理している市政長官は、権力だけでなく自らの懐に入る金も大きいため、高級役人の中でも特別に魅力的な地位であった。
中流階級の一役人に過ぎなかったミンチンが市政長官に抜擢されたということは、次に市政長官に収まるはずであった名門一族を退け、ミンチンの一族が名門と呼ばれた8つの一族の仲間入りを果たしたことを意味していた。
ミンチンを推薦する有力者がいたということは、そのために人と金の力が必要であっただろうことが想像できた。
「恐そうな人物だな。」
そう言ってシェリルが目を細めると困ったような表情でバクウェル見た。
「いや、街の女性たちからは人気がありますよ。」
シェリルの後ろに座っているビリーがそう言って声を掛けた。
「そうなのか。」
シェリルが半分後ろを振り向いた格好でビリーに尋ねた。
「女性なのに男と対等に張り合っていることが凄いと、結構人気がある。」
「ふーん。」
シェリルが後ろのビリーがそういうのを聞いて、空を見上げた。
「そう言えば、この間も女性達と一緒に街を練り歩いていたな。」
「それなら俺も見ましたよ。」
バクウェルとルードがそう言い合った。
「何が目的なんだ。」
「女性の給料を高くしろって言いながら、たくさんの女性と街を歩いていましたよ。」
シェリルの問い掛けにルードがそう答えた。
この時代、同じ仕事をしたとしても、女性であるという理由だけで給料は男性の半分程度になった。また子どもであればさらに低くなった。
だがそれは当たり前の話であったので、給料を高くしろと主張している女性がこの街に姿を現し始めていることが、シェリルにはたくましく思えた。
「へえ、凄いな。たくましい。何か、この街を見直したよ。」
シェリルのその言葉にバクウェルは笑顔を見せた。
「確かにたくましいですな。女性がたくさん集まると、もう、お手上げですからな。」
バクウェルはそう言って、お手上げというように肩をすくめた。
「ははは。まあ、女性に優しいなら私の話を聞いてくれそうだな。」
シェリルはバクウェルに向かって笑顔を向けた。
「ビリー、交替よ、降りて。」
いつの間に来ていたのか、シェリルとビリーが乗っている馬のすぐ横でルーが走っていた。
「何だよルー、俺とシェリルさんの間を邪魔するなよ。」
ビリーが眉間に皴を寄せると口を尖らせた。
「そんなことどうでもいいから、早く降りなさいよ。こっちは大事な話があるの。」
ビリーは小さく溜め息をつくと左手をルーに向かって伸ばした。
「捕まれよ、引き上げるから。」
ルーはビリーの左手を握った。
ビリーは一気にルーを馬の上に引き上げた。
「それじゃシェリルさん、この続きはまた後で。」
ビリーは額に手をかざしてシェリルに挨拶すると、さっと馬の上から消えた。
「何あれ、すっかりシェリルさんの彼氏気取りね。」
呆れた様子でルーがそう言った。
「まあ、可愛いから許してやろうよ。」
シェリルの言葉を聞いた途端にルーが表情を変えた。
「可愛いですって、どこが。シェリルさんが甘やかすから調子に乗っているのよ。」
「ははは。」
シェリルはしようがなく苦笑いをしてごまかした。
「ところで、ルー。どうしたんだい。」
シェリルは後ろに座っているルーに尋ねた。
「うん。あのね、シェリルさんにお願いがあるの。」
「どんなお願いかな。」
シェリルは思わず笑顔になった。
「ええっと、簡単に言うと、ミンチンさんに伝えて欲しいの。」
「何を伝えればいいのかな。」
前に座っているシェリルの頭が傾げて、髪がふわっとした。
「私の友達のベッキーがミンチンさんの屋敷で働いているんだけど、いじわるなモーリーさんにいじめられているの。」
ルーは手綱を握って前を向いたまま、シェリルの頭に向かってそう言った。
「なるほどね。ベッキーの仕事はモーリーさんにいじめられることなのかな。」
「そんな訳ないじゃない。」
ルーは驚いた顔をしてそう言った。
「それなら、仕事でもないのにわざわざいじめられてやる義理はないよね。」
そう言ったシェリルの頭がまた傾げて、髪がふわっとした。
「ん?そうね。」
ルーはシェリルの頭を見ながらそう言ったものの、シェリルの言っている意味が良く分からなかった。
「それで、ルーはどうするの?」
シェリルの頭が動いてまたルーに聞いた。
「私はベッキーと話をしてみる。ベッキーがどうしたいのか聞いてみる。」
「そう、分かった。ただ、ルー1人じゃないよね。」
「ええ、マリーウェザーとアレンティーが一緒に来てくれるって。」
するとシェリルは一気に振り向くとルーの瞳を力強く見つめた。
「分かった。私は必ずミンチンさんには伝えるから安心して。」
シェリルはルーに笑顔を向けた。
「良かった。ありがとう、シェリルさん。」
シェリルは嬉しかった。
ルーが私にちゃんとやって欲しい事を伝えてくれた。
それはルーが私を信頼しているというだけでなく、ルーが生きるために周りの人間をきちんと巻き込んで生きようという意志の現れだ。
人は一人では戦えない。
周りの人間を巻き込むぐらいのたくましさが必要なのだ。
それならば、私は存分にルーの期待に応えて見せようじゃないか。
シェリルのやる気に火が付いた。
「シェリルさん、あれです。ミンチン市政長官の屋敷は。」
ルーが言った方を見ると、進んでいる通りの左手側に屋敷が見えて来た。
ミンチン市政長官の屋敷は街の大通りであるウェイン大通りから、横道に入ったところにあった。
上級役人といっても仕事をするための事務所が用意される訳ではない。
もともとの自分の仕事をしながら、回り持ちで役人の仕事をするため、自分の住んでいる屋敷が事務所なのだ。
とは言っても、上級役人の仕事は忙しいため、もともとの自分の仕事がおろそかになってしまう。
だから役人の仕事は、1年ごとの回り持ちとされているのが普通だ。
「市政長官の屋敷というよりは、商売をやっている父親の屋敷だろう。」
シェリルは少し離れたところを進んでいるバクウェルに声を掛けた。
「まあ、そうだろうな。」
バクウェルはそう応えた。
ミンチンの場合は、父親の商売は長男が継いでいるだろうから、ミンチンは商売に気を遣う必要はなく、安心して市政長官の仕事に専念できると想像できた。
「もしかして、あれがベッキーかな。」
シェリルが屋敷の前に立っている小柄な女性を見てそう言った。
「そうね、ベッキーだわ。」
エバ達は、ベッキーの前で馬を止めた。
「ルーさん。朝早いですね、配達ですか。」
ベッキーがルーに声を掛けた。
「いいえ、今日は配達じゃないの。ミンチンさんに用があって。」
「えっ、ルーがミンチン様に!何の用なの。」
「私はただの案内役。お連れしたのはエルファのお偉いさんよ。」
ルーは馬から降りると手綱を握ったままベッキーの前に立った。
「ちょっと待ってて、事務員のアメリアさんを呼んでくるから。」
ベッキーは箒を壁に立て掛けると屋敷の中に入って行った。
キッドとビリーはさっと馬から降りると、馬のロープを括り付けておくための横木に素早く馬のロープをくくりつけた。
「少し、大人しくしているんだぞ。」
シェリルがまつげの長い馬の瞳を見つめながら、シルブラウンとプリモを優しく撫でた。
「あの娘は知り合いなのか。」
いつの間にかシェリルの側に来ていたエバが、屋敷に入って行ったベッキーの事をシェリルに尋ねて来た。
「ルーの友達だって。苦労しているらしいよ。」
「なるほどな。」
エバがそう言って目をつぶった。
「ここが市政長官のお屋敷ね。」
馬車からマリーウェザー、アレンティー、マーリンが降りて来た。
4階建ての木造の建物だが、両隣も似たような建物であるので特に目立つということもなかったが、1階は土間ではなく床が貼られていた。
「ミンチン市政長官はどんな方なのかしら。楽しみだわ。」
「話の分かる方だといいわね。」
ソフィとエイリスがそう言ってエバの側に立った。
すると屋敷の扉が開いて1人の女性が現れた。
「まあ。」
その女性は目の前の人の多さに驚いたようだ。
女性の後ろからベッキーも出て来た。
「えっと、何の御用でしょうか。」
女性が誰にというわけでもなく問いかけた。
するとバクウェルが女性の前に進み出た。
「ガヤンのバクウェルだ。ミンチン市政長官はいるかな。」
「ミンチン様は10時以降でなければお会いになりません。」
その女性は少しおどおどした様子でそう言った。
女性の言葉を聞いたバクウェルは、後ろを振り返ると、シェリルに向かって眉毛を上げた顔を見せた。
そして元に戻るとその女性に尋ねた。
「失礼だが、あなたは。」
「私は事務員のアメリアです。ですが、ミンチン様から誰も通さないように言われています。」
アメリアはおどおどしているものの通すつもりはないようだった。
バクウェルは食い下がった。
「至急の話なんだ。一度掛け合ってくれないか。」
「それは・・・、難しいです。一度お引き取りください。」
「なるほど。」
バクウェルがため息をついた。
するとシェリルが大股で歩いて来ると、バクウェルの肩を叩いてアメリアの前に立った。
「分かったよ。それなら、そこをどいて貰えないか。」
「何ですか?」
アメリアが不審げな眼差しでシェリルを見た。
「こっちは重大な案件で来ているんだ。残念ながら、お前が事務員を首になるのだとしても帰る訳にはいかない。無理矢理通らせて貰う。」
シェリルは腰に提げた剣に手を添えると何気なくアメリアに見せた。
アメリアの表情に緊張が走った。
「安心しろ、話をしに来ただけだ。それにお前の事は悪く言わないから。」
シェリルはそう言うと、じっと固まっているアメリアの耳元に口を寄せた。
「お前は脅されて無理やり道を開けさせられた。そうだろう。」
シェリルはそう言うと、そのままアメリアの横をすり抜けて屋敷の中に足を踏み入れた。
「みんな、行くぞ。」
シェリルが振り返って手を挙げた。
エバ達もシェリルに続こうと足を上げた。
「シェリルさん。」
ルーが声を掛けた。
「ちょっとベッキーと話をして来るわ。」
「分かった。終わったらそっちに行くから。」
シェリルがルーに笑顔を見せた。
「シェリル姉さん、私達もルーと一緒に行くね。」
マリーウェザーがシェリルに声を掛けると、それに合わせてアレンティーもシェリルに向かって頷いた。
「行ってらっしゃい。危ない事は止めてね。」
「分かった、大丈夫だよ。」
シェリルはそう言って屋敷の奥に進もうとした。
「ミンチン様の部屋は、正面の階段を上って奥です。」
事務員のアメリアが手で示しながら大きな声で言った。
「分かった、ありがとう。」
シェリルはそう言って、玄関から続く階段に向かって進み始めた。
建物は奥に長い長方形の形をしていた。
階段を昇ると、シェリルはそのまま突き当りの部屋に向かって歩いて行った。
「ここだな。」
シェリルは迷いもなくコンコンコンコンとドアを4回叩いた。
「何ですか。アメリア、10時以降と言ったはずですよ。」
中から女性の声がした。
「アメリアはいないよ。」
シェリルは扉越しにそう答えた。
すると部屋の中を扉に向かって歩いて来る人の気配がした。
そして扉が少し開くと、その隙間から女性が姿を現した。
目つきが鋭く鼻が高い女性だが、不機嫌な様子で余計に目が吊り上がって見えた。
「誰ですか、お前は。」
目つきの鋭い女性はシェリルに声を掛けた、すると慌ててバクウェルがシェリルの前に身を乗り出した。
「ガヤンのバクウェルです。」
バクウェルは口元を少し緩めてニコッとした。
「何ですか、大勢で押し掛けて、失礼です。出直して遊ばせ。」
女性は扉を閉めようとした。
するとシェリルが閉まろうとする扉を押し止めた。
「悪いがこの街の重要な事で来たんだ。無理矢理でも話を聞いて貰う事になるが。」
そう言ったシェリルを女性は睨みつけた。
「ふざけないでください。私を誰だと思っているんですか。」
女性は扉を抑えているシェリルの手を払うと扉を閉めた。
そして扉に内側から閂を掛ける音が聞こえた。
「さっさと帰りなさい。さもないと衛兵を呼びますよ。」
締めた扉の向こうから女性の声が聞こえた。
「あの人誰?」
ソフィがバクウェルに尋ねた。
「ミンチン市政長官だ。」
バクウェルが渋い顔を見せると、ソフィとエイリスが驚いた顔を見せた。
「思っていたのと全然違う。」
「女性に人気があるって本当なの?」
そう言ってソフィとエイリスはビリーを見た。
「いやいやいや、本当だって。俺は街で聞いたんだから。」
2人の女性に詰め寄られてビリーが思わず後ろにのけ反った。
「つまり、外にはいい顔をしているけど、中に向けては豹変する部類の人間ね。」
ソンドラがソフィとエイリスに声を掛けた。
「何で外と中で態度が変わるのかしら。同じにできないの?」
ソフィがそう言って不満そうに腕を組んだ。
そんなソフィの様子を見てソンドラは思わずふふっと笑った。
これまでソフィは存在を消して生きてきたというのに、まるで自分は生まれつき裏表がない人間であるかのような口ぶりではないか。
ついさっきまで外の世界から隔離された世界で生きて来たというのに。
「ソンドラ、何笑っているの。」
ソフィがソンドラを目を細めて見た。
「いえ、何でもありません。」
ソンドラが別にという感じで答えた。
「どうしますか、シェリルさん。」
ビリーが顔をしかめるとシェリルを見た。
「問題ない。ミンチンはいいネタを提供してくれたよ。」
シェリルはそう言うと、面白いいたずらを思いついた少年のように、ニヤリとした笑顔をビリーに向けた。
シェリルは通路の壁に寄り掛かって立っているエバを見た。
「エバ、この扉を蹴破れるか。」
「任せろ。」
エバが壁から体を起こすと歩いてきた。
「おいおい、ちょっと乱暴じゃないか。」
バクウェルが心配そうにシェリルを見た。
「問題ない、やってくれ。」
「そういう事なら、俺も手伝いますよ。」
ビリーがエバの隣に立った。
「じゃあ、ビリーは取っ手側の方を頼む。扉に横木がついているだろう。そこを蹴るんだ。」
「オーケー。」
エバが扉の蝶つがい側、ビリーが取っ手側に立った。
「せいの!」
「大事な話って。」
ベッキーがルーに尋ねた。
シェリル達が屋敷に入った後、マリーウェザー、アレンティー、ルーそれにベッキーが外に残っていた。
「ええっと、」
ルーが戸惑った様子を見せた。
「ルー、私が話をしてもいい?」
マリーウェザーが横からルーに声を掛けた。
人に嫌われるようなことを言うのは気が引けてしまう。
すると伝えたいことが正確に伝えられなくなる。
こういう時は、ベッキーの友達ではない、関係のない私が言う方がきちんと伝わるはずだ。
「私はルーの友達のマリーウェザー、こっちは妹のアレンティー。」
マリーウェザーがベッキーに自己紹介した。
「こんにちは。」
アレンティーがそういってベッキーに微笑んだ。
「姉妹なんだ。」
ベッキーがそう言った。
ベッキーは初めて会った人と話をしているためか、おどおどした様子だった。
「そうよ。で、ルーがね、あなたの事でもやもやしているの。」
「もやもやしている?」
ベッキーが分からない顔をした。
「あなたいじめられているでしょ?このままでいいのかなって。ルーも分からないんだって。」
マリーウェザーは何でもないことというように、さらっとそう言った。
いじめられているとか、こういう言い難い事をさらっと言うのも、私みたいに関係ない者が間に入った方が話がし易いのだ。
「悪いけど、あなたには関係ないと思うのですが。」
ベッキーが嫌そうな顔をした。
「そんなことは関係ないから、とにかくあなたがいじめられていることが、ルーはもやもやしているんだって、話を聞いてあげて。」
関係ないということは関係ない。マリーウェザーはそう思った。
それに、私の役割はベッキーに必要な事を伝えること。
ベッキーが私に嫌な顔をしたとしても、それこそ私の役割には関係ないのだ。
「そうなんですか。」
ベッキーはルーに尋ねた。
「そう。ベッキーはモーリーにいじめられているよね。」
「そうですけど、雇ってもらっているし、しようがないと思うんですけど。ルーもそう言ってたよね。」
「そうなんだけど、本当にそれでいいのかなって。」
ルーは首を傾げると迷っている表情を見せた。
「でも、じゃあ私はどうすればいいんでしょうか。」
ルーが迷っている表情を見て、ベッキーも分からない顔をした。
「どうすればって、ベッキーがどうしたいのか聞きに来たんだけど。」
ルーはベッキーと分からない顔を見合わせた。
「私が・・・、私は頭も悪いし、良く分かりません。」
やっぱりね。ベッキーの姿を見てルーは思った。
ベッキーは諦めているのだ。
そうである以上、戦うなんて無理だ。やっぱり耐えるしかないのだ。
「ベッキーはこのままずっといじめられ人生でも嫌じゃないの。」
マリーウェザーがルーに尋ねた。
「それは嫌ですけど。」
ベッキーが下を向いてそう言った。
「嫌なら止めて貰うように言おうよ。」
マリーウェザーはベッキーの目を見つめた。
「でも・・・、騒ぎを起こして仕事を首になるのは嫌です。」
ベッキーはそう言って目を伏せた。
「ちょっと、マリーウェザー、無理矢理は止めようよ。ベッキーがどうしたいのかでしょう。」
ルーが慌てた様子でマリーウェザーに強い調子で言った。
「別に無理矢理しているつもりはないけど。ベッキーがどうしたいのか聞いているだけよ。」
「そうなのかな。」
マリーウェザーも強い調子で言い返すと、ルーにはどうなのか良く分からなくなってしまった。
マリーウェザーは改めてベッキーを見た。
「じゃあ仕事を首にならなければ、言いに行くことはいいんだよね。」
「そうだけど。」
マリーウェザーが尋ねるとベッキーは頷いた。
ベッキーが頷いたのを見て、マリーウェザーは続けた。
「だったら安心して、私達にはすっごく頼りになる仲間がいるから。首にはならないと思うわ、ね。」
マリーウェザーはベッキーにそう言うと、ルーに向かってニコッとした。
するとマリーウェザーを見たルーもはっとした表情をした。
ルーの心の中のもやもやが、だんだんと薄らいで来ているように感じた。
「本当。」
ベッキーがマリーウェザーに尋ねた。
するとマリーウェザーの替わりにルーが口を開いた。
「それは本当よ。今の私達には力になってくれる強い仲間がいるから。」
そうだ、今ならシェリルが力になってくれる。ルーはそう思った。
私はシェリルに事前に話をしておいたのだ。
恐らくシェリルだけでなく、エバもマーリンもみんな力になってくれる気がする。
ベッキーは仕事を首になるのが嫌なのだ。
でも首にならなければ、言いに行っても良いと言っている。
だったら。
ルーの胸の中のもやもやはすっかり消えていた。
「今からモーリーさんに言いに行こうよ。」
「えっ!今からですか。」
ルーの言葉にベッキーは驚いた顔をした。
「そう、今よ。」
「今すぐは・・・、私、もっとお金を稼いだら孤児院にいる弟たちを呼んで一緒に生活しようと思ってるんです。なので、それまで待って貰う訳にはいかないですか。」
「それは、」
ベッキーの言葉を聞いてルーは言葉に詰まってしまった。
するとアレンティーがベッキーに向かって言った。
「弟と一緒の生活が始まったら、余計にその生活を失うのが恐くなってしまうわよ。そうなったらモーリーさんに言いに行くことなんて無理になってしまうわ。それに、今なら私達も力になってあげられるけど、この機会を逃したらもう二度と来ないかもしれないわよ。」
アレンティーの言葉を聞いても、ベッキーはまだ迷っていた。
「いきなりそんなこと言われても、私どうしたら良いのか。」
「何言っているの!いきなり起こるのよ。洪水だって疫病だって戦争だって、いきなり起こるんだから。だから、目の前の起こっていることから目を逸らさないで。ちゃんと考えて見て。」
マリーウェザーが居ても立っても居られない様子でベッキーにそう言った。
「ルーはどう思う。」
ベッキーはルーに尋ねた。
「私はね、初めはそんなこと止めた方がいいと思ってた。我慢するしかないんだって。今まではお互いにそう言い合って来たよね。でも、今はベッキーがやる気なんだったら応援したいと思ってる。もしベッキーが一生いじめられてひたすら耐えるだけの人生で良いというのなら、それでもいいと思ってる。だけど、人生のどこかで、いじめられない人生にしたいというのなら、今しかないと思う。私は、ベッキーがやる気なら一緒にやるよ。」
ルーが力強い目でベッキーの目を見つめた。
「どう、一緒にやらない?私も全面的に協力するから。」
マリーウェザーもベッキーに言った。
ベッキーはとうとう覚悟を決めた。
「分かりました。恐いけど、私やってみます。」
ベッキーの言葉にルーもマリーウェザーもアレンティーも笑顔になった。
「良かった。」
「一緒に頑張りましょう。」
皆でそう言い合うと、アレンティーが口を開いた。
「でも、問題はこれからよ。」
「じゃあ、作戦会議をしなきゃね。」
マリーウェザーが皆を見渡して言った。
「作戦会議。」
ベッキーが首を傾げた。
「そうよ。行動する前に良く考えてから行動しなければいけないからね。」
マリーウェザーはそう言うと、シェリルを真似て人差し指を顎に当てた。
「せいの!」
エバとビリーが扉に蹴りを加えると、蝶つがいが外れ、閂がバキっと折れて、扉が大きな音を立てて吹き飛んだ。
「結構簡単に壊れるのね。」
両腕を組んだソフィが、何か納得したように頷いた。
「石造りの城ならともかく、土壁に木枠をはめた扉なら、扉の厚さも薄いし、まあこの程度だ。」
エバがソフィに説明した。
扉がなくなった向こう側に、机に座って大きく目を見開いているミンチン市政長官の姿があった。
「なっ!何をしているのお前達は!」
ミンチンはかん高い声で叫ぶように言った。
「お前、目が付いているんだろう。見て分からないのか。」
シェリルはミンチンをあざけるようにそう言った。
「私の事をお前とは、失礼でしょう!」
ミンチンがまた叫んだ。
するとシェリルは、両手の平をミンチンに見せると呆れた表情を見せた。
「何を言っているんだ、お前が私の事をお前と呼んでいるんだろうが、私が失礼だと言うなら、まずはお前が私に非礼を詫びるのだな。そうしたら考えてやる。」
「何で私が謝罪しなければならないの!扉を壊したのはお前でしょう!」
ミンチンは怒りが収まらない様子で、机を平手で叩いて見せた。
だがシェリルは特にひるむ様子もなかった。
「私はお前にはっきりと言ったぞ。街の重大な案件だから無理矢理でも話を聞いて貰うと。みんな、私はちゃんと伝えたよね。」
シェリルはバクウェルを見た。
バクウェルは一瞬目を大きくさせてシェリルを見ると、眉間に皴を寄せて拳でトントンと自分の額を叩いた。そして1つ咳払いをすると言った。
「確かにシェリルは、あなたに警告したな。」
シェリルはバクウェルを見て、それから皆を見渡して満足そうに頷くと、ミンチンに向き直った。
「ここにいるのは全部私の証人だ。警告を無視したのはお前なのだから、お前自身の責任だ。」
「何ですと。」
ミンチンは思わず歯ぎしりした。
確かにこの場には、シェリルにはたくさんの証人がいるが、ミンチンは自分1人だけ。
この時代の裁判は、法と契約を象徴するガヤン神の前で、嘘偽りがないことを宣誓した証人の人数が判決に重要な影響を与えた。
証人の数が多いほど、確かである、嘘ではないと考えられていたからだ。
シェリルは大股で部屋の中を一気に抜けると、足を高く持ち上げミンチンが席についている机をドンと足で踏みつけた。
そしてミンチンを睨みつけると言った。
「街の重大な案件だと言ったろう、10時以降でないと会わないとはどういう了見だ。」
「あなたには関係ないでしょう。私がそう決めているのです。絶対に会いません。」
ミンチンが興奮した様子でそう言うと、シェリルは片方の口元を引き上げてニヤリと笑った。
「ほう、なるほど。それなら、国王が大変だと言ってお前を訪ねて来ても、10時前なら追い返すんだろうな。」
「・・・。」
ミンチンが答えに窮して黙り込んだ。
「どうなんだ、はっきりしろ!追い返すんだな。」
もしミンチンが追い返すと言えば、国王を侮辱したとして不敬罪に問われる可能性があった。
しかも目の前にいるバクウェルはガヤンの神官だ。
ガヤンというのは正義と法の神であり、その神の教えを実践している信者達は、そのガヤンの法を犯す悪人を捕まえ、法の前で裁く権限を国王から与えられていた。
さらにガヤンの信者は、国王を含め王宮に対する罪を取り締まり、裁く権利も与えられていた。
ガヤンのバクウェルがミンチンに鋭い視線を送った。
「それは・・・、ありません。」
ミンチンが力なくそう答えた。
シェリルが目を細くするともう一度ドンと足でミンチンの机を踏みつけた。
「ふざけるな!お前はたった今、そう決めていると言ったばかりじゃないか。それがどうした。決まっていないじゃないか。」
「絶好調だな、シェリル。」
壁に寄り掛かったエバがぼそっと独り言のように言った。
「もう私達が出る幕もない感じね。」
ソフィがそう言ってエバを見た。
エバは思わず肩をすくめると目を閉じて見せた。
するとマーリンが何となしにエバに近付いた。
「エバ、屋敷の前に男が2人いる。剣を腰に提げている。」
マーリンがエバにそう囁いた。
「どっちの入り口に入るか分かるか。」
エバは目を閉じたままそう言った。
エバは2人の男が屋敷の正面玄関か、それともベッキーのような使用人が使う裏口か、どちらから入るのかと確認した。
マーリンはエバを見ながらも、どこかあらぬ方向も見ているような様子で少しの間じっとしていた。
マーリンは魔法使いなのだ。
そしてマーリンはエバに言った。
「正面玄関の方だ。事務員のアメリアが話しをしている。」
「分かった。」
エバは目を開けると、タタッと自分達が上って来た階段の横に移動すると壁に寄り掛かった。
すると、おしゃべりをしながら複数の人間が階段を上って来た。
エバは階段を上って来る最初の人物の頭が見えた瞬間、斜め後ろからスッと近付いて、右手で上から髪の毛を掴んで顔を上向かせると、同時に首元に抜いた剣を当てがった。
男だった。マーリンが言ったように確かに2人。
その2人の後ろに事務員のアメリアがいた。
「剣を捨てろ。」
エバが言うと、男は腰に提げた剣を階段に落とした。
落とした剣が階段を滑り落ちて行った。
「お前もだ。」
エバは2人目の男にも言った。
2人目の男も大人しく、腰に提げた剣を階段に落とした。
「余計なことはするな、姿を消していろ。」
エバはアメリアにそう言うと、アメリアは慌てて階段を降りて行った。
「ゆっくりと上がって来い。」
男2人はゆっくりと階段を上がって来た。
階段を上がると、エバが髪の毛を掴んでいる1人目の男はエバよりも一回り体つきが大きい男だった。
2人目の男は男性としては標準的な大きさで、腹が出ていた。
「エバ、手伝いましょうか。」
ソフィが両腕を組んだ格好で、エバに首を傾げて見せた。
ソフィがビリーと一緒に近くに来ていた。
「じゃあ、こいつを捕まえておいてくれないか。」
エバは2人目の腹が出た男を顎で示した。
ソフィは腹が出た男の右手を取った。
「お嬢さん、あなたのような美しい人には、乱暴なんて品の無い事は無理だよ。」
腹が出た男はソフィに微笑んだ。
するとソフィも微笑み返した。
「私はあなたの理想の女性になるつもりはないわ。」
ソフィは男の右手を背中に回すと手首の関節を極めた。
「いい!」
腹が出た男は痛みで思わず苦悶の声を上げた。
「変な事はするなよ。」
ビリーが2人の男にそう言った。
「エバさん。その方は城の騎士様と衛兵隊長ですよ。」
バクウェルの部下のルードがそう言って近づいてきた。
「お主は。」
エバに髪を掴まれている騎士様と呼ばれた大柄な男がルードに尋ねた。
「私はガヤン神官のルードと申します。」
「であれば、この男の剣を下ろさせてくれぬか。」
大柄な男がルードに指示した。
「だめだ、お前が誰であろうと関係ない。俺たちの用事が済むまでこのまま大人しくしていて貰おう。」
エバがあっさりとそう言った。
「抵抗はしない。それにもう丸腰であるぞ。」
大柄な男は食い下がった。
「だめだ。信用して欲しければ大人しくしていることだ。ビリー、ロープはあるか。」
「馬の所に行けば。」
「取って来てくれ。」
「了解。」
ビリーが素早く階段を駆け下りて言った。
「何ですかお前は。私が誰だか分かっているのですか!」
部屋の中では、ミンチンがシェリルに大声を出した。
「知らないね。今日初めて会うんだから。」
シェリルが座っているミンチンを見下ろすとそう言った。
「何ですか!この街の市政長官、ミンチンですよ。知っていて当たり前でしょう。あなたこそ失礼です。もう顔も見たくない。とっとと出て行きなさい!」
ミンチンが椅子から立ち上がると、また机をバンバンと叩いた。
ミンチンは、この厄介な無礼者を何とか目の前から消し去ろうと必死な様子だった。
「失礼するぜ。」
ビリーがそう言うと、ロープで両手を後ろ手に縛られた男が2人小さくなって部屋に入って来た。
シェリルとミンチンも何事かと思わず目を向けた。
「そこに座れ。」
エバが2人に指示すると、男2人は部屋の中にあった長椅子に腰を下ろした。
そしてエバは、腰を下ろした2人の男の後ろに立った。
男2人はバツが悪そうにミンチンを見た。
「これは衛兵隊長と騎士様。どうしました。」
ミンチンが驚いた表情で2人を見た。
「いや、気にしないでくれ。少し話があって寄ったのだが、先客の用事が終わってからでいい、な?」
腹の出た衛兵隊長がそう言って、大柄な男の騎士を見た。
「そうだ。まだ10時前だし、もともと待っているつもりだったのだ。」
腹の出た衛兵隊長と大柄な男の騎士は何でもないからという風を装ってそう言った。
助けようとして捕らえられてしまったとは、恥ずかしくてとても言えなかった。
もしこの話が広まってしまったら、街中の笑い者にされるのが必至だ。
「邪魔したな、続けてくれ。」
エバがシェリルに向かってそう言うと、シェリルは一つ咳払いをすると、気を取り直して話に戻った。
「お前が誰なのか知らないから失礼だとか、自分で言っていておかしいと思わないのか。」
シェリルが軽蔑するような目つきでミンチンを見た。
「どこがおかしいのですか?自分の街の市政長官ですよ。知らない方がおかしいのです。つまり、あなたがおかしいし、失礼です。」
ミンチンはシェリルに向かって指を突き付けた。
「じゃあ聞くが、この街の全ての住人が市政長官の名前を知る方法があるのか。」
「そんなこと、街の掲示板に告示されます。」
「告示が剥がされた後にこの街に来た人はどうするんだ。」
「周りの人に聞けばいいでしょう。」
「なら、たまたま周りに知っている人がいなかったらどうするんだ。この街には、市政長官が誰かを周りの人に聞かなければならないという法律でもあるのか。」
「そんな法律、ある訳ないでしょう。」
「だったら、街の住人の全てが市政長官を知っている訳はないだろう。違うのか。」
シェリルの言葉にミンチンが答えに窮して黙り込んだ。
「どうなんだ!」
シェリルがドンと足でミンチンの机を踏みつけた。
「・・・まあ、そうでしょうね。」
ミンチンが力なくそう答えた。
「よく考えなくても分かるだろう。街の人間であるかどうかなんて関係なく、お前のことを知っている人もいれば知らない人もいる。それが当たり前だ。そんなこと、失礼なことでも何でもない。」
ミンチンはただ黙っていた。
「お前もしかして、私以外にもいままでこうやっていじめて来たのではないだろうな?」
シェリルは視線を鋭くしてミンチンを見た。
ミンチンはただ黙っていた。
するとしようがないという風に、シェリルは両手の平をミンチンに見せると肩をすくめた。
「我々はエルファの使節団だ。街の北側の丘を越えたところに現れたエルファの軍隊の話でここに来た。」
「何ですと。」
シェリルの言葉にミンチンは驚いた表情を見せた。
衛兵隊長と大柄な男の騎士も驚いた表情で、お互いに顔を見合わせた。
「だが、この街の市政長官ときたら、街の重大案件だと言っているのに話も聞かない。自分でお前と言っているくせに自分が言われると失礼だと言い掛かりをつける。10時以降でないと会わないと嘘を付く。市政長官の名前を知らないのは失礼だと言い掛かりをつける。こんなくだらないことで馬鹿にされたならもういい、もう結構だ。お前に話しをすることはない。」
シェリルは机からようやく脚を下ろすとミンチンに背を向けた。
そして顔だけを後ろに向けると横目でミンチンを見た。
「我々は今日、この街の領主に会いに行く予定だ。その時には、お前の事はしっかりと領主に報告させて貰うから。さらに、この街の参事会総裁にも苦情を入れさせて貰う。お前は市政長官には相応しくないとね。せいぜいお前の得意な言い訳を考えておくといい。」
そう言うとシェリルは前を向くと部屋から出て行こうとした。
参事会とは、この街を市民が経営する際に、重要な事を決めるための最高決定機関である。
12人の審議役によって構成されており、その審議役が市政長官、司法長官、衛兵隊長、大市監督官などの要職を務めていた。
参事会においては、その12人の審議役がそれぞれ1票を投じて、多数決によって物事が決定された。よって、それぞれの審議役は同じ1票を投じる権利を持ち、審議役に優劣はなく平等であったが、表向きに参事会の代表が決められており、それが参事会総裁だった。
「まっ、待ってください。」
ミンチンが声を掛けた。
シェリルは足を止めた。
「私が悪かった。」
ミンチンが立ったままでそう言った。
「何?」
シェリルはゆっくり振り返るとミンチンを睨んだ。
「私が悪うございました!」
ミンチンはそう言って頭を下げた。
するとシェリルはまた大股でミンチンに近付くと、足を高く持ち上げミンチンの机をドンと足で踏みつけた。
「私に謝ってどうするんだ。私の話を聞いていなかったのか、我々はエルファの使節団だ。謝るならエルファの代表に、だろうが。どれだけ無礼を働けば気が済むんだ。親からそう教わったのか。両親はお前にどういう教育をして来たんだ。もういい、お前じゃ話にならない。親御さんに会わせて貰おうか。直接苦情を言って謝罪して貰おう。そうでなければお前に話などしない。」
ミンチンの顔から血の気が失せた。
「りょっ、両親なんて。そんな、みっともない。」
「そのみっともないことをしているのはお前だよ!もういいから、我々は失礼する。」
ミンチンにとって、両親はとても尊敬している存在だった。
それに、両親にとってもミンチンは誇れる娘だった。
市政長官になるためにどれほど両親が力になってくれたか。
そして、市政長官となった自分にどれだけ期待しているのか。
ミンチンには痛いほどそれが解った。
その両親を、自分の失敗のために頭を下げさせるなどと、こんな屈辱的な事はさせる訳にはいかなかった。
「待ってください。」
ミンチンはシェリルに近付くと目の前に立った。
そしてシェリルの前でおもむろに膝を突くと、頭を垂れた。
「私が申し訳ございませんでした。このとおり、二度とこのようなことがないよう深く反省いたします。ですから、どうか私にご慈悲をお与え下さい。」
ミンチンは震える声でそう言った。
シェリルはミンチンを黙って見下ろした。
そして言った。
「分かった。だが、言っただろう。謝るなら代表にだ。」
そう言って、シェリルは扉の外に立っているロミタスを手で示した。
ミンチンは立ち上がり、ロミタスの側まで歩いて行くと、同じように膝を突いた。
「申し訳ございませんでした。」
ミンチンを見下ろしてロミタスは言った。
「また俺を都合よく利用しているだろう。」
ロミタスはエルファ語でそう言って、シェリルに向かって片方の眉を器用に吊り上げて見せると、肩をすくめた。
そんなロミタスにシェリルは笑顔を見せた。
ちょっとやり過ぎたかな。シェリルは思った。
しかし、ルーのお願いとあっては手を抜く訳にはいかない。ミンチンには申し訳ないが、ミンチンには私の言う事を全て呑んでもらおう。
「おい!ちび豚。何を油を売っているんだ!仕事が溜まっちまったじゃないか!さっさと片付けるんだよ!」
ベッキーが厨房に戻ると、使用人のモーリーが眉間に皴を寄せて怒りを露わにした。
だがそう言われてもベッキーは、ただじっと突っ立っていた。
「ちび豚!何をボーっと突っ立っているんだよ。豚だから言葉が分からないのかい!」
動かないベッキーを見て、モーリーはもう一度声を荒げた。
すると、ベッキーの横にルー、マリーウェザー、アレンティーが姿を現した。
「何だい、あんた達は。」
モーリーは眉間に皴を寄せたままルー達に尋ねた。
「ベッキーの友達よ。モーリーさん、あなたに用があって来たの。」
ルーが答えた。
ルーは心臓のドキドキがいつもより大きく感じられた。
この恐そうなモーリーと対決するのだ。
気持ちを強く持たなければ。
ルーは握った両手に力を込めた。
「私に用だって。」
モーリがそう言うと、ルーはモーリーに頷いてみせた。
「ベッキーをいじめるのを止めて貰いに来たの。」
ルーの言葉を聞くと、モーリーは馬鹿にするように口元に笑みを浮かべた。
「はっ、何言っているんだい。私がこの豚をいじめているだって、そんな訳ないだろう。大体、豚が言う事を聞かなかったら叩いて言うことを聞かせるのは当たり前だよ。」
モーリーの言葉にマリーウェザーが思わず口を開いた。
「何を言っているのよ。ベッキーは人間よ。見て分からないの?」
「覚えは悪いし、仕事もとろいし、豚って呼んで何が悪いんだよ。ちっこいからちび豚さ、ぴったりの名前だろ。」
悪げもないモーリーのその態度に、ルーもマリーウェザーも呆れて言葉もなかった。
するとアレンティーが静かに言った。
「分かったわ。じゃあ、人間と豚の違いが分からないモーリーさんは、これからは馬鹿って呼んでもいいかしら。」
その言葉を聞いたモーリーは豹変した。
「何で私が馬鹿なんだよ!」
だが豹変したモーリーを見ても、アレンティーは動じる様子もなかった。
「あら、人間と豚の違いも分からないんだから馬鹿って呼んで何が悪いの。モーリーさんにぴったりの名前でしょう。」
アレンティーがまた静かに言った。
モーリーは咄嗟に何か言おうとしたが、言葉が出てこないようで、あうあうと口を動かした。
そして何とか言葉を捻りだした。
「生意気なんだよ、小娘の癖に。」
アレンティー凄い。ルーはそう思った。
そして勇気が湧いてきた。
私も頑張らなければ。
「モーリーさん、馬鹿って呼ばれて気分はどうですか。」
ルーがモーリーに尋ねた。
「いい訳ないだろう。」
モーリーがそう言った。
「そうでしょう。ベッキーだって一緒だよ。」
「何言ってるんだ、ベッキーは呼ばれて喜んでいるんだよ。」
モーリーが当たり前のような顔をしてそう言った。
「そうなの?ベッキーは喜んでいるの?」
ルーがベッキーに尋ねた。
「喜ぶわけないじゃないですか。私だって、豚と呼ばれるのは嫌です。」
ベッキーの言葉を聞いて、ルーは大きな声でモーリーに言った。
「モーリーさん、聞こえた?ベッキーはずっと嫌だったんだって。」
「分かったよ!止めればいいんだろ!止めれば。」
モーリーは、うるさい蠅でも追い払うようにそう言って嫌な顔をした。
モーリーは厨房にある椅子に腰を下ろすと、顔をルー達とは反対側に向けてテーブルに頬杖を突いた。
ベッキーはたくさんのジャガイモを水場に運んで、水洗いを始めた。
「いつまでそこにいるんだよ。」
モーリーは部屋の入り口辺りで立っているルー達を見て言った。
「私達がいなくなったら、ベッキーがいじめられるかもしれないでしょ。」
「勝手にしろ。」
モーリーは話にならないとうように両手の平を見せると、顔を背けて頬杖を突いた。
その様子を見てルーはまた口を開いた。
「ちょっとモーリーさん。ベッキーだけ働かせて何でモーリーさんは休憩しているの。」
するとモーリーはカッとなってルーを睨んだ。
「うるさいね!そんなこと私の勝手だろ!」
恐い。ルーは思った。
小刻みに自分の手が震えているのが分かった。
でも負けられない。
「洗っていない人参が山ほどあるわよ。何で洗わないの。」
「しつこいね。洗うのはちび、じゃなかった、ベッキーの仕事なんだよ。」
モーリーの言葉に今度はマリーウェザーが口を開いた。
「何でベッキーの仕事なの?モーリーさんも一緒にやれば早く終わるじゃない。何で仕事しないの。」
「私は他に仕事があるんだよ。」
モーリーの言葉にマリーウェザーがかぶりを振った。
「いえ、今の事を言っているんだけど。今モーリーさんは何もしていないよね。」
「これからするんだよ。」
そういうとモーリーは席を立った。
「どこ行くの。」
「倉庫の整理だよ。」
こいつ逃げようとしている。ルーは思った。
そしてだんだんと恐さよりもモーリーに対する怒りの方が心に溢れて来た。
「そうじゃなくて、今は正餐(昼食)のための下準備をしているのでしょう。大体、あなたは厨房の使用人でしょう。倉庫の整理なら小間使いのベッキーの仕事じゃない。あなたが野菜を洗って、切って、ベッキーを倉庫に行かせなさいよ。」
「うるさいうるさい!」
モーリーがルーを拒否するようにそういって、机を叩いた。
「なぜベッキーはいじめられなければならないの?ベッキーはただ、真面目に仕事をしているだけでしょう。」
「・・・。」
ルーが問いかけてもモーリーは黙ってそっぽを向いていた。
「ルーをいじめると何か得する事でもあるの。」
「・・・。」
「何で普通に仕事をする事ができないの?ただ黙って、自分の仕事をすればいいだけでしょう。なぜそれができないの。」
「・・・。」
何なのこのおばさん。
何で何もしゃべらないの。
意味が分からない。
こんなおばさんのために、何で私達が振り回されなければならないの。
するとルーの心に感情が溢れ出して、止められなくなった。
ベッキーは、あんたにいじめられるために生きているんじゃないんだ!
「モーリーさん、あなたの仕事って何なの?水甕に水を一杯にするのは誰なの?暖炉に火を起こして湯を沸かすのは誰なの?朝の買い物は誰なの?玄関の掃除は誰なの?馬に餌をやるのは?全部ベッキーがやっているよね。野菜を洗って、切って下準備をするのは厨房の仕事だよね、それくらいモーリーさんはやらないの。悪いけど、これからベッキーは旦那様の部屋を回ってシーツや服を洗濯しなくてはならないの。ベッキーにばかり仕事を押し付けないでよ!」
そう言ってルーはモーリーを激しく睨んだ。
「ルー。」
ベッキーはジャガイモを洗うのを止めて立ち上がるとルーを見た。
するとベッキーは唾をごくんと飲み込むとモーリーを見た。
「モーリーさん。私はモーリーさんと一緒に仕事がしたいです。でも、いじめられるのは嫌なんです。いじめるのだけは止めて貰えませんか。」
「ベッキー。」
ルーはベッキーを見た。
するとベッキーもルーを見た。
「うるさいって言っているだろう!あのな、この程度のこと当たり前なんだよ。私だっていじめられて来たんだ。仕事は押し付けられるし、馬鹿にされるし、仲間外れにされるし。そういうものなんだよ。文句は一人前になってから言えってゆうんだよ。全く、今時の若い娘はぜんぜんなっちゃいないよ!」
そう言ってモーリーもルーとベッキーを睨み返した。
お互いに睨み合って、拮抗した状況となった。
「モーリーさん、あなたは厨房の使用人よね。」
アレンティーが静かにそう言った。
「だから何だよ。」
「ということは、あなたの仕事は野菜や肉の下ごしらえ、洗い物などの料理人を補助することが仕事です。あなたの仕事はベッキーをいじめることではないし、あなたに支払われている給料は、ベッキーをいじめたことで支払われたものではない。」
「そんなこと言われなくても分かっているよ。何が言いたいんだ、馬鹿。」
モーリーがアレンティーを馬鹿にするようにそう言った。
そのアレンティーの言葉を聞いて、ルーははっとした。
そして、シェリルの言葉を思いだした。
そうだ、仕事でもないのにわざわざいじめられてやる義理はないんだ。
ルーは口を開いた。
「ベッキーだって同じよ。ベッキーの仕事はあなたにいじめられることではない。ベッキーのお給料にはいじめられた分は入ってないんだからね。だから、これからもいじめるのを止めないって言うのなら、その分、お金を払いなさいよ。」
「何だって!」
ルーの言葉にモーリーが驚いた顔を見せた。
ルーは続けた。
「何で仕事でもないのに、あなたにいじめられなきゃならないの。大体、あなたにいじめられているおかげで、ベッキーの仕事が遅れてしまっているじゃない。ベッキーはこのお屋敷のたくさんの仕事をこなしているのよ、ベッキーの仕事が遅れるということは、このお屋敷の掃除も洗濯も片付けも進まないということじゃないの。あなたのいじめがこの屋敷全体に悪い影響を与えていることが分からないの。そのことを知ったら、このお屋敷の旦那様だって黙っていないと思うわ。」
ルーがそう言うとマリーウェザーが続いた。
「そうよ、あなたが昔いじめられていたかどうかなんてこっちは知ったこっちゃないわよ。少なくとも、あなたの仕事をベッキーに押し付けるというなら、その仕事分のお金をベッキーに払いなさいよ。」
「ふざけんじゃないわよ。誰が金を払うもんか!」
モーリーはカッとして、近くにあったお玉を掴むと右手を振り上げた。
「何よ、暴力を振るうつもり、それならこっちは4人なんだからね。」
マリーウェザーがそういうと、モーリーは右手を挙げたまま動きを止めた。
「ちくしょう!」
モーリーは右手を挙げたまま悔しがった。
「何が4人なんだ。」
すると厨房の入り口に中年の親父が姿を現した。
「ジェームス、良いところに来てくれたよ。」
モーリーが本当に嬉しそうな顔をした。
ジェームスは壁に掛かっていたフライパンを手に持つと、モーリーの隣に立った。
「きゃんきゃんきゃんきゃん吠えやがってこのメス犬どもが。腫れ上がるまでケツを叩いてやるから覚悟しろよ!」
そう言うとジェームスはじりじりと間合いを詰めて来た。
「そうだジェームス。こてんぱんに伸してやってくれよ。生意気な小娘共にはお仕置きが必要だからね。」
モーリーが口元に笑みを浮かべながらいやらしい目でルー達を見た。
さすがに細腕の女4人では男には立ち向かえない。
ジェームスの顔がいやらしく歪んだ。
その歪んだ顔が徐々に距離を詰めて来ていた。
シェリル、お願い、早く来て。ルーは思った。
その時だった。
「よう。」
ルー達の後ろから声がした。
ルーが後ろを振り向いた。
「キッド!」
ルーの顔が笑顔に変わった。
「何だお前は。」
ジェームスが驚いた顔を見せた。
「フライパンで女性のケツを叩くなんて。それ、何ていう調理法だ?」
キッドはそう言って、腰に提げた剣に手を添えると何気なくジェームスに見せた。
「形勢逆転ね。」
アレンティーが笑顔でそう言った。
「さあ、モーリーさんどうするの?いじめを止めるか、それともお金を払うか。」
ルーが威勢よくモーリーに迫った。。
「ううっ。」
モーリーは思わず後ずさりすると黙り込んだ。
「どっち!さあ、どっちよ!」
マリーウェザーもモーリーを追い込んだ。
すると、ジェームスがいきなり叫んだ。
「くっ、首だ!お前なんか首だ!とっとと出て行け!」
ジェームスがベッキーに狂ったようにそう言った。
やっぱりこうなったか。ルーはそう思った。
想定はしていたことだった。
言われたときにはどうするか、一応考えてはいた。
だが、首という言葉の衝撃はやはり大きかった。
ルーは心配してベッキーを見た。
ベッキーの顔から血の気が失せていた。
「さあ、どうした。さっさと出て行かないか!」
ジェームスがベッキーに圧力を掛けた。
まだ正念場は続く。
ルーが覚悟を決めて口を開こうとした、その時だった。
「誰が首だって?」
ルーは当然、その声に聞き覚えがあった。
「シェリル!」
厨房の入り口からシェリルが姿を現した。
「良いタイミングだっただろう。」
シェリルはルーに片目を瞑って見せた。
ルーは一気に勇気を取り戻した。
するとシェリルの後ろから、小さくなってミンチンも姿を現した。
「ミンチンお嬢様。」
モーリーとジェームスがかしこまって身を小さくした。
「ミンチン、女性が輝くためにとかいって、街の大通りを歩いていたって聞いたけど、これはどういうことだ。」
シェリルがミンチンを目を細くして見た。
ミンチンは慌ててモーリーを睨みつけた。
「モーリー、何をしているんですか。恥を知りなさい。」
ミンチンに叱りつけられたモーリーは納得がいかない様子だった。
「ミンチンお嬢様だっておしゃっていたじゃないですか、ベッキーに罰を与えろって。」
モーリーの言葉を聞いて、シェリルがミンチンを睨んだ。
「ミンチン、どういう事だ。」
「それは・・・、何を言っているの。モーリー、あなたが怠けて良いとは私は言っていませんよ。今後は二度とこのようなことがないように。いいですね。」
慌ててモーリーを叱りつけたミンチンだったが、シェリルは睨みつけた目を緩めることはなかった。
「分かっていないようだな。お前がモーリーをいじめるから、いじめがモーリーにも伝染しているんじゃないのか。お前は男と女の差別を無くそうと躍起になっているようだが、いじめは女性同士の方が陰険で酷い。お前が女性を男性と同等に扱って欲しいと言っていながら、女性同士では立場の弱い者を奴隷のように扱う。自分でおかしいと思わないか、しかもお前が住んでいる屋敷の中の話だぞ。」
「ううっ。」
シェリルの言葉をミンチンは黙って聞いていた。
すると黙っていたベッキーが口を開いた。
「あの、私はモーリーさんが嫌いなわけじゃないんです。だから、いじめるのさえ止めて貰えれば、仲良くできると思うんです。」
するとその言葉を聞いたモーリーがベッキーを睨みつけた。
「ふん、自分だけいい子のふりしやがって。いやらしいんだよ。」
「モーリー!」
モーリーの言葉に、またミンチンがモーリーを叱りつけた。
「分かってるよ。いじめなければいいんだろう。分かってるよ。」
モーリーはそう言うと、ミンチンやシェリルの横を通って厨房から出て行った。
「お、俺も倉庫を見て来よう。」
残ったジェームスもそう言って、厨房から出て行った。
ミンチンが眉をしかめて額を手で押さえると、頭を左右に振った。
「はあ。これでも私はこの街を良くしようと頑張っているつもりだったのですが。先月も、女性が輝く街運動でたくさんの女性達と一緒に、私が先頭に立って大通りを行進して歩きました。」
「何だい。その、女性が輝く街運動というのは。」
シェリルがミンチンに尋ねた。
「女性達の働ける場所をもっと増やしていく、そして男よりも安い給料を上げていこうという運動です。」
「素敵だわ。たくましいわね。」
離れて聞いていたソフィがそう言った。
「思った以上にたくさんの女性達が集まって、盛況でしたのよ。」
表情を歪めていたミンチンが、少し穏やかな表情をした。
「でも、何でミンチンが参加しているんだよ。」
シェリルが首を傾げてミンチンを見た。
「私が参加してはだめということはないでしょう。」
ミンチンが眉をしかめてシェリルを見た。
「いや、それは分かるけど。じゃあ、どんな気持ちで参加したんだ。」
「気持ち?」
「気持ちさ、思いでもいいけど。」
「・・・。」
ミンチンが分からない顔をして視線を天井に向けた。
「例えば、私は、女では話にならないとか、女は出て行けとか門前払いされて悔しい思いをしたことがある。私がその運動に参加するなら、その悔しい思いを胸に、そういう不平等はやめろという気持ちで参加するだろうね。じゃあ、お前はどんな経験がもとになって、どんな気持ちで運動に参加したんだ。自分から先頭に立って、働ける場所を増やそうとか、給料を上げろと大声を出して大通りを歩いたんだろう。その時、お前はどんな気持ちで大声を出していたんだ。」
「・・・。」
黙っているミンチンを見て、シェリルは小さく溜め息をついた。
「遠慮なしに言わせて貰うと、お前の親は商売で儲かっているみたいだし、お前は収入の心配もなく役人の仕事に専念できるんだろう?収入で困っている訳ではないのに、なんで先頭に立って歩いたんだ。」
ミンチンは横目でシェリルを見ると口を開いた。
「私はその時、女性で初めてこの街を管理する役人になったのです。だから先頭に立って歩いたのです。」
「何で役人だと先頭を歩くのは当たり前なんだ。」
シェリルが無邪気な様子で聞き返した。
「偉いからです。」
「偉い?お前は役人として女性が輝くためにこれまで何をしてきたんだ。他の人では真似できないような偉いことをしてきたのか。」
ミンチンが困った表情になった。
ミンチンが役人をしていた時の仕事は市場の売上税の管理であり、女性が輝くこととは無関係だった。
「そういうことは特にありませんけども。」
「じゃあ、先頭を歩くのはおかしいだろう。気持ちも思いもない。偉くもない。ただなんとなくお手伝いがしたい。だったら、先頭じゃなくて一番後ろに並ぶべきだ。違うか。
「・・・。」
ミンチンは黙ってしまった。
「これからはちゃんと後ろに並ぶんだぞ。」
シェリルがミンチンに念押しした。
シェリルの言っていることは理解できる。ミンチンはそう思った。
だがミンチンには納得できなかった。
ミンチンは少しの間黙っていて、そして独り言のように呟いた。
「嫌です。・・・後ろは嫌です。私は先頭じゃなきゃ嫌です。」
「何で先頭じゃなきゃ嫌なんだ。」
シェリルは思わず笑顔を見せた。
「私は目立ちたいのです。いえ、先頭に立って目立たなければダメなのです。」
女性達の先頭に立って歩いたからこそ、女性の代表者としてこの街で一目置かれるようになったのだ。ミンチンはそう思った。
市政長官になる前は、ミンチンは街の財政を管理する管財役の役人をしていた。
もちろん、父親のコネで入った役人の世界であったが、男性ばかりの役人の世界でミンチンは初めての女性の役人だった。
他の男性の役人は、自然にミンチンを仲間外れにした。
役人同士の会合に呼ばれることはなかったし、新しい仕事を与えられることもなかった。
何か問題が起こった時でさえ、その話がミンチンの耳に入ってくることはなかった。
そうやって、ただもの珍しい存在というだけで役人の世界で埋もれてしまっていた。
そのミンチンを一躍有名にしてくれたのが、女性が輝く街運動なのだ。
市政長官になれたのも、もともとはこの運動のお陰であると言っても過言ではないのだ。
「いいじゃないか。女性が輝くとか、偉いとかそんなことは関係ない。お前は目立ちたいから先頭に立つ。それでいいじゃないか。その方がよっぽどお前らしい。」
シェリルは満足そうに頷くと、ニッコリとしてミンチンを見た。
「そうですか。」
ミンチンは少し疑うような視線をシェリルに送った。
「そうさ。自分に遠慮することなんてない。これからもいろいろな事に首を突っ込んで、先頭に立って歩けばいい。目立つことなら私に任せろって。その替わり、偉いからとか変なことは言うな。素直に目立ちたいからやっていると言えばいいんだ。その方が、よっぽどお前の事をみんな理解できるし、好きになってくれるよ。」
「そうですか。それでいいのですね。」
ミンチンは納得したように頷いた。
「そんな目立ちたがり屋のお前に、良い話を持って来てやったぞ。」
そう言ってシェリルは、ミンチンに片目を瞑って見せた。
「ルー、ありがとう。」
ベッキーはルーにニコッとした。
「私もすごく良い経験になった。」
ルーもベッキーにニコッとした。
ルー達は、エバ達よりも先に屋敷の外に出て来ていた。
エバ達は、まだ少しミンチン市政長官と話があるようだった。
「マリーウェザーさんもありがとう。何も関係ないのに巻き込んでしまってごめんなさい。」
「違うよ。私は好きでやったんだから気にしないで。」
ベッキーの問い掛けに、マリーウェザーが何でもないというように、手をひらひらとさせた。
「でも、モーリーは心から反省しているとは思えないけど。」
アレンティーが静かにそう言った。
「しばらく大人しくしていると思うけど、モーリーはまたうっかりいじめを再開するかもしれないわね。」
マリーウェザーがそう言って口を尖らした。
「そうね。モーリーは自分もいじめられた経験があって、それが当たり前だと思っているから、たぶんモーリーのいじめ癖は一生治すことはできないかもしれない。でもね、その時にはまた懲らしめてやれば良いのよ。そうやって、いじめが始まりそうになったらその度に叩いて押さえ込む。そうやって上手く付き合っていくしかないと思う。」
自分自身に言い聞かせるようにルーはそう言って頷いた。
「そうね、ベッキーはモーリーさん自体は心底嫌いって訳じゃないんだものね。」
マリーウェザーはベッキーを見ると首を傾げた。
「私にはモーリーさんは悪い人には思えないです。確かにいじめられるのは嫌だけど、ああいうおばさまはこの街に普通にたくさんいます。いちいち嫌っていたらこの街で生活できないと思うんです。それに、私、お芋を洗ったり切ったりするの、嫌いじゃないんです。」
ベッキーはそう言って控えめにマリーウェザーを見た。
「ベッキー!なんていい子なんだお前は。」
マリーウェザーはベッキーの肩をポンポンと叩いた。
「そうね、だからといって黙っていじめられているのはおかしいわ。だから、いじめ癖のおばさまが普通にいることを踏まえて、私達は対策を図っておく必要があるわね。」
アレンティーが静かにそう言った。
「うん、だけど今回の経験でどうやって戦えば良いか分かった気がする。ベッキー、もっと友達を増やしましょう。そしてお互いに助け合うのよ、今回みたいにね。」
ルーがそう言うと、マリーウェザーが大事な事を発見したようにぱあっと顔が明るくなった。
「そう!戦うためには仲間が絶対に必要なの。一人では絶対に戦えないから。」
「うん、私一人だったらそもそも初めから諦めてしまっていて、モーリーさんに一言いってやろうなんて思いもつかなかった。」
マリーウェザーとルーがそう言い合うと、お互いに顔を見合わせた。
「だいぶ盛り上がっているね。」
「シェリルさん。」
屋敷から出て来たシェリルがいつの間にか近くに来ていた。
「シェリルさん、私のために本当にありがとうございました。」
ベッキーがシェリルに頭を下げた。
「私は役に立てただろう?いつでもお役にたってあげるからね。」
シェリルは笑顔をベッキーに向けた。
そして続けた。
「でもね、これはベッキーだけの問題ではないんだ。きっとこの街には、ベッキーと同じ思いをしている人達がいるし、もっと言うなら、他の街にも、他の国にも同じ思いをしている人達がいる。今回こうやっていじめに立ち向かっていくことで、ルーやベッキーがいじめを克服することができたら、そういう同じ思いをしている他の人達を助けてあげられるのじゃないかな。」
シェリルはルーを見て、次にベッキーを見た。
「私やベッキーが。」
ルーが思いがけない顔でシェリルを見た。
「そうだよ。ルーやベッキーがいじめを克服したとする。すると、その話は噂として街に広がる。すると、同じ悔しい思いをしている人がルーやベッキーを訪ねて来る。どうやっていじめを克服したのですか、と。」
そう言うとシェリルは人差し指を顎に当てると、考えているような素振りを見せた。
「次にその訪ねて来た人がいじめを克服したとする、すると同じように他の人に広がっていく。そして次には他の街に、そして他の国に広がる。そうやって世界は変わっていく。」
「凄い。」
シェリルの言葉にルーが目を輝かせた。
「ちょっと大袈裟に言い過ぎたかな。でもね、いじめだけじゃないんだ。私達が普段生きている中で困ったことがたくさんある。こんなちょっとしたこととか、私が我慢すれば良いこととか、そういう自分の身近な困ったことを一つずつ克服していく。そしてそのことを世界に発信していく。それがこの世界全体にとって、とても大切なことなんだ。」
少し照れた素振りでそう言うと、シェリルは皆に笑顔を見せた。
「そろそろ行きましょう。」
側に来たソフィがシェリルにそう声を掛けた。
「じゃあベッキー、また後でね。」
ルーがベッキーにそう言った。
「ルー、気を付けて。私は一緒に行けないけど、終わったら私にも話を教えてね。」
ベッキーもニコッとしてそう言った。
「分かった。」
ルーはそう言うと、キッドやビリーと一緒に、出発のため馬のロープをほどき始めた。
ベッキーは屋敷の正面玄関の隣にある使用人が使う裏口に向かって歩き出した。
今日は大切なお客様を迎える日なのだ。その準備をしなければならない。
大金持ちのお嬢様で、しばらくこの屋敷に滞在されるということだった。
よし、私も頑張るぞ。
ベッキーは両手を肩の高さまで上げると、軽く握った拳に力を入れた。
「キッド。」
出発するため、馬車の御者台に座ったキッドにシェリルが横から声を掛けた。
「何ですか。」
「御者台、交替してよ。」
シェリルがキッドにそう言った。
「いいですよ。」
キッドはそう言うとサッと御者台から飛び降りた。
「結構揺れますから、気を付けて。」
「ありがとう。」
シェリルはそう言うと、先に御者台に乗っていたエバの横に座った。
御者台から降りたキッドは、どうしようかと周りを見渡した。
「キッド。俺の馬に乗れよ。」
そんなキッドにビリーが声を掛けた。
「ビリーはどうするんだ。」
キッドがビリーに近付きながら尋ねた。
「俺か、俺はルーと交替して馬車に乗るよ。」
そう言うとビリーは、馬車に乗り込もうとしているルーに向かって手を挙げた。
「ルー、キッドと一緒に俺の馬に乗ってくれよ。」
「分かった。」
ルーが馬車に乗るのをやめるとこちらに向かって歩いてきた。
「2人の娘さんと仲良くしておかないとな。」
ビリーはそう言ってキッドに向かってウィンクすると、馬車に向かって歩き始めた。
たくましい奴だな。キッドはビリーの後ろ姿を見送りながらそう思った。
ビリーとルーはすれ違いざまに互いに相手の手の平を叩いた。交替の挨拶だ。
キッドはビリーの愛馬、シルブラウンに跨った。
ルーがキッドの下に到着した。
「ルー。」
キッドがルーに手を伸ばした。
キッドはルーの腕を掴むと馬の上に引き上げた。
「出発するぞ!」
キッドが右手を挙げて皆に合図した。
エバ達はまた進み始めた。
キッドの前に座っているルーが、キッドが前を見易いようにカウボーイ・ハットを脱ぐと、隠れていたブロンドの髪が溢れた。
ルーが後ろのキッドに話し掛けた。
「キッド助けてくれてありがとう。タイミングばっちりだったね。」
「まあな。」
キッドが何でもない事というようにそう言った。
「エバさんに言われたんだ、後ろから付いて行けって。出番が無いことに越したことはないが、出番があった時のことを考えろってね。」
「そうか。」
ルーは前を向いたまま嬉しそうにへへっと笑った。
「それはいいとして、何で俺に何も言わなかったんだよ。」
キッドが目を細くするとルーの頭に聞いた。
「あっ、そうか。」
ルーは悪げもなくそう言った。
「あっそうか、じゃないぜ。」
キッドが呆れた様子で首を左右に振った。
「次、言わなかったら怒るからな。」
キッドはそう言うと周囲に目を配りながら手綱を握り直した。
「キッド。」
ルーがまた声を掛けた。
「何だ。」
するとルーが一気に振り向くと、とびっきりの笑顔をキッドに見せた。
「かっこ良かったよ。」
キッドは思わずルーの笑顔をじっと見た。
やられた。完全な不意打ちだ。キッドはそう思った。
「ふざけてるんじゃねえよ。」
キッドはカウボーイ・ハットを被りなおすと正面を向いた。
「何、シェリルだと。」
その女性の名前を聞いたボワロは思わず笑みを浮かべた。
「全く驚いた。ミンチン卿も目を白黒させていた。まさか、あんな小娘にこてんぱんに伸(の)されてしまったのだからな。」
「ははははは。」
ボワロは大柄な男の騎士から、シェリルがミンチン市政長官をこてんぱんに言い負かす様子を聞いて、額を手で押さえながら本当に可笑しそうに大声を上げて笑った。
さすがシェリルだ。
それにシェリルは、相手を打ち負かすだけでなく、しっかりと相手の人間性を理解し、正しく評価している。
ただ相手を否定して、切り捨てるのではない。
ボワロは、やはりシェリルは自分の想像通りの女だと思った。
「それで、なんで貴卿はミンチン卿の屋敷の話を知っているのだ。」
ボワロの問い掛けに大柄な男は眉をしかめて気まずい顔をした。
「何だ、言えないことをしていたのか。」
ボワロが大柄な男に鋭い視線を送った。
「そんな事はないが。」
「だったら何だ。さっさとしろ。」
大柄な男は嫌々口を開いた。
「その時に屋敷にいたのだ。」
「何?その場にいたのなら、なぜミンチン卿を助けなかったのだ。」
ボワロの表情がみるみる険しくなっていった。
大柄な男はボワロを見ることができずに、視線を伏せた。
「いや、助けようと思ったのだが、拘束されてしまったのだ。」
「まさか、シェリルか!」
ボワルの問い掛けに、大柄な男は黙っていた。
「ははははは。」
ボワロは思わず大声を上げて笑った。
すると、大柄な男も上目遣いでボワロを見ると、何を勘違いしたのか笑みを浮かべた。
ボワロは、笑みを浮かべる大柄な男の顔を見て、また声を上げて笑った。
こいつは本物の阿保だ。ボワロはそう思った。
騎士とは戦うのが仕事ではなかったか。それが、助けようとして逆に一般人に拘束されてしまうとは。それではただの役立たずではないか。
こいつは本当に騎士なのだろうか。
気がたるんでいるとしか思えない。そして迂闊(うかつ)だ。
そもそもこいつは騎士としてどんな技量を持ち合わせているのだろうか。
しかも、俺が馬鹿にして笑っているのに、それが分からず、自分も笑みを浮かべているとは、まさに生きている喜劇だ。
なるほど、自分の人生をネタにして俺に笑いを提供するのが、お前の利用価値という訳か。
「はははは。実に可笑しかった。で、結局シェリルは何のために市政長官のところに来たのだ。」
「おお、そうだ。前振りが長くなってしまったな、うっかり大事な話を忘れるところだった。」
笑みを浮かべていた大柄な男の顔が、真面目な顔つきに変わった。
「シェリルは、例のエルファの軍隊のことを伝えに来たのだ。エルファ軍は人間と争いに来た訳ではなく、人間たちと、この街を守るために森から出て来たのだと言うのだ。」
「ふむ、なるほど。では、エルファは何から人間たちを守っているのだ。」
大がらな男の話を聞いたボワロは、一旦頷いて見せるとそう尋ねた。
「悪魔だ。なんとエルファの森は、悪魔に襲われているというのだ。その悪魔が、この街に入り込まないよう守っているということだ。」
大柄な男の騎士は、ボワロも喜ぶだろうと思わず笑みを浮かべた。
「なるほど。それでエルファと戦う準備の必要もなくなったと、こういう訳だな。」
「そのとおりだ。」
そういって大柄な騎士は声を出して笑った。
ボワロもつられて大柄な男と一緒に笑った。
するとボワロは、急に表情を固くすると言った。
「裏は取ってあるのだろうな。」
「裏?」
大柄な騎士は分からない顔をした。
「分からんのか?証拠だ。シェリルが言った事が本当であるという証拠だ。」
「証拠?証拠と言われても。」
大柄な騎士は言葉に詰まった。
「この馬鹿が!証拠もないのに鵜呑みにしていたのか!」
大柄な男は唖然とした顔のまま表情を凍り付かせた。
「もし嘘だとしたら、どういうことになるのか分かっているのか卿は!」
「嘘!嘘だと。」
大柄な男の騎士は思わずたじろいで体をのけ反らせた。
「そうだ。騎士らはまるで戦いの準備が整っていない状況で、エルファ達がこの街に押し寄せたらどういうことになるか。こんな簡単なことも分からんのか。」
「そんなことが。」
「もしシェリルがわざと偽の情報を流していたとしたらどうする。貴卿はまんまと敵の偽情報に踊らせているではないか!」
「・・・。」
大柄な男は口をぽかんと開けたまま、表情を固まらせた。
これが本物の阿保面だ。ボワロはそう思った。
その阿保面を見て、ボワロは心の中で笑って見ていた。
2つ目の笑いのネタがもう飛び出したか。
「貴卿、まさか戦いの準備を止めてしまったのではなかろうな。」
大柄な男の顔がぴくっと動いた。
「さっさと戦いの準備を終わらせないか!」
「しょ、承知した。」
大柄な男は踵(きびす)を返すと、慌てた様子で広間の出口へ向かおうとしたが、慌てたお陰で足を絡ませて大袈裟に転倒した。そしてすぐに立ち上がると、広間の出口から出て行った。
ボワロは大柄な男の騎士が部屋の扉を閉めるのを見届けると、もう一度一人で笑みを浮かべた。
馬鹿な男だ。
それにしても、またシェリルの名前を聞くことになるとは思ってもみなかった。
ボワロは、失くした物が見つかった時のように嬉しい気持ちになった。

デートの約束を覚えていてくれていたのか。まさか、シェリルの方から近づいて来るとは。
ならば絶対に逃す訳にはいかない。
ボワロは聞いてみたかった。
シェリルを自分のすぐ側に置いて。あの賢いシェリルが何と言うのかを。
俺が悪人であることが解ったら、シェリルは俺を蔑(さげす)むだろうか。
俺が他人を利用し尽くす様を見たら、シェリルは俺を止めようとするだろうか。
俺が欲望のままに生きる姿を見たら、シェリルは俺をどう評価するだろうか。
ただ直感的に思うのは、俺の事を理解できる世界でただ唯一の女は、シェリル以外にいないと思えることだ。
人としてあり得ないとか、殺さないと治らないとか、そんな言葉など聞きたくない。
そんな事は、俺が一番良く分かっている。
じゃあ、俺は人ではないのか。俺はさっさと死ぬしかないのか。
馬鹿どもが!
俺は、人間だ!
シェリルだけは、俺の生き様について理解し、分析し、正しく評価をしてくれるだろう。
シェリルの言葉であれば受け入れられる。
なぜなら、シェリルは悪人の俺にでさえ寄り添ってくれる。そう思えるからだ。
だから俺は、絶対にシェリルを手に入れて見せよう。
ボワロは振り返ると、後ろで椅子に座っている偽物の領主であるマックレを見た。
「今の話を聞いていたであろう、この有事に真偽の分からない話で街を混乱させるとは、立派な騒乱罪だ。衛兵に命じて至急シェリルを捕まえさせろ。シェリルの言っていることが嘘か本当か、俺が見極めてやる。」
この街では、裁判で判決することができる司法権を持つ者は3つ存在した。
法と契約の神であるガヤン神。そのガヤン神が定めた法律を犯した者や、国王に対する犯罪を裁くガヤン法廷。
街の重大な犯罪や、領主と市民との間で交わした契約を違反した者を裁く領主裁判。
市民の間での問題事や、街で定めた約束事を破った者を裁く市政裁判。
しかし裁判は、まず手数料が収入として得られるだけでなく、罰金や財産を没収するなど多額の収入を得ることができたので、金になる事件は3者で取り合いになることはよくあった。
また、自分に有利な判決をしてくれる者に裁判を依頼することや、判決を下す判事や、判事とともに罪や罰を決定する参審員に金を渡すことはとても効果的だった。
だから裁判は金持ちに有利だった。
ボワロがやろうとしているのは、領主であるマックレの裁判権によって、シェリルを裁こうとしているのである。
騒乱罪と判決されれば、財産の没収か絞首刑となるのが普通だった。
「承知しました。」
マックレが答えた。
「事は一刻を争う。全ての衛兵を動員しろ。」
「承知しました。」
待てよ、シェリルを捕まえるのは良いとして、シェリルは何をしようとしている。
するとボワロは一瞬にして状況を理解した。
違う、反対だ。
シェリルは、俺が何を考えているかを考えている。
つまり、俺は戦争を起こそうとしている。ならば、シェリルは戦争を起こさせないようにしている、そう仮定してみよう。
そしてシェリルが動いたことで間抜けな騎士は実際どうなったか。
すっかり戦う気を失くして、戦う準備を止めてしまっているではないか。
仮定したことと目の前で実際に起こっている事実に矛盾はない。ならば。
「マックレ、伝令はどうした。もう手配は済んだのか。」
「伝令であれば、早朝に既に出立しております。」
「そうか。だが念のため、隣のステインの街に伝令が到着したか確認しろ。」
「承知しました。」
ボワロはマックレにそう言うと、自分の応接室への扉を開けて、部屋に入った。
応接室の中には男の侍従が目を伏せて立っていた。
するとボワロは応接室をさっさと抜けて、さらに隣にある自分の執務室に入った。
ミンチン市政長官なら問題はない。歩きながらボワロは思った。
俺はミンチンが市政長官になるために推薦人になってやったのだ。
俺が言えば、ミンチンを抑えるのは容易い。
シェリルは賢い女性だ。だが、まだまだ俺の方が上手だったな。
ボワロは愛用の椅子に腰掛けると、壁に掛けられている絵画に目をやった。
ボワロが気に入っている合戦の絵画だ。
長い槍に兵士が串刺しにされている。
炎に焼かれている兵士もいる。
するとボワロはふと思った。
待てよ、シェリルにしてやられた騎士が間抜けなのではなく、騎士よりもずっと相手の方が技量が上だとしたら、どうなるか。
ボワロは少しの間絵画を見てじっと眺めた。
そして思った。
シェリルは俺を殺しに来るのか?
ボワロは顎に手をやってまた少しの間絵画を眺めると、部屋の外にいる侍従に声を掛けた。
「おい。」
「いかがいたしましょうか。」
侍従が扉の外から応えた。
「うちの商会の用心棒を呼んで来い。必要になるかもしれん。」
「承知しました。」
ボワロは愛用の椅子に深く座り直した。そしてまた、合戦の絵画に目をやった。
どの程度のものか楽しみだ。ボワロはそう思った。
こちらも全力で迎えてやらなければ、失礼というものだろう。
ボワロは口元の片方を吊り上げると、ニヤリと笑みを浮かべた。
これからシェリルが何をするのか、ボワロはなぜか楽しくなった。
「エバ。」
「何だ。」
馬車の御者台に座っているシェリルが、隣に座っているエバに声を掛けた。
「何で立っていたんだよ。」
シェリルがそう尋ねるとエバが前を向いたまま分からない顔をした。
「いつの話だ。」
「伝令と私が話をしていたとき、伝令たちの後ろで立っていただろう。何していたんだよ。」
「ああ、あれか。」
エバは少しの間黙って考えると言った。
「マーリンがな。」
「マーリンだって?」
エバの言葉にシェリルが驚いて笑顔になった。
「マーリンがどうしたんだ。」
シェリルがクスッと笑うとエバに聞いた。
「マーリンが・・・、踊り始めてな。」
「はは、マーリンが踊れるとは知らなかった。どんな踊りなんだ。」
シェリルがエバを見つめると、エバは前を向いた。
「いや、そうだな・・・、サンバ的な。」
シェリルが吹き出すと笑いだした。
「ははは、サンバ!マーリンが!サンバとは予想外だよ。」
シェリルが笑顔を見せた。
「マーリンに今度見せて貰おうかな。」
シェリルがそう言ってエバを見た。
エバがちらっとシェリルを見た。
「いや、マーリンは恥ずかしがり屋だから女性の前では踊らないぞ。」
「そうなのか?でも、ここにはソフィもエイリスもいるだろう?女性の前で踊ったのではないか?」
エバは前を向いて少し考えると言った。
「そこがマーリンの妙技だ。女性が見ていない瞬間を狙う。」
「女性が見たら?」
「止まる。」
「見なかったら?」
「踊る。」
「ははははは。」
シェリルが堪らないといった様子で笑った。
シェリルはいつの間にか緊張が解けて、体から力が抜けた感覚があった。
シェリルは少しの間黙って馬車に揺られていた。
「エバ。」
「何だ。」
「少し眠い。」
エバはちらっと横目でシェリルを見た。
シェリルが目を細くしていた。
まあ、あれだけ一人で大騒ぎすれば疲れてもしようがないか。エバはそう思った。
驚いたり、怒ったり、笑ったり、本当に忙しい奴だ。
見ているこっちは飽きなくて良いのだが。
まあでも、頑張っていたな。こいつ。
「馬車に乗ったらどうだ。」
エバがそう言ったがシェリルは首を左右に振った。
「それは嫌だ。」
「何でだ。」
「エバが御者台に座っている理由と一緒だ。」
「なるほど。」
疲れても武術家ということか。エバはそう思った。
エバが御者台に座っているのは、いざという時に素早く対応するためだ。
馬車の中に入っていては、周囲の変化に気付きにくいし、事への対応も遅くなる。
すると、シェリルの重心がエバに移ってきているのが分かった。
眠りに入りそうだ。
シェリルの頭がゆっくりとエバの肩に寄って来た。
「恥ずかしいから、止めてくれ。」
エバがシェリルにそう言った。
エバは女性とくっつくとか、女性に甘えたりというのは好きではなかった。
「分かっている。」
シェリルが小さくそう言うと、頭の傾きを修正した。
シェリルは一応姿勢を真っ直ぐに保とうと努力している様子だったが、シェリルが眠りに入るのは時間の問題だった。
このままでは危ないな。エバはそう思った。
それに、もともと御者台はそんなに大きいものではなく、大人二人が並べばくっつかなければ座れない。そこまで目立ちはしないだろう。
エバはシェリルの頭を自分の肩に寄せてやった。
マーリン「どうでもいい話ですが、シェリルは何で人の事を呼ぶときに「さん」をつけないのですか?普通は名前の後に「さん」をつけますよね。」
エバ「ああ、それ、前から俺も気になっていた。」
シェリル「ええっ、私「さん」つけてなかったっけ?」
エバ「とぼけるのか。とぼけて何とかなると思っているのか。」
マーリン「証拠はいくらでもあるんですが、どの番号の章の、何行目とか羅列するかね。」
シェリル「とぼけてました。すみません。」
マーリン「シェリルは何で「さん」つけないのでしょうか。」
シェリル「ちょっと待った。マーリン、お前だって私の事を「さん」つけてないだろうが。」
エバ「それはあれだろう。」
マーリン「そう、そのとおり。我々3人の親しい仲ならともかく、シェリルの場合初対面の相手でも「さん」つけないからね。」
シェリル「ちょっと待ってくれよ。想像して欲しい。私が威勢よく啖呵を切るって言う時に「さん」つけるかね。どうよ?」
エバ・マーリン「・・・・。」
シェリル「例えばさ、「ふざけるな!ミンチンさん。」どうよ、おかしいだろうが。」
エバ「まあ、確かに。」
マーリン「そうだねぇ。」
シェリル「ふんっ。」
エバ「ただシェリル、あれだぞ。「さん」つけるのは普通だぞ。年上でも年下でも、男でも女でも、上司でも部下でも「さん」をつければ無難で失礼がない。万能につかえる便利な代物だ。」
シェリル「まさか、エバの口からそんな言葉を聞くとは思わなかった。ショックだ。」
エバ「おいおい。」
マーリン「最近は、性的差別、上司部下の間での差別とうるさいから、誰に対しても「さん」づけて呼ぶのが無難だと思うぞ。」
シェリル「いつの時代の話だよ。」
マーリン「違和感があるのは分かる。だが、慣らして行けばシェリルにも出来るって。」
シェリル「・・・。」
エバ・マーリン「・・・。」
シェリル「エバ、さん。マーリン、さん。」
エバ・マーリン「・・・。」
シェリル「無理だあ。恥ずかしくて、死ぬ。」
エバ「俺も恥ずかしいわ。止めてくれ。」
マーリン「恥ずかしいですね。止めましょう。」
シェリル「私、頑張ったよね。」
エバ「頑張った。」
マーリン「シェリルは頑張ったよ。」
シェリル「ねえ。」
エバ「何だ。」
シェリル「結局、私はいいよね。「さん」つけなくても。」
エバ「まあな。」
マーリン「すまぬ、勧めた俺が悪かった。」
シェリル「安心した。それで・・・、ええっと・・・。」
エバ「どうした?」
シェリル「いいのかな。こんな意味のない会話で。」
エバ・マーリン「・・・。」
エバ「だからどうでもいい話なんだろ。」
マーリン「そうそう、どうでもいい、どうでもいい。こんなのどうでもいい。」
シェリル「そうか。どうでもいいなら、この辺でさっさとお開きにして、じゃあ、呑みにでも行っちゃう?」
エバ・マーリン「おー。」
シェリル「ジェシーおばさんの仕込んだエールが本日樽出しなんだってさ。」
エバ・マーリン「おー!。」
シェリル「何て幸せなんだろう。樽出しのエール。」
エバ「全くだぜ。」
マーリン「ジェシーおばさんのところなら、マスタードと胡椒を利かせた豚肉の串焼きだな。」
シェリル「まだ太陽も高い。明るいうちから呑むエールもまた格別なんだよな。」
エバ「昼呑みって奴か。」
マーリン「無職の特権。背徳感が堪らないですよねえ。」
シェリル「野郎ども、昼呑みしたいか!」
エバ・マーリン「おー!」
シェリル・エバ・マーリン「ひーるのみ!ひーるのみ!ひーるのみ!ひーるのみ!」
3人が徐々にフェードアウトしていく中、何か思い出したようにエバが呟いた。
エバ「あっ、俺もつけてねえわ。「さん」づけ。」
ミンチン市政長官の屋敷を後にしたエバ達は、エルファ軍が駐留している北の丘を越えた平野を目指して、まずは街の出口である北門に向かって馬車を進めていた。
北門の前には、街から出ようとする人たちの行列が出来上がっており、出るまでにおよそ15分程度はかかりそうな塩梅であった。
「かなりの行列ね。」
ソフィが行列に並ぶ人たちを見て眉をしかめた。
「そうなの?」
ソフィの前に座っているエイリスが尋ねた。
ソフィとエイリスは同じ馬に乗っているのだ。
すると、ソフィたちの隣にキッドとルーの乗った馬が近づいた。
「これは普通じゃないな。」
キッドが言った。
「そうなんだ。」
キッドの言葉を聞いてエイリスが言った。
ソフィとエイリスは、領主の城に閉じ込められていたので、街の様子が普通なのかどうか分からなかった。
「街に入る時はともかく、街から出る時は税金が取られる訳でもないから、こんなに並ぶ事はないんだ。」
キッドがソフィとエイリスに説明した。
エバ達は行列の最後尾についた。
「どうかしたのか?」
シェリルが目を開けると、隣のエバに尋ねた。
「さあな。だが、この街から一斉に出て行こうとしているのだろう。」
「エルファの軍隊か。」
「だろうな。思ったより動きが早いな。」
この街を通過するだけの商人や旅人が、北門に押し寄せたのだろう。
「街を出ることを制限される訳ではないだろうから、じきに解消するだろう。」
エバ達は行列の流れに従ってゆっくりと進んでいた。
するとガヤン神官のバクウェルが前に並んでいる商隊の男に声を掛けた。
「こんにちは。行列が出来ていますが、何かありましたか?」
「知らないのですか?」
商隊の男は驚いた顔でバクウェルを見た。
「何がですか?」
バクウェルが尋ねると、少し呆れた様子で商隊の男は言った。
「この街の近くにエルファの軍隊が姿を現したのだ。宿でその話を聞いて慌てて出てきた。」
「ふむ。」
バクウェルは頷くとまた男に聞いた。
「何でエルファの軍隊が姿を現したのだろう。」
「それは分からない。だが、戦場になってから慌てても手遅れになる。今のうちに逃げ出すのが得策だ。」
「なるほどな。」
バクウェルはそう言って、後ろを振り向くとエバたちに顔を向けた。
「まあ、想定の範囲内だな。」
バクウェルはそう言った。
エバとシェリルも小さく頷いて見せた。
エバたちは行列が進んでいくのに合わせて、のろのろと馬を進めた。
ソフィが前に座っているエイリスに尋ねた。
「ねえ、エルファの軍隊には友達がいるんでしょう。」
「いると思うけど、私がこの街に連れてこられた時はまだ子供だったし、成人してどんな風になっているか。見れば分かると思うけど。人間世界の生活でいろいろありすぎて、子どもの時の私と今の私は変わり過ぎてしまって。」
エイリスは静かにそう言った。
「そっか。そうだよね。」
ソフィも静かに頷いた。
エイリスはこの街に連れて来られてもう50年も経っている。
その間に、この街の領主が2代、代替わりをしている。
初代ヤドゥイカ子爵のジョン、2代目カーター、それから3代目のマックレだ。
もちろん、領主のご家族、領主に仕える人たち。
それらの人生をエイリスは実際に目にして来た。
エイリスの心の内は、想像したとしても理解できるものではない。
でも、ソフィが冗談を言うと、エイリスは笑った。
ソフィとエイリスは、ヤドゥイカの丘に建つ屋敷で最初に出会った時から、お互いに似た者同士だと感じていた。
「でも、どきどきしちゃうね。」
ソフィがエイリスに言った。
「何で。」
エイリスは分からない顔をした。
「好きだった男の子と会えたりして。」
ソフィがそう言うと、エイリスが目を細めた。
「ソフィ、それは言ってはだめでしょう。」
エイリスが抗議の声を上げた。
「あれ?何か悪い事言ったかな。」
今度はソフィが分からない顔をした。
「その男の子に会えたとしても、結婚して子供が2人いるとか、そういうことになるわよ。」
「しまった。」」
エイリスの言葉にソフィは残念な顔をした。
ソフィは思い出した。この話は2度としないと、以前にエイリスと誓ったはずなのに。
この時代、女性は12歳で成人を迎えると、早々に結婚して20歳までに子どもを1人、2人もうけるのが普通だった。
それからすると、ソフィとエイリスはもう立派な行き遅れだ。
それに子どもを産むなら体力のある30歳までと言われていた。
結婚をどうしようとか、子どもをどうしようとか、2人で話しているとそこはかとなく気分が暗く落ち込んでくるので、2人の間でこの話は2度としないと封印したのだった。
「迂闊だったわね。」
「ごめんなさい、自覚が足りていませんでした。」
ソフィは大袈裟にガクッと首を垂れた。
すると突然、老人がソフィとエイリスの乗っている馬の前に現れた。
「危ない!」
ソフィが慌てて手綱を引くと馬を止めた。
「何、何!」
急に馬が止まったのでエイリスも慌てて馬に捕まった。
馬は老人の直前で止まった。
おばあさんだった。
ソフィとエイリスが唖然として見ていると、そのおばあさんがソフィとエイリスを見た。
おばあさんは言った。
「この阿保が。」
おばあさんはそう言い終わると、また歩き出した。
おばあさんはウェイン大通りの反対側へ歩いて行った。
「びっくりした。」
「びっくりしたね。平然と行列に突っ込んでくるんだもの。」
ソフィとエイリスがそう言い合った。
「困ったものですね。」
ルードの馬に乗っていたソンドラが2人に声を掛けた。
ソンドラは、ソフィとエイリスが城から逃げ出して駆け込んだ娼館で、2人を助けてかくまってくれた娼婦だ。
「正常な判断が出来ない程に、頭が老いてしまっている。」
ルードがしようがないという様子でそう言った。
ルードはガヤン神官でバクウェルの部下だ。
ソンドラが困った顔でソフィを見た。
「馬車が行き交っている危険な大通りでも平気で横断するし、道を歩いていて人とぶつかりそうになっても避けようともしない。注意をしても馬鹿にして聞こうともしないし、口を開けば馬鹿とか阿保とか罵るばかりで話にならない。」
ソンドラがソフィにそう説明した。
「そうなんだ。」
ソフィが悲しそうに眉をしかめた。
「何が楽しくて生きているのかしら。」
エイリスがソンドラに尋ねた。
「どうだろうかね。ただ、私はあんなババアにはなりたくないね。」
ソンドラが嫌そうにそう吐き捨てた。
「本当ね。あんな風に醜態を晒して迷惑を掛けるくらいなら、頭がまともなうちに死んだ方がましだわ。」
ソフィもそう言って頷いた。
するとエイリスが口を開いた。
「きっと、死にたくても死ねなかったのよ。死ぬのは恐い。でも頭がおかしくなるのも恐い。そうして気が狂ってしまうんだわ。」
エイリスの言葉があまりに怖くて、その場が静かになった。
「エイリス。怖いわよ。蛇を平然と生け捕りにした時くらいに。」
ソフィが茶化すとエイリスがてへっという感じでソフィを見た。
「ねえ、後ろから何か来るよ。」
一番後ろを進んでいたキッドとルーが皆に声を掛けた。
見てみると、行列の最後尾から腰に剣を提げた男たちが、並んでいる人々を確認しながらエバたちの馬車の方へ近づいて来る。
街の衛兵たちだ。
チリン、チリン。
シェリルの首輪につけられた紅(あか)い鈴が鳴った。
紅い鈴には魔法が掛けられていて、危険が近づくとさりげなく鳴って教えてくれる。
シェリルは首輪の紅い鈴を指で転がした。
「エバ。」
シェリルは隣のエバを見た。

「ああ、どうやらお前を狙っているらしいな。」
エバはニヤリと笑みを見せると、御者台から飛び降りた。
「時間を稼いでこよう。」
そう言うとエバは衛兵らに向かって歩いて行った。
「エバ!」
すると今度は馬車の窓からマーリンが声を掛けた。
エバは振り向くとマーリンを見た。
「相手は素人だ。」
マーリンが言った。
するとエバはニヤリと笑った。
「稽古を付けてやるだけさ。」
そう言うとエバは、いつの間にか手に持っていた木剣をマーリンに見せた。
エバはまた歩き始めた。
「俺も行きます。ルー降りてくれないか。」
キッドがルーに声を掛けた。
「分かったわ。」
キッドの前に座っていたルーが馬から飛び降りた。
「キッド、戦ってはだめだ!」
シェリルがキッドに声を掛けた。
「戦いませんよ。俺は、ライダーとして行くんです。」
キッドは手綱を引いて馬の向きを変えると、衛兵たちとは別の方向に馬を進めた。
ルーが馬車の御者台に飛び乗ると、シェリルの横に座った。
「あいつ、急に強くなったな。」
シェリルが隣に座ったルーに言った。
「本当ね。」
ルーがシェリルに笑顔を見せた。
衛兵たちは行列の両側に分かれて、並んでいる人たちを確認しながら前に進んでいた。
衛兵は左右に3人ずつ、全員で6人だった。
エバは先頭の衛兵の前まで来ると、木剣の切っ先を衛兵の鼻先に置いた。
「何のつもりだ。」
衛兵はエバを睨んだ。
「この剣より先に進むのは止めた方がいい。怪我をすることになる。」
エバは静かにそう言った。
「こいつ、何を言っているんだ。」
「班長、何ですかこいつ。」
他の衛兵たちも、エバが木剣を突き付けている衛兵の周りに集まって来た。
エバが木剣を突き付けている衛兵は班長と呼ばれていた。
班長と呼ばれた衛兵が口を開いた。
「悪いが、馬鹿に付き合ってやれる程暇がないんでね。」
班長がそう言ってエバの横を通り過ぎようとした。
だが、エバは、動こうとする班長に合わせて木剣で鼻先をぴったり押さえていて、班長は動けなかった。
「はははは。」
その班長の様子を見て、周りの衛兵が笑い声を上げた。
班長は後ろを振り向くと、手に負えないというように肩をすくめて見せた。
そして改めてエバの方に向き直った。
「冗談もいい加減にするんだな。」
班長はそう言ってエバの木剣を右手で払いながら、エバの横を通り過ぎようと歩き出そうとした、その瞬間だった。
「何!」
班長は唖然としてそう言った。
班長は、気が付くと地面に倒れていた。
班長には何が起こったのか分からなかった。
右手で木剣を手で払って、横に動いたら地面に倒れていたのだ。
班長は立ち上がるために上半身を起こそうとした。
だが失敗して、また地面に倒れ込んだ。
右手が上がらない。
上半身を支えようとした右手が上がらないのだ。
班長の右鎖骨は折れてしまっていた。
「俺は冗談とは言っていないぞ。」
エバはそう言うと、次は誰かと問いかけるように周りの衛兵に剣先を向けた。
「何をしたんだ。」
衛兵の一人が思わずそう呟いた。
周りの衛兵たちからも、エバが何をしたのかが分からなかった。
班長が横に動こうとして、いきなり足をすくわれたかのように地面に倒れてしまった。
衛兵たちは訳が分からず、その場で金縛りにでもかかったようにじっとしていた。
「助けなくていいのか?」
エバはそう言うと木剣を大きく振りかぶった。
このまま振り下ろされれば、地面に倒れている班長に当たる。
「あっ、危ない!」
衛兵の一人が気付いて班長の右手を掴むと思いっきり引っ張った。
「うぎゃああああ!」
エバの振り下ろした木剣は地面に突き刺さった。
間一髪のところでエバの木剣を避けた班長だったが、鎖骨の折れた右腕を仲間に思いっきり引っ張られて、あまりの痛さに体を小さくして必死に耐えていた。
「大丈夫ですか、班長。」
衛兵たちが心配そうに声を掛けたが、返事はなかった。
「この野郎!」
衛兵の一人が興奮してエバに斬りかかろうとした。
「あぐぁ!」
するとその衛兵も前のめりに地面に倒れ込んだ。
「あ・・・あ・・・あ・・・っ。」
地面に倒れ込んだ衛兵は、腰に提げた剣を抜くことも出来ずに、ちょうど鳩尾(みぞおち)辺りを両手で押さえながら呻いていた。
声が出ない様子で、呼吸ができなくて苦しそうだった。
「おい、大丈夫か!」
周りの衛兵たちが心配そうに声を掛けた。
だが、無情にもエバは、また木剣を大きく振りかぶった。
「こ、殺される!」
近くの衛兵が慌てて地面に転がった仲間を引っ張り戻した。
周りの衛兵たちには、エバが何をしたのかが分からなかった。
「この剣より先に進むのは止めた方がいい。怪我をすることになる。」
エバはまた同じことを言うと、同じように衛兵たちに剣先を向けた。
「こいつ、やばいですよ。」
衛兵の1人がそう口走った。
だが、数でいけばエバは1人、衛兵は2人減ってもまだ4人。
衛兵たちは、ここから逃げ出したい衝動に駆られていたが、人数では圧倒的に優っていたため、逃げ出すのも情けないという思いがあった。
かといって、不気味なエバに剣を向けることは恐ろしくてできなかったから、その結果として、衛兵たちはまた金縛りにでもかかったかのようにじっとしていた。
「エバさん!」
するとそこへキッドが馬を駆って現れた。
キッドは馬の足を少し緩めた。
「飛び乗ってください!」
エバは思いっ切り地面を蹴った。
そして馬の背に両手をついて跳び上がると、鐙に付けられた革紐をつかんで馬の背にしがみついた。
「やあ!!」
キッドが掛け声を上げて馬を加速させた。
衛兵たちはじっとエバたちを見送っていた。
キッドは大通りに並ぶ行列の横を走り抜けた。
「いいタイミングだ。シェリルたちは。」
エバが聞いた。
「シェリルさんたちは北門に入りました。だから拾いに来たんです。」
なるほど、いい仕事をする。エバはそう思ってニヤリとした。
北門が見えて来た。
そして、北門をくぐり抜けた向こう側にシェリルたちの馬車が待っていた。
北門の外で合流したエバ達は、昨日キッドたちの案内で向かったじいさん岩へ続く道を馬車で進んでいた。
途中、昨日エバが殺害した野盗たちの死体が眠る広場を通り過ぎると、左手の丘の上にこの街の領主の屋敷が見えて来た。
「昔はあのお屋敷に住んでいたのよね。」
ソフィが屋敷に目をやりながらエイリスに声を掛けた。
「久し振りに見たわね。」
エイリスが懐かしむ様子で目を細めて屋敷を見ていた。
「確か前代の領主の奥さんと一緒に住んでいたのだったな。」
エバが御者台からエイリスに声を掛けた。
「ええ、そのとおりだわ。」
エイリスが屋敷を眺めながらそう言った。
エイリスとソフィは、前代の奥様と一緒に屋敷に住んでいた。そして前代が亡くなって、ボワロが偽物の子爵マックレを連れて来ると、エイリスとソフィは屋敷から街の城に移されたのだ。
「あの屋敷の向こう側。丘を下ったところに北の平原が広がっている。エルファの軍隊が駐留しているのはきっとそこだわ。」
ソフィがエバにそう言った。
エバたちはその丘の北側にある平原を目指して、丘を迂回する形で左回りに馬車を進めていた。
1人で馬に乗っていたロミタスも屋敷を眺めていた。
ロミタスもあの屋敷に捕らわれていたのだ。
あの屋敷でロミタスは、偽物の子爵マックレからエルファが森で育てているプファイトの実で商売することを持ち掛けられた。プファイトの実を使って戦争に使う武器を作るのだと。
ロミタスはその商売を断ったせいで、娘のエイリスには合わせて貰えず、交渉を有利に進めるための人質として拘束されたのだった。
ロミタスは眉をひそめた。
すると御者台に座っていたシェリルがロミタスに声を掛けた。
「ロミタス、エルファの軍隊を指揮しているのは、話の分かる奴だろうか。」
声を掛けられたロミタスはシェリルを見た。
すると、近くにいたエイリスがシェリルの言葉をエルファ語にしてロミタスに伝えた。
ロミタスは頷いた。
「恐らく、指揮をしているのはバランヤだろう。軍隊を指揮する部族長は回り持ちなんだが、俺の次の番がバランヤだ。だが、バランヤなら気心も知れているし問題ない。」
ロミタスはそう言った。
「なら安心だな。ロミタス頼んだぞ。」
シェリルはそう言ってロミタスに笑顔を見せた。
「任せてくれ。」
シェリルにそう言うとロミタスは視線を前に向けた。
しかし、内心ロミタスは不安だった。
それは昨日、夕食の時にマーリンと話をしたエルファの生き方、円環についての会話が思い出されたからだ。
エルファ社会では、それぞれの者がそれぞれの役割を、永遠に安寧と果たし続けるという生き方、円環という生き方が厳格に守られていた。
それは生まれついた身分は上がることも下がることもなく、エルファ社会の底辺にいる者たちは死ぬまでその底辺にいる者としてあり続けた。
ロミタスはその生き方についてこれまで疑うこともなかったが、昨日マーリンと話をして、それはロミタスが生まれながらに族長というエルファ社会の上位階級に生まれたからであって、底辺にいる者たちは、必ずしもそうとは限らないことが分かった。
それにシェリルを見ていて分かったことは、シェリルは、エバ、キッドら、エイリスら、バクウェルらの意思をとても大切にしていることだ。
これまで俺は、森を守るためという目的を掲げてたくさんの部下を従えて来た。
ただそれは、やはりとても強引で一方的なものであったのだと思う。
俺はこれから元部下らを説得するにあたって、ただ森のため、円環のためと一方的に説得するのではなく、シェリルのように人の意思を大切にする。そんなことが俺にできるだろうか。
「お父様、」
するといつの間にか隣に来ていたエイリスが声を掛けた。
「大丈夫ですか。」
ロミタスはエイリスを見ると、片方の眉を器用に吊り上げて見せた。
「問題はない。だが、正直気が滅入るな。」
ロミタスの言葉を聞いて、エイリスは少し考える様子を見せると言った。
「良く聞くこと。それから、今のお父様の気持ちを分かり易く伝える。それしかないのではないですか。」
エイリスの言葉を聞いてロミタスは笑顔になった。
「はは、確かにな。お前の言うとおりだ。」
「見えて来たぞ。」
キッドが皆にそう声を掛け、左手でこの先を示した。
キッドが示した方向を見ると、赤や緑色の色とりどりの幾何学模様が描かれた布で覆われた、特徴的な形をした天幕がいくつも見えた。
また、天幕の周囲にはたくさんの人の姿が見えた。
「馬車が入れるのはここまでだな。」
そう言うとキッドは、少し道が広がった広場で左手を挙げると、皆に止まる合図をした。
エルファの軍隊が駐留している草原は、道がない野生の草原で、ところどころ茶色の地面が見えていて、岩が顔を出しているところもあり、無理に進むと馬車が壊れてしまう恐れがあった。
「ここからは徒歩で行こう。」
「分かったわ。」
キッドが皆にそう言うと、一緒の馬に乗っていたルーが飛び降りた。
そして、馬車を曳いていた2頭の馬に近付くと、馬の首につけられた馬車と馬を繋いでいる馬具を取り外した。
そして手綱を引くと、近くの木の側まで連れて行き、手綱を木に縛りつけた。
「お疲れ様。」
ルーはそう言って馬の長い鼻を撫でた。
ビリーも馬車から素早く降りて来ると、他の馬の手綱を近くの木に縛り付けた。
草原には小さな小川が流れていて、エバたちはその小川に沿ってエルファの軍隊の駐留している場所を目指して歩き始めた。
「この小川には来たことがあるのよね。」
ソフィがそう言ってエイリスを見た。
「夜中に奥さんと3人で屋敷を抜け出して、よくこの小川に来たわね。」
エイリスが懐かしむようにそう言った。
「この辺りに、他に川はあるのか。」
エバがソフィに尋ねた。
「水溜りはあったと思うけど、川はないわね。」
ソフィが首を傾げてそう言った。
「この小さな小川がエルファ軍の生命線になっているようだな。」
エバがそう言って頷いた。
軍隊にとって、水源の確保は死活問題だ。
水源を失った軍隊は、地獄の苦しみを味わう事となり、敗北が決まったと言っても過言ではなかった。
エバたちが小川に沿って進んでいくと、先に2人の人の姿が見えて来た。
「エルファの見張りだろう。俺が話をしよう。」
ロミタスはそう言って皆の先頭に出た。
見張りとの距離が近くなると、見張りの方から声を掛けて来た。
「ロミタス族長・・・。」
2人の見張りはそう言って、左手を挙げた。エルファの挨拶だ。
ロミタスも見張りの2人に左手を挙げて頷いた。
ロミタスは、2人の見張りの様子に少しよそよそしさを覚えた。
少しの間軍隊を離れていたためだろうか。
「部族長と話がしたいが、繋いでもらえるか。」
「私が案内しましょう。」
見張りの1人がそう言って、ロミタスと並んで歩き始めた。
「今の部族長は誰か。」
ロミタスが歩きながら見張りに尋ねた。
エルファの軍隊を指揮しているのは1人の部族長だった。
部族長は12人の族長らによって、おおよそ8年から12年周期で順番に交替する回り持ちとなっていた。
12人の族長はそれぞれに一族を創り上げていた。
一族の規模は大きかったり小さかったりしたが、ロミタスの一族は中規模と言ったところだ。
だが、勇猛さではどの一族にも負けない。
ロミタスはそう思っていた。
「今はドリューソン部族長です。」
見張りのエルファがそう答えた。
「何だって?」
ロミタスが眉をしかめた。
「バランヤではないのか?」
「いえ、ドリューソン部族長です。」
そう言った見張りは不思議そうな顔をしていた。
おかしい。ロミタスはそう思った。
回り持ちの順番は変わることはない。
それがエルファの円環という生き方を表してもいるのだ。
順番が変わるとすれば、何か事情があったのだ。
ロミタスはまた不安になった。
見張りに案内されたエバたちは、エルファ軍の駐留地に足を踏み入れた。
そこではたくさんのエルファが働いていた。
食糧を調理する調理人、武器の刃を鍛えなおす職人、斥候に出発する小隊、食糧の獲物を狩るため森に向かう小隊、戦闘訓練を行う者、食糧や衣類や医療品を数えて確認している者。
ソフィはエルファに対して静かな生き物という印象を持っていたので、意外にも駐留地に活気があることに驚いていた。
「凄くにぎやかね。」
ソフィがエイリスに声を掛けた。
「本当ね。」
エイリスも驚いた様子でそう言った。
「これがエルファの軍隊か。」
ガヤンのバクウェルが辺りを見回しながら感心した様子でそう言った。
「もっと原始的な印象を持っていましたが、かなり機能的ですね。細かな職能集団に分かれて仕事を分担している。」
バクウェルの部下のルードがそう言うと、バクウェルも頷いた。
「エイリスか?」
すると、戦闘訓練の様子を見ていた中年のエルファがエイリスに気付いて、近付いてきた。
「おお!本当にエイリスだ!体は大丈夫か。見ない間にすっかり大きくなって。」
「バランヤおじさん。」
そう言うとエイリスは左手を挙げた。
するとバランヤおじさんも左手を挙げた。
エルファの挨拶だ。
「バランヤ。」
ロミタスが横からバランヤに声を掛けると、左手を挙げた。
「おお、ロミタス。無事だったか。」
バランヤも左手を挙げてロミタスに応えた。
「これはめでたい。まさか、ロミタスもエイリスも無事に帰って来るなんてなあ。」
そういうとバランヤは振り返って、周りのエルファに声を掛けた。
「ロミタスとエイリスが帰って来たぞ!」
バランヤの掛け声に、続々とエルファが集まって来た。
集まって来たエルファは、ロミタスとエイリスを取り囲んだ。
「おお!エイリス。」
「元気か、ひどいことされていないか。」
中年のエルファが次々に声を掛けた。エイリスはおじさんエルファたちに凄く人気があった。
「見てのとおり元気です。だから安心して。」
エイリスはニコッとした。
「エルファの森を出る時はこんなに小さかったのになあ。」
おじさんエルファの1人が昔を懐かしむようにそう言った。
エイリスは今からちょうど50年前、人間同士の戦争からエルファの森を守るため、エルファが人間に対して不可侵であることを証明する人質として、シャロムの街の領主の元に差し出されたのだ。
「お前は本当に偉い子だ。プファイト一族の誇りだ。」
「いや、エルファの森で一番の自慢の娘だ。」
プファイト一族というのは、エルファの森を襲う敵と戦うのが役目の部族だ。
森に生きるエルファはたくさんの部族に分かれ、その部族にはいくつか種類があった。
プファイトというのもその種類の1つだ。
エイリスはあまりの人気に驚いてしまって、ただただ笑顔を返すしかなかった。
ただ、エイリスの心から不安な気持ちが一気になくなっていた。
正直、皆が自分の事を覚えているか、受け入れてくれるのか不安だった。
ただただ、皆の温かい気持ちが伝わって来て、エイリスはその思いで胸が一杯になった。
「俺もいるんだけどな。」
ロミタスはそう言って苦笑した。
「ロミタス、あの人間たちは。」
バランヤが離れたところにいるエバたちを見て、ロミタスに尋ねた。
「俺と娘の命の恩人だ。人間の街で難儀をしていたところを助けてくれたのだ。」
「おおそうか。それなら我らの同朋も同然だな。」
バランヤはそう言って頷いた。
「ロミタス・・・族長。」
ロミタスに声を掛けて来たエルファがいた。
ロミタスが顔を向けるとロミタスは笑顔になった。
「何だ、お前か。」
声を掛けて来たのは、ロミタスの部下、同じ一族の者だ。
「悪かったな、族長の俺が不在にしてしまって。皆に変わりはないか?」
ロミタスが尋ねると部下のエルファは眉をしかめた。
「まだ聞いていないのですね。」
ロミタスは部下の言った事が分からなかった。
「ロミタスか。」
すると別の人物がロミタスに後ろから声を掛けてきた。
ロミタスは声を掛けられた方に顔を向けた。
濃い緑色の髪を細くたくさん束ねた髪形が特徴的なエルファが立っていた。
「ドリューソンか。」
ロミタスはそう言って、思わず真剣な表情になった。
「今回は災難だったな。」
「まあな。」
「こっちで話をしよう。」
ドリューソンが奥に建っている天幕の方を手で示した。
「エイリスって本当にお姫様だったんだね。」
ソフィが驚いた様子でエバに言った。
エイリスの取り巻きがあまりに凄くて、ソフィはエイリスに近付けなかった。
「騙されている奴がたくさんいるな。」
エバがニヤリと笑みを浮かべた。
「シェリル姉さん。」
少し離れたところにいるマリーウェザーがシェリルにそう言って手招きした。
シェリルが近付くと、マリーウェザーは大きな鍋を火にかけているエルファの調理人を手で示した。
「キャッサバを茹でているんだよ。」
マリーウェザーがシェリルにそう言った。
「へえ、そうなんだ。」
マリーウェザーとシェリルは大きな鍋を覗き込んだ。
「へえ、キャッサバってこんなお芋なんだね。初めて見た。」
鍋の中には皮の剥かれた白くて大きな芋がごろごろと茹でられていた。
「茹でてどうするの?」
いつの間にか側に来ていたルーも鍋を見ながらマリーウェザーに聞いた。
「このままでも食べられるわ。エルファにとっては人間のパンみたいなものね。」
マリーウェザーがルーにニコッとした。
「へえ、エルファのパンはこんな芋なのか。」
ビリーが珍しい物でも見るように鍋を覗き込んでそう言った。
ビリーの隣にキッドも来ていた。
「何よ、馬鹿にしているの?」
マリーウェザーが目を細めてビリーを見た。
「違う違う、警戒し過ぎだって。」
ビリーがそう言うとかぶりを振った。
「お前、馬車の中で仲良くなったんじゃないの?」
キッドがビリーに聞いた。
「仲良くなるためには、まずぶつかり合わないとな。」
「失敗か。下心がばれたか。」
キッドにそう言われて、ビリーは一瞬言葉を失くした。
そしてぼそっと言った。
「・・・俺は負けねえ。」
キッドは呆れた様子で肩をすくめた。
「面白い。ねえねえ、味は?おいしい?」
ルーがマリーウェザーに聞いた。
「おいしいよ。ココナッツミルクをつけてもおいしいし、オレンジの果汁を加えてもおいしいよ。」
「うわあ、食べてみたい。」
ルーが目を輝かせた。
「小麦ではないのね。エルファの料理は初めて見たわ。」
「私も初めてです。これは貴重ですね。」
今度はソフィとソンドラが興味深そうに鍋を覗き込んできた。
「私はパンケーキが好きだわ。クルミを混ぜて焼いたのが好き。」
アレンティーがそう言った。
「そうか、潰して伸ばして焼くのね。」
ソフィが分かった顔で頷いた。
「いろいろな食べ方があるのね。おいしそう。」
ルーが唾を飲み込んだ。
「本当だ。食べてみたいね。」
シェリルとルーが笑顔で顔を見合わせた。
「パンは分かったけど、お肉とか野菜はどうするの?」
ソフィがマリーウェザーに尋ねた。
「お肉は森に狩りに行くのよ。野菜は森に野菜を育てている部族がいるから、その部族から貰えるわ。」
「なるほどね。」
ソフィがそう言って頷いた。
「やはり食糧はほぼエルファの森からの輸送か。だが、手慣れているな。日常生活に必要な職人や医師も揃っているのか。」
エバが独り言のようにそう言った。
「俺もそこが驚いた。急きょ編成された軍隊とは思えない。原始的な印象とは裏腹に、組織として洗練されている。」
バクウェルがエバに話し掛けた。
「プファイトの一族はもともとエルファの森の中を移動生活している部族だから、基地の設営や運営は慣れているのですよ。」
側に来たマーリンがエバにそう説明すると、それを聞いたエバとバクウェルはなるほどと頷いた。
「そうか。これは手強いな。」
バクウェルは視線を伏せると右手で顎を撫で回した。
「ねえ、茹でてどうするのですか?」
マリーウェザーがエルファ語で調理人に尋ねた。
「茹でて、潰して、クルミを混ぜたらお団子にして蒸し焼きにする。」
調理人が、隣で木の実を砕いている別の調理人を目で示した。
「おいしそう。」
マリーウェザーが瞳を大きくさせた。
「できたら食べさせてあげよう。」
調理人がそう言ってニコッとした。
「やった、ありがとう。」
マリーウェザーが笑顔を向けた。
「おい、何をしているんだ。」
3人のエルファがそう言うとエバたちに近づいてきた。
「そいつらは人間だろう。なぜ基地の中にいるのだ。」
3人のエルファは眉をしかめると、一番近くにいたマリーウェザーにそう言った。
どうやら見回りの衛兵のようだ。腰に鉈(なた)を提げている。
「何を言っているのだ。」
シェリルがそう言いながら、マリーウェザーの肩に手を置いて後ろに下がらせると衛兵の目の前に立った。
「人間が基地にいるのはまずいって。」
マリーウェザーが前に立っているシェリルに背中越しにそう言った。
シェリルは衛兵を見たまま頷いた。
「マリーウェザーはもっと下がって。マーリン、こっちに来て通訳してくれ。」
マーリンは歩いてきてシェリルの斜め後ろに立った。
「何で人間がいるのはまずいのか聞いて貰えないか。」
マーリンが衛兵に尋ねた。
衛兵は言った。
「これから俺たちは人間たちと一戦交えようとしているのだ。基地内に敵がいるのに、平気にしているほうがおかしいだろう、なあ。」
そう言った衛兵が別の衛兵に聞くと、聞かれた方の衛兵も当たり前だと腕を組んで相槌を打った。
衛兵らの言葉をマーリンがシェリルに伝えると、シェリルはうんうんと頷いた。
「今の状況が知りたいな。何のために一戦交えようとしているのか聞いて貰えないか。」
マーリンがまた衛兵に尋ねた。
「それは人間たちがエイリスを人質に取っただけでなく、ロミタス部族長も人質に取って、無理矢理、我々エルファを従わせようとしたからだろう。」
その言葉をマーリンがシェリルに伝えた。
するとシェリルは首を傾げた。
「ロミタス部族長もエイリスも戻って来た訳だから、もう戦う必要はないだろう?」
マーリンがまた衛兵に尋ねた。
すると衛兵たちは少し困った顔をした。
「いや、戦う事は既に決まっている。」
マーリンがシェリルに伝えると、シェリルは分からない顔で衛兵たちを見た。
「どうしてだ。決まっていたかもしれないが、ロミタス部族長もエイリスも戻って来たことで事情が変わっただろう。」
衛兵たちは言った。
「もともとドリューソン部族長からは、ロミタス部族長やエイリスが戻って来ても来なくても、人間たちと戦い勝利すると命令されていた。」
マーリンが衛兵の言葉を伝えると、ソフィやルーたちはみな眉をしかめた。
状況はあまり良くないようだ。
シェリルはエルファにさらに尋ねた。
「それは分かったが、人間たちと戦う理由は何なのだ。」
シェリルの言葉をマーリンが伝えると、衛兵は顔をしかめた。
「それは分からない。」
衛兵の言葉にシェリルは目を細めた。
「ドリューソン部族長は何と言っていたのだ。」
「俺たちはドリューソン部族長から直接聞いた訳ではないが、我々の族長からは何も聞いていない。」
衛兵の言葉を聞いて、シェリルはやれやれと肩をすくめた。
すると目を瞑って黙って両腕を組んで立っていたエバが口を開いた。
「お前たちはこれまで戦争を経験したことはあるのか。」
エバの言葉に衛兵たちは顔を見合わせた。
「それは・・・、ない。」
「なるほど。」
エバがまた黙って目を瞑った。
シェリルは小さく溜め息をついた。
エバはもう、エルファの軍隊をどう殲滅するか考え始めている。シェリルはそう思った。
戦う理由も分からず、ただ人間たちと戦争をしようと考えているエルファの軍隊を、エバは危険な存在だと判断しているだろう。
その時が来たら、エバは殺戮を開始する。
だが、まだやれることはあるはずだ。
シェリルは口を開いた。
「お前たち、戦争は、森で獣を追い払うのとは訳がちがうのだぞ。お前たちは人を殺しに行く。つまり人殺しになるのだ。それなのに自分が何のために人を殺しに行くのか分からないのか。」
すると衛兵の1人が食って掛かって来た。
「俺たちは命令されて戦うのが仕事だ。そんなこと知る必要はない。」
そう言った衛兵をシェリルは見つめた。
「その命令が誤りだったらどうする。その時に誰が止めるのだ。」
「何だと・・・、それは我々エルファが間違っているというのか。」
衛兵が眉をしかめた。
「じゃあ逆に聞くけど、お前たちがこれからやろうとしている人殺しは正しいのか?そうだと言うなら、その理由を説明してみろ。」
「・・・。」
衛兵は何も言えずに黙り込んだ。
だが衛兵の一人が必死の抵抗を試みた。
「これから戦争しようとしているのだぞ、そんな緊急事態にああだこうだと悠長に考えていられるか。」
だがシェリルは言った。
「何を言っている。お前たちは敵に攻められている訳ではない、準備万端に整えて攻めようとしているのだぞ。緊急事態とするかどうかはお前たち次第だろう、違うのか?」
衛兵たちは黙ってしまった。
シェリルは話を続けた。
「部族長だからといって絶対に正しいと言える理由は何だ?部族長がうっかり間違ってしまったら?ひょっとしたら本当の心を隠して悪い事を企んでいるかもしれないぞ。その時に誰が止めるのだ。」
シェリルはそう言うと衛兵たちを順番に見回した。
衛兵たちは何と言って良いのか分からず、シェリルと目を合わすことができずに目を伏せた。
「しっかりしろ、お前たちしかいないんだぞ。お前たちが自ら歩みを止める。それしかないんだ。そのためには自分の頭で考えなければ、正しいのか正しくないのか。それなのにお前たちは、自分から考えることを放棄して、間違っていても構わずに突き進もうとしている。そんな危険な軍隊なら必要ない。すぐに解散してしまえ。」
衛兵たちはシェリルの言葉を黙って聞いていた。
「私にここまで言われて、何か言うことはないのか。」
シェリルが両腕を組むと衛兵たちを細めた目で見た。
「こんなことを言われたのは初めてだ。正直、驚いている。」
「戦士なら黙って命令に従って戦うもの。そう考えていたからな。」
衛兵たちはシェリルを見て、素直にそう言った。
シェリルの表情が穏やかになった。
この戦士たちは聞く耳を持っている。それに素直だ。
ロミタスはいい教育をしているな。シェリルはそう思った。
シェリルは口を開いた。
「そんな訳はない。戦士なら戦士なりに自分の考えを持たなければ。別にその考えが間違っていてもいいのだ。良く聞いて、良く話をして、良く考える。そして、間違いに気付いたらすぐに正せばいい。黙ってしまうのが一番危険だ。黙ってしまったら、理解しているのか、していないのか、賛成なのか、反対なのか、お互いに分からなくなる。そうなればお互いにお互いが信じられなくなって、とてもじゃないが一丸となって戦う事などできなくなる。」
シェリルはそう言うと改めて衛兵たちを見回した。
「今からでも遅くはない。ドリューソン部族長を問い詰めに行こうじゃないか。そして納得できる説明がないならはっきりと言ってやればいい。戦争にはお前1人で行けと。」
「ロミタス、まあ座ってくれ。」
天幕の中に入ったロミタスとドリューソンは地面に敷かれた赤や緑色の色とりどりの幾何学模様が描かれた毛織物の上に胡坐をかいた。
すると、天幕の奥から1人のエルファが現れた。
「お久しぶりです。」
そのエルファは少し微笑んでいるような表情でロミタスにそう言ったが、ロミタスには誰であったか分からなかった。
「分かりませんか?私は良く覚えていますが。」
「申し訳ない。思い出せなくてな。」
そのエルファの表情が真剣なものに変わった。
「あなたに森を追放されたマノフです。」
その言葉に、ロミタスの脳は感電したように衝撃を受けた。
ロミタスは言葉を失った。
ロミタスの記憶の中にあるマノフと、目の前のマノフはすっかり変わり果てていた。
頬骨が飛び出すほど頬がこけてしまっていて、眼の周りが黒ずみ、骸骨のようだった。
「自分で私を森から追い出しておいて、すっかり忘れているとは。まあ、そんなものでしょう。私など生ゴミとしか思っていなかったことが、ばれてしまいましたね。」
マノフはロミタスを蔑(さげす)むように上から見下ろした。
「マノフ、何故ここに。」
ロミタスは驚いた表情のままそう呟いた。
ロミタスの言葉にマノフは口元を歪めた。
「ああ、分ります分ります。死んでいた方が都合が良かったでしょうからね。」
「まあ、そこまでにしておけ。」
ドリューソンが2人の間に割って入った。
「今回は、大変だったな。」
ドリューソンがロミタスに言った。
「ああ、まあな。」
ロミタスは、落ち着かない様子でそう言った。
「今までご苦労だったな。1小隊を護衛に付けてやるから、すぐにエルファの森へ送ってやろう。エイリスと一緒にエルファの森に戻ると良い。」
ドリューソンの言葉にロミタスは顎に手をやると頷いて見せた。
「それはありがたい。それなら、皆でエルファの森に戻るというのはどうだ。」
だがロミタスの言葉を聞いてドリューソンは首を左右に振った。
「いや、戻るのはお前とエイリスだけだ。」
「どういう事だ。」
ロミタスが視線を鋭くした。
「我々は人間たちと戦って勝たなければならない。」
「何だと。」
ロミタスが眉間に皴を寄せた。
「まあ、お前の気にすることではない。すぐに出発することだ。」
「ちょっと待て、何のために戦うのだ。」
するとマノフが突然大きな声を出した。
「お前にはもう関係のない事だ。説明する必要はない。」
マノフがロミタスを睨んだ。
「何だと。どういう事だ。」
ロミタスもマノフを睨んだ。
ロミタスとマノフの視線が交差した。
するとマノフは、ロミタスを蔑(さげす)むように上から見下ろした。
「お前はもう部族長でもなければ、族長でもない。プファイトの一族ですらない。」
「何い!」
ロミタスは立ち上がると、怒りに任せてマノフの首を掴んだ。
「おい、止めろ。」
ドリューソンがロミタスの腕を掴んだ。
「マノフの言っていることは本当だ。お前には悪いが、お前が人間に捕らわれた後、お前の族長の地位は空席となった。それをマノフが引き継いだのだ。」
だがロミタスは納得しなかった。
「そんなこと・・・、長老らが許すはずがない。」
ドリューソンはかぶりを振った。
「いや、長老らから了は得ているのだ。」
そう言うとドリューソンは、ロミタスの腕を引き剥がすと、乱暴に払いのけた。
ドリューソンの言葉を聞いて、ロミタスには心当たりがあった。
ドリューソンの祖父は、森のエルファの最高決定機関である長老会議の構成員だ。
ドリューソンが祖父を取り込めば、不可能ではない。
「私がマノフ族長だ。せいぜいお前の一族をこき使ってやるよ。」
マノフがロミタスに顔を近づけると息を吹きかけてそう言った。
「不満だろう。だが緊急事態であるし理解するしかない。長老らからの命は下っている。もう議論の時間は終わっているのだ。」
そう言ってドリューソンとマノフはロミタスを残して天幕を出て行った。
1人取り残されたロミタスは唖然として立ちすくんだ。
すると天幕の外で声が上がった。
「なんだお前たちは。」
ドリューソンの声だ。
ロミタスが天幕を出てみると、エバたちと一緒にたくさんのエルファが集まっていた。
「何をしているのだ。」
ドリューソンが近くにいたバランヤに聞いた。
「いやなに、この人間のお嬢さんが至極まっとうな事を言うのでな。」
バランヤがそう言ってニヤリと笑みを浮かべると、ドリューソンを見て、次にロミタスを見た。
そんなバランヤにロミタスも苦笑いを浮かべた。
「お前がドリューソンか。」
シェリルがドリューソンに声を掛けた。
「どういうことだ。誰に聞いても何のために人間と戦うのか分からないと言っているじゃないか。お前は指揮官だろう。何をしているんだ。」
シェリルがドリューソンに指を突き付けた。
「何を言っているのかな、このお嬢さんは。」
ドリューソンが困った顔で周りを見た。
すると、シェリルの斜め後ろにいたマーリンがドリューソンの前に進み出た。
「私はこの人間たちの通訳をしている者です。私がお伝えいたしましょう。」
「お前はエルファか、人間との通訳の仕事をしているとは珍しいな。まあ良い、彼女が何を言っているのか教えてくれ。」
マーリンはドリューソンにシェリルの言葉を伝えた。
するとドリューソンは笑った。
「ははは、それならご心配には及びませんよ。私は十分に説明しているし、部下たちも心得ている。バランヤ族長、このお嬢さんたちを静かなところにお連れしてはどうか。」
ドリューソンがバランヤにそう指示したが、バランヤは首を左右に振った。
「ドリューソン、それは無理だ。このお嬢さんたちは言う事を聞いてくれない。」
「何を言っている。だったら無理矢理にでも連れていけ。」
ドリューソンがイライラした様子でそう言った。
「だから無理だと言っている。感情的になって手を出した兵士がいたが、一瞬で伸されてしまった。この者たちはめっぽう強くて、歯が立たない。戦争する前に怪我人が続出してはいけないので、俺が何とか抑えているようなありさまだ。」
「ぬう。」
ドリューソンは唸って眉間に皴を寄せた。
「納得したらすぐに姿を消してやるから、何のために人間と戦うのかさっさと教えろよ。」
ドリューソンは可愛らしい顔をしているのに容赦のないシェリルの態度に面喰ってしまった。
「強力な奴を連れて来たな。」
バランヤがロミタスの横に来て話し掛けた。
「まあな。」
ロミタスが苦笑いをしたままそう言った。
「ロミタス、何を笑っているのだ。お前の軍隊の話をしているのだが。」
シェリルにそう言われてロミタスは苦笑いを向けた。
ドリューソンは怪しい。だが、自分も今までは強引な面があった。ドリューソンを責められないな。ロミタスはそう思っていた。
ここで皆に話をしなければならないだろう。
「みんな、俺の話を聞いてくれないか!」
ロミタスは大きな声でそう言って皆を見渡すと、兵士たちは静かにロミタスを見た。
ありがたい。ロミタスはそう思った。
部族長ではなくなったこの俺でも、まだ話に耳を傾けてくれると言うのか。
「我ら誇り高きプファイト一族の使命は何か?それは、エルファの森を外敵から守り、エルファの平穏を守ることだ。違うか?」
ロミタスがそう言って兵士たちを見回した。
兵士たちの中には頷く者もいて、納得しているようだ。
「そのために部族長は、ここにいる皆の命を預かる。そして死ぬかもしれない戦地に行けと命令する。俺はいままでそれは当たり前の事だと思っていた。理由などいらない、黙って命令に従っていれば良いのだと。そしてそれがエルファの生き方、円環であると。」
ロミタスは手で顎を撫でると、少し考えながら横に歩いた。
「だが、俺は人間に捕まって、人間たちの生活を見る中で考えたことがあった。人間は、自分の意思で行動するのだという。意思がなく無理矢理やらせるのは奴隷と一緒だと言うのだ。そして、人間は奴隷ではないと言うのだ。」
ロミタスはそう言うと左手を胸に当てた。
「俺たちは奴隷になっていないか?」
ロミタスの問い掛けを皆は静かに聞いていた。
「俺は、この人間のお嬢さんが言っている事はもっともだと思う。指揮官なら語るべきだ。戦いの理由と目的を。納得できなければ問い正すべきだ、何度でも!それができない指揮官なら不要だ、首だ!。そして我々プファイト一族は、奴隷などではない!」
ロミタスはそう言うと、胸に当てていた左手を勢いよく横に薙ぎ払った。
まるで邪魔をしている何者かを振り払うように。
「皆はどうだ!黙っていては分からないぞ。答えてくれ!」
そういうとロミタスは拳を振り上げた。
すると、最初はぽつぽつ上がっていた兵士の拳が、だんだんと加速し、ついにはたくさんの拳が突き上げられた。
ありがたい。ロミタスはそのたくさんの拳を見てまたそう思った。
俺の事を信頼してくれているのだ。
確かにこれまで、厳しい規律を課し、強引なところもあった。
指導する時には、一方的にやれと命令してきた。
だがそれは、プファイト一族の使命のため、誇りの為であった。
その点は揺らいだことはない。
森を外敵から守る。その使命の為ならば、長老たちの命に背くことも厭わない。それが我らプファイト一族の本来あるべき姿、誇りだ。
温厚な性格のエルファの中で、唯一牙を剝く戦士。孤高の狼だ。
そのことがプファイト一族の信頼を培ってきたのだ。
確かに足りないこともある。
それはシェリルと会って思い知った。
だが、これまで行ってきたことが間違っていた訳ではない。
ロミタスは嬉しくなって、近くにいたマーリンを見た。
「マーリン見てくれ、俺の部下は立派だろう!」
ロミタスの嬉しそうな顔を見て、マーリンも嬉しくなって頷いて見せた。
ロミタスは兵士たちを見渡して大きく頷くと、ドリューソンに指を突き付けた。
「ドリューソン部族長、説明して貰おうか。人間たちと戦わなければならない訳を。」
ロミタスとドリューソンの視線が交差した。
ドリューソンは少しの間黙っていたが、仕方なく口を開いた。
「何の為か・・・、それはエルファの尊厳の為だ。我々エルファは人間に馬鹿にされたのだ。」
ドリューソンは人間と戦う理由をそう言った。
マーリンから通訳して貰ったシェリルは手を挙げた。
「それなら問題はない。ロミタスを人質に取ったのはマックレとボワロという2人の犯罪者だ。」
シェリルがそう言うと、マーリンが周りのみんなに通訳した。
するとドリューソンは目を大きく見開いて驚いた表情を見せた。
何か知っているな。シェリルはそう思った。
シェリルは話を続けた。
「だから街の人間たちは関係がない。尊厳を守りたければ犯罪者の2人に罰を与えれば良いだろう。関係のない街の人間と戦争をするのは誤りだ。」
マーリンがまたみんなに通訳すると、その場は騒然となった。
兵士たちはお互いに思い思いの意見を言い合っていた。
すると、騒然としたその場を鎮めるようにドリューソンが大きな声で言った。
「だが、マックレは街の領主だ!人間たちの代表がエルファを貶(おとし)めたのだ!これは人間がエルファを貶めたのと同じだ!」
ドリューソンがそう言うとその場は静かになった。
だが、マーリンから通訳して貰ったシェリルは今度は両手を挙げて手を振った。
そしてシェリルは兵士たちをゆっくりと見渡すとはっきりと言った。
「マックレは偽物の領主だ、本物の領主ではない。」
シェリルのその言葉に、マノフは思わずシェリルを見た。
シェリルとマノフの視線が交差する。だがすぐにマノフは視線を外した。
そしてシェリルの言葉をマーリンが通訳すると、またその場が騒然となった。
ドリューソンは驚いた表情を見せた。
「そんなことなどない。こいつの言っていることは嘘だ。そうだろう?」
ドリューソンは横にいたマノフに尋ねた。
「当然です。」
マノフはドリューソンにそう答えると、前に進み出た。
そして兵士たちの動揺を抑えようと両手を広げて見せた。
「この人間の言っていることは嘘だ。我々を騙そうとしているのだ。静かにしないか!」
マノフはそう言いながら、兵士たちの前を行ったり来たりした。
するとロミタスが手を挙げた。
「みんな聞いてくれ。」
ロミタスは皆が静まるまで待つと口を開いた。
「この人間たちは、俺と、娘のエイリスを命懸けで助けてくれたのだ。そして、俺とエイリスは見た。マックレは偽物の領主だという証拠をこの目で見たのだ!」
ロミタスが言い終わると兵士たちは今まで以上に騒然となった。
するとマノフはますます必死になった。
「この戦いは、長老たちの命を受けての事なのだ。我々で勝手に取り止めることなどできるか!一度受けた屈辱は晴らさねばならない、長老らの命は果たさねばならないのだ!」
マノフは兵士たちを恫喝した。
すると兵士たちのマノフに対する視線が変わった。まるで異常な者を見るかのように醒めた視線になった。
必死だなマノフは。シェリルはそう思った。
部族長のドリューソンと比較して、マノフの方が必死だ。
するとシェリルが両手を挙げた。
「それなら一緒に連れて行ってやるよ。マックレとボワロの元に。そこで存分に屈辱を晴らせば良いだろう。」
シェリルの言葉をマーリンが通訳して皆に伝えた。
だが皆はシェリルの言った事が良く分からなかった。
シェリルは改めてマノフを見て、それから兵士たちを見回すと言った。
「みんな聞いてくれ。私たちは、これからロミタス族長とエイリスを拘束した犯罪者、マックレとボワロに罰を与えに行くつもりだ。ここにいるドリューソン部族長とマノフ族長は、何としてもエルファの屈辱を晴らしたいそうだから、エルファの代表として同行して貰おうと思うが、誰か異論はあるか。」
シェリルはそう言うとマノフを見た。だがマノフはシェリルを見なかった。
シェリルの言葉をマーリンが皆に通訳した。
「何だと!!」
マノフは驚いた表情をした。
すると兵士の1人が手を挙げた。
「俺も行っていいのか。」
シェリルは思わず声を出して笑うと、その兵士に笑顔を向けた。
「それはだめだ。さっきも言ったとおり、悪い犯罪者が2人いたという話で、街の人間たちは今回の件と関係がない。戦争ではないのだ。ロミタスとエイリスは連れて行く。被害者本人だからな。そして、ドリューソン部族長とマノフ族長は長老の命を受けているから連れて行く、そういうことだ。」
シェリルの言葉に兵士たちは納得したようだ。
シェリルはマノフに近付くと肩を叩いた。
「マノフ族長には、マックレとボワロの息の根を止める役をやって貰うことにしよう。皆はマノフ族長の武勇伝を楽しみにして待っているといい。」
シェリルがそう言って兵士たちを見渡すと、兵士たちから歓声が上がった。
すると、マノフは隣に立っているシェリルを睨みつけた。
しかし、シェリルはマノフに向かって笑みを浮かべると、マノフの耳元に口を寄せた。
「お前、人間の言葉をどこで覚えた?」
マノフの表情が固まった。
「上手くかわしたつもりか?残念だったな。」
シェリルの言葉が終わらないうちに、マノフはさっと踵を返すと、ロミタスとドリューソンを押しのけて天幕の中に入って行った。
「おい、どうしたんだ!おい、マノフ!」
ドリューソンが後ろから声を掛けた。
「ロミタス!マノフが逃げるぞ!エバ!行け!!」
ロミタスとエバが駆けだした。
その場はまた騒然となった。
ロミタスを追い掛ける兵士が出始めた。
すると、ドリューソンがさりげなく、少しづつ横移動を始めた。
「どこに行くのだ?お前はここにいろ。」
シェリルがドリューソンの顔に剣を当てがった。
シェリルの後ろには、キッド、ビリー、バクウェル、ルードが並んだ。
ドリューソンはひきつった顔を青くした。
マノフは天幕の中を素早く通り抜けると、反対側の出口から外に出た。
そして走った。
丘の上のヤドゥイカ砦を目指して。
「くそう。」
マノフはそう口走った。
この辺りの平原は、大きな岩など身を隠せるものがほとんどなかった。
走っている姿はすぐに見つかってしまう筈だ。
とにかく丘の上のヤドゥイカ砦まで辿り着ければ、身を隠すことができるはずだ。
ハッハッハッ。
走っている自分の息遣いが聞こえる。
なぜだ。なぜこうなってしまった。
俺はどこで間違った。
さっきまで俺は族長だったのだ。
そして、人間たちとの戦争でドリューソンは戦死。俺が部族長になるはずだった。
部族長になれば、エルファの森の愚かな老人どもをぶち殺して、俺がエルファの頂点に立つはずだった。
ついさっきまで、その野望に胸を躍らせていたというのに。
「くそう、ひどいじゃねえかよ。」
マノフはそう吐き捨てた。
結局、俺はいじめられ役かよ。
人生で良い事なんか一つもねえのかよ。
マノフは生まれつき卑木だった。
卑木とは、エルファ世界において最底辺にいる者達だ。人間の世界で言えば乞食が比較的近い。
卑木はエルファの社会の一員とは認められておらず、社会に寄生する者、卑しい者、未熟者と認識されており、いつエルファの森を追い出されるか分からない身分だった。
そしてマノフも追放された。
ロミタスに。
ハッハッハッ。
走り続けたマノフは息が上がって来た。
まだ追っ手が来る気配はない。
マノフは足を緩めた。
そして丘のどこまで上がって来たのか確認するため後ろを見た。
するとマノフは驚いた。
エバがすぐ近くまで迫っていたからだ。
そのエバから少し距離を空けてロミタスが来ていた。
そして、ロミタスから相当距離を空けて兵士たちが続いていた。
マノフは慌てて加速しようとした。
だが、見る見るうちにエバの足音が後ろからマノフに迫った。
エバの方がはるかに足が速かった。
マノフは気持ちは慌てているものの、疲労で足を絡めてしまった。
マノフは地面に転がった。
そして走ることを諦めた。
エバも足を止めると、座り込んでいるマノフを見下ろした。
「見るな、ボケが。」
マノフは肩で息をしながらエバにそう言った。
エバはただじっとマノフを見ていた。
だがエバは、そもそもエルファ語は分からなかった。
すると遅れてロミタスが到着した。
ロミタスとマノフは目を合わせた。
「ざまあみろ、この卑木のボケが。そう思っているんだろう。」
マノフがロミタスに悪態をついた。
「いいんだぜ、本性を出してみろよ。俺を追放した時のように。汚物を見るように俺を見ろ。汚い言葉をゲロみたいに吐いてみろ。それがお前たち、エルファ社会の本性だ!」
マノフにそう言われたロミタスは、右手で口を抑えるとじっと黙ってマノフを見下ろした。
ロミタスは言った。
「お前の言うとおり、そういう汚い気持ちが俺の心にはある。それは認める。」
ロミタスは片膝を突くと、マノフと視線の高さを合わせた。
「俺は、お前を追放したことを人生の中で何度も後悔してきた。俺は若かった。物事が分かっていなかった。お前の気持ちが分からなかった。一時の感情に任せて、お前を追放してしまった。」
ロミタスはマノフを見つめた。
「本当に、申し訳ございませんでした。」
ロミタスはそう言って頭を垂れた。
その瞬間、マノフは立ち上がった。
「ふざけるなよ!!」
マノフは激しくロミタスを睨んだ。
「そんなことで、そんなことで、俺は、俺は・・・、こんなの不平等だろうが!!」
マノフの目から涙が流れた。
エルファの森を追放されて、マノフは人間たちの街に潜り込んだ。
人間の言葉など分からない。
いつも腹を空かせていた。
どうやって生きて行けば良いのか、一人で途方に暮れていた。
それなのにこいつは、喰うにも寝るにも困らない生活をしながら、あの時はしまったしまったと後悔していたのだと言う。
ふざけるな!許せる訳がないだろうが!
人の命をないがしろにするのなら、自分の命もないがしろにされる覚悟を持つべきだ。
やはり俺は正しかった!俺はお前に復讐する権利が十分にあったのだ。
マノフは鼻をすすった。
「だから何なんだ。自分だけ気持ちを吐き出して、すっきりしてから俺を殺そうと、そういうことか。」
マノフはロミタスを睨んだ。
ロミタスは頭を上げてマノフを見た。
「謝罪して許される問題ではない。だが、俺はプファイト一族として今のお前を許す訳にはいかない。」
するとロミタスは立ち上がると、背中に差した鉈を抜いた。
「これが俺が出した結論だ。」
「何だと。」
マノフは、ロミタスの握った鉈を見た。
「今のお前がエルファ社会に恨みを持っていることは、俺に要因がある。だから、俺に復讐する権利は当然お前にある。だが、同じように、俺は今のプファイト一族の一員として、エルファの平穏を乱そうとしたお前を許すことはできない。お前を排除する権利を行使させて貰う。つまり、公平に、お前と俺のサシの勝負だ。お前が俺に勝ったら、このまま行かせてやる。どうだ?」
そう言ったロミタスとマノフの視線が交差した。
なるほど。少しは考えていたようだな。マノフはそう思った。
全力で戦って生き残った方が勝ち。
公平じゃねえか、エルファ社会よりもよっぽど公平だ。
「いいぜ、乗った。」
マノフはそう言って腰に差していた短刀を抜いた。
「エバ、悪いがサシでやらせてくれ。」
ロミタスがそう言うと、言葉は分からないがエバは何となく理解した。
2人が手に持った刃物を構え、間合いをとった。
するとマノフは、着ていた長袖の上着を脱ぐと左手で持った。
「何のつもりだ。」
ロミタスが声を掛けた。
「人間社会で覚えた、汚い戦闘術よ。」
マノフが左手に持った上着をひゅんひゅんと振り回した。
「なるほど。」
ロミタスが左手を背中に隠すと、右手に持った鉈を握りなおした。
2人はじりじりと左回りに回りながら、間合いを計った。
ロミタスの鉈の方が、マノフの持っている短刀よりも間合いが広かった。
だがマノフは、左手に持った上着を振り回しながら、ロミタスに間合いを読み間違えさせようと幻惑した。
お互いに牽制のため刃物を出しながら、相手の失敗を誘った。
「エバ。」
ようやく辿り着いたシェリルがエバに声を掛けた。
シェリルと一緒にたくさんの兵士たちも来ていた。
「サシでの勝負。手を出すなということらしい。」
エバがシェリルにそう言うと、シェリルは頷いて2人を見守った。
兵士たちも2人の様子を見て状況を理解すると、自然と2人を見守った。
「お父様。」
到着したエイリスが必死に声を掛けた。
エイリスと一緒にマリーウェザーやルーたちも到着した。
「前に出るな。俺とシェリルの後ろに居るんだ。」
エバがそう言って、エイリスやマリーウェザーを後ろに下がらせた。
そしてエバがエイリスに言った。
「親父が自分で決心したことだ。親父を信じるんだ。」
エバが真剣な目でエイリスを見た。
エイリスはエバの真剣な目を初めて見た。そして、この戦いが父親にとって重要なものであることを悟った。
エイリスはエバに頷いて見せると覚悟を決めた。
お父様、必ず生き残ってください。
エイリスは両指を握ると父親を強く信じた。
刃物による戦いは、一度間合いに入るとどちらかが致命傷を負い、そこで決着することが多い。
だから、不意打ち、2の手、奥の手が有効になる。
もちろん、用意した奥の手が最も効果的となる時機を逃さないようにすることが必要であり、また困難なことでもあった。
マノフには、今まで誰にもばれていない奥の手があった。
なぜなら、その奥の手を使った相手は必ず殺害してきたからだ。
ここぞという時に俺を助けてくれた奥の手だ。
だからマノフは、その奥の手を使う事に慣れていたし、信頼していた。
まずはその奥の手を使う環境を整える必要がある。
マノフは、左手に持った上着をロミタスの顔面に向けて、何度も繰り出した。
まずはこの上着が、ただの上着であることを印象付けなければ。
だがマノフは、ロミタスが背中に隠している左手が気になっていた。
あの左手が2の手か奥の手か、何か用意されていることは明らかだ。
だが警戒しすぎて時機を逸してしまってもいけない。
2人はお互いの些細な動きも見逃すまいと視線を鋭くして、じりじりと左回りに足を進めた。
ロミタスはどう戦うかを考えていた。
ロミタスは、プロの軍人として様々な戦闘訓練を積んでいた。
基本的には、マノフの攻撃に合わせて体に染みついた反撃技術で撃破していくことになるだろう。
マノフは何を仕掛けて来るか。
目潰しか、隠しナイフか、投げナイフか、それとも捨て身の突撃か。
するとじりじりと左回りに足を進めていたロミタスの視界に、娘のエイリスが映った。
エイリスの前を塞ぐように、エバがしっかりと立っていた。
ありがたい。
エバは、エイリスがマノフに狙われることを警戒しているのだろう。
その瞬間、ロミタスははっとした。
そうか、俺には大切な娘のエイリスがいるのだ。
せっかく娘を取り戻すことができたのに、俺が死んで、また娘を1人にする訳にはいかないな。
俺は勘違いをしていた。
俺は戦うのではない、必ず生き残らなければならない。
それならば。
ロミタスは覚悟を決めた。
このまま左回りに回って、ちょうどエイリスを背中に回した時、決着を着ける!
2人はじりじりとお互いを牽制しながら左回りに回った。
マノフが繰り出す上着攻撃が、時々ロミタスの顔をかすめるようになった。
つまり、この柔らかな上着なら、顔に当たったとしても怪我はしないと、知らず知らずのうちに刷り込まれてきているということだ。
そろそろ頃合いだな。
マノフはそう思った。
マノフはふと、ロミタスの後ろに、父親を心配そうに見つめる娘のエイリスの顔を見つけた。
マノフは不愉快になって、ぎりぎりと奥歯を噛んだ。
すると、ロミタスが背中に隠していた左手を露わにした。
その瞬間、マノフはロミタスの左手を見た。
ロミタスの左手には何も握られていなかった。
するとロミタスは、その左手でマノフがひゅんひゅんと振り回す上着を掴もうと手を伸ばした。
馬鹿が!マノフは思った。
マノフは上着を握っていた左手の力を緩めると、上着に仕込んでおいた鉄の棒を遠心力を利用して伸ばした。
そして鉄の棒が仕込まれた上着で、振り回した勢いのままロミタスの側頭部を打った。
だがマノフの動きはまだ止まらない。
マノフは一歩踏み出すと、視界を奪われ、頭部を打たれて身動きもできないロミタスに、右手に握った短刀を突き出した。狙っているのはロミタスの心臓だ。
「死ねえええええええええええ!」
マノフは叫んだ。
だが同じ瞬間、マノフが右手の短刀を突き出すのと同じ瞬間。
マノフは、ロミタスの右手がマノフに向かって伸びて来るのを見た。
そしてロミタスの右手には、さっきまで握られていたはずの鉈が握られていなかった。
ロミタスの右手に握られている物が何かを認識したとき、マノフは叫びながら目を見開いた。
プファイトの実だった。
ボワロが戦争で使う武器に利用しようと企んだプファイトの実。
ロミタスらプファイト一族が、育て、加工し、戦いに使用するプファイトの実。
ロミタスの右手には、そのプファイトの実が3つ握られていた。
ロミタスの右手はマノフの目の前で、そのプファイトの実を握りつぶした。
プファイトの実は爆発した。
爆発はロミタスの右手の指を全て吹き飛ばしたが、マノフの顔面も吹き飛ばした。
爆発した実の中から尖った種子が高速で飛び出し、マノフの全身の肉を抉(えぐ)った。
マノフは爆発の勢いで後ろに倒れ込んだ。
ロミタスも地面に倒れ込むと、頭を守るために覆っていた左腕の隙間からマノフを見た。
マノフの首はあらぬ方向に曲がり、顔面は肉が抉れて飛び散っていた。
マノフが身動きしないことを見届けると、ロミタスは気を失った。
ロミタスが目を覚ますと、すぐ側に娘のエイリスが居た。
エイリスは床にぺたりと座り込むと、目を瞑ってうとうとしていた。
ロミタスは右手に激しい痛みを感じたので右手を上げてみると、右手は布でぐるぐる巻きにされていた。
出血は止まっていたが、布は赤黒く染まっていた。
右手の指は失った。
だが、確実に生き残った。
プファイトの実を、指に隙間を作って握り潰すことによって、爆発の方向をマノフに集中させる事に成功した。
普通、プファイトの実は敵に投げつけて使用する。
確かに、敵の口の中でプファイトの実を爆裂させるという冗談は昔から聞いたことはあったが、まさかそれに近い事を実際にやる事になるとは。
「お父様、大丈夫ですか。」
エイリスが目を覚ましたようだ。
「心配を掛けたな。」
ロミタスはそう言って上半身を起こした。
「お父様、起きて大丈夫なのですか。」
「なあに、右手以外は特に怪我もないよ。」
ロミタスはそう言ってニヤリと笑った。
ロミタスは、自分が寝ていたのはエルファ軍の救護所だと分かった。
2人は少しの間黙っていた。
すると、エイリスが言った。
「マノフとの戦いは、避けることはできなかったの?」
ロミタスはエイリスを見ながら、何と言うべきか言葉を選んだ。
そして言った。
「避けることはできただろう。だが、俺は幸運だったと思っている。」
「幸運だった?」
エイリスが不思議そうな顔をした。
「ああ、そうだ。俺が若い時に犯した罪を、償う機会を与えられた。」
ロミタスはそう言って天井を見上げた。
「お前に話しをした事はなかったが、時折マノフの事を思い出しては、その度に後悔を繰り返してきた。俺は族長という立場を利用して、立場の弱いマノフを追放した。俺はその時、一族にとって役に立たない者は必要ないと考えていた。そして必要ない者を追放することも俺の仕事だと勝手に思っていた。」
ロミタスは一旦そこで話を切ると、エイリスを見た。
「だがその後、お前が生まれてふと思った。俺の娘が追放されたらどうだろうかと。俺の愛する娘が、1人の族長が必要ないと思ったせいで追放されたとしたら納得できるかと。納得できる訳がない。俺はただ、俺が気に入った者、俺の言う事を聞く者だけをえこひいきしていただけだ。気に入らないマノフに思い知らせてやると、族長という立場を利用して弱い者いじめをしただけだ。大体、プファイト一族の使命はエルファの平穏を守ることだろう、マノフはエルファではないのか?エルファの平穏を守るといいながら、平気でエルファの平穏を壊すとは、まさに本末転倒だな。」
そういうとロミタスは自分を嘲笑うように笑みを浮かべた。
エイリスは分かったというように頷いた。
「マノフは納得したかしら。」
ロミタスはかぶりを振った。
「納得することなどない。俺はマノフの未来を奪ったのだからな。それに、俺が罪を犯したことは俺自身が良く分かっている。どれだけ償っても罪は消えない。死ぬまで背負い続けるしかない。だからマノフの復讐を受け止める義務が俺にはあったのだ。だが、幸運にも俺は、受け止めるだけではなくて、同時に、俺の考える償いを1つすることができた。」
するとロミタスは、片方の眉を器用に吊り上げて見せた。
「悪い事をしたら、ごめんなさいと言う。お前にもそう教えて来たしな。」
ロミタスの言葉に、エイリスも微笑んで見せた。
ロミタスは立ち上がるとエイリスと一緒に天幕から外に出た。
外では、エバたちが焚火を囲んでエルファ軍の兵士たちと一緒に昼飯を食べていた。
マーリン兄妹は、エバたちと旅をしながらこれまでいくつもエルファの森を訪れて来たので、兵士たちからいろいろと尋ねられて人気があった。
もっとも、エルファの軍隊に女性のエルファが少ないことも人気の理由でもあった。
そこにロミタスとエイリスがやって来た。
「ロミタス、調子はどうだい。」
シェリルが尋ねた。
エイリスがロミタスに通訳した。
「想定の範囲内だよ。」
ロミタスは右手を挙げて答えると、激痛で顔を歪めた。
シェリルはロミタスに笑顔を向けた。
「良かったけど、これ以上は無理だな。」
するとシェリルはエイリスに言った。
「エイリス。ロミタスと一緒にここに残った方がいい。マックレとボワロが何と言うのか、それはソフィにしっかり聞いて貰うから。」
シェリルにそう言われたエイリスだったが、何と答えて良いのか分からなかった。
するとエイリスにソフィが声を掛けた。
「こっちに来て座りなよ。」
ソフィに誘われて、エイリスはロミタスを連れてソフィの隣に座った。
「とりあえず食べながら考えよう。はい。」
ソフィはくるみ入りのお団子をエイリスとロミタスに渡した。
ソフィは自分のお団子をかじるともぐもぐと食べた。
「おいしいね。素朴で綺麗な味がする。」
ソフィがエイリスにそう言った。
エイリスもお団子をもぐもぐと食べた。
「懐かしい味だわ。おいしい。」
ソフィとエイリスが笑顔になった。
すると近くに座っていた兵士がエイリスに話し掛けて来た。
「エイリスさん、人間と一緒にどんな生活をしていたのですか?」
「あの丘の上に砦が見えるでしょう?その隣にお屋敷が建っているんだけど、そこに住んでいました。」
「おお。」
なぜか兵士たちから歓声が上がった。
「私は領主のご家族と、それから隣にいるソフィと一緒に生活をしていました。」
そう言うとエイリスは隣のソフィと腕を組んだ。
「えっ、何々?」
腕を引っ張られながらソフィはエイリスを見た。
「お屋敷に住んでいた時の話をしているところ。」
「ああ、そういうこと。そうよ、エイリスと私は親友だからね。」
ソフィが仲が良いところを兵士たちに訴えた。
「お屋敷で何をしていたのかと言うと、私とソフィは奥様のお手伝いをしていました。お客様がいらっしゃれば奥様と一緒におもてなしの準備をして、時にはお客様にエルファの森の話を披露することもありました。」
「おお。」
また兵士たちから歓声が上がった。
「人間たちはエルファの事をどう思っているのですか?」
兵士の1人が手を挙げるとそう尋ねた。
「印象は良いです。私はエルファのお姫様と呼ばれていました。人間よりも華奢で体の線が細いことがよく羨ましがられました。」
「おお。」
また兵士たちから歓声が上がった。
「エイリスは美人だからな。」
兵士の一人がそう言うと、皆が頷いた。
エイリスは嬉しくなって笑顔になった。
「私が美人だって。」
エイリスが小さな声でソフィにそう言った。
「えっ、私の事は何か言ってないの?」
ソフィがエイリスに聞いた。
「そうね・・・、」
エイリスは少し考えた。
「もう少し大人しくしていた方が可愛いって。」
「絶対言っていないから、その嘘。」
ソフィが細い目をしてエイリスを見た。
エイリスはてへっという表情をした。
ロミタスは黙ってお団子をかじって座っていた。
「エルファの生活と人間の生活。どっちがいいですか?」
兵士の1人が手を挙げるとそう尋ねた。
「うーん、そうね。」
エイリスは少し考えた。
「好みはあると思いますが、どちらでも一緒だと思います。」
「おお。」
兵士たちから歓声が上がった。
「一緒とは以外でした。」
尋ねた兵士が驚いた顔でエイリスを見た。
エイリスはどう説明しようか少し考えると口を開いた。
「確かに私は、領主の屋敷から自由に外に出ることはできませんでした。でも、兵隊のみなさんだって、いつもは森に籠って生きていて、森の外に出ることはないでしょう。実はシャロムの街に住んでいる人間たちも、街の壁の中に籠って生活しているのですよ。一緒だと思いませんか?」
エイリスがそう言って兵士たちを見回すと、兵士たちは素直にうんうんと頷いた。
「それに、兵隊のみなさんは、エルファの森を守ることに誇りを感じたり、やりがいを感じていませんか。私も領主のご家族のお役に立つことにやりがいを感じていましたし、エルファの森の話をする時には、エルファとしての誇りを感じていました。一緒だと思いませんか。」
「おお!なるほど。」
また兵士たちから歓声が上がった。
「エイリスは大人気だね。」
シェリルがマリーウェザーに話し掛けた。
「ふふ、本当ね。でもちょっと悔しい。」
マリーウェザーがそう言うと、アレンティーが口を開いた。
「エイリスが来るまでは、私たちが人気者だったのに。」
アレンティーがそう言うと口を尖らせた。
「ははは、本当だね。これだけちやほやされると勘違いしそうだな。」
シェリルが2人に笑顔を向けた。
「それで、エイリスは何を話しているのかな。」
シェリルが尋ねた。
「うーん。エルファの生活も、人間の生活も同じだって、そんなことを言っていたかな。」
マリーウェザーがそう言って首を傾げた。
シェリルは納得した様子で何度も頷いた。
「なるほどね。エイリスが言った言葉。私は凄いな、と思ったよ。」
「そうなの?」
マリーウェザーが分からない顔をした。
シェリルは微笑んだ。
「エイリスはね、人間の世界で人質として生きたとしても、エルファとして森で生活していたとしても、一緒だと言ったのだと思う。そんな言葉、なかなか言えるものではないよ。」
「そうなんだ。」
マリーウェザーにはいまいちピンと来なかった。
「想像してごらんよ。突然なんだ。突然人質として連れていかれてしまう。今の生活とは何もかもが変わってしまう。父親であるロミタスにも、友だちにも会うことはできなくなる。見張られて、自由に外を出歩くこともできなくなる。普通に考えれば、自分は何て不幸なのだろうと考えてしまうだろうし、そう考えてもしようがないと思わないか?」
シェリルがそう尋ねると、それは分かったとマリーウェザーは頷いた。
「でもエイリスは、エルファとして森で生活するのと一緒だと言う。それは何ででしょう?」
シェリルは人差し指を立てると、マリーウェザーの顔の前でぐるぐると動かした。
マリーウェザーは首を傾げた。
するとアレンティーが言った。
「それはエイリスが言っているとおり、ソフィと一緒に奥様のお手伝いをして、やりがいを感じたからなのでは?」
アレンティーの言葉を聞いて、シェリルはアレンティーに笑顔を向けた。
「アレンティー、私もそう思う。」
アレンティーは少し照れて、でも嬉しそうにニコッとした。
「そっか、やりがいか。」
マリーウェザーがじっと黙りこんだ。
「どうかしたの?」
シェリルがマリーウェザーに聞いた。
「私のやりがいって何だろう、と思って。」
不安な気持ちが出てきたな。シェリルは思った。
マリーウェザーは時々、自分が希薄な存在なのではないかと、不安になることをシェリルは知っていた。
アレンティーにはそんな様子はなかったが、それは安心して良いということではなく、アレンティーの場合は、自分が気が付かないうちに不安を溜め込んでしまうのだった。
初めてマリーウェザーの手首を握ったとき、シェリルは、その手首のあまりの細さに衝撃を受けた。
幼い時に十分な栄養も摂れず、相当辛い経験を重ねて来たのだろうと、シェリルは胸が締め付けられる思いがした。
そしてマリーウェザーとアレンティーの2人は、ほとんど笑うことがなかった。
話さない訳ではないのだが、嬉しかったり楽しかったりということを、顔の表情に表すことがほとんどなかった。
辛さをどうにか軽減しようと、辛いという感情を一旦忘れてしまう、自分から切り離してしまう技術を身に着けたのだろう。
シェリルは2人と一緒に旅をして3年が経つが、その間、できうるかぎり2人に愛を注いできたつもりだ。
だがふとした瞬間に、後遺症のように、心の闇の部分が顔を出した。
「マリーウェザーは何の役に立つのだろうね?」
突然シェリルがそう言った。
だが、マリーウェザーもアレンティーも意味が分からなかった。
するとシェリルは、腰の剣に手を添えると2人に見せた。
「この剣は、人を殺す目的のために造られた。だから、人を殺すのに役に立つ訳だ。じゃあ、マリーウェザーは何の目的のために造られたのだろう。」
マリーウェザーは両腕を組むとうーんと考えた。
「そうか、私には造られた目的などないんだ。」
「そう、目的などない。マリーウェザーだけじゃない、私もアレンティーにも、造られた目的などない。そもそも人がこの世界に存在していることに目的などない。」
そう言ってシェリルはマリーウェザーとアレンティーを見た。
「じゃあ、役に立つとか、役に立たないというのは何なの?」
マリーウェザーがシェリルに尋ねた。
「例えば、このお団子は私のお腹を一杯にしてくれるから、私にとってお団子は食糧としてとても役に立つ。森に落ちているどんぐりは、豚さんのお腹を一杯にしてくれるから、豚さんにとって森に落ちているどんぐりは食糧としてとても役に立つ。だけど、私はどんぐりが嫌いだから、役には立たない。」
マリーウェザーがくすっと笑った。
「そっか、役に立つとか立たないというのは、絶対的なことではないんだね。人によっても物によっても、いろいろ違うものなんだ。」
マリーウェザーが分かった顔で頷いた。
シェリルはマリーウェザーとアレンティーを見た。
「マリーウェザーは、怪我をしたロミタスを魔法で治してくれたよね。アレンティーは、ルーに魔法の仕組みを詳しく教えてあげた。奥様やエイリスのために、マックレとボワロをどうするか、2人とも私と一緒に考えてくれた。奥様を殺したバークから証拠を吐かせるために、2人はキッドたちと協力して成し遂げた。それから、昨日宿屋で寝る時に、背の届かないルーの替わりに天井に吊るされたランプをマリーウェザーが取ってあげたよね。その後に、2人がベッドを魔法で綺麗にしてくれた。いじめ癖のあるモーリーと対決するベッキーを2人で応援してやっつけた。そして、お兄さんのマーリンを、2人はいつも気に掛けてあげている。」
シェリルはマリーウェザーとアレンティーを交互に見ながらそう言った。
「ちょっと照れるなあ。」
マリーウェザーがそう言うと、アレンティーがくすくすと笑った。
「私は知っているよ、2人が価値のある存在であることを。だから、一人で黙って抱え込まないで、不安になったら私に聞いて。2人に価値があることを、いくらでも教えてあげるから。」
シェリルはそう言ってマリーウェザーとアレンティーの肩をぎゅっと抱いた。
「人が存在することに目的などはない。だからマリーウェザーだけじゃなくて、私もアレンティーもみんな不安なんだ。自分に価値がないんじゃないかって。でも、みんな一緒なんだから1人で絶望する必要なんてないし、好きに生きていいんだよ。好きに生きていく中で、ちゃんと作られているんだ、2人の存在する価値が。」
「分かったよ。」
「私も分かったよ。」
マリーウェザーとアレンティーは嬉しそうに笑顔でそう言った。
本当に伝わったかな。シェリルはそう思った。
似たようなことは今までも何度も口にしてきた。
だが気を抜くと、後遺症のように、心の闇の部分が顔を出す。
2人は今まさに、自分自身を取り戻している最中だ。
だがそれには時間が必要なのだ。
その間に、2人がうっかりとその闇に落ちてしまわないように、私は何度でも2人に語り掛ける。
そう、何度でもだ。
「マーリン、いいか。」
ロミタスがマーリンに声を掛けた。
娘のエイリスは兵士たちとの会話が忙しく、ロミタスの居場所もなくなってしまったので、ロミタスはマーリンの横に移動したのだった。
「ロミタスさん、怪我はどうですか。」
「この程度、なんて事はない。」
ロミタスはそう言うとマーリンに白い歯を見せた。
「ひょっとして、お前が治療してくれたのか。」
マーリンは頷いた。
「ええ、出血がひどかったので、その場で私と妹で止血し、包帯でぐるぐる巻きにしました。」
「そうか、ありがとう。」
ロミタスはマーリンを横目で見ると、ニヤリと笑った。
「ドリューソンのことですが。」
マーリンが言った。
「悪いな。それが聞きたくてお前の所に来たんだ。」
ロミタスが申し訳なさそうに笑った。
「私は、自分の事は良く分かっていますよ。」
マーリンは笑顔を見せた。
そしてマーリンは話を続けた。
「ドリューソンは、裏切り者として拘束されました。手足を縛られて、顔だけを出して地面に埋められています。」
「そうか。」
ロミタスは頷いた。
「ドリューソンは、マックレもボワロも知っていましたよ。ただ、直接会ったことは無くて、マノフを通じて話をしていたようです。」
ロミタスは左手で口を覆った。そしてそのまま左手を下に下ろすと顎を撫でた。
「ドリューソンは何が目的だったのだろう。」
「ドリューソンは、マックレと手を握るつもりでした。そして、人間の協力を得ながらエルファの森を支配するつもりでした。」
「マノフは?」
「マノフは、マックレが偽物の領主であることを知っていました。そして、ドリューソンに自分の都合の良い情報だけを渡して操っていたようです。マノフが何を目的としていたのかは死んでしまって分かりませんが、恐らく、ドリューソンがエルファ社会の中で実力を持ったところで、ドリューソンを殺して自分が支配者となることを考えていたのではないでしょうか。」
ロミタスは納得したように頷いた。
「そうか。そんなところだろうな。」
ロミタスは溜め息をついた。
昨日の夜、マーリンと食事をしながら、エルファ社会に不満を持っている者がくすぶり始めていると聞いたばかりだ。
それがまさか、自分が生まれた森で起こっていたとは。
ロミタスはあまりの衝撃に額を手で抑えた。
もう対岸の火事ではない、防火対策を始めていく時期に来ていたようだ。
「まさか、マックレとボワロがエルファにまで手を伸ばしていたとはな。」
ロミタスはそう言って溜め息をついた。
「恐ろしいのはボワロでしょう。とても賢くて、思慮深い男です。とても危険な男です。危うくエルファは、ボワロの罠に陥れられるところでした。」
「そうだな。間一髪というところか。」
ロミタスは憂鬱になって目を伏せた。
「気を落としている暇はないかもしれませんよ。ロミタス部族長。」
マーリンはそう言ってロミタスを見つめた。
ロミタスはじっと目を伏せていたが、マーリンの言葉の意味に気付いて顔を上げた。
「今、このエルファの軍隊は、指揮官がいない危険な状態になっています。」
マーリンは言った。
「確かにな。だが、俺は族長でもなく、プファイトの一族でもない。」
「でも、兵士たちは、そうは思っていないみたいですが。」
そう言うとマーリンはニヤリと笑った。
ロミタスは左手で顎を撫でた。
そして片方の眉を器用に吊り上げて見せると、肩をすくめた。
「俺をこき使おうと言うのか?結構痛いのだぞ、この右手。」
「痛い方が良いのではないですか。」
マーリンの言葉にロミタスが不思議そうな顔をした。
「右手が痛む度に、マノフを思い出すでしょう。」
マーリンの言葉にロミタスは少し驚いた顔をした。
そしてロミタスは、片方の口元を引き上げると目を閉じた。
「そうだな。」
ロミタスはそう言った。
トーン、トーン、トーン、トーン。
時間を告げる兵士が太鼓を叩いた。
昼食時間が終了した合図だ。
「エイリス、ありがとう。頑張るんだぞ。」
「困ったら、俺に言うんだぞ。」
おじさんエルファたちはエイリスに思い思いの応援の言葉を掛けると、立ち上がると仕事に戻るためそれぞれの持ち場に歩いて行った。
兵士たちがいなくなると、エバたちは調理人と一緒に後片付けを始めた。
すると、座っていたロミタスが立ち上がると、エイリスの側まで歩いて来た。
「エイリス。」
ロミタスが声を掛けると、エイリスが顔を向けた。
「俺はここに残ろうと思う。シェリルの言うとおり、深手を負ってしまったし、どうやら俺のやるべきことがあるようだからな。」
エイリスは頷いた。
「それで、お前はどうする?」
どうしようかな。エイリスは迷っていた。
マックレが何と言うのか、聞かずには森に戻るつもりはない。
ソフィと一緒に行きたい気持ちはある。
だが、利き手が不自由となってしまった父親を放っておくわけにはいかない。
すると、エイリスの様子を見ていたロミタスが言った。
「迷っているなら、行ってきたらどうだ。」
エイリスがはっとしてロミタスを見ると、ロミタスは笑った。
「俺なら1人でも大丈夫だ。ここで待っているから。」
「お父様。」
ロミタスはエイリスの頬に左手で触れた。
「お前が50年も過ごしてきた街だ。お前の人生の大きな節目になるだろう。けじめをつけるためにも、行ってきなさい。」
エイリスは微笑んだ。
「行ってきます。」
するとエイリスは、周りを見て、片づけをしているソフィを見つけると速足で近付いた。
「私も片付けるわ。」
エイリスがソフィに声を掛けた。
「いいわよ。私たちでやるから、お父様と座っていたら?」
ソフィがそう言った。
「違うわよ。マックレとボワロを私も片付けるわ!」
ソフィが瞳を大きくしてエイリスを見た。
「いいの。」
「いいの。一緒に片をつけに行きましょう。」
エイリスが右手を差し出した。
ソフィはエイリスの手を握った。
2人は目を合わせるとニッと笑った。
「少しは静かになるかと思ったがな。」
2人の横を通り過ぎながらエバがぼそっとそう言った。
エバのその言葉にソフィが表情を一変させた。
「何よ、失礼ね。」
するとすぐにエイリスが続いた。
「そうよ、私に失礼だわ。」
「違うから、私だから。」
ソフィがすぐに訂正した。
二人の様子に、エバは肩をすくめると目を閉じて見せた。
「何だと」
ボワロは目を細めてマックレを見た。
「ですので、隣のステインの街に伝令が到着したか確認したところ、到着しておりませんでした。」
マックレはボワロの機嫌をなるべく損ねないように、申し訳なさそうに頭を下げた。
「何故だ。」
ボワロが尋ねた。
「分かりません。そこで他の街にも確認のため、既に使用人を向かわせております。」
「馬鹿!」
ボワロがマックレを罵った。
マックレは訳が分からず唖然とした。
「時間が無いのだぞ、今やるべきことは援軍を要請することだ。さっさともう一度伝令を走らせろ!」
するとボワロの言葉を聞いたマックレが顔を青くした。
「で、ですが、使用人を既に確認に向かわせてしまったため、走らせようにも人がおりません。」
マックレが恐る恐る頭を下げた。
この阿保が!!
ボワロはマックレの頭を鷲掴みにすると、マックレの顔面を床につけた。
そして言った。
「また、貸しができたな。いったいどうやって返すつもりだ。生きているうちに返済できるのか。」
ボワロはぐりぐりとマックレの顔面を床に擦りつけた。
「も、申し訳ございません。お、お許しください。」
マックレの情けない姿に、ボワロは心の中で笑って見ていた。
こいつ、完全に俺の奴隷だ。
ボワロは立ち上がると、マックレを見下ろした。
そして言った。
「許すに決まっているだろうが。」
マックレは右手で顔を抑えると、ゆっくりと顔を上げてボワロを見た。
ボワロはマックレに手を差し出すと、マックレを立たせてやった。
「言ったはずだ、俺が爵位を手に入れるには実績が必要なのだと。それには、エルファたちに勝たねばならないのだぞ。間抜けな騎士だけでエルファに勝てると思うか?援軍は必ず必要だ。それが、お前が高級役人に戻れることに繋がるのだ。自分事として胆に命じろ。」
「ボワロ将軍。」
マックレはそう言うと、力なく頭を垂れた。
「金を使え。城の伝令でなくとも、街の配達人に依頼すれば良いだろうが、書状をすぐに準備しろ。」
「承知いたしました。早速取り掛かります。」
マックレはそう言って顔を上げると、ボワロを見て、そして執務室から出て行った。
ボワロは愛用の椅子に身体を預けると、気に入っている合戦の絵画に目をやった。
シェリルだな。
ボワロはそう思った。
他に障害となりそうな人物は心当たりがない。
何をどうしたのか見当もつかないが、伝令を取り込んだのか、もしくは排除したのか。
最初に出立した伝令は切り捨てた方が良いだろう。
それにしても、シェリルは楽しませてくれる。
デートの時間が楽しみだ。
ボワロはニヤリと笑みを浮かべた。
「ボワロ将軍、商会の用心棒が参りました。」
部屋の外にいる侍従が声を掛けた。
「入れ。」
ボワロがそう応えた。
扉が開くと、背中に大きな剣を背負った男が顔を見せた。
「ボワロ将軍、獲物は何だ。」
大剣の男はそう言いながら、扉をくぐって部屋に入って来た。
「おうおう、久し振りの獲物だ。手強い奴を用意してくれよ。」
大剣の男の次に、背が低くずんぐりとしていて、顎髭を長く伸ばした男が刃の大きな斧を手に持って入って来た。
「金持ちならもっといいねえ。略奪品が楽しみだぜ。」
次に、細身のぴっちりとした服を着た男が入って来た。腰にいくつもナイフを提げていた。
「この愚か者たちに、神の思し召しがあらんことを。」
次に扉をくぐって部屋に入って来たのは、大きな紋章の入った上着を着た男だった。その紋章から神に仕える神官であることが分かった。
「我らを敵に回そうという、愚か者がいようとはな。」
最後に入って来たのは、大きなこぶのついた杖を持ち、赤色のローブを被った男だった。
最後の全身赤色の男が部屋に入ると、侍従が扉を閉めた。
ボワロは愛用の椅子に座ったまま、大剣の男に言った。
「お前たちの出番があるかもしれん、この城でしばらく待機して貰おう。」
すると大剣の男が言った。
「勿論だ。俺たちはプロだ。命令とあらば、ドラゴンであろうが、悪魔であろうが、ぶっ倒してやるぜ。だが1つ教えてくれ、今回の敵はどんな奴だ?」
大剣の男が目を鋭くしてボワロを見た。
ボワロは言った。
「女だ。」
すると、その言葉を聞いた大剣の男が、ガクッと大袈裟に態勢を崩した。
「ボワロ将軍、ちょっと待ってくれ。本当に俺たちが必要なのか?」
ボワロは大剣の男を睨んだ。
「聞いていなかったのか、出番があればだ。それに、女は殺すな、生け捕りにしろ。仲間がいるようなら殺して構わん。」
すると細身の男がクックックと独特に笑った。
「女を捕まえるのなら、俺があっという間に捕まえてやるよ。」
「大した自信だな。」
「任せておけ。」
すると細身の男がまたクックックと独特に笑った。
「敵の人数はどれくらいだ。」
背の低いずんぐりとした男がボワロに聞いた。
「その時にならなければ、それは分らん。」
「何だと。」
背の低いずんぐりとした男が眉をしかめた。
すると背の低いずんぐりとした男の肩を、全身赤色の男がポンポンと叩いた。
「そのような些細な事、問題ではない。いつものとおり、お前たちが前面に立って時間を稼ぎさえすれば、この爆炎の魔術師が、全て焼き払ってくれるわ!」
全身赤色の男がそう言ってヒッヒッヒと笑った。
「万が一のために、お前たちのような無法者に大金を払っておるのだ。成果を出せよ。」
ボワロが男たちにそう言った。
「安い仕事だ。余裕だぜ、ボワロ将軍。」
「我が強大な魔力の前に、ひれ伏すがよい。」
全身赤色の男がまたヒッヒッヒと笑った。
「よし、もう行け。」
ボワロがそう言うと、男たちは部屋から出て行った。
この男たちは、ドラゴンを打ち倒したという猛者どもだ。
シェリルの相手としては十分だろう。
シェリルに喜んで貰えるかな?
ボワロは笑みを浮かべた。
エバたちは、駐留地の入り口、馬車を止めて来た小さな広場に戻って来た。
キッド、ルー、ビリーが出発のために馬に飼葉を食べさせたり、小川で水を飲ませたりしていた。
ロミタスはバランヤと数人の部下を連れて、エバたちを見送りに来ていた。
「シェリルさん、準備出来ました。」
キッドたちが準備の終わりを伝えに来た。
ロミタスとマーリンは横に並んで立っていた。
「ありがとう、マーリン。いろいろと世話になったな。」
ロミタスが左手を差し出すと、二人は手を握った。
「いえ、ロミタスさんがいなかったら、エルファ軍を止められなかったかもしれない。こちらこそですよ。」
次に、ロミタスは、マーリンの後ろに立っていたマリーウェザーに手を差し出した。
マリーウェザーはロミタスの手を握った。
「貴方が俺の傷を治してくれたのだったな。恩に着る。何かあったらすぐに言ってくれ。エルファの軍隊はいつでも駆け付けてやるからな。」
「ありがとうございます。」
マリーウェザーは笑顔を向けた。
次にロミタスは隣のアレンティーに手を差し出した。
アレンティーはロミタスの手を握った。
「貴方は見た目よりも強い女性なんだな、横で見ていて感心していたんだよ。これからもお兄さんを助けてやってくれ。」
「ありがとうございます。」
アレンティーもニコッとした。
次にロミタスは、隣にいるキッド、ビリー、ルーに手を差し出した。
「お前たちにもすっかり助けられてしまったな。若いのに強く、逞しく、優しい。」
アレンティーがロミタスの言葉を3人に伝えた。
「ありがとうございます。」
「へへっ。」
「ありがとう。」
ロミタスは順番に3人と握手した。
「いつかエルファの森に来てくれ。歓迎しよう。」
ロミタスがそう言って3人に片目を瞑って見せた。
次にロミタスは、その隣にいるバクウェル、ルードに手を差し出した。
「あまり話をする機会もなかったが、人間の街では世話になった。ありがとう。」
ロミタスとバクウェルは手を握った。
マーリンがロミタスの言葉を伝えた。
「いやなに、エルファ軍を止めた貴方の功績は大きい。貴方に会えて良かったよ。」
次にロミタスはルードと手を握った。
すると改めてロミタスはバクウェルを見た。
「実は、お前たちには親近感が湧いてな。」
ロミタスはそう言ったが、バクウェルとルードは良く分からなかった。
「実は、俺もシェリルに一度こてんぱんにやられていてな。」
ロミタスはそう言ってニヤリと笑みを浮かべた。
マーリンから伝えられたロミタスとルードは声を出して笑った。
「マックレとボワロが気になるが、よろしく頼む。」
「任せてくれ。」
バクエルとルードは力強く頷いた。
次にロミタスは、隣にいるエバに手を差し出した。
「皆を守ってやってくれ。」
「まあな。」
ロミタスとエバは手を握った。
次にロミタスは、隣にいるソフィ、ソンドラに手を差し出した。
「娘と仲良くしてくれてありがとう。貴方のおかげだ。娘が心に明るさを持ち続けられたのは。」
ロミタスとソフィは手を握った。
マーリンがロミタスの言葉を伝えた。
「いえ、それはお互い様よ。私もエイリスから受け取ったわ。明るさを。」
ソフィは笑顔を向けた。
「貴方がエイリスを娼館にかくまってくれたのだったな。」
ロミタスとソンドラは手を握った。
「別に大した事はしていないさ。」
ソンドラは何でもないというようにかぶりを振った。
「もうしばらく娘をよろしく頼む。」
ロミタスは2人を見た。
「任せといて。」
ソフィは頷いた。
最後にロミタスはシェリルの前に立った。
「最初に出会った時の事を思い出すな。」
ロミタスはシェリルに微笑んだ。
ロミタスがバークにリンチされていたところに、シェリルがたまたま通りかかったのだ。
マーリンがロミタスの言葉を伝えた。
シェリルがロミタスに笑顔を向けた。
「あの時のロミタスの姿は良く覚えているよ、お前、道に捨てられたボロ布のようだったからな。」
シェリルとロミタスは声を出して笑った。
「最初の出会いは、もう少しかっこ良い姿で出会いたかったな。」
ロミタスは頭を掻いた。
「まさか、あの時はここまで話が大きくなるとは思っても見なかったよ。」
シェリルも昔を懐かしむようにそう言った。
「分かっていたら、助けなかったか。」
ロミタスはニヤリとした。
「まさか、助けたさ。ただ、さっさと正直に話せばいいのに、お前、意地になって黙り込んでさ。さらに私に噛みつこうとした。」
シェリルがロミタスを目を細くして見た。
「しようがないだろう、あれは。お前が信頼できるか分からなかったのだし。だが、一度噛みついておけば良かったな。俺はお前と一緒で負けず嫌いなんだ。お前にこてんぱんに伸されっぱなしで、お前に一矢報いていないのは納得がいかんな。」
ロミタスが猛獣のような目でシェリルを見た。
「おい、何を言い出すんだ。野生の目で私を見るな。」
シェリルが思わずのけ反った。

ロミタスはシェリルの怯えた態度に満足した。
「ははは、冗談だよ。冗談だ。」
ロミタスはシェリルに微笑んだ。
「昨日ごちそうしてくれた人間の料理も酒も、美味しかった。お礼を言っていなかったな、ありがとう。」
シェリルもロミタスに笑顔を向けた。
「事が終わったら、またみんなで食べよう。」
ロミタスはシェリルに手を差し出した。
シェリルはロミタスと手を握った。
シェリルの手は白くて、すべすべしていた。
すると、その手を握った感触が、ロミタスの心を不安にさせた。
確かにシェリルは強くて賢い。
だが、年齢はまだ若い。見た目で言えば娘のエイリスと同じ位だ。
ロミタスは親父の顔でシェリルを見た。
「気を付けてな。やばいと思ったら、すぐに逃げて帰って来い。お前の事を待っているから。」
「ありがとう。気を付けるよ。」
シェリルは少し照れた様子で頷いた。
シェリルはロミタスの手を離した。
「それでは行こうか。」
シェリルが皆に声を掛けた。
キッドとビリーは素早く馬に跨った。
マーリン兄妹は馬車に乗り込んだ。
ソフィとエイリスは同じ馬に跨った。
バクウェル、ルード、ソンドラも馬に乗った。
エバとシェリルは馬車の御者台に乗った。
皆の準備が整った。
「やあ!」
キッドが掛け声を掛けると、エバたちは進み始めた。
これからまた、シャロムの街に戻るのだ。
マリーウェザーとアレンティーが馬車の窓からロミタスに手を振った。
エバたちの姿が見えなくなるまで、ロミタスはエバたちを見送って、草原に立ち続けた。
マーリン「どうでもいい話ですが、シェリルは、気付かない振りをして人に尋ねることありますよね。」
エバ「ああ、あるな、それ。あるある。」
シェリル「ええっ、私そんなことしたことあったっけ?」
エバ「紙面の無駄だ。止めてくれ。」
シェリル「とぼけてました。すみません。」
マーリン「大体、いつも分かってますよねえ。分かっていて気付かない振りをしている。」
シェリル「ちょっと待った。気付かない振りなんて良くある話じゃない。何で私だけおとしめようみたいな空気になっている訳?」
エバ「だって、それは、なあ?」
マーリン「そうそう。シェリルの場合、誘っているというか、罠にはめようとしているというか。」
シェリル「そんな訳ないじゃない。自然体よ、自然体。」
エバ「自然体・・・、バーク、ゲーリー、伝令たち、ミンチン、ドリューソン、マノフ、その他やられた人。みんな自然体ではめられたという訳か。」
シェリル「はめられたというか、自分からはまったというか。てへっ。」
マーリン「無理だ。てへっ程度では中和できない恐ろしさだ。」
シェリル「あのねえ、自分は良い子ちゃんみたいな事言っているけどさ、普通にやっているでしょ。気付かない振り。」
エバ・マーリン「さあ。」
シェリル「朝、眠くて心を無にして歩いている時、よく喋る面倒な先輩を見つけたらどうよ?気付かない振りするだろう?」
エバ「ははっ、まあな。」
マーリン「あるっちゃ、ある。」
シェリル「混雑している訳でもないのに、背中のリュックを下ろせと言って来る変な親父がいたらどうよ?気付かない振りするだろう?」
エバ「そんな親父会ったことないけど、まあな。」
マーリン「酔っ払いか?」
シェリル「順番に並んで歩いていて、自分より5人位前の人が、うっかり横入りされちゃったんだけど、誰も文句言う人はいなくて、自分も5人も前だから文句を言おうにも言い辛くて、言ったら言ったで、こいつ器小さいなって白い目で見られるだろうなって、うーってなったとき、どうよ?そもそも横入りなんて自分は気付かなかったことにするだろう?」
エバ「ははは、まあな。」
マーリン「失くした方が良い記憶もあるか。」
シェリル「どうかね?皆の衆。」
エバ「結構面白かった、認めるよ。」
マーリン「頑張ったシェリルを認める。」
シェリル「良し。じゃあ、どうでもいい話はお開きにして、今回も呑みに行っちゃう?」
エバ・マーリン「おー。」
シェリル「じいさん岩から夕陽を眺めてワインを一杯やるのはどう?」
エバ・マーリン「おー!」
シェリル「何て言うんだろう?外呑み?」
マーリン「まあ、外呑みかな。」
シェリル「ジェシーおばさんのところでテイクアウトしよう。」
マーリン「ワインは樽ごと持っていこう。」
シェリル「樽ごとか、飲めるかな?」
エバ「夕陽が沈んだら、そのまま星空を眺めてホットワインといくか。」
シェリル「す!素敵すぎる。」
マーリン「いいねえ、ファンタジーだねえ。」
シェリル「野郎ども、外呑みしたいか!」
エバ・マーリン「おー!」
シェリル・エバ・マーリン「そーとのみ!そーとのみ!そーとのみ!そーとのみ!」
3人が徐々にフェードアウトしていく中、何か思い出したようにエバが呟いた。
エバ「あっ、俺も気付かない振りしてたな、タバスコ入りのレッドアイ。」
キッドたちと一緒にライダーとして働いているジミーは、午後の配達を届けにステインの街を出発すると、シャロムの街に来ていた。
シャロムの街に着いたジミーは、まず最初に街の集配所に行った。
ジミーは集配所に着くと、この街を通過するだけの書状をまず専用の木箱に入れた。
次に、城やら役所やら各組合やらの書状をそれぞれの専用の木箱に入れた。
木箱に入れる時には、集配所にいる計数人が書状の数を数えると、計数板にピンを刺して記録した。
「ジミー、何か面白い話ねえか。」
「ねえよ。」
計数人とつまらない話をしながら、書状を振り分けると、城やら役所やら組合やらの書状を紐で一括りに縛って、自分のずだ袋に放り込んだ。
このずだ袋に入れた書状が、ジミーがこれから配達する分という訳だ。
集配所は配達業組合によって運営されており、その組合の運営は、所属している配達人らが分担して仕事をしていた。
ジミーは集配所を出ると、ずだ袋を馬に括り付けた。
これから配達先を回って、書状を配達するのだ。
まず最初に向かうのはこの街の領主だ。
ジミーは領主の城に到着すると、空濠に掛けられた跳ね橋を渡って、城の入り口に来た。
入り口には衛兵たちが立っていた。
「おはようございます。」
ジミーが立っている衛兵たちに声を掛けた。
「おはよう、ジミー。待っていたぞ。」
すると衛兵の1人がジミーに向かって手招きした。
「何ですか?」
ジミーが分からない顔で尋ねた。
「事務員から、配達人が来たら連れてくるように言われていてな。」
衛兵はそう言うと先に立って歩き始めた。
ジミーは馬から降りると、馬を曳いて衛兵に付いて行った。
いつも荷物の受け渡しをしている事務所の建物につくと、馬を繋いでおくための横木に馬の手綱を結び付けた。
そしてずだ袋を背中に背負うと、衛兵と一緒に事務所に入った。
「配達人が来たぞ。」
衛兵が机に座っている事務員に声を掛けた。
「やっと来たか、待っていたんだ。」
事務員は立ち上がるとジミーを見た。
「配達物はそこの箱に入れてくれ。」
ジミーはずだ袋から城宛ての配達物を箱に入れた。
「お前のところは、配達人は何人いるのだ。」
事務員がジミーに聞いた。
ジミーは頭の中で考えた。
キッド、ルー、ビリー、バック、アイク、そして俺。全部で6人か。
「6人だな。」
すると事務員が頷いた。
「ちょうどいいな。」
事務員はそう言うと、奥の部屋からずだ袋を6つ持って来た。
「こいつを至急届けて欲しい。これが配達先だ。」
事務員から配達先の紙を受け取ったジミーは眉をしかめた。
「これは・・・、城の伝令が運ぶものじゃないのか。」
事務員が眉をしかめた。
「伝令が出払っているから依頼しているのだ。至急だ。金は払う。」
そう言うと事務員は机の上に金が入った袋を置いた。
ジミーが袋の中身を確認すると、相当な金が入っていた。
怪しいな。だが、いい商売だ。
「時間が無い。頼んだぞ。ええっと、お前の所は何という配達屋だったか。」
すると入り口に立っていた衛兵が口を開いた。
「仔馬便だ。」
「仔馬便だな。分かった、頼んだぞ。すぐに行け。」
ジミーはずだ袋を手に持つと事務所を出た。
「良い話だったろう。運が良かったな、ジミー。」
衛兵がジミーにそう言った。
とりあえず、この配達物の量は俺一人ではさばけない。
仲間の力が必要だ。
だがその前に、今持っているこの街の配達物をさっさと配ってしまわなければ。
ジミーはずだ袋を馬に括り付けると、馬に跨った。
「てや!」
ジミーは馬を走らせた。
エルファの軍隊の駐留地を出発したシェリルたちは、シャロムの北門に到着した。
だが、木材を組み合わせて作られた北門は、観音開きの扉を閉めていた。
「門は閉鎖だ!中には入れない!迂回しろ!」
門の物見櫓の上には何人か見張りの男たちがいたが、その中の1人が大きな声で声を掛けて来た。
「戦時体制か。」
馬車の御者台に座っているエバがぼそっと言った。
「これじゃ入れないわね。どうしよう。」
馬に乗ったままソフィが顔をエバに向けた。
「この程度の壁なら、馬車を諦めさえすれば、入る方法はいくらでもあるが。」
そう言うとエバは、北門の物見櫓を見上げた。
エバの隣に座っているシェリルも物見櫓を見上げた。
「見たことある顔がいるな。」
シェリルが嬉しそうな顔をしてそう言った。
「ああ、そうか。」
エバが分かった顔でそう言った。
シェリルは櫓の上に向かって手を振った。
「おーい!おじさーん!怪我はもう大丈夫なのか!」
シェリルが声を掛けると、見張りの中の1人が気付いてシェリルの事をじっと見た。
それからシェリルに向かって手を振った。
「何だ、あんた達か。怪我は大丈夫だぞお!」
おじさんは元気そうにそう言った。
「もしかして、昨日ガヤンの前で助けてあげたおじさん?」
ソフィが驚いた様子でエバに尋ねた。
「そうだ。」
エバがそう言うと、ニヤリと笑った。
昨日エバたちが、バークをやっつけるためにガヤンの詰め所に向かった時、詰め所の前で門番のおじさんが襲われていて、それをエバたちが助けてあげたのだ。
「おじさーん。ここ開けてくれないかあ!お願ーい!」
シェリルがおじさんに両手を合わせた。
すると、おじさんが他の見張りと話をして、それからおじさんと他の見張りの何人かが姿を消した。
すこし待つと、北門の片側の扉が内側にぎぎっと開いた。
エバたちの乗った馬や荷車は北門をくぐった。
都合良く、ちょうど北門の前にはエバたちしかいなかったので、すんなりと街に入ることができた。
北門はすぐに閉じられた。
北門の内側には、助けた北門のおじさんと他のおじさんが立っていた。
北門のおじさんたちは北門に閂を掛けた。
シェリルは御者台を下りると、1人で北門のおじさんの側まで歩いて行った。
「おじさんありがとう。」
シェリルは北門のはおじさんに笑顔を向けた。

「なあに、命の恩人のあんた達の頼みなら、断る訳にはいかねえだろう。」
北門のおじさんもニッと笑うと、歯が抜けて隙間のある笑顔を見せた。
昨日殴られた後が青あざになっていて痛々しかった。
「おじさん、顔が青く腫れているよ。」
シェリルが自分の顔で、北門のおじさんの青あざの場所を指で示しながら、笑顔でそう言った。
「ははは、大丈夫。女に水瓶で殴られたときに比べたら、屁でもないさ。」
北門のおじさんが陽気にそう言った。
「おい、それはいつの話だ?お前に女房なんていないだろうが。」
隣にいた別のおじさんがそう言って話に入って来た。。
「馬鹿野郎、俺が若い頃は、毎日とっかえひっかえ、チューチューかましてたのよ。」
北門のおじさんがそう言った。
「何言ってやがる、かましていたのはネズミだろうが。こいつ、門番の前はネズミ捕りをやっていたんだ。チューチューしてたのは女じゃねえ、ネズミだよ。」
さっきとはまた別のおじさんが、ネズミの真似をして前歯を見せながらそう言って近付いて来た。
シェリルは可笑しくなって声を出して笑った。
北門のおじさんたちは、シェリルが笑顔になったので、余計に喜んだ。
「ふざけるな、俺の事言える立場かよ。こいつだってな、門番の前は墓荒らしだよ。墓場でネズミとチューチューだからな。」
「はははは。」
楽しくて愉快なおじさんたちだ。シェリルは思った。
やっぱり助けておいて良かった。
仕事はできそうな感じはしないが、何だかんだで、幸せそうなおじさんたちだ。
シェリルが笑って出た涙を指で拭った
「この子だな、お前を助けてくれた可愛い子ちゃんというのは。」
「本当だ、顔に刀傷が2つついとる。女剣士か、勇ましいな。」
「凛々しい目をしとるな。」
北門のおじさんたちが陽気な下心満々の視線でシェリルを見た。
「ありがとう。で、北門を閉めていたのはエルファの軍隊のせいか?」
シェリルが北門のおじさんたちに尋ねた。
「そうだよ。」
おじさんの一人がそう言った。
すると北門のおじさんが心配な顔をした。
「そんなことより、衛兵が血眼になってお嬢ちゃんを捜しとるぞ。嘘の噂を流したと言っていたな。」
「そうか。ありがとう。」
シェリルが笑顔でそう言った。
「何かフードのような物で、顔を隠した方がいいぞ。」
さっきとはまた別のおじさんがそう言った。
すると、別のおじさんが良い事を思いついたように言った。
「そうだ、俺の上着を貸してやろう。被ると臭いぞ。」
シェリルはまた笑った。
「臭いのはいらないよ。ありがとう。」
そう言ってシェリルはおじさんたちに手を振りながら、エバたちの元に戻った。
「どうだった。」
エバがシェリルに尋ねた。
「私が街にデマを流したということで、お尋ね者になっているらしい。」
するとエバは、納得したように深く頷いた。
「そのとおりだからな。」
エバがそう言うと、思わずソフィがくすっと笑った。
さらに、キッドもルーもビリーもつられて吹き出した。
最後に、バクウェルとルードも声を出して笑った。
「ちょっと、皆で笑う事はないだろう。」
シェリルもつられて笑顔になった。
笑い終わったルーがふと気付いたように言った。
「でも、狙われているにしては、衛兵の姿が見えないわね。」
するとシェリルが思わせ振りな視線をルーに送った。
「恐らく、私の作戦が効いているのだと思うよ。」
シェリルはニヤリと笑みを浮かべた。
すると、ルー以外のここにいる皆が、ああ、あれねという顔をした。
「ええ、何でみんな知っているの?キッドは?」
ルーは振り向いて後ろに座っているキッドを見た。
「ああ・・・、ビリーから聞いたな。」
「ずるい!私だけなの。」
ルーがほっぺを膨らませた。
ルーの様子を見て皆は声を出して笑った。
「ルー、そのうち嫌でも見えて来るから安心して。」
シェリルがルーに片目を瞑って見せた。
エバ達は、街の北側を貫いているウェイン大通りを南に向かって進んだ。
目指しているのは、マックレとボワロがいる城だ。
すると、通りの先にたくさんの人だかりができているのが見えた。
「ルー、見えて来たよ。」
シェリルがルーに声を掛けた。
「あれなの?」
ルーが驚いた顔をした。
ウェイン大通りを埋め尽くした人だかりに近付いて行くと、人だかりの中心に、演台に上がって演説をしている人物が見えた。
「おっ、ミンチンが頑張っているな。」
シェリルがそう言ってみんなを見た。
「相当な人ですね。」
ルードがシェリルに嬉しそうな顔で言った。
「何々?」
馬車に乗っていたマリーウェザーとアレンティーも窓から顔を出した。
「あれ、ミンチンさん?」
マリーウェザーが驚いた顔をした。
「そうだよ。ミンチンを見直したかい?あれが彼女の力だ。」
シェリルが笑顔でそう言った。
演台の上でミンチンは声を張り上げた。
「この街は、私たちの祖父母の時代から、エルファとこれまで長い間に渡って、良好な関係を築いてきました。その間に、この街は戦争を2回経験しています。その時攻めて来たのは誰であったか?それは人間です。エルファではないのです。」
ミンチンはたくさんの市民を前にして、とうとうと語り続けていた。
「ミンチンさん、凄いね。」
ルーがそう言うと、皆も同じように頷いた。
「これだけの市民を相手にしているんだ、ミンチンの奴、快感に痺れているだろうな。」
シェリルがニヤリと笑みを浮かべた。
エバたちは、ミンチンに近付くため人だかりを迂回しながら演台に近付いた。
すると、ミンチンがエバたちに気付いた。
「アメリア、シェリルたちが来たわ。早くこっちに連れてきてちょうだい。」
ミンチンは演台の下のアメリアに言った。
アメリアは慌てて周りを見渡すと、エバたちを見つけた。
アメリアはエバたちのところに小走りで近付いた。
「遅いじゃないですか!早くこっちに来てください。」
アメリアがエバたちに苛立った顔でそう言った。
エバたちは演台のすぐ側まで馬を進めた。
ミンチンが演台の端まで来て、シェリルに話し掛けた。
「エルファの代表はどこです?代表にお話しいただかないと。」
ミンチンがシェリルにそう言った。
「悪いなミンチン。エルファの代表は都合により欠席となりました。」
シェリルがそう言って、てへっという表情をした。
「何ですと!」
ミンチンが驚いた顔をした。
「その替わり、エルファの姫君、エイリス姫にお願いしようと思う。」
シェリルがそう言ってエイリスを見た。
「行ってくるね。」
エイリスは、後ろに座っているソフィに声を掛けると馬を下りた。
エイリスは、アメリアに促されて演台に上がった。
「みなさん、大変長らくお待たせしました。私の話が本当であるということを証明するために、エルファの姫君、エイリス姫からお話をいただきます。」
ミンチンが街の人たちにエイリスを紹介した。
すると、数人の男たちが人混みを掻き分けながら演台に近づいてきた。
「何をしている!やめだ、やめだ!」
そう言って先頭を歩いている男にエバたちは見覚えがあった。
「あれは衛兵隊長だな。」
エバが言った。
「本当だ、ミンチンさんの家で私が腕関節を極めた人だわ。」
ソフィがそう言ってエバを見た。
衛兵隊長は演台の下からミンチンを見上げた。
「ミンチン市政長官、すぐにこの集会を取り止めろ。」
「なぜですか、私は参事会総裁から承認を得ているのです。」
ミンチンは鋭い目で衛兵隊長を見た。
「ヤドゥイカ子爵の命令だ。それに、ボワロ将軍がお怒りの様子だ。」
「何ですと!」
衛兵隊長の言葉を聞いた途端に、ミンチンは目を大きくしてとても驚いた表情を見せた。
「いけない!バクウェル、ルード、一緒に来てくれ。」
シェリルが、バクウェルとルードを引き連れて演台に近付くと、ミンチンに声を掛けた。
「ミンチン、ちょっと待て。」
「シェリル。」
ミンチンは驚いた顔をシェリルに向けた。
「何!シェリルだと!」
衛兵隊長も驚いた様子でシェリルを見た。
シェリルは2人に両手の平を見せると、落ち着くように2人の目を見た。
そして言った。
「ミンチン、お前に言っていないことがあった。衛兵隊長もよく聞いてくれ。今の子爵であるマックレは偽物だ。そして、それを仕組んだのはボワロだ。」
シェリルがあまりに唐突に言ったので、ミンチンも衛兵隊長も分からない顔をした。
「シェリル、もう一度聞いていいですか。」
ミンチンが尋ねた。
するとシェリルは、すぐ後ろにいるバクウェルに言った。
「バクウェル、反逆罪の執行令状を。」
バクウェルは頷くと、前に進み出た。
「ガヤンのバクウェルだ。」
バクウェルが2人に自己紹介した。
「ルード。」
バクウェルが後ろに控えているルードに手を差し出した。
ルードが、肩から提げている麻で作られた鞄から書状を取り出すと、バクウェルに手渡した。
バクウェルが、その書状をミンチンと衛兵隊長に見えるように両手で広げた。
「3年間もの間、ヤドゥイカ子爵の継承者であるとして国王を欺き、私利私欲のために領主の地位を利用し、国王が得るはずだった領地からの収入を領得した。国王の利益を大きく害した反逆者として、マックレとボワロを強制排除する。」
「何ですと!!」
ミンチンと衛兵隊長は、目を大きく見開くと驚いた表情を見せた。
「シェリル!なぜそのような大事な事を言ってくれないのですか!ひどいじゃないですか。」
ミンチンがシェリルを睨んだ。
「ごめん。そこは申し訳ないが、逆に知ってしまうとお前が動きづらいだろうと思ったんだ。」
シェリルが両手を胸元で合わせると、てへっという顔をした。
「証拠はあるのか?」
衛兵隊長がバクウェルを鋭い目で見た。
「私はガヤンだぞ。当然だ。」
バクウェルも負けじと衛兵隊長に胸を張った。
「・・・そうか。承知した。」
衛兵隊長はそのまま後ろに引き下がって行った。
「さあミンチン、続けてくれ。」
シェリルがミンチンに促した。
「勿論ですとも。」
ミンチンはエイリスを演台の中心まで手を引っぱって行った。
エイリスは演台から大通りに集まった人々を見渡した。
凄い人の数だ。エイリスは思った。
本当はお父様がこの場所で語る筈だったのだ。
でも今は、替わりが務まるのは私しかいない。
これまで領主の奥様と一緒に、上流階級のお客様をおもてなししたことは何度もあったけれど、このようなたくさんの人の前で話をするのは初めてだ。
さすがに緊張するな。
エイリスは深く深呼吸した。
エイリスは目を瞑った。
こういう時は、まず、自分が緊張していると自分で認めることだ。
だから、普段話をしているように上手く話せなくてもしようがない。
そう覚悟を決めることだ。
だめでもともと。谷底からの始まり。0点から得点を積み上げていくのだ。
エイリスはゆっくりと目を開いた。
「みなさん、私はエルファのエイリスです。どうか、私の話を聞いてください。」
エイリスは、父親のロミタスがそうしたように、皆が静かになるまで待つと、話し始めた。
「私がこの街に来たのは今から50年前、青の帝国よりも古いザノン王国が、この街に進撃したときのことでした。私が来た時には、この街はオルセチカという名前でした。知っていますか?オルセチカはヤドゥイカ砦で悪魔を打ち倒したという英雄ですね。昔話で聞いたことがあると思います。では、シャロムと言うのは何でしょうか?私は初代ヤドゥイカ子爵のジョン様から聞いたことがあります。シャロムというのは、当時の市政長官の名前です。シャロム市政長官はジョン様に直訴したそうです。ザノン王国と開戦するよりも、賠償金を支払った方が安く済むだけでなく、街の人々の命も守れますと。」
エイリスは、大事な何かを守るように、目を瞑ってそう言った。
そして改めて皆を見渡した。
「ジョン様は、シャロム市政長官の意見を聞きいれました。街の人々も、開戦すれば敗けることが分かっていたため、受け入れました。そして、ジョン様は、あの丘の上にあるヤドゥイカの砦で、私の父であるロミタスと会談しました。そして、父ロミタスは、ジョン様に協力することを約束したのです。その証明が私なのです。」
エイリスはそう言って、自分の胸に手を当てた。
「では、この街がシャロムという名前となったのは何故でしょうか。」
エイリスは顎に右手を添えると、演台の上を少し歩いて見せた。
「それはジョン様が名付けたのです。シャロム市政長官は、敵を無傷で街を通過させたとして、反逆罪で処刑されました。それを悲しんだジョン様が、戦後この街の名前をシャロムとしたのです。」
街の人々の中には驚いた表情をする者もいれば、静かに聞いている者もいた。
シャロムの街の由来はそれなりに知られているようだ。
エイリスは話を続けた。
「ジョン様は私によく言っていました。シャロム市政長官は、処刑される直前まで胸を張っていたと。ジョン様が自分を信頼してくれたことが、誇りであり、自慢ですと。そう言った時ジョン様は、目に涙を浮かべていました。自分はシャロム市政長官を、守ってやることができなかったと。」
「バクウェル、知っていたか?」
シェリルがバクウェルに聞いた。
「記録は見たことはあったが、ジョン様が語った言葉など、初めて聞いた。」
バクウェルが大きく頷いた。
「彼女は本当に、この街にとって貴重な存在ですね。」
バクウェルの隣で、ルードも大きく頷いた。
エイリスは街の人々を見渡した。
「私はこの街に来て50年が経ちますが、それを昨日の事のように覚えています。その私が、エルファを代表して皆さんに伝えます。エルファはあなたたちの敵ではありません。私は変わらずに、エルファが人間の敵ではないことを証明いたします。」
そう言い終わると、エイリスは、街の人々が自分を信頼してくれることを祈って、目を瞑って、胸の前で両指を握った。
街の人たちを相手に、初代ヤドゥイカ子爵であるジョンの話をするのはこれが初めてだ。
街の人たちの中には、初代ヤドゥイカ子爵であるジョンが決めた、戦争をしないという政策を、良かったと考えている人もいるだろうし、悪かったと考えている人もいるだろう。
だが、少なくともジョンは、エルファであるエイリスを、自分の家族と同じように接してくれた。
領主一家の一員と認めてくれたのだ。
その時にエイリスはまだ幼くて、その意味が良く分かっていなかった。
エルファの森から連れて来られて、ひどい仕打ちを受けなくて良かったと、ただ、そう思っていた。
そのジョンは、39歳で亡くなった。
内臓に疾患を持っていたジョンは、度々腹痛でベッドに伏せていたが、最後は熱を出し、苦しみ、衰弱して亡くなった。
その時エイリスは、ベッドの側で、2代目の子爵のカーターと一緒にジョンを見送った。
ジョンの奥さんは、カーターを出産した時に既に命を落としていて、ジョンは独り身だった。
ジョンは、肉体も精神も疲れ果てた様子だったが、意識が無くなってしまう前に、エイリスを見て言った。
「今まではあえて口にしたことはなかった。口にすれば、お前を悲しませてしまうと思ってな。でも、私ももう最後のようだから言っておこうと思う。」
するとジョンは、寂しそうな目でエイリスを見た。
「私の娘でいてくれて、ありがとう。私はお前との生活が、とても幸せであったよ。」
ジョンはそう言うと、エイリスの頬に手の平で触れた。
「エイリス、本当の気持ちを口に出して言ってごらん。言ってくれていいんだよ。偽物の父親だというのに、長い間付き合わせてしまって、本当に、申し訳なかった。」
その時、エイリスの目から涙が溢れた。
エイリスはその時にようやく理解した。
ジョンは、ずっと罪の意識に悩んで来たのだ。
私を本当の父から引き剥がしてしまったことに、一番娘が成長する大事な時期であるのに、共に過ごす時間を奪ってしまったことに。
だから私を家族と同じように接してくれたのだ。
エイリスは、ジョンの苦しみを少しでも楽にしてあげたいと思った。
エイリスは涙を堪えて言った。
「お父さま・・・今までありがとうございました。これが、本当の気持ちです。」
エイリスはジョンの右手を両手で握った。
ジョンは左手で顔を覆うと、ぎゅっと口を結んで、静かにむせび泣いた。
私は政治のことは良く分からない。
けれども、私がはっきりと言えるのは、ジョンが私にとって誠実で、優しさの溢れる人物であったということだ。
その事が、少しでもこの街の人々に伝わって欲しい。
このシャロムの街は、そのジョンの思いによって名付けられた街なのだから。
エイリスは握った両指に力を込めた。
すると、ぽつぽつと拍手の音が聞こえてきたが、それがだんだんと大きくなり、ついにはたくさんの人がエイリスに向かって拍手を送った。
「信じてるよ。エイリス姫!」
「引き籠っている領主より、よっぽど信頼できらあ!」
「エイリス姫、素敵!」
街の人々が思い思いの言葉をエイリスに送った。
エイリスが思わず涙ぐんで、指で拭った。
「エイリス、凄いね。」
マリーウェザーが嬉しそうにそう言った。
「街の人々の多くは、理屈ではなく、自分の味方になってくれる人物かどうかを、動物のように本能で見極める。やっぱり、本当の自分を曝(さら)け出さないと、信頼されないよね。上辺だけの言葉や態度は、すぐに見透かされてしまうよ。」
シェリルがマリーウェザーとアレンティーにそう言った。
「そっか。」
そう言うとマリーウェザーもアレンティーも小さく頷いた。
演台の上では、エイリスに替わってミンチンが話を続けていた。
「みなさん、これで分かったと思います。エルファの軍隊は心配ありません。これからエルファの使節団が、ヤドゥイカ子爵に説明に行きます。安心してください。子爵の誤解もきっと解けるでしょう。この街の平和は守られるのです。」
ミンチンがそう言って拳を突きあげると、街の人々から歓声が上がった。
「私たちはそろそろ行こうか。」
シェリルはそう言うと、演台から降りて来たエイリスの肩を叩いた。
「で、衛兵たちは結局どこに行ったのかしら?」
マリーウェザーが首を傾げた。
「衛兵たちなら、この人だかりの中にいるぞ。」
キッドがそう言って、人だかりの中を顎で示した。
「そうなの。」
「ああ。恐らく、シェリルさんを捕まえるどころではなくなっているのだろう。エルファの軍隊はこの街にとって一大事だからな。」
シェリルたちは、人だかりの出来ている大通りを一旦迂回して横道に入ってから、大回りをして、またウェイン大通りに戻って来た。
エバたちはウェイン大通りを南下すると、マックレとボワロがいる城の入り口に到着した。
今朝、伝令たちから書状を受け取った時には、城の入り口に架かっていた跳ね橋は跳ね上げられ、渡ることができないようになっていた。
跳ね上げられた跳ね橋は城の入り口を塞いでいた。
「これじゃあ、中に入れないわね。」
ルーが後ろに座っているキッドにそう言った。
キッドは左手を挙げると、馬を止めた。
「何が起こったのだろう。」
キッドが閉じられた跳ね橋を見た。
「戦時体制という事だろう。つまり、この街が戦場になると思っている訳だ。」
御者台に座っているエバがキッドにそう言った。
キッドは心配そうにエバを見た。
「戦場になるなんて・・・、そんなこと、ないですよね。」
「勿論だ。」
エバはキッドを安心させようとニヤリと笑みを浮かべた。
「何だ、安心した。」
キッドがふうと息を吐くと肩を下ろした。
「だが、これでは城に入れないぞ。」
バクウェルが馬に乗ったままそう言った。
「そう言えば、見張りもいないですね。」
ルードが額に手をかざして城壁の様子を窺った。
「どうします?シェリルさん。」
ビリーがシェリルを見た。
「なあに、こっちには、この城のことをよーく知っている人物がいるじゃないか。」
シェリルが横目でソフィとエイリスを見た。
「えっ、何々。もしかして私たちの事かな、それは。」
ソフィが、同じ馬で前に座っているエイリスの肩に手を置くと、偉そうな風を装ってそう言った。
「そういえばいたな。城を抜け出すのが得意なお転婆姫が、二人も。」
エバがニヤニヤした顔でそう言った。
「何よそれ、普段から城を抜け出していたみたいじゃない。」
ソフィが頬を膨らませた。
「違うのか。」
「さすがに城の外に出たりしないわよ、ね。」
ソフィが前のエイリスを見た。
エイリスは少し空を見上げて考えた。
「そうね。せいぜい、城壁沿いにぐるっと1周したりとか、その程度よ。」
「十分頼もしいな。」
エバがそう言って肩をすくめると目を瞑った。
「でも、どうやって中に入るのですか。」
キッドがソフィに尋ねた。
するとビリーが分かった顔で手を上げた。
「あっ、分かった。聞いたことがある。・・・小麦袋の中に身を隠して潜入する。」
「なるほど、食糧に偽装する訳か。」
エバが感心した様子で頷いた。
「そうか、お城の兵士もお腹が減るからね。」
馬車の窓から顔を出して聞いていたマリーウェザーが、頷いてそう言った。
するとルーが良い事を思いついた顔をした。
「だったら、大きなパンの中に隠れるというのはどう?」
すると、ルーの言葉に皆が声を出して笑った。
「ルー、面白い。」
「それなら楽しくて、中に入れて貰えそうだわ。」
マリーウェザーとエイリスが笑顔でそう言った。
「ルー、とっても面白かった。でも、違うんだなあ。それじゃあ、私とエイリスが脱出した道を逆に辿って、お城の中に行くわよ!」
ソフィがそう言うと、皆を見渡した。
「おー!」
皆がそう言って拳を突き上げた。
「じゃあまずは、馬を休ませに行きましょう。お城の中には歩いて行くからね。馬を休ませたら、次に娼館に行くわよ。」
「娼館って、昨日ソフィとエイリスに会った娼館の事。」
ルーが不思議そうな顔でソフィに尋ねた。
「そうよ。」
ソフィがルーにニコッとした。
「見たらびっくりするわよ。」
「うわあ、何だろう。楽しみ。」
ルーがわくわくした様子で笑顔を見せた。
「それじゃあ、まずはガヤンの詰め所に向かおう。次に、ジェシーおばさんの宿屋に行って馬車をしまったら、最後に娼館に向かうことにしよう。」
シェリルが皆にそう言うと、城の前を出発した。
エバたちはウェイン大通りを南下し、まずガヤンの詰め所に向かった。
ガヤンの詰め所は、この街の中心を通っているファネリー大通りとウェイン大通りが交わる位置にあり、いわゆる街の中心にあった。
街の人々は、エルファの軍隊のことが心配で、仕事にならない様子だった。
「エルファの軍隊は攻めてこないんだろう、じゃあ、早く街の門を開ければいいじゃねえか。」
「ヤドゥイカ子爵とエルファの間で話がついていないらしい、それが終われば、ミンチン市政長官から開門の指示が出るそうだ。」
「どっちにしたって、早く決着を付けて貰わねえと仕事にならないぜ。門の前で商品が立ち往生しているんだ。」
街の人々は軒先に出ると、お隣さんと集まって何度も同じ話をしていた。
「街の人々の為にも、早く決着をつけてあげなくちゃね。」
ソフィが前に座っているエイリスに言った。
「そうね。」
エイリスが頷いた。
ガヤンの詰め所の入り口には、椅子にどかっと座って足を組み、周囲を眺めているガヤン神官の男がいた。
バクウェルが椅子に座っているガヤン神官の前まで来ると、馬を止めた。
「非番だというのに、ご苦労な事だな、バクウェル。」
椅子に座っているガヤン神官が、ニヤニヤした笑顔を見せた。
バクウェルの同僚だ。
ガヤンは、当番の朝から次の日の朝まで勤務する、交代制の当直勤務だ。
バクウェルは、本当は今朝までの勤務で、実は今は非番なのだ。
目の前で椅子に座っている同僚が今日の当番だった。
「行きがかり上、放っておく訳にもいかなくなってな。」
バクウェルが口をへの字に曲げると困った顔をした。
「確かにな。」
同僚のガヤン神官も同じように困った顔をした。
「一報は朝一便で送ってくれたか。」
「ああ、お前の申し送りのとおり、朝一便で送っておいたよ。」
バクウェルは、王宮への報告書を作成し、朝一番の定期連絡で送付するように申し送っておいた。
最初の一報は速さが大事だ。
王宮が変な疑念をこの街に持って、軍隊が派遣されるようなことがないよう、こちらが先に手を打っておかなければならない。
勿論、エルファの軍隊は平和的で問題はないと記載してある。
「ありがとう。助かるよ。」
「なあに、王宮への報告は面倒だからな。報告書をまとめるお前の苦労を考えると、お安い御用だ。」
同僚がそう言うと、椅子に座ったまま背伸びをした。
バクウェルの部下のルードは、乗って来た馬を馬屋に引き入れると、詰め所の入り口に戻って来た。
すると、キッドがルードに声を掛けた。キッドの隣には、ビリーとルーも一緒だった。
「ルードさん。弟さんのテッドの様子を見に行くんでしょう?」
「ああ、まあ大人しくしているだろうが。」
ルードがそう言って苦笑いをした。
「だったら、俺たちも一緒に行っていいですか?バークの様子を見に行きたいと思って。」
「そうか、じゃあ一緒に行こうか。」
ルードとキッドとビリーとルーは、同僚と話をしているバクウェルの後ろを通って、詰め所の中に入った。
ルードが先頭に立って、入ったすぐの執務室から取調室、談話室を抜け、宿直室、備品庫の扉を横に見ながら進むと、奥に並んでいる牢が見えた。
ルードはどんどん奥に進むと、弟のテッドが入っている牢の前で止まった。
「バークはこの先だ、分るよな?」
「分かります。じゃあ。」
そう言うと、キッドたちは突き当りにあるバークが入っている牢に向かった。
牢の扉は木製で、補強のため鉄の板が横向きに2本取り付けられ、小さなのぞき窓が一つ付いていた。
キッドとビリーがのぞき窓から覗くと、バークは仰向けになって床に転がっていた。
バークは、偽物の領主マックレの命令で、領主の奥さんを殺した男だ。
「寝てるのかな。」
ルーが牢の中を覗き込むとそう言った。
「覗き込んでんじゃねえよ。見世物じゃねえんだ。」
バークは寝転がったままキッドたちにそう言った。
ビリーはバークに話し掛けた。
「バーク、お前、マノフっていうエルファを知っているか。」
ビリーの問い掛けに、バークは少しだけ体を動かした。
「いや、知らねえな。」
「偽物の領主マックレは、エルファと手を握る筈じゃなかったの?」
ルーがバークに尋ねた。
「そんな訳ねえよ。マックレにはエルファの顔見知りなどいなかった。」
キッドたちは、顔を見合わせて分からないという顔をした。
だが、キッドは、少しの間じっと黙って考えると独り言のように呟いた。
「ボワロか。」
するとルーとビリーがキッドを見た。
「えっ。」
「何だ。」
ビリーとルーが分からない顔を見せた。
「マノフは、人間と手を握るつもりだった。それに、マノフはマックレとボワロを知っていた。だがマックレは、マノフを知らなかった。だとすると、マノフが手を握るつもりだった人間とは誰だ。」
「なるほど・・・、それでボワロか。」
「そうか。」
ビリーとルーが頷いた。
「マノフがマックレとボワロを知っているのに、マックレがマノフを知らないのはなぜか。それはボワロがマックレにマノフの事を教えていなかったからだ。きっと、マノフが都合の良い情報だけをドリューソンに与えて操っていたように、ボワロはマックレとマノフを操っていたんだろう。」
「じゃあ、やっぱりエルファの軍隊を止めて良かったという事だよな。」
ビリーがキッドとルーにそう言った。
「だってボワロは、諸侯に援軍を要請する程戦争がしたかったのだろう?それなのに、エルファであるマノフが手を握るなんてできるのかよ。俺はマノフが、ボワロに騙されていたのだと思うね。だから、マックレはマノフを知らないのさ。」
ビリーがそう吐き捨てた。
「ボワロって、シェリルさんに纏わりつくエロ親父だと思っていたけど、凄く悪い人みたいね。」
ルーがそう言った。
「おい!」
突然バークが大きな声を出した。
「何だ。」
キッドがバークに尋ねた。
「マックレとボワロはどうなった。捕まえたのか。」
バークは天井を見つめながらそう言った。
「これからだ。これから城に行ってくる。」
キッドが答えた。
「そうか、なら、お前たちが返り討ちに会う事を祈ってるぜ。」
バークの言葉を聞くと、キッドたちは顔を見合わせて、その場を離れた。
「ああ痛え、痛えよう。暴力を振るわれた顔が痛ええよお!」
バークはキッドたちに聞こえるように、わざと大きな声で何度もそう言った。
キッドたちは、戻る途中でルードに会った。
「どうでした?弟さん。」
ビリーがルードに声を掛けた。
ルードがかぶりを振った。
「まったく、あんなことがあったというのに、反省が足りていない。」
ルードの弟のテッドは、ごろつきのゲーリーとつるんで、弱い者から金を巻き上げたりしていたが、バークから依頼を受けて、エイリスの父親のロミタスを捕まえようとして暴力を振るった。
そして昨日の夜中、エバたちと戦闘となりゲーリーは死亡。テッドも殺されそうになったが、兄のルードが命懸けで、エバたちからテッドを守ったのだ。
「テッドは何て言っていたんだ?」
キッドがルードに尋ねた。
「今度は兄貴に迷惑を掛けないように、上手くやるからって。」
ルードがそう言うと困った顔をした。
「何だそれ。」
「全く反省してねえな。」
キッドとビリーが苦笑いを見せた。
するとルーが、いじめ癖のあるモーリーおばさんの事を思い出した。
ルーはマリーウェザーと言い合ったのだ。モーリーのいじめ癖は一生治すことはできないかもしれない。でも、その時にはまた懲らしめてやれば良いと。
ルーはルードを見た。
「テッドが悪い事をしないか、私も目を光らせておくことにするわ。何かあったら、教えてあげる。」
ルーはルードにそう言った。
ルードが驚いた表情をした。
するとキッドとビリーも顔を見合わせると小さく頷いた。
キッドはルードに言った。
「俺たちも配達で街を回るから、テッドの事を気にしておくよ。何かあったら連絡するぜ。」
ルードは、キッドたちの言葉に温かい気持ちになった。
ルードがキッドたちに笑顔を向けた。
「そうか、ありがとう。確かに、悪い事をするのは、悪い事ができる環境があるからだ。皆が目を光らせていると知れば、抑止力になりそうだな。」
ルードの言葉にルーの顔がぱあっと明るくなった。
「そうよ、悪い人間なのだとしても、悪い事ができなければ、良い人間と一緒だわ。みんなで悪い事をうっかりしてしまわないように、目を光らせれば良いのよ。」
「それにテッドも、兄貴に迷惑を掛けることは今後しないと、一応心に誓ったんだろうからよ。」
ビリーがそう言った。
「そうだな、ありがとう。」
ルードは、自分の後輩とも言える目の前の若者たちの逞しさ、そして優しさがとても嬉しかった。
「それなら、早速テッドに挨拶しておくか。」
ビリーがそう言うと、テッドの入っている牢の中を覗き込んだ。
「テッド!俺はライダーのジミーだ。これからはお前が悪さをしないよう、俺も目を光らせておくからな、覚悟しろよ!」
牢の中のテッドは、床に寝転んで顔だけをビリーに向けると、訳が分からず唖然としていた。
「キッドもルーも、こっちに来いよ。」
ビリーはキッドとルーの腕を引っ張った。
「こいつがキッドで、こいつがルー。2人もライダーだ。2人もお前の事を見張っているからな、よろしくな。」
牢の中のテッドは、良く分からない顔をしてビリーに右手を上げた。
「それじゃ、そろそろ行きますか。」
ビリーがそう言った。
「何しているのよ、テッドが不思議そうな顔していたじゃない。」
ルーが呆れた様子でそう言った。
「全く、何を考えているんだか。」
キッドも頭を左右に振った。
「良いって事よ!」
ビリーは1人で満足そうに頷いた。
「ええっと、ビリー。」
ルードが笑顔でビリーを見た。
「おう、何だ。」
「弟のルードは、お前たちよりもずっと年上なんだが。」
ルードがそう言うと、ビリーは少しの間じっとして考えた。
「大丈夫。俺は全く、年の差なんて気にしませんから!」
ビリーが右手の拳をぐっと握って見せた。
「本当は気にしているくせに。」
ルーがすかさずそう言った。
ルーの言葉に、みんなで声を出して笑った。
そしてルードとキッドたちは詰め所を出た。
「そろそろ行くぞ。」
外に出ると、シェリルと話をしていたバクウェルが、ルードとキッドたちに声を掛けた。
エバたちは、今度はジェシーおばさんの宿屋に向かった。
ガヤンの詰め所がちょうど街の真ん中にあって、ジェシーおばさんの宿屋はここからファネリー大通りを南下し、横に走っているプチヘンリー通りに入ると、少し進んだところの左手側にある。
ジェシーおばさんの宿屋は、ライダーであるキッドたちが、仕事が遅くなって一泊する時によく使っている宿屋だ。
「あそこよ。」
ルーが皆に声を掛けた。
通りの突き当り左側、荷車が宿屋の前に止まっていた。
エバたちは宿屋の前につくと、キッドたちはサッと馬を下りた。
キッドは宿屋の大きな両開きの扉を開けると、ビリーとルーが乗って来た馬を宿屋の中に引き入れた。
入り口を入った正面の奥が、馬屋となっているのだ。
「おい、キッド」
キッドに横から声を掛ける者がいた。
キッドは声が聞こえた宿屋の広間の方に目を向けた。
宿屋の入り口を入った右側は大きく開けた広間になっており、中央に暖炉が置かれ、暖炉の周りを囲むように背もたれの無いベンチが置かれていた。
キッドに声を掛けて来た人物がそのベンチに座っていた。
「ジミー!」
キッドがベンチの人物に向かってそう言った。
ベンチに座っていたジミーは立ち上がるとキッドの方に歩いて来た。
手に、ずだ袋を6つも持っていた。
「そっちは順調か?」
ジミーはそう言って右手を挙げた。
「まあ順調だ。」
キッドはそう言って右手を挙げると、お互いに相手の手の平を叩いた。異常なしの挨拶だ。
「そっちは?」
キッドはそう言って、ジミーの持っているずだ袋を見た。
「実は、手に余る仕事を押し付けられて困っていたんだ。」
ジミーはずだ袋を持ち上げて見せた。
すると、馬屋に馬を繋ぎ終えたビリーとルーも近付いて来た。
「よう、ジミー。」
「お疲れ、ジミー。」
ビリーとルーも、ジミーとお互いに相手の手の平を叩いた。
「どうしたの?それ。」
ルーがそう言って首を傾げた。
「城からの依頼でな。至急だそうだ。」
するとビリーはピンと来た。
「ちょっ、これは。シェリルさん!」
ビリーはシェリルを呼んだ。
「どうしたんだ、ビリー。」
外で待っていたシェリルやエバたちが宿の中に入って来た。
「城から依頼があったって。」
ビリーはそう言ってジミーの持っているずだ袋を手で示した。
「何か、見たことがあるような代物だな。」
シェリルはそう言いながら歩いて来ると、ジミーを見上げてニコッとした。
ジミーはシェリルに見つめられてちょっとどきどきした。
「ビリー、この方は。」
ジミーがビリーに尋ねた。
「俺たちライダーを雇っているお客さん、シェリルさんだ。」
ジミーは驚いた顔をした。
「あなたがシェリルさんですか。ライダーのジミーです。ビリーたちと一緒に働いています。」
ジミーはシェリルに手を差し出すと、シェリルと手を握った。
シェリルの手は白くて、すべすべしていた。
「それで、このずだ袋は何でジミーが預かることになったんだ。」
シェリルが首を傾げてジミーを見た。
「いや、ええっと。伝令が出払っているからって依頼されました。至急だって。」
ジミーは少し緊張してそう答えた。
「そうか、1つ見せてくれないか。」
シェリルはそう言ってずだ袋の1つを示した。
するとジミーはビリーを見た。
「見せて大丈夫だ。」
ビリーの言葉を聞いてジミーは、ずだ袋の1つをシェリルに渡した。
シェリルが袋を開けると、中には書状がたくさん入っていた。
「配達先は?」
シェリルがジミーに聞くと、ジミーは思い出したように別のずだ袋から丸めた1枚の紙を取り出した。
「配達先と言って渡されたものです。」
「ソフィ、一緒に見てくれないか。」
シェリルはソフィに声を掛けた。
シェリルとソフィは広げた紙を覗き込んだ。
「これは、領内の騎士らに宛てたものと、周辺の諸侯に宛てたものね。」
ソフィは配達先を見てそう言うと、はっとした表情を見せた。
「やっぱりね。」
シェリルは頷くと、書状の1つを手に取ってマーリンに投げた。
マーリンは危なげな様子で書状を何とか掴むと、書状を広げて確認した。
「援軍の要請だ。」
マーリンは言った。
「しつこいな、あいつら。」
ビリーが嫌な顔をした。
「だけど運が良かったな。また俺たちの手元に書状が来たぜ。」
キッドそう言うとニヤリと笑った。
そして少しの間、皆は黙ってじっとしていた。
すると、ビリーが我慢できなくなったように小さくククっと笑った。
ビリーの小さな笑いにつられて、キッドもフッと笑った。
「はははは!」
シェリルが堪らずに思わず声を出して笑うと、この場にいるみんなで声を出して笑った。
マックレが諸侯に援軍を要請した書状を、シェリルたちは伝令から回収することができた。
そして、恐らくマックレはその事に気付いて、もう一度書状を送ろうとしたのだろう。
だが、その書状さえも、こうしてシェリルたちに回収されてしまったことになる。
「こんなことあるか?」
「どんだけ運が悪いんだよ。いや、俺たちの運が良すぎるのか?」
「マックレとボワロが知ったら、さぞ残念がるだろうな。」
そう言うと、また皆で声を出して笑った。
「何がおかしいのかさっぱり分からねえ。」
ジミーだけが分からない顔で皆を見渡していた。
「ジミー、お前の押し付けられた仕事は、私が全部引き受けよう。つまり、お前が押し付けられた面倒な仕事は消えてなくなった。」
「本当ですか!やった!」
シェリルの言葉にジミーは両手を上げて喜んだ。
「ちょうどいい、書状は全て燃やしてしまおう。間違って出回っても厄介だ。」
シェリルがビリーを見た。
「分かりました。」
ビリーは伝令から回収した書状の束と、ジミーから受け取った書状の束を持って、暖炉の前に来た。
「あばよ。」
ビリーは書状の束を炎に投げ込んだ。
「それじゃあ、この金はシェリルさんにお渡しします。」
ジミーが金の入った袋をシェリルに渡した。
シェリルが中身を確認すると、相当な金額の金貨が入っていた。
「ジミーこれは?」
「城の事務員から貰った配達料です。やってもいない仕事の金はいりません。どうせ、親父さんに巻き上げられるだけですから。」
ジミーがしようがないという顔でそう言った。
「分かった。ジミー、今日はこの街で泊りかな?」
「そうですね。今日はこの宿で一泊です。」
「分かったよ。」
その後キッドたちは、まだ通りに残っていた馬を馬屋に曳き入れたり、馬車を納屋にしまった。
「それじゃあ、行きますか。」
ビリーが皆に声を掛けた。
ジミーはキッドたちがいない分、ライダーの仕事が忙しいので、エバたちと一緒には行かなかった。
「ちょっと待った、ビリー、今日の夜はどうするんだい?」
ジェシーおばさんが外に出ようとするビリーに声を掛けた。
「今日の夜?」
ビリーは分からない顔をするとシェリルを見た。
「当然、帰って来るさ。ジェシーおばさん、夕食の準備をお願いします。」
「分かったよ。気を付けてね。」
エバたちはジェシーおばさんの宿を出て、次はソフィとエイリスが隠れていた娼館に向かって通りを歩き始めた。
馬に乗っているのは、あとソフィとエイリスだけだ。
娼館につけば、そこからは徒歩で、ソフィとエイリスが脱出した道を逆に辿って、城に向かうのだ。
「トロマおじさん、行ってきます。」
ビリーが玄関先に出ていたトロマおじさんに声を掛けた。
トロマおじさんは、手を振ってエバたちを見送った。
「閣下、戦いの準備は目途がつきました。ですが、すぐにヤドゥイカ砦に出立するのはいかがなものか。」
大柄な男の騎士が、マックレにそう申し立てた。
大柄な男の騎士の後ろには、9名の騎士たちが立っていた。
「なぜだ。」
マックレが尋ねた。
「シェリルが言っています。エルファは敵ではないと。しかし、それはきっと嘘なのでしょう。だが、まずはシェリルを捕らえて、シェリルの言っている事が本当に嘘だと分かってから、ヤドゥイカ砦に向かっても遅くないのではないか。」
大柄な騎士はマックレを正面から見た。
「ふむ、ではシェリルはいつ捕まるのだ。」
マックレは肘を椅子の肘掛けに乗せ、その乗せた手で顔を支えると困った様子でそう言った。
「シェリルは、午後にでもエルファの使節を連れて、この城に説明に来ると言っていた。」
「それが本当だと言える証拠はあるのか。」
マックレは詰まらないことでも話すように大柄な騎士にそう言った。
「・・・。」
大柄な騎士は、一瞬、じっと黙り込んだ。
そしてまた口を開いた。
「閣下、街をご覧ください。大通りで市民が集まって騒ぎを起こしている。エルファは敵ではないのだと。エルファと戦うのは間違いだと。そこを我々が武装して通りかかれば、暴動が起きかねない。」
大柄な騎士が強い調子でそう言った。
「だからどうしたのだ。」
マックレの態度に、大柄な騎士は思わず眉間に皴を寄せた。
「閣下、そうなれば我々に被害が出るだけでなく、市民にも被害が出ることとなりますぞ。」
大柄な騎士はマックレを睨んだ。
だが、マックレは表情を変えることはなかった。
「我は別に卿らに市民へ暴力を振るえとは言っておらぬが。さっさとヤドゥイカ砦に出立すれば良かろう。」
「・・・。」
大柄な騎士はマックレの言葉に唖然とした。
ああ言えば、こう言う。大柄な騎士は思った。
しかし、マックレの口から出ている言葉はその場を取り繕うばかりで、結局、閣下は何をする気もないのだ。
いや、何もする気はないのはいつものことだが、なぜ閣下は、ボワロの言うことだけは黙って従っているのだろうか。
「ボワロ将軍か。」
大柄な騎士はそう口にするとマックレを睨んだ。
「何だ?」
「閣下、ボワロ将軍は一介の商人に過ぎません。ボワロ将軍の言う事をなぜそこまで重んじられるのか。」
マックレは一瞬の間、黙って大柄な騎士を見た。
そして口を開いた。
「ボワロ将軍の言っていることは正しい。卿もそうは思わぬか。」
何をしらじらしい。大柄な騎士は思った。
正しいとか正しくないとかで、行動するようなタマではなかろうが。
お前は俺と同じ俗物(ぞくぶつ)。
楽して金を得ることだけを考えているようなタマであろうが。
すると大柄な騎士ははっとした。
そうか、マックレは弱みを握られているのだ。
ボワロに。
だからボワロに服従しているのだろう。
ならば、さらに一押ししてみる価値はあるか。
大柄な騎士は口を開いた。
「恐れながら閣下。我ら城の騎士は、閣下の騎士でございます。」
大柄な騎士はそう言ってマックレを見た。
「どういう意味か。」
「閣下が命令を下されば、一介の商人など一瞬で剣の錆となりましょう。」
「・・・。」
マックレの片方の眉がピクリと動いた。
「今は戦時。何が起こっても不思議はありません。例えば、戦時であることを良い事に、それにつけ込んで儲けようとする不届きな商人がいれば、罰して財産を没収されてしまうことは、ありえる話ではないか。」
大柄な騎士は鋭い目でマックレを見た。
マックレと大柄な騎士の視線が交差した。
なるほど。手を組もうという事か。マックレは思った。
いかにボワロがずる賢いといっても、所詮は人間。
これだけの人数で打ちのめせばただの肉の塊となろう。
だが、マックレはボワロを裏切ることはできないと考えていた。
この目の前の大柄な騎士は、所詮これまでボワロに打ちのめされて来ただけの小者。
ボワロと大柄な騎士、どちらを信頼するかと言えば、そんなこと選択の余地もない。
ボワロに決まっている。
確かにボワロから暴力を振るわれることがある。だがそれは、俺が失敗したことが悪いのだ。
その証拠に、ボワロは最後には必ず俺を許すのだ。
それに、俺とボワロは危険な秘密を共有しているのだ。
ここまで来た以上、もう引き返すことなどできない。
何とか無難に領主役をやり切って、高級役人に返り咲くのだ。
マックレは口を開いた。
「止めておくことだ。」
「何?」
マックレの言葉に、大柄な騎士は分からない顔をした。
「貴卿はボワロ将軍にこれまで何度打ちのめされたのか忘れたか。己が分というものを、わきまえるが良い。」
「閣下!閣下は悔しくないのですか!確かにこの街は、ボワロから巨額の金を借りておるのでしょう。かと言って、我々はボワロの奴隷ではないのですぞ!」
大柄な騎士は、唾を飛ばしながらまくし立てた。
「そういう問題ではなかろう。ボワロ将軍の言っていることが正しいというだけだ。」
くそう。大柄な騎士は思った。
マックレなら味方に付けられると思ったが、仕方がない。
判断を誤ったことを地獄で後悔するが良い。
大柄な騎士は剣を抜いた。
「おい、マックレ。」
大柄な騎士はニタリと笑みを浮かべるとマックレに近寄った。
大柄な騎士の異様な態度に、マックレは立ち上がると、椅子を盾にするように後ろに回り込んだ。
すると、マックレの後ろに控えていた家令たちが、慌てて大広間の端の方へ逃げた。
「この、偽物が!」
大柄な騎士はそう言ってマックレを見た。
さすがのマックレも思わず目を見開いた。
「お前が領主になってから、給料は減らされるし、面倒な仕事は増えるし、阿保なボワロに馬鹿にされるし、良い事など一つもなかった。それで今度は戦争だと!ふざけるな!どこまで俺たちをコケにすれば気が済むのだ!」
大柄な騎士はそう言うと、思いっ切り床を踏みつけた。
踏みつけれらた木の床が大きな音を出して、広間に響き渡った。
「追加報酬が出る訳でもなく、死ぬかも知れぬのだぞ。」
大柄な騎士は一歩マックレに近付いた。
「お前たちが死ね。」
大柄な騎士は剣を高く振り上げた。
「行くぞ、ヤドゥイカの騎士よ!不届き者を血祭りに上げるのだ!」
「おお!」
他の騎士もそれに続いた。
大柄な騎士は剣を後ろに大きく振りかぶると、マックレが盾にしている椅子に剣を叩きつけた。
剣は椅子の背もたれの半分程を斬り裂き、背もたれがばっくりと割れた。
マックレは顔を青くして後ろに後ずさった。
大柄な騎士は大股でマックレに近付くと、わざと大きく剣を振り上げた。
「ひい!」
マックレは床をごろごろと転がった。
大柄な騎士は剣を振り下ろした。
大柄な騎士が振り下ろした剣は、床を激しく打った。
「戦争ですからな。思いもよらない事が起こりますぞ。」
大柄な騎士は興奮した様子でマックレを見下ろした。
その時だった。
部屋の扉が開いてボワロが現れた。
「ボワロ将軍!」
マックレが床を這って、ボワロの足元に転がり込んだ。
すると、ボワロだけでなく5人の人物がボワロの応接室から現れると、ボワロの後ろに並んだ。
マックレは知っていた。ボワロの後ろに並ぶ5人の人物は、ボワロが雇っているならず者たちだ。
「閣下、どうやら不届きな騎士どもが謀反を起こしたようですな。」
ボワロがそう言って大柄な騎士を睨んだ。
「どうやら悪の黒幕が姿を現したようだな。」
大柄な騎士もそう言ってボワロを睨んだ。
「何かおかしいと思っていたのだ。なぜ閣下がお前のような一介の商人の言いなりになっているのか。これまで良くも騙してくれたな。」
大柄な騎士はボワロにそう言った。
「何の事だ。」
「ふざけるな!マックレは偽物。偽物の領主だ!ガヤンも言っていた、証拠があると。」
だが大柄な騎士の言葉にも、ボワロは眉一つ動かさなかった。
「そうか。で、」
ボワロは何でもないというように大柄な騎士に尋ねた。
「で・・・、ガヤンは後からここに来るそうだ。お前たちを排除するために。だが、その前に、我らヤドゥイカの騎士が、不届き者を血祭りに上げるのだ!」
大柄な騎士が何かを払いのけるように剣を横に薙ぎ払った。。
「なるほど。で、それだけか。」
ボワロが尋ねた。
「何?」
大柄な騎士が分からない顔を見せた。
「それだけかと聞いておるのだ。」
大柄な男はボワロの言葉に、何と言えば良いのか戸惑った表情をした。
「この馬鹿が!」
ボワロの言葉に、大柄な騎士は反射的にたじろいで体をのけ反らせた。
「まんまと敵の嘘に騙されおって。そんなこと、証拠なら我らにもある。」
「何。」
大柄な騎士は唖然とした顔に変わった。
「国王から賜った授与状だ。」
「何!」
大柄な騎士が目を大きく見開くと驚いた顔を見せた。
「貴卿も知っていよう。前代子爵が亡くなり、その領地を引き継ぐ際には、王宮で相続のための叙任式が執り行われる。そこで国王から賜るのが、王宮財授与状だ。」
「まさか!」
大柄な騎士は床に転がっているマックレを見た。
「もちろん、持っておる。」
マックレがそう言った。
大柄な騎士の顔から一気に血の気が失われた。
大柄な騎士は後ずさりした。
「さて、」
ボワロは、大柄な騎士とその後ろに集まった騎士どもをゆっくりと見渡した。
そして静かに言った。
「この中で不届き者は誰か。」
するとボワロは、猛獣が獲物に襲い掛かるような表情に豹変すると大きな唸り声を上げた。
「不届き者は、誰だあああああああ!!」
大柄な男もその後ろに並んだ騎士たちも、ボワロの声に思わず怯んでしまった。
すると、大柄な男の後ろに並んでいた騎士たちがゆっくりと後ろに下がっていった。
それに気付いた大柄な騎士が顔を後ろに向けた。
「おい、何だ。儂(わし)だけ置いて行くなよ。」
ボワロはゆっくりと大柄な騎士に近付いた。
大柄な騎士は青い顔でボワロを見ると、じっと動けないでいた。
騎士としての誇りが、ほんの一かけら残っていたか。ボワロは思った。
忠誠を誓ったはずの領主を、己の誤った思い込みで殺害しようとしたのだ。
誰が考えても死罪に値する。
だから大柄な騎士は、剣を抜いて襲い掛かって来ないのだろう。
なかなか面白い男であった。
まだ利用することはできた。
だが、さすがに謀反を起こした騎士を許してしまっては、騎士という組織が成り立たなくなってしまう。
残念だが、お前を利用するのはここまでのようだ。
当然、俺が終わらせてやる。それが道具の所有者である俺の義務だ。
ボワロは大柄な騎士の前に立つと、大柄な騎士が右手に握っていた剣をむしり取った。
「貴卿は領主に刃を向けた。分かるな、もう騎士ではない。」
大柄な騎士はじっとボワロを見た。
大柄な騎士は動かなかった。
するとボワロは、むしり取った剣でおもむろに大柄な騎士の腹を刺した。
「あうあ!」
大柄な騎士は剣が腹に突き刺さったまま、その場で床に膝を突いた。
ボワロは、刺さった剣をしっかり握ると勢いよく引き抜いた。
「あああああ!」
大柄な騎士は、腹を抱え込んだ格好のまま、床にごろごろと転がった。
あまりの痛みに、言葉にならない呻き声を出しながら、床をのたうち回った。
腹から流れ出た血液が、床に血溜まりを作った。
他の騎士たちは、大柄な騎士があらぬ方向を見ながら、のたうち回る様子を唖然とした様子で見ていた。
するとボワロは、のたうち回る大柄な騎士に近付くと、剣を大きく振りかぶった。
「この、ど阿保おおおおおおおぅ!!」
ボワロが剣を力一杯に振り下ろした。
振り下ろされた剣は、大柄な騎士の頭を割って、床に突き刺さった。
頭をかち割られた大柄な騎士は、体の反射でぴくぴくと体を震わせていたが、もう生きてはいなかった。
ボワロは血の滴る剣を持ったまま、他の騎士たちを鋭い目で見た。
他の騎士たちは、猛獣に睨まれた家畜のように身を縮めた。
すると、ボワロは情けない騎士どもに怒りが込み上げて来た。
この汚物どもが!
この情けない騎士どもは、これまで一体何をした?
大柄な騎士にすがっているだけ。
そして情勢が不利となった途端に大柄な騎士も見捨てるとは。
こいつらは、大柄な騎士以下の連中だ。
「おい。」
ボワロが後ろに立っている5人のならず者に声を掛けた。
「どうしたボワロ将軍。」
背中に大きな剣を背負った男がボワロを見た。
「粉砕しろ!」
ボワロがそう言った。
「あいよ。」
大剣を背負った男がそう言うと大きく跳躍した。
「なに!」
大剣の男の跳躍があまりに大きく人並み外れていたので、騎士たちは思わず驚いてそう言った。
大剣の男は背中に背負った剣を両手で鞘から引き抜くと、空中で大きく振りかぶった。
「危ない!」
騎士たちは身の危険を感じて慌ててその場を離れた。
「おうらあ!」
大剣の男は着地と同時に大剣を打ち下ろした。
大剣は木の床に突き刺さっただけだったが、何か普通ではない凄い印象を与えた。
「やっぱり人間はちょろちょろして当たらねえな。ドラゴンの方が楽に当たるぜ。」
すると騎士らの1人が大剣の男に剣を振りかぶると走り寄った。
「たあああ!」
大剣の男が隙だらけに見えたのだろう。騎士は叫びながら大剣の男に近付いた。
だが大剣の男に近付いた騎士は突然つまづいて床に転がった。
「いっ、痛あああ。」
転がった騎士の右の太腿にナイフが突き刺さっていた。
「へへっ、素敵な援護だろう。」
細身のぴっちりとした服を着た男がそう言った。
そして、腰にいくつも提げているナイフを1本右手に持つと、クックックと独特に笑った。
「おらあ、どこ見とるんじゃい!」
背が低くずんぐりとしていて、顎髭を長く伸ばした男が、刃の大きな斧を振り回しながら騎士たちに近付いた。
「なんだ、このずんぐりむっくりは。」
騎士たちが警戒して距離を取った。
「馬鹿にしとると痛い目を見るぞ。そらあ!そらあ!」
ずんぐりとした男は、恐れを知らないかのように斧を振り回しながら近づいた。
「このお!」
騎士が剣を横に薙ぎ払うと、ずんぐりとした男の二の腕を斬り裂いた。
「ふん。」
だがずんぐりした男は痛みを感じないのか、お返しとばかりに斧の刃で騎士の胴を払った。
「あがあ!」
騎士は、斬られた胴を抑えて床に転がった。
騎士は、小さな鎖を繋ぎ合わせて編んだ服を着ていたが、ずんぐりした男の斧は、その服ごと腹を斬り裂いていた。
「よくもやりやがったな。」
他の騎士がずんぐりした男の胸を剣で斬り付けた。
「うが。」
ずんぐりした男も小さな鎖を編んだ服を着ていたが、剣の刃は鎖の表面を滑ってしまって、致命傷を与えることはできなかった。
しかし、ずんぐりした男は、剣で打たれた衝撃で後ろに転がった。
「全く、ドワーフはこれだから。しようがないですね。」
大きな紋章の入った上着を着た男がそう言った。その紋章から神に仕える神官であることが分かった。
神官は懐から扇を取り出すと、その扇を広げて顔を隠した。
すると広げた扇で円の形を描きながら、神官はくるくると舞った。
「ジンマイウ、アーメラ、ギウマスセツダ、セツダ、セツダ、マーセツダ。この愚か者に、神の慈悲を与えたまえ。アーメラ。」
すると床に転がっていたずんぐりした男はむくっと起き上がると、また斧を振り回して騎士に迫った。
ずんぐりとした男の二の腕についていた、剣で斬り裂かれた斬り傷は塞がっていた。
「おらあ!」
大剣の男も剣を大きく左右に振り回し、一歩ずつ騎士に迫った。
「ふん!ふん!ふん!」
大剣の男も、ずんぐりした男も、持っている武器自体が重く威力があったので、騎士たちは警戒して周りを取り囲むと、2人が疲れるのを待った。
そうやって騎士たちが反撃の機会を伺って様子を見ていた時だった。
「ヒッヒッヒッヒッヒ。」
5人のならず者の中で、一番後ろでぼそぼそと呟きながら杖を振り回していた全身赤色の男が、突然笑い始めた。
その瞬間、大剣の男とずんぐりした男はさっと左右に分かれて飛び退いた。
「灰となれ!この愚か者どもが!」
全身赤色の男が杖を突き出すと、その先から小さな炎の玉がヒュンと飛び出した。
そしてその玉は騎士らの中心まで飛んで行った。
「何だ。」
騎士らが警戒しながら空中に浮いている炎の玉を見た。
すると、その炎の玉は突然大爆発を起こした。
「うおおおおお。」
騎士らが叫び声を上げた。
膨張した炎が全ての騎士の全身を焼いて、爆風でその体を吹き飛ばした。
あまりの高熱に全身が黒こげてしまう騎士もいた。
腕がもげ落ちた騎士もいた。
どちらにしても、戦うことのできる騎士はもういなかった。
爆発が収まると、壁際に下がって立っていたボワロが大広間の中央に歩いて来た。
「不届き者はお前たちだったな。」
ボワロは床に転がった騎士の頭を足で踏み潰した。
赤黒く皮膚がただれ、目が焼かれ、もう生きてはいなかった。
「おい。」
ボワロが大剣の男を呼んだ。
「どうしたボワロ将軍。」
「事情が変わった。騎士がいなくなったことで、この城の兵士を指揮する者がいなくなった。臨時でお前たちが指揮を執れ。」
「ボワロ将軍、そりゃ無茶だぜ。」
大剣の男は肩をすくめてみせた。
「そんなことは言わなくても分かる。お前たちのやり方で構わん。この城を守るのだ。」
「へいへい。」
次にボワロはマックレを見た。
ボワロは床に転がっているマックレに手を差し出すと、立たせてやった。
「援軍の要請は終わったか。」
「はい、既に手配が済んでおります。」
「よし。どうやら正念場を迎えているようだな。」
ボワロは視線を正面に向けた。
「エルファの軍隊がこの街に来る。援軍が到着するまで、抜かるなよ。」
ボワロはそう言って立ち去った。
怒られなかったな。マックレは驚いていた。
エバたちはジェシーおばさんの宿を出発すると、プチヘンリー通りからウェイン大通りに出て、さらに南下してソフィたちが隠れていた娼館を目指した。
エバたちが向かっている娼館は、街の中心を通っているファネリー大通りに面して建っていた。
飲食店通りを抜けるとすぐに娼館に到着した。
ソフィとエイリスとソンドラは、乗っていた馬を馬屋に休ませるため、娼館の建物の横を通って奥に入って行った。
そして少し時間が経って、ソフィたちが戻って来た。
娼館は2階建てで、1階は土間ではなく床が貼られていた。
「それじゃあ、ここからは私が案内するよ。」
ソンドラはそう言うと、数段の木の階段を上がると娼館の扉を開けた。
ソンドラはこの娼館で働いているのだ。
ソンドラは娼館の中に入ると、1階の左右に延びている通路を左に折れると、どんどん歩いて行って、突き当りの部屋に着いた。
「最初は本当に驚いたよ。」
ソンドラがみんなを振り返ってそう言った。
「この部屋の中のこと。」
ルーがソンドラに聞いた。
「そうだよ。」
するとソンドラが部屋の扉を奥に押し開いた。
部屋はそれなりに広さがあったが、部屋の床板がほとんど外され、床下の地面が見えていた。
そして、その地面には大きな穴が開いていた。
その穴は階段になっていて、地下にずっと続いていた。
「何これ!凄い。」
ルーが驚いた顔でそう言った。
「凄いでしょ。」
ソフィが笑顔をルーに向けた。
「床下から声がした時はびっくりしたよ。しかも、まさか馬まで出て来るなんてね。」
ソンドラが呆れた様子でそう言った。
「それはびっくりだな。」
ルードが穴を覗き込みながら言った。
「じゃあ皆さん、ここから入りますよ。」
ソフィが建物の床から地面に下りると、ぽっかりと開いた階段を下りようとした。
「ソフィさん、ちょっと待ってください。」
マーリンがそう言うと、ソフィの隣にのそのそと下りて来た。
「ソフィさんがここから出てきたのだから大丈夫だと思いますが、空気が流れているかどうか、確かめさせてください。」
そう言うと、マーリンは階段を少し下りると、人差し指を立てて穴の先に腕を伸ばした。
「こういう古い通路や洞窟は、ちゃんと空気が流れていれば良いのですが、淀んでいる場合は非常に危険なんです。」
マーリンは少しの間じっとして、何か分かった様子で頷くとみんなを見た。
「空気が流れていますね。これなら大丈夫でしょう。冷たい風が奥から流れて来ています。」
「じゃあ行きましょう。」
改めてソフィが階段を下りようとした。
「ソフィ待って。私がいないと真っ暗で何も見えないわよ。」
エルファであるエイリスがソフィに声を掛けた。
エルファは、月が出ていないような暗闇でも、灰色の濃淡で、物の形を判別出来る程に見ることが出来た。
「そうね。じゃあエイリス、一緒に行きましょう。」
ソフィとエイリスが手を繋ぐと、横に並んで階段を下り始めた。
「ちょっと待って、明かりは点けないの?」
ルーがみんなに声を掛けた。
するとマーリンが言った。
「暗闇でも目が見えるエルファが、ここには結構な人数います。明かりを点けないで進めるのであれば、その方が良いですね。」
マーリンがそう言ってルーに笑顔を見せた。
「そうなんだ。」
ルーが感心した様子で頷いた。
「敵に見つかる可能性を考えると、確かに明かりは無い方がいいな。」
エバもルーにそう言った。
エバとマーリンは、ソフィとエイリスの後ろに続いた。
次にマリーウェザーとルー、キッドとビリー、バクウェルとルード、ソンドラ、最後にシェリルとアレンティーが続いた。
階段を下ると、穴は横に続いて坑道となっていた。
坑道の壁は、穴を掘ったときのまま土が剥きだしとなっていたが、木材と石材が等間隔に壁や天井に入れられ、坑道を支えていた。
坑道は人が十分に立って歩ける程度に高さがあり、人が横に2人並んで歩ける程度の幅があった。
少し進むと、明かりの無い坑道はすぐに真っ暗になった。
「これは兵士を移動させる為に造られたものだな。」
エバの声が坑道に反響した。
「やっぱりそう思う?私もそうじゃないかと思ったんだよね。」
ソフィが真っ暗な闇のどこかにいるエバにそう言った。
「ただ、俺だったら出口は街の外まで伸ばすけどな。城から脱出するとすれば、街の外まで伸ばした方が都合が良いと思うが。」
「確かにそうですね。」
どこかにいるキッドがそう言った。
エバたちが坑道を横に進んでいくと、5分ほどで先頭を歩いているエイリスがみんなに声を掛けた。
「別の坑道に出るわ。水が流れているから気を付けて。」
エイリスはソフィの手を引きながら、今歩いている坑道から別の坑道に出た。
別の坑道は左右にずっと道が伸びていて、どちらかと言えば、今まで歩いて来た坑道が横道で、そこから本道に入ったような形だった。
「本当だ、水が流れている。」
横道から出て来たルーが、足で水に触れた。
坑道の真ん中に向かって傾斜が付けられていて、その真ん中を水が流れていた。
だが水量は多くなく、ちろちろといったところだ。
「そうか、分かった。これは水道だな。城で使う水を確保しているんだろう。」
エバがそう言った。
「正解。良く分かりました。」
ソフィの声がした。
「きっと、街の共同井戸から城まで水を送っているんだろう。」
ソンドラがそう言った。
「まず水道を作るのが目的で、せっかくだから人が移動できるようにしたんだろう。」
ソンドラに続いてエバがそう言った。
「そうか。」
「なるほどね。」
エバの説明にみんなが感心したように頷いた。
「で、何で進まないんだ。」
横道から出て来たところで、みんなで立ち止まっている状況に、ビリーが不思議そうにそう言った。
「大丈夫だと思うけど、どっちだったかな?と思って。」
エイリスの声がした。
どちらに進むのか少し戸惑っているようだ。
「それなら、水の流れを見てみるのがいいでしょう。水の流れている方向が正解ですね。」
マーリンがそう言った。
「そっか。」
ルーはしゃがみ込むと流れている水に触れた。
「ひゃあ、冷たい。」
ルーが水に触れると思わずそう言った。
「そんなに冷たいのか。」
キッドとビリーもしゃがみ込むと水に触れた。
「本当だ、冷てえ。」
「おおう!」
エバたちは思わず声を出して笑った。
「地下水だからな、そりゃ冷たいだろう。」
エバがそう言った。
「それで、どっちが正解かしら。」
エイリスがルーに尋ねた。
「こっちよ。」
ルーが真っ暗な先を指差した。
エルファのエイリスには、ルーの姿が良く見えた。
「こっちね、分かった。皆さん、こっちに進みますよ。声のする方に来てください。」
「はあい。」
エバたちはまた進み始めた。
坑道はわずかに下っていて、水がその傾きに沿ってちろちろと流れていた。
真っ暗な中を30分程進んだところで、先が明るくなっているのが見えた。
「おお!」
エバたちは坑道を出た。
目の前には、大きく深く、四角く掘られた穴が開いていて、たくさんの水が溜められていた。
天井も高くて大きな空間が広がっていた。
「水の流れは少しなのに、こんなに溜まっているんだ。」
ルーが驚いた様子でそう言った。
この四角い部屋の隅の天井に穴が開けられていて、そこから光が差し込んでいた。
差し込んだ光に照らされて、細かな埃がちらちらと輝いて見えた。
「あの光が差し込んでいるところが、城の中庭にある井戸よ。」
ソフィがみんなに光の差し込んでいる穴を示しながらそう言った。
「貯水池か。こんな小さな街の城にしては、立派な設備だ。」
エバが感心したようにそう言った。
「こんなものが地面に埋まっていたとはな。」
バクウェルとルードも単純に驚いた様子で、大きな空間を眺めていた。
「さあ、通路はこっちよ。行きましょう。」
エイリスがみんなに声を掛けると、エバたちは大きな貯水池を横に見ながら、通路を進んだ。
貯水池の部屋を出ると、通路は緩やかな上りになった。
通路はまた真っ暗になった。
「この先はどこに繋がっているのだ。」
最後尾のシェリルがソフィに尋ねた。
「この城には、前、中、奥と3つの中庭があるのだけど、一番奥の中庭に建っている裏手の塔に繋がっているわ。」
ソフィがそう言うと、エイリスも続いた。
「私たちが閉じ込められていたのが、裏手の塔よ。」
「そうなんだ。」
シェリルがそう言うと小さく頷いた。
エバたちが通路を進んでいくと、上り坂の突き当りが階段になっていて、その出口が木材の板で蓋がされ、行き止まりになっていた。
「ソフィ、持ち上げるわよ。」
「分かったわ。」
ソフィとエイリスは木材の板に背中を押し付けると、両足を踏ん張った。
「うーん。」
すると、木材の板が持ち上がって、木材と床の隙間から薄明りが漏れた。
「開いたね。」
「開いた。」
ソフィとエイリスが持ち上げた木材を横にずらすと、通路を上がって上の部屋に出た。
「着いたね!」
「着いた!」
ソフィとエイリスが笑顔で顔を見合わせた。
「本当にたくましいな。」
部屋に上がったエバがそう言って2人に笑顔を見せた。
上がった部屋は四角い形の部屋で、木材の柱が何本も入れられ、建物を支えていた。
囲んでいる四方の壁は石が積まれていた。
そして、部屋の床には藁が敷かれ、何匹かの豚と馬がいた。
「ここに・・・、閉じ込められていたのか?」
上がって来たバクウェルが少し驚いた様子でエイリスを見た。
どう見ても、ここは豚と馬の飼育小屋だ。
「ふふふ、ちゃんと上の階に部屋があるのよ。」
そう言うとエイリスは、部屋の端に設置された階段を示した。
「そういうことか。」
バクウェルが安心した様子でそう言った。
「まだマイクが生き残ってたよ!」
ソフィが1匹の豚に近付くと豚の身体を撫でた。
「ケンは食べられてしまったみたいね。」
エイリスが少し悲しそうな顔をした。
「豚に名前を付けているのか?」
エバが笑顔でそう言った。
「だって、やる事無いし。」
「豚だけじゃなくて、馬にも付いているわよ。名前。」
ソフィとエイリスがそう言うと、皆が声を出して笑った。
「でも、こんな隠し通路、よく城の兵士に見つかりませんでしたね。」
ルードが不思議そうな顔で部屋を眺めていた。
「この塔の入り口の扉はね、内側に倒れるの。跳ね橋みたいに。」
ソフィがルードに説明した。
「なるほど、良くできているな。」
エバが感心したように頷いた。
「入り口の扉が内側に倒れると、ちょうど隠し通路の入り口を塞いでしまうという訳。」
「そういうことか。」
ルードも感心したように頷いた。
「私もソフィも、何で内側に入り口の扉が倒れるのかなって、不思議に思っていたのよ。そうしたら、入口の扉が閉まることで、隠し通路が開けられるようになっているの。」
エイリスが得意になってそう言った。
「つまり、中に閉じ込められないと開けられないのね、凄い。」
ルーも感心したように頷いた。
「城はまさに戦場となる場所だから、敵の動きに合わせて、兵隊を城の隅々まで速やかに移動させる必要がある。だから、様々な仕掛けがされているんだが、これはなかなか良くできた仕掛けだ。」
エバも感心したように頷いた。
「それじゃあ、上の部屋に行きましょう。」
ソフィがみんなにそう言った。
部屋の隅の階段を2階に上がると、様々な大きさの木箱や、樽、衣装箪笥、木製のベンチ、風呂桶、薪などが置かれていた。
2階は物置きのようだった。
2階はすぐに通り過ぎると、エバたちは3階に上がった。
3階には、壁に暖炉が設置されていて、床には絨毯が敷かれ、物書き用のテーブル、ベンチ、分解された食卓、食器棚などが置かれ、2つの鎧戸が開け放しになっていた。
開け放たれた2つの鎧戸を貫くように、風が吹き抜けていた。
「私たちが逃げ出した時のままだわ。」
エイリスがそう言った。
「見て。」
そう言ったソフィを見ると、開け放たれた鎧戸からソフィが外に身を乗り出していた。
エバがソフィに近付いた。
「ここからはサリカの大聖堂が良く見えるの。」
エバも鎧戸から身を乗り出して外を見ると、シャロムの街並みを見ることが出来た。
盛り土の上に造られた城からは、高さがあるので、シャロムの街並みの全てを見渡すことができた。
確かに、サリカ大聖堂が周囲の建物よりも圧倒的に大きく空に向かって出っ張っていた。
「あの丘の向こうから日が昇って、シャロムの街並みの奥に陽が沈むわ。」
ソフィがエバに説明した。
「そうか。」
エバは静かにそう言った。
きっと、何度も何度もここから街並みを眺めたのだろう。エバはそう思った。
太陽はまだ出ていたが、夕刻に向けて日が傾き始めていた。
「チェスがあるのね。」
ルーがそう言ってエイリスを見た。
物書き用のテーブルの上には、チェス盤と駒が転がっていた。
「本当のチェスはやらないけどね。」
エイリスがルーに言った。
「そうなんだ。何で。」
ルーが分からない顔を向けた。
「私もソフィもルールが分からないの。」
「そうなんだ。私も分からないけど。」
ルーがそう言うと、てへっという顔をした。
「だからね、チェスはやらないんだけど、ソフィと一緒に駒を使って人形劇をやるの。」
「そうなの!面白そう。」
ルーの顔が笑顔になった。
「結構楽しいわよ。ねえ。」
エイリスはソフィに話し掛けた。
「ええ、確か、私がエイリスの恋人を奪ってしまって、エイリスが王女にそのことを密告して、私が恋人を連れて逃亡する、といったところだったかな。」
ソフィがそう言うと、皆で声を出して笑った。
「なんだそれ、愛の逃避行か。凄いな。」
ビリーが苦笑いした。
「人形劇って、ソフィとエイリスも出て来るのね。」
ルーが笑顔でそう言った。
「出て来ないと面白くないじゃない。」
「せっかくの夢物語なのよ、凄い経験がしたいわ。」
ソフィとエイリスはそう言うと、だよね、と顔を見合わせた。
「たくましいな。」
エバは独り言のようにそう言った。
自分であれば1年と持たないだろう。エバはそう思った。
こんな塔に閉じ込められて、何もやることがないのだ。
気が狂って飛び降りて死ぬかもしれない。
ソフィとエイリスの2人は、そんな極限状況を3年間も生き抜くための精神力と知恵を持っているのだ。
本当にたくましい。
「何だか、何のためにここに来たのか忘れてしまいそうね。」
ソフィが街並みを眺めながらぼそっと言った。
エバはソフィの横顔を見た。
「このままここにいたら、何もなく日が暮れて、1日が静かに終わっていく気がするわ。」
「名残惜しいのか?」
エバが尋ねた。
「まさか、ここの生活は最悪よ。生きているのに、死んでいるようだわ。」
ソフィはそう吐き捨てた。
「でも、」
ソフィは視線を遠くに向けた。
「何か、懐かしい気がしてしまうのは、なぜだろう。」
そう言ったソフィの瞳が、潤んでいるのをエバは見た。
「それでも、あんたの人生だからだろう。」
エバはそう言うと、シャロムの街並みに視線を移した。
ソフィが指で瞼を拭(ぬぐ)った。
「そうだね、それでも私の人生だ。」
ソフィはそう言うと、窓から離れるとみんなに顔を向けた。
「それじゃあ行くわよ。マックレのところに!」
ソフィの言葉に、キッドが分からない顔をした。
「ここからマックレのところに、どうやって行くのですか?」
「まずはこの上の階に上がりましょう。」
そう言うとソフィは、部屋の端にある登り階段を見た。
エバたちは4階に上がった。
4階に上がると、木製の衝立で部屋が仕切られ、天蓋付きのベッドが2つ置かれていた。
ベッドの横に、脱いだ服を掛けておく棒状の衣紋掛けがあり、壁際に衣装箪笥や物置きのための木箱、ベンチ、水差し、洗面桶が置かれていた。
「寝室ね。」
上がって来たルーが言った。
「そうなんだけど、あの衣装箪笥の上からこの塔の屋上に出られるわ。」
そう言うと、ソフィが衣装箪笥の上の天井を指差した。
天井には、横に長い木の板が何枚も貼られていた。
確かに、ソフィが指差した天井のところだけ、長い木の板が四角く切り取られ、別の木材がはめ込まれていた。
「よいしょ。」
ソフィは衣装箪笥の上によじ登った。
「本当にお転婆姫だな。」
エバがそう言うと、皆で声を出して笑った。
「しようがなくやっているだけだからね。いつもこんなことはしていないのよ。」
ソフィがそう言いながら、天井にはめ込まれた木材を上に押し上げた。
天井に四角い穴が開いた。
「ここから上に上がるわよ。」
エバたちは順番に衣装箪笥をよじ登って塔の屋上に出た。
「わあ、見晴らしがいい!」
ルーが塔の屋上から周りを見渡した。
屋上からは遮るものがないので、広がる空、街並みや遠くの丘まで良く見えた。
「今私たちがいるのが奥の中庭。マックレがいるのはあそこ、中の中庭に建っている大塔ね。あの中に大広間や、マックレの部屋もあるわ。」
エバたちのいる塔から周囲を眺めると、この城は、入口に近いところから、前、中、奥と城壁によって3つに分けられており、城壁の角や中庭には塔が建てられていた。
その中でも一番大きな塔が、中の中庭に建てられている大塔だった。
中の中庭では、洗濯物を取り込んでいる女性や、荷車を修理している男たち、荷物を運んでいる男たち、遊んでいる子供たちの姿が見えた。
「城の中で生活しているんだ。」
様子を眺めていたビリーがそう言った。
「本当だ。まあでも、そりゃそうか。」
キッドが納得したように頷いた。
「兵士がいるな。」
エバが独り言のようにそう言った。
「確かにいますね。まだ気付かれていないようですが。」
キッドがそう言った。
城壁の角に造られた塔の中に、ちらちらと兵士の姿が見えた。
「それでは、これから私たちは、今からこの塔から城壁の上に下ります。そして城壁の上を伝って行って、あの大塔に行きたいと思います。」
ソフィがそう言うと、ビリーが咄嗟に尋ねた。
「どうやって城壁の上に下りるのでしょうか?」
ビリーが驚いた顔でソフィに尋ねた。
確かに、今エバたちがいる裏手の塔は城壁のすぐ横に建っていたが、ここから城壁に飛び降りるには高過ぎた。
「安心して、ちゃんと降り口があるわ。」
ソフィが手で示したところに、塔から突き出た石の足場があった。
「ええ!ここを下りるんですか!」
ビリーが驚いた顔をした。
塔から石の板が飛び出していて、その板が階段のように連なっていた。
だが、最初の足場から次の足場まで途切れてしまっていた。
「階段が途切れてしまっていますが。」
キッドが覗き込んでそう言った。
「そのために、そこに木の渡し板があるでしょう。」
エイリスが隅に置いてある木の板のようなものを手で示した。
「これで橋渡しするのですか。」
「そうよ。」
お転婆とは分かっていたが、相当なお転婆だ。
ビリーとキッドは唖然とした表情をした。
すると、ソフィとエイリスは置いてある木の板を二人で持ってくると、最初の石の足場と次の石の足場を繋げた。
「ここを下りて行くわよ。大丈夫、塔の方に体重を掛けながら下りれば大丈夫だから。ちょうど半周回れば、城壁の上に下りられるわ。」
ソフィはそう言うと、さっそく石の足場を下り始めた。
次にエイリスが続いた。
「なるほど。敵が塔に上ってきたら、足場を外して登れなくする訳だ。」
エバは1人で納得するとエイリスの後に続いた。
仕方なくキッドもエバの後に続いた。
石の足場はしっかりしていたが、手すりも囲いもなかった。
塔に寄り掛かりながらキッドは足場を下りて行った。
「ちょっと待ってくれ、凄く恐いって。」
キッドが上を見ると、ビリーが最初の足場で青い顔で立っていた。
「大丈夫か?」
キッドが心配そうに見上げた。
「いやだめだ。ごめん。本当に恐いんだ。」
ビリーが真剣な顔でキッドを見た。
ここで皆の足を引っ張る訳にはいかない。キッドはそう思った。
キッドはビリーのところまで戻ると、ビリーの右手を握った。
「ルー、ビリーの左手を握ってくれ。」
「分かったわ。」
ルーがビリーの左手を握った。
「ビリー、塔の方を向いて。横歩きで下に下りるぞ。」
キッドがゆっくりと、強くビリーの手を引っ張ると、1段、また1段と足場を下りて行った。
「サンキュー、キッド。本当は、屋上に上がった時から恐かったんだ。」
ビリーが顔を青くしたままそう言った。
「ははは、頑張ろうぜ、もう少しの辛抱だ。」
キッドとビリーとルーが横歩きで下りて行った。
「私たちも横歩きで行こうか。」
シェリルがマリーウェザーとアレンティーに言った。
「いいわ。」
シェリルとマリーウェザーとアレンティーが手を繋いだ。
するとアレンティーが兄のマーリンに声を掛けた。
「お兄様も一緒に。」
「うむ、その方が無難だな。」
シェリルたちも横歩きで下りて行った。
「それじゃあ、我々も。」
バクウェルとルードとソンドラも手を繋ぐと横歩きで下りて行った。
先頭を進んでいたソフィが塔をぐるっと半周すると城壁の上に下り立った。
城壁の上は通路になっていて、人が余裕をもって歩けるほど道幅があった。
通路の両側の壁は鋸の刃のようにでこぼこした形になっていて、でこぼこの隙間から矢を放ったり、でこぼこの陰に隠れる事ができた。
「エイリス。」
ソフィが下りて来たエイリスに向かって手を伸ばした。
「ありがとう、ソフィ。」
エイリスはソフィの手を握ると、城壁の通路に下り立った。
するとその後すぐに、エバも城壁の通路に下り立った。
少し経って、キッドとビリーとルーも通路に下りて来た。
「ふう。」
「死ぬかと思ったぜ。」
その後に、シェリルたち、バクウェルたちと続いた。
「ソフィ、ここからはどうするんだ。」
シェリルがソフィに尋ねた。
「後はこの通路を真っ直ぐ行けば、大塔と繋がっている吊り橋があるから、そこを渡れば中に入れるわ。」
ソフィが手で通路の先を示しながら説明した。
「ただ、ここからは危険があるわよ。」
するとエイリスがみんなにそう声を掛けた。
「どうして?」
ルーが心配そうな顔をした。
「今私たちがいるところは、ちょうど裏手の塔の陰になっていて、他の塔から見えないのよ。だけど、ここから城壁の通路を進めば、他の塔から見下ろせば見つかってしまう。」
エイリスがそう言ってみんなを見た。
「今まで私たちは、別に見つかったとしても見逃して貰えていたけど。今はそういう訳にはいかない。」
ソフィもみんなにそう言った。
「その吊り橋は上げられるかな。」
バクウェルがソフィに尋ねた。
「大塔の中に入ったすぐのところに歯車みたいな機械があって、たぶんそれを回せば上げられると思う。・・・左右に2つあったと思う。」
ソフィが両手で何かを引くような動作をした。
「そんな感じの機械なんだな。」
「そう、こんな感じ。」
ソフィが両手で奥から手前に引く動作をした。
「この中で一番足が遅いのは。」
キッドがそう言ってみんなを見た。
するとマーリンが控えめに手を上げた。
「だろうな。・・・ちょっと見て来るか。」
エバが通路の壁に身体をぴったりと付けると、少しだけ進んで通路の先の様子を窺った。
そして戻って来た。
「この通路を走って吊り橋のところに行くまでの距離に比べて、一番近い塔から兵士が駆け付ける距離の方が長そうだ。つまり、何とか間に合うだろう。」
エバがみんなにそう言った。
「俺がマーリンの後ろ、つまり、しんがりを務めよう。」
エバが言った。
「それなら、俺とルード、キッドとビリーで先に走って行って、歯車みたいな機械を動かすという事でどうだ。」
バクウェルがそう言ってルードとキッドとビリーを見た。
「いいですよ。」
キッドが言った。
「じゃあ、誰が先頭に行く?通路は並んでは走れないぞ。」
バクウェルがルードとキッドとビリーを見た。
「この中なら、キッドが一番速いと思うぜ。」
ビリーがバクウェルにそう言って、キッドを見た。
「オーケー。俺が先頭を行こう。」
キッドが頷いて見せた。
「決まりだな。キッド、ビリー組が先頭だ。その後を俺たちが追う。」
ビリーとルードが分かった顔で頷いた。
「じゃあ行くか。準備はいいか?」
エバが声を掛けると、みんなが走るために低く身構えた。
「3・2・1、行け!」
エバたちは走った。
キッド、ビリーを先頭にして、バクウェル、ルード、ルー、ソフィ、エイリス、ソンドラ、マリーウェザー、アレンティー、シェリルと女性たちが続いて、最後にマーリン、さらにその後ろをエバが続いた。
マーリンは明らかに足が遅かった。
キッドが一番に吊り橋に到着した。
吊り橋のある場所は、ちょうど3つの城壁が交わる交差点のような場所だった。
キッドが正面と左手側に伸びている城壁を見ると、ちょうど塔から兵士が出て来て、こちらに向かって駆けだして来るのが見えた。
「兵士が来るぞ!早くしろ!」
キッドは後ろから走って来るみんなに声を掛けると、吊り橋を走って渡った。
吊り橋を渡り終わると、大塔へ入る扉を押し開いた。
扉に閂は掛けられていなかった。
「キッド。」
後ろからビリーが到着した。
キッドは扉をくぐると、部屋の中を確認した。
中は物置きとして使われているようで、人の姿は無かった。
キッドが入って来た入り口以外に、正面と右手側に扉があった。
「ビリー、閂をかけるぞ。ビリーは正面を頼む。」
「おう。」
キッドとビリーは、この部屋に人が入って来れないよう、キッドが右手側の扉を、ビリーが正面の扉の閂を掛けた。
閂を掛け終わった二人が振り向くと、ソフィが言ったように、歯車のついた機械が部屋の左右に2つあった。
天井近くの壁に開けられた穴から鎖が伸びていて、その歯車の付いた機械に巻き付いている。
「こいつだ。ビリーはそっちを。」
「ああ、分かった。」
2人は機械装置に近付いた。
機械には、鉄の握り棒が2つ付いていた。
「どっちだ、どっちの棒だ。」
キッドが試しに1本を握って動かしてみた。
棒は少し上に動くとそこで止まった。
キッドはもう1本を動かそうとしたが、もう1本はビクビクするだけで動かなかった。
「くそ、動かない。」
「大丈夫か。」
バクウェルとルードも部屋の中に入って来た。
「ビリー、どうだ。」
キッドがビリーに聞いた。
「だめだ、こっちも動かねえ。」
バクウェルが走ってキッドに近付いた。
「一緒に動かしてみるか。」
キッドとバクウェルは力一杯、上に下に鉄の棒を動かしたが、やはりビクビクするだけで動かなかった。。
「何か動かない理由があるのか。」
バクウェルは歯車の部分に座り込むと目を凝らした。
ルードもビリーの方に座り込むと歯車に目を凝らした。
「間に合った。」
ルーが部屋に入って来た。
続いて、ソフィ、エイリス、ソンドラが入って来た。
「どう。」
ソフィがキッドに尋ねた。
「歯車が動かなくて。」
「ええ!そうなの。」
ソフィが心配そうに機械を見た。
部屋の外の吊り橋では、マリーウェザー、アレンティー、シェリルが渡り始めていた。
「ぎりぎり間に合いそうだな。」
シェリルが振り返ってマーリンとエバを見た。
この速さなら、兵士が吊り橋に到着するよりも、マーリンとエバの方が早く吊り橋に到着する。
「先に中に入って。」
シェリルがマリーウェザーとアレンティーをそう促した。
するとマーリンが吊り橋に到着した。
「全く、私は走るのが嫌いなんですよ。」
マーリンは、はあはあと息を切らしながら、それでも悪態をついた。
「マーリンは頑張ったよ。」
シェリルはそう言うと、マーリンを吊り橋の方へ押しやった。
すると大塔の扉が開いて、マリーウェザーがシェリルに大きな声で言った。
「吊り橋が上がらないの!」
シェリルはすぐに状況を理解した。
「分かった、時間を稼ぐ。」
するとちょうどそこにエバが到着した。
「エバ、時間を稼ぐぞ。」
シェリルがエバに言った。
「分かった。」
エバは頷くと、シェリルの後ろを顎で示した。
「俺が右手側、お前が後ろだ。」
シェリルが顔を後ろに向けると、まだ距離はあるが、背後からも兵士が走って来ていた。
ちょうどエバたちは、右手側からと後ろからと兵士たちが迫って来ていた。
「牽制するだけだ。時間を稼げ。」
「分かった。」
エバとシェリルは2手に分かれた。
エバとシェリルは腰に提げている剣を抜くと、右手で握った剣を肩の高さでまっすぐに前に伸ばした。
これは敵を牽制し、防御に優れた構えで、エバの流派では旗の構えと呼ばれている。
すると走って来た兵士がエバの前で止まった。
城壁の上の通路は、人が2人並んで戦える程の広さはない。
どうしても1対1となる。
「何だお前は、どうやって城に入った。」
先頭の兵士がエバに尋ねた。
だがエバは、話をする必要もないので、黙って剣先を兵士の顔面に向けていた。
「どうやって城に入ったのかと聞いているんだ。」
エバは黙っていた。
「なるほど、そういうことなら無理矢理にでも、ひっ捕らえるしかないな。」
先頭の兵士はそう言うと、腰の剣を抜いた。
だが先頭の兵士は、腰の剣を抜いたはいいが、先に進もうとするとエバの剣に顔面を串刺しにされそうで、進めなかった。
エバの剣は、先頭の兵士の動きが分かっているかのように、常に兵士の顔の中心を捕らえ続けた。
先頭の兵士は、エバの剣を払おうと、自分の剣を横に払ったが、エバの剣は滑らかにスッと動いて兵士の剣をかわすと、またすぐに兵士の顔の中心に戻った。
先頭の兵士は唖然として、動けなくなった。
大塔の部屋の中では、歯車の機械を囲んでみんなで大騒ぎしていた。
「錆びついて動かないのじゃないのか。」
ビリーがそう言った。
「いや、これは錆とかではないだろう、何かが邪魔していると思うんだが。」
バクウェルがそう言いながら歯車に目を凝らした。
「いっその事、吊り橋の鎖を断ち切れないかな。」
ルーが歯車を見ながらそう言った。
「細い鎖だが鉄で出来ている。ナイフなんかじゃ歯が立たない。」
キッドが鉄の棒をガシガシと上下に動かしながらそう言った。
「ちょっと、兵士が来ちゃってるよ。エバとシェリル姉さんが戦ってる。早くして!!」
マリーウェザーが必死な顔でそう言った。
「とにかく、4人でやってみようぜ。」
ビリーが強い調子でそう言うと、バクウェルとルードとキッドとビリーは鉄の棒を4人で握った。
「せいの、で引き上げるぞ。せいの!!」
「うおおおおおお。」
4人で鉄の棒を握って力を込めた。
「ふぬぬぬぬぬ。」
ガーン!!
すると、何か固くて質量のあるものが弾け飛んで、壁にぶつかって大きな音を立てた。
身の危険を感じた男たちが頭をかばった。
「何だ?」
バクウェルが周りを見渡した。
「あっ!」
ビリーが驚いた声を上げた。
「どうした。」
ビリーがみんなの顔を見た。
「動くようになった。」
ビリーが鉄の棒を上下に動かして見せた。
「これだ。」
ルードが走って行って、床から何かを拾い上げてみんなに見せた。
結構な大きさのある石だった。
「こいつが機械のどこかにはめ込まれて、動くのを邪魔していたんだ。」
ルードが言った。
するとバクウェルは慌ててもう一つの歯車の機械に近付くと、歯車が付いている機械の反対側に回り込むと、しゃがみ込んだ。
「あった、あったぞお!!」
バクウェルも石を掴んだ右手を高く掲げた。
キッドが鉄の棒を握ると上下に動かした。
「良し!動く!」
キッドがそう言ってみんなを見た。
みんなの顔が思わず笑顔になった。
マリーウェザーは部屋の扉を開けて外に出た。
「エバ、シェリル姉さん!橋が上がるわ!」
マリーウェザーが大きな声で言った。
エバはゆっくりと後退した。
そして吊り橋の前に来ると、シェリルと背中合わせになった。
吊り橋を吊っている鎖が少しずつ巻き上げられ始めた。
「先に行け。」
エバがそう言うと、シェリルがパっと吊り橋に乗り移った。
吊り橋は上がり始めた。
「エバ!」
シェリルが声を掛けると、エバも吊り橋に飛び移った。
そして、兵士たちが飛び移ってこないように剣先を向けた。
吊り橋が吊り上がって角度がつくと、エバが吊り橋を滑り下りた。
兵士たちは、少しの間様子を見ていたが、そのうちに来た道を戻って行った。
「さて、とうとうマックレと対決ね。」
ソフィがエイリスにそう言った。
「そうね。」
エイリスが頷いた。
「マックレの部屋は?」
バクウェルが尋ねた。
「この扉の向こうに物置部屋があって、その隣よ。」
「おお、そうか。」
バクウェルが驚いた顔をした。
マックレの部屋は、吊り橋を渡って大塔に入ったら、2つ隣の部屋だったのだ。
「ルード。」
バクウェルがルードに声を掛けた。
「何ですか。」
「令状はあるな。」
ルードが背負い袋の中身を確認した。
「大丈夫です。あります。」
バクウェルは大きく頷いた。
「最初は、ソフィとエイリスに任せていいかな。」
シェリルがソフィとエイリスに尋ねた。
ソフィとエイリスが顔を見合わせた。
「それでいいわ。」
ソフィとエイリスがそう言って、決意を込めた目でシェリルを見た。
「分かった。じゃあ、令状は様子を見てからということにしよう。バクウェル、それでいいな。」
シェリルが今度はバクウェルを見た。
「承知した。」
バクウェルが頷いた。
「ちょっと待て、この部屋には奥に続く扉が2つある。どっちがマックレだ。」
エバがソフィに聞いた。
「こっちがマックレよ。」
ソフィが正面の扉を示した。
「じゃあ、こっちは。」
エバが横の扉を示した。
「そっちは侍従の控室になっているわ。」
「分かった。じゃあ、そっちの扉には閂を掛けておこう。」
「エバさん。」
キッドがエバを呼んだ。
「閂なら、この部屋に入った時に掛けていますよ。」
キッドの言葉に、エバが扉をもう一度確認した。
「なるほど。」
エバはキッドにニヤリとした笑顔を見せた。
「それじゃあ、行くぞ。」
エバは正面の扉の閂を外すと、奥に扉を開いた。
すると、ソフィが言ったとおり、そこはたくさんの木箱が置かれた物置き部屋だった。
エバたちはさっさと通り抜けると、さらに奥の扉を押し開けた。
背もたれの付いた椅子に、テーブル、ベンチ、物置き棚、木箱が置かれていた、壁には大きなタペストリーが掛けられていた。
応接室のようだ。
そして背もたれの付いた椅子には、男が1人座っていた。
豪華な刺繍が施され、毛皮の裏地がついた青色のマントで体を覆っていた。
緑色に金色の糸が織り込まれた靴を履いていた。
マックレだった。
エバたちは部屋に足を踏み入れた。
「なんだ!お前たちは。」
マックレは慌てて座っていた椅子から立ち上がると、椅子を盾にするように後ろに回った。
「忘れっちゃったの?あなたに閉じ込められていたソフィとエイリスだけど。」
ソフィとエイリスが前に出た。
「そうか、何をしに来た。」
マックレは警戒した様子でそう言った。
「あなたに聞きたいことがあって。」
ソフィがマックレをじっと見た。
「余には何も話すことはないが。」
マックレはそういって首を左右に振った。
「マーリンさん、悪いけど言葉が通じないみたいなの、翻訳をお願いできないかしら。」
ソフィがマックレをみつめたままそう言った。
「承知いたしました。」
するとマーリンは、コートの内側にいくつもついているポケットから木の枝を取り出すと、人差し指と親指で摘まみ、皆が見えるように立てて見せた。
「ちょっと待った。最初にいくつか聞きたいことがある。」
そう言うとシェリルは、ソフィの肩をポンと叩くと、ソフィの前に出た。
マックレはシェリルの顔を見てはっとした表情をした。
顔に二つの刀傷の女。
「お前がシェリルだな。」
だがシェリルはそれには答えずに、マックレを見つめると言った。
「マックレ、お前は今、武器を持っているか。」
シェリルの言葉に、マックレは片方の口元を引き上げた。
「お前に答える必要はないな。」
するとシェリルは視線をマックレからマーリンに移した。
マーリンの持っている枝は大きく左右に触れた。
「なるほど、持ってはいない。なら、この部屋のどこかに武器を隠しているか。」
シェリルはマックレに尋ねた。
マックレは不思議そうな表情で黙って様子を窺っていた。
シェリルがまた横目でマーリンを見ると、マーリンの持っている枝は動かなかった。
「そうか、隠しているのだな。どこに隠している。」
シェリルがマックレを見つめた。
するとマーリンの持っている小枝が部屋に置いてあるテーブルを示した。
シェリルはテーブルに近付くと、テーブルを上から下まで一度見渡した。
そして、テーブルの裏に手を差し込んだ。
手を差し込んだシェリルは、何かに気付いた表情をすると、差し込んだ手を引き抜いた。
シェリルの手には短剣が握られていた。
マックレはピクリと眉を動かした。
「他に武器はあるか?」
シェリルが尋ねると、マーリンの小枝は動かなかった。
「よし。それなら、この部屋に隠し通路はあるか。」
シェリルがマックレに尋ねた。
マックレは眉をしかめた。
するとマーリンの小枝は動かなかった。
「どこにある?」
シェリルがさらに尋ねた。
するとマーリンの小枝は、部屋の壁に掛けられた織物のタペストリーを示した。
「俺がやりますよ。」
ビリーがシェリルにそう言うと、壁に向かって歩いて行った。
「これか。」
ビリーが近付いてタペストリーをめくると、隠されていた扉が現れた。
「見つけたぜ、これで逃げ道はなくなったって訳だ。」
ビリーがマックレにニヤリとした笑顔を見せた。
マックレは真剣な目でビリーを見た。
「他に隠し通路はあるか?」
シェリルがマックレに尋ねた。
だがマーリンの小枝は動かなかった。
「ありがとう、素直に教えてくれるから助かったよ。キッド、ビリー、この部屋の扉に閂をかけろ。これで、この部屋に入ることも出ることも、簡単には出来なくなる。」
シェリルはマックレに笑顔を見せた。
「これで気が済んだ。選手交代だ。」
そう言うとシェリルはまた、ソフィの肩を叩くと後ろに下がった。
口先だけが最大の武器であったのに、その武器を失った。マックレはそう思った。
マックレは真剣な顔のまま表情を凍り付かせた。
「あなたは前代の領主カーター卿の弟なの?」
マックレは黙って目を伏せた。
ソフィがマーリンを見た。
マーリンの小枝は激しく左右に揺れた。
「本当に偽物だったんだ。」
ソフィがマックレを睨んだ。
「前代の奥様は本当にお亡くなりになっているの?」
エイリスがマックレに尋ねた。
マーリンの小枝は動かなかった。
エイリスが眉をひそめた。
「あなたがバークに奥様を殺すように命令したの?」
エイリスがマックレに尋ねた。
マーリンの小枝は動かなかった。
「そうだったのね。」
エイリスはそう言うと深く溜め息をついた。
「あなた言ったよね。この街の経営に奥様が必要だからって。関係のない私たちは介入できないように離れてくれって。それは嘘だったという事。」
ソフィがマックレに尋ねた。
マーリンの小枝は動かなかった。
「それも嘘だったんだ。」
ソフィはそう言うと下を向いた。
あの時、マックレがそう言った時、私もエイリスも奥様もいた。
マックレは言っていた。
領主となって間もなく、街の事も良く分からない。だから奥様の協力が絶対に必要なのだと。
その時、奥様は何も言わずに黙っていた。
私もエイリスも、街の経営に介入するつもりなど毛頭なかったから、奥様が良いのならしようがない、そう思っていた。
そもそも街の経営の話をされても、私もエイリスも良く分からなかった。
奥さまが黙っているということは、きっと奥様も納得しているのではないか。
そう思っていた。
だから私もエイリスも、良いとも悪いとも言わずに、黙っていたんだ。
ソフィは下を向いたまま、少しの間じっとしていた。
「奥様はいつ亡くなったの。」
エイリスがマックレに尋ねた。
マックレは黙って何も言わなかった。
「ソフィさんとエイリスさんを屋敷から追い出した後、すぐにバークを屋敷に招き入れた。」
マーリンがソフィとエイリスに向かってそう言った。
マーリンはそう言うと、マックレを見た。
「あなたは、バークがどのように奥様を殺したかご存じでしょうか。」
マックレは黙って首を左右に振った。
するとマーリンはソフィとエイリスを見た。
「すいません。ソフィさんとエイリスさんには、とても残酷な話を今からします。」
ソフィとエイリスは覚悟を決めるようにマーリンに頷いた。
マーリンは2人に頷いて見せると、またマックレを見た。
「あなたは指示をしただけでしょうから、知らないでしょうが。バークは、奥様の寝室に入ると、逃げる奥様を追い詰め、助けてと言っている奥様に短剣を突き刺しました。奥様は抵抗したので、バークは奥様に馬乗りになって押さえつけ、抵抗する奥様の腕を幾度か斬り付けて傷を負わせ、その後で、心臓に短剣を突き刺して殺害しました。これが、あなたがバークに指示したことで起こった顛末です。」
マックレはただ、じっとマーリンの言葉を聞いていた。
すると、エイリスがじっとしているマックレに向かって言った。
「私は、本当は奥様はまだ生きているのじゃないか、私たちと同じようにどこかに閉じ込められているのではないか、その可能性があるかもしれない。そうあって欲しいと願っていた。だから、マックレから直接話を聞かなければって、そう思っていた。」
エイリスは目を伏せた。
「でも、それは、私が創り出した幻想だったのね。あなたに騙された愚かな私が、事実を信じたくないと思って生み出した幻想。」
「エイリス、違うよ。」
下を向いたままのソフィがそう言った。
エイリスがソフィを見た。
「マックレが私とエイリスに奥様から離れるように言った時、私は何となくおかしいと思っていた。でも、そのままにしてしまった。勝手に奥様も納得しているのだろうと、自分の都合の良いように思い込んで、そのままにしてしまった。まさか、その後に殺されてしまうなんて。」
ソフィはそう言って目を伏せた。下を向いたソフィの手が小刻みに震えていた。
「妥協してはいけなかったんだ。はっきりと奥様に尋ねるべきだった。曖昧にしてはいけなかったんだ。なぜ経営に奥様が必要なのか、なぜ介入するつもりのない私たちが側にいてはいけないのか、離れる必要があるといっても、なぜ私とエイリスが城に移されなければならないのか、マックレに問い正すべきだった。」
すると、下を向いたソフィが両手を強く握り込んだ。
「私はエイリスと奥様との友情を一番大事に思っていたのに。その友情が必要だった一番大事な時に、私は妥協してしまった。なんて、私は・・・、馬鹿なんだろう。」
すると下を向いたソフィの目から涙がこぼれ、ぽろぽろと絨毯に落ちた。
「奥様を救ってあげられた誰かは、私だったんだ。」
ソフィは涙を流した目でエイリスを見た。
エイリスははっとすると、その目から涙を流した。。
「それは私も一緒よ。一緒だから。」
エイリスはソフィを強く抱きしめた。
「ソフィごめんなさい。私も言えなかったの。私もそう思っていたの、でも言えなかった。恐くて言えなかったの。」
2人は一緒に泣いた。
「奥様に、本当に申し訳なかったね。」
エイリスがそう言った。
ソフィも目を瞑って頷いた。
二人を見ていたビリーが鼻をすするとマックレを睨んだ。
「違う、違うぜソフィさん。お前さあ、ふざけんなよ。これを見て、何とも思わないのかよ。この2人のお嬢さんは、奥さんを殺した訳じゃないんだぜ。なのにこんなに傷付いてしまって。お前が殺したんだろうがよ、お前は何にも感じないのかよ!」
するとマーリンの小枝は激しく左右に揺れた。
マーリンが寂しそうな表情をして口を開いた。
「マックレは分かっている。マックレは・・・、分かっているんだ。」
マーリンの言葉を聞いて、ビリーが表情を豹変させた。
ビリーはマックレにずんずんと近付くと、絹のシャツを毛皮の裏地がついた青色のマントごと力一杯握り上げた。
「お前分かってんじゃねえかよ!」
ビリーはマックレを激しく睨んだ。
「バークが言っていたよ。お前は偉い役人をやっていたって。それなのに分からない筈がないんだ。俺みたいな馬鹿でも分かる理屈が、分からない筈がないんだ。なのに、何で殺したんだよ。頭がいいお前が、何で殺したんだよ!!」
とうとう堪え切れなくなったように、マックレは両手で自分の両眼を塞ぐと、下を向いた。
すると意を決したようにマックレは顔を上げると、ビリーに言った。
「俺だって、ボワロが恐かったんだ。逆らう事なんて、できなかった。」
マックレは泣いていた。
ビリーはマックレの情けない態度に、思わず言葉を失くした。
「もう一つ教えて。」
ソフィが涙を堪えてキッとした表情をした。
「エルファが嫌がるのに無理矢理商売をさせようとしたのも、ボワロに逆らえなかったからなの?」
ソフィの言葉にマックレが下を向いた。
マーリンの小枝は動かなかった。
「エルファと戦争になって、たくさんの人が死んだかもしれないのよ。」
エイリスもそう言ってマックレを見た。
やはりマーリンの小枝は動かなかった。
マーリンが寂しそうな表情をして口を開いた。
「それもマックレは分かっていた。」
するとマックレは、耐え切れないように頭を垂れた。
「頼む勘弁してくれ。俺はボワロの命令に従っただけなのだ。ただそれだけなのだ。勘弁してくれ。」
シェリルは、蔑むようにマックレを見ていたが、眉をしかめるとバクウェルに顔を向けた。
「バクウェル、どうだ。反逆罪として執行するにはこれで十分だろう。」
「ああ、そうだな。」
バクウェルは目を瞑ると何度も小さく頷いた。
「バクウェル、執行を。」
シェリルがバクウェルに言った。
「ルード。」
バクウェルがルードに声を掛けた。
「はい。」
ルードは背負い袋から令状を取り出すと、バクウェルに手渡した。
バクウェルは令状を広げると、マックレに見えるように前に進み出た。
「3年間もの間、ヤドゥイカ子爵の継承者であるとして国王を欺き、私利私欲のために領主の地位を利用し、国王が得るはずだった領地からの収入を領得した。」
バクウェルは広げた両手をパンと畳んで書状を丸めると、棒状にした令状でマックレを指した。
「マックレ、ガヤンの強制執行だ。覚悟を決めろお!!」
バクウェルが吠えた。
「待ってくれ、殺さないでくれ。」
マックレは襟首を掴んでいるビリーの手から力づくで逃れると、後ずさった。
するとシェリルがマックレに一歩踏み出しながら口を開いた。
「マックレ、お前だって頑張って生きたさ。だがお前は、助けて欲しいと命乞いをする奥様を殺した。そんなお前に、命乞いをする権利はない。」
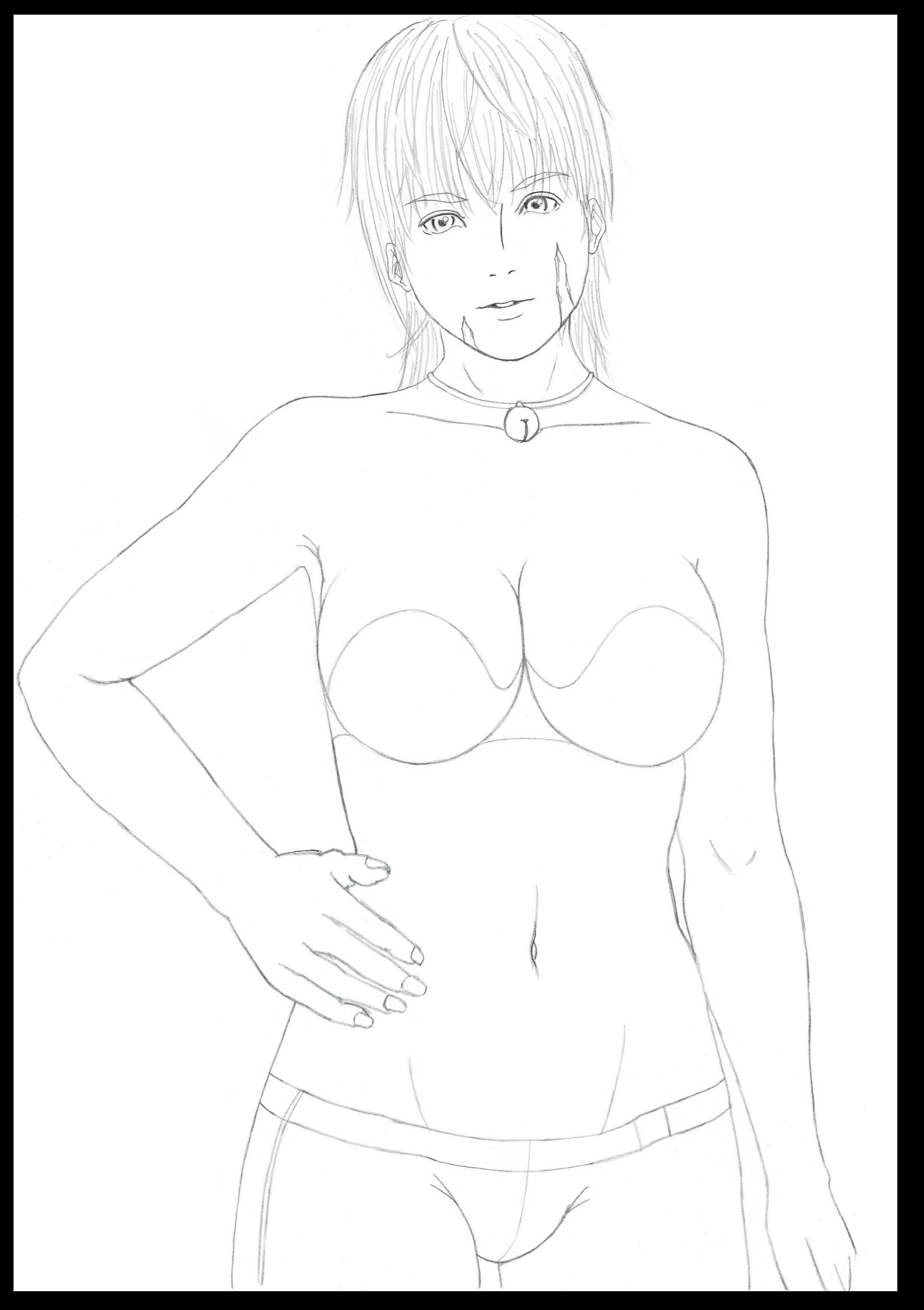
マックレはさらに後ろに下がると、石の壁に背中をくっつけた。
もう後ろに下がることが出来ない事が分かると、マックレは必死な顔でシェリルに言った。
「政(まつりごと)には犠牲がつきものなのだ。犠牲を恐れていては、政治はできないのだ。」
マックレの言葉にシェリルは眉をひそめると足を止めた。そして、マックレを見下ろすように見た。
「何が政(まつりごと)だ。じゃあ聞くけど、お前は、何の罪もない奥様の命を助けるために何をした。エルファとの戦争を回避するために何をした。何か策を打ったのか。」
シェリルの言葉に、マックレは黙り込んだ。
「何もしていないな。」
マーリンはそう言うと、首を左右に振った。
「奥様を殺さなくて済むように、ボワロを説得しようと挑戦して、それでもダメだった。エルファとの戦争を回避しようと挑戦して、それでもダメだった。そういう事なら私たちだって、お前の言う事を聞いてやらなければ、自分の気持ちと折り合いをつけられないかと考えもするよ。だがお前は何をした?何もしなかったことの言い訳を考えただけだ!」
シェリルはマックレに指を突き付けた。
マックレはシェリルを見ることができずに目を伏せた。
「お前はボワロのせいにしているが、自分が殺されると分かっていたら、それでもボワロの命令に従っていたかな。人の命を奪う決断をする時には、自分の命を失う覚悟を持たなければならない。お前は他人の命は平気で奪っておいて、自分だけは大丈夫と勝手に思っていたようだな。だが、私はそんなに甘くはない。」
「あああああ!」
シェリルの言葉に、マックレが体を横にして壁に張り付くと、目を瞑って頭を抱えた。
「正々堂々と死ね!マックレ!」
次の瞬間、エバがマックレに向かって大きく跳躍すると、剣を耳から差し入れて頭を横に串刺しにした。
剣が頭を貫通したマックレは、少しの間、反射で体を震わせていたが、とうとうその動きを止めた。
「痺れる。痺れるねえ。ボワロ将軍が夢中になる訳だ。」
突然、知らない誰かの声が聞こえた。
その場にいるみんなが驚いて声が聞こえた方向を見た。
「おっと動くなよ。動くとこのお兄さんの首がスパッといくぜ。」
細身のぴっちりとした服を着た男が、ビリーの首元にナイフを当てがった。
ビリーがしまったという顔でシェリルを見た。
ビリーの後ろにある隠し扉が、いつのまにか開いていた。
「俺は別に殺したいと思っている訳じゃないんだ。シェリル。あんたがこっちに来てくれれば、このお兄さんは殺さない。」
そう言うと、細身のぴっちりとした服を着た男が、シェリルに左手で手招きした。
「分かった、行くよ。ビリー、安心してじっとしているんだ。」
シェリルはそう言うと細身の男に近付こうとした。
「おっと、腰の剣は捨てて貰おうか。」
男の言葉に、シェリルは素直に腰の剣を長椅子に置いた。
シェリルは両手の平を細身の男に見せると、ゆっくりと歩き出した。
魔法の紅い鈴が鳴らなかったな。シェリルは不思議に思った。
「よし、いいぞ。そのままゆっくりと俺の元に来い。」
細身の男はシェリルをじっと見ていた。
その時ビリーは、細身の男がシェリルに気を取られていると感じた。
俺のせいで、シェリルさんを奪われる訳にはいかない。
今だ!!
ビリーは細身の男の腕を掴もうとした。
「馬鹿が!」
細身の男は瞬時にビリーの喉元を斬り裂いた。
ビリーはどっと床に倒れ込んだ。
「ビリー!」
シェリルが思わず両手で口元を覆った。
細身の男は素早くシェリルの右手を握ると引き寄せた。
だが次の瞬間、エバが飛び込んでくると、細身の男の目に剣を差し込み、そのまま頭を串刺しにした。
細身の男は小刻みに体を痙攣させた後、立ったまま動かなくなった。
シェリルは慌てて床に倒れ込んだビリーを抱き上げた。
ビリーは驚いた表情でシェリルを見た。
「私なんかのために、何をしているんだよ。本当に馬鹿だな、お前は。」
そう言うと、シェリルはビリーを抱きしめた。
「それは・・・、こっちの台詞・・・ですよ。男だから。」
「馬鹿野郎!」
シェリルは強くビリーを抱きしめた。
ビリーの喉元からは血液がどくどくと流れ出た。
そうか、私ではなくてビリーが危険だったから、魔法の紅い鈴は鳴らなかったのか。シェリルはそう思って後悔した。
「マリーウェザー、アレンティー、すぐに魔法で傷口を塞いで。」
マーリンが2人に言った。
「はい、お兄様。」
マリーウェザーとアレンティーは腰に結び付けている小袋を引っ張り外すと、魔法を掛ける準備を始めた。
「大丈夫だ。ナイフには毒は塗られていない。」
細身の男が持っていたナイフを調べていたエバが、マーリンにそう言った。
「良かった。」
マーリンがほっとした表情を見せた。
ビリーは、身体が冷えて、意識が曖昧となるような感覚を覚えながらも、シェリルのやわらかな身体の感触も感じていた。
しくじったな。ビリーはそう思った。
だが、そうだとしても、やはりあのままシェリルを男に渡す訳にはいかなかった。
シェリルは大丈夫だと言ったとしても、俺のせいで体に傷を付けられてしまったら、そんなことは、俺が俺を許せない。
俺の男としての誇りは貫くことが出来た。
そもそも、平穏で安寧な人生を送るなどと、俺は俺の人生に期待などしていない。
それに、神様は最後に俺にご褒美をくれた。
それは、シェリルさんのやわらかな身体の感触だ。
そうだ、俺が求めていたものはこの感触だ。
この感触が欲しかったのだ。
ビリーはもっとこの感触を味わおうと、シェリルのやわらかな胸に顔をうずめた。
シェリルの身体の温かさが心地よかった。
シェリルの心臓が脈打つ鼓動が聞こえた。
「ちょっと、いつまでママに甘えているつもりなの。」
マリーウェザーの声が聞こえた。
するとビリーは、何かおかしい事に気付いた。
さっきまで感じていた、身体が冷える感覚がなくなっていた。
首に絡みついていた血液の、生温かい感覚もなくなっていた。
ビリーは首に手を当てた。
「あれ?」
ビリーは目を開けると、覗き込むシェリルの顔の横に、不機嫌なマリーウェザーの顔が見えた。
ビリーの傷口は塞がっていた。
「エロビリー、さっさと離れろ!」
マリーウェザーがビリーのお尻を平手で叩いた。
ビリーは思わずごろごろと転がった。
「何で?」
ビリーが驚いた顔で周りを見渡した。
その様子に、みんなで声を出して笑った。
「マリーウェザーとアレンティーが、魔法で治してくれた。」
エバがそう言うと、ビリーにニヤリと笑みを見せた。
ビリーはありがたいのかどうなのか良く分からない顔をした。
「お前は運が良かった。普通なら死んでしまってもおかしくはない怪我だった。」
シェリルがほっとした様子で胸をなでおろした。
「自分のために他人が死ぬなんて、私には本当に耐えられないことなんだ。私の事を大事に思ってくれているのなら、私だけではなくて、私もビリーも両方助かる方法を考えて欲しい。」
そう言ってシェリルは、床にぺたりと座り込んだまま、ビリーに笑顔を向けた。
「分かりました。シェリルさん。」
転がったままの格好でビリーが頷いた。
チリン、チリン。
シェリルの首輪につけられた鈴が鳴った。
その鈴の音に、みんながシェリルを心配そうに見た。
次の瞬間。
ドンドンドンドン!
部屋の入り口の扉が乱暴に叩かれた。
「どうやら兵士たちが到着したようだな。」
エバが扉を眺めながらそう言った。
「ソフィ、エイリス、ボワロの部屋にはどう行けば良いかな。」
シェリルがビリーを立たせてやりながらそう尋ねた。
「ドンドン叩かれているその扉を出ないと行けないわ。」
ソフィがそう言って首を左右に振った。
「じゃあ、その隠し扉から逃げるのはどう?」
ルーがみんなに提案した。
「恐らく、隠し通路にも兵士が入り込んでいるだろう。」
エバがそう言った。
するとエバは、この部屋に1つついている窓の鎧戸に近付いた。
鎧戸は、外側に押して上に開くもので、突っ張り棒で閉まらないように固定する仕組みだった。
「みんな、窓から離れていてくれ。」
するとエバは、鎧戸を開けて押さえておくための長い突っ張り棒を手に取ると、その突っ張り棒で鎧戸を外側に押し開けた。
すると、何本かの矢が鎧戸に刺さったり、勢いのなくなった矢が部屋の中に入ってきたりした。
エバは鎧戸を閉めた。
「どうやら外にも敵がいるらしいな。」
エバがそう言ってみんなにニヤリと笑みを向けた。
「エバ。」
シェリルがエバに声を掛けた。
エバがシェリルを見た。
「隣の部屋を。」
シェリルの言葉にエバが頷いた。
この部屋には扉が3つあった。
1つはドンドン叩かれている扉、1つはビリーが見つけた隠し扉、そしてもう1つが奥の部屋に続いている扉だ。
「キッド、ビリー、一緒に来てくれ。」
エバは奥の部屋に続いている扉を開けた。
「バクウェル、ルード、扉を塞ぐぞ。手伝ってくれ。」
シェリルはそう言って、部屋に置いてある背もたれの付いた椅子、テーブル、ベンチ、物置き棚、木箱を示した。
エバたちが奥の部屋に入ると、そこはマックレの寝室だった。
「キッド、ビリー、この部屋に他に扉がないか調べてくれ。」
部屋には大きな天蓋の付いたベッドが1つ、衣装箪笥、小さなテーブル、椅子、木箱などが置かれていた。
窓が1つあって、鎧戸がついていた。
「扉はないですね。」
壁に沿って調べていたキッドがそう言った。
「ベッドの下にもないぞ。」
床に這いつくばっていたビリーもそう言った。
「よし、この部屋は行き止まりだな。」
部屋を一回りしたエバもそう言って頷いた。
「エバ、どうだ。」
シェリルたちも部屋に入って来た。
「もう終わったのか。」
「ソフィもエイリスも、みんな手伝ってくれたからね。」
シェリルがニコッとした。
「この部屋は使えそうか?」
シェリルがエバに尋ねた。
「行き止まりで窓が1つ。悪くない。ここで迎え撃とう。」
エバの言葉にシェリルも頷いた。
「エバ、作戦を説明してくれ。」
シェリルの言葉に、エバは頷くと口を開いた。
「作戦は簡単だ。俺とシェリルは、隣の執務部屋で兵士を迎え撃つ。残りのみんなはこの部屋にいて、あの窓からこの部屋に入ろうとする兵士を突き落とす。マーリン兄妹は、この部屋から俺とシェリルを応援してくれ。以上だ。」
エバの説明があまりに簡単すぎて、みんなは理解するのに少し時間がかかった。
「兵士の数はどの程度だろうか。」
バクウェルがエバに尋ねた。
「この城の規模なら50人程度だろう。エルファの軍隊の10分の1に過ぎない。」
「そうか。」
何が過ぎないのかバクウェルには理解できなかったが、エバがあまりにもあっけらかんとしているので、バクウェルはそれ以上何も言えなかった。
「私もエバと一緒に戦うわ。」
ソフィがそう言ってエバを見つめた。
エバは少しの間じっとソフィを見た。
「いいだろう。一緒に戦おう。」
ソフィがエバに笑顔を見せた。
するとキッドが右手を上げた。
「窓から来る敵を、どうやって突き落とせばいいですか。」
するとエバは、部屋に置いてある衣装箪笥に目をやった。
「あの衣装箪笥がちょうどいい大きさだ、中身を取り出して空にする。そして、敵が鎧戸を引き上げて、部屋に入ろうと上半身を出したら、衣装箪笥を突き出して下に落とす。すると、敵が下に落ちて、また鎧戸が閉まる。」
エバが、肩に担いだ何かを突き出すような素振りを見せた。
「なるほど。」
キッドがそう言って頷いた。
「念のため、鎧戸の突っ張り棒を持って1人が待機しているといいだろう。なかなか落ちない奴がいたら、突っ張り棒で顔面を突けば、さすがに落ちるだろう。それから、気になったとしても、鎧戸を中から開けて顔を出したりしてはいけない。さっきのように矢で射られる。」
エバの言葉にみんなが分かったように頷いた。
「じゃあ、俺とキッドとバクウェルさんとルードさんで、衣装箪笥をやりますか。」
ビリーがそう言ってキッド、バクウェル、ルードを見ると、3人は頷いた。
「じゃあ、私は突っ張り棒を持つわ。」
ルーが言った。
「私は何をすればいいかね。」
ソンドラがキッドに尋ねた。
「ソンドラとエイリスさんは、誰かが疲れた時の交代要員ということで待機していてください。」
「そうだな、何があるか分からないし。」
ビリーが言った。
「分かったわ。」
ソンドラとエイリスが頷いた。
「兵士の本体はどちらでしょうか?もしかしたら、部屋の扉をドンドン叩いている兵士が陽動で、窓から入って来る兵士が本体とか。」
ルードがそう言うと心配そうな顔をした。
「それはない。窓から侵入しようとすれば、どうしても1人ずつとなってしまう。一斉に攻撃できないから、1人ずつ各個撃破される恐れがある。本体は部屋の扉をドンドン叩いている兵士たちの方だ。」
エバの説明にルードだけでなくみんなが納得したように頷いた。
「それじゃあ、エバ、ソフィ、行こうか。」
シェリルがエバとソフィを見た。
「シェリル姉さん。気を付けて。」
マリーウェザーがシェリルを見た。
「マリーウェザーが応援してくれるのだから、やられはしないよ。」
シェリルはマリーウェザーを見て微笑んだ。
そしてシェリルは、隣に立っているアレンティーにも微笑んだ。
アレンティーもシェリルに向かってニコッとした。
「私たち3人がこの部屋を出たら、扉に閂を掛けるのだ。」
そう言うと、シェリルとエバとソフィは寝室を出て行った。
キッドが部屋の扉を閉めると、閂を掛けた。
「それじゃあ、衣装箪笥の中身を出しますか。」
ビリーがそう言うと、みんなで衣装箪笥に向かった。
シェリルとエバとソフィは、がらんとした部屋の中心に立った。
部屋にあった調度品は全て入り口と隠し扉の前に立て掛けてあった。
この執務部屋は、30人は人が入れる程度の大きさがあり、隣の寝室よりも大きかった。
エバがシェリルとソフィを見た。
「悪いが、俺が縦横無尽に斬りまくるから、二人は俺の左右斜め後ろで付いて来て、俺の背中を守ってくれ。」
エバの説明を聞いて、ソフィが納得したように頷いた。
「分かったわ。エバを先頭にした三角形の形。つまり、三英傑の陣ね。」
ソフィの言葉を聞いて、エバが少し驚いた顔をした。
「そんな風に呼ぶのか。俺の流派では、楔(くさび)戦法と呼んでいる。」
するとシェリルも2人に言った。
「私の流派では、三流星と呼んでいるぞ。」
シェリルがそう言うと、3人は声を出して笑った。
「流派によって呼び方が違うんだな。まあ、当たり前か。」
すると、ようやく入り口の扉に立て掛けられた物置き棚などが倒されると、それを乗り越えて兵士たちが部屋に入って来た。
だが、入って来た兵士たちの中に、明らかに兵士らしくない男たちがいた。
「全く、城の扉がこんなに丈夫にできているとは。これでは不意打ちどころじゃねえな。」
背中に大きな剣を背負った男がそう言うと、両手の平を見せた。
「ええい、くそう。乗り越えるのに一苦労じゃわい!」
背が低くずんぐりとしていて、顎髭を長く伸ばした男が、物置き棚を必死で乗り越えていた。
手足が短いので苦労しているようだ。
刃の大きな斧を腰に提げていた。
「この愚か者たちに、神の思し召しがあらんことを。」
ずんぐりした男の横を通って、大きな紋章の入った上着を着た男が部屋に入って来た。
その紋章から神に仕える神官であることが分かった。
「我が魔力を味わってみたいなどという、身の程知らずの愚か者というのはお前たちか?」
大きなこぶのついた杖を持ち、赤色のローブを被った男が部屋に入って来た。
大剣の男は、部屋の端に転がっているマックレと細身の男を見た。
「おいおいおい、死んでんじゃねえか。」
大剣の男はそう言うと、顔を右手の平で覆うと、ガクッと大袈裟に態勢を崩した。
「これじゃあ、ボワロ将軍に顔向けできねえよ。」
大剣の男は、顔を覆っていた手を外すと、真顔でエバたちを見た。
そしてシェリルに顔を向けた。
顔に二つの刀傷の女。
「お前がシェリルだな。」
大剣の男がそう言った。
だがシェリルはそれには答えなかった。
「お前ら、いいか、顔に二つの刀傷のある女。この女は殺すな。それ以外は殺せ。分かったか。」
大剣の男が兵士たちに指示した。
50対3。
大剣の男は、あまりの戦力差に勝利を確信した様子で笑みを浮かべた。
俺たちが手を出す必要もない。
「お前ら、ぶっ殺せ!」
大剣の男が兵士らに命令した。
「おらあ!わしに続けえ!」
背が低くずんぐりとしていて、顎髭を長く伸ばした男が、刃の大きな斧を振り回しながら一番に走り出した。
「うおおおお。」
すると兵士らも腰の剣を抜くと、ずんぐりした男に続いた。
「全く、ドワーフはこれだから。しようがないですね。」
大きな紋章の入った上着を着た男がそう言うと肩をすくめた。
ずんぐりとした男はエバに走り寄った。
もう1歩、もう1歩踏み出したら、この斧を胸板に突き立ててやる。ずんぐりとした男はそう思って斧を握っている手に力を込めた。
「おらあ!」
背が低くずんぐりとした男が吠えると、斧を振り上げた。
だがその瞬間、エバの剣がずんぐりとした男の首を刎ねた。
ずんぐりとした男の首が胴体から離れ宙を飛んだ。
そして首の無くなったずんぐりとした男の胴体が前につんのめると、勢いでごろごろと転がった。
エバは、左手に持っている剣についた血糊を振るうと、タタッと走り出した。
するとシェリルがソフィを見た。
「ソフィ、行くぞ!」
シェリルがソフィに声を掛けるとエバに続いて走り出した。
ソフィも反射的にシェリルに続いた。
「エバに合わせて、エバの背中を守るんだ!」
シェリルの言葉に、ソフィは走りながら頷いた。
するとエバがまたタタッと走って、ずんぐりした男の後ろにいた兵士に近付くと剣を伸ばした。
エバの剣は、兵士の顔面に抵抗もないようにスッと深く入り込んだ。
兵士の体は小さく痙攣した。
エバが剣を引き抜くと、その兵士はバタンと地面に倒れた。
「おい、神官!ドーワフを魔法で何とか治療しろよ!死んじまうぞ!」
大剣の男が大声でそう言った。
しかし神官はかぶりを振った。
「首と胴体が離れているのに、魔法でどう治療すればいいんだよ。こんなの無理だ。」
「くそう、役立たずが。」
エバはまたタタッと走ると、今度は別の兵士の顔面に剣を伸ばした。
すると、別の兵士もバタンと地面に倒れた。
エバは、兵士たちがひしめく中を進みながら、次から次と兵士らをバタバタと倒していった。
大剣の男は、今、目の前の現状をどう理解すれば良いのか分からなかった。
何でこうも易々と兵士たちが次々に死んでいくのだろうか。
兵士たちはエバの剣を避けようとしていないのだ。
とりあえず大剣の男は、反射的に背中の剣を抜いて構えを取った。
シェリルは、エバの背中を追いかけながら、横からエバに近付こうとする兵士に剣を繰り出し、牽制した。
シェリルは、エバの剣術の腕前を誰よりも良く知っていた。
エバは、人間の動きというものを熟知している。
人間が次にどのような動きをするのか分かるのだ。
さらに、人間の視界のどこに穴があるのかも知っている。
また、敵を見ないで斬ることも出来るし、斬るという動作をしないで斬ることもできる。
エバはただ、うっかり隙を作ってしまった兵士を見つけては、相手の見えない位置から剣を伸ばして、剣を差し込んでいるだけなのだ。
エバの剣は見えないし、避けられないのだ。
だから、エバが背後から攻撃されないよう、後ろだけ守っていれば、あとはエバが突き進んで敵を殲滅する。
目の前に広がる光景は、まさに一方的な殺戮だった。
エバの右後ろにシェリルが立ち、左後ろにソフィが立つ。
エバたちは、兵士たちの群れに打ち込まれた三角形の楔(くさび)のようだった。
楔が打ち込まれる度に、兵士が1人死んだ。
「距離を取れ、距離を取るんだ!全滅するぞ!」
大剣の男がそう叫ぶと、兵士らは散り散りになって距離を空けた。
距離を空ければ、エバの動く距離も大きくなる。
エバの足が疲れで鈍(にぶ)れば、付け入る隙が出て来るはずだ。
「隣の部屋では戦いが始まったみたいだな。」
衣装箪笥の脇に立っていたビリーが皆にそう言った。
「エバさんなら大丈夫さ。」
キッドが皆にそう言った。
「そうだな、俺たちは俺たちの心配をしよう。」
バクウェルがそう言った。
「来る気配はないですね。ひょっとしたら来ないかも。」
ルードが言った。
ガタガタガタ。
窓の鎧戸が揺れて音がした。
みんなに緊張が走った。
「来やがったな。」
ビリーが窓に目をやりながらそう言った。
「外から鎧戸を開けようとしているんだ。」
「衣装箪笥を準備しよう。」
キッドたちは衣装箪笥に手を掛けると肩に担ぎ上げた。
みんなは黙ってじっとしていた。
ルーは突っ張りっ棒を両手でしっかりと握った。
鎧戸は、何度かガタガタと音を立てていたが、とうとうゆっくりと外側に開いていった。
外から太陽の光が部屋に差し込んだ。
すると、開いた窓の下から兵士の顔が上がって来た。
「今だ!」
「うわあああああああ!」
キッド、ビリー、バクウェル、ルードは衣装箪笥を担いだまま突撃すると、その勢いのまま、窓から覗いている兵士に衣装箪笥ごと体当たりした。
衣装箪笥を顔面に喰らった兵士が、窓から離れて吹き飛んだ。
「ああああああ!」
突撃した衣装箪笥が、ちょうどぴったりと窓にはまっていた。
「退却するぞ。」
「退却、退却だ。」
そう言うと、キッドたちは衣装箪笥を担ぎなおして後ろに下がった。
窓にはまっていた衣装箪笥が引っ込んだので、鎧戸がまたパタンと閉じた。
一旦、衣装箪笥を床に下ろすと、キッドたちは顔を見合わせた。
「やったぜ!」
「ははは。」
「やってやりました。」
キッドとビリーとバクウェルとルードは、お互いにそう言い合って相手の手の平を叩いた。
すると、窓の鎧戸がまたガタガタと鳴った。
「また来たみたいよ。」
ルーが男たちに声を掛けた。
「よっしゃあ!やったるぜ!」
ビリーがそう言うと、男たちはまた衣装箪笥を肩に担いだ。
ビリーたちの様子を眺めていたマーリンは、魔法の目で、壁越しに隣の部屋のエバの戦いも見ていた。
エバほど戦闘に熟練した職人はいない。マーリンはそう思っていた。
職人が一生かけて身に付けるような達人の技術を、エバはその若さでいくつも身に付けているのだ。
エバの学んだ武術が、たくさんの達人たちの経験と知恵と技術を、失伝することなく、余すことなく伝承していたことが幸運だったのだろうが、飽きることなくひたすら剣を振り続け、それら全てを身に付けたエバの、剣に対する異常と呼べるほどの執着心が、エバを熟練した職人に育てたのだろう。
エバのその常軌を逸した剣術は、他の戦士の追随を許さない水準だった。
だが、そのエバに弱点があるとすれば何だろうか?
マーリンはそう考えて、ある結論に達していた。
疲れだ。
人間が人間という存在である限り、生物としての限界を超えることはできない。
どんな人間でも、全力で走り続ければ、十数秒で失速する。
足が止まれば、いくらエバでも戦い続けることはできないのだ。
そろそろだな。マーリンは思った。
「マリーウェザー、アレンティー、そろそろ補給の時間です。ちょうどこの壁の向こう側に3人がいます。私がエバを、マリーウェザーがシェリルを、アレンティーがソフィを。」
マーリンがマリーウェザーとアレンティーに声を掛けた。
「はい、お兄様。」
「分かりました。」
マリーウェザーはそう言うと、アーモンドの形をした小さな盾“タナク”を胸の前に掲げた。
魔法を掛けるのに必要な魔法の杖にあたるのが、この小さな盾“タナク”だった。
マリーウェザーは、首から提げているネックレスに付けられた赤い木の実を指で擦った。
そして、両手足を柔らかく円のような軌跡で動かしながら、小川の流れるように、囁くように歌った。
「・・・ファシソ、シッサス、ジショウソウ、ソウニ、シポビサンセ、シポビサンセハ、サイショウセイサ、クノセイ、シンセス・・・」
アレンティーは腰に提げたいくつもの小袋から、細長い緑の葉を2枚取り出すと両手に1枚ずつ持った。
そして両手を自分の頭の上で交差させると左腕をぶるんと勢いよく震わせた。
すると、腕にはめている丸い腕輪がぶつかり合って、楽器のようにシャランと音を立てた。
アレンティーはその場でくるくると回りながら、両手を伸びやかに広げるように動かすと高い声で囁くように歌った。
「・・・アピミマ、ソカンバニープヨ、アピミマ、ソカンバニープヨ、アピミマ、ソカンバニープヨ、ボクバーアイ、プパカバー・・・」
2人の妹が魔法を掛けるのを見届けると、マーリンは、じっと身動きすることもなく、無言で隣の部屋にいるエバに魔法を掛けた。
エバの弱点は疲れだ。
ならば、その疲れを魔法で取り除いたらどうなるか?
すると、エバは無敵となった。
エバは、一瞬も立ち止まることなく、剣を止めることもなく、流れるように兵士らを殺害し続けた。
この部屋にある1つの窓からも、梯子で上って来た兵士がこの部屋に入り込んだ。
だが、そんなことも全く構わない様子で、エバは兵士を殺害し続けた。
「こいつ、いつまで殺し続けるつもりだ。」
兵士らが驚きの声を上げた。
兵士らは、鎖を編んで作られた服で全身を覆っていたが、エバは、覆われていない顔から剣を差し入れた。
腕で顔を守ったとしても、少しの隙間からエバの剣は入り込み、目、鼻、口、喉を通って、脳や延髄を破壊した。
「あ、悪魔だ!」
次々に兵士が倒れていく様を見て、兵士の1人がそう口走った。
兵士らが散り散りに分かれた分、エバが背後から襲われる可能性はさらに減っていた。
「体が疲れを感じないわ。」
ソフィが、両手に持ったアーモンドの形をした小さな盾“タナク”を、牽制のためにヒュンヒュンと振り回しながら、シェリルに言った。
シェリルも自分の体の異変に気付いていた。
動き続けているのに、少しも息が上がらないし、筋肉が熱を持つことも無かった。
意識も明晰。
疲労によって、集中力が欠けることもなかった。
これなら、鬼ごっこをしても負ける気がしない。逃げる相手を冷静に、全力でいつまでも追い続けられる。
「マリーウェザーとアレンティーが、力を貸してくれている。」
シェリルはソフィにそう言うと、片目を瞑ってウィンクしてみせた。
シェリルは横から剣を繰り出そうとしている兵士を牽制しながら、勇気が体中に溢れてくるのを感じた。
「よし見えた!」
ビリーが窓の下から出て来た兵士の顔を確認した。
「せいの!」
キッドたちは拍子を合わせると3回目の突撃を行った。
「おらあ!」
だが、突撃が少し早過ぎたのか、兵士は吹き飛ばずに指だけで窓にしがみついて粘った。
「やべえ、兵士が残っているぞ!」
ビリーが慌てた様子で言った。
「だが、一旦引くしかない。」
バクウェルがそう言った。
「引いたら、兵士が入って来ちまうよ!」
ビリーが必死な顔になった。
「一度引っ込めて、すぐにもう一度突撃を掛けるんだ!」
バクウェルが力強い口調でビリーに言った。
「よし、やろう。」
ルードが覚悟を決めた顔で3人を見た。
「ルー、悪いが、衣装箪笥を引っ込めたら、中に入らないように棒で突いてくれ。」
キッドがルーに言った。
「分かったわ。」
ルーが突っ張り棒を構えた。
「一度引くぞ、せいの!」
男たちが窓から衣装箪笥を引っ込めた。
すると、窓枠にしがみついていた兵士が体を持ち上げた。
「わああああああ!」
ルーが気合を入れると、突っ張り棒を兵士に向かって突き出した。
すると突っ張り棒は、窓に上ろうとした兵士の胸に当たった。
「うお。」
窓に上がろうとした兵士の動きが止まった。
「せいの!」
男たちが衣装箪笥で突撃を掛けた。
衣装箪笥は見事に兵士に当たって、兵士は吹き飛んだ。
「退却するぞ。」
そう言うと、キッドたちは衣装箪笥を窓から外して後ろに下がった。
窓にはまっていた衣装箪笥が引っ込んだので、鎧戸がまたパタンと閉じた。
衣装箪笥を担いだまま、男たちとルーは顔を見合わせた。
「よっし!」
「やったね。」
「ルー、ありがとうな。」
みんなでそう言い合った。
「みんな大丈夫、疲れていない?」
エイリスが心配そうに声を掛けた。
「俺は大丈夫。」
「大丈夫だ。まだ、いけるぜ。」
キッドとビリーは力強く頷いた。
「替わろうか?」
ソンドラがルードに声を掛けた。
ルードは、4人の男たちの中で1回り体つきが小さかった。
「いえ、もう少し頑張ります。」
ルードは男の意地を見せた。
「くっ、来るな!」
1人の兵士がエバに怯えて後ずさった。
エバはあっさりと怯える兵士の顔に剣を差し込んだ。
エバが剣を引き抜くと、兵士は怯えた顔のまま地面に倒れた。
「ちっ、くそう。何でこうなるんだ。」
大剣の男が大きな剣を振り回すこともできずに、煩(わずら)わしい表情で舌打ちをした。
たくさんの兵士が入り乱れている状況では、大きな剣は使えない。
使えば味方を巻き込んで斬ってしまうからだ。
こうなったら、魔法で一気に片をつけてやる。
大剣の男は、ちらっと後ろにいる全身赤色の男を見た。
全身赤色の男は、ぼそぼそと呟きながら杖を振り回していた。
よし、もう少し時間を稼げば、あの独特のヒッヒッヒという笑い声が聞こえてくるはずだ。
そうすれば、この戦いは終了。終幕だ。
「あが。」
また1人、兵士がエバの剣に倒れた。
すると、それを目の前で見た別の兵士が、その場で床にへたり込み、武器を投げ出してしまった。
「あ、あ、あ、あ。」
とうとう兵士たちの中に、戦意を喪失する者が出始めた。
「に、逃げろ!逃げろ!みんな死ぬぞ!」
1人の兵士がそう言うと、背中を見せて走って逃げた。
すると他の兵士も、慌てて次々と走って逃げた。
部屋の入り口に逃げる兵士が殺到した。
ちっ、くそう。魔法はまだかよ。大剣の男はそう思った。
大剣の男は全身赤色の男に目をやった。
すると、全身赤色の男は、まだぼそぼそと呟きながら杖を振り回していた。
だが、何かおかしい。時間がかかり過ぎている。
大剣の男は、慌てて全身赤色の男に近付いた。
「何をしている、魔法はまだか?」
すると、全身赤色の男は、血の気の引いた白い顔を大剣の男に向けた。
「魔法がっ、唱えられないんだ。口が引きつっれしまって。正確に魔法がっ、唱えられないんだよ。」
全身赤色の男はすがるような顔でそう言った。
大剣の男ははっとした。
これは敵の魔法だ。俺たちは、何処からか魔法で攻撃されている。
大剣の男は周囲を見渡そうとした。
だが、全ての兵士を殺害したエバが、すぐそこに迫っていた。
大剣の男は全身赤色の男を見捨てた。
「こんなくっ、だらないことで、私の強大な魔っ力が、敗れるとは!!」
全身赤色の男は最後にそう言うと、エバの剣で首を刎ねられてしまった。
エバは大剣の男を追った。
大剣の男はエバと距離を空けると、大きな剣を振りかぶった。
他の兵士がいなくなった事で、大きな剣が使えるようになっていた。
何なんだこの男は、なぜこうも無防備に近寄って来る。
俺はドラゴンを殺した男だぞ。
人間に後れを取ることなどあり得ないのだ!!
大剣の男は走って来るエバを睨んだ。
剣の長さではこちらの方が長い。つまり、こちらの方が先に斬ることができるのだ。
あと一歩で、この男を斬る!
だが、その瞬間、大剣の男の首は宙を飛んでいた。
その時、大剣の男は不思議な体験をしていた。
なぜか自分が宙を飛んで、自分の体を見下ろしていたのだ。
まるで幽体離脱でもしたかのように。
だが、見下ろした自分の体には首が無かった。
そうか、俺は首を刎ねられたのだ。
まだ間合いの外だった筈なのに、なぜ。
大剣の男の首は床に落ちて転がると、自分の身体が床に倒れ込むのを見た。
悔しいが、完敗だ。大剣の男はそう思った。
だんだんと視界がぼやけて来て、とうとう周りを見ることが出来なくなった。
兵士たちの逃げる足音だけが耳に響いた。
そして、脳の機能がだんだんと停止していくことで、首を斬られたことによる痛みは消えていった。
目を瞑ると、暖かい日の光に包まれたような、心地よい感覚に包まれた。
これが、死んだ戦士が迎えられるという喜びの園か。・・・心地よい。本当にあったのだな。大剣の男はそう思った。
そして、大剣の男は死んだ。
1人生き残った神官の男は、黙って両手を上げるとエバに対して降参の意志を示した。
エバはゆっくりと周囲を見渡した。
殺戮は終わった。
この部屋には、およそ50人の死体が転がって、足の踏み場もない状況になっていた。
エバが剣を抜いてから1分程しか経っていなかった。
エバは剣についた血糊を振るうと、倒れた兵士の衣服で刃を拭い、鞘に収めた。
「せいの!」
キッドたちは拍子を合わせると5回目の突撃を行った。
「うお!」
衣装箪笥の突撃を喰らって、窓から上半身を乗り出していた兵士は、吹き飛んで下に落ちて行った。
「よし、退却だ。」
キッドたちは衣装箪笥を部屋の中に引っ込めた。
窓の鎧戸がパタンと閉じた。
キッドたちは息を吐いた。
キッドたちは、衣装箪笥を担いだまま、喜んで顔を見合わせた。
「よし。」
キッドたちの額にいくつもの汗の玉が浮かんでいた。
さすがにキッドたちの表情に疲れが出て来た。
緊張した中での力仕事は、余計に体力を消耗させた。
キッドたちは黙って鎧戸を睨んでいた。
だが、それ以降、鎧戸はガタガタと言わなくなった。
「一度、下ろしますか。」
ビリーがそう提案すると、キッドたちは衣装箪笥を床に置いた。
「諦めてくれたかな。」
ルーが祈るような声でそう言った。
「そうだといいわね。」
エイリスも祈るように両手を握るとそう言った。
トントントントン。
突然、部屋の入り口の扉を誰かが叩く音がしたので、みんなはビクッとした。
「私だ、シェリルだ。終わったから開けてくれ。」
扉の外からシェリルの声がした。
シェリルの声を聞いて、ほっとした様子でみんなで顔を見合わせた。
ビリーが扉に近付くと、閂を外して扉を引き開けた。
「うわ!」
ビリーが驚いた顔を見せた。
他のみんなも入り口の扉に近付くと言葉を失った。
「何だこれは、・・・地獄か。」
バクウェルが眉をしかめると、独り言のように呟いた。
部屋の中に転がっている大量の死体を見て、誰もが言葉を失った。
「そうだ、地獄だ。だからお前たちは、人なんて殺さない方がいい。」
エバが独り言のようにそう言った。
エバの言葉が寂しくて、誰も何も言えなかった。
「さあ、みんな。まだ終わった訳ではないのだ。ボワロのところに乗り込もう。」
シェリルがみんなにそう言った。
「足元に気を付けて、滑るから。」
ソフィがみんなにそう言った。
エバたちは死体だらけの部屋を抜けると、大広間に出た。
大広間の壁は漆喰で白く塗られ、絵画や毛織物によって飾られていたが、大広間の真ん中辺りが、まるで大きな穴が空いているかのように真っ黒になっていた。
良く見ると、床に敷かれたイ草が真っ黒に燃えてしまっていて、さらに、その下の床板までも、真っ黒に焦げてしまっているのであった。
さらに、高座に据えられた領主の椅子は、縦に裂けて壊れてしまっていた。
大広間にはもう人の姿はなかった。
「何があったんだ。」
キッドがぼそりと呟いた。
「ボワロの部屋はこっちよ。」
ソフィの案内でエバたちは大広間を横切ると、マックレが居た部屋から左手側の部屋にやって来た。
エバは入り口の扉を押し開いた。
その部屋には、長椅子とテーブルが置かれていた。
部屋の反対側には、奥の部屋に続く別の扉が付いていて、その扉の横に男の侍従が1人立っていた。
「ボワロは?」
部屋に入ったソフィが侍従に尋ねた。
侍従は黙って奥の部屋に続く扉を示した。
「俺が開けよう。」
エバがそう言ってソフィを追い越すと、扉の横に立った。
侍従は慌てて、この部屋を出て行った。
エバは扉の横に立つと、扉を奥に押し開いた。
特に何も起きなかった。
エバが部屋に入ると、窓際に置かれた背もたれの付いた椅子に、男が足を組んで座るとガラス窓越しに外の景色を眺めていた。
シェリルたちもエバに続いて部屋に入った。
この部屋にも、小さなテーブルとそれを囲むように背もたれの付いた長椅子が置かれ、その他に、暖炉、食器棚、物置き棚が置かれ、壁には朱色が特徴的な大きな絵画が飾られていた。
「ボワロ。」
ソフィが椅子に座っている男を見てそう言った。
ボワロは首を回してエバたちを見た。
するとボワロの視線が動いて、目の前に立っているエバたちの中から、シェリルを見つけた。
「シェリル嬢。まさか貴方の方から私に会い来て頂けるとは、思ってもいませんでしたよ。私のデートの誘いを受けていただけますか?」
ボワロはそう言ってシェリルに微笑んだ。
「まさか。こうなる事が分かっていれば、昨日シャロムの街の入り口で会った時に、お前を捕まえておいたのに。・・・残念だよ。」
シェリルの言葉に、ボワロは目を瞑ると、肘掛けに片肘をつくと拳を顎に当てた。
そんなボワロの態度に、シェリルは目を細めてボワロを見た。
「悪いが、私たちはお前に死んで貰いに来た。」
「ほう。」
ボワロは目を瞑ったまま頷いて見せた。
「バクウェル、執行を。」
シェリルがバクウェルに言った。
「ルード。」
バクウェルがルードに声を掛けた。
「はい。」
ルードは背負い袋から令状を取り出すとバクウェルに手渡した。
「ボワロ!」
バクウェルがボワロに声を掛けると、ボワロは目を開けた。
バクウェルは令状を広げると、ボワロに見えるように前に進み出た。
「3年間もの間、ヤドゥイカ子爵の継承者であるとして国王を欺き、私利私欲のために領主の地位を利用し、国王が得るはずだった領地からの収入を領得した。」
バクウェルは広げた両手をパンと畳んで書状を丸めると、棒状にした令状でボワロを指した。
「強制執行だ。ご覚悟を。」
だがボワロは、組んだ足をピクリとも動かすこともなく、ただ顔を持ち上げるとバクウェルを見下ろすように見た。
そして言った。
「何が強制執行だ。殺すなら部屋に入るなりさっさと殺すがいい。だが、そうしないのは、俺から何か聞きたい事があるのだろう。」
ボワロの言葉に、エバたちは思わず言葉を失った。
するとボワロは、エバたちを順番に一通り見渡すと、最後にシェリルを見た。
「せっかくここまで辿り着いたのだ、いいだろう。敬意を表して話をしましょう。」
ボワロはシェリルに向かって右手の平を見せた。
「だが、条件があります。私は、シェリルとしか話をしない。」
ボワロは開いた右手を閉じて人差し指を立てると、エバたちに向かって左右に振って見せた。
「いいだろう。」
シェリルがボワロに向かって頷いた。
「それでは・・・、そちらで話をしましょう。さあ、余計なみなさんも座ってください。」
ボワロは組んでいた足を解くと、立ち上がってエバたちに長椅子に座るよう促した。
エバたちは長椅子に腰を下ろした。
ボワロは物置き棚から瓶詰のワインを取り出すと、食器棚から焼き物のコップを取り出した。
「ワインでもいかがですか。」
ボワロはシェリルにそう声を掛けた。
「聞いてどうする?飲みたければ飲めばいいだろう。」
「これは手厳しいですな。」
ボワロがコップを持ったまま口をへの字に曲げた。
「お前を甘やかしに来たのではないからな。」
シェリルが冷ややかな視線をボワロに送った。
ボワロは長椅子に腰を掛けると、テーブルにコップを2つ置き、そこにワインを注いだ。
ボワロはコップを1つ手に取ると、コップを口元に持っていき目を瞑った。
「ワインは、高貴な飲み物であると、言われている。」
ボワロは黙って、ワインの香りを嗅いだ。
「こんな腐ったようなブドウ汁が高貴だと。笑わせてくれる。」
ボワロはそう言うとワインを口に含んだ。
そしてシェリルを見た。
「これはただの腐ったブドウ汁だ。私は自分にそう言い聞かせて、いつもこいつを飲み干してきた。そこに高貴な存在があるのだとすれば、それはワインではなく、飲み干している人間であると。」
ボワロはそう言うと、視線をシェリルから壁に掛けられた絵画に移した。
「バークを知っているだろう。」
シェリルはボワロに尋ねた。
「当然だ。」
ボワロは視線を絵画に向けたまま、無造作にそう言った。
「バークは前代領主の奥さんを殺した。」
「私がマックレにそう指示したからな。」
ボワロは目だけを動かしてシェリルを見た。
「なるほど。」
シェリルは目を閉じて大きく頷いた。
「マックレは死んだよ。最後までお前の事を信頼していたようだ。」
シェリルは目を瞑ったままそう言った。
「騙されていたというのに、愚かな男だ。」
ボワロがニヤリと口元に笑みを浮かべた。
「マックレは、何故お前の事を信頼していたのだろう。」
「マックレには、エルファとの商売がうまくいけば、高級役人に戻してやると約束していた。」
シェリルは目を開いてボワロを見た。
「そんなのは嘘だろう。真相を知っているマックレを、お前が生かしておくとは思えない。」
「ははは、そうだな。」
ボワロは微笑むと目を瞑って見せた。
「マノフというエルファを知っているだろう。」
そう言うとシェリルは足を組むと、両腕を組んだ。
「ああ知っている。結構頑張っていたな。最後にへまをしたが。」
ボワロはそう言うと、目を開けて、首を少し傾げてシェリルを見た。
「マノフは何のために頑張ったのだろう。」
ボワロは顔を上向きにすると、見下ろすようにシェリルを見た。
「マノフには、成功したらエルファの代表として扱う事を約束していた。俺がこの街の領主となって、エルファの森を植民地化したら、それを管理する者が必要だからな。」
すると即座にシェリルが言った。
「嘘を付け。お前がマノフを生かしておく訳がないだろうが。マノフはお前がどのように領主になったか知っているのだからな。」
「ははは、そのとおり。」
ボワロは愉快そうに笑った。
「ひどい。」
ルーが思わずそう口走った。
「本当ね。何でそんなことが出来るのかしら。」
ソフィがそう言ってボワロを睨んだ。
ボワロはちらっとソフィを見ると、わざとニヤリと笑みを浮かべて見せた。
そして何でもないというように、またシェリルに視線を向けた。
「お前、何とも思わないのか、マックレとか、マノフとか。」
シェリルが組んでいた足を解いて、ボワロの方に身を乗り出した。
「それが・・・、」
ボワロは体を起こすと、一変して真剣な表情を見せた。
「何とも思わんのだ。」
ボワロは身を乗り出すと、真剣なその顔でシェリルを見た。
そうだ、俺は人間ではない。ボワロはその事を思い出していた。
幼い時からそうだった。
俺は人の気持ちが分からなかった。
成長するにつれて、自分にもはっきりと分かった。
他人のために泣いたことなど無かった。
泣くのは自分が愚かな人間だと分かった時、つまり自分の為だけだった。
そして母親が死んだ時も、父親が死んだ時も涙は出なかった。
ただ、死んだという事実を受け入れただけだ。
両親が死んだ時くらい涙を流すかと思っていたが、自分という人間はそうではなかった。
両親は俺を守ってくれた。温もりを与えてくれた。育ててくれた。
とても立派な両親だった。
なのに俺の心は、なんと冷たいのだろう。
俺は人間ではないな、その時に俺はそう自覚した。
だが、商売を始めて、人の気持ちが分からない事が自分の長所だと気付いた。
相手を傷つけても、罪悪感を感じないのだ。
平気でいくらでも傷付けられた。切り捨てられた。
すると、金がたくさん懐に入るようになった。
要は、他人から金を奪えば良いのだ。
他人を利用し、傷付け、切り捨てる程に金が儲かる。それが金を儲けるためのこの世界の法則。
その法則を徹底する才能が、俺にはあったのだ。
なんだ、世界は俺を認めているではないか。
俺が壊れているだけでなく、この世界も壊れていたのだ。
そうして俺は、自分を偽るのを止めた。
するとボワロは、向かいに座っているシェリルの目が涙で潤んでいることに気付いた。

「マックレとマノフが可哀想か。」
ボワロが無表情でそう言った。
シェリルが目を閉じると、溜まっていた涙が頬を流れた。
「ああそうだ。お前と話をして分かった。2人はお前の言葉を信じていたんだ。その気持ちは本当だったんだなって。2人はお前に裏切られているとも知らずに、一生懸命、頑張って生きたよ。」
シェリルが潤んだ目でボワロを見た。
「そうか。」
ボワロは寂しそうな顔をした。
「でも、お前には分からないんだな。」
「そうだ。」
シェリルは指で瞼を拭った。
ボワロは黙ってシェリルの様子を見ていた。
そして言った。
「シェリル、お前はこんな私をどう思う?」
「・・・知りたいのか?」
「ああ、興味があるのだ。ぜひ、聞かせてくれないか。」
シェリルは、両手を合わせて口元に持っていくと、少しの間じっと考えた。
そして言った。
「そうだな・・・、正直、お前も苦労しているのだなって思うよ。」
シェリルの言葉に、思わずボワロは体を起こすと声を出して笑った。
「ははは、そうなのか。すまないな、気を遣って貰って。てっきり、お前は人間ではないと、そう言われると思っていたよ。」
するとシェリルは、フッと笑みを浮かべた。
「まさか、それはお前が自分の事をそう思っているのだろう。」
「・・・。」
ボワロは一瞬で真顔になった。
「お前が人間じゃないとしたら、お前は一体何なんだ。」
「・・・なるほどな。それで、俺が苦労しているというのはどういう意味だ。」
そう言うとボワロは、またシェリルの方に身を乗り出した。
「だって、そもそもお前、自分の事が嫌いだろう?どうだ。」
「なぜ、そう思う。」
ボワロが鋭い視線でシェリルを見た。
するとシェリルは目を伏せた。
「お前、人からありがとうって言われたことはないか?怒鳴られて怒られたことはないか?好きだって告白されたことはないか?悲しいねって涙を見たことはないのか?」
シェリルの言葉に、ボワロは急に目から涙を流した。
母親から笑顔で言われたありがとう。
父親が本気で見せた怒り顔。
人生で一度だけ告白された時の幼馴染の顔。
そして、父親が死んだ時に母親が見せた悲しみの涙。
ボワロの頭の中で、その時の情景が浮かび上がった。
「でも、お前には理解できないのだ。なぜ理解できないのか、自分では理由も分からないのだ。その結果、自分は人間ではないと考える。人間ではない自分は、生きていて良いのだろうかと悩む。そして、死にたいと、そう思う。」
シェリルは目を伏せたままそう言った。
「お前が今、私の目の前で生きているのは、とりあえず、お前なりにその苦しみを乗り越えて来た結果だ。私は、お前のその苦労は認めているんだよ。」
シェリルはボワロを見た。
「お前だって、好きでそうなった訳ではないからね。お前は、立派に人間だ!」
ボワロは涙が止まらなかった。
いつからだろう、涙を流した記憶など、もう残っていない。
だが、この瞬間をずっと待っていたのだろう。
人間ではない俺の事を、人間と認めてくれる瞬間を。
結局、俺も人間だったのだ。
「ボワロ、泣くなよ。お前、極悪人だろう。思わずもらい泣きしちゃうじゃないかよ。」
シェリルが瞼を指で拭った。
ボワロが堪らずに目を伏せて、絨毯にぽろぽろと涙を落した。
そしてぐっと気持ちをこらえた声で言った。
「ああ、悪かった。こんな事で涙がこぼれるとは、思わなかったのでな。」
ボワロは右手で顔を覆った。
「人の気持ちが分かると、もっと暖かい気持ちになるんだ。できれば、お前がもっと若い時に味合わせてあげたかったな。」
「そうなのか。お前ともっと早く・・・会っておきたかったなあ。心から・・・、そう思う。」
シェリルとボワロは、お互いに気持ちを落ち着かせようと、黙ってじっとしていた。
そしてボワロが決心したように顔を上げると、眉間に皴を寄せた顔で、足を組みなおした。
「やはり貴方は、私の想像どおりの女性だったな。さて、どうするかね。」
ボワロがシェリルに尋ねた。
「悪いがお前には、情けなく死んで貰おうと思う。でなければ、お前のせいで亡くなった前代領主の奥様や、マックレやマノフに、顔向けできないからな。・・・天罰だ。」
するとボワロの視線が急に鋭くなった。
「天罰だと。聞き捨てならないな。神にでもなったつもりか。放漫だとは思わんのか。」
ボワロがそう言うと、シェリルは人差し指を左右に振った。
「何を言っている。天罰とは、古来から人が下すものだ。神が下した事など一度もない。」
するとボワロは声を上げて笑った。
「なるほどな、お前の言うとおりだ。そうか、俺は天罰で死ぬという訳か。面白い。だが・・・、私が大人しく死ぬと思っているかね。」
「まさか。」
シェリルが目を鋭くした。
ボワロもシェリルを睨みつけた。
その場にいるみんなに緊張が走った。
ボワロとシェリルの視線が交差した。
「ふん!」
すると突然、この場の真ん中に置かれたテーブルが跳ね上がった。
ボワロが足でテーブルを蹴り上げたのだ。
一瞬、シェリルの視界からボワロの姿が消えた。
ボワロは懐から短剣を取り出すと、シェリルに突撃した。
蹴り上げたテーブルが床に落ちると、短剣を脇に構えたボワロがシェリルの目の前まで迫っていた。
「シェリル、私と一緒に死ねええええええええええ!」
だがその瞬間、エバの剣がボワロの首を刎ねた。
そしてエバは、首のなくなったボワロの身体を蹴り飛ばした。
ボワロの首は、空中を放物線を描いて飛んだ。
ここまでか。
首だけになったボワロは、空中を飛びながら壁に飾られたお気に入りの絵画を見た。
俺の人生に悔いはない。
だが、このまま死にたくはない。
死ぬのなら、シェリルを道連れにして死にたい。
そう考えた時、心に何者かの声が響いた。
「あなたを助けてあげましょう。」
優しい声だった。男か女か分からなかった。
助けてくれ!
ボワロは思わずそう思った。
すると、ボワロは全身が何か生暖かい物で包まれる感じがした。
痛みは消えた。
それよりも気持ちよさを感じた。
水の中に浮いているようだ。
「エバ!」
シェリルがエバに声を掛けた。
シェリルは床に転がったボワロの頭を指差した。
ボワロの頭は笑っていた。
しかもニタニタと。
「何、何なのこれ!」
ソフィがそう言って口を押えた。
気持ち良さの波に揺られていたボワロは、ふと目を開けた。
すると、目の前に首のない自分の身体が長椅子に倒れ込んでいるのが見えた。
シェリルが口を押えて自分を見ていた。
何だこれは。
ボワロは現実を取り戻した。
この体の気持ち良さは欺瞞。目の前の地獄こそ現実だ。
すると、また、優しい声が頭の中に聞こえた。
「なあに、すぐになれますよ。あなたは気持ちよさに震えていれば良いのです。私と一緒になりましょう。」
何だと!
そんなことは俺は望んでいない。
俺はたとえ人間でなくとも、俺自身であり続けるのだ。死んでもだ!
だが、ボワロの頭の中はゆっくりと快楽で満たされていった。
頭が気持ち良い信号の連続で麻痺していくように感じた。
「何だこいつ。床の絨毯とくっつき始めてやがる!」
驚いた表情でキッドが叫んだ。
「悪魔だわ!これが、悪魔だわ!」
エイリスが叫んだ。
その時、ボワロの首が叫んだ。
「俺を殺してくれ!速く!速く!俺が人間でいるうちに!!」
「エバ!」
シェリルが叫んだ。
その瞬間、エバは跳躍すると、着地と同時にボワロの頭を剣で串刺しにした。
そして剣でぐりぐりとボワロの頭を絨毯から無理矢理引き剥がすと、剣を振り抜いて頭を飛ばし、頭を壁に叩きつけた。
壁に叩きつけられた頭は、落ちて床に転がった。
エバはもう一度跳躍すると、足で頭を踏み潰した。
そしてエバは、何度も何度も足で頭を踏み潰した。
とうとうボワロの頭は、ぺちゃんこの皮膚と赤黒いどろどろの何かに変わって、蠢くのが止まった。
みんな黙って、しばらく床のどろどろを眺めていた。
「死んだの?」
ルーがどろどろを眺めながら言った。
「悪魔であっても、憑りついている肉体が破壊されれば、それ以上活動することはできません。だから、目の前のどろどろした悪魔については、大丈夫でしょう。」
マーリンがそう言うと、ルーが黙って頷いた。
「ボワロは、悪魔だったのか?」
バクウェルがマーリンに尋ねた。
「いえ、ボワロが言っていたように、ボワロは死ぬ間際になって悪魔に誘惑されたのでしょう。だから、ボワロは人間です。ただ、ボワロを誘惑した悪魔がどこに潜んでいたのかが分かりません。」
「そうか。悪魔祓いについて資料を読んだことはあったが、本当に目にするとは思わなかった。」
バクウェルがそう言うと右手で口を押えた。
「悪魔が本来の姿を現す前に、退治することができたのだと思います。幸運でしたね。」
マーリンがそう言うと、みんなに向かって頷いて見せた。
「じゃあ、終わったのか、これで。」
ビリーがみんなを見渡してそう言った。
バクウェルは左手で顎髭を何度か撫でた。
「そうだな。執行、終了だ。」
バクウェルもそう言ってみんなを見渡した。
「終了ですね。」
ルードもそう言った。
するとみんなが安心した表情に変わった。
「衝撃的な最期だったが、これで終わりだ。」
シェリルが振り返ると、みんなに笑顔を見せた。
「だが余韻に浸る前に、まずはこの城から無事に脱出することにしよう。」
シェリルの言葉に、みんなも頷いて見せた。
エバたちは、首がなくなったボワロの死体を床に仰向けに置くと、両手を胸の前に置いて形を整えた。
「さようなら、ボワロ。」
ソフィがボワロの死体に向かってそう言った。
エイリスがソフィの肩に手を置いた。
そしてエバたちはボワロの部屋を出た。
エバたちは隣の執務室をさっさと抜けると大広間に出た。
大広間には、やはり誰も人がいなかった。
エバたちは大広間をまっすぐに抜けると、大広間の出口の扉を開けた。
扉を開けるとそこは踊り場になっていて、1階へ下りるための階段が続いていた。
階段には、頭をうな垂れた兵士が何人も座り込んでいた。
エバたちは階段を下りると、大塔の入り口の扉は開けっ放しになっていた。
エバたちは城の中庭に出た。
陽が沈みかけていた。
中庭では、兵士や城で働く使用人たちが、ところどころで集まって話をしていて、非常に騒がしかった。
「突然領主が死亡したからな、混乱するのは当たり前だ。」
バクウェルが眉間に皴を寄せた。
「私も、強制執行した後の事を心配していました。これを治めるのは、頭が痛いですね。」
ルードがそう言って頭を左右に振った。
「行きましょう。城の出口はこっちよ。」
ソフィがみんなを促した。
エバたちは城壁を抜けると、中の中庭を抜けて、前の中庭に入った。
前の中庭にある見張り塔、馬屋、事務所を通り抜けると、エバたちは城の出入り口に来た。
城の出入り口の跳ね橋は、下ろされていた。
エバたちは跳ね橋を渡って、城の外に出た。
エバたちは一度足を止めると、後ろにそびえる城を見上げた。
城は夕陽に照らされて真っ赤に染まっていた。
「以外とあっさり出られましたね。」
キッドがエバにそう言った。
「そうだな。」
「これからどうするの?」
ルーがみんなに尋ねた。
少し寂しい雰囲気がみんなを包んでいた。
みんなの目指した目的は達成された。
この仲間で一緒に行動するのもこれで終わりなのだろうか。
するとビリーが両手を上げた。
「決まってるだろう、一仕事終わったんだ。みんなで打ち上げしようぜ!」
ビリーがそう言うと、みんなの顔が明るい顔に変わった。
「それ、いい。」
「いいんじゃねえか。」
次にシェリルが両手を上げた。
「1つ提案があるんだけど、これからジェシーおばさんのご馳走とエールを持って、ロミタスのところに報告に行かないか?」
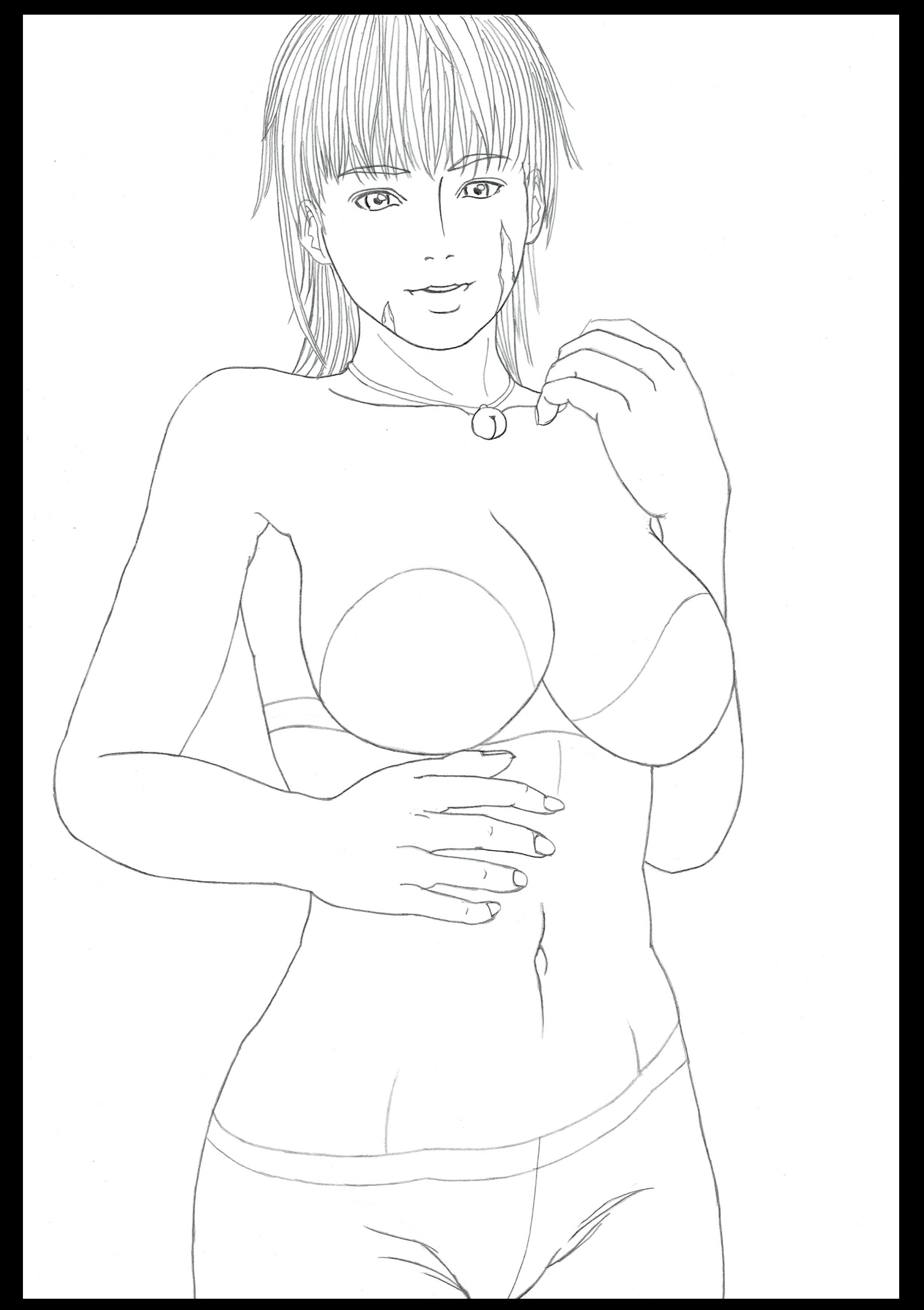
シェリルがそう言うと、みんなの顔がさらに明るくなった。
「それ、凄くいい!」
「楽しそうだな。」
キッドとビリーが顔を見合わせた。
「ロミタスさんも喜ぶわね。」
「きっと喜ぶわ。」
ソフィがエイリスと笑顔で顔を見合わせた。
「ちゃんと、酒とご馳走を調達するための金も用意してあるんだぜ。」
ビリーが得意気に腕を組んだ。
シェリルが伝令らから巻き上げた金を、ビリーは持っているのだ。
「やるじゃん。」
ルーがビリーに笑顔を向けた。
すると、バクウェルが渋い顔で手を上げた。
「申し訳ない、シェリル嬢。城の中の混乱ぶりを見ただろう。城の連中がガヤンに説明を求めに来るだろうし、ボワロの財産を差し押さえなければならないし、報告書もまとめなければならない。」
バクウェルは残念そうな顔でシェリルを見た。
「ですよねえ。」
ルードも肩を落として頷いた。
するとシェリルは、バクウェルに向かって人差し指を左右に振った。
「考え方を変えるんだ。バクウェル、ルード。例えば、ボワロがまだ死んでいなくて、この城から逃亡していたとしたら、当然、これからボワロを追い掛けて執行しなければならないだろ。つまり、お前たちの仕事はまだ終わっていないんだ。だとしたら、どうする?」
シェリルがバクウェルとルードに尋ねた。
バクウェルがフッと笑みを浮かべると肩をすくめた。
「そうですな。命懸けでエルファの軍隊を止めてくれたロミタスさんだ、報告することは重要な仕事だ。」
バクウェルはルードを見た。
「大体俺たちは非番だというのにこんなに頑張ったんだ、仕事のし過ぎだろう。少しは今日の当番に仕事をして貰わないとな。」
バクウェルがルードに笑顔を見せた。
「ですよねえ。」
ルードが嬉しそうに頷いた。
「じゃあ、バクウェルとルードはガヤンに戻って、今日の当番に仕事を押し付けてこい。」
シェリルの言葉に、バクウェルとルードが頷いた。
「ソフィとエイリスとソンドラは、娼館に行って馬を引き出して連れて来るんだ。」
「分かったわ。」
ソフィとエイリスとソンドラは頷いた。
「私たちはジェシーおばさんの宿に行って、美味しい料理と酒を荷車に積んで来よう。」
シェリルはそう言うと、キッド、ビリー、ルーを見た。
「分かったわ。」
ルーがそう言うと、キッドたちも頷いた。
「それじゃあ、ガヤンの前で合流するということで、一旦解散だ。」
シェリルがそう言うと、エバたちは街を貫いているウェイン大通りを南に歩き始めた。
バクウェルとルードがガヤンに到着すると、やはりガヤンの詰め所の入り口には、椅子にどかっと座って足を組み、周囲を眺めているガヤン神官の男がいた。
「バクウェル、お疲れ様。」
同僚のガヤン神官がバクウェルに声を掛けた。
「ルード、馬の準備をして来てくれ。」
バクウェルはルードに指示した。
「承知しました。」
ルードは馬屋に歩いて行った。
次にバクウェルは同僚のガヤン神官を見た。
「マックレ卿が亡くなった。」
バクウェルが同僚のガヤン神官にそう言った。
「そうか、これから大変な事になるな。」
同僚のガヤン神官が溜め息をついた。
「悪いが、俺たちはこれからエルファの代表への報告が残っている。城から問い合わせがあると思うが、うまく対応してくれ。」
「何だって!」
バクウェルは何でもないというように同僚を見た。
「城の家令やら侍従長やらミンチン市政長官やらが押し掛けるかもしれんから、うまく説明しておいてくれ。」
「俺にできるかよ。」
同僚のガヤン神官が立ち上がった。
「概要は知っているだろう、こっちはまだ仕事が終わらない。今日の当番はお前なのだからしようがないだろう。」
「おい、バクウェル、ふざけるなよ!」
同僚のガヤンは表情を豹変させるとバクウェルに迫った。
しかしバクウェルは全く表情を変えることは無かった。
全く恐くないな。バクウェルは同僚のガヤンの顔を見てそう思った。
城での戦いや、マックレとボワロと対峙した時のことを考えれば、全く持って迫力不足だ。
だいたい何がふざけるなだ。
申し送りはしておいただろうが、なのに何もせずにさぼっていたのはお前だろうが。
バクウェルは淡々とした態度で話を続けた。
「悪いな。あと、ボワロ商会の財産を差し押さえておいてくれ。」
「はあ!」
同僚が悪態をついたが、あえてバクウェルは無視することにした。
「おい、バクウェル!」
同僚がバクウェルの腕を握った。
するとバクウェルは同僚に指を突き付けた。
「もう一度言っておくが、俺はまだ重要な仕事が残っている。だが、お前はどうだ。何か重大な仕事でも抱えているのか?もし、お前が正当な理由もなくボワロの財産を流失させるような事があればどうなるか。その時俺は、口を閉ざしたりはしないからな。」
バクウェルはそう言うと、そっぽを向いた。
すると、少しの間、同僚のガヤンは黙って考えていると、バクウェルに声を掛けた。
「おい、バクウェル。・・・分かったから、ちょっと教えてくれ。確認しておかないとこっちも動けない。」
同僚のガヤンがバクウェルにそう声を掛けた。
「分かった、何を教えればいい。あまり時間は無いぞ。」
バクウェルは同僚のガヤンに向き直った。
ソフィとエイリスとソンドラは娼館の2階にあるソフィの部屋に来ていた。
エイリスは、エルファの森に帰るため、城から持ち出した荷物を背負い袋に詰め込んでいた。
「とうとう帰るんだね。」
ベッドに腰掛けたソフィが、衣類をきつく絞るように丸めているエイリスを見ながらそう言った。
「そうだね。」
エイリスが手を動かしながらそう言った。
「ソフィはどうするの?」
エイリスがソフィに聞いた。
「そうなんだよね。」
ソフィがベッドに腰掛けたまま、前屈みになると憂鬱そうに頬杖をついた。
「一緒にエルファの森に来る?歓迎するわよ。」
「ありがとう。でも遠慮しておくわ。」
ソフィがエイリスに微笑んだ。
「そう。」
エイリスがそう言った。
ソフィはベッドの上にごろんと横になった。
すると急に、ソフィの心の中が空虚で寂しい気持ちになった。
ソフィは右腕で顔を覆った。
「ソフィ。」
ソフィが目を開けると、ソンドラが覗き込んでいた。
「ソフィ、この娼館にずっと居てもいいのですよ。」
ソンドラがソフィにそう言った。
だがソフィは、首を左右に振った。
「私もしてみたいな。世界中を回る旅を。」
ソフィが昨日初めてエバと会った時、ソフィはエバにそう言った。
するとエバは、ソフィを見つめてこう言った。
「したらいいんじゃないか。」
その時私は、エバが世界中を回る旅に私を誘ってくれているのだと思った。
でも今考えると、本当にそうなのだろうか。
エバからはっきりと一緒に来ないかと言われた訳ではないのだ。
ソフィはとても不安な気持ちになった。
でも、そうだとしても、もうこの娼館にいるつもりはない。
言われるがままに色々な貴族の家を転々とするのはもうこれで終わりだ。
「私も荷物を纏めるわ。」
そう言うとソフィはベッドから起き上がると、素足でタタッっと物置きのための木箱まで歩いて行くと、中から背負い袋を取り出した。
そして衣装箪笥の中から、持っていく衣類の品定めを始めた。
エバとキッドたちはジェシーおばさんの宿に戻って来ていた。
キッドたちが馬や荷車を準備している間に、シェリルたちは宿に置いてきた荷物を整理して、宿を出る準備をしていた。
「もう戻らないの?」
ずだ袋に放り込んだ衣類を、一旦ベッドの上に並べて整理していたマリーウェザーがシェリルに聞いた。
「ああ、もう戻らない。今日はロミタスのところに泊まらせて貰うつもりだ。そして日が明けたら、この街を出ようと思う。」
「そうか。」
マリーウェザーが衣類に目をやりながらそう言った。
「もう少し、この街に居たかった?」
シェリルがマリーウェザーに聞いた。
「う〜ん。ルーと仲良くなったから。」
マリーウェザーがうつむいてそう言った。
「ルーはとっても良い子だ。」
ベッドの上でたくさんの小袋を並べて眺めているアレンティーもそう呟いた。
シェリルが2人に微笑んだ。
「良かったね。でも神聖王国に行った帰りにまたこの街に寄るから、きっとまた会えるよ。」
「そうね。」
マリーウェザーがシェリルにニコッとした。
3人は荷物をまとめると、部屋を出て広間に来た。
広間では、テーブルに大皿の料理が並んでいて、ビリーとジェシーおばさんが腕を組んで立っていた。
「おいしそうな料理だ。ジェシーおばさんありがとう。」
シェリルがジェシーおばさんに微笑んだ。
ジェシーおばさんもシェリルにニコッとすると、すぐに困った顔になった。
「それはいいのだけど、どうやって料理を運ぶかね。」
「このままじゃ中身はこぼれちまうし、皿は割れるし。」
ビリーも困った様子でそう言った。
「何かで蓋をするしかないだろう。」
シェリルが人差し指を顎に当ててそう言った。
「お皿のパンで蓋をしたら。」
アレンティーが控えめに言った。
「それはいいわね。料理のつゆがこぼれそうになっても、お皿のパンが吸い取ってくれるし。」
「そうか、なるほど。じゃあ、皿のパンで蓋をして紐で縛ってしまおう。」
マリーウェザーとビリーが嬉しそうに顔を見合わせた。
「じゃあ、皿のパンを持ってきてあげるよ。」
ジェシーおばさんがそう言って厨房に歩いて行った。
「じゃあ、俺は紐を探して来よう。」
ビリーが馬屋の方に歩いて行った。
「ちょっと、私も一緒に行くわ。」
マリーウェザーがビリーの後に続いた。
「何だ、手伝ってくれるのか。」
「まあそうだけど。ビリーに任せておくと、汚い紐でも平気で持ってきそうだから。」
「何だって、そんなことかよ。」
ビリーが左右に頭を振ると、マリーウェザーと並んで馬屋の方に歩いて行った。
「仲良くなったみたいだな。」
いつの間にかシェリルの隣に来ていたエバがそう言った。
「本当だね。」
シェリルがエバに微笑んだ。
「もうこの街を出るという事でいいんですか。」
エバの横に立っているマーリンがシェリルに尋ねた。
「ああ、私ができることはやり切ったよ。」
シェリルがマーリンにニコッとした。
「エバさん、馬と荷車の準備はできましたよ。」
宿屋の外からキッドとルーがそう言って広間に入って来た。
「ありがとう。」
エバたちはジェシーおばさんの料理を皿代わりの固いパンで蓋をすると、ビリーとマリーウェザーが持って来た藁の紐でぐるぐるに縛り付けた。
そして木箱に藁を詰めると、ジェシーおばさんの料理を詰め込んで蓋を閉めた。
「エールは酒屋で買っていきな。」
ジェシーおばさんがシェリルにそう言った。
「ありがとう。ジェシーおばさん。」
シェリルはそう言って、金貨を1枚ジェシーおばさんに渡した。
「毎度あり。気を付けて行くんだよ。」
「分かったよ。」
するとそこに、馬を曳いたジミーが宿屋に帰って来た。
「ジミー!」
シェリルが嬉しそうな顔で声を掛けた。
「シェリルさん。」
「今からみんなで打ち上げに行くんだ。ジミーも一緒においでよ。」
「何々?何ですか?」
不思議そうな顔をしているジミーを見て、キッドたちは笑った。
エバたちは料理を詰め込んだ木箱を荷車に載せると、荷車にマーリン兄妹とルーが乗り込んだ。
荷車の御者台にエバとキッドが座った。
そして、ビリーとシェリルが同じ馬に乗った。
ジミーも馬に跨った。
エバたちはジェシーおばさんの宿を出発すると、ガヤンの詰め所に到着した。
すると、ガヤンの詰め所の前には、バクウェルたちとソフィたちが待っていた。
「問題なしか。」
バクウェルがシェリルにそう言うと、眉毛を上に引き上げて目を大きくした。
「ああ、問題なしだ。行こうか。」
シェリルがそう言うと、バクウェルとソフィたちも馬に跨って、ガヤンの詰め所を出発した。
エバたちは北門に向かってウェイン大通りを北に進み始めた。
途中、路上でエールを量り売りしている酒屋から、エール樽を樽ごと購入して荷車に載せた。
シェリルたちが北門に着くと、ちょうど北門のおじさんがいた。
「日も暮れたというのに、これからお出掛けかい。」
北門のおじさんがシェリルに声を掛けた。
「そうなんだ、悪いけど通してくれないか。」
「分かったよ。」
シェリルがお願いすると、北門のおじさんは快く北門を開けてくれた。
シェリルたちは北門を出ると、農道を進んでエルファの居住地の入り口に来た。
昼間に来た時と同じように、少し道が広がった広場でエバたちは馬を止めた。
ここから小さな川沿いを上がれば、エルファの駐留地だ。
ここからでもエルファの駐留地で焚かれている焚火の火がいくつも見ることができた。
エバたちは、料理の木箱やエール樽を男たちで担ぐと、川沿いに進んだ。
エバたちが小川に沿って進んでいくと、昼間の時と同じように、先に2人の人の姿が見えて来た。
エルファの見張りだ。
すると見張りの方から声を掛けて来た。
「エイリスさん、よくご無事で。」
見張りのエルファがエイリスに声を掛けた。
「悪い人間たちと決着を着けてきました。」
エイリスがニコッとした。
「そうですか、部族長のところにご案内します。」
見張りのエルファが先頭に立って歩き始めた。
「おお!エイリスが戻って来たぞ!」
すると、さっそく、焚火を囲んでいたエルファたちがエイリスを見つけて集まって来た。
「ただいま戻りました。」
エイリスがおじさんエルファたちにそう言った。
「よく無事に帰って来たなあ。」
エルファの1人がそう声を掛けた。
エイリスは微笑んだ。
「もう、終わったのか。」
「ええ、もう終わりました。全て。だから、明日にはみなさんと一緒にエルファの森に帰れますよ。」
取り囲んでいたエルファが歓声を上げた。
「それはとても良い事じゃないか。」
「さすがエイリス。部族長の娘だ。」
すると、1人のおじさんエルファがシェリルの前に来た。
「ありがとう。人間だというのにエイリスの力になってくれて。」
おじさんエルファの言葉は分からなかったが、嬉しそうな表情から、シェリルはおじさんエルファに微笑んだ。
昼間の時と違って、エイリスだけでなくエバたちもおじさんエルファたちに歓迎された。
「おお、エイリス!シェリル!」
するとエルファたちの騒ぎに気が付いて、ロミタスが急ぎ足で歩いて来た。
「ただいま、お父様。」
「ただいま。」
エイリスとシェリルがロミタスに言った。
「よく帰って来たな。」
ロミタスが笑顔で迎えた。
「俺は後悔していたんだ。やっぱり一緒に行けば良かったとな。良かった。本当に良かった。」
ロミタスは本当に嬉しそうに笑顔を見せると、エイリスとシェリルの肩をポンポンと叩いた。
「約束しただろう、事が終わったらまたみんなで食べようって。ご馳走と酒を持って帰って来たぞ。」
マーリンがシェリルの言葉をロミタスに伝えた。
「そうか、そうか。偉かったな。じゃあ、こっちでやろうじゃないか。」
ロミタスはそう言って焚火の1つを示した。
「よし下ろすぞ。」
エバたちは料理を詰め込んだ木箱を下ろすと、中身の料理を取り出し始めた。
「へえ、皿のパンで蓋をするなんて、よく考えたわね。」
ソフィが嬉しそうで驚いたような顔をした。
「よくできているでしょう。」
マリーウェザーが、料理をぐるぐる巻きにしている藁紐をほどきながらそう言った。
「エール樽はここでいいか。」
エール樽を担いでいたバクウェルたちがシェリルに聞いた。
「石を並べるからちょっと待って。」
マリーウェザーとルーが、樽を安定して置くために、地面に石を置いて整え始めた。
「こいつは豪勢だな。」
ロミタスが並べられた大皿を眺めて嬉しそうな顔をした。
「コップは?」
樽からエールを注ぐために、ルーがみんなに声を掛けた。
マリーウェザーが笑顔でルーを見た。
「私は自分用のコップがあるんだ。」
マリーウェザーがそう言うと、背負い袋から銀色のコップを取り出した。
「そっか、旅慣れているからコップを持ち歩いているんだね。」
ルーが感心したようにそう言った。
この時代、食事のための自分用のナイフを持ち歩く習慣はあったが、旅をしないルーはコップは持ち歩いていなかった。
「私も。」
アレンティーも銀色のコップを手に持っていた。
マリーウェザーとアレンティーがルーにコップを渡した。
すると受け取ったルーが不思議な顔をした。
「このコップ、金属なのに触った感じが何か柔らかい。」
「これは錫のコップだよ。」
「スズ?」
ルーが不思議な顔でマリーウェザーを見た。
「そう、金属の名前だよ。」
マリーウェザーが言った。
「とても軽いし、触った感触も柔らかいし、コップを清潔に保つ力もある。」
アレンティーがそう言った。
「へーっ、いいな。どこで買ったの?」
ルーが2人に尋ねた。
「前に話した、このシャロムの街から遥か東、グラダス半島にあるバドッカという街よ。」
マリーウェザーが言った。
「そっか。」
「でも、錫製品なら、大市であればこの街でも手に入ると思うけど。」
「そうなんだ。」
ルーが嬉しそうな顔をした。
旅をしているエバたちは、自分のコップをルーに渡し、持っていないキッドやバクウェルたちは、エルファの調理人から木製のコップを借りた。
「みんな、エールは行き渡ったかな。」
ルーがみんなに声を掛けた。
「おー。」
みんながコップを掲げて答えた。
「シェリルさん、乾杯しようぜ。」
ビリーがシェリルにそう言った。
シェリルは立ち上がるとみんなを見渡した。
「じゃあみんな、どの神様に祈るかな。」
シェリルがみんなに尋ねた。
「幸運の神タマットだな。今日の戦いに生き残れたのは、全くの幸運だった。」
エバが独り言のようにそう言った。
「やはり思い出の神アルリアナよ。今回の冒険の思い出は、一生忘れないと思うわ。」
ソフィがそう言ってエイリスを見ると、エイリスも頷いてソフィにニコッとした。
「おいおい、ガヤン神を忘れては困るな。ボワロもマックレも、ガヤンで定めた法律に基づいて執行したのだからな。」
バクウェルがそう言って皆を見渡した。
「それなら俺も言わせて貰おうか。緑の月の恵みによって豊かな森があるからこそ、こうやって美味しく酒も呑めるし、ごちそうも食べられるのだぞ。」
ロミタスがみんなにそう言った。
エルファは、神様ではなく、空に浮かぶ緑色の月を神のように崇めていた。
緑の月が自然の恵みをもたらし、世界を豊かな森で覆って、平穏をもたらすことを願っているのだ。
「よし、分かった。ちゃあんと全部に祈るからね。」
シェリルが小さく咳払いをすると、コップを掲げた。
焚火を囲んでいる皆の顔が、焚火の炎にゆらゆらと赤く照らされていた。
「まずは、今日の戦いに勝利をもたらしてくれた、タマット神に感謝を。」
シェリルがそう言ってエバを見ると、エバが頷いて見せた。
「次に、みんなと乗り切った冒険の思い出が、良い思い出として永遠に心に残るように、アルリアナ神に祈りを。」
シェリルがソフィとエイリスを見ると、2人が小さく頷いた。
「それから、悪と戦うための勇気を法で示してくれたガヤン神に敬意を。」
シェリルがバクウェルとルードを見ると、2人はコップを掲げて見せた。
「最後に、ロミタスらエルファの軍隊を、強くまっすぐに育つのを見守ってくれていた、緑の月に感謝を。」
シェリルの言葉をマーリンがロミタスに伝えると、ロミタスは嬉しそうに頷いた。
「おっと、本当の最後だ。今日も料理に腕を奮ってくれた、ジェシーおばさんに大きな感謝を。」
シェリルの言葉にみんなの顔が笑顔になった。
シェリルは一旦みんなを見渡すと言った。
「ゴッソ!」
そういうとシェリルは、隣に座っているマリーウェザーとアレンティーと3人でコップをぶつけた。
コンという軽快な金属音と共に、中のエールが勢いよくこぼれ落ちた。
そして、エバとソフィとエイリスが、キッドとルーとビリーが、マーリンとロミタスとバクウェルが、ルードとソンドラが、お互いにコップをぶつけ合った。
ようやくみんなの顔が笑顔になった。
「なんか、今日の乾杯は、昨日よりも凄く気持ちいい。」
ルーが笑顔でそう言うと、みんなも大きく頷いた。
相手を替えては皆延々とコップをぶつけあい、乾杯を楽しんだ。
「シェリルさん、いただきましょう。」
ビリーがそう言って、両手を合わせるとすりすりと擦り合わせた。
「食いしん坊が笑顔になったな。」
シェリルが嬉しそうな顔でビリーを見た。
「バクウェルさん、ロミタスさんに報告しましょう。」
マーリンがバクウェルに言った。
「ああ、そうだな。」
バクウェルがロミタスを見た。
「ロミタスさん、ボワロとマックレの執行は終了しました。つまり、死にました。」
マーリンがバクウェルの言葉をエルファ語でロミタスに通訳した。
ロミタスは頷いた。
「奴がエルファと戦争をする目的は。」
「ボワロは、シャロムの街の領主となって、エルファの森を植民地化するつもりだったようだ。」
「ふざけるな!何を勝手な事を!」
ロミタスの目が獣の目に変わった。
「だけど、ボワロは卑怯者ではなかったですよ。正々堂々としていました。まあ、シェリルに泣かされてしまいましたが。」
マーリンがロミタスにそう言った。
「ははははは。」
ロミタスは愉快そうに大きな声で笑った。
「確かに、ボワロはマックレと違って大物感があったな。ただの金持ちではない、何か信念を持っている人間だった。」
バクウェルもロミタスとマーリンの顔を見ながらそう言った。
「なるほどな。そういう事はあるかもしれんな。やっていることは悪だが、人間性に見るべきものがあるということか。ならば、マックレはどうだった。」
バクウェルがフッと笑みを浮かべた。
「マックレは、木っ端役人の典型のような奴だったな。」
バクウェルの言葉をマーリンから教えて貰うと、ロミタスは笑った。
「木っ端役人とは分かり易いな。」
「マックレは、全てボワロの命令で動いていたようです。そして、自分は命令に従っただけだから悪くないと言っていました。」
「なるほど。俺たちが思っていたとおりだったな。」
ロミタスがそう言って頷いた。
「そうですね。まあ、シェリルに粉砕されましたが。」
「ははははは。」
ロミタスはまた愉快そうに大きな声で笑った。
「ですが、マックレが罪深いのは、マックレはちゃあんと分かっていました。前の領主の奥様を殺すことで悲しむ人がいることも、エルファと戦争をすることでたくさんの人が死ぬかもしれないことも。そして、そんな事はしてはいけないのだということも。分かっているのに、ボワロのせいにして知らない振りをしていました。」
「なるほどな。・・・だからマックレは死んだのか。当然だ。まあでも、良くやってくれた。ありがとう。これで安心して森に帰ることが出来るというものだ。」
ロミタスがバクウェルに左手を差し出した。
ロミタスとバクウェルは手を握った。
「今回はシェリル嬢に対して格好いいところを見せようと、無理をし過ぎた。普段はもっと楽な仕事しかしていないのだ。こんな危険な仕事は二度とご免だ。」
そう言うとバクウェルは肩をすくめて見せた。
「何を言っている、まだ若いくせに。俺を見ろ、右手がこんなになってもこき使われているのだ。お前だけ楽しようなんて不公平だろう。これからも頼りにさせて貰うからな。」
ロミタスが握っている手に力を込めると、ニヤリと笑みを見せた。
「先輩にはかないませんな。」
バクウェルがそう言うと頭を掻いた。
「マーリンもな。」
次にロミタスはマーリンに手を差し出した。
「私は気ままな自由業ですから。役には立たないと思いますが。」
マーリンはロミタスと手を握った。
「マーリン君は自由業か。それで生活ができるのなら羨ましいですな。」
バクウェルがマーリンを驚いた顔で見た。
「何が自由業だ。怪しいだろう、この男。お前、魔法で人の心を読んでいるのだろう。」
ロミタスがマーリンを細い目でじっと見た。
「そうか、マーリン君は魔法使いか。不思議な木の枝でマックレの嘘を暴いていたが、魔法だったのだな。」
バクウェルもマーリンを横目でじっと見た。
「いや、全く大したものではありませんから、本業は医術の研究でして。」
マーリンが何でもないというように手をひらひらと振った。
「嘘だな。」
「詐欺師だな。」
ロミタスとバクウェルがそう言った。
マーリンがやれやれといった顔つきをすると口を開いた。
「分かりました。先輩方の言葉ですから甘んじて受けます。詐欺師で良いですよ。ただし、私は、本当の事を語る詐欺師です。」
マーリンの言葉に、ロミタスとバクウェルが分からない顔をした。
「これで終わったわね。」
エイリスがソフィに声を掛けた。
「終わったわね。」
ソフィが頷いた。
「納得できたか。」
エバが2人に聞いた。
するとソフィが力なくうな垂れた。
「納得なんてできないわよ。打ちのめされたわ。」
「そうか。」
エバがそう言うと、目を瞑って見せた。
「そんなに衝撃的だった?」
エイリスがソフィに聞いた。
「ボワロの操り人形だったマックレ。でも、私だって一緒。今までただただ周りに流されて生きて来たのだから。そうやって妥協して生きて来て、遂には、助けられたかもしれない奥様を見殺しにしてしまった。」
「ソフィ。」
エイリスが心配そうな顔をした。
「妥協したっていい事は何もない。本当に思い知らされたわ。ボワロの言われたままに操り人形だったマックレは死んだ。ここで私も変わらなければ、きっとマックレと同じように死ぬわ。そして死ぬ時にこう言うの、私は言われたとおりにやっただけ、何も悪くないのに!って。」
「そこまで分かっていれば、奥様だって納得してくれるさ。」
エバが独り言のように言った。
「私はマックレみたいな生き方は絶対に嫌だ。もう妥協なんて絶対にしないから!」
ソフィがぐっと拳を握ってエイリスを見た。
するとエイリスが思わず微笑んだ。
「良かった、元気印のソフィに戻って。」
「エイリスはどうなの?」
ソフィがエイリスに首を傾げて見せた。
「私は、ソフィとはちょっと違うんだけど。私は、諦めてしまっていたの。」
エイリスはそう言うと、両手で握った自分のコップを見つめた。
「前前代の領主だったジョン様は39歳で体を悪くして亡くなったのだけど、前代の領主のカーター様も同じ39歳で体を悪くしてお亡くなりになった。そして前前代の奥様は2代目のカーター様を出産した時にお亡くなりになって。」
「そうだったんだ。」
ソフィが小さく頷いた。
「何だがね、無力感っていうのかな。私の思いとは裏腹に、長くは生きられないのねって。それで、私たちが前代の奥様と引き離される時に、これも運命なのかなって勝手に諦めてしまっていた。」
「そっか。」
「だめだよね、最初から諦めてしまったら、絶対に助けることなんてできないのにね。」
エイリスの肩にソフィの手が触れた。
エイリスがソフィを見た。
「だからね、長く生きているからって、悟ったような気になって、勝手に諦めるのは止めようって。マックレが何と言うのか、それをきちんと聞き遂げなければ、森には戻らない。そう思ったの。」
「それなら、目的達成だな。」
エバがそう言って二人にニヤリと笑顔を見せた。
「そう、目的達成。だからもう、これで終わりでいいよね。」
ソフィが笑顔になった。
「そう、終わりだね。」
エイリスも笑顔を見せた。
「もう一度乾杯しよう。エバも。」
ソフィとエイリスとエバは、改めて木のコップをお互いにぶつけ合った。
コンという子気味良い音がした。
「おいしいね。」
ルーが青菜のミルク煮をスプーンで口に頬張りながら嬉しそうな顔をした。
「うん、おいしいね。」
マリーウェザーがルーに笑顔で答えた。
「ジェシーおばさんは世界一料理が上手いんだ。」
ビリーが得意気にそう言った。
ビリーは大皿をシェリルに回した。
「シェリルさんもどうぞ。」
「ありがとう、ビリー。」
シェリルは大皿からスプーンでミルク煮をすくうと、自分用のカップに入れた。
この時代の料理は、細かく切り刻んで煮込んだものが多かったので、カップとスプーンがあれば十分に食事が出来た。
シェリルは大皿を隣に座っているエバに渡すと、自分のカップからスプーンでミルク煮をすくって口に入れた。
「本当だ。おいしいね。」
シェリルが笑顔でマリーウェザーやルーたちを見た。
みんなでミルク煮を頬張ると、エールをぐいっと喉に流し込んだ。
「ルー、お城の中はどうだった?あんな奥まで入ったことはなかっただろう。」
シェリルがルーに聞いた。
「そうね、ライダーの仕事で城の中に入ったことはあったけど、入口に入ってすぐの事務所までだった。奥の中庭とか大広間や領主の部屋を見るのは初めてだったから、普段入ることができない場所が見れたのは貴重な体験だったわ。」
ルーが城の中を思い出しながらそう言った。
「まず濠を掘って、掘って出た土で城の土台を作る。その土台の上に城壁を立てて、城壁を守るための塔を建てる。このシャロムの街の城も、城壁と塔の組み合わせだったね。」
「そうか、押し寄せる敵を城壁で押し止める。それが城の目的なんだな。」
シェリルの言葉に、キッドがそう言って頷いた。
「それから、どこから押し寄せるか分からない敵に対応するため、城には、全ての部屋が通路で結ばれていて、兵士を効率的に運用できるよう工夫されていた。」
「まさか、街の地下に秘密の地下通路があったなんてな。」
ビリーが両腕を組むと得意気にそう言った。
「おおよそ城がどういうものか分かって貰えたと思う。それはいいのだけど、城というのは、戦争となった時の最終防衛拠点。機密の塊なんだ。私たちはその機密を知ってしまった。だから、街に戻っても城の中の話は人前でしてはいけない。特に、地下通路の話は絶対に人前でしてはいけないよ。」
シェリルはそう言うと、視線を鋭くしてキッドとビリーとルーを順番に見た。
「シェリルさん、脅かさないでくださいよ。」
ビリーがこの場を和ませようと冗談めかしてそう言った。
するとシェリルが人差し指を立てると、自分の唇に当てた。
「本当の機密事項だ。後でバクウェルにもよく言っておくから。絶対に話をしてはいけないよ。私たちは、内通者の騎士の手引きで城に入った。その騎士は戦闘で死んでもう分からない。いいね。」
シェリルの言葉にキッドたちは大きく頷いた。
「シェリル姉さん、ちょっと分からない事があるのだけど。」
マリーウェザーがシェリルに尋ねた。
「何だい。」
「ボワロは一体何だったのかしら。途中で泣き出したから、悪い奴なのか何なのか分からなくなって、何だかすっきりしないのよね。」
マリーウェザーがそう言うと、続いてビリーも口を開いた。
「俺もそう思った。マックレは、分かっているくせに気付かないふりをしている怠け者で、分かり易かった。だけど、ボワロは一体何だったのだろう。」
ビリーとマリーウェザーが顔を見合わせた。
「そうだね。」
シェリルはコップに入っているエールを少し口に含んだ。
「ボワロは、心に障害を持っている男だった。」
「心に障害。」
マリーウェザーが分からない顔をした。
シェリルは頷いて見せた。
「不幸な事に、生まれつき手足の骨や筋肉が変形してしまって、足を引きずらなければ歩けなかったり、手の指がくっついてしまっていたりと、障害を持っている人がいる。」
「そんな人がいるんだね。」
ルーが驚いた顔をした。
シェリルはルーに頷いた。
「だが、障害は手足だけとは限らない。頭に障害を持って生まれて来ることもあるし、心に障害を持って生まれて来ることもある。頭に障害を持っている人は、手足を上手に動かすことが出来なかったり、上手く話すことが出来なかったりする。だけど、心に障害を持って生まれて来た場合には、手足が不自由な訳でもないし、話をしても不自然なところがないから、周りの人が気付いてあげることができない。」
「そういう事か。」
そう言ったキッドは、焚火の炎を見つめながら何か考えている様子だった。
「ボワロも心に障害を持っていて、人の気持ちを心で理解することができない、共感することが出来なかった。ボワロは頭が良いから、理屈では分かっている。だが、嬉しかったり、悲しかったりしなければならない時に、ボワロの心は何も感じなかった。ボワロの心は、共感するための機能を持っておらず、とても冷酷だった。」
「寂しい人ね。」
アレンティーが静かにそう言ってシェリルを見た。
「そうだね、でも、ボワロはその寂しさも感じない。」
シェリルはそう言ってアレンティーと目を合わせた。
「ボワロは一人で死にたい位に悩んだ。だが残念な事に、ボワロが悩んで出した結論は、自分の障害を他人を傷つけることに利用することだったんだ。」
「何でそうなるんだよ。」
ビリーが納得できない様子で吐き捨てた。
「これは私の想像だけど、他人を傷つけることでボワロは商売に成功したのだと思う。自分が今まで忌み嫌っていた心の冷酷さが、商売の世界ではとても役にたった。ボワロにとっては、冷酷な自分を否定することなく、自分に正直に生きるための唯一の生き方、それが商売であり、他人を傷つける生き方だったのだろう。」
「何て迷惑な生き方。」
アレンティーが思わずそう言った。
「そうだね。でもそうなってしまった要因は心の障害であって、ボワロのせいではないから、その生き方を、全てボワロの責任と言ってしまうのは酷だと思う。」
「でも、だからといって、ボワロを放置しておけば、傷ついたり、命を落とす人が出て来るのではないですか。」
キッドが眉をひそめた。
「なんだよそれ。あーもう、どうすればいいんだよ。」
ビリーがそう言って頭を抱えた。
「ボワロを生かしておけば犠牲者が出る。だが、ボワロはその生き方でしか生きられない。とても難しい問題だ。だが、この類(たぐい)の問題の解決策は、私は1つしか思い浮かばない。それは・・・、対決することだ。同じ人間として。」
「そうか。」
キッドが小さく頷いた。
「私がボワロを理解し、ボワロが私を理解し、お互いに分かり合ったからこそ、対決せざるを得なかった。私がボワロに対して誠意を見せられるとすれば、それは、同じ人間として、全力でもって対決すること。それしかないと思う。分かり合ったからこそ避けられない。今回の戦いは、そういう戦いだったと私は理解している。」
シェリルがそう言い終わると、何かしんみりとして寂しい雰囲気になった。
「そういう事ならよ。ボワロはとんでもなく幸せ者だぜ。」
ビリーが突然大きな声を出した。
「やりたい放題生きたうえに、全力で対決して、シェリルさんに優しさまで貰ってさ。羨ましい位だぜ。満足して死んだに決まっている。ボワロは俺たちに感謝するべきさ。そうだろう。」
ビリーがニヤリとしてみんなを見渡した。
「確かにな。」
キッドもビリーにニヤリとした笑顔を見せた。
「という事は、私たちは奥様の仇を討つだけでなく、仇のボワロも救ってあげたという事?」
アレンティーが首を傾げた。
「何それ。そんなに私たちお人好しだったの?」
マリーウェザーが笑顔でそう言った。
するとシェリルが思わず声を出して笑った。
「本当だ。とんだお人好し連中だな。」
シェリルがみんなに笑顔を向けた。
「よっしゃあ。お人好しの神様に乾杯しようぜ!」
ビリーが立ち上がってコップを持ち上げた。
「お人好しの神様って誰よ。」
ルーが笑顔でそう言った。
「それならベッキーが良いと思う。」
アレンティーが静かにそう言った。
思わずルーが声を出して笑った。
「確かに、ベッキーは世界を代表するお人好しだわ。」
「じゃあ、ベッキーに決まりだな。」
ビリーが大きく頷いた。
そしてシェリルやキッドたちも立ち上がった。
ビリーがみんなを見渡すと、わざと1つ咳払いをした。
「それでは、お人好しの神様ベッキーに、俺たちの更なるお人好しの発展を願って。」
ビリーがわざともう一度みんなを見渡した。
「ゴッソ!」
みんなでお互いにコップをぶつけ合った。
「ビリー、悪いけど、更なるお人好しって意味が分からない。」
マリーウェザーがビリーに笑顔を向けた。
「そんなこといいんだって。俺だって意味が分からないけど、頑張ったんだぜ。」
そんなビリーの言葉にみんなで笑った。
「ソンドラさんは、この街に来て長いのですか。」
ルードは、勝手に盛り上がっているシェリルたちに目をやりながら、隣に座っているソンドラに尋ねた。
「そんなに長くはないよ。この街に来て4年かな。」
「その前はどこに?」
ルードの言葉に、ソンドラはちらっと横目でルードを見た。
「気になるかい。おばさんだけど。」
そう言ったソンドラの表情を見て、ルードは、ソンドラがわざと話をはぐらかそうとしていると感じた。
「いえ別に・・・、ただ、せっかく一緒に仕事をした仲間だというのに、気になったらおかしいですかね。」
ルードの言葉に、ソンドラは少しの間ルードの目をみつめた。
「わたしが悪かったよ。」
ソンドラはそう言うと、はしゃいでいるキッドたちに目をやった。
「生まれは神聖王国の首都、ルークスさ。芸妓(げいこ)をしながら旅をして、このシャロムの街に流れ着いた。大したものでもないだろう。あんたは?」
ソンドラはルードに尋ねた。
「私はもともとシャロムの街に生まれました。親父がガヤンの神官だったので。俺も跡を継いでガヤンに。分かり易いでしょう。」
ルードがそう言って笑顔を見せた。
「確かに、分かり易い。」
ソンドラはそう言うと、お互いに軽く笑い合った。
「それにしても、実力行使とは、ガヤンも思い切ったね。」
ソンドラがそう言ってルードを見た。
「そうですね、私もバクウェル神官長がここまでやるつもりだったとは、思っていなかったですね。私もガヤンを勤めて初めてです。」
「しかも相手が首都ルークスでも有名な豪商だ。国王もさぞ驚かれるでしょう。」
「本当ですね。」
「没収する財産も多額に上るでしょう。まさに輝条勲章ものではないかしら。」
「そうか。確かに、その可能性はありますね。まったく頭になかった。」
輝条勲章とは、国王へ大きな貢献をしたガヤンに国王から授与される勲章で、金、銅、青の3等級があった。
確かに、豪商であるボワロから没収する財産の大きさを考えれば、最高位である金輝条勲章が授与される可能性もありえるように思えた。
「そうなったら、確実に昇進ね。バクウェルは神官長から高司祭へ、あんたも神官から神官長へ。」
「はは、まあそうかも知れませんけど。こんな田舎のガヤンじゃ、昇進したって、やる仕事は変わらないですよ。」
そう言うと、二人はまたお互いに軽く笑い合った。
するとソンドラは、何か思い出した様子を見せると、真面目な顔でルードを見た。
「悪い。あんただから聞くんだけどさ。」
「何ですか。」
ソンドラは、一瞬何て言おうか黙って考えると口を開いた。
「今朝、ジェシーおばさんの宿屋でみんなで話し合っただろう。その時に、起こってもいない犯罪人に仕立て上げる冤罪の話があったよね。バクウェル神官長が、我々なら上手くやってみせると言っていた。」
「確かに。」
ルードがそう言うと眉間に皴を寄せた。
「もし、シェリルが分かったと言っていたら、あんたたちは上手くやって見せたのか?」
ソンドラがルードを見た。
ルードはじっと少しの間黙っていたが、とうとう口を開いた。
「上手くやる事は出来ただろう。」
「そんなことをして、ガヤンの中でばれたり、止められたりしないのか。」
「ばれないと思う。上手く言えないが、・・・難しいだろう。」
言い難そうにルードがそう言った。
「そうか。」
ソンドラは1人で納得したように頷いた。
「いや、悪かった。詰まらない話をしてしまった。」
二人は黙ってコップのエールを口に運んだ。
「私も、聞きにくい事を聞いていいですか。」
ルードがソンドラにそう言った。
「何だい。」
すると、ルードは声を潜めてソンドラに尋ねた。
「ソフィさんがマックレに捕らわれていた理由は、何だったのでしょうか。」
するとソンドラは、ルードに向かって首をゆっくりと左右に振った。
「さあ、それは私も知らないし。知らない方が良いと、私の勘が言っている。」
「なるほど。」
ルードが納得したように頷いた。
すると本当に分かったのか怪しむように、ソンドラがルードをじっと見た。
「大丈夫ですよ。それこそ、上手くやって見せます。」
ルードがそう言うと、ソンドラがニッコリと笑った。
ルーが立ち上がると、シェリルの後ろに歩いてきた。
「シェリルさん。」
ルーが後ろからシェリルに声を掛けた。
「交替しよう。」
すると隣に座っていたエバが立ち上がった。
「ありがとう。」
ルーはそう言ってシェリルの隣に座った。
するとすぐにシェリルが口を開いた。
「ありがとう、ルー。手伝ってくれて。すっかり世話になったね。」
「そんな、お礼を言うのは私の方です。教えて貰う事ばかりで。こんな冒険は、私の人生の中でもう2度とないかも。」
「もう2度とこりごりだと思った?」
シェリルは首を傾げてルーを見た。
「そんなことはないけど。正直半々かな。」
ルーはそう言うとてへへという表情をした。
「でも、シェリルさんは凄いな。そう思った。」
「私の何が凄いと思った。」
「みんなの事をいろいろと考えているから。亡くなった領主の奥様のことだけじゃなくて、エイリスさんや、仇だったボワロやマックレの事まで考えていて、でも、自分の事もちゃんと考えていて、そこが凄いなって。」
「そう思ってくれるなら、とっても嬉しいよ。」
シェリルはルーに笑顔を見せた。
「生きるってことは、それだけでも大変なことだよね。ルーだって、自分の人生を考えて見ればそう思わないか?だから、みんな同じ。そこに人として存在していることは、大変なことなんだ。だから、単に見た目や言動でその人を理解したと思うのはとても浅はかなことだ。本当に相手を理解したいのなら、やはり実際に対決して聞いてみるしかない。心の中で、本当はどう考えているのかと。」
「そうか。」
「それから、自分の事をちゃんと考えることは、とても大事な事だ。それに気付いたルーはとっても偉い。」
「へへっ。」
ルーが照れながら嬉しそうな顔をした。
「例えば、ルーが荷物の積み下ろしをしている時に、頭から血を流した怪我人が、お手伝いしますよってルーに声を掛けて来たとしたら、どう思う?まずは、その怪我を治してから来てくださいって思うよね?それに、怪我人にお手伝いして貰っても嬉しくないよね。」
ルーが思わず声を出して笑った。
「そうね。」
「人を助けるという時、相手の事を大切に考えることも大事な事だけど、同じように、自分の事も大切に考えなくてはいけない。相手が助かれば自分はどうなってもいいというのは、同じ対等の人間として行う事ではないし、逆に、相手にとってみればいい迷惑だよ。」
「ビリーみたいにね。」
ルーの言葉に、シェリルは少し驚いた表情をした。でもすぐに笑顔になった。
「はは、良く分かっているね。そういう事。」
「何?何か言った?」
ビリーがわざとらしく声を掛けて来た。
「何も言っていないわよ。」
ルーがうるさい客引きでも追い払うかのように手を振った。
「何だよ、いじわるだなルーは。略して、いじわルーだ。」
ビリーがお返しとばかりに嫌味を言った。
ルーが下らないとでも言うように肩をすくめた。
その様子を見て、シェリルが思わず声を出して笑った。
エバは、ルーが座っていた場所に移動した。
座ると隣にはキッドがいた。
「いいですね。」
キッドがエバに言った。
「そうか。」
エバは横目でキッドを見た。
キッドは空を見上げた。
「星がきれいだし。みんなで焚火を囲んで、何か、収穫祭のようで楽しいですね。」
「なるほど。キッドは農村の生まれなんだな。」
「あっ、話していなかったですね。そうなんですよ。」
エバとキッドはコップに入ったエールを喉に流し込んだ。
「やっぱり、さすがですね。」
「何がだ。」
「50人相手でもあっと言う間で。」
「なるほど。」
エバがそう言うと、焚火に目をやった。
「たった3人でどうやって戦ったのですか。」
「そうだな、」
エバは少しの間黙って考えると、口を開いた。
「敵が多人数で、こちらが少数の場合、少数の方が有利な点は何だと思う。」
エバがそう言ってキッドを見た。
キッドは少しの間考えると言った。
「団結力ですか?」
エバは可笑しそうに笑った。
「いいぞ、ほぼ正解だ。正確には連携の差だ。」
「連携ですか?」
「そうだ。」
分からない顔をしたキッドをエバは見た。
「敵は指揮官が1人、およそ50人の兵士たちは、その1人の指揮官の指示で戦っていたが、指揮官の指示といっても突撃か退却かだ。しかもこちらの人数はたったの3人。そうなると、状況としてはどうなるか。」
キッドが頭を捻った。
「敵に囲まれるのではないですか。」
「なるほど。だが、実際にはそうはならなかった。およそ50人のうち、数人がこちらに走り寄って来たが、残りの連中は横に展開し、特に何もせず戦況を見守っていた。つまり、具体的に誰が何をするのかがあらかじめ決まっていなかったのだろう。兵士余りの状況となって、自分が何をしたら良いのか分からない兵士が、多数発生することになった訳だ。」
「なるほど。」
「それに比べて、こちらはあらかじめ戦術を決定し、3人のそれぞれが何をするのか理解している。状況によって3人のそれぞれが、誰が指示をする訳でもなく、最善と思われる行動を取る。連携は完璧だ。その状況で俺は、何をしたら良いのか分からず、まごまごしている兵士を見つけては、縦横無尽に走り寄って殺害した。俺の感想を言わせて貰えば、今回の戦いはただの殺戮だった。」
「なるほど。」
「いくら50人と数が多くても、連携が取れなければ、1人ぼっちの兵がたくさんいる、ただそれだけのことだ。およそ1人1秒、1分程度で片がついた。」
「そうか。連携か。」
キッドが感心したように頷いた。
「後は、魔法使いが1人いたが、それはマーリンが魔法で無力化した。」
「そうだったのですか。マーリンさんは部屋の隅でもごもごしていましたが、全く分かりませんでした。」
「マーリンは相手に気付かれないように魔法を使う。敵の魔法使いは赤いローブを着て杖を持っていた。一目で魔法使いと分かる奴だったから、マーリンにとっては楽な仕事だっただろう。そもそもマーリンは、俺たちが戦っている部屋の隣の部屋にいたのだから、敵の魔法使いはマーリンに気付くことも出来なかっただろう。」
「そうか。」
キッドが感心したように頷いた。
「やっぱり凄いなあ。」
キッドがそう言って空を見上げた。
「連携が大事な事が分かったか。」
「もう存分に。」
キッドがニヤリと笑った。
エバは満足そうに頷いた。
2人はコップのエールをまた喉に流し込んだ。
「エバさん、また稽古を付けてくださいよ。」
キッドがエバにそう言った。
「いいぞ。明日やるか。」
「ぜひ。」
そう言って、エバとキッドはコップをぶつけた。
するとカツンという子気味良い音がした。
エバたちは、その後も夜が更けるまで、みんなで語り合った。
途中でエルファのおじさんたちが加わったりした。
ロミタスとバクウェルが結託して、シェリルからご褒美を貰っていないと騒ぎ出し、女性の笑顔の重要性をとうとうと語ったりした。
そしてロミタスとバクウェルのために、シェリルが飛びっきりの笑顔で2人の手を握ったりした。
書状の配達料として城から貰った大金を、みんなで山分けにした。
バクウェルが事件の後始末について愚痴を言って、それがしつこかったのでシェリルに怒られた。
酒を呑んで気が大きくなったロミタスとバクウェルが、エルファの森とシャロムの街の未来について語り始めると、エイリスさんはシャロムの街にとって必要な人だとルードが熱く語り始めた。
するとシェリルが、シャロムの街が落ち着いて、エルファと人間が何度か交流を重ねて友好な関係を築く必要があると言い、エイリスが人質という形は良くないので、ちゃんとエルファの大使として迎えるべきだと言った。
シャロムの街の未来の話が終わると、ビリーが自分の未来について話し始めた。
ビリーは事業で成功して、大金持ちになると言った。
するとキッドも、絶対に成功してやると言った。
アレンティーの踊りが素敵という話になって、アレンティーが恥ずかしそうに南国ザムーラ島で覚えた踊りを披露した。
その後みんなで変な踊りを踊ったりもした。
そして眠たくなった者から、焚火を囲んで毛布の上にごろんと横になった。
真っ暗な空には、色とりどりの七つの月と、たくさんの星が広がっていた。
ソンドラは、ルードに用事があるから先に帰ると伝えると、エルファの駐留地を1人離れて、農道をシャロムの街に向かって歩いていた。
今日は7つの月の全てが顔を出していて、月明かりが明るかったので、道に迷う心配も無かった。
虫の元気な鳴き声が心地良かった。
すると、通りの向こうから人が歩いて来るのが分かった。
ソンドラはさっと道端の茂みの中に身を隠した。
こんな時間帯に出歩いている人物は、普通ではない可能性が高い。
すると、農道を歩いて来た人物が声を掛けた。
「ソンドラ、ソンドラ」
ソンドラは安心すると茂みから立ち上がった。
「ミシェル。」
ソンドラはミシェルに近付いた。
ミシェルと呼ばれたその男は、目尻が少し上がった特徴的な眼差しをしていて、銀髪で雪のような白い肌で端正な顔つきをしていた。
エバが娼館を訪れた時、玄関で鉢合わせとなった男だった。
「心配になってな。」
「ご安心ください。ソフィは無事です。ご報告に戻る途中でした。」
「ありがとう。」
ミシェルとソンドラは横に並んでシャロムの街に向かって歩き始めた。
「ソフィは、明日この街を離れる見込みです。」
「そうか、では我々も、この街を後にすることとしよう。」
2人は黙って横に並んで歩いた。
「す、」
「ソ、」
同時に2人は何か話しをしようとしたので、お互いに話ができずに詰まってしまった。
二人は顔を見合わせた。
「どうぞ。」
ソンドラがミシェルに話を促した。
「すまないな、ソフィの面倒を見させてしまって。もう、ソフィに仕える理由もないというのに。」
「小さい頃から見て来ましたから、情が移ってしまって。誰かがやるというのであれば、私にお任せください。」
「ありがとう。それで・・・、そっちは?何を言い掛けていたのかな。」
ミシェルがソンドラに尋ねた。
「ええ。ソフィは、自由に生きると言っていました。ですから、ミシェルの思い通りになるとは限りません。」
ソンドラの言葉を聞いてミシェルは前を向いた。
「分かっているさ。もともと一人でやるつもりだったのだ。それにしても、エバという男。相当な剣の使い手だな。」
「確かに、あの水準の戦士は、神聖王国には存在しないかと。」
「利用させてもらおう。」
ミシェルがそう言うとニヤッと笑みを見せた。
「無理ですね。」
ソンドラがあまりにそっけなくそう言うので、ミシェルはガクッと態勢を崩した。。
「そんなに無理なのか。」
「無理ですね。あの連中は、人の言う事を聞く連中ではありませんよ。自分がやりたい事をやる連中です。だから言っているのです。ソフィは自由に生きるでしょうって。」
ソンドラの言葉に、ミシェルは頭を掻いた。
「なるほどな。まあ、嬉しい限りだ。」
そう言うと、2人は並んでシャロムの街へ続く道を歩いて行った。
シェリルは、身体の冷えに気付いて目を覚ました。
まだ夜明けには早く、薄暗かった。
シェリルは体を温めるために地面に敷かれている毛布にくるまると、体温が上がるのを待った。
周りを見渡すと、近くにマリーウェザーとアレンティーが毛布にくるまって眠っていた。
体の温まったシェリルは毛布から抜け出した。
昨日囲んでいた焚火には、既に新しい薪がくべられ、炎が勢いよく踊っていた。
シェリルは黙って焚火の炎にあたっていたが、身支度を整えようと背負い袋から小袋を取り出すと、手に持って小川に向かった。
小川には、早起きのエルファが何人も来ていた。
シェリルが小川に近付くと、エルファたちは、小さな桶で小川から水を汲むと、その水で顔を洗ったり体をふいたりしていた。
小川の水に直に手を入れて、顔を洗っているエルファはいなかった。
小川の水が汚れないように、みんな水を綺麗に使っているのだ。
シェリルは、たまたま近くに置いてあった小さな桶を手に取ると、小川から水を汲んだ。
そして小袋から亜麻でできたリネンの布を取り出すと、桶の水に浸した。
小川の水はとても冷たかった。
布を軽く絞ると、優しく顔を拭いた。
シェリルは服の首元を緩めて少し肩を出すと、新しく絞った布で首元から胸元と肩を拭いた。
次にシェリルは小袋からブラシを取り出し、寝ている間に絡まった髪をとかし始めた。
毛先の方から優しくとかしていって、最後に毛の根本から汚れを掻きだすようにブラシをあてた。
髪をとかし終わると、ブラシやリネンの布を小袋にしまった。
残った桶の水を流して、地面に吸わせた。
シェリルは立ち上がった。
だんだんと薄暗さがやわらいで来た。
そろそろ日の出が近いようだ。
シェリルは小川に沿って歩き始めた。
ひんやりとした空気が水で洗った肌に触れると心地よかった。
ふと、ヤドゥイカ砦の方に目をやると、丘の途中で2人の人影が見えた。
2人は剣と盾を持っていて、同じように揃って剣を振り、剣で突き、盾で打ち、2人の動きが揃っていて、爽やかで綺麗だった。
エバとキッドだな。
シェリルは思わず頬を緩めた。
「シェリルさん。」
後ろからシェリルを呼ぶ声がした。
シェリルは振り返った。
「ビリー。」
そこにビリーが立っていた。
「おはよう。」
シェリルがそう声を掛けた。
でも、ビリーは黙っていた。
ビリーはじっとシェリルを見た。
シェリルもそんなビリーを見つめた。
「シェリルさん、俺、分かりましたよ。俺がシェリルさんに告白する意味。」
「そう。」
ビリーは思い出していた。
マックレのいる城で喉を斬り裂かれ、シェリルの胸に抱かれたその時の感触を。
俺は、シェリルさんを助けたい、守りたい、大切にしたい、そう思っている。
でも、それは告白しないとできないことではない。
なら、告白する意味は何なのか。
ビリーは、シェリルの胸に抱かれたことで、その意味が分かった。
「俺は、シェリルさんを抱きしめたい。エバさんには絶対に渡したくない。」
ビリーは自分の胸に手を当てた。
「あなたを独占したいんです。あなたを抱きしめる権利は、俺だけのものにしたい。他の誰にも触れて欲しくない。」
ビリーはシェリルに向かって1歩踏み出した。
「あなたを抱きしめる権利を独占すること、それが、俺の答えです。」
ビリーは真剣な目でシェリルを見た。
シェリルはそんなビリーをじっと見た。
そしてフッと笑みを浮かべた。
「ご名答。見事だ。・・・ビリー、私は、」
するとシェリルの言葉を遮ってビリーは言った。
「シェリルさん、俺、諦めますから。」
言葉を遮られたシェリルは、一瞬戸惑った。
ビリーはゆっくりとシェリルに向かって歩き始めた。
「ビリー。」
シェリルはビリーが何を考えているのか分からずに不安な気持ちになった。
するとビリーは歩きながら笑顔を見せた。
「安心してください、何もしませんよ。」
そう言いながらも、ビリーは確実にシェリルに歩み寄った。
「ビリー、言っている事とやっている事が、違ってしまっているぞ。」
シェリルがそう非難した。
だがシェリルの非難にもかかわらず、ビリーは歩みを止めることは無かった。
そしてとうとう、ビリーはシェリルの目の前に来た。
シェリルはビリーを見上げた。
「何もしないって、言っているじゃないですか。」
ビリーはそう言ってシェリルを見下ろした。
するとビリーは、いきなりシェリルをぎゅっと抱きしめた。
ビリーの腕に込められた力の強さが、ビリーのシェリルに対する思いの強さを現していた。
「嘘つき。」
シェリルがビリーの腕の中でそう言った。
「シェリルさんには、言葉ではかなわないから。」
ビリーは、シェリルの身体の温かな体温と柔らかな感触を感じていた。
この瞬間が永遠に続いて欲しい。
ビリーは目を閉じた。
シェリルさんに振られてしまうことは分かっていた。
だとしても、万が一の可能性に賭けてみたかった。
ビリーには夢があった。
商売で成功して、大金持ちになるのだ。
シェリルさんが側にいてくれれば、絶対に成功できる気がした。
シェリルさん、ずっと、俺の側にいてください。
ビリーは強く願った。
だが、終わりは不意に訪れた。
「ビリー、もういいだろう。離してくれ。」
ビリーは腕の中のシェリルを見た。

シェリルはビリーを見上げていた。
「私はお前の女になるつもりはない。可能性は、ゼロだ。」
シェリルの言葉が、ビリーの心を打ちのめした。
「それから、これは老婆心で言っておくが、女性が男性を断るのに理由などない。なぜ断ったのかと理由を聞かれても答えることはできないから、聞かないでくれ。」
ビリーの腕に込められた力が弱くなった。
シェリルはビリーの胸を両腕で押しやると、ビリーから離れた。
「永遠に、よい親友でいよう。」
シェリルはビリーに笑顔を向けた。
そしてビリーに背を向けると、エバたちのいる丘の方へ歩き出した。
ビリーもシェリルに背を向けると、とぼとぼと歩き始めた。
涙がこぼれて来たので上を向いた。
「俺・・・、頑張ったんだけどなあ。・・・だめ、だったなあ。」
心が破れてしまって、苦しかった。
思わず右腕で顔を覆った。
ビリーは立ち止まって、顔を上に向けたまま、静かに泣いた。
歩き出したシェリルも、とぼとぼとした様子で丘を登り始めた。
だが、前を向くことが出来ずに目を伏せてしまった。
少女な訳でもあるまいし、慣れていたつもりだった。
嫌な女になる覚悟もしていた。
それでも、ビリーの期待に応えてあげられなかったことが、ビリーの心を傷つけてしまったことが、シェリルの心を打ちのめした。
シェリルは覚悟を決めると丘を見上げた。
すると、ちょうど昇って来た朝陽の光が、丘の上で剣を振るエバとキッドを明るく照らした。
シェリルには、光を浴びた2人の姿が輝いて見えた。
エバとキッドは、勾配が緩やかな場所を見つけると、朝陽を浴びながら、基本稽古を行っていた。
するとシェリルが様子を見に丘を登って来て、少し後にソフィもやって来た。
最後にはエルファの軍隊のおじさんも何人か丘を登って来て、一緒に稽古を行った。
エルファ軍は腰に鉈を提げていた。
森の中で茂みを払ったり、木の枝を切断したりにするのには、剣よりも鉈の方が断然使い易い。
だから、エルファの軍隊は剣ではなく、腰に鉈を提げているのだ。
エバとキッドは、エルファ軍のおじさんから、鉈を使って戦う方法を教えて貰った。
剣よりも重さに偏りがある鉈を自在に扱うには、独特の手首の返しが必要だとキッドは分かった。
それが終わると、みんなでレスリングを行った。
エバもキッドもエルファのおじさんたちも、汗まみれ、土まみれになった。
その後みんなで小川の水を桶に汲んで頭から被った。
熱くなった筋肉に、小川の清冽な水が心地良かった。
エバたちは、エルファたちと一緒に軽い朝食を取った。
マリーウェザーとアレンティーとルーが、エルファの調理人を手伝って、一緒に朝食の準備をした。
朝食はキャッサバの粉で焼いたパンケーキと、豚のソーセージとアーモンドミルクだ。
体を動かした男たちは、パンケーキとソーセージをパクパクと胃袋に放り込んだ。
朝食が終わると、みんなで一緒に後片付けをして、出発のための荷物をまとめた。
エルファ軍は天幕を畳んで、下に敷いていた絨毯を丸め、食器や道具を布でぐるぐる巻きにしてまとめた。
まとめた荷物を小さな荷車に載せると、紐で縛り付けて固定した。
エルファ軍は森に、キッドやバクウェルはシャロムの街に、エバたちは神聖王国を目指し次の街に向かって出発する。
エルファ軍は、順番にエルファの森を目指して駐留地を出発していった。
荷物を積んだ荷車を、体の大きなヤギが引っ張て歩いて行った。
エバたちは、最後に残ったロミタスとエイリスを見送るため、森への入り口に集まっていた。
ロミタスとエイリスがいて、エイリスの隣にソフィがいて、それを囲むようにエバたちは立っていた。
「みんな、本当に、ありがとう。」
ロミタスがそう声を掛けた。
みんなは笑顔で応えた。
すると並んで立っていたエイリスがソフィに言った。
「ソフィ、元気でいてね。」
「エイリスもね。」
二人は顔を合わせると微笑んだ。
「またきっと会えるよね。」
ソフィがエイリスに言った。
「会えるわ。その気になればいつでも。」
ロミタスが1人ずつ握手をして回って、また最後にシェリルと手を握った。
「必ず顔を見せに、エルファの森に来るんだぞ。」
「分かった、そうするよ。」
ロミタスは振り返ると、エイリスを見た。
「そろそろ行こうか。」
エイリスはロミタスに頷いて見せた。
「じゃあ、行くね。」
「うん。」
エイリスがそう言って、ロミタスと並んで歩き始めた。
エイリスは途中で一度振り向くと、ソフィに手を振った。
そして前に向き直ると、ロミタスと歩いて行った。
「お別れだな。」
いつの間にか隣に来ていたエバが、ソフィにそう言った。
ソフィが小さく頷いた。
するとソフィの心に、エイリスとの別れが、急に現実の事として心の中を覆い始めた。
突然、何かを思い出したようにソフィが呟いた。
「大事な事を言い忘れた。」
ソフィは走った。
「エイリス!」
ソフィの声にエイリスが振り向いた。
走って来たソフィがエイリスの前で止まった。
「どうしたの?」
エイリスが少しニコッとしてソフィを見た。
「言い忘れていた事があった。」
「何?」
「4年間、一緒に居てくれてありがとう。お礼を言っていなかったから。」
ソフィの言葉に、エイリスも思い出したような顔をした。
「私の方こそありがとう。ソフィのおかげで、何とか生き延びることができた。ありがとう。」
ソフィは頷くと、エイリスに手を差し出した。
「私、忘れない。エイリスと過ごした4年間を、絶対に忘れないから。」
「私も忘れないわ。」
エイリスはソフィの手を握った。
二人はぎゅっと握った手に力を込めた。
するとソフィは、エイリスの顔をじっと見た。
「ソフィ。」
エイリスは、目を細めてソフィを見た。
エイリスをじっと見ていたソフィの目から、涙が溢れた。
「やっぱり、いやだよう。・・・本当はエイリスと別れたくないよう。」
ソフィは、ぽろぽろと流れ出る涙を指で拭いながら、わんわんと泣き始めた。
エイリスはハッとしてソフィを抱きしめた。
「私も、・・・ソフィと離れたくないよう。」
エイリスもそう言うと、二人は立ったままわんわんと泣いた。
決して楽な生活ではなかった4年間だった。
何度も思い出したい思い出がある訳でもなかった。
でも、その4年間を理解し共感し合えるのは、この世界でたった2人だけだった。
感情が現実の別れを受け入れるまで、涙が二人の心を穏やかにしてくれるまで、二人は思いっきり泣いた。
そして2人がだんだんと落ち着きを取り戻して、しゃくり上げながらエイリスが言った。
「そろそろ、行くね。」
「うん。」
「絶対にまた会いましょう。」
「うん。」
エイリスがソフィに背を向けると、ロミタスのところに歩いて行った。
「行こうか。」
ロミタスがエイリスを見た。
「はい、お父様。」
ロミタスとエイリスはまた歩き始めた。
ソフィも背を向けると、エバたちのもとに帰って来た。
「いいのか、手を振ってやらなくて。」
エバが帰って来たソフィにそう言った。
「えっ。」
ソフィが振り返ると、エイリスが大きく手を振りながら、歩いて行くのが見えた。
ソフィもエイリスに大きく手を振った。
やがてロミタスとエイリスは、森の中に消えていった。
「さあ、私たちも行こうか。」
シェリルが声を掛けると、エバたちも荷物を背に担ぐと歩き始めた。
エバたちは、駐留地の入り口、馬を止めて来た小さな広場に戻って来た。
キッド、ルー、ビリーが出発のために馬に飼葉を食べさせたり、小川で水を飲ませたりした。
「シェリルさん、準備出来ました。」
キッドが準備の終わりを伝えた。
「それでは行こうか。」
シェリルが皆に声を掛けた。
エバたちは馬に跨り、荷車に乗り込むと進み始めた。
そしてとうとう、シャロムの街と次の街に繋がる分かれ道まで辿り着いた。
キッドが手を上げてみんなを止めた。
荷車の御者台に乗っていたエバとシェリルは地面に下り立った。
マーリン兄妹も幌を開けて荷車から下りて来た。
下り立ったシェリルにキッドとビリーが馬の向きを変えて近付いて来た。
「キッド、ルー、ビリーお疲れ様。道案内はここまでで大丈夫だ。」
シェリルが馬に跨ったキッドたちを見上げた。
「分かりました。」
キッドと一緒の馬に乗っていたルーが、飛び降りてシェリルの元に来た。
「シェリルさんは、ずっと旅を続けるのですか。」
ルーがシェリルに尋ねた。
「そうだね。1つのところに長く留まれなくてね。」
「そうなんだ。」
「このシャロムの街ともお別れだ。」
ルーが少し寂しい表情をした。
「正直、寂しいな。」
「そうだね。でも、首都ルークスに行った帰りに、必ず立ち寄ることにするから。」
「本当。」
ルーの顔が明るくなった。
「絶対に立ち寄るから、安心して。約束する。」
マリーウェザーがルーにそう言った。
「分かった。待ってるね。」
ルーがそう言ってニコッとした。
すると、いつの間に用意していたのかシェリルが小袋をルーに渡した。
「道案内の料金だ。店のマスターがうるさいだろうからな。」
ルーは小袋の中を確認した。
「毎度ありがとうございます。」
ルーがシェリルに笑顔を見せると、シェリルもルーにニコッとした。
「元気でね。」
ルーがマリーウェザーとアレンティーに言った。
「ルーもね。」
マリーウェザーが笑顔を向けた。
「じいさん岩からの景色、綺麗だったよ。」
アレンティーもそう言ってニコッとした。
「達者でな。」
バクウェルがシェリルに言った。
その後ろからルードもシェリルに向かって頷いて見せた。
「バクウェル、悪いな。後始末を任せてしまって。」
「なあに、俺の仕事だからな、ぼちぼちやるさ。」
バクウェルが両手の平を見せながら肩をすくめた。
「それから、」
シェリルはベルトに付けた小袋から鉄製の鍵を取り出した。
「テッドの牢の鍵だ。もう開けてやってもいいだろう。」
シェリルはバクウェルに鍵を渡した。
バクウェルは鍵を受け取るとニヤリと笑った。
「忘れるところだった。」
シェリルも笑顔で頷いて見せた。
「エバさん、また俺に稽古を付けてください。」
キッドがエバに声を掛けた。
エバはニヤリとした笑顔をキッドに見せた。
「じゃあ、みんな、ここで別れよう。」
シェリルがそう言うと、みんなはシェリルに向かって頷いた。
「ビリー。」
シェリルが突然、馬に乗っているビリーに声を掛けた。
するとビリーは、シェリルに笑顔を向けた。
「シェリルさん、この街に寄ったら、また一杯やりましょう。親友として。」
ビリーはそう言うと、カウボーイ・ハットに指を当てると左目をつむりウィンクして見せた。
「ああ、そうさせて貰う。」
シェリルはビリーに笑顔を向けた。
「それじゃあ。また会おう。」
シェリルはそう言って、キッドたちに手を振ると、次の街に続く道を歩き始めた。
そのシェリルの後に、マーリン兄妹が続いた。
「俺たちも行こう。」
キッドがみんなにそう声を掛けると、キッドたちやバクウェルたちも馬の向きを変え、シャロムの街の方向に進み始めた。
すると、その場に、ソフィと1頭の馬だけが取り残された。
この馬は、ソフィとエイリスがマックレの城から脱出する時に、一緒に連れ出した馬だ。
やっぱり、こうなるよね。ソフィはそう思った。
エイリスが居なくなって、ソフィは1人ぼっちになってしまった。
想定していたことだったが、やっぱり心が寂しかった。
これからどうしようか。ソフィはまつ毛の長い馬の瞳を見つめながら途方に暮れた。
「乗らないのか。」
すると突然、ソフィの背後からエバの声がした。
ソフィが振り返ると、エバが何となしに立っていた。
するとエバは、何も言わずに黙ってソフィの馬に跨った。
ソフィが呆気に取られて見ていると、手綱を握ったエバがソフィに手を差し出した。
「一緒に来るか。」
エバはニヤリと笑った。
「うん。」
ソフィはエバの手を握った。
エバは一気にソフィを馬の上に引き上げると、自分の前に座らせた。
そして軽く馬の横腹に蹴りを入れると、馬はシェリルたちを追い掛けて歩き始めた。
「凄く長く感じたけれど、終わってしまえばあっと言う間の3日間。何だか、今思い出してみると、夢みたいだったな。」
御者台に座っているルーが、隣を馬で進んでいるキッドにそう声を掛けた。
「良い例えだな。確かにこの冒険は、一時の夢のようなものだ。そして、俺たちの現実が、これから始まるのさ。」
キッドたちは、シャロムの街に続く道を進んで行った。
「太陽が眩しいぜ、いい天気だなあ。」
ビリーが、晴れ渡った青空を、眩しそうに見上げた。
マーリン「どうでもいい話ですが、本日はお客様をお呼びしています。」
シェリル「へえ、そうなんだ。」
エバ「誰だ。」
マーリン「ボワロ将軍です。」
エバ「ど阿保おおおお!の将軍か、大御所だな。」
シェリル「よく来る気になったな。」
マーリン「シェリルが居ると言ったらその気になったみたいで。それではどうぞ。」
シェリル・エバ「・・・。」
ボワロ「失礼させて貰うぞ。」
シェリル「本物だ。」
ボワロ「失礼だな。本物だ。ただ、死んでいるだけだ。」
エバ「言っている事がおかしいだろ。」
ボワロ「何がおかしい。現実こそが真実だ。すぐに対応して見せたまえ。」
シェリル「この年代のおやじは相手するのが面倒くさいな。」
マーリン「せっかくですから、いろいろと話を伺ってみましょう。」
シェリル「シャロムの街の1件ではどうも。」
ボワロ「うむ。」
シェリル「で、結局何で戦争したかった訳?」
ボワロ「ほう。そこは分からなかったか。実は、戦争に必要な人と武器は俺が押さえていたのだ。戦争になりさえすれば、お前たちでは想像もできない程度の儲けがあったはずだ。」
シェリル「そういう事か。」
ボワロ「準備に3年かかっている。一大事業だったのだ。それが、まさか。」
エバ「何だ、俺の方を見て。俺が何かしたか?」
ボワロ「よくそんな口が叩けるな。お前みたいな、存在自体がイカサマみたいな奴が仕込まれているとは、想像もつかんかったわ。完全に、詐欺の範疇だ。」
エバ「言いたい放題だな。」
シェリル「お前が死んじゃって、商売の方はどうなるんだ?」
ボワロ「別にどうなっても構わんさ。ただ、財産は親戚筋が取り合いになるんだろうな。」
シェリル「跡継ぎはいないのか。」
ボワロ「いない。俺は俺のやりたいように生きる。だから、逆にいつ死ぬのか分からない。だから跡継ぎはいらない。俺が死んだら、きれいさっぱり無に帰れば良いのだ。」
エバ「なるほど。」
マーリン「潔いですね。」
シェリル「そういうところは好きだよ。」
ボワロ「ははは、嬉しいな、お前に言われると。ところで、シェリル。お前は何をしているのだ。」
シェリル「私?、・・・旅をしている。」
ボワロ「世直しの旅か?詰まらんことをしているのだな。」
シェリル「違うよ。私もある意味お前と同じさ。私も、私のやりたいように生きるんだ。だから旅をしている。お前の事が許せなくなったから、対決することにした。」
ボワロ「うんうん、そうかそうか。」
エバ「ところで、死んだらどうなるんだ。」
ボワロ「なんだ、知りたいか。」
エバ「ああ、死んだことがないからな。」
ボワロ「教えてやる訳ないだろうが。」
エバ「面倒くさいおやじだな。」
ボワロ「まあそうだな、死ぬときというのは以外に穏やかな感覚があるな。」
マーリン「そうなのですか。」
ボワロ「ああ、死ぬまで痛みに苦しむということはない。痛みは次第に治まって、穏やかな感覚に包まれる。」
エバ「そうか。」
マーリン「それは単に、脳が徐々に機能を停止していくからでは。」
ボワロ「お前たち、良く覚えておけよ、死後の世界では俺の方が先んじているのだからな。お前たちが死んで死後の世界に来る頃には、包囲網を整えて待っていてやるからな。今度こそ、シェリルは俺がいただく。」
エバ「まったく、死んでも性懲りないおやじだな。」
マーリン「話を聞かないおやじですね。」
シェリル「ボワロ。」
ボワロ「何だ。」
シェリル「お前、今回の件、反省しているのだろうな。」
ボワロ「反省。」
シェリル「死後の世界で何をやっているのか知らないが、お前は頭もいいし、もう自分ひとりぼっちじゃないのだから、人を使い捨てにするような真似はするなよ。もし、そんな事を死後の世界でもするようなら、もう2度とお前の話は聞いてあげないからな。」
ボワロ「・・・。」
シェリル「愚痴なら私が聞いてやるから、我慢するんだぞ。」
ボワロ「・・・分かった。そこは胆に銘じておく。(やっぱり、シェリルを妻に欲しいいなあ。)」
シェリル「良し。じゃあ、どうでもいい話はお開きにして、今回も呑みに行っちゃう?」
ボワロ「それなら、俺がいい店を知っているから、連れて行ってやろう。」
シェリル・エバ・マーリン「おー。」
ボワロ「俺のおごりだ。任せておけ。」
シェリル・エバ・マーリン「おー!」
マーリン「高級な香りがしますね。」
シェリル「どんな店なんだろう。」
ボワロ「俺が接待で使っていた店だ。本来は深夜帯までの営業なのだが、最近は時短で、閉まるのが早くてな。」
マーリン「でも、まだ日が高いですから。閉まるまで十分時間がありますよ。」
エバ「3密は大丈夫か。」
ボワロ「十分に距離を空けて、カウンターで横並びだ。」
エバ「そうか。」
シェリル「私はボックスよりもカウンターの方が好きかな。」
ボワロ「それなら好都合。」
マーリン「エールとワインと両方あるのかな。」
ボワロ「勿論。透明な氷の入った18年物のウィスキー、米をみがき抜いたすっきり辛口の日本酒もあるぞ。冷えた奴な。」
シェリル「ぶ厚いお肉とか出ちゃうのかな?」
ボワロ「出ちゃうぞ。目の前の鉄板でジュージュー焼いちゃうぞ。」
シェリル「嬉しい。」
エバ「お前、これが狙いだったな。」
ボワロ「ははは、いいだろうが。野郎ども、出陣じゃあ!」
シェリル・エバ・マーリン「おー!」
シェリル・エバ・マーリン「将軍!将軍!将軍!将軍!」
ボワロ「はははは!」
4人が徐々にフェードアウトしていく中、何か思い出したようにエバが呟いた。
エバ「ボワロの奴、金持ってねえんじゃねえの?」
シェロムの街を出たエバたち一行は、神聖王国に向かってさらに街道を北に向かっていた。
広々とした丘が広がる風景は一変し、今は、山と山の間に挟まれた平地を進んでいた。
大地の岩盤が強大な力で圧縮され、隆起し、高い山脈を形作り、その山脈と山脈の谷間の平地に造られた細い街道を、小さな人間たちが列をなして進んでいく。
街道の両側はアカマツの森に覆われていて、その森が山脈の中腹まで続くと、その森の上から岩の頭が顔を出していた。
「凄い。風景が変わった。ね、シェリル姉さん。」
マリーウェザーが、道の両側に壁のようにそびえる山々を見上げながらそう呟いた。
「本当だ。迫力があるね。山があるというか、いきなり壁が立っているみたいだ。」
山々を眺めながら隣を歩いていたシェリルは、そう言ってマリーウェザーと顔を見合わせた。

「生えている木々も独特ね、幹の色が赤色をした木がたくさん生えている。」
シェリルのすぐ後ろを歩いていたアレンティーが言った。
「アカマツだよ。寒いところでも生きていけるように、葉っぱが先の尖った針のような形をしているんだよ。」
一行の一番後ろを歩いていたマーリンが後ろから声を掛けた。
マーリンの言葉を聞いてアレンティーが森の木々に目を凝らした。
「本当ね。葉っぱが針のようにとげとげしている。」
アレンティーが感心したように頷いた。
「あんなに針のように細くて、太陽の光をたくさん浴びられるのかしら。」
マリーウェザーが頭を傾げた。
「1年を通して寒い季節が長く続くから、薄くて広い葉っぱでは、寒さに耐えられないんだよ。」
「なるほどね。」
マーリンの説明に、マリーウェザーが納得したように頷いた。
するとアレンティーの後ろを歩いていたエバが言った。
「そうか、薄い葉っぱをくるくると丸めて、先を尖らせると針のようになる。そんな感じか。」
エバの言葉にみんな分からない顔になった。
エバの横を歩いているソフィも首を傾げた。
ソフィは馬を曳きながら歩いていた。
「何を言っているのか意味が分からんが。」
マーリンが後ろからそう言った。
「ほら、寒いと思わず身を縮めるだろ。葉っぱも同じなんだな、てね。」
「ああ。」
ソフィが分かった顔で頷いた。
「なるほど。」
「そういうことか。」
みんなが分かった顔で頷いた。
「なんか発想が可愛い。」
ソフィがエバに笑顔を向けた。
「ん?何か俺、気持ち悪かったか。」
ソフィが首を横に振った。
「別に気持ち悪くはないよ。」
するとマーリンがまた後ろからエバに声を掛けた。
「まあでも、正直、そんな可愛い話でもないよ。植物の世界も。」
「へえ、そうなのか?」
シェリルがそう言って、マーリンの方に振り向いた。
マーリンは頷くと話を続けた。
「何も語ることなく黙っている植物だけど、太陽の光や大地の栄養を周りの植物と激しく奪い合っている。その奪い合いに負けた植物は、太陽の光を遮られ、大地からの栄養も十分に確保できず大きく育つことはできなくなる。例えば・・・。」
マーリンは周囲に広がるアカマツの森に目をやった。
「この周辺の森にはアカマツばかりが目立つけど、これはつまり、アカマツがこの周辺を制圧していて、他の植物が大きく育つことができないということさ。」
「わお。この辺り一帯がアカマツ帝国という訳ね。」
シェリルが感心したように頷いた。
「帝国かどうかは分からなけどね。まあ、シェリルの好きな弱肉強食だよ。」
するとマリーウェザーがマーリンの顔を見て言った。
「お兄様、目が恐いです。」
「妹よ、それは生まれつきだ。」
マーリンが無表情で答えた。
するとシェリルが両手を上げた。
「ちょっと待った、勝手に私イコール弱肉強食と断定しないでよ。」
「違うのか?」
マーリンが言った。
「別にいいじゃねえか、イコール私で。」
エバが言った。
「なっ!失礼だな。大体、私が弱肉強食でああだこうだではないだろうが。私に関係なくこの世界が弱肉強食なのだろう?どうだ?」
するとシェリルの言葉にエバが分からない顔をした。
「そうなのか?でもお前、9歳から弱肉強食じゃなかったっけ。」
シェリルが目を細めてエバを見た。
「エバ、これまでお前にそんな説明をした覚えはないが。何がどうなってそんな記憶が生成された。一体お前の頭の中で何が起こったというのかな。」
エバは目を瞑ると肩をすくめて見せた。
「ふっ、どうだかな。俺には分からないが、お前なら分かるんじゃないか。」
エバの態度に、シェリルが呆れたように両手の平を見せた。
「まあ、確かにな。・・・お前が適当人間だ、ということはよーく理解しているよ。」
「しまった、とうとうばれちまったか。」
エバがニヤリと笑みを浮かべた。
「とっくにばれてるよ!ばれて数年は経ってるわ!」
シェリルがエバのほっぺたを摘まむとぐーと引っ張った。
エバがマリーウェザーとアレンティーにその顔を向けた。
「気を付けろ。いいかげんに生きていると、シェリルにつねられるぞ。」
エバの顔を見て、マリーウェザーとアレンティーが可笑しそうに笑った。
エバたちが進んでいく先に、朱色のとんがり屋根が特徴的な建物が見えて来た。
「おっ、街が見えて来たな。」
エバが言った。
「今日一泊する街ね。屋根が赤色をしていて可愛い。」
マリーウェザーがそう言った。
「本当だ。小さくて可愛い街だね。」
シェリルがそう言ってマリーウェザーを見た。
先に見えている街は、いくつかの建物が寄り添うように建っていて、こじんまりとした印象だった。
「この赤い屋根の街並みは、神聖王国の特徴的な街並みの一つね。」
ソフィがマリーウェザーに説明した。
するとソフィの言葉にアレンティーが分かったように口を開いた。
「赤色の・・・瓦(かわら)かな。」
ソフィが驚いた顔をアレンティーに向けた。
「そう。良く分かったわね。瓦って。」
「へえ、そうなんだ。あれっ、何て街だっけ?」
マリーウェザーが首を傾げた。
「ロボルの街ね。さっき旅の人から聞いたでしょう。」
ソフィが笑顔でそう言った。
「そうだそうだ。忘れちゃってたよ。」
マリーウェザーがてへっという顔をした。
エバたちが街に近付くと、街を囲んでいる土壁が見えてきた。
そして、土壁の外にも、藁で屋根を葺(ふ)いた家々が建っていた。
街の壁の中に住居を持てなかった人々の、住居や商店だ。
その中には、格安で一晩の寝床を提供する宿屋も見えた。
そしてマリーウェザーは見た。
街の壁に寄り添うように座り込む人々、家々の隙間で座り込んでいる人々の姿を。
「街の中にも入れず、自分の住居を持つことも出来ず、今日食べるものさえ困窮している乞食の人々だ。」
シェリルがマリーウェザーの隣で一緒に歩きながらそう言った。
乞食の中には子供の姿も見えた。
生まれた時から貧しく、いつもお腹を空かせている。
街の中には入れないので、街の外をうろうろしたり、街から街へ移動して何か食べ物がないか、何か仕事がないかと探しながらうろうろしている。
そのような乞食の人々を救済するため、街のサリカ信者の人たちが毎日食べ物を配って歩いている。
サリカというのは豊穣の神であり、友愛の神でもある。
そのサリカ神を信仰する信者は、貧しい人々を救済するために街で寄付を集めて、その寄付で食べ物を用意して乞食の人々に配り歩いている。
だが、街の中にも乞食の人々はいるし、街の外の乞食全員に行き渡るほど食べ物がある訳ではない。
運よく一時的に仕事をもらって働いたりすることもある。
例えば、道路の整備であるとか、街の壁を修復するとか。
そういう大きな工事の時にはたくさんの人手が必要となる。
乞食は給料がとても安く済むので、体が動ける乞食は強制的に連れていかれ、そして働かされた。
そして工事が終わればまた乞食に戻った。
奴隷のように固いパンと水でこき使われ、必要がなくなれば捨てられるだけだった。
それに乞食の人々は字の読み書きができないし、簡単な算数もできない、それが普通だった。
教えてくれる人がいないし、親も教えられないのだ。
だから、まともな仕事に就くことなどできないし、生活していくのに十分に金を稼ぐこともできなかった。
ゆえに、マリーウェザーは、自分にはどうしようもできない人々なのだと。
そう思っていた。
一時的に食べ物を恵んだからといって、それが何になるというのだろう。
数日、死ぬまでの日数が伸びるだけなのだ。
「私たちの生きる世界は、このような貧しい人々が人知れず静かに死んでいく、その屍(しかばね)の上に成り立っている。忘れてはいけないことだ。」
シェリルはそう言って、マリーウェザーの肩に手を置いた。
マリーウェザーは頷いた。
自分にはどうすることもできない人たち。
マリーウェザーはあえてその人々から目を逸らした。
エバたちは街の入り口の門に到着すると、徴税人に道路税と町に入るための料金を支払った。
「旅をしているとお金が取られることばかりね。」
マリーウェザーが愚痴を言った。
「ははは、まあね。でも、街を通過するだけでも通行料を取られるから、せっかくならまともな食事とベッドにありつこうよ。」
シェリルがマリーウェザーをなだめるようにそう言った。
「そうね。それに、買い物もしたいし。」
エバたちは入場門をくぐると、ロボルの街の中に足を踏み入れた。
メイン通りは馬車が3台並べば一杯となってしまう程度の横幅しかなかった。
小さな通りであるが故に、行き交う人々や馬や馬車がひしめくように進んでいく。
通りに面した商店から行き交う人々に向かって客寄せの声が掛かる。
その様子はとても活気があった。
「靴下欲しかったんでしょ。」
アレンティーがマリーウェザーに尋ねた。
「そう、もうすぐ穴が空きそうなの。」
マリーウェザーが、背負っている鞄に吊り下げられてブラブラしている靴下を指差した。
確かに、かかとの生地が薄くなってしまって、透けて見えそうだった。
この時代、旅といえば徒歩での移動が普通だったから、尖った石や陶器の破片など危険なものから足を守ったり、汗を吸収して足を清潔に保ってくれる靴と靴下は、旅人にとってとても大切な品物だ。
マリーウェザーも、丈夫な牛革を縫い合わせて作られた靴に、羊毛を編んで作られた靴下を履いていた。
靴下はこまめに取り換えて、洗濯をして背負い袋からぶら下げて乾かしておく。
そのうちの1足が穴が空きそうになっていた。
「私も買っておこうかな。」
アレンティーがマリーウェザーの穴が空きそうな靴下を見てそう言った。
「それじゃあ、仕立屋さんに行ってみよう。」
シェリルが笑顔で2人に声を掛けた。
「そうだ、俺も気になっているものがあったんだ。」
エバが何か思い出した顔をしてそう言った。
「何か欲しい物があるの?」
ソフィがエバを見た。
「まあ、こんな小さな街にある訳はないと思うが。刀剣屋に行きたいな。」
エバがそう言うとニヤリと笑みを見せた。
「へえ、そうなんだ。」
ソフィが興味のある顔をしてエバにそう言った。
「はいはいみなさん。迷子にならないように団体行動で行きますよ。」
一番後ろに立っていたマーリンが両手を叩いてみんなにそう言った。
「じゃあ、通りを歩きながら店を探そうよ。見つけたら止まるんだよ。」
シェリルがそう言うと、エバたちはエバを先頭にして通りを歩きながら、通りに並んでいる店を見て回った。
まずエバたちは、通りに出ていた屋台で柔らかなソフトプレッツェルを屋台のおじさんから購入すると、みんなで歩きながら食べた。
蜂蜜がかかったソフトプレッツェルは、その甘い魅力でシェリルら女性たちを一瞬で虜にしてしまった。
次に木彫りの人形が並んでいる店で、いろいろな表情や姿勢をした人形を眺めると、痩せているだの、貧乏そうだの、奥さんが怖そうだの、毒入りソーセージを食べさせられて日に日に痩せているだのと言って、女性たちは喜んでいた。
お店のおじさんは、この人形は精霊の人形で、死んだ人が精霊になってあの世から街に戻って来るのだと言った。
ようやくエバたちは仕立屋を見つけると、マリーウェザーが軒先から店内を覗き込んだ。
「わっ凄い!」
店内の正面の壁には、大きな狼の毛皮が広げて飾られていた。
「シルバーウルフだね。“War with the Wolf”。神聖王国ルークスは、狼との闘いの歴史が有名だからね。」
シェリルがそう言ってマリーウェザーにニコッとした。
狼の毛皮は、ふさふさとしていて暖かそうだった。
そして銀色の毛並みからは不思議な光沢が放たれていて美しかった。
「どうだい?立派だろう。」
店のおじさんが話し掛けて来た。
「ルークスではしょっちゅう狼とやり合っているから、狼の毛皮はいくらでも取れるんだが、こんなに綺麗な形の毛皮は滅多にないよ。」
「そうなんだ。」
マリーウェザーが頷いた。
「ルークスの戦士は、三つ又の槍“トライデント”で狼と戦うんだ。」
シェリルがマリーウェザーにそう言った。
「そうなんだ。」
「良く知っているね。強い戦士は槍の一撃で狼を仕留める。だが不慣れな戦士はそうはいかない。どうしても無駄に刺したり、毛皮を斬り裂いちまう。こんな見事で綺麗な毛皮が取れるという事は、仕留めた戦士も一流ということさ。だから、価値があるっていうものなのさ。」
店のおじさんが自分の事のように得意気な口調でそう言った。
「なるほど。ということは、この狼は頭を槍で一突き、というところかな。」
エバが納得したようにそう言った。
「俺もそうじゃないかと思っているよ。体の部分には傷一つ無いからね。」
「これは売り物なの?」
ソフィが尋ねた。
すると店のおじさんは被りを振った。
「これは売れないな。店のお守りだからね。でも、ファーの着いた帽子や上着はどうだい?肌触りは最高だし、暖かいよ。」
女性たちは顔を見合わせた。
「遠慮しとくよ。これから神聖王国の首都ルークスに向かうんだ。」
シェリルがそう言うと、店のおじさんはしまったという顔をして頭を撫でた。
「なんだ、そうか。ルークスはこれから夏を迎えるからな。」
シェリルはおじさんにニコッとした。
「でもちゃんと買いたいものがあるんだよ。靴下が欲しいんだけど。羊毛で肌触りが良くて丈夫なやつ。」
「それならぴったりのがあるよ。うちは組合の基準どおりにしっかりと羊毛を使っているから、丈夫だし肌触りも最高だよ。」
そしておじさんに勧められながら、マリーウェザーとアレンティーは靴下を購入した。
マリーウェザーは青色と黄色の靴下を購入した。
アレンティーは草色と茶色の靴下を購入した。
「毎度あり!帰りも寄ってくれよ。」
エバたちはおじさんに手を振ると、仕立屋を後にした。
「おっ、ようやく武具屋らしい店があるな。」
仕立屋を出て少し歩いたところで、エバがそう言うとその武具屋に歩いて行った。
エバは店の前に来ると、店頭から店内に陳列された商品を一通り見渡した。
剣が一振り壁に掛けられてはいたが、それよりも鋏やナイフ、包丁や釘などの日用品の方が多かった。
「これは期待薄だな。」
エバがそう言って頭を掻いた。
「一応聞いてみれば。」
ソフィがそう言うとエバの顔を覗き込んだ。
エバは頷くと、店内で針金を切断している店員に話し掛けた。
「すいません。」
店員は立ち上がると軒先に顔を出した。
「何がご入用で?」
店員がエバに尋ねた。
「隕鉄を鍛えて造られた製品はないか。」
「隕鉄だって?流星剣の事かい?こんな街にあると思うかい?ここにはないね。首都のルークスなら、ドワーフが加工した製品が手に入ると思うが。」
店員はそう言うとエバにかぶりを振った。
「そうか。邪魔して悪かったな、ありがとう。」
エバは右手を軽く上げて挨拶すると、隣に立っているソフィを見て肩をすくめて見せた。
「この街にはないだろう?」
シェリルが後ろからエバに声を掛けた。
「ああ、まあな。」
エバがそう言って目を瞑った。
「隕鉄って?」
ソフィがエバに尋ねた。
「夜空を流れる流れ星を知っているだろう?その流れ星に含まれている鉄の事だ。その隕鉄で造られた特別な剣は、流星剣と呼ばれている。」
ソフィが驚いた顔になって目を大きくさせた。
「流れ星でできた剣なんて素敵ね。」
エバが小さく頷いた。
「隕鉄を鍛えるのには特殊な製法が必要で、神聖王国に行けば手に入ると聞いた。何でも、深い山奥に隠れ住んでいるドワーフだけがその特殊な製法を知っていて、神聖王国にだけは流星剣が出回っているらしい。」
「そうなんだ、知らなかった。エバはその流星剣を探しているの。」
エバはまた小さく頷いた。
「一応な。絶対に見つけてやると思っている訳でもないんだが。せっかくだから見てみたいと思っている。どうやら流星剣は、真っ黒な色をしているらしい。」
そう言うエバの言葉を聞いて、ソフィが少し残念な表情になった。
「流れ星なのに真っ黒なの?流れ星なのに光っている訳じゃないのね。残念。」
すると思わずエバがソフィに微笑んだ。
「俺も最初に聞いた時はそう思っていた。だが、本当かどうかはまだ分からない。もしかしたら、眩しく光っているのかもしれない。それは後のお楽しみという訳だ。」
エバがニヤリと笑みを見せた。
武具屋を後にしたエバたちは、適当な宿を探して通りを歩いていた。
すると、街の中心にある広場に辿り着いた。
広場の真ん中には人だかりが出来ていて、ただでさえ混雑している大通りよりも、さらに混雑さが増していた。
「何かしら。」
アレンティーが怪訝そうな顔をした。
「ああ、公開処刑だな。」
エバがあっさりとそう言った。
「ええ!」
マリーウェザーが驚いた表情をすると背伸びをして広場を見た。
広場の中心には十字に組まれた木材が立っていて、そこに女性が縄で縛り付けられていた。
縛り付けられた女性は、力無く頭を垂れていた。
その周りを囲むように、数人の男たちによって束ねられた薪が綺麗に組み上げられていた。
「あれは火あぶりにするつもりだな。魔女とされてしまったかな。」
シェリルがマリーウェザーにそう言った。
「ええ!あの女性魔女なの?」
マリーウェザーが驚いた表情をした。
「火あぶりの刑が執行されているということは、魔女裁判で魔女だと判決されたからだ。つまり、表向きには魔女だということになる。」
「表向きですか?」
アレンティーがシェリルの横に顔を出した。
「そう、表向きさ。だって、魔女か魔女でないかだなんてどうやって判断するんだ?」
マリーウェザーとアレンティーが首を傾げた。
「魔女裁判なんていうのは、魔女かどうかというよりも、裏の何かが一番の問題さ。」
「裏の何か。」
「疫病が流行ったり、雨が少なくて小麦が取れなかったり、そういう不幸が起きたときに魔女狩りが行われる。そして不幸を魔女のせいにして見せしめのために殺す。そうやって人々の心を静めるのさ。」
「じゃあ、あの女性も本当は魔女じゃないということ。」
「恐らくね。なぜ魔女に仕立て上げられてしまったのか分からないが。」
「おっ誰か来たぞ。」
エバが広場をみながらそう言った。
薪の束の積み上げが終わった広場の中央に、白い衣装に身を包んだ人物と豪華なファーのついた上着を羽織った男女が現れた。
白い衣装には黒と白で塗り分けられた円の紋章が描かれていて、その人物がサリカ神の神官であることが分かった。
神官はファーのついた上着を着た男と短く言葉を交わすと、脇に抱えていた大きな経典を開き、木材に縛り付けられた女性に向かって何かを語り始めた。
そして神官の語りが終わると、神官は脇に控えていた男たちに向かって右手を上げた。
「火がつけられるぞ。」
エバがそう言った。
その時だった。
「待てえ!」
どこからか大きな声がした。
マリーウェザーが広場の隅を指差した。
「あれ!」
マリーウェザーが指差した人混みの中から子どもが駆けだしてきた。
さっきの掛け声は駆けだしてきた子供の声のようだ。
駆けだして来た子どもは、広場の隅で燃えていた焚火に走り寄った。
火あぶりに使うために燃やされていた焚火だ。
「いっけえ!」
子どもは大きく右足を後ろに振りかぶると焚火を蹴り飛ばした。
焚火がバラバラに飛び散った。
すると、木材に縛り付けられ、今までうな垂れていた女性が顔を上げた。
女性は子どもの姿を見て叫んだ。
「コナン!」
子どもも女性を見て叫んだ。
「ラン!今助ける!」
子どもが女性を見て頷いた。
どうやら子供がコナンで、女性がランという名前のようだ。
すると、ファーのついた上着を着た男がコナンを遮るようにランの前に出て来た。
「待っていたぞ悪魔少年コナン。おい、小僧を捕まえろ。」
ファーのついた上着を着た男は、周囲の男たちにそう指示するとコナンを指差した。
「ちょっと待った!」
今度は人混みの中から1人の小太りの男が現れた。小太りの男は立派な口ひげが特徴的な男だった。
「ちょっと待っていただこう。ブラックマン総監。」
小太りの男はファーのついた上着を着た男にそう言った。
総監とは、街の人々から税金を徴収し、裁判の判事を務めるなど、街を領主に替わって管理監督する総責任者のことで、街で力を持っている大金持ちの市民がその役目を務めていた。
年に数回、王宮の執事が監査のために街を訪れることがあったが、実質的に街を支配していたのは総監だった。
「これはガヤンのメグレ神官長。ご苦労様です。ですが・・・、何か御用がありましたかな。」
ブラックマン総監は口ひげの男に鋭い視線を送った。
ガヤンというのは正義と法の神であり、その神の教えを実践している信者達は、そのガヤンの法を犯す悪人を捕まえ、法の前で裁く権限を国王から与えられていた。
口へげの男、メグレは、そのガヤンの神官長のようだ。
「コナンが殺害事件の犯人を見つけたのですよ。その仕掛けも。」
メグレ神官長がそう言ってブラックマン総監を睨んだ。
「お前達の企みは全て分かった。観念しろブラックマン夫妻!」
コナンもそう言ってブラックマン総監と総監の隣に立っている奥さんを睨んだ。
「何だと。」
ブラックマン総監はコナンを睨みつけた。
コナンは懐から針金の束を取り出した。
「これが殺害に使われた凶器だ。あなたたちは、屋敷の入り口にある門に針金で輪っかを作り罠を設置すると、馬に乗って勢いよく走って来た被害者の首を針金で切断した。大体、女性の力では、包丁で首が斬れる訳がないんだ!」
コナンはそう言うと、人差し指をブラックマン総監に突き付けた。
するとメグレ神官長が続けて口を開いた。
「鍛冶屋の親父が言っていましたよ。あなたの屋敷で働いている女中が針金を買いに来たとね。」
するとコナンがブラックマン総監の奥さんを見た。
「あなたなら分かる筈だ。被害者の後ろから馬で追いかけていたあなたなら。」
ブラックマン総監の奥さんは黙ってコナンを見つめていた。
コナンは続けた。
「あなたは始めから知っていたんだ。被害者が死んでしまう事を。被害者の首が切断された時、あなたの流した涙が動かぬ証拠だ。あなたの涙は横に流れていた。涙は、馬にでも乗っていない限り横には流れないのですよ。」
コナンの言葉にブラックマン総監の奥さんは言葉を失った。
広場を取り囲んでいる人々も静かになって、成り行きを見守っていた。
「はははははは。」
すると突然、ブラックマン総監は大声を上げて笑った。
「だからどうしたというのだ。殺したのはこの女だ!」
ブラックマン総監はそう言うとランを指差した。
「私は殺していません!」
ランが叫んだ。
「黙れ!この人殺しが!」
ブラックマン総監はそう一喝した。
「確かに、普通の女性なら包丁で人の首は斬れんかもしれん。だが、このランという女は違う!普通の女ではない!」
ブラックマンが力強く右手を薙ぎ払った。
「このランという女は、この街の何人もの男たちを、拳で殴りつけたり足で蹴りつけるなどして暴力を振るってきた女なのだ。その被害者は何人もいる。この広場に集まっている者の中にもいるだろう。」
ブラックマン総監はそう言いながら、広場に集まった男たちに目をやった。
すると、何人かの男たちが小さく頷いていた。
どうやら、ランという女の暴力性は本当のようだ。
「そのような女であれば、包丁で人の首を斬ること位できる。つまり、針金などという小細工など要せずとも殺せるという訳だ。」
「私はやってません!」
ランが必死にそう叫んだ。
「さらにこのコナンという小僧。」
ブラックマン総監はコナンを睨んだ。
「みなさん、この小僧の見た目に騙されてはいけません。この小僧、見た目は子供だが、実はこのランという女性と同い年なのです。」
ブラックマン総監はそう言って広場の人々を見回した。
「コナンとランがこの街に来たのが10年前。つまり、この街に来て10年が経っている訳だ。だがどうだ?ランが大人の姿をしているのに、コナンは子供のままだ。変わらない。これが何を意味しているのか。」
ブラックマン総監はあえてそこで言葉を切ると人々を見回した。
「悪魔だからだ。」
ブラックマン総監はゆっくりと、そしてはっきりした声で人々にそう言った。
広場に集まっている人々が一気に騒ぎ始めた。
「今からこのランという女性を火あぶりにするのは、悪魔を10年もの間かくまっていた悪魔の手先、つまり魔女だからだ。そして、悪魔であるコナンも火あぶりにする必要がある。」
ブラックマン総監がそう言って周囲の男たちに右手を上げた。
男たちがコナンに迫った。
「やめんか。」
メグレ神官長がコナンの前に立ちはだかった。
「メグレ神官長、手出しするのは止めて貰おう。これはサリカ神の悪魔裁判によって悪魔と判決されたことによる公開処刑。ガヤン神官のあなたに手出しをする権利はない。さっさとこの場から退場して貰おう。それに、悪魔の手助けをするというのなら、あなたにも疑いがかかるやもしれませんぞ。」
ブラックマン総監がメグレ神官長を睨んだ。
「く、くそう。」
メグレ神官長が悔しそうに地面を踏みつけるとコナンに振り向いた。
「すまん、コナン。」
メグレ神官長は目を瞑ると力なく肩を落とした。
「メグレ神官長、あなたのせいじゃありませんよ。今まで、ありがとうございました。」
コナンはメグレ神官長にニヤリと笑みを向けると、迫る男たちに向かって走り出した。
「さあて、やるだけやりますか。」
コナンは迫る男たちの足の間をくぐり、たくさんの手を避けながらランに迫った。
だが、広場に集まっていた周りの男たちもコナンの捕獲に加わったことで、コナンを追い掛ける男たちは十数人となっていた。
いくら俊敏さに自信があったとしても、これだけ多人数となれば捕まるのは時間の問題だった。
コナンは男たちに押しつぶされ、捕らえられた。
「さすがに、何の道具もないのは厳しいぜ。」
コナンは肺が押しつぶされそうな位に圧迫されながらそうぼやいた。
「捕まっちゃったね。」
成り行きを見守っていたマリーウェザーがそう言った。
「マーリン。結局、ブラックマン総監とコナン、どっちが嘘を付いているんだ。」
シェリルが後ろに立っているマーリンに尋ねた。
「聞いてどうするんですか?」
マーリンがそう言うと嫌そうに目を細くした。
「どうするのかは、聞いてから考えるに決まっているだろう。」
シェリルも目を細くしてマーリンを見た。
マーリンはやれやれという顔をすると口を開いた。
「人殺しはブラックマン夫妻です。そしてブラックマン夫妻は、その罪をランに被せて処刑するつもりです。」
「それじゃあ、やっぱりランさんは魔女ではないということ。」
マリーウェザーが驚いた表情を見せた。
「まあ、そういう事ですね。」
マーリンが淡々とそう言った。
「可哀そう。」
アレンティーが呟いた。
「うーん。」
シェリルが人差し指を顎に当てて考える素振りを見せた。
「あれっ?エバは?」
マリーウェザーが周りを見ながらそう言った。
マリーウェザーの言葉にみんなが周りを見渡したが、エバの姿はなかった。
すると、シェリルがマリーウェザーに向かって手をひらひらとさせた。
「大丈夫だよ。いつものとおりさ。」
シェリルはそう言うと、この後どうするのかについて考え始めた。
「くそう。」
男たちに押しつぶされたコナンは顔だけをブラックマン総監に向けた。
ブラックマン総監は周りを見渡したが、男たちは全員コナンを押さえて動けないので、しようがなく自分で地面に転がった燃えている薪を拾い集めた。
「そこで大人しく見ていろ。仲間が死ぬ姿を。」
ブラックマン総監は燃えている薪を次々と無造作に薪の束に投げ入れた。
よく乾燥した薪の束は、すぐに煙を上げてくすぶり始めると、次々と炎が上がった。
「けほけほっ。」
ランが煙でむせた。
「ラン!」
「コナン。」
必死な形相でコナンはランを見た。
ランは煙から逃れようと顔を左右に振っていたが、どちらに顔を向けても煙から逃れることはできずに咳き込んで涙を流した。
「く、くそう。」
「安心しろ、女が死んだらお前もすぐに炙ってやる。すぐに女を追い掛けられるようにな。」
ブラックマン総監は満足そうに笑みを浮かべた。
すると、ブラックマン総監のすぐ横を1人の男が通り過ぎた。
その男が足音も立てずにいきなり目の前を通り過ぎたので、ブラックマン総監は驚いて後ろにのけ反った。
ブラックマン総監は呆気に取られた様子で男の様子を見ていると、男は燃えている薪の束の目の前で止まった。
すると突然、男は燃えている薪の束を蹴り飛ばし始めた。
「おい!何をしているんだ。」
ブラックマン総監はそう言って男に近付こうとした。
すると男は燃えている薪の束を手に取ると、ブラックマン総監に投げつけた。
「な、何をするんだ。」
避けようとしたブラックマン総監は思わず足を取られて地面に転がった。
そこにさらに男が燃えている薪の束を叩きつけた。
「ぎゃあ〜。」
ブラックマン総監は慌てて薪の束を払いのけると、衣服の炎を払った。
薪の炎は、ブラックマン総監が来ていたファーを黒く焦がしてしまった。
「あっ、エバだ。」
マリーウェザーが薪を蹴り飛ばしている男を指差した。
「はいはい本当だ。エバだねえ。」
シェリルはそう言って苦笑いを浮かべた。
エバは、広場で円の形にきれいに並べられた薪の束を次々と蹴り飛ばしていた。
「お前たち何をやっている、この馬鹿を何とかしないか。」
ブラックマン総監は、コナンを取り押さえているたくさんの男たちに指示した。
「コナンを逃がしてしまってもいいんですかい?」
コナンに覆いかぶさっている男たちの一人がブラックマン総監に尋ねた。
「馬鹿者!コナンを捕まえつつ、あの男を何とかしろと言っとるんだ!」
すると、コナンに覆いかぶさっていた男の数人が立ち上がると、エバに向かって歩いて行った。
「エバ。」
エバに横から呼び掛ける者がいた。
エバは声の方に首を回した。
「ソフィか。」
ソフィはニコッとしてエバを見た。
「気付かれていたのか、さすがだな。」
エバはソフィにニヤリと笑みを見せた。
「ほら、あっちから男の人たちが近寄って来るけど。」
ソフィが歩いて来る男たちを指差した。
「ん?それはいいけど、お前も戦うつもりか?」
エバがソフィを見た。
「悪い?」
ソフィがまたニコッとした。
「たくましいな。」
エバが肩をすくめると目を瞑って見せた。
「それじゃあ、二人でぐるぐる回るやつ、やるか。」
エバが人差し指をくるくると回した。
「ぐるぐる回るやつ?」
ソフィが分からない顔をした。
「円を描いて回りながら、お互いに相手の背中を追い掛けるやつ。」
ソフィの顔が分かった顔に変わった。
「ああ、ダブルドラゴン。双龍陣ね。」
「ドラゴンとは勇ましいな。俺の流派では虎なんだが。」
「じゃあ、龍と虎で、龍虎の陣でいいんじゃない。」
ソフィが自分とエバを順番に指で示しながらそう言った。
「なるほど。お前が龍で俺が虎か。了解。それじゃあ行こうか。」
「オーケー、エバ。」
するとエバは、足元に転がっている薪の束から、手ごろな長さの薪を手に取ると、こちらに向かって来る男たちにタタッと小走りで走り寄った。
「うらあ。」
エバの前に1人の男が立ちはだかった。
エバを捕まえて抑え込もうと両手を構えた。
するとエバは、あっという間に男の伸びた右腕、鎖骨、側頭部を薪で打つと、男は地面に転がった。
「うおおっ。」
地面に転がった男は左手で頭を押さえながら膝を抱え込んで丸くなった。
「この野郎。」
別の男が怒りを露わにしてエバを追い掛けた。
するとエバは、その男を無視すると別の男に向かって右手側に進んだ。
無視しやがって。
エバに無視された男は、エバの後ろから襲い掛かろうとした。
だが、すぐにソフィが右手に持った小さな盾を振り回して男を牽制した。
「この女。」
男はソフィに向き直った。
するとソフィはその男を無視すると別の男に向かって右手側に進んだ。
ソフィに無視された男は、今度はソフィの後ろから襲い掛かろうとした。
だがすぐにまたエバが現れると、男の右腕、頭頂部を薪で打つと、男は地面に転がった。
「何だ。訳が分からねえ。」
男はくらくらする頭を右手で押さえると地面に丸くなった。
エバとソフィは、円を描くようにぐるぐると回りながら、エバはソフィの背中を、ソフィはエバの背中を追い掛けた。
そうして、ぐるぐると追い掛けながら、エバがソフィの背中を守り、ソフィはエバの背中を守る。
お互いの背中をお互いに守りながら、ぐるぐると回って近付いて来る男たちを打ち倒す。
双龍陣。
ソフィの流派ではそのように呼ばれている。
お互いの死角となる背後をお互いに守りながら戦う、守りに強い戦術だ。
1人の男がソフィを捕まえようと右腕を伸ばしてきた。
するとソフィは、伸びて来た右腕を左手で軽く押さえると、腕の先にある指を小さな盾で打ち抜いた。
「あ、痛!」
指の骨が折れてしまった男が思わず腕を引っ込めた。
だがソフィは深追いはしない。すぐにその場を移動する。
するとそこにエバが近付くと、痛そうにしている腕を掴んで固定すると、薪で男の側頭部を打つと同時に相手の足を払うと地面に転がした。
「あっ、いったああああ!」
地面に転がった男は強く背中を打ってごろごろと転がった。
エバとソフィはまるで、ぐるぐると渦巻くつむじ風のようだった。
触れる男たちを弾き飛ばしながら、エバとソフィのつむじ風は広場を蹂躙した。
数十秒後には、十数人の男たちが全て地面に転がされてしまった。
エバとソフィはその歩みを止めた。
エバは周囲を見渡すとコナンを見た。
コナンを押さえつけていた男たちがエバを見ていた。
エバが男たちに近付くと、手に持っていた薪を振り上げた。
「うわあ。」
男たちは立ち上がるとコナンから離れた。
コナンは素早く立ち上がるとランに走り寄った。
「ラン、今外してやる。」
コナンは、ランを木材に縛り付けている縄を解き始めた。
「何なんだお前たちは。」
ブラックマン総監が地面に座り込んだ状態でそう言った。
「おい、衛兵を呼んで来い。」
ブラックマン総監が近くの男に指示した。
「ねえ、エバ。どうするの?」
ソフィがエバに尋ねた。
「ん、俺の出番は終わりさ。あとは、シェリルが何とかしてくれるだろう。」
エバはそう言ってニヤリと笑みを見せた。
「ぷっ。」
無責任なエバの態度に、思わずソフィは吹き出してしまった。
「どうやら気が済んだみたいですね。」
マーリンがエバとソフィを見てそう言った。
「もう、いつも勝手なんだから。」
マリーウェザーがほっぺを膨らませた。
「ははは。エバのやる事だからな、しようがないさ。それにマリーウェザーだって、あのまま火あぶりになって殺されてしまうのは良い事ではないと思ったのじゃないか?」
シェリルがマリーウェザーに笑顔を見せた。
「まあね、そうだけど。」
「だったらいいんだよ。それで。」
「そうね。」
そうは言ったけど、あのランという女性は助けてあげて、街の外で困窮している乞食には手を差し伸べない。それってどういうことなのだろう。無責任でいい加減なだけではないのだろうか。
マリーウェザーはそう思った。
でも、すぐには答えが出そうにはなかったし、この場でシェリルに聞くのもどうなんだろうと思った。
「さて、後始末をつけに行くとするか。」
シェリルはそう言うと、マーリンとマリーウェザーとアレンティーを見た。
「私もあのコナンとランを助けたいと思っている。マリーウェザー、一緒に来てくれないか。アレンティーは、マーリンを助けてあげてくれ。」
「オーケーだよ。」
アレンティーはシェリルにニコッとした。
シェリルもアレンティーにニコッとした。そしてマリーウェザーを見た。
「それじゃあ行こうか。」
「うん。」
シェリルはマリーウェザーと一緒に広場の中央に向かって歩き始めた。
するとシェリルが歩きながらマリーウェザーに聞いた。
「エバってさあ、何考えていると思う?」
マリーウェザーは首を傾げた。
「エバはね、何も考えてないんだよ。」
シェリルの言葉に、マリーウェザーはくすくすと小さく笑った。
「でもさ、向いている方向は合っている気がするんだよな。」
シェリルが正面を向いたままそう言った。
「ランという女性が火あぶりにされたとき、彼女は頭を左右に振って苦しんでいた、それってさ、もっと生きたいって叫んでいるのと一緒だよね。その時にエバはこう考えたんじゃないかな、俺なら何とかできるかもって。」
マリーウェザーははっとして、横を歩くシェリルを見た。
「手伝ってくれないか、マリーウェザー。私も何とかできるかもしれないって、思っているんだ。」
シェリルがマリーウェザーを見た。
「シェリル姉さん。」
マリーウェザーは小さく頷いた。
「おっと、自分で言っていて矛盾していたな。エバがそんなこと考えている訳はない。うん、それは絶対に間違いない。」
シェリルはそう言うとマリーウェザーにニコッとした。
マリーウェザーもシェリルにニコッとした。
「コナン。ありがとう。」
木材から解放されたランがコナンを抱きしめた。
「遅くなっちまって、ごめんな。」
「ううん、絶対来てくれるって信じてたから。」
「バーロー。俺が見捨てる訳ないだろ。」
コナンはランの上体を起こした。
「さあて、問題は、ここからどうするかだ。」
「ブラックマン総監め。ぶっ飛ばしてやるんだから。」
ランが立ち上がると拳を固めた。
「おいおい、そんなに余裕がある状況じゃないぜ。すぐにでも衛兵たちがやって来ちまう。俺たちを助けてくれたあの人たちが、何者なのかも分からないしな。」
コナンがエバとソフィを見てそう言った。
「確かに。何で私たちを助けてくれたのかしら。」
「会ったこともないし、この街の人間でもなさそうだ。」
コナンはそう言うと、周囲をうかがった。
「コナン。逃げられると思うなよ。もうすぐ衛兵たちが駆け付ける。そうしたら、また火あぶりの続きだ。お前たちもひっ捕らえてやるからな。」
ブラックマン総監が立ち上がりながら、コナンとランとエバとソフィを睨んだ。
コナンは頭を回転させた。
俺の秘密が知られてしまった以上、もうこの街には居られない。
何とかこの街から脱出するしかねえ。
コナンはふと、十数人の男たちをあっという間に打ち倒し、自分たちを助けてくれた男女を見た。
さすがに、戦う訓練を積んだ衛兵たち数十人を相手に、たった2人の男女で太刀打ちできるとは思えない。
かといって、ランと二人で走って逃げたとしても、門を閉められたら脱出は困難。
狭い街だから、どこかに隠れたとしてもすぐに見つかってしまう。
「とは言っても、じっとしている訳にはいかないか。」
コナンは、駆けだすなら左右のどちらにしようかと周囲を確認した。
その時だった。
「さあどいた、どいた。」
人混みを掻き分けながら、広場の真ん中にシェリルとマリーウェザーが出て来た。
するとシェリルは、広場に集まっている人々に向かって叫んだ。
「何をこんなに集まっているんだ、あの2人は悪魔だよ。知らないのかい?近付くと病気にかかっちまうよ。」
「みなさん、危ないから下がってえ!」
シェリルとマリーウェザーはそう言いながら広場に出て来ると、シェリルはブラックマン総監のところへ、マリーウェザーはエバとソフィに近付いた。
マリーウェザーはエバとソフィに近寄ると言った。
「シェリル姉さんが後始末をするから、エバとソフィは、コナンとランさんを守って。」
マリーウェザーの言葉に、エバは目を瞑って頷いた。ソフィはニコッとしてマリーウェザーを見た。
シェリルは、ブラックマン総監を睨みつけると、大股でずんずんと歩いて目の前まで近付いた。
ブラックマン総監は何事か分からずにシェリルを見ていた。
するとシェリルは、突然ブラックマン総監の襟首を締め上げた。
「とんでもない事をやらかしてくれたな!」
シェリルは周りの人たちにも良く聞こえるように、わざと大きな声で喋った。
ブラックマン総監は訳が分からず目を白黒させた。
「あの2人の悪魔は、火あぶりにしてはいけない。火が一番危険なんだ。火であぶると周りに危険な病気を撒き散らす。なのになぜ火あぶりにした!通知が来ていた筈だぞ。」
シェリルの言葉に、ブラックマン総監は余計に目を白黒させた。
「何を言っているのだ。私には分からん。」
するとシェリルはさらに襟首を締め上げた。。
「我々は王宮から派遣された悪魔祓いだ。コナンとランの2人の処分を命じられている。だから事前に通知を送ったのだ。我々が到着するまで手を出すなと。特に火を使うなと。」
「そんな通知、・・・知らぬ。」
ブラックマン総監は驚いた顔をした。
シェリルはブラックマン総監を地面に引き倒した。
周囲の人たちからどよめき声があがった。
「知らなかったで済むか。あの2人は悪魔なんだろう。違うのか!人間なのか!」
ブラックマン総監は一瞬の間黙り込んだ。
「・・・悪魔だ。」
シェリルはブラックマン総監から手を離し立ち上がると、総監を見下ろした。
「悪魔なんだな。悪魔なら、なぜ王宮に連絡しなかったのだ。なぜお前の勝手な判断で火あぶりにしたのだ。」
「そ、それは。」
ブラックマン総監は言葉を失った。
そもそもコナンとランの2人は悪魔ではないし、自分の殺人の罪をランに被せようとしているのだから、王宮になど連絡できる筈もなかった。
「お前は、自分の勝手な判断で、火を使ってはいけない悪魔を勝手に火あぶりに処し、街のたくさんの人々の命を危険に晒したのだ。」
「そ、そんな。」
ブラックマン総監の顔から血の気が引いた。
周囲の人たちがまたどよめいた。
「ところで、誰が火をつけた。」
「はい?」
ブラックマン総監は分からない顔をした。
「火あぶりにする時に、誰が火をつけたかと聞いているのだ。」
シェリルの言葉に、ブラックマン総監が恐る恐る手を上げた。
「私だ。」
シェリルが瞳を大きくさせた。
「お前、火をつけたのか。」
シェリルが思わずのけ反った。
「なっ、何だ!火をつけると何があるのだ。」
シェリルはごくりと唾を飲み込むと、大きな声でゆっくりと言った。
「この悪魔は、最初に火をつけた者に、必ず病気をうつす。」
「なっ、何だと。そんな事がある訳。」
ブラックマン総監はそう言いながらもうろたえた素振りを見せた。
シェリルはチラッとマーリンを見た。
するとマーリンが小さく頷いた。
「あっ、あなた。顔が、顔が。」
ブラックマン総監の奥さんが口を押さえるとそう言った。
奥さんはブラックマン総監の顔を指差すとたじろいだ。
「何だ、何だ、何が起こっている。」
すると、ブラックマン総監の顔面の右半分が、明らかにビクンビクンと大きく脈動していた。
ブラックマン総監は右手で顔に手をやると、ビクンビクン脈動する頬や顎や瞼に触れた。
「何だこれは!」
ブラックマン総監は、慌てて痙攣を抑え込もうと顔面を手で強く押さえた。
だが、脈動は一向に収まることはない。
「ちょっと来てくれ。」
シェリルはエバのところに立っているマリーウェザーを呼んだ。
「彼女は悪魔専門の医師だ。」
シェリルはブラックマン総監にマリーウェザーをそう紹介した。
「どうだろう、この症状は。」
マリーウェザーがブラックマン総監の顔を覗き込んだ。
「これは・・・、間違いなく悪魔の病です。」
「病状の程度は。」
シェリルが眉間に皴を寄せた。
「症状が重い上に、進行も速い。これは、相当やばいです。」
マリーウェザーは必死な表情でシェリルを見た。
シェリルはマリーウェザーの腕を掴むと一緒に立ち上がった。
「どうやら総監は悪魔の病にかかってしまったようだ。こうしてはいられない、市民を避難させよう。」
シェリルはそう言うとマリーウェザーの肩を叩いた。
マリーウェザーは頷くと、広場に集まっている人々に声を掛け始めた。
「みなさん!危ないからもっと下がって!ブラックマン総監の悪魔の病気がうつってしまう!」
シェリルも周囲の人々に向かって大声を張り上げた。
「家の中に入れる人は、早く入るんだ!入れない人も出来るだけ遠くに離れて!」
すると、その様子を見ていたマーリンはピンと来た。
「あっ。」
そう言うとマーリンはいきなり地面に倒れ込んだ。
突然の事にアレンティーが驚いて口元を両手で押さえた。
「お兄さま!どうされたのですか。お兄さま!」
アレンティーはしゃがみ込むと、必死にマーリンに声を掛けた。
「きゃあ!」
その様子を隣で見ていた女性が慌てて駆けだした。
「うわああ!」
広場から一斉に人々が離れ始めた。
「お兄さま、お兄さま!」
アレンティーがマーリンを抱きかかえ必死で呼び掛けると、マーリンが薄目を開けて何か小さくつぶやいた。
アレンティーはマーリンの口元に耳を寄せた。
「う・そ。」
アレンティーは思わず兄マーリンの頭を引っぱたいた。
その広場の様子を見ていたエバは小さく頷いた。
「なるほど。何となく分かった。」
エバはソフィと顔を見合わせると、唖然とした様子で立っているコナンとランに近付いた。
「さっきはどうも。」
コナンがエバにそう言った。
エバが小さく頷いた。
「どうやら、あんた達を助けることになったらしい。脱出経路ができあがりつつある。」
エバはそう言ってコナンにニヤリと笑みを浮かべた。
あれだけたくさん広場に集まっていた人々は、みるみるうちに少なくなっていった。
すると通りの向こうから、逃げる人々に逆らうように衛兵たちが近付いて来た。
「ブラックマン総監。わっ!」
街の衛兵たちが広場に到着すると、ブラックマン総監の顔を見て足を止めた。
「ブラックマン総監に近付くな!死にたいのか!」
シェリルがキッとした顔で叫んだ。
すかさずマリーウェザーが衛兵の前に立った。
「ブラックマン総監は悪魔の病にかかっています。ここにいるのは危険です。あなた達も病にかかってしまいますよ。」
「何だって。」
衛兵たちが驚いた顔を見せた。
「二度言わないと分からないのか。我々は王宮から派遣された悪魔祓いだ。ここは我々に任せてすぐに離れろ。さもないと、お前たちもああなるぞ。」
シェリルが衛兵たちにそう言うと、ブラックマン総監の顔面を指差した。
「うわ。」
衛兵たちが思わず後ずさった。
「ここにいては危険です。できれば建物の中に避難してください。他の衛兵にも伝えてください。」
マリーウェザーが衛兵たちの背中を押した。
すると、顔面の右半分を押さえたブラックマン総監がシェリルの前に立った。
「おいあんた、頼む、この悪魔の病気を何とかしてくれ。頼む。」
ブラックマン総監が必死な顔でそう言った。
だがシェリルは目を細くして総監を見た。
「お前が勝手にやったことだろう。自業自得だ。それに私は、悪魔である2人の処分を命じられただけだ。金も貰っていないしね。」
「そんなこと言わないでくれ、頼む。」
「うるさいな!見て分からないのか?お前が市民を危険にさらしたせいで、市民を避難させるのに手一杯なんだぞ!お前のせいなんだぞ!」
シェリルが冷たくあしらった。
だが、ブラックマン総監は食い下がった。
「じゃあ、一つだけ教えてくれ。この病気は、これからどうなるのだ。このまま顔がビクビクするだけか。」
シェリルは黙って総監の顔を見ていたが、大きく溜め息をつくと口を開いた。
「今は右半分がビクビクしているだけだが、最終的には頭全体がビクビクして、最後は・・・、頭が爆裂する。」
シェリルの言葉を聞いたブラックマン総監の顔から血の気が引くと真っ白に変わった。
そして、慌てた様子で懐から小袋を取り出した。
「頼む何とかしてくれ、金は払うから、頼む。お願いだ。頭が爆裂して死ぬなど耐えられん。」
シェリルはじっとブラックマン総監の顔を見た。
「病を治すにはあまり時間が無い。それに、私の指示に従って貰う必要があるが、それができるか。」
「分かった。お前の指示に従う。だから何とかしてくれ。」
ブラックマン総監は、必死な形相で何度も頷いた。
シェリルはブラックマン総監から金の入った子袋を受け取った。
シェリルは右手を上げるとマリーウェザーを呼んだ。
「ブラックマン総監を治療したい。まず、治療できるかどうかみてくれ。」
マリーウェザーはブラックマン総監を見た。
「・・・そうですね。今の状態では症状が激しすぎて治療ができません。まずは症状を抑えないと。」
マリーウェザーがシェリルを見た。
「やはり、何か嘘が関係しているか。」
すると、マリーウェザーが大きく頷いた。
「そうです、・・・これは、この悪魔の典型的な症状です。この悪魔は、人間の嘘の心に病をうつすのです。つまり、症状が激しいという事は、大きな嘘を抱えているということになります。」
シェリルは大きく頷いた。
「やはりな。ブラックマン総監、聞いたとおりだ。あなたは何か大きな嘘を抱えている。それが悪魔の病を激しくしているのだ。まずはその嘘を取り除くことだ。そうすれば治療できる状態になる。」
「何だって!」
ブラックマン総監が唖然とした表情をした。
「どうした、さっき私の指示に従うと言っただろう。時間がないんだ。さっさと従え。どんな大きな嘘を抱えているのだ。」
シェリルがブラックマン総監に詰め寄った。
「ぐぬぬぬ。」
ブラックマン総監がうつむいて地面を見た。
そこでシェリルは離れたところで地面に突っ伏しているマーリンをちらっと見ると、視線を移動させてブラックマン総監の奥さんを見た。
マーリンが小さく頷いた。
「きゃあ!」
ブラックマン総監の奥さんが悲鳴を上げた。
「どうした。」
ブラックマン総監が顔を上げて奥さんを見ると、奥さんの顔の右半分が、総監と同じようにビクンビクンと脈打っていた。
「何だと!」
ブラックマン総監が驚愕した。
「いけない!このままでは奥さんもやばいぞ。」
シェリルがそう言った。
「あなた、もうだめよ。もうだめ!何とかしてえ!」
奥さんがそう叫ぶと、ブラックマン総監はシェリルにすがりついた。
「分かった。言うとおりにする。言うとおりにするから、どうすればいいのだ。」
「嘘を付いた相手に謝罪しろ。それが一番の方法だ。」
「何だってえ。」
「早くしろ!時間が無いぞ。」
ブラックマン総監は地面を這いつくばってコナンとランの目の前に来た。
ブラックマン総監は歯をくいしばった。
「悪かった。許してくれ。殺したのは俺だ。許してくれえ。」
ブラックマン総監はがっくりと首をうな垂れた。
シェリルはブラックマン総監を蔑むように見下ろした。
「お前、悪魔に嘘をつくなんてとんでもないことだぞ。どうりで、症状が激しかった訳だ。」
シェリルはそう言うと、マーリンをちらっと見た。
マーリンは小さく頷いた。
「さあ、顔を上げて。どうですか?顔のビクビクは治まっていると思うが。」
シェリルに促されてブラックマン総監が顔を上げると、顔のビクビクは治まっていた。
「ああ。」
ブラックマン総監は、右手で顔を撫でて確認すると、ほっとしたように地面に突っ伏した。
「大事な奥さんも治まっているはずだ。あとは、症状が治まっている今のうちに治療を受ければ大丈夫だ。」
そう言うとシェリルは、マリーウェザーに目配せした。
「後は専用の魔法の薬を塗っておけば大丈夫。」
マリーウェザーは腰に提げた袋から金属でできた丸い容器を取り出し蓋を開けると、中に入っている軟膏をブラックマン総監と奥さんのほっぺに塗った。
「これですぐに良くなりますよ。」
奥さんのほっぺに軟膏を塗りながらマリーウェザーがそう言った。
「それでは、我々はコナンとランの2人の悪魔をこれから処分する。そのために2人は我々が連行する。」
そう言うとシェリルは、離れたところにいるエバとソフィに右手を上げて見せた。
「という訳だ。一緒に街の外まで来てもらおうか。」
エバはそういうと、コナンとランに向かってニヤリと笑みを見せた。
エバたちは、街を出るため、すっかり人通りがなくなってしまった通りを堂々と歩いて行った。
街を出たエバたちは次の街に向かって街道を歩いていた。
「やったね。」
「ありがとうマリーウェザー。素晴らしい出来だった。」
シェリルとマリーウェザーがぱちんと互いに相手の手の平を叩いた。
「私の出番が無かった。」
アレンティーがすねたようにシェリルにそう言った。
「そんな事ないよ。アレンティーの必死な演技のおかげで、街の人がすっかりいなくなったじゃないか。街を出る時には堂々と通りを歩けた。最高の気分さ。」
シェリルにそう言われてアレンティーは嬉しそうにニコッとした。
「助けて貰ってありがとうございました。」
コナンがエバにそう言った。
「まあな、だが、俺も好きでやったことだ。気にしないでいい。」
コナンが驚いた顔をした。
「好きであんな事をしているんですか。」
コナンの驚いた顔を見て、エバは少しの間考えた。
「考えて見たが、やはり好きでやっていることだ。」
「そうですか。」
コナンが苦笑いを浮かべた。
「それで、これからどうするの。」
エバの隣を歩いていたソフィが尋ねた。
コナンとランは顔を見合わせた。
「他の街に逃げるしかないんだろうな。」
コナンがそう言った。
「そうね。」
ソフィが頷いた。
「だけど、このまま街道を進むのは危険だ。ブラックマン総監があのまま引き下がっているとは思えない。」
シェリルが歩きながらコナンとランを見てそう言った。
「確かに、街を支配しているブラックマン総監なら、いくらでも言い逃れはできる。追手がいつ来てもおかしくないか。」
コナンが顎に手をやった。
「そう。だから、私たちは一旦この街道から外れ、ブラックマン総監の勢力圏から脱出する必要がある。」
するとマリーウェザーが何か気付いた顔になった。
「そっか、私たちも狙われちゃう可能性もあるんだ。」
シェリルがマリーウェザーに頷いて見せた。
「私の嘘がばれるという可能性もあるけど、コナンとランの2人の悪魔が、確かに処分されるのかどうか確認するために監視人を寄こすことは十分ありえると思う。監視人に付きまとわれると面倒だ。」
シェリルがそう言うと、ソフィがシェリルを見た。
「それは分かったけど、本道であるこの街道を外れてしまって大丈夫かしら。私たちはこの辺りの道に詳しくないのよ。道案内を雇うべきだわ。」
「そうだよね。適当なのがいないかな、なんて、思っているんだけどさ。」
シェリルが頭の上に腕を組んでうーんと背伸びをした。
「それなら、俺が案内しますよ。」
コナンがシェリルにそう言った。
「本当かい。」
シェリルが嬉しそうにコナンを見た。
「俺もランも、この近くの村出身なんです。その村への道なら俺が分かるし、その村から次の街に向かうこともできる。」
コナンの言葉にシェリルが笑顔になった。
「いいじゃないか。みんな、コナンの道案内でいいかな。」
シェリルがみんなに聞いた。
「いいんじゃねえの。」
エバが言った。
「いいと思いますよ。森の中でさまようのは勘弁ですからね。」
マーリンが言った。
マリーウェザーとアレンティーも頷いた。
「じゃあ決まりだ。コナン、よろしく頼む。」
シェリルはコナンに笑顔を見せた。
「オーケー、分かったぜ。」
コナンはシェリルに向かって親指を立てて見せた。
「ちょっとコナン。村に戻っても大丈夫なの?」
ランが心配そうにコナンにそう言った。
「あれから10年経ってるんだぜ。状況は変わっているはずさ。それに、いつかは訪れなければいけないと思っていた。ランだって、そう思っていたんじゃないか?」
コナンがランを見上げた。
「コナン。」
ランは心配そうにコナンを見下ろした。
エバたちは、コナンの案内で街道から横道に入ると、鬱蒼としたアカマツの森の中へ足を踏み入れた。
マーリン「どうでもいい話ですが、今回もお客様がいらっしゃいます。」
エバ「今日は誰だ。」
シェリル「誰かな?」
マーリン「コナンさんです。どうぞ。」
コナン「こんにちは。」
エバ「おお、本物だ。」
シェリル「小さくて可愛いね。」
コナン「見た目だけね。」
シェリル「ああそうか、歳は17歳だもんね。」
コナン「そうそう。」
マーリン「どうでしたか?悪魔少年コナンは。」
コナン「いいよ。良い感じです。いつもと違う感じでできるのがいい。特に、ランに秘密がばれているのがいい。自然体で。」
エバ「秘密っていうと、見た目は子ども頭脳は大人ってやつ?」
コナン「そうそう。」
シェリル「でも、今回でランさんにばれてしまって驚いたりされなかったの?」
コナン「全然。」
シェリル「そうなんだ。」
コナン「っていうか、もうばれてるし。」
マーリン「ばれてるんですか?」
コナン「ばれてますよ。本屋に行けば単行本が置いてあるし、定期的に映画もやるでしょ?それでばれない方がおかしい。」
シェリル「アユミちゃんは?」
コナン「ばれてる。」
マーリン「ゲンタは?」
コナン「ばれてるよ。」
エバ「以外と大変なんだな。」
コナン「現場では皆、知らない振りをしている。まあ、皆プロだし、長くやっているから慣れているけどね。そもそも・・・。」
シェリル「そもそも?」
コナン「そもそも、見た目は子ども頭脳は大人は俺だけじゃないんだ。アユミもゲンタもミツヒコもそうなんだ。だって、もう20年以上やっているんだぜ!アユミもゲンタもミツヒコも頭脳は大人になっちまってるよ。」
エバ「隠された苦労があるんだな。」
シェリル「ランとはどうなっているの?」
コナン「どうって?リアルで?」
シェリル「リアルで。付き合ってるの。」
コナン「一時期付き合あったこともあるけど、今はお互い気にして距離を置いている。」
シェリル「何で?」
コナン「付き合ってもお互い17歳から先に進まないだろ。大学生にもならないし、大人にもならない。やっぱり人生の進展がないと恋も進展しない。」
シェリル「そうか。」
コナン「普通の女の子と付き合うとしても、彼女ばっかり歳を取ってしまって、俺だけが置いてけぼり。いつまでも17歳でバーローバーロー言っている彼氏なんて、俺の方がご免だぜ。俺が本当の恋をするとしたら、大人の身体に戻ってからだろうな。」
シェリル「そっか、世間が大人になることを許してくれないと無理だね。大変だ。」
コナン「こんなディープな話これまでしたことなかったけど、今日は聞いて貰えて良かったよ。」
エバ「俺たちで良ければいつでも聞いてやるぜ。」
コナン「ところで、エバさんたちは何をしているんですか。」
エバ「俺たちか。」
コナン「ええ。」
エバ「何しているんだろうな?俺たち。」
シェリル「私に聞くな!北へ向かうって言い出したのはお前だろうが。」
エバ「そうだったけ。」
コナン「無職で旅をしているんですよね。」
マーリン「知ってましたか。」
コナン「事前に今までの話を読んでますから。・・・一応、話の流れで聞いた方がいいかと思ったんですけど。」
シェリル「私たち、好き勝手に生きているせいで、定職にはつけなくてさ。」
エバ「うんうん、そうなんだよな。」
シェリル「お前が言うか!」
コナン「でも、中世の旅ってかなりお金がかかるイメージがあるけど。その経費はスポンサーから出てるの?」
シェリル「そんな訳ないじゃん!私が一生懸命稼いでいるの!」
コナン「ええ!ガチですか?補助とかないんですか?」
シェリル「ガチだよ。この2人を見てよ、金を稼ぐ才能があるように見える?」
エバ・マーリン「・・・・。」
コナン「・・・シェリルさん倒れたら終わりですね。」
シェリル「そうさ。・・・何だか心配になって来た。」
エバ「シェリル。」
シェリル「ん?」
エバ「安心しろ、いざとなったら、俺が何とかしてやる。」
シェリル「エバ!」
エバ「マーリンをベッドリフレで一生懸命働かせるから、安心しろ。」
マーリン「そうだよね。この流れだと俺に来ますよね。分かってましたよ。」
エバ「じゃあ、話が早いな。」
シェリル「はあ・・・。お前なあ、少しお前の事かっこいいと思った自分にがっかりだわ。」
コナン「はははは。」
シェリル「良し。コナンに呆れられたところで、どうでもいい話はお開きにして、今回も呑みに行っちゃう?」
エバ・マーリン「おー。」
コナン「あー、わりい。俺まだ未成年でさ、お酒とか無理なんだわ。精神年齢的にはとっくに20歳は過ぎてるけど、肉体的には7歳だからさ。」
マーリン「お酒はだめでも、食事は問題ないのでは。せっかくだから一緒にどうですか。」
コナン「・・・サンキュー。でも、街を出歩くとどうしても目立っちまうからさ。遠慮しとくぜ。」
エバ「現代ならな、中世ならどうだ?シャロムの街にいい店がある。」
マーリン「シャロムの街であれば、コナンさんも有名人ではありませんね。」
シェリル「いいねえ。中世なら、子供でもお酒が呑めるし。」
コナン「・・・確かに、中世いいかもな。」
シェリル「それじゃあみんな、中世行っちゃう?」
エバ・マーリン・コナン「おー!」
シェリル・エバ・マーリン・コナン「ちゅーせい!ちゅーせい!ちゅーせい!ちゅーせい!」
4人が徐々にフェードアウトしていく中、何か思い出したようにエバが呟いた。
エバ「あっ、そういえば俺も、現代じゃ未成年だったぜ。」
ロボルの街を出発したエバたちは、コナンの案内で背の高いアカマツの森の中、細い山道を進んでいた。
細い道ではあったが、定期的に人が行き来しているようで、どこが道であるかはっきりと分かるし、藪が払われていて歩き易かった。
「木こりの道だね。」
シェリルが前を歩いているコナンに言った。
「正解。アカマツは燃料としても優秀だし、建築材としても使える。アカマツは自然に真っ直ぐ成長するんだけど、この辺りのアカマツを見ると見事に真っ直ぐ育っているだろ。これは木こりの手が入っているってことさ。今歩いているこの道は、木こりの道だぜ。」
コナンがそう言ってシェリルを見上げると、シェリルはニコニコしてコナンを見下ろしていた。
するとコナンは目を細めてシェリルを見た。
「だから止めてくれって、俺17歳なんだからさ。」
シェリルが両手を合わせて首を傾げて見せた。
「ごめん。だって、小さくて可愛いのに生意気な口をきくから、余計に可愛くてさ。ねえ。」
シェリルがそう言って後ろを歩いているマリーウェザーとアレンティーを見た。
「小さいのに、生意気可愛い。」
アレンティーがそう言うと、マリーウェザーが笑顔で頷いた。
2人とも、くせのあるプラチナブロンドの髪の間から、長く尖った耳が伸びていた。
彼女達はエルファという人間に似た生物だった。
エルファと人間は非常に近い生物であるが、その長く伸びた耳によって一目で見分けることができた。
「バーロー。」
コナンがそう言うと、歩きながら前を向いた。
「成長が止まった感じか。」
隣を歩いていたエバがコナンに聞いた。
「まあ、そんな感じかな。」
「医者には見て貰ったのか?」
「一度ね。月と星々の位置が悪かったせいで、体を流れる体液の調和が壊れてしまったらしいぜ。」
コナンが横目でエバを見た。
「そうか。」
エバが目を瞑ると肩をすくめた。
「まあでも、大体分かってるんだ。」
「ほお。」
エバがコナンを見た。
「小人さ、たぶんね。」
「小人?」
エバが分からない顔をした。
すると、後ろを歩いていたシェリルが言った。
「障害の1つさ。成長が止まってしまって、大人になっても小さなままなんだ。大きな街に行くとまれに見かけるね。」
エバが後ろにいるシェリルに顔を向けた。
「そうなのか。治るのか。」
すると一番後ろを歩いていたマーリンが口を開いた。
「今の医術では、治療法はないと思う。あとはまあ、神様に祈ることぐらいか。」
マーリンの耳も、マリーウェザーやアレンティーと同じように尖った長い耳をしていた。
マーリンとマリーウェザーとアレンティーはエルファの兄妹であった。
「そうか。」
エバは両腕を組むと頷いて見せた。
この時代の医術は、争いごとが多かったこともあり、矢の刺し傷、剣の斬り傷などを切り開き、矢じりや異物を取り除いた後、ワインで消毒し、卵の白身で傷を塞ぐ外科的処置は頻繁に行われたが、内臓などの身体内部の疾患については、サリカ神殿や主婦が自宅で栽培するハーブを料理に混ぜたり、煮詰めてシロップにして飲んだり、布に包んで巻き付けたりするハーブ治療がほぼ全てだった。
医者はハーブ治療以外に、夜空に浮かぶ月や星々が体に与える影響や、食事の食べ物を変えることで体に流れる体液を整えることを患者に指導したが、患者に安心感を与える以上の効果はなかった。
アヘンを使用して体の感覚を失わせ、腹を切り開いて詰まっている石を取り除いたり、お腹から出て来られなくなった赤ちゃんを取り出したりすることも行われたことはあるが、とても危険が伴うし、そもそもそのような技術を持つ者は滅多にいなかった。
故に、ハーブ治療が効果がない場合には、できることと言えば神に祈りを捧げるくらいしか方法がなかったから、ちょっとした風邪であっても、こじらせれば命を失う危険性がこの時代にはあった。
「そろそろ広い道に出るぜ。」
コナンが歩きながらそう言った。
エバたちは馬車が2台並んでもさらに余裕がある程度の広さがある道に出た。
「本当に詳しいな。」
エバが感心した様子で頷いた。
「街の周辺はほぼ知り尽くしているからな。」
「ほう。」
「コナンはガヤンの使用人として働いていたのよ。」
後ろを歩いているランがそう言った。
ガヤンというのは正義と法の神であり、その神の教えを実践している信者達は、そのガヤンの法を犯す悪人を捕まえ、法の前で裁く権限を国王から与えられていた。
コナンはそのガヤンで雇用されている使用人ということだった。
「ガヤンのメグレ神官長が味方になってくれたのは、そういう事なのね。」
エバの隣を歩いていたソフィがそう言って頷いた。
ソフィは馬を曳きながら歩いていた。
メグレ神官長は、ランが魔女として火あぶりにされそうになった時、コナンと一緒にランを助けようと味方になってくれたのだ。
「メグレ神官長には感謝してるさ。仕事がなかった俺を雇ってくれたからな。でも俺だって、メグレ神官長に協力して、たくさんの事件を解決してきたんだぜ。」
「へえ、すごいね。使用人なのにさ。そんなに仕事ができるんだ。」
シェリルが感心したように頷いた。
「でもそのせいで、ブラックマン総監の恨みを買ってしまったけどねえ。」
ランが目を細めてそう言った。
「しょうがねえだろ、悪い事してるのが分かっちまったんだから。許せるかよ。でもよ、そもそもブラックマン総監に目をつけられたのは、ランがブラックマン総監の用心棒を一発で伸しちまったせいだからな。」
コナンが目を細めて後ろのランを見た。
「だって女性のこと馬鹿にするんだもの、しようがないじゃない。馬鹿にしているわりに一発でうずくまってしまって、情けない奴だったわ。」
「なかなか破壊力のある方たちですね。」
一番後ろを歩いていたマーリンが苦笑いを浮かべた。
「やれやれ、たくましいのがまた増えたな。」
エバがそう言うと、隣を歩いているソフィをチラッと見た。
するとエバの視線に気付いたソフィが目を細めた。
「ん?どうしたの?今、私をチラッと見たよね?」
するとエバは被りを振った。
「虫かなあ。虫が飛んでいたかなあ。」
エバがとぼけて見せた。
するとソフィは、エバのほっぺたを摘まむとぐーと引っ張った。。
「本当だ。こんなところに虫が付いていたよ。びっくり。」
エバがマリーウェザーとアレンティーにその顔を向けた。
「気を付けろ。目を合わせただけなのにつねられることも、人生にはあるぞ。」
エバの顔を見て、マリーウェザーとアレンティーが可笑しそうに笑った。
エバたちは、誰も歩いている人もいない広い山道を進んでいた。
「この道、山道なのにやけに広い。」
アレンティーがシェリルにそう言った。
「本当だ。それなのに私たち以外に誰も歩いていないな。」
シェリルがアレンティーを見た。
「10年前はこの道が本道だったのさ。」
コナンが歩きながらそう言った。
「へえ、今は本道じゃなくなったのか?」
シェリルが尋ねると、隣を歩いていたランがシェリルを見た。
「橋ができたのよ。ここから北に向かうと深い谷があるんだけど、昔は橋が無かったから、旅をする人はみんな谷を迂回して山を越えて行ったの。その迂回する道が今歩いているこの道なのよ。橋が出来たらみんな橋を利用するようになって、この道は本道ではなくなったの。」
「なるほどね。でも、それにしてはちゃんと道が残っているよね。」
シェリルがそう言ったとおり、道はしっかりと踏み固められていた。
「この先にいくつか農村があるからさ。旅人は利用しなくなっても、村の人々にとっては、街に出るための重要な道だからな。」
コナンがシェリルの疑問に答えた。
「そうか、なるほどね。」
シェリルが納得したように頷いた。
すると、マリーウェザーが何かに気付いた。
「本当だ。村の人がいるね。」
マリーウェザーが道の先を指差した。
「確かにな。子どもか?」
エバもそう言った。
道の端で小さな人影が座り込んでいた。
するとコナンが顎に手を当てた。
「いや、こんなところに村の子どもがいる訳はない。子どもが遊ぶにしては村から遠すぎる。」
エバたちが歩いて行くと、やはり子どもだということが分かった。
5、6歳くらいだろうか、道の端に座り込んでいた。
汚れたボロ布のような麻のチュニックを被っていた。
髪はぼさぼさで、両足は裸足だった。
「ああ、山賊の子か。」
コナンが子どもを見てそう言った。
「知っているのか。」
シェリルが尋ねた。
「まあね。さっきも言っただろ、この辺りの道には詳しいって。」
「山賊が出るの?この道。」
ソフィが驚いた顔をした。
「今から18年前、南の青の帝国が神聖王国へ進撃するという大きな戦争があったんだけど、その戦争が終わったら、戦争に参加した兵士が仕事を失っちまって、たくさんの失業者が出ちまった。それでという訳でもないんだろうけど、ここから北にある深い谷に橋を架けるという大工事が始まって、失業した兵士もそっちに流れた。でも10年前にその大工事も終わっちまって、また失業者に戻っちまった兵士がこの山に棲みついたらしいぜ。」
コナンがそう説明すると、ソフィがまだ分からない顔で聞いた。
「でも、この道って本道じゃなくて脇道でしょ?山賊をやるなら、獲物が多い本道を縄張りにする方が儲かるんじゃないの?」
「そんなの当たり前だろ。だからさ、この山にいる山賊は、本道の山賊連中からつまはじきにあったようなちんけな連中だってこと。だいたいこの道は、農民しか通らないんだぜ。襲ったって金目の物が手に入る訳がない。自分たちの食糧がなくなると、食糧目当てに農民を襲っているようなケチな奴らさ。」
コナンがそう言って手の平を見せた。
「その山賊の子、という訳か。」
シェリルがそう言って座り込んでいる子どもを見た。
「みんな、ちょっと止まって。エバ、マーリン。」
シェリルが手を上げて立ち止まると、エバとマーリンに声を掛けた。
「ああ、大丈夫じゃないか。」
エバが周りを見渡してそう言った。
「不審な様子は無いですねえ。」
マーリンがそう言って首を左右に振って見せた。
マーリンは魔法の目を使って、上空から山道を見下ろしていたが、不審な人影は見当たらなかった。
マーリンは魔法使いなのだ。
「そっか。」
エバたちはまた山道を進み始めた。
するとちょうど子どもの横を通り過ぎようとした時だった。
パタン。
子どもが体を横にして地面に倒れた。
「倒れたね。」
マリーウェザーがそう言って立ち止まった。
子どもは薄目を開けてエバたちの方を見ていた。
「大丈夫かしら。」
アレンティーが心配そうな顔をした。
「マリーウェザー、アレンティー、不用意に近付いちゃだめだ。マーリン。」
シェリルがそう声を掛けると、マーリンは頷いた。
そしてマーリンは少しの間じっとして子どもを見つめていると、みんなに顔を向けた。
「大丈夫。変な病気にかかっている訳ではなさそうだ。お腹が空いているんだろう。何日も何も口にしていないようだ。」
マーリンの言葉を聞いて、マリーウェザーがシェリルを見た。
するとシェリルはマリーウェザーに微笑んだ。
「大丈夫、すぐに死んだりはしないさ。私たちに甘えているんだよ。お腹が減って死にそうだってね。でも・・・、子どもは親に甘えるものだし、甘えていいんだよ、子どもなんだからね。」
シェリルは横になっている子どもを改めて見た。
手足が針金のように細かった。
明らかに成長に必要な栄養が不足していた。
コナンと比べても一回りも二回りも小さかった。
あの時と一緒だ。シェリルはそう思った。
少年のその姿が、シェリルの右手にあの時の感覚を蘇らせた。
それは初めてマリーウェザーの手首を握ったときのことだ。
シェリルは、その手首のあまりの細さに衝撃を受けた。
それはマーリン兄妹と初めて会って、間もないときのことだった。
そしてマリーウェザーは、自分が異常なまでに痩せ衰えてしまっていることに気付いていなかった。
異常なまでの細さと、そのことに全く気付かず、普通のことのように振る舞うマリーウェザーの違和感に、シェリルの心は大きな不安に包まれた。
幼い時に十分な栄養も摂れず、相当辛い経験を重ねて来たのだろう。
シェリルは自分の心臓が誰かにぎゅうっと握られているような感触がして苦しかった。
その時の苦しい感覚が蘇って来て、シェリルの胸を締め付けた。
シェリルはコナンを見た。
「ここから一番近い村までどの位だ。」
「あと2時間位だね。今日はその村で一泊しようと考えている。」
「わかった。」
シェリルはそう言うと、みんなを見渡した。
「どうだろう、この子に夕食を食べさせてあげようと思うが、一緒に連れて行ってもいいかな。」
するとエバが目を瞑ると肩をすくめた。
マーリンも口をへの字に曲げると、しようがないという表情を見せた。
マリーウェザーとアレンティーも小さく頷いた。
その場の雰囲気が、子どもを連れて行ってもしようがないという雰囲気に包まれた。
その時だった。
「悪いけどさ、ガヤンで働いていた俺から言わせて貰えば、止めた方がいいと思うぜ。」
コナンがそう言ってみんなを見渡した。
「そんな山賊の子なんか助けたって誰のためになるって言うんだ。ロボルの街の人間だって、この辺りの村の人間だって、迷惑な山賊の子どもが死んだからって悲しむ奴なんかいやしない。よっぽど死んだ方が喜ぶだろうぜ。どうせろくな大人にならないんだろうからよ。」
「ちょっと、コナン。」
ランがコナンに声を掛けた。
「そりゃあシェリルさんのお節介には感謝してるさ、それで俺もランも助かったんだからさ。でもよ、俺たちが今やらないといけない事は、早くブラックマン総監の勢力圏から抜け出すことだろう。厄介ごとを抱え込んじまってどうするのさ。山賊たちが追って来るかも知れないぜ。冷静に考えてくれよ。」
すると以外にも、一番後ろにいたマーリンが口を開いた。
「コナンさん。私は冷静に考えていますよ。それでも私は、シェリルに賛成です。コナンさん。あなたは、子どもの時に何日もご飯が食べられなかった事はありますか?」
「それは・・・、ねえけどよ。」
マーリンが小さく頷いた。
「それは幸運でしたね。でも、私はあります。子どもの時に何日も食べられなかった事がね。だから分かるんですよ。どんなにみじめで悲しいのか、という事が。」
マーリンの言葉に、コナンは言葉を失った。
「コナン。」
今度はシェリルがコナンに声を掛けた。
コナンはシェリルを見た。
「お前さっき、この子どもの事を知っていると言っていたな。」
「ああ、まあね。」
「何で助けてやらなかったのだ。」
「助ける?」
コナンが驚いた表情を浮かべた。
シェリルの言葉で、コナンの頭の中に、あの時の記憶が鮮明に蘇った。
コナンは口を開いた。
「俺だって、助けようとしたことはあったさ。でも、メグレ神官長は首を縦には振らなかった。そりゃそうさ、ガヤンはロボルの街の治安を守るのが仕事だからな。それに山賊の子どもが死んだって、何の問題にもなりはしない。ガヤンにとっては、街の人間でもなく、村の人間でもない者など、人間扱いする価値もないのさ。それなのに俺が我儘を通せば、規則違反になる。同じガヤンの仲間に迷惑がかかる。余計な仕事が増える。下手をすれば、俺が職を失う。」
コナンはそう吐き捨てると視線を伏せた。
ガヤンというのは正義と法の神であり、その神の教えを実践している信者達は、そのガヤンの法を犯す悪人を捕まえ、法の前で裁く権限を国王から与えられていた。
だがそれは、街の治安を守るため、街の住人を守るためであったし、法律を犯した者を捕まえて罰金や財産を徴収することも大きな目的だった。
だから、街の住人ではなく、助けても金にならない山賊の子など、ガヤンが助けようとする訳がなかったのだ。
「良く分かっているじゃないか。」
シェリルがそう言ってコナンに微笑んだ。
「えっ。」
コナンが驚いた様子でシェリルを見た。
「今のお前は、ガヤンじゃないだろ。」
エバもそう言ってコナンを見た。
「助けようとしてくれたんですよね。」
マーリンもコナンを見た。
「お前がせっかく一つの命を救おうというのに、それを徹底的に阻止しようとするガヤンという組織は、とんだクソ野郎集団だな。」
シェリルがそう言うとコナンに向かってニヤリと笑った。
「ぶっ、はははははは。」
コナンは思わず声を上げて笑った。
「笑っているということは、お前だってそう思ったんだろう?」
コナンは笑い終えると、シェリルを笑顔で見上げた。
「シェリルさん、最高だぜあんた。そうさ、俺がせっかく助けようとしているのに、あいつらできない言い訳ばっかり言いやがって。その時俺は心の中でこう思ったんだ。このガヤンという組織、クソだなってね。」
コナンの言葉に、今度はシェリルが大声を上げて笑った。
「お前はちゃんと挑戦したじゃないか。子どもを助けようとして挑戦した。それでもダメだったんだ。だから何もそんなに自分を卑下する必要はない。クソ野郎は、言い訳ばかりしているガヤンの奴らさ。規則を破る事が何だというのだ、規則を破って一人の命を救ったとして、一体だれが咎めると言うのだ。そもそも、規則のせいで人の命が助けられないのだとしたら、それは規則がおかしいということだろう。そんな当たり前の事も分からないのは、ただのクソ野郎さ。なあ、みんな?」
シェリルがそう言うと、マリーウェザーとアレンティーを見た。
するとマリーウェザーとアレンティーは苦笑いを浮かべた。
「本当ね。でも、クソ野郎はちょっと下品かな。」
マリーウェザーがそう言ってニコッとした。
するとアレンティーが首を傾げると言った。
「・・・うんち男たち?」
アレンティーの言葉に、シェリルはまた声を出して笑った。
「それは失礼だろう。」
シェリルがそう言うと、みんなで声を出して笑った。
一しきり笑ったところでシェリルはコナンを見た。
「私たちはね、自分の生きたいように生きているのだ。お前とランを助けたのも、助けたいと思ったから助けたのだ。だから私たちは、私たちが助けたいと思えば、助けるんだ。」
シェリルはニッと白い歯を見せると笑顔を向けた。
「お前だって助けたいと一度は思ったのだろう?それにもうお前はガヤンではないし、ロボルの街に戻るつもりもないのだ。お前を縛り付けるものはもう何もないのだぞ。そうであれば、自分の好き勝手に生きて何が悪い?」
シェリルはコナンに右手を差し出した
「一緒にこの子を助けてやろうじゃないか。」
コナンはシェリルを見つめると、フッと小さく笑って目を瞑った。
「好き勝手に生きるねえ。面白いじゃねーか。」
コナンは目を開けるとシェリルの手を握った。
「いいぜ、楽しみになって来た。だったら俺だって好き勝手にやらせて貰うからな。後で迷惑だとか言わないでくれよ。」
そう言ってコナンがニヤリと笑みを浮かべた。
するとシェリルがそんなコナンを見てフフッと笑った。
「だから止めてくれって、俺17歳だって言ってるだろう。」
「ごめんごめん。だって可愛いからつい。」
すると側にいたアレンティーが控えめに言った。
「小さいのに、生意気可愛い。」
「バーロー。」
コナンがそう言って、シェリルから手を離すとそっぽを向いた。
そんなコナンの態度を見て、みんなで声を出して笑った。
その男は隊長と呼ばれていた。
それは実際にその男が、戦争において小隊長を務めていたからだ。
その戦争では、兵士が何万人も徴集される程大きな軍隊が編成されたので、読み書きも出来ないような馬鹿な男でも、小隊長を任された。
戦争に勝っていたあの頃は良かった。
敵を殺して、家々に押し入り、金目のものを奪った。
うまい肉を食って、酒を呑んだ。
今日は何を奪い取ったか、お互いに自慢し合った。
みんなで女をまわして、騒ぎまくった。
勝利した喜びをみんなで分かち合った。
最高だった。
男は目の前でめらめらと燃える焚火の炎を眺めながら、あの頃を思い出していた。
戦争が負け始めると、男は、気の合う仲間とつるんでさっさと戦場から逃げ出した。
戦争は勝たなければ儲けにならない。
敗ける戦争に命をかけて戦うなど馬鹿がやることだ。
男は戦場から逃げ帰ると、戦争で稼いだ金を街で派手に使った。
酒と賭博と女だ。
街の人たちからは羽振りのいい旦那としてちやほやされた。
ちやほやされると気分が良かった。
仲間と一緒に、街の大通りを我が物顔で横に並んで歩いた。
その頃の生活も楽しかった。
「隊長、ボニーが見つからないぜ。」
ボサボサの髪に伸ばしっぱなしの髭面、原始人のような男が現れて、声を掛けてきた。。
「ちゃんと探したのか。川の上流の方は。」
隊長と呼ばれた男は髭面の男に顔を向けた。
「探したぜ。いなかったよ。死んだんじゃねえの。」
原始人のような男とは別の男が現れてそう言った。
ボサボサの髪を麻ひもで結んでいた。
「死んだんなら死体があるだろうが。農道の方に行ったんだろう。そっちを探してこい。」
「なんだと、おら!」
髪を麻ひもで結んだ男が凄んで見せた。
頭の悪い連中だ。
隊長の男は立ち上がると麻ひもの男に近付いた。
そして麻ひもの男の髪の毛を掴むと乱暴に振り回した。
「いいか、村の連中は俺たちのことを信用してねえんだ。商売をするには信用が大事なんだ。それにはガキを連れている方がいいんだよ。分かったか。」
隊長の男は麻ひもの男の頭を散々引っ張り回してから、ようやくその手を離した。
麻ひもの男と原始人の男は、隊長の男に背を向けると歩き出した。
そして離れたところにいる別の男たちと一緒に森の中を歩いて行った。
隊長の男が言っていた商売とは、人身売買だった。
男たちがいる神聖王国のお隣の国、青の帝国では、まだまだ帝国の拡大に力を入れていて、軍隊の増強、城や宮殿などの拠点整備、軍隊の行軍が可能な道路の整備が行われており、たくさんの奴隷を周辺の国々から輸入していた。
成人した大人の奴隷も重労働をさせるためにたくさん必要であったが、7歳程度の少年少女であっても、軽労働者としてたくさん必要とされていたのだった。
そこで農村では、子どもが大きくなると、現金収入を得るために奴隷商人に売り払うということが行われていた。
奴隷の子どもは親と同じく奴隷であったので、奴隷の主人が奴隷の子どもを売り払うことは可能だったし、奴隷ではなくとも、貧しい生活をしている農民の中には、その貧しさゆえに子供を売り払うということがあった。
豊穣の神であり、友愛の神でもあるサリカ神の神殿では、奴隷に暴力を振るうことを禁じてはいたものの、雨が降らなかったりして小麦が取れなくなると、生活の貧しさから密かに子どもを売り払うということがあったし、神殿もしようがないこととして黙認していたのだった。
隊長の男は、農村から子どもを引き取ると、街まで連れて行って奴隷商人に引き渡し、その手間賃を稼ぐという商売をしていた。
だが、隊長の男は不満だった。
こんなちまちました仕事はやりたくなかったのだ。
本当は高級品をたくさん運んでいる商人を襲って、一気に大金を稼ぎたかった。
だから新しい橋が出来上がって、立派な広い道が整備されると、その縄張り争いに名乗りを上げた。
だが、縄張り争いで負けて、仲間がたくさん死んだ。
自分も大きな傷を負った。
そしてこの森に逃げ帰って来た。
橋が出来上がると、わざわざ山を越えて行かなければならないこの道を通る獲物なんていなくなった。山賊なんて商売は成り立たなくなった。
そんなぎりぎりの状況で、何とかありついたのがこの商売だった。
文句が言える立場ではなかった。
だが、とてもではないがこの商売の手間賃では、隊長の男とその仲間4人で生活していくのには全く金が足りていなかった。
「くそ!俺たちは死ねってことかよ!」
隊長の男は思わず悪態をついた。
「また大きな戦争でも起こってくれねえかなあ。」
隊長の男は最高だったあの頃を思い出しながら、そう呟いた。
それにしても、あのガキはどこに行ったのだろう。
隊長の男には息子が1人いた。
別に作りたくて作った子どもではなかった、たまたま馬が合った馬鹿女がいて、一緒にいたら子どもが産まれたのだ。
だが、その馬鹿女はもういない。
子どもだけ残して逃げていなくなった。
隊長の男は子どもを何とも思っていなかった。
けれど、殺すのはダメだと思っていた。
隊長の男の親父が言っていたのだ。
親が子どもを殺すのはダメだと。
理由は分からなかったが、何となくダメな気がした。
だから、子どもを殺さずに放っておいたのだ。
すると、この人身売買の商売では、ガキがいた方が都合が良かった。
ガキがいると客も何となく安心するし、少年少女を連れて行く時にも、大人しく言う事を聞く気がした。
親父の言ったことが役に立った。
まあ、人身売買するために言ったのではないだろうが。
隊長の男の息子ボニーは、この3日間姿を消していた。
腹が減って食い物を探しているのだろうが、そろそろ戻って来てもいい頃ではないか。
隊長の男とその仲間たちは、自然の洞窟に隠れ住んでいた。
その洞窟の中では声が反響するので、ボニーは良く洞窟の中で大きな声を出して遊んでいた。
だが3日前のこと、腹が減っていらいらしているのに、止めろと言っても騒ぐのを止めないので思いっ切り腹を蹴り飛ばして追い出してやったのだ。
言う事の分からない馬鹿な奴には、体で覚えさせる必要がある。
俺の言う事を聞かなければどうなるか、存分に思い知るがいい。
しかもこれが初めてではない。
これまでも何度も罰を与えて来たのに、まだうっかりと騒ぎやがる。
馬鹿は罰を与えられてもしようがない。
二度と忘れることがないよう、体に刻み込まれるまで、粘り強く何度でも罰を与え続けてやる。
子どもが言う事を聞かなければ罰を与えて無理矢理言う事を聞かせる。
それが親の役目というものだ。
隊長の男は焚火の炎を眺めながら、目を細めてニヤリと笑みを浮かべた。
エバたちは、山道を上がったり下ったりしながら、今日一泊する村に向かって歩いていた。
エバたちは、持っていた固いパンに水をふくませてふやかすと、山賊の子どもに食べさせた。
「私たちと一緒に来たら、もっと美味しい物をお腹一杯食べさせてあげるよ。」
シェリルがそう言うと、山賊の子どもは小さく頷いた。
そしてシェリルと手を繋いで一緒に歩き出したのだ。
「村についたら何を食べようか。」
シェリルが山賊の子どもに聞こえるようにそう言った。
「干し肉があるから、それを茹でて柔らかくしてから、ナイフで細かく切って鉄鍋に入れよう。干し肉は豚さんだよ。」
シェリルがそう言っても、山賊の子どもは何も言わなかった。
「それから農家の人から野菜を分けて貰って、リーキと人参がいいかな。それも細かく切り刻んで鉄鍋に入れちゃおう。」
するとマリーウェザーが後ろから口を出した。
「だったら私はミルク煮がいいなあ。」
シェリルは笑顔でマリーウェザーを見た。
「それなら、農家の人から牛乳とパンを買おう。固いパンでも、ミルクで煮れば柔らかくなってとっても美味しいよ。」
「美味しそう、楽しみ。」
マリーウェザーが笑顔になった。
「塩と胡椒は持っているから、そこにハーブを加えて、味を整えれば完成だ。」
「何だかお腹が減って来ちゃった。」
アレンティーも笑顔になった。
するとコナンが山賊の子どもに近付いた。
「僕コナンって言うんだ。君の名前は?」
コナンが話し掛けたが、山賊の子どもはおどおどした様子で答えなかった。
「兄弟はいないの?」
コナンがまた話し掛けたが、山賊の子どもは黙ったままだった。
「ねえねえ、豚って知ってる?」
コナンがもう一度話し掛けたが、やっぱり返事をしなかった。
「けっ、同年代風に話し掛けたのに無視されちまったぜ。」
コナンがそう言ってそっぽを向いた。
「もうばれっちゃってるのよ。今更可愛い感じにしたって怪しまれるだけよ。」
ランがコナンに苦笑いを向けた。
「だけどこの子、暴力を受けてるぜ。」
「えっ。」
ランが不安な顔になった。
「この子のあばらの辺り、黒いあざになってる。殴られたか、蹴られたか。」
コナンの言葉にみんなが静かになった。
「まあ、そんなところだろうな。こんな小さな体をしているのに、許せないな。」
シェリルが静かにそう言った。
「ねえ、豚さん知らない?見たことないの?」
マリーウェザーが子どもに話し掛けた。
「鼻がこんな感じで、ブウブウ、ブウブウって鳴くんだよ。」
マリーウェザーが豚の物真似をした。
「私は牛さんよりも豚さんの方が好きだな。ブウブウって鳴き声も可愛いし、森の落ち葉に鼻を突っ込んで、ガサガサ歩き回って何でも食べちゃう。すぐに大きくなるし、赤ちゃんもたくさん産むんだよ。ブウブウって。しかも食べても美味しいんだから。私は豚さん大好きだよ。」
シェリルが笑顔でそう言った。
すると、一番後ろを歩いていたマーリンが言った。
「この子は、豚という言葉を知らない。教えられていないんだ。」
「そうか・・・、名前は?兄弟は?」
シェリルがマーリンに尋ねた。
「名前かどうか分からないが・・・ボニーと呼ばれている。他に兄弟はいないようだ。」
「ボニー?」
シェリルが分からない顔をするとマーリンが言った。
「骨(ボーン)みたいにガリガリに痩せているからだろう。」
「なるほど。」
シェリルが歩きながら目を下に伏せた。
「マーリンさんは何でそんなことが分かるんですか?」
コナンが不思議そうな顔をした。
「あれは全部マーリンの妄想さ。」
エバがコナンにそう言った。
「妄想?」
「ああ、妄想。でも、結構当たるんだぜ。」
エバが目を瞑ると肩をすくめて見せた。
「ふうん、妄想ねえ。」
コナンは目を細めて後ろを歩いているマーリンを見た。
「もう、そういうこと言うなよ。」
マーリンがそう言ってエバとコナンを見た。
エバとコナンが沈黙した。
するとエバが言った。
「空気読めよ。ふざけている場合じゃないだろ。」
「お前が言うな!」
マーリンがそう抗議した。
「でもさあ、この子がどんな生活を送っているのか、大体分かったな。もっとも、山賊の子の暮らしがどんなにひどいのか想像はつくけどよ。靴も履いていねえし、奴隷かよ。」
コナンが吐き捨てるように言った。
この時代、奴隷は靴を履かせて貰えなかった。
一目で奴隷と分かるように、靴を与えられないことが普通だったからだ。
この子どもは裸足だった。
この辺りは冬になると、一面雪に覆われるというのに。
「可哀そうね。」
ランがそう言ってコナンを見た。
「まあね。だけど、この子はきっとそうは思っていないぜ。」
「どうして?」
ランが分からない顔をした。
「どうしてか。それは、この子どもにとっては、この可哀そうな暮らしが普通になっちまっているからさ。」
コナンがそう言うと、それを聞いたシェリルが頷いた。
「そのとおりだな、コナン。」
シェリルはそう言うと、すぐ後ろを歩いているマリーウェザーとアレンティーを見た。
「子育てというのは、街や村に住んでいれば、街の人、村の人がお互いに助け合って行うものなんだ。例えば、おっぱいが出ないママは、おっぱいが出るママにお乳を分けて貰う。おっぱいが飲めないという事は、赤ちゃんが死ぬという事だからね。赤ちゃんが2歳を過ぎてゆりかごから飛び出す年齢になると、年長の子どもが幼い子の面倒を見てくれる。ママは日中仕事をしていて子どもの面倒を見ることができないから、子ども同士で面倒を見るようにしているのだ。そうやって子ども同士で遊んでいく中で、自分が住んでいる街や村の事をなんとなく理解していく。そしてママとパパが一生懸命働いたお金で、子どもに食べ物や、着るものや、靴を与える。また、街や村のサリカ神殿では、サリカ神のお話を子どもにいろいろ話して聞かせる。そのお話を聞いて子どもたちは、困った人には手を差し伸べなさいとか、欲張らずに周りの人に分け与えなさいとか友愛の精神を学ぶのだけど、同時にいろいろな言葉も学ぶ。」
この時代、街でも農村でも、ママはたくさんの仕事を抱えていた。
家事をするにしても、洗濯を全て手作業で行わなければならない、衣服を縫うためには糸を紡がなければならない、料理は全て下ごしらえから始めなければならない、そんな時代だった。
もちろん家事だけではない。金を稼ぐために、街でも農村でも、ママはパパと一緒に働いた。
だからママに選択する余地などはなくて、ママが子育てだけに専念する時間など持つことはできなかったのだ。
だから逆に、街でも村でも、仕事をしながらでも子育てができる環境をママたちは作り上げていた。
困ったときはママ同士で助け合う。
たまに手が空いたママがいれば、子どもの面倒を見て貰う。
そして、子どもは子ども同士で面倒を見るようにさせていた。
ママが手を掛けられない分、子ども同士の遊びの中で、友達と仲良くする方法や、住んでいる街や村の近道や裏道、秘密の場所、優しくしてくれる人、恐い人、怪しい人、などなど、たくさんの事を学んだ。
そして周りの大人たちも、自分が子どもの時はそうやって育てられたので、子どもは存分に遊ぶもの。遊びの中で学ぶものと理解していたから、子どもたちは街や村中を好きなだけ走り回って遊ぶことができたのだ。
確かに、親の目が行き届かないことで、悲惨な事故が起こる事があった。
この時代、子どもの事故を防ぐための工夫がされているものなどなかったから、周囲にあるあらゆるものが、子どもの突拍子もない行動によって、思いもよらない事故につながる可能性があった。
そんな悲しい事故が起こった時にはママ同士で慰めあった。
サリカ神の神官も、どうしようもなかったことだと、ママを励ました。
残念ながら、そのような不幸な事故を未然に防ぐことはとても難しかったし、それに、そのような事故だけでなく、謎の病気や飢饉や災害や戦争と、子どもたちの命を脅かすどうしようもないものは、他にもたくさんあったからだ。
つまり、ママを励ましている他のママたちも、子どもを失っていたのだった。
また、この時代、教育というのは神学の事だった。
どの街や村にもサリカ神殿があって、その神殿では、サリカ神に仕える神官が子どもたちにサリカ神にまつわる様々な物語を教え聞かせた。
その目的は、サリカ神殿が世界の多くの人々に受け入れられ、根付き、大きな影響力を持つためであり、サリカ神殿の偉くて賢い人たちが考えた戦略であった。
だが街や村で子どもたちに教え聞かせていた現場のサリカ神の神官たちは、以外にも、そんな戦略の事などすっかり忘れて、子どもたちを正しい信仰に導こうと、一生懸命だったのである。
サリカ神の神官は分厚い教典を持っていて、そこに書かれている物語を自分なりに読み解きながら、子どもたちに様々な事を教えた。
この世界がどのようにつくられ、人がどのように生まれたのか。
サリカ神がどのように現れたのか。
そしてサリカ神がどのように人々を救ったのか。
洪水が起こったり、飢饉が起こったり、疫病が流行した時に何が起こったのか。
分厚い教典に書かれている物語の中には、太陽が地球の周りを回っているという話も書かれていたから、この時代の人々は疑いもせずに太陽が地球の周りを回っていると信じていた。
もっとも人々にとっては、太陽が地球の周りを回っていようが、地球が太陽の周りを回っていようが、どっちでも構わないことだった。
「そっか、こんな山に住んでいたら、誰も助けてくれないものね。」
マリーウェザーが頷いた。
「そうだ、誰も助けてくれない。そうなると、子育ては親だけが頼りだ。だがこの山賊の子どもは、食べ物に餓えていて、靴も与えられず、言葉もろくに教えられていない。そのうえ、暴力まで受けている。親がまともに子育てできていないという事だ。食べさせるだけの金が無い、物事を教えるだけの教養がない、子どもには子育てが必要だという事を理解していない。でもね、こういう悲惨な状況は、私たちの身近なところに普通にあるんだ。マリーウェザーもロボルの街の外で見ただろう。街の中にも入れず、自分の住居を持つことも出来ず、今日食べるものさえ困窮している乞食の人々を。」
「あっ。」
マリーウェザーの顔が何かに気付いた顔になった。
「あの人たちも一緒さ。金が無い、教養も無い、子育てができない人たち。だから大人になって子どもが産まれても、自分と同じようにほったらかしにする事しかできない。だがそれはしようがないことだ。だって、自分だって子どもの時に親から大切にされたことがないのだから。」
シェリルはマリーウェザーとアレンティーにニコッとした。
「だから私は、この山賊の子どもに、人から大切にされるということを経験させてあげたいのだ。」
マリーウェザーは、シェリルの言葉が自分に向けられているのだと分かった。
マーリンとマリーウェザーとアレンティーは3人兄妹だった。
マーリン兄妹には両親がいなかった。
3人はエルファの森に居場所はあったが、乞食のように食べ物を恵んで貰っていた。
災害が森を襲って食べ物が少なくなると、途端に施しはなくなって、食べられなくなった。
あまりの空腹と寒さで、体が勝手にぶるぶると震えた。
人に大切にされた覚えなどなかった。
だからマリーウェザーには、この子どもが何を考えているのか想像がついた。
お腹減った。辛い。苦しい。何か食べたい。
この子どもが考えていることは、ただそれだけだ。
あとは何も考えられない。
でも、子ども時代の思い出が、お腹が減った思い出ばっかりだとしたらとても寂しい。
私と一緒になってしまう。
だったら。
「シェリル姉さん。」
マリーウェザーがシェリルに声を掛けた。
「私も手伝うから。」
マリーウェザーが右手を小さく拳を握って見せた。
「シェリル。」
今度はアレンティーが声を掛けた。
「私もいるよ。」
アレンティーもそう言ってニコッとした。
「ありがとう。」
シェリルの顔が笑顔になった。
「なるほど。こうやってシェリルさんのお節介が始まるという訳ね。」
コナンが肩をすくめた。
「なによ、コナンだって助けてあげるつもりなんでしょう。」
ランがコナンに言った。
「俺は、俺のやり方があんの。さっきも言ったろう。好き勝手にやらせて貰うって。」
「それって、ただ素直じゃないだけなんじゃないの?」
「バーロー。」
コナンがそう言って、歩きながら腕を頭の上で組んだ。
「おい、あれ、ボニーじゃねえか。」
ボサボサの髪に伸ばしっぱなしの髭面、原始人のような男がそう言った。
「ボニーだな。」
長い髪を麻ひもで結んだ男が頷いた。
山賊の男たちだった。
森の茂みの陰から、山道を歩いているエバたちを見ていた。
シェリルと手を繋いで歩いているボニーを見つけた。
「珍しいな。」
「珍しい。」
山賊たちはそう言い合って頷いた。
農民以外の連中がこの道を通ることなど滅多になかったからだ。
「何だ、あいつら。」
「分からねえ。」
男はエバとマーリンの2人。
あとはシェリル、マリーウェザー、アレンティー、ソフィ、ランと女が5人。
子どものコナンが1人。
ボニーが1人。
商売人でも街の役人でもない。
山賊たちにはエバたちが何者なのか分からなかった。
「女が多い。」
「ああ、女が多い。」
山賊たちはエバたちを黙って見ていた。
「女、犯してえ。」
原始人の男がぼそっとそう言った。
原始人の言葉に他の山賊たちが可笑しそうに笑った。
金が無いので、街の売春婦のお姉さんからえっちなサービスをして貰うことなどできなかった。
この農道を通る農民たちも、警戒して集団でこの道を通るので、女を襲う事は容易なことではなかった。
しようがないので、山賊たちは山に放し飼いになっている家畜の豚を女の替わりにして、性欲を発散させていた。
「俺はおっぱいが大きい金髪の女がいいなあ。」
「俺は銀髪の女がいいなあ。」
「耳が尖っている女もいい。」
山賊たちは思い思いに妄想を膨らませた。
すると山賊の1人が言った。
「あの女たち、捕まえて売ったら高く売れるんじゃねえか?」
山賊たちが沈黙した。
「すげえ!」
「すげえよ。」
山賊たちが色めき立った。
山賊たちは金を持っていなかった。
金は全部隊長の男が握っていたからだ。
しかも目の前の女たちは、農村の女と違って垢抜けた感じで、高く売れそうな気がした。
「でもよ、それじゃあヤレねえじゃねえか。」
原始人の男が顔をしかめた。
「馬鹿だなあ、ヤってから売ればいいだろうが。」
髪を麻ひもで結んだ男がそう言った。
「ヤッてから売るううううう!」
原始人の男の顔が嬉々とした表情に変わった。
「そうだよ。ヤッてから売るんだよ!」
「すげえ!」
「お前、天才じゃねえか!」
山賊たちが嬉しさでピョンピョンとその場で跳び上がった。
「でもよ、隊長はどうするんだよ。隊長は良いって言うかな。」
すると髪を麻ひもで結んだ男が顔を歪めた。
「何で隊長が関係あんだよ。俺たちが見つけたんだから、俺たちの女に決まってんだろうが。」
「よっしゃあ!」
「うほっ!」
山賊たちはまたピョンピョンと跳び上がった。
「なあなあ、隊長がいなかったら、俺たち4人だろ。」
原始人の男が真面目な顔で聞いた。
「おお。」
「女は5人だよな。」
「おお。」
原始人の男の顔が満面の笑顔に変わった。
「余っちゃうよおおおおお!」
「はははは。」
山賊たちは腹を抱えて可笑しそうに笑った。
一しきり笑い終えると、山賊たちはお互いに顔を見合わせた。
「さっさと女をさらっちまおうぜ。」
「男は2人だけだし、そのうち1人はひょろひょろしてっから敵じゃねえ。」
「ぶっ殺してやる。」
今にも駆けだしそうな勢いで3人の山賊がそう言った。
すると髪を麻ひもで結んだ男が3人を制した。
「まあ待て、剣が使えそうな男が1人いるだろう。」
それはエバの事だった。
「ここで死んじまっても勿体ねえだろ。何とか、男を女から引き離して罠に掛けるんだよ。そうしたらその後は、楽しい鬼ごっこの始まりだ。」
髪を麻ひもで結んだ男がそう言うと舌なめずりした。
山賊の男たち4人は、山の中を走ってエバたちを先回りすると、小さな小川に到着した。
小川には、丸太を束ねて、それをいくつか繋いだ簡素な橋が掛けられていた。
この小川を越えるには、この丸太橋を渡るしか他に方法がなかった。
すると、髪を麻ひもで結んだ男の指示で、山賊の1人が丸太橋の上でうつ伏せになった。
1人は橋を渡ったところの丸太が乗っかっている石積みの陰に身を隠した。
髪を麻ひもで結んだ男は、橋は渡らずに、橋の手前で待機。
そして原始人の男は、女が逃げて道を引き返して行った時のために、さらに後ろの茂みに身を隠している。
作戦は簡単だ。
橋の上にうつ伏せになった男を見れば、誰でも不審に思うだろう。
そうすれば、まずは剣が使えそうな男が様子を見るために橋を渡ろうとするに違いない。
そうして剣が使えそうな男が橋の真ん中まで来たら、前と後ろから挟み撃ちにして、魚を捕まえる網を投げつけて動きを封じる。
あとは、網でもがいている男をナイフでめった刺しにして殺したら終わりだ。
男を殺したら、後は好きな女のケツを追っかけて楽しむだけだ。
山賊たちは息を潜めると、今か今かとエバたちが来るのを待った。
丸太橋から一番遠いところで茂みに身を隠していた原始人の男は、山道をエバたちが歩いて来るのが見えた。
原始人の男が茂みの陰からうかがっていると、山道を歩いて来たエバたちが、もう少しで原始人の男が潜んでいる茂みの前に差し掛かるところだった。
すると突然、先頭を歩いていたエバがバタンと倒れた。
何だ?
原始人の男が様子をうかがっていると、倒れたエバを囲んで女たちが慌てている様子だった。
すると、囲んでいる女たちの中から子どもが飛び出して、こちらに向かって山道を走って来た。
その子どもは、ボニーとは別の子どもだった。
走っている子どもがちょうど原始人の男の前を通過しようとした時。
子どもがふっと顔を横に向けると、原始人の男と目が合った。
子どもはコナンだった。
コナンは立ち止まると、原始人の男に話し掛けた。
「おじさん!大変なんだ!助けてよ!」
コナンは必死な形相で原始人の男に声を掛けた。
「どうしたんだ。」
原始人の男は何の考えもなく、軽い気持ちでそう言った。
「用心棒のお兄さんが倒れたんだ!このままだと死んじゃうよ!」
「何だって!」
原始人の男は茂みの中から山道に出て来た。
「お姉さんたちが、誰でもいいから連れて来てって。」
コナンが真剣な顔で原始人の男を見た。
原始人の男は丸太橋の方に目をやった。
だが、丸太橋までは結構な距離があるので、髪を麻ひもで結んだ男を見ることはできなかった。
「おじさん!早く!」
コナンがそう促した。
「ああ。」
しようがなく原始人の男は走り出したコナンの後ろを追いかけた。
コナンと原始人の男は倒れているエバの側に来た。
確かに、山賊たちが罠に掛けようとしたエバが地面にうつ伏せに倒れていた。
身動き一つしておらず、死んでいるようだった。
そして地面に倒れているエバの周りを、心配そうに女性たちが囲んで立っていた。
2人で抱き合って泣いている女もいた。
ヤッてから売ろうとした女たちだ。
近くで見ると余計に綺麗な女たちだった。
原始人の男は女たちを見ながら目をきょろきょろさせた。
女たちは原始人の男の周りに寄って来た。
その女たちの1人が原始人に話し掛けて来た。
「歩いていたら急に倒れて死んでしまったの。私たちにはどうしたらいいか。」
胸が大きい金髪の女だ。
原始人の男が気に入った女だった。
それはシェリルだった。
シェリルは両手の指を胸の前で組むと、原始人の男を見上げた。
「助けて。とても恐いの。」

シェリルに見つめられて原始人の男はどきどきした。
「ああ。」
原始人の男はもう一度、丸太橋の方に顔を向けた。
だが、仲間の山賊が見える訳も無かった。
しようがない。
原始人の男はそう思った。
だがそう思ってすぐに思い直した。
待てよ。
俺たちは何をしようとしていたんだ?。
原始人の男は髪を麻ひもで結んだ男の言葉を思いだした。
剣が使えそうな男を罠に掛ける。そうしたらその後は、好きな女のケツを追っかけて楽しむ。
剣が使えそうな男はもう死んだ。
という事は、あとは、・・・好きな女のケツを追っかけて楽しむ!
原始人の男は、見上げているシェリルの胸をじっと見つめると唾を飲み込んだ。
仲間の山賊を連れて来た方がいいだろうか。
だが、もう、我慢の限界だった。
「うがああああ!」
突然、原始人の男は唸り声を上げると、両手を広げてシェリルに抱き着こうとした。
「ハッ。」
「いああああ!」
原始人の男の左右に分かれて立っていたソフィとランが、瞬時に原始人の男を蹴った。
ソフィが右足を高く伸び上げると、原始人の頭を後ろから蹴り飛ばした。
ランはくるっと原始人の男にお尻を向けると、原始人の腹に踵をめり込ませた。
原始人の男は、前と後ろから蹴られた衝撃で、うつ伏せの格好で地面に激突した。
「あがあ。」
原始人の男はしばらくうつ伏せのままじっとしていたが、ようやく顔を上げると、足を震わせながら立ち上がった。
脳震盪を起こしたことで足がふらついていた。
「歩く肉穴のくせによお、・・・やってくれるじゃねえか。」
原始人の男が右手で額を抑えながらシェリルを睨んだ。
「絶対に許さねえ。お前ら全員ぶっこんで、ぐちゃぐちゃにしてやる。」
原始人の男がわざといやらしい笑みを浮かべた。
「汚ねえ肉棒ぶっこまれて、ニコニコ腰振ってりゃいいんだよ!」
原始人の男がそう言うと、ふらつく足でシェリルに近付こうとした。
すると、今まで泣いて抱き合っていた2人の女性が、パっとシェリルの方に振り返った。
マリーウェザーとアレンティーだ。
「シェリル姉さん!」
マリーウェザーがそう言って、胸の前で持っていた剣をシェリルに投げた。
シェリルは剣を受け取ると、受け取った勢いのまま鞘から剣を抜き放ち、原始人の男の喉元に剣を突き立てた。
!!
シェリルの剣は、喉元の窪んだところから喉を突き破ると、そのまま侵入して延髄を破壊し、首の後ろ側、うなじを貫通して剣先が飛び出た。
原始人の男は小刻みに体を痙攣させた後、立ったまま動かなくなった。
なかなか来ないな。
髪を麻ひもで結んだ男は苛立っていた。
そろそろ頃合いという時間になっても、エバたちが来る気配がなかった。
橋の上でうつ伏せになって待っている男がチラッと顔を上げてこちらを見た。
髪を麻ひもで結んだ男は手の平を下に向けて合図を送ると、橋の上でうつ伏せになった男も顔を伏せた。
おかしいな。
髪を麻ひもで結んだ男がそう思った時だった。
子どもがこちらに向かって山道を走って来た。
その子どもは、ボニーとは別の子どもだった。
走っている子どもがちょうど髪を麻ひもで結んだ男の前を通過しようとした時、子どもがふっと顔を横に向けると、髪を麻ひもで結んだ男と目が合った。
子どもはやはりコナンだった。
コナンは立ち止まると、髪を麻ひもで結んだ男に話し掛けた。
「おじさん!大変なんだ!助けてよ!」
コナンは必死な形相で髪を麻ひもで結んだ男に声を掛けた。
ちっ、見つかったか。
髪を麻ひもで結んだ男が心の中で舌打ちした。
計画が狂っちまった。何とか上手くやるしかねえか。
「どうしたんだ。」
そう言うと、髪を麻ひもで結んだ男が茂みから顔だけを出した。
「山賊に襲われたんだ!用心棒のお兄さんが刺された!」
「何だって!」
髪を麻ひもで結んだ男は思わず茂みの中から山道に出て来た。
「山賊ってどんな奴だ。」
「髪の毛がボサボサで猿みたいなやつ。いきなり茂みの中から襲って来たんだ。用心棒のお兄さんが剣で刺したんだけど、お兄さんも山賊にナイフで刺された。」
あいつだ。
髪を麻ひもで結んだ男はそう思った。
あいつとは当然、原始人の男のことだ。
あいつは我慢が出来ない男だった。
きっと、本物の女のケツが目の前でぷりぷり揺れたせいで、我慢が出来なかったのだ。
あいつならあり得る話だ。
「それで、山賊と用心棒はどうなった。死んだのか。」
「山賊は死んだ。用心棒のお兄さんはまだ生きてる。でも、このままだと死んじゃうよ!」
「そうか。」
なるほど。状況は悪くない。
剣を使えそうな男にとどめを刺せれば、考えていた作戦とは違うが、成功したも同然だ。
「お姉さんたちが、誰でもいいから連れて来てって。」
コナンが真剣な顔で髪を麻ひもで結んだ男を見た。
髪を麻ひもで結んだ男は丸太橋の方に目をやった。
仲間を呼んで連れて行くか?
いや、まだだ。
もし、剣を使えそうな男が以外にも元気だったら、初めの作戦どおり丸太橋で殺す必要がある。
ここは俺一人で行こう。
「おじさん!早く!」
コナンがそう促した。
「ああ。」
髪を麻ひもで結んだ男は走り出したコナンの後ろを追いかけた。
コナンと髪を麻ひもで結んだ男は、倒れているエバと原始人の男の側に来た。
山賊たちが罠に掛けようとした、剣が使えそうな男と原始人の男の2人が地面にうつ伏せに倒れていた。
身動き一つしておらず、死んでいるようだった。
そして地面に倒れている男の周りを、心配そうに5人の女性が囲んで立っていた。
2人で抱き合って泣いている女もいた。
すると、離れたところに立っていたマーリンがシェリルに頷いて見せた。
シェリルが髪を麻ひもで結んだ男に近付いた。
「歩いていたら急に後ろから襲い掛かって来たの。」
シェリルは両手の指を胸の前で組むと、髪を麻ひもで結んだ男を見上げた。
「助けて。とても恐いの。」
シェリルに見つめられて髪を麻ひもで結んだ男はどきどきした。
「ああ。」
やはり予想通りだ。
我慢ができずに原始人の男が後ろから襲い掛かったのだろう。
ならば後は、目の前で倒れている剣を使えそうな男にとどめを刺すだけだ。
「見るぞ。」
髪を麻ひもで結んだ男はそう言うと、エバの側に歩み寄り、片膝を突いた。
うつ伏せに倒れているエバはじっとしているが、まだ生きているように見えた。
倒れている人間の背中からは、ナイフで心臓は刺すことはできない。
だが、首が露わになっているから、首元から後頭部にナイフを深く突き刺せば殺せるだろう。
上半身をエバに被せるように身を乗り出すと、懐のナイフに右手を伸ばした。
その時だった。
「おじさん。」
コナンがそう声を掛けた。
髪を麻ひもで結んだ男がコナンの方に顔を向けると、目の前に剣が伸びていた。
その剣はシェリルの手に握られていた。
さっき見た時は剣など持っていなかったはずなのに。
「私たちをヤってから売るつもりなんだろう。」
シェリルが目を細めると、思わせ振りな表情でそう言った。
「おじさん。言ってなかったけど、おじさんが山賊だってことはばれてるから。」
コナンが残念そうにそう言った。
髪を麻ひもで結んだ男の目が真剣なものに変わった。
シェリルが剣の刃を首にあてた。
「お前の仲間は他に何人いるのだ。」
髪を麻ひもで結んだ男が黙ってシェリルを睨んだ。
「他に仲間が3人いる。」
離れたところに立っていたマーリンが突然そう言った。
「そうか。3人全員近くに来ているのか。」
シェリルがまた尋ねた。
髪を麻ひもで結んだ男は黙っていた。
「近くに来ているのは2人だ。」
またマーリンがそう言った。
髪を麻ひもで結んだ男が分からない顔でマーリンを見た。
シェリルがマーリンの言った言葉に頷いた。
そして髪を麻ひもで結んだ男の首に剣を喰い込ませると、さらに尋ねた。
「あの山賊の子は誰の子どもだ。お前の子どもか。」
シェリルがそう言って、山道の端で木に寄り掛かって座っている、山賊の子どもを顎で示した。
「そんな訳ねえだろう。」
髪を麻ひもで結んだ男がそう言った。
するとマーリンが口を開いた。
「山賊の中で隊長と呼ばれている男の子どもだ。」
その言葉にシェリルが頷いた。
すると髪を麻ひもで結んだ男は、我慢ならないという様子でシェリルの剣の刃を突然右手で掴んだ。
「いい気になってんじゃねえよ。このメスブタが!」
髪を麻ひもで結んだ男がわざと剣を握っている右手を少し横にすらすと、右手の平が斬れて、血が流れた。
髪を麻ひもで結んだ男は剣を握ったまま立ち上がると、右手にさらに力を込めて血を滴らせた。
そしてシェリルにニヤリと笑みを浮かべると、舌なめずりして見せた。
どうやら不気味さを演出しているようだった。
「おじさん!」
コナンが髪を麻ひもで結んだ男に横から声を掛けた。
髪を麻ひもで結んだ男が恐い顔でコナンを睨んだ。
「おじさん、ごめん。生き返ったみたい。」
コナンはそう言うと、髪を麻ひもで結んだ男の背後を指差した。
「何?」
髪を麻ひもで結んだ男が後ろを振り返ると、地面に倒れていたはずのエバが立っていた。
!!
次の瞬間、エバの剣が髪を麻ひもで結んだ男の目に突き刺さると、頭蓋骨を貫通し、頭の後ろから剣先が突き出てしまった。
髪を麻ひもで結んだ男は小刻みに体を痙攣させた後、立ったまま動かなくなった。
エバは剣を引き抜き血糊を振るうと、男の汚れた衣服で刃を拭い、鞘に収めた。
「ちょっと、可哀そうな気もするわね。」
ランがコナンにそう言った。
「まあ、ランの言う事も分からなくはないけどな。だけどあいつらは、これまでに人を殺している。ガヤンに捕まれば絞首刑間違いなしの奴らだ。それに、ここで見逃せば村の人間がさらに襲われる。・・・まあ、あいつらが悪さをしないように、ランが責任をもって一生見張ってくれるって言うなら、別だけどな。」
「そんなこと・・・、無理だわ。」
ランはしようがないという顔をした。
「だったら、俺たちが責任をもってここで殺しておくのが正解さ。」
すると、エバは何気なくこちらを見ている山賊の子どもの視線に気付いた。
エバは山賊の子どもに近付くと、上から見下ろした。
「山賊は人を襲って金を奪う。だが、襲った相手が強ければ自分が死ぬ。良く見ておけ、山賊というのはこういう商売だ。」
小川に架かっている丸太橋の上では、山賊が今か今かとうつ伏せになってエバたちを待っていた。
エバたちが丸太橋に差し掛かれば、木陰から髪を麻ひもで結んだ仲間の男が現れて、挟み撃ちにするはずだ。
だが一向にエバたちが現れる様子はなかった。
「どうしたんだ。遅すぎるだろう。」
丸太橋を渡ったところ、丸太の下に身を隠していた仲間の1人が声を掛けて来た。
「だけどよ、他の奴らもまだ隠れているんだろう。勝手に抜けたら、俺たちの取り分がなくなるぜ。」
「確かにな。」
2人の山賊は、また黙ってエバたちを待ち始めた。
すると、山道を男と子どもが走って来るのが見えた。
それはエバとコナンだった。
「大変だ!大変だ!」
コナンが大きな声で山賊に声を掛けた。
エバとコナンは丸太橋に到着した。
橋の真ん中でうつ伏せになっていた山賊が立ち上がった。
「どうしたんだ。」
コナンに声を掛けた。
「山賊に襲われたんだ。お姉さんたちが乱暴されてる!」
「何だって!」
山賊が驚いた顔をした。
「山賊ってどんな奴だ。」
山賊がコナンに尋ねた。
「髪がボサボサの奴と、束ねた奴。2人組だよ。僕たちは恐くて逃げて来たんだ。」
「何だって!」
山賊は慌てて橋の下の仲間に手招きした。
「おい!早く上がって来い。早くしろ!」
道理で遅い訳だ。
あいつら、女どもを2人占めしようというつもりだったんだ。
そういえば原始人の男は女に餓えていたし、髪を束ねた奴は金を欲しがっていたからな。
俺たちを裏切って、2人だけで女も金も手に入れるつもりだったんだ。
「どうしたんだ。」
橋の下にいた山賊が橋の上に上がって歩いて来た。
「山賊が女を襲ってるってよ。しかも2人で。」
「何だと!」
橋の下にいた山賊もすぐに状況を理解した。
橋の上でうつ伏せになっていた山賊が仲間に何度も頷いて見せた。
そういえば、自分たちは山道に潜んでいて、俺たち2人だけ丸太橋に置いてけぼりにしたのも、2人占めしようとしていたと考えれば納得が行く。
くそお。騙しやがったな。
「よし、山賊は俺たちがぶっ殺してやる。お前たちは村に行って助けを呼んで来い。」
橋の上でうつ伏せになっていた山賊がコナンにそう言った。
「分かったよ。」
そう言ってコナンが頷いた。
橋を渡ろうとした2人の山賊が、橋のまん中でエバとコナンとすれ違った。
その時だった。
エバはすれ違おうとする山賊の右足を踏みつけると、髪の毛を掴んで頭をがっしりと固定した。
「な!」
山賊が髪の毛を掴んでいるエバの手に気を取られて、エバの手を外そうと両腕を頭に上げようとした時、エバはがら空きとなった山賊の顎の下から剣をスッと差し入れた。
「あっが!」
エバの剣は頭を下から縦に貫通し、脳を破壊すると、頭蓋骨のちょうどてっぺんから剣先が飛び出した。
山賊の1人は小刻みに体を痙攣させた後、立ったまま動かなくなった。
「なにいきなり刺してんだよ!!」
後ろでその様子を見ていた山賊が、たじろいで思わずそう口走った。
「山賊だからじゃない。」
コナンが何でもないと言うようにそう言った。
エバはサッと剣を引き抜くと、頭を串刺しにされていた山賊が橋の上に倒れた。
残った山賊の1人が慌てて逃げようとエバに背中を見せた。
だが、エバの反応は速かった。
エバは逃げようとする山賊の後頭部のへこんだところから剣を差し込んだ。
エバの剣は山賊の延髄を破壊して、口から剣先が飛び出した。
最後の山賊もまた、小刻みに体を痙攣させた後、立ったまま動かなくなった。
エバが剣を引き抜くと、この山賊も同じように橋の上に倒れた。
エバは剣の血糊を振るうと、男の衣服で刃を拭い、鞘に収めた。
「とりあえず5人の山賊のうち、4人まで始末できたのは良かったぜ。これで村人が襲われることもなくなる。」
コナンが倒れた山賊を見下ろしてそう言った。
「まあな。」
エバがそう言うと、倒れた山賊の頭側にしゃがみ込んだ。
「コナン。悪いが足側を持ってくれ。」
エバがそう言うと、死んでいる山賊の両腕を握ると持ち上げた。
「オーケー。」
エバとコナンは山賊の死体を橋の上から動かし始めた。
「エバさん。何か納得していないようだけど、何か気に障ることがありました?」
コナンは、エバから少し不機嫌な雰囲気を感じていた。
「いや、まあ、そうでもないんだが。」
エバは一旦そう言って、少しの間黙っていると口を開いた。
「お前が言っている、村人のためというのが気になってな。」
するとコナンは口を尖らせた。
「あいつらは時々農民たちを襲って食糧を奪う。だけどそれだけじゃない。農民を殺すことだってあったんだ。だけどガヤンは、わざわざ山に入って山賊を討伐することはしない。あんなちんけな奴らを討伐したって、苦労するばかりで、金にならないからね。だから放置されて来た。俺はそれを横で見て来たんだぜ。それが、たった今ここで終わったんだ。俺は、エバさんの人殺しにはちゃんと意味があるって、そう言っているつもりなんだけどさ。」
コナンの言葉に、エバはニヤリと笑みを見せた。
「そうか。ありがとう。でも、何と言うか、逃げているみたいで嫌なんだ。」
「逃げている?」
コナンが分からない顔をした。
エバはコナンに頷いて見せた。
「村の人のため、と言うと、俺はやりたくないけれど、村の人のために殺した。つまり、俺に責任は無いって言っているように聞こえる。」
エバの言葉に、コナンが何かに気付いた顔になった。
「そっか、なるほどねえ。」
「俺が戦っているのは、もちろんシェリルたちを守るためという理由が大きい。かと言って、戦いの責任をシェリルたちに押し付けたくはないんだ。俺は、俺の意思で人を殺す。」
エバの言葉にコナンが頷いて見せた。
なるほど。
人を殺すというのであれば、その責任は自分で負うという訳だ。
逆に、その責任を負う気が無いのなら、殺してはいけないと、エバは言っているのだろう。
あの山賊たちは金を奪うために人を殺した。
だが、あの山賊たちはその覚悟を理解していただろうか?
いや、理解しているとは思えない。そもそも考えてもいないだろう。
だからエバは、平気で山賊を殺すのだ。
同じ人殺しとして。
コナンは納得した様子で口を開いた。
「俺は人を殺した事がないから分からなかったけど、いい勉強をさせて貰ったぜ。」
「そうか?」
エバとコナンは山道の端まで死体を運んでいくと、茂みの中に死体を投げ込んだ。
「おーい、終わったのか?」
シェリルたちが山道を歩いて来た。
エバとコナンがシェリルたちに顔を向けた。
「とりあえず、ここにいる山賊は全部やっつけましたよ。」
コナンがシェリルにそう言った。
「上手く行ったな。山賊の4人をできるだけバラバラにして、一番危険が無い方法で排除できた。ありがとう。さすがコナンだな。」
シェリルが笑顔でコナンにそう言った。
「コナン。大丈夫だった?」
ランが一応コナンにそう聞いた。
「俺が戦った訳じゃねえし、楽な仕事さ。」
そう言ってコナンが頭の上で腕を組んだ。
「でも、これは騙されるわね。本当に、無邪気な子どもにしか見えないのだもの。」
ソフィがコナンを見て小さく頷いた。
「本当に、悪魔少年みたい。」
アレンティーがぼそりとそう言った。
「おいおい、俺は好きで子どもやっている訳じゃないんだぜ。勘弁してくれよ。」
コナンがやれやれと両手の平を見せた。
コナンの様子にみんなで声を出して笑った。
「それにしても、ランさん。ダルケスが使えるのね。後ろ蹴りの踵がよく伸びていて綺麗だったわ。」
ソフィがランにそう言った。
ダルケスというのは、華麗な蹴り技が特徴的な武術の一つで、ソフィはダルケスの使い手だった。
「ソフィさんこそ、上半身が動いていないのに、蹴り足だけがスッと伸び上がって、相当な腕前ですね。」
「ありがとう。」
ソフィとランがお互いに顔を見合わせた。
「はいはいみなさん。」
一番後ろで立っているマーリンがみんなに声を掛けた。
「あと残っている山賊が1人いますが、山賊の子どもを捜して追いかけて来るかも知れませんよ。」
「何で?」
コナンがマーリンに尋ねた。
「どうやら我々が排除した4人の山賊は、もともとはこの山賊の子どもを捜していたようですから。」
「なるほどな。」
エバが頷くと目を閉じて見せた。
「そんなの、知ったことか。」
シェリルはそう言うと、山賊の子どもの手を引いて山道を歩き始めた。
エバたちは、今日1泊する村に到着した。
予定より到着が遅くなってしまって、もう太陽が沈みかけようとしていた。
エバたちはまず村の総監に会いに行った。
総監とは、村の人々から地代を徴収し、農民たちを働かせて領主に収める穀物を作ったり、村の裁判の判事を務めるなど、村を領主に替わって管理監督する総責任者のことで、村で力を持っている金持ちの農民がその役目を務めていた。
総監の住んでいる屋敷は村の中心にあって、石を積んで造られた建物なのですぐに分かる。
この時代、農民の家は、土壁に藁で屋根を葺(ふ)いた家が普通だったからだ。
総監の住んでいる屋敷は、村で行われる裁判の裁判所としても使用されるし、領主から派遣された執事や、宮廷からのお客様が村に滞在する際の客室としても使用された。
また農村には、まれに訪れる旅人のために宿屋を経営している者などいないので、農村で屋根付きの宿泊場所の提供を受けるのであれば、総監に金を渡すのが手っ取り早かった。
もっとも、村の中に入らずに、村の周辺で勝手に一泊したとしても、うるさく言われることもなかったが。
すると、総監の屋敷からシェリルとエバとマーリンが出て来た。
「村の入り口にある空き家なら使っていいって。」
シェリルが石の階段を下りながら屋敷の外で待っていたマリーウェザーたちにそう言った。
「きっと、ここに来る途中に見た家だね。」
マリーウェザーがそう言うと、総監の屋敷から男が1人石階段を下りて来た。
男は階段を下りると、ちょうど目の前にいたマリーウェザーをちらっと見て、すぐに目を逸らすと横を通り過ぎた。
「一応、案内してくれるらしいよ。」
シェリルがそう言って苦笑いした。
「行こうか。」
シェリルがそう言って、黙って歩いて行く男の後をエバたちは付いて行った。
山賊の子どもはマリーウェザーが手を握って連れていた。
男は1軒の家の前で立ち止まると、手で示した。
「ここだ。」
低い声でそう言うと、さっさと来た道を戻って行った。
「愛想も素っ気もない人ね。」
ソフィが口を尖らせた。
「しようがないよ。村は商売をするところではないからね。旅人をおもてなしするという発想はないだろうね。」
シェリルがまた苦笑いした。
家は、横に長い長方形の形をしていて、土壁に藁で屋根を葺(ふ)いた家だった。
まん中に木の扉があって、その両隣に小さな窓がついていて、何となく口を開けた人の顔みたいだった。
「9人だと小さいかな。」
ソフィが両腕を組むとそう言った。
エバたちは、山賊の子どもを含めると人数は9人だった。
目の前に立っている家はせいぜい6人用の大きさに見えた。
「屋根と壁があるだけ十分だ。」
エバがそう言うと木の扉を開けた。
家の中を見ると、家のまん中に石を並べて作ったかまどがあって、かまどの上に鉄鍋が置かれていた。
右側を見ると壁で仕切られていて、小さな小部屋が2つあった。
左側を見ると天井と床の間に中二階が造られ、中二階に上がれるように梯子が掛けられていた。
中二階には藁が山のように積まれていた。
床は踏み固められた土間だった。
食事用のテーブルや椅子が分解されて置かれており、その他にも、掃除のための箒や薪をはさむための火ばさみなどが置かれ、生活のための道具がかなり残されていた。
「いいじゃん。」
シェリルがエバの横から家の中を覗いた。
「いいんじゃない。」
「まだましな方。」
マリーウェザーとアレンティーもエバの横から家の中を覗いた。
「農村の家はこんな感じなのね。」
ソフィが珍しそうに家の中を覗き込んだ。
「ソフィさんは村は初めて?」
ランがソフィに聞いた。
「ええ、凄く興味がある。」
「私が住んでいた家もこんな感じだったな。」
「へえ。」
ソフィが小さく頷いた。
「農村の家は大きい小さいはあるけど、基本的な造りはこんな感じさ。」
家の扉の前でひしめき合うエバたちを後ろで見ていたコナンがそう言った。
「よし、じゃあ、もうあまり時間が無い。ごはん担当と掃除担当に分かれよう。」
シェリル、マリーウェザー、アレンティーはごはん担当。
ソフィ、ラン、エバ、マーリン、コナンは掃除担当になった。
シェリルたちごはん担当は、パンと野菜と牛乳とエールを貰いに総監の屋敷に向かった。
山賊の子どもも一緒に連れて行った。
総監は貯蔵室に保存していた固いパンと今日絞った牛乳、それからエールを分けてくれた。
野菜は裏の畑から勝手に持って行って良いことになった。
「野菜は大抵勝手に持って行って良いと言われるんだけど、ちゃんと許可を貰っておかないとね。」
シェリルは山賊の子どもにそう言った。
シェリルたちごはん担当は、もう暗くなってしまった畑に入ると、畑に植えられているリーキを引っ張って抜き始めた。
「一緒にやってみよう。」
マリーウェザーが山賊の子どもに声を掛けた。
引っ張れば簡単に抜けるので、山賊の子どもでも簡単に抜けた。
「上手に抜けたじゃん。」
マリーウェザーが山賊の子どもにニコッとした。
山賊のこどもはそう言われても黙っていた。
「人参とにんにくと、パセリもあるね。一緒にいただいていこう。」
掘り起こすのが面白くて、4人は人参を掘り起こし、にんにくも掘り起こした。
「野菜とるの楽しいね。」
アレンティーが笑顔になった。
パセリはナイフで根本から刈り取る。
「やってみる?」
シェリルは山賊の子どもにナイフを渡した。
「刃が付いているだろう。」
シェリルがナイフの刃を指で触れた。
「切りたいところに刃をあてて、手前に引くと切れるからね。逆に、手で刃に触れている時には引いてはいけないよ。手が切れてしまうからね。」
シェリルが説明すると山賊の子どもは頷いた。
山賊の子どもはシェリルの真似をしてパセリを根元から刈り取ると、立ち上がってシェリルに渡した。
「上手に取れたね。」
シェリルが微笑んだ。
「つい、とり過ぎちゃうんだよね。」
アレンティーが手に持ったにんにくを見せながら笑顔を見せた。
ごはん担当は、野菜を持って村の共用井戸に向かうと野菜を水で洗い始めた。
するとエバが鉄鍋を持って現れた。
「鍋を洗いに来たの。」
「まあな。」
家にあった汚れた鉄鍋をエバが井戸水で洗った。
そして綺麗になった野菜と固いパンを鉄鍋に乗せると、それをエバが持った。
それから牛乳、エールそれから水の入った桶をシェリルとマリーウェザーとアレンティーが持って家に帰った。
「ちょうど薪に火がついたところよ。」
家の入り口に立っていたソフィがそう言った。
ソフィは、家の中の砂やら小さい石やら落ち葉やら何かのくずやらを箒で掃いて、家の外に掃き出していた。
家の中では、石を並べて作られたかまどで薪が勢いよく炎を上げていた。
マーリンとコナンが、火ばさみで薪が良く燃えるように、薪を起こしたり寝かしたりしていた。
焚火から上がった煙は、ちょうどかまどの上にある、屋根に空いている穴から外に出て行った。
「薪はどこにあったの?」
マリーウェザーがマーリンに聞いた。
「家の横に積んであったんだ。運ぶ必要がなくて助かったよ。」
「へー、良かったね。」
すると家の中二階からランが梯子を下りて来た。
「藁が腐ってなくて良かったわ。寝床の準備はこれで完了ね。」
ランは中二階を掃除した後、藁をかき混ぜて中に空気を含ませると、中二階に藁を十分に敷き詰めた。
ただ、中二階だけでは寝場所が足りないので、1階にも藁を敷き詰めていた。
「それじゃあ料理を始めよう。」
シェリルがマリーウェザーとアレンティーにそう言った。
まず鉄鍋を火にかけると、鍋に水を注いだ。
それから保存食としていつも持ち歩いている干し肉を、鍋に入れてふやかしておいた。
固くなったパンは牛乳に浸して、これもふやかしておいた。
湯を沸かしながら、取って来たリーキ、人参、にんにくを3人で分担してナイフで細かく切って次々と鍋に放り込んだ。
まな板がなかったが、かまどの石をまな板替わりに使って、器用に野菜を切った。
「本当は下茹でしてから野菜を切って、すり鉢ですり潰してから鍋に入れるんだけど、面倒だし、こっちの方が美味しいから生のまま入れちゃう。」
シェリルが山賊の子どもにそう説明した。
多少柔らかくなった干し肉を一旦鍋から取り出すと、ナイフで削ぎ切りにしてもう一度鍋に入れた。
それをぐつぐつと一煮立ちさせると、灰汁(あく)が浮いて来るのですくい取って捨てた。
野菜と干し肉から出たうまみで、薄い琥珀色のスープができた。
にんにくのいい臭いがした。
山賊の子どもが鍋の中をじっと覗き込んでいた。
「美味しそうでしょう。まだ完成じゃないからね。できたら食べようね。」
シェリルがそう言うと山賊の子どもは頷いた。
シェリルたちは、牛乳に浸していたパンをナイフで細かく切ると、琥珀色のスープに放り込んだ。
残りの牛乳も鍋に入れた。
それから鍋をかき混ぜて、放り込んだパンと牛乳がスープとなじんでとろとろとした状態になったら、いつも持ち歩いている塩と胡椒を入れ、最後に細かく切り刻んだパセリを加えた。
「味見してみるね。」
アレンティーがかき混ぜていた木のスプーンを取り出すと、手の甲に少しだけスープを乗せて味を見た。
「もう少し胡椒を強くした方がいいかな。」
アレンティーが胡椒を入れて味を整えると、ミルク煮が完成した。
「やったあ、美味しそうにできた。」
マリーウェザーが山賊の子どもの手を握って喜んだ。
「テーブルの準備も出来ているわよ。」
料理をしている間に、食事用のテーブルと椅子をソフィたち掃除担当が組み立てていた。
もっとも、テーブルに座れるのは4人までだったが。
出来上がったミルク煮を、アレンティーが家に残っていた木皿やコップに注いだ。
エールがたっぷりと入った土器のピッチャーから、それぞれ自分用のカップにシェリルがエールを注いだ。
「私のを貸してあげるね。」
山賊の子どもの分は、アレンティーが余分に持っていたカップとスプーンを貸してあげた。
どちらも錫でできていて、鈍い銀色の光沢を放っていた。
コナンとランの分は、シェリルとマリーウェザーが貸してあげた。
食事用テーブルには、シェリルたちごはん担当が座った。
山賊の子どももテーブルに座った。
他のみんなは1人用の丸椅子に腰掛けたり、木箱に座ったり、石に座ったりした。
ようやく全員にミルク煮とエールの入ったカップが行き渡ると、シェリルが立ち上がってみんなを見渡した。
「じゃあ、みんなで乾杯しよう。海賊風の乾杯だけどね。」
「海賊風の乾杯?どうして海賊なの?」
コナンが分からない顔をした。
「そうか、言っていなかったな。私は海賊なんだよ。」
するとコナンは笑った。
「冗談でしょう。」
「いや、本当だから。」
コナンが周りを見渡すと、エバもマリーウェザーもアレンティーもマーリンも頷いていた。
「そうなんですね。確かに、格好がちょっと・・・露出が多いかなと思っていましたけど。じゃあ、みなさんは海賊一家なんですか?」
「いやいや、シェリルだけが海賊。俺たちは俺たち。」
エバがコナンにそう言った。
「私たちは自由に生きているからね。」
シェリルがコナンにニコッとした。
「何だか分かりませんけど。まあいいですよ。ところで、海賊風の乾杯はどうやってやるんです?」
コナンがシェリルに尋ねた。
「神様にお祈りした後に“ゴッソ”と掛け声を掛けるから、景気よくコップをぶつけて中のエールを溢れさせるんだ。」
「へえ。確か、ここから南、青の帝国の先にあるゼクス共和国でも、乾杯の時にグラスをぶつけて音を鳴らすらしいぜ。カチンという音が悪魔を祓う効果があるんだとか。」
「ふーん、そうなんだ。面白い。」
コナンの説明にシェリルが頷いた。
「じゃあ、早速乾杯しようぜ。」
「それじゃあ、その前に神様に感謝の祈りを捧げよう。今日はどの神に祈るかな。」
シェリルは皆に問いかけた。
「どの神かな。」
エバが言った。
「そうですね。」
マーリンが言った。
コナンとランはあっけにとられていた。
それというのも、食事のお祈りのときには、豊穣の神であるサリカ神に祈ることが決まっていて、どの神に祈るのかなどと考えたこともなかったからだ。
「サリカ神に祈るんじゃないのか?」
驚いた様子のコナンにシェリルは言った。
「力になってくれなかった神に祈る必要などないさ。今日はどの神が力になってくれたかな。」
するとエバが言った。
「幸運の神タマットだな。今日皆が無事に生き残れたのはまさに幸運だった。」
するとすぐにコナンが言った。
「タマット神って、盗賊の神様だろ。今日襲ってきたのは山賊だったんだぜ。だめだろう。」
コナンが目を細めてエバを見た。
だがエバは気にしていない様子だった。
「いや、別にいいんじゃないか。盗賊の神様を利用して、山賊を倒した、みたいな。」
「何毒を以て毒を制すみたいなこと言っているんですか。上手いことを言ったみたいな顔してますけど、意味になってませんよ。・・・まあ、いいですよ。早く食べましょう。」
コナンが両手の平を見せて肩をすくめた。
「ははは、じゃあタマット神でいいかな。」
シェリルは両手の指を胸の前で組んだ。
「背中を伸ばして、こうやって指を組んで。」
マリーウェザーが山賊の子どもにお祈りの時の姿勢を教えた。
「それじゃあ、今日の我々の幸運をもたらしてくれたタマット神に感謝を。ありがとう、タマット。それでは、ゴッソ!」
「ゴッソ!」
みんなが一斉にエールの入ったコップをぶつけ合った。
シェリルとマリーウェザーとアレンティーが。
エバとコナンとマーリンが。
ソフィとランが。
そしてじっとしている山賊の子どものコップに、シェリルが自分のコップをぶつけた。
するとカチンという音と共に、中のエールが勢いよくこぼれ落ちた。
山賊の子どもが驚いた顔をした。
「楽しいだろう。ほら、みんなと乾杯しよう。」
「ゴッソ。」
マリーウェザーがそう言って山賊の子どもにコップに自分のコップをぶつけた。
「ゴッソ。」
アレンティーも同じようにぶつけた。
それからエールをごくんと飲み込んだ。
この時代のエールはアルコール度数が1%程度と低かったし、家庭の主婦が自宅でエールを醸造するのが普通だったので、子どもでもエールを普通に飲んでいた。
エールに含まれる麦汁は栄養が豊富だったので、栄養が不足しがちなこの時代においては、栄養を補うためにもエールは大人も子どもも食事のたびに水代わりに飲んでいたのだ。
山賊の子どももエールをごくんと飲み込んだ。
「美味しいだろう。初めて飲んだかな?」
シェリルの言葉に、山賊の子どもは黙って頷いた。
それからみんなが一斉にスプーンでミルク煮を頬張った。
山賊の子どもも真似してスプーンで頬張った。
「美味しい。」
「美味しいね。」
マリーウェザーとアレンティーが顔を見合わせた。
「柔らかくて優しい味がする。」
「ああ。」
コナンとランも顔を見合わせた。
「にんにくの臭いがあまりしないわ。」
ソフィが独り言のようにそう言った。
「牛乳を入れると臭いが抑えられるよ。」
シェリルがソフィにそう言った。
山賊の子どももパクパクと食べていた。
「どう?美味しい。」
シェリルが尋ねた。
「うん。」
山賊の子どもがそう言って頷いた。
「良かった!」
シェリルがとっておきの笑顔を山賊の子どもに向けた。
食べ終わるとみんな次々におかわりした。
山賊の子どもも2杯もおかわりした。
気が付くと鍋の中は空っぽになっていた。
エバたちはお腹が一杯になると、やる事も無いし、明かりも家の中心の焚火しかなくて暗いので、それぞれ寝る準備を始めた。
「今日は藁の上でみんなで川の字になって寝るしかないわね。」
ランが残念そうにそう言った。
「そうね。」
ソフィがそう言った。
「ちくちくするのよね。あと、シーツが2枚あれば、シーツの間に潜り込めるのにね。」
ランがそう言うと、少し申し訳なさそうにソフィが口を開いた。
「実は、私たちは毛布を持ち歩いているの。」
「えー、そうなんだ。」
ソフィが頷いた。
「私も旅生活を始めたのは最近なんだけど、毛布1枚あるだけで、野外で寝る時に全然違うのよね。」
「凄い、旅慣れてるのね。」
ランが感心した顔でソフィを見た。
「いえ、全然。どちらかと言うと勉強中かな。」
「そうなんだ。」
「良かったら、私のマントを貸してあげるけど。大きいから、中にくるまれば暖かいし、羊毛で厚みもあるから、ちくちくもしないと思うけど。」
「ありがとう、助かる。そうさせて貰うわ。」
ランは、火あぶりの刑に処せられそうになったところをシェリルたちに助けられ、そのままロボルの街から逃げて来たので、旅に必要なものは何も持っていなかった。
するとソフィは、中二階と1階の藁の寝床を見た。
「上と下とどっちで寝るのかしら。」
ソフィがそう言うと、ランがすぐに口を開いた。
「2階がいいと思うわ。1階は虫がごそごそすると思うから。」
「そうね、1階は男たちに任せて、2階にしましょう。」
ソフィとランは顔を見合わせてニコッとすると、梯子を上り始めた。
「いい、指でこうやって、歯を磨くんだよ。」
マリーウェザーが山賊の子どもにそう言うと、水で濡らした人差し指で前歯をこすり始めた。
山賊の子どもが不思議そうに見ていた。
「ほら、見ているだけじゃだめだろう?真似してやるんだよ。」
シェリルがそう言って山賊の子どもに促した。
山賊の子どもが真似して指で歯をこすり始めた。
「そうそう、歯は大事なんだから。ちゃんと綺麗にしないと、歯がなくなっちゃうぞ。」
シェリルがそう言っておどかした。
この時代、料理に砂糖を使う事は滅多になかったので、若いうちに虫歯になることはあまりなかったが、年を重ねれば、栄養が不足した生活を長く続けたことで、虫歯になったり、歯茎が細くなったり、腫れたりした。
虫歯になって、我慢が出来ない程痛くなってしまったら、歯を抜くしか方法がなかった。
「こすっていると、歯がキュッキュッてして来るのが分かるだろう。」
シェリルがそう言うと、山賊の子どもが頷いた。
「前だけじゃなくて、奥の歯も、歯の裏もこすらないとだめよ。」
アレンティーも横で見ていて、思わずそう言った。
4人で指で歯を磨いたら、家の外に出て水で口をゆすいだ。
「ちゃんと水で流すんだよ。そうしないと、また汚れがくっついてしまうでしょう。」
マリーウェザーが山賊の子どもにそう注意した。
マリーウェザーとアレンティーが山賊の子どもに歯磨きを教えている姿を見て、シェリルは嬉しくなって微笑んだ。
夜空には、この世界に7つもある全ての月が出ていて、とても明るい夜だった。
家の前には小麦畑が広がっていて、麦の穂がさわさわと揺らいでいた。
歯磨きが終わって家の中に戻ると、シェリルたちも寝るために中二階に上がった。
シェリルが毛布を広げると、山賊の子どもに言った。
「ここに寝てごらん。」
山賊の子どもは素直に毛布に横になった。
するとシェリルは、山賊の子どもの顔だけを出して、毛布を体に巻き付けた。
「ふふ、芋虫みたい。」
アレンティーがそう言うとクスクス笑った。
「えい!」
シェリルは芋虫みたいになった山賊の子どもをごろごろと転がした。
「ははは!」
すると、山賊の子どもが初めて笑った。
「笑ったね!」
マリーウェザーが驚いた顔でシェリルを見た。
シェリルは笑顔で頷いた。
「マリーウェザー、今度はそっちから転がしてよ。」
マリーウェザーは頷くと、芋虫をシェリルの方にごろごろ転がし返した。
「わあああ!」
山賊の子どもが喜びの声を上げた。
「また行くよ、えーい。」
山賊の子どもが喜んだので、シェリルたちは何度も何度もごろごろと転がしてあげた。
「私も転がす。」
アレンティーがシェリルにそう言った。
「いいよ。交替しよう。」
シェリルは転がし役をアレンティーと交替した。
これが普通の子どもだ。シェリルはそう思った。
たくさん食べて、たくさん遊んで、たくさん学んで大きくなるのだ。
それに、マリーウェザーやアレンティーにもいい経験になる。
子どもと一緒に遊んだときに、子どもが喜んだり、悲しんだりする。
子どもに物事を教えたときに、子どもが理解したり、分からなかったり、嫌がったりする。
するとその姿を見て、なぜだろうと疑問に思う。
そして、自分はどうだっただろうと自分自身を見つめる。
すると、今まで考えもしなかった自分自身の新しい一面を発見する。
そうやって子どもと一緒に周りの人も成長していくのだ。
「わっ、危ない!」
マリーウェザーが転がす勢いが強かったせいで、中二階の端の方に芋虫が転がった。
このまま転がったら落ちるかもしれない。
「おっと。」
咄嗟にシェリルが芋虫を受け止めた。
「はい、そろそろ終わりにして、寝るよ。」
シェリルがそう言うと、芋虫の向きを縦に変えて、形が崩れた毛布を巻きなおした。
シェリルは山賊の子どもの髪を指で整えながら言った。
「私たちはお前の味方だ。だから安心して、今日はもう眠りな。」
山賊の子どもは大人しく頷いて目を瞑った。
それからシェリルとマリーウェザーとアレンティーは、丸めて背負い袋に括り付けていた自分の毛布を広げると、毛布にくるまった。
「良かったね、ようやく元気が出てきたみたい。」
マリーウェザーがそう言った。
するとアレンティーの向こう側から、ソフィが顔を出した。
「シェリル。コナンの話じゃないけど、この子を助けるとしてもどうするつもりなの?」
ソフィがシェリルに尋ねた。
「うん、このまま一緒に連れて歩くか、街のサリカ神殿に預けるか、どちらかかなと考えている。でも、それはこの子に相談して決めたいと思っているんだ。」
「そう、なるほどね。分かったわ。良いんじゃない。」
ソフィはあっさりとそう言った。
シェリルは少し驚いた顔をした。
「ちょっと意外だったな。」
「何で?」
「いや、反対されるかと思った。特に、一緒に連れて歩くのはね。」
シェリルの言葉に、ソフィはニコッとした。
「そうね。そう言われればそうかも知れない。でも、私もエイリスと別れて1人になった時に、受け入れてくれたでしょう。エバもシェリルもマリーウェザーもアレンティーも。」
「ふふ、お兄さまが抜けてるけど。」
横で聞いていたアレンティーがすかさずそう言った。
「あら、ごめんなさい。マーリンもね。」
ソフィがふふっと小さく笑った。
「私、本当に嬉しかったから。この子がそう望むなら、私は受け入れるわ。」
ソフィはシェリルに向かって笑顔を向けた。
シェリルもソフィに微笑んだ。
「でも、こんなに大人しい子が山賊の子どもなんて信じられない。」
マリーウェザーが山賊の子どもを見てそう言った。
「でも山賊ってひどいわ。ヤッてから売るだなんて。」
中二階の一番端で横になっていたランも、上半身を起こして話に入って来た。
「ちゃんと街の売春婦のお姉さんにお金を払って、サービスして貰えばいいのよ。何でそうしないのかしら。」
マリーウェザーがそう言うとほっぺを膨らませた。
「残念だけど、彼らは売春婦に払う金を持っていないよ。」
シェリルがそう言うと右手の平を開いて何も持っていないことを示した。
「それはちゃんと働いていないからでしょ。怠けているのは彼らなんだから、山賊が悪いのよ。」
マリーウェザーがそう言うとシェリルは小さく頷いて見せた。。
「まあね、怠けていることもあるかもしれない。だけど、山賊って乞食と一緒なんだよ。」
「乞食?」
「ロボルの街の外にたくさん乞食の人たちがいるのを見ただろう?」
「うん。」
マリーウェザーが街の様子を思い出して小さく頷いた。
「山賊なんていうのは、乞食の中でも乱暴な者たちがつるんで、金欲しさに人を襲うようになる。そして街の近くにいられなくなって、山に入って山賊になる。そんなものなんだ。もともとまともな教育を受けていない、だからまともな仕事に就けない。そういう奴らだ。だから、金が稼げないお前たちが悪いと責めるのは、少し可哀そうな気がする。」
「じゃあ、可哀そうだからいいわよって、受け入れてあげないといけないの。」
マリーウェザーが口を尖らせた。
「そんなことはないさ、襲ってきたのはあいつらなんだからやっつけてやればいい。ただ、奴らが金を持っていれば、わざわざ山に入って女性を襲う必要もない訳だ。」
「あいつらがただの変態なんじゃないの?」
ランがシェリルにそう言った。
「確かに、山で女性を襲うのが好きな変態もいるかもしれないね。だけど、変態じゃない普通の奴もいるはずだし、そっちの方が多いのじゃないかな。普通の奴であれば、金を持っているのにわざわざ山に入って女性を襲うという事はしないだろう。」
「確かにそうだわ。」
ランが頷いた。
「金が稼げないという貧困の問題は、ただ貧しい人たちが勝手に死んでいくというだけだと思ったら大きな間違いだ。貧しい人々の中には、乱暴な奴らもいる。そいつらはまともな教育を受けていないし、人から大切にされたこともないから、平気で人を襲うよ。金が物が女が欲しくなれば、持っている者を襲って奪えばいい。だって、彼らが生き残るための唯一の武器は、暴力だからね。」
するとアレンティーがハッとした表情で口を開いた。
「そっか、だからこの子には、ちゃんと教えてあげないといけないね。」
シェリルの顔がぱあっと笑顔に変わった。
「そうなんだよ!アレンティー。この子の運命を変えられるとしたら、今なんだよお。」
シェリルは嬉しそうにアレンティーのほっぺを右手を伸ばして触れた。
「へへへ。」
アレンティーも嬉しそうにほっぺを触れられていた。
すると1階からマーリンの声が聞こえてきた。
「山賊どもに襲われたら、豚を渡してやればいいと思うよ。」
マーリンの言葉に、女性たちが顔を見合わせると首を傾げた。
「何で?」
マリーウェザーが下の1階にいるマーリンに声を掛けた。
するとマーリンが言った。
「あいつら、女が手に入らないから、替わりに豚で性欲を発散していたらしい。」
マーリンの言葉に、女性たちが一気に騒ぎ始めた。
「何々?今何て言った?」
「ちょっと止めてよ。」
「一番聞きたくなかったわ、その話。」
「絶対に止めて!私の大好きな豚さんが可哀そう。」
するとエバが寝返りをうってマーリンを見た。
「やめろよマーリン。うるさくて寝られないだろう。」
するとエバの言葉に余計に女性たちは騒ぎ始めた。
「うるさいって何よ。」
「男の話をしているんだけど。」
「ヤッてから売るって、どういうことよ。女を馬鹿にしている訳。」
「なんで男の性欲のせいで、女のわたしたちが悩まなきゃならないのよ。」
横になっていたコナンがエバに顔を向けた。
「エバさんのせいっすよ。何で油注ぐっすかね。」
「期待されたら裏切れなくてな。」
悪びれることも無くエバがそう言うと、さらに女性たちはエバに非難の言葉を浴びせた。
「寝ちゃったね。」
マリーウェザーが隣で寝ている山賊の子どもを見てそう言った。
「帰りたいとか言わないね、この子。」
マリーウェザーの背中越しにアレンティーがそう言った。
「たぶん、家から追い出されるのが日常になっているんだろう。しばらくしたら帰ればいいと、思っているのじゃないかな。」
山賊の子どもを挟んで向かい側に寝ているシェリルがそう言った。
「ふーん。こんなに大人しくていい子なのに何で追い出すんだろうね。」
するとシェリルが目を細くしてマリーウェザーを見た。
「大人しくていい子かどうかは分からないよ。大人しく見せているだけかもしれないし。」
「えっ、そうなの。」
「そうだよ。一緒に暮らしたら、やんちゃで大暴れなのかもしれない。でも、それくらいの方が子どもらしくていいよ。追い出すなんておかしい。」
するとマリーウェザーが首を傾げた。
「おかしいのかな、どうだろう?私の場合は、親の方が出て行ったんだけどね。親だからって子どもを愛しているとは限らない。」
マリーウェザーはそう言うと目を伏せた。
「いや、どうかな。私は、親は子どものことを愛していると思うよ。」
マリーウェザーは顔を上げてシェリルの目を見た。
「じゃあ、何で私たちをほったらかしにして出て行ったんだろう。」
「愛にはね、厚みがあるんだよ。」
「厚み?」
チリーン、チリーン。
シェリルが首に付けている紅い鈴が突然鳴った。
「どうやら、追いかけて来たみたいだな。ちょっと外を見て来る。」
1階からエバの声が聞こえた。
エバは藁の寝床から立ち上がると、家の扉を開けて外に出て行った。
「どうしたの?」
毛布にくるまったソフィがマリーウェザーに顔を向けた。
「この子の親が追い掛けて来たみたい。」
「うそ。」
ソフィが驚いた顔をした。
「かも知れない。」
すると一番端で横になっていたランも体を起こしてマリーウェザーを見た。
「何で分かるの?」
ランがマリーウェザーに聞いた。
「シェリルの首輪につけられた紅い鈴は魔法の鈴で、危険が近づくと鳴って教えてくれる。」
アレンティーがランにそう言った。
「魔法なんだ。」
「そう。」
驚いた様子のランにアレンティーが頷いてみせた。
「この子を取り返しに来たのかな。」
マリーウェザーがそう言って心配そうな顔でシェリルを見た。
「どうかな。」
「とにかく、下着姿じゃまずいわよね。」
ソフィがそう言うと、女性たちは慌てて服を着始めた。
「この子も起こした方がいいかな。」
「そうだね。」
マリーウェザーが山賊の子どもを揺さぶった。
「起きて、お父さんが来たみたい。」
「このボロ、着させる?」
アレンティーが山賊の子どもが着ていた麻のボロ布を手で広げた。
「そのボロはもう捨てちゃおう。大きいかもしれないけど、私のチュニックを着させる。」
マリーウェザーが寝る時に畳んでおいた自分のチェニックを広げながらそう言った。
「着替えたら、下に下りていよう。」
女性たちは、衣服を身に付けると中二階から1階に下りて来た。
コナンがかまどに新しい薪をくべた。
みんなでかまどを囲むようにして座った。
山賊の子どもはマリーウェザーの大きなチュニックを被ると、腰を紐で締めていた。
炎が燃え上がって、座っているみんなの姿をゆらゆらと照らした。
みんな黙って、めらめらと踊る炎をじっと眺めていた。
すると、家の外で足音が聞こえた。
そして家の扉が開いた。
するとそこに、知らない男が立っていた。
黒い帽子を被って、膝までの長さがある黒のチュニックを着て、ベルトで腰を締めていた。
黒いズボンは膝上辺りで破れていて、太腿が剥きだしになっていた。
足には靴を履いていたが、靴先が破れて足の指先が見えていた。
無精でだらしなく伸びた髭が不潔な印象を与えた。
隊長の男だった。
かまどで燃える薪の炎が、隊長の男をちらちらと照らした。
「どうした、中に入れ。」
すると、隊長の男の後ろにエバが立っていて、エバが中に入るように促した。
隊長の男とエバは中に入ると扉を閉めた。
「村の入り口でうろついていたから連れて来た。」
エバがそう言った。
良く見ると、エバが後ろから隊長の男の後頭部に剣先をあてていた。
「だんな、勘弁してくださいよ。」
隊長の男が後ろに立っているエバに薄ら笑いを浮かべた。
だがエバは何も言わなかった。
しようがなく隊長の男は狭い家の中を見渡すと、家の中央にあるかまどの奥に、マリーウェザーとアレンティーの間に座っている自分の息子、ボニーを見つけた。
「ボニー!」
隊長の男は山賊の子どもに声を掛けた。
「あのおじさんはお父さん?」
マリーウェザーが山賊の子どもに尋ねると、子どもは隊長の男を見ながら頷いた。
かまどの脇で立っていたシェリルがマーリンを見ると、マーリンは小さく頷いた。
シェリルは隊長の男に向き直ると、隊長の男を正面から見た。
「お前は誰だ。何しに来た。」
シェリルが隊長の男を睨んでそう言った。
「誰って、俺は、後ろのお兄さんに連れて来られて何が何だか。けど、あそこにいるのは俺の息子で、何で俺の息子がこの家に連れ込まれているのか、俺には分からない事ばかりで。」
隊長の男はシェリルに困った顔でそう言った。
まだ若くて可愛い顔をした女だ。隊長の男はシェリルを見てそう思った。
きっと世間を知らないあまちゃん女に違いない。
俺の後ろに立っている物分かりの悪い男より、こっちの方が話がし易そうだ。
隊長の男はシェリルに向かって、少し微笑んで見せた。
すると、シェリルは腰の剣を抜き放つと隊長の男の鼻先に向けた。
「へえ、私たちを騙そうとしているのだな?いいぞ、続けてみろよ。その代わり、お前がもし山賊の隊長だということが後から分ったら、容赦しないからな。私は怒っているんだ。山賊どもに私の可愛い仲間が襲われてね。ヤッてから売るだなんてさ、ひどい話だろう。だからしようがないよね。山賊の隊長が詫びの一つもしないというなら、まずは股間についているソーセージを切り落とすよ。二度とヤレないようにね。」
シェリルが剣先を隊長の男の鼻先から股間に移した。
「それから四肢を一本ずつ切り落としてやる。二度と人を襲わないようにね。そうしたらちょうど雪だるまみたいな形になるから、村の入り口に飾っておいてやるよ。いや、雪じゃなくて、肉だるまかな。」
この女、イカレてやがる。隊長の男はそう思った。
可愛い顔をしているから、思わず油断してしまった。
とんだ気違い女だ。
それに山賊の仲間が山道で死んでいたが、こいつらを襲って逆に殺されたのだろう。
こいつらはヤバい。
ここは言うとおりに謝っておいて、さっさとボニーを連れて離れる方がいい。
こいつらから離れて、二度と顔を合わせないのが賢明だ。
だが、俺が山賊の隊長だとなぜ知っているんだ。
そうか、ボニーだ。
あいつが教えたんだ。それ以外にない。
このクソガキが。帰ったらじっくり、たっぷりとしつけて思い知らせてやる。
子どものしつけは親の責任だからな。
すると、隊長の男は突然地面に両手をついて頭を下げた。
「申し訳ありませんでした。親分。仲間がご迷惑をお掛けしたみたいで。ただ俺は、仲間から隊長って呼ばれてはいますが、ただのお飾り。実は一番の下っ端なんです。どっちかっていうと、あいつらが襲うと言った時、俺はやらねえって言ってそこから逃げたんですよ。」
「ふーん、そうか。」
シェリルは表情を変えることもなく隊長の男を見ていた。
「そうなんです。なんで、このとおり。勘弁してください。」
隊長の男は一瞬シェリルを見上げて、すぐに部屋の奥に座っているボニーを見た。。
「おい、ボニー。何をしているんだ。さっさとこっちに来い。すいませんねえ、息子が迷惑かけちまったみたいで。」
隊長の男は立ち上がるとボニーに手招きした。
「ほら、早くしろ!聞こえねえのか!迷惑をかけるんじゃねえ、このバカが!」
山賊の子どもが隣に座っているマリーウェザーをチラッと見て、それから立ち上がると、隊長の男に向かって歩き出した。
そして、山賊の子どもがちょうどシェリルの脇を通り抜けようとした時だった。
シェリルは子どもを抱き寄せると、首元に剣をあてがった。
「なっ、何をするんですか。」
隊長の男が驚きの声を上げた。
するとシェリルが隊長の男を鋭い目で見た。
「お前は山賊だろう。山賊というのは、人から暴力で奪い取るのが仕事だ。」
「何が言いたいのか分からねえ。」
隊長の男が思わず苛ついた様子でシェリルを見た。
シェリルは顔を上向きにすると、見下ろすように隊長の男を見た。
「実は、私は海賊なんだ。同業者だねえ。だから、この子は海賊の私が頂いた。返して欲しければ金を払え。身代金、2千ムーナだ。」

「何だと!」
隊長の男が呆気にとられた。
「何だと、じゃないよ。身代金2千ムーナだ。簡単な話だろう。払えるのか、払えないのか、どっちだ?」
隊長の男は目の動きが定まらずおどおどしていた。
冗談で言っているのではないかと、シェリルの表情をうかがっていた。
「・・・払え、ない。」
隊長の男はとりあえずそう言った。
「じゃあ、あきらめろ。この子に話をするんだ。お金がないので、お前を見捨てると。今後、二度と会う事も無いとね。」
シェリルはあっさりとそう言った。
こいつ馬鹿だ。隊長の男はそう思った。
世の中の道理というものを教えてやる。
隊長の男は口を開いた。
「親分、それはいくら親分でも無理な話ってもんですよ。親分も分かっているんでしょう。この子は俺の子なんだから、子どもは親と一緒に暮らすのが一番だ。」
隊長の男は、若いシェリルをなだめようと、微笑んで見せた。
そう言った隊長の男を、シェリルは冷ややかな目で見た。
「お前、自分の子どもが目の前で奪われようとしている時に、よく笑っていられるな。」
シェリルの言葉に、隊長の男は真剣な表情に変わった。
これは冗談ではない。
この女は本気だ。
何が目的か分からないが、本気で息子を奪い取ろうとしている!
シェリルと隊長の男の視線が交差した。
シェリルは山賊の子どもの服をめくり上げて見せた。
左のあばらの下辺りに、大きく黒いあざが付いていた。
「子どもに暴力を振るう父親なら、そんな父親は不要だ。」
シェリルが隊長の男を睨んだ。
「それは・・・、しつけだ。親なら、悪い事をした時に体罰を与えることもある。」
隊長の男が真剣な顔でそう言った。
「そうか、どんな悪い事をしたのか言って見ろ。」
「それは、」
シェリルが問い正すと隊長の男は一瞬言い淀んだ。
すると、マーリンが替わりに口を開いた。
「大声を上げて子どもが騒いでいて、静かにするように注意したが言う事を聞かなかったので、腹を蹴り飛ばして家から追い出した。」
隊長の男が驚いた顔でマーリンを見た。
「お前、何を言っているんだ・・・」
隊長の男が何か言い掛けると、マーリンは何でもないという顔をして口を開いた。
「この子が教えてくれた。」
マーリンが子どもを示しながらそう言うと、隊長の男は何も言えなくなった。
「なるほど。この子は何も悪い事をしていないな。街でも村でも、子どもは子ども同士で集まって大騒ぎしてにぎやかに遊ぶ。そんな子どもをわざわざ叱りつける大人はいない。子どもは大騒ぎして遊ぶものだし、子どもは未熟で、いくら注意してもうっかり騒いでしまうから、しかたがないことが分かっているからだ。だいたい、自分の気持ちを抑えて、注意されたことを守ることが出来るのなら、それは子どもではない。大人だよ。この子が大声を上げて騒ぐのは子どもなら当たり前の話だし、それを怒りに任せて蹴りを入れるなんて、お前の方がよっぽど自分の気持ちを抑えられない、子どもだ。お前がやったことは断じてしつけではない。ただの暴力だ。」
シェリルが隊長の男にヒュンと剣先を向けた。
「私はしつけだからといってこの子に暴力は振るわない。私の方がお前より、ずっと親にふさわしい。さっさと諦めるんだな。」
隊長の男が思わず後ずさりしようとすると、後頭部にあてられているエバの剣先が突き刺さった。
「ひっ。」
隊長の男は、何とかこの状況を乗り切れないかと必死で考えた。
だが、どうすればいいのか分からない。
とりあえず、何でもいい、何か言わなければ。
「そっ、そんなの無茶苦茶だ。俺はこの子の親なんだ。子どもは親の側にいるのが一番なんだ。」
するとシェリルがすぐに口を開いた。
「じゃあ聞くけど、お前は親としてこの子に何をしてあげた?何を教えたのだ?言って見ろ。」
隊長の男は、シェリルの睨んだ視線が恐かった。
何を言っても負ける気がした。
「めっ、飯を食わせてやって、」
「ふざけるな!」
シェリルの剣先が喉にスッと刺さった。
後頭部のエバの剣も、剣先がさらに深く刺さった。
「ひっ!」
「同年代の子どもと比べて、一回りも二回りも体つきが小さい。私たちとこの子が出会った時、この子はお腹が空いて道端に倒れ込んだんだぞ。どこが食わしてやっているんだ。言葉もほとんど知らない。靴も履かせて貰えない。食事の前に神様にお祈りすることも、寝る前に歯みがきすることも知らない。何してんだよ、お前。」
隊長の男は何も言えずに黙り込んだ。
シェリルは、黙っている隊長の男の様子を少しの間見ていた。
そしてまた口を開いた。
「一つ安心させておいてやる。親がいなくたって、大きくなって立派に生きている子どもはたくさんいる。少なくとも、お前よりもはるかに立派だ!」
隊長の男は目を伏せて黙っていた。
シェリルは、隊長の男の伏せた目を下からうかがった。
「どうだ、これで分かったろう。この子は諦めろ。」
「そんな・・・、」
隊長は目を伏せたままそれだけを口にした。
シェリルは、隊長の男が諦めがつかない様子なのでマーリンを見た。
「マーリン。こいつがこの子に固執している理由は何だ。」
すると、マーリンは嫌そうな顔をしてシェリル見ると言った。
「実はこの男は・・・、人身売買をやっている。農村で子どもを引き取って、奴隷商人に引き渡して金を稼いでいるんだ。そこで親から子どもを引き取る時に、この子がいた方が仕事がやり易いようだ。」
隊長の男はあまりの驚きでマーリンを唖然とした顔で見た。
「・・・この子が教えてくれた。」
マーリンが両手の平を隊長の男に見せた。
ブス。
のどに刺さっているシェリルの剣先がさらに深く差し込まれた。
「あっ、がっ。」
隊長の男が声にならない声を上げた。
「ひどい!あなたが親から子どもを引き離しているんじゃない。」
ソフィがそう言って隊長の男を睨んだ。
「子どもは親の側にいるのが一番だなんて、よくもそんな台詞が言えたわね。」
ランも隊長の男を睨んだ。
「本当にいるんだね、クズみたいな人間。」
コナンが子どもを装ってそう非難した。
もうだめだ。隊長の男はそう思った。
俺の嘘はばれてしまった。
こいつらには全てばれているんだ。
適当なことを言って、上手く乗り切ることはもう無理だ。
だが・・・。
男がじっと何かを見つめて動かなくなった。
だが・・・、殺される訳ではない。
そうだ、殺される訳ではないのだ。
最悪の事態にはならない。
子どもを諦めれば、最悪の事態は回避できるのだ。
人身売買の商売はあきらめるしかないが、俺が生きてさえいれば、何か他の仕事があるかもしれない。
俺が生きてさえいれば、女とヤッてまた子どもができるかもしれない。
それに、俺の親父は、親が子どもを殺すのはダメだと言っていたが、俺は子どもを殺す訳ではないし、イカレた女海賊が無理矢理俺から子どもを奪っていくのだから、俺のせいではないのだ。
隊長の男は何となく頭の中がすっきりとした。
大人しくさっさと子どもを捨てちまえば、それで良かったのだ。
シェリルが恐い目で隊長の男を睨んでいた。
シェリルは言った。
「お前がこの子を愛していないとは言わない。子どもを取り返しに来たのだからな。だが、お前の愛はあまりにも薄っぺら過ぎて、この子をまともに育てることはできない。親ではない私の方が、よっぽどこの子に対する愛はぶ厚い。これで分かったろう。まずはこの子に謝れ、謝罪しろ。親なのにまともに子育てをしませんでした、とね。それから宣言しろ、お金がないので、子どもは見捨てます。今後、二度と会う事もありません、とね。」
隊長の男はシェリルの言葉を聞いて少しの間じっと立っていたが、とうとうゆっくりと息子の方に向いて膝を突いた。
そして一度自分の息子の目を見ると、ゆっくりと頭を垂れた。
「親なのに、子育てをしませんでした。お金がないので、この子は見捨てます。今後、二度と会う事もありません。」
隊長の男はそう言って頭を垂れたままじっとしていた。
「よし、分かった。この子は私がしっかり育てるから、安心しろ。」
ひざまずいた隊長の男を見下ろして、シェリルはそう言った。
隊長の男は頷くと、頭を垂れたままゆっくりと立ち上がった。
そしてゆっくりと後ろを振り向くと、とぼとぼとした様子で家を出て行こうとした。
「おい。」
シェリルが隊長の男に声を掛けた。
「何でしょう。」
隊長の男が気落ちした様子でそう言った。
「どこに行くつもりだ。まだ話は終わっていないが。」
「えっ。」
隊長の男は思わずシェリルを見た。
「父親の話は終わったが、まだ山賊の話が終わっていない。お前の部下に襲われたし、お前も人を殺しているそうだし、人身売買までやっているみたいだからな。なあ、コナン。」
「せっかく5人目の山賊が自分から来てくれたというのに、そのまま逃がすなんてことがある訳ないよね。それに、悪い事をしたというのになんにも罰がないなんて、そんなのおかしいよ。おじさんも大人なら分かるでしょう?」
コナンが無邪気な表情でそう言った。
「えっ!」
隊長の男が唖然とした表情をした。
「まあ、ここでは何だから、外で話をしようか。」
シェリルはそう言うと、また剣先を隊長の首にあてた。
「外で話をしてくるから、この子を見ていてくれないか。」
シェリルはそう言うと、山賊の子どもをマリーウェザーに渡した。
「分かったわ。」
マリーウェザーは山賊の子どもを引き取ると、アレンティーと自分の間に座らせた。
エバとシェリルとコナンは、隊長の男を間に挟み込んだ状態で家の外に出て行った。
「一緒に行くわ。」
「私も。」
ソフィとランもそう言って、エバたちと一緒に外に出て行った。
エバたちは外に出ると家の扉を閉めた。
家の外に出たエバたちは、少し進んだところで足を止めた。
隊長の男を、シェリルとエバとコナンで囲んだ。
エバとシェリルの剣が、隊長の男の首を、前と後ろからまるで鋏の刃のような形で挟み込んでいた。
そして、そこから少し距離を置いて、ソフィとランが見守っていた。
7つの月がエバたちを明るく照らしていた。
コナンが隊長の男を見上げて言った。
「お前は農民たちを何人も殺している。男も女も。このままお前を生かしておいたら、この辺りの村の人々に被害が出る。それに、お前はガヤンに捕まれば死刑間違いなしの男だ。ここで始末しておくのがみんなの為なのさ。ガヤンの死刑は苦しいぜ、両手で喉を締め上げるからなかなか死ななくてさ、たっぷり苦しむんだ。それに比べたら、エバさんなら一撃で脳を壊してくれる。きっと、痛いと感じる暇もなくあの世に行けるよ。」
コナンが自分の頭を人差し指でトントントンと叩いた。
すると今度はシェリルが口を開いた。
「お前だって、いつかこうなる事は覚悟のうえで山賊をしていたんだろう?その時が来た、それだけのことさ。・・・男だったら、最後くらい覚悟を決めな。」
すると、隊長の男は急に涙を流し始めた。
「ひどいよ。助けてくれるんじゃなかったのかよ。急に殺すなんてよ。」
コナンが冷めた目で男を見た。
「お前だって突然殺してきたはずだ。それなのに、自分が殺される直前になって後悔しても、もう遅いんだよ。もっと早く後悔して、自分の人生を見直すべきだったな。」
コナンが冷たく突き放した。
「おい、待ってくれ。助けてくれよ。もう、山賊はやめる。やめるから。」
隊長の男がぽろぽろと涙をこぼした。
「お前のその言葉、どうやって信用すればいいんだ?担保は何だ。」
シェリルが淡々と聞いた。
「たんぽ?何だよ、たんぽってよお。」
隊長の男が泣きながらそう言った。
「それに、山賊をやめたからといって、今まで人を殺した罪が消える訳ではないしね。」
コナンがそう言った。
「おい!ゆっくりとひざまずくんだ。下手に動かれると、手元が狂う。お前が苦しむぞ。」
「ああああ!」
シェリルにそう言われて、隊長の男は泣きながら地面にひざまずいた。
「死んだら・・・、息子にも会えねえよ。・・・もう、息子にも会えねえよ。息子にも・・・。」
隊長の男の心の中に、急に自分の息子に対する気持ちが大きく膨れ上がった。
俺はなんて愚かだったのだろう。
親だというのに、子どもについて何も分かっていなかったのだ。
子どもなんて、放っておけば勝手に大きくなるものだと思っていた。
それでいいと思っていた。
俺は馬鹿だった。
自分勝手だった。
このイカレた若い女の方が、よっぽど子どものことを知っていた。
でも、今更後悔してももう遅かった。
もう、遅かったああああああああああああ!
隊長の男は初めて自分の息子を思って後悔の涙を流した。
家の中では、残されたマリーウェザーとアレンティーと山賊の子どもがエバたちが戻るのを待っていた。
「どうしたの、みんないなくなった。」
そう言って、山賊の子どもがマリーウェザーを見上げた。
ずっと黙っていた山賊の子どもが突然喋り出したので、マリーウェザーは少し驚いた。
「お父さまとお別れの挨拶があるんだって。すぐに戻って来るから、ここで待っていよう。」
マリーウェザーはそう言って、山賊の子どもの頭を撫でた。
3人は黙って、かまどでめらめらと踊る炎をじっと眺めていた。
すると、山賊の子どもを挟んで座っていたアレンティーが子どもを見て言った。
「しりとりでもする?」
「しりとり?」
山賊の子どもが分からない顔でアレンティーを見上げた。
「おしりの言葉から始まる言葉を順番に言っていくの。ちょっとやってみるね。」
そう言うとアレンティーはマリーウェザーと顔を見合わせた。
「しりとり。」
アレンティーが言った。
「りんご。」
マリーウェザーが言った。
「ごちそう。」
「うし。」
アレンティーが子どもを見た。
「どう?分かった。」
山賊の子どもは頷いた。
「じゃあ、次はあなたの番よ。うしだから「し」ね。」
アレンティーに言われて、山賊の子どもは考え始めた。
「し、し、し、・・・死ね。」
山賊の子どもが言った言葉に、マリーウェザーもアレンティーも驚いた。
「いきなりそんな事言うなんて、恐いじゃない。もっと優しい言葉にしてよ。」
マリーウェザーが山賊の子どもの頭をまた撫でた。
「死ぬとか、子どもらしくないぞ。」
アレンティーもそう言った。
山賊の子どもは2人に不思議そうな顔をした。
「でも、パパとかはよく死ねって言ってる。」
「そうなんだ。お姉さんは言わないよ。だから死ねなんて言わないで。」
「はい。分かりました。」
山賊の子どもはそう言って頷いた。
なんだか今の返事だけやけに丁寧だな。マリーウェザーはそう思った。
「ねえ。」
山賊の子どもがまたマリーウェザーに聞いた。
「なあに?」
「パパはどこかに行っちゃうの?」
マリーウェザーは咄嗟に何と言って良いのか分からなかった。
マリーウェザーは少しの間黙って考えると口を開いた。
「パパは悪い事をしたから罰を受けに行くんだって。だけど安心して、あなたのことは私たちがちゃんと面倒を見るから。」
マリーウェザーはそう言うと、山賊の子どもの手を握った。
すると、アレンティーも山賊の子どもの肩に手を置くと口を開いた。
「これからはご飯もちゃんと食べられるし、服も靴も買ってあげる。こんなダボダボな服じゃなくてね。」
アレンティーが山賊の子どもの肩をポンポンと叩いた。
「さあ、しりとりの続きをしましょう。」
マリーウェザーが山賊の子どもにそう言った。
その瞬間だった。
山賊の子どもの手が、マリーウェザーの手の中からスッと抜けた。
タタタタッ!
山賊の子どもが突然立ち上がると、家の出入り口に向かって走って行った。
「待って!」
マリーウェザーがそう声を掛けたが、山賊の子どもはわき目も振らずに家の扉を開けると外に飛び出して行った。
隊長の男は、顔が地面についてしまいそうな程に頭を垂れていた。
隊長の男は情けなく、声を上げて泣いていた。
後悔の涙がポロポロと地面に降り注いでいた。
泣いている隊長の男をシェリルは見下ろしていた。
シェリルは言った。
「お前に殺された人たちの中にも、もう家族に会う事ができないことを悲しんで死んでいった者もいた筈だ。お前にも、ようやくその気持ちが分かったか。お前が殺した人たちに申し訳ないと思うなら、お前も覚悟を決めろ。残された息子は、私が立派に育てると言っている。だから、お前は安心して死ぬがいい。」
シェリルは目だけを動かしてエバを見た。
エバは小さく頷いた。
「死ね。」
シェリルがそう言った。
次の瞬間、エバの剣が隊長の男の目に突き刺さると、頭蓋骨を貫通し、頭の後ろから剣先が突き出てしまう、はずだった。
だがシェリルがそう言った後も、エバの剣は少しも動くことはなかった。
シェリルは思わずエバを見た。
その時だった。
シェリルの足元を何かが駆け抜けると、頭を垂れている隊長の男の前に立った。
山賊の子どもだった。
山賊の子どもは両手を横に広げると、シェリルに向かって言った。
「だめだ。」
隊長の男は殺させない。
そう言っているようだった。
「シェリル姉さん!」
後ろからマリーウェザーの声がした。
シェリルが振り向くと、マリーウェザーとアレンティーが家の中から外に出て来ていた。
「シェリル姉さん。急にその子が走って家を飛び出してしまって。」
マリーウェザーがそう言うのを聞いて、シェリルは分かったと頷いた。
シェリルは山賊の子どもに向き直ると、片膝をついて目の高さを山賊の子どもと同じにした。
そして山賊の子どもの目を正面からじっと見た。
そして言った。
「お前の親父は、命を助けて欲しいと言っている人を殺して、金を奪って来た。そうやって人を殺して、金を奪って生きている者は、逆に襲った相手が強ければ自分が殺される。お前の親父はそういう世界を生きて来た。そして、今日、とうとう自分が殺される番がやって来たのだ。」
「だめだ、殺しちゃだめだ。」
シェリルがそう言っても、山賊の子どもの目は揺るがなかった。
次にコナンが山賊の子どもに話し掛けた。
「こんな父親、お前が助ける価値がどこにある。よく思い出すんだ。食べ物もろくにもらえない、お前を平気で蹴り飛ばす父親なんだぞ。」
「だめだ。絶対にだめだ!」
山賊の子どもは、じっとシェリルの目を見つめていた。
シェリルは右手の平で山賊の子どもの頬に触れた。
「お前の知らないところで、親父を殺そうとしたことは謝るよ。でも、このままこの親父と一緒にいて、もしお前が親父と同じように山賊になってしまって、そしてみじめに殺されて死んでいく。そんな事になるのは嫌なんだよ。」
シェリルの瞳に涙が浮かんだ。
「私と一緒に行こうよ。私がこの世界を君に教えてあげる。剣の使い方はエバが君に教えよう。不思議な魔法の世界をマーリンが君に教える。そうして君は大きくなって、自分の足で、自分の行きたいところに行って、自分の好きなように生きるのだ。素晴らしいと思わないか?だから、その親父から離れて、私のもとにおいで。」
シェリルはそう言って両手を伸ばすと、山賊の子どもを受け入れようと手を伸ばした。
だが山賊の子どもは、頭を左右に振った。
「だめだ!」
山賊の子どもは両手を広げたまま、頑として動こうとはしなかった。
「あああああ!ボニー。」
隊長の男は、頭を垂れたまま歯を食いしばって、涙をぽろぽろ地面に落として泣いた。
「俺は馬鹿だ。本当に馬鹿だ!俺はさっきお前を捨てた。お前を捨てたんだよお。だのにお前は、こんな俺を助けてくれるのかよおおおお!」
隊長の男は、息子を引き寄せると、ぎゅっと強く抱きしめた。
「悪かった。本当に、俺が悪かったあ!」
隊長の男は泣きながら、何度も何度も息子に謝った。
「この野郎!吹けば飛ぶような薄っぺらな愛しか与えないくせに、子どもに執着心だけは植え付けやがって。本当に情けない男だ、お前は!この子さえいなければ、即行で斬り殺してやるのに。」
シェリルは指先で涙を拭いながらそう言った。
シェリルは立ち上がると隊長の男を見下ろした。
そして言った。
「勘違いするなよ。この子はまだ知らないだけなんだ。自分がどのような仕打ちを受けて来たのか、ちゃんと分かるようになれば、お前など助ける価値がない事に気付くはずだ。今回はこの子に免じて、お前を殺すのはやめておく。だが、お前を信用することなどできない。だから、」
シェリルは一旦気持ちを落ち着かせると、はっきりと言った。
「お前には、この子にとって良い父親に生まれ変わって貰う。」
夜空に浮かぶ7つの月が、むせび泣く隊長の男とその息子、それから周りにいるエバたちを明るく照らしていた。
エバたちは、隊長の男から靴を取り上げて裸足にすると、走れないように右手と右足をロープで固く繋いだ。
隊長の男はナイフを持っていたが、それはすでにエバに取り上げられていた。
隊長の男を子どもと一緒に家の中に入れた。
「お前は私たちの奴隷だ。それが嫌なら、この子にとって良い父親に早く生まれ変わることだ。胆に銘じておけ。それから、もし私たちに危害を加えようとすれば、即行でその首を刎ねるから、覚悟して行動しろ。分かるだろう、私は本当にやるから、十分に気を付けるんだぞ。」
シェリルがそう言うと、隊長の男は黙って頷いた。
「それでは最初の命令だ。お前は、自分の息子をぎゅっと抱きしめて寝ろ。とりあえず、そこから始めよう。」
「分かった。」
とはいったものの、隊長の男はどうしていいか分からないようだった。
「しようがない奴だな。」
シェリルは藁のうえに毛布を広げた。
「おいで。」
シェリルは山賊の子どもに声を掛けた。
山賊の子どもはシェリルを見てニコッとすると、毛布の上に横になった。
シェリルは毛布で山賊の子どもをくるむと、隊長の男を見た。
「この子の横に寝ろ。お前なんか・・・、毛布はなしだ。」
隊長の男はゆっくりと息子の横に横たわった。
「ほら、腕を回して。」
隊長の男はぎこちなく、息子に腕を回した。
「ぎゅっと抱きしめるんだ。」
隊長の男は毛布にくるまれた息子をぎゅっと抱きしめた。
山賊の子どもは黙って抱きしめられていた。
子どもって奴は、温かいんだな。
隊長の男は両腕で息子の体温を感じていた。
シェリルは、藁の上で横になっているエバを見た。
「じゃあ、私たちは上で寝るよ。」
「任せろ。何かあれば、殺すまでだ。」
シェリルたち女性たちも、中二階に上がるとそれぞれ毛布やマントにくるまった。
「シェリル姉さん。」
「ん。」
マリーウェザーが毛布から顔を出すと、シェリルに話し掛けた。
「愛には厚みがあるって、何となく分かったよ。」
シェリルは頷くと、何か思い出したように視線を少し下に向けた。
「そうなんだよね。愛している。その言葉は絶対で、ただ唯一のもののように思える。けれど、愛の中身をよく見てみれば、それは全く違っている。とても良く調べて、良く考えた上で、たくさんの事を与えてくれる。そんなぶ厚い愛もあれば、大した考えもなく上辺だけで、結局何もしていない薄っぺらな愛もある。ただ、いくら上辺だけの愛であっても、愛しているのか?と聞けば、人は愛していると答える。だから愛しているといったときに、その愛がどれくらいの厚みを持っているのか、それが重要だ。」
シェリルの言葉を聞いて、マリーウェザーは目だけ上を向いて少し考えた。
「そっか、じゃあ、私を捨てた両親にもきっと愛はあるんだ。」
マリーウェザーが独り言のようにそう言うと、隣で聞いていたアレンティーもこちらに顔を向けた。
シェリルはマリーウェザーとアレンティーに頷いて見せた。
「そうさ。当たり前だ。あんなちんけな山賊にだって、我が子への愛があったんだ。だから、マーリンやマリーウェザーやアレンティーを捨てた両親も、きっと3人を愛しているはずだよ。ただ、3人を手放さなければならない事情が、その愛を上回ってしまった。その事情がどんな事情であったのかが分かると、納得がいくのにね。」
マリーウェザーがうんうんと頷いた。
「そっか。じゃあさ、あの子が父親を助けたのは何だったのかな。私なら、あんな親父と一緒にいるより、シェリルと一緒にいる方が絶対にいいと思うけど。子どもが親を愛していたのかな。」
シェリルはマリーウェザーに笑顔を向けた。
「ありがとう。私もマリーウェザーのことが大好きだよ。もちろん、アレンティーのこともね。」
マリーウェザーとアレンティーが照れくさそうに笑った。
シェリルは人差し指を顎にあてて、少し考える素振りを見せた。
「そうだね。子どもが親を愛していたとも思うけど、父親のために自分の命をかけて守る。だなんて、そんなことをあの幼い子が考えただろうか?そうではなくて、ただただ止めなくてはという気持ちに突き動かされたのだと私は思う。じゃあ、あの子をそんな気持ちにさせたものは一体何だったのだろうか。それは当然、自分の父親が殺されるのはダメなことだと感じたから。けれどもそれだけではない。自分に優しくしてくれた私たちが人を殺す。そのこともダメだと感じたからじゃないかな。父親の命を守る事、私たちが人を殺すのを止める事。つまりあの子は、父親と私たちと、両方を救おうとしたんだよ。」
「凄い。」
アレンティーが思わずそう言った。
「そう、凄いよね。もちろん、あの子がその理屈を理解している訳はない。まだ未熟な子どもなんだから。ただ逆に、理屈も分からないのに何となくダメだという気持ちが自然に生まれ出る。それって、あの子が優しい気持ちを心に持っているって事だ。あんなひどい父親だというのに。」
「何ていい子なんだろう。」
マリーウェザーがそう言った。
「そう、とても優しい子だよ、あの子は。それを、あんなろくでなしの父親のせいで、山賊にさせる訳にはいかない。」
「そっか、分かったよ。」
マリーウェザーが毛布を口元に被りながらそう言った。
「私も分かったよ。」
アレンティーもそう言った。
「動物の世界も、植物の世界も、自然というのは弱肉強食の世界だ。もちろん人間の世界も。でも、あの子の姿を見ていたら思わず期待してしまうじゃないか。人間とは、もともと優しさを持った存在なのではないかと。そして人間だけが、弱肉強食の法則を打ち破り、弱い者と共に生きる事ができる唯一の存在なのではないかと。」
シェリルが独り言のようにそう言った。
「それじゃ、そろそろ寝ようか。おやすみなさい。」
シェリルがマリーウェザーとアレンティーにニコッとすると毛布に顔をうずめた。
「おやすみなさい、シェリル姉さん。」
「おやすみなさい。」
マリーウェザーとアレンティーもそう言って毛布に潜り込んだ。
マリーウェザーは目を瞑った。
マリーウェザーは、ようやくシェリルがなぜ私たち兄妹に優しくしてくれるのか分かった気がした。
これまでは何となく、分かったような分からないような感じだった。
なぜ自分の子どもでもない私たちに、こんなに一生懸命優しくしてくれるのか分からなかった。
ただ単に、お節介好きなのかなと思ってもいた。
でも今なら分かる。
私たちも山賊の子どもと一緒だったんだ。
両親に捨てられて、人から大切にされた思い出などなかった。
マリーウェザーはシェリルが言った言葉を思い出した。
「だから私は、この子どもに、人から大切にされるということを経験させてあげたいのだ。」
きっとシェリルは、あの時も、私たち兄妹の運命を変えられるとしたら、今しかないと思ったのだろう。
マリーウェザーは目を瞑ると、初めてシェリルと出会った時の事を思い出していた。
そうして目を瞑って考えていると、まどろんで意識が曖昧となって、眠りの世界に入って行った。
マーリン「どうでもいい話ですが、シェリルが動物の中で一番好きなのは何ですか?」
シェリル「私は豚さんが大好きだ。」
エバ「そう言えば、そんな事言っていたな。」
マーリン「動物というか、家畜ですよね。」
シェリル「何で。別にいいじゃん。見た目が可愛い、鳴き声も可愛い、食べても美味しい。私は豚さんが大好きだ。」
エバ「でも、食べちゃうんだろ。」
シェリル「そりゃ食べるよ。美味しいもの。エバは食べないの?」
エバ「食べるよ。じゃなくて、そうだな・・・、」
マーリン「つまり、可愛がる一方で、殺して食べるというのに矛盾を感じる、と。」
エバ「そう、それそれ。」
シェリル「全然。全く矛盾を感じない。可愛がるのは可愛がる豚さん、だから可愛がる。殺して食べるのは食べるための豚さん。だから食べる。矛盾は生じない。」
エバ「ええ?」
マーリン「なるほど、つまり、豚さんと一括りにするなという事ですかね。」
エバ「良く分からんが、豚が大好きという事は分かった。」
シェリル「豚はこんなに可愛いのに、なぜ保護団体は保護に動き出さないんだ。」
エバ「何言ってるんだよ。」
マーリン「保護するとして、どうするんですか?」
シェリル「豚さんと楽しく遊べる、豚さんランドを作るのはどうかな。」
エバ「ははは、何だそれ。」
シェリル「ネズミとたわむれるランドがあるんだから、豚さんランドがあってもいいだろう。」
マーリン「あれは、ネズミ風の生き物で、ネズミではありません。」
エバ「だいたい、豚さんランドを作ることが何で保護に繋がるんだよ。」
シェリル「豚さんランドでは、豚はランド内の森を放し飼いだ。豚の自由だ。そして、可愛がりたい人は可愛がって、食べたい人は捕まえて殺して食べればいい。」
マーリン「凄いランドですね。」
シェリル「人間も豚も平等という訳さ。立派な保護だろう。」
エバ「だが、複雑なランドだな。可愛がっている横で、丸焼きになっている。」
シェリル「・・・。」
エバ「豚的にも、天国に来たと思ったら、地獄だった、みたいになるんじゃないか。」
マーリン「ターゲット的にも、子どもに来て欲しいのか、大人に来て欲しいのか微妙ですね。」
エバ・シェリル・マーリン「・・・・。」
シェリル「やっぱりランドはやめようかな。」
エバ「丸焼きをやめればいいんだろう。」
シェリル「だめだよ。食べて美味しいというのは、私にとって豚の大事な構成要素だ。豚を保護するのなら、可愛さと美味しさの両立を目指すべきだ。」
マーリン「保護するのも難しいですね。」
シェリル「エバは何の動物が好きなんだ?」
エバ「そうだな・・・、ペガサスがいいなあ。」
シェリル「へえ、素敵だね。」
マーリン「動物ではないけどね。」
エバ「空を馬で駆けるなんてかっこいいなあ。一度乗ってみたい。」
シェリル「だったら、競争しよう!山をぐるっと回って、どちらが先に戻って来れるか。」
エバ「いいねえ!」
マーリン「ちょっとちょっと。シェリルは乗馬できないでしょ。落馬したら死ぬよ。」
シェリル「そうだった。やっぱり豚さんの方がいいや。」
エバ「おいおい、ペガサスと豚の何を比べたんだ。」
コナン「ちーす。」
シェリル「コナンくん!」
コナン「シェリルさん、ラン風に言うの、止めてくれない。」
シェリル「申し訳ございませんでした。」
コナン「で、何を話していたんですか。」
マーリン「好きな動物の話ですよ。」
シェリル「私が豚さんで、エバがペガサス。」
コナン「へえ、中世に行けばペガサス乗れるんですか?」
エバ・シェリル・マーリン「・・・・。」
コナン「何か変な事言いました?」
エバ「ペガサスは見たことないな。」
シェリル「どこにいるんだろう。」
マーリン「聞かないですね。」
コナン「じゃあ、CG入れちゃえばいいんじゃないですか?」
シェリル「コナン・・・。実はこの作品、CGも合成も使っていない、ガチ作品なんだよ。」
コナン「えっ!じゃあスタントマンは?使ってないの?」
シェリル「使ってないよ、全て本人だから。」
コナン「うわ!じゃあ、俺も危ないじゃないですか。ひょっとしたら山賊に刺し殺されていたかもしれないんでしょう?」
エバ「知らなかったのか。」
コナン「聞いてないですよ。」
エバ・シェリル・マーリン「はははははは。」
マーリン「そう言えば、コナンさんは好きな動物とかあるんですか。」
コナン「うーん・・・、人間かな。人間観察。」
マーリン「だからそれ動物じゃねえよ!素直に犬とか猫とか愛玩動物の名前を言う人間はここにはいないのかよ。」
エバ・シェリル・コナン「はははははは!」
シェリル「良し。じゃあ、どうでもいい話はお開きにして、今回も呑みに行っちゃう?」
エバ・マーリン・コナン「おー。」
シェリル「おっ、今回はコナンもノリがいいねえ。」
コナン「中世は自由で居心地悪くないからな。」
シェリル「良かった。じゃあ今日もジェシーおばさんのお店で、豚さんのソーセージとローストポークにエールの組み合わせはどうかな?」
エバ・マーリン・コナン「おー!」
エバ「ソーセージは、燻(いぶ)した香りがいいんだよな。」
マーリン「あのローストポークは、にんにくとコリアンダーが効いていて美味しいですよね。」
コナン「へえ、いいじゃん。うまそう。」
シェリル「よし、じゃあ豚さんを食べに行こうぜ!」
エバ・マーリン・コナン「おー!」
シェリル・エバ・マーリン・コナン「ぶうたさん!ぶうたさん!ぶうたさん!ぶうたさん!」
4人が徐々にフェードアウトしていく中、何か思い出したようにエバが呟いた。
エバ「丸焼きの豚はただの豚か。そりゃそうだな。ん?何か違ったっけ。」